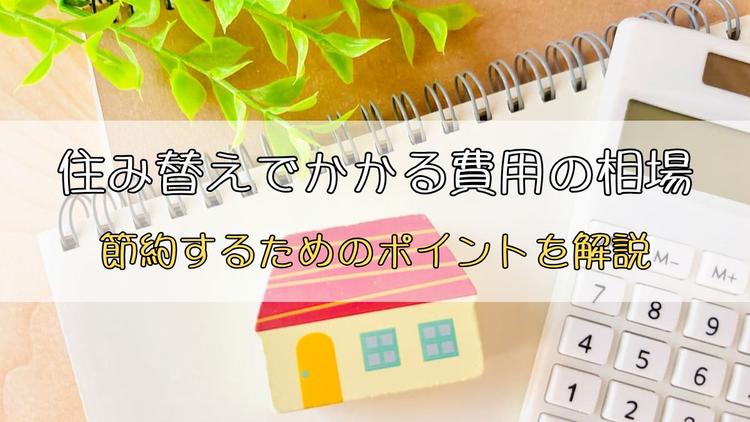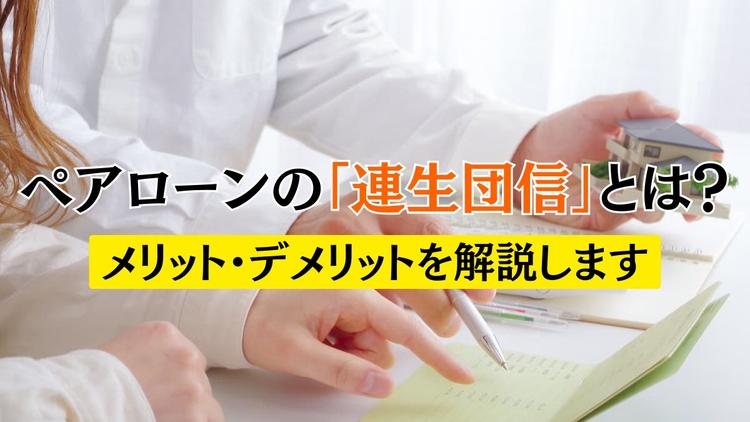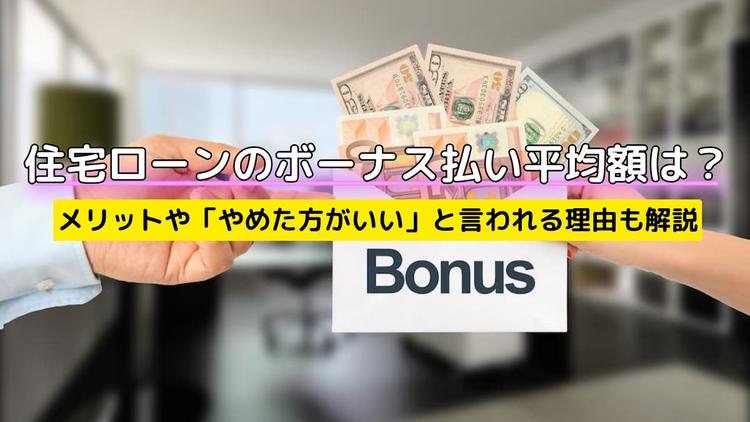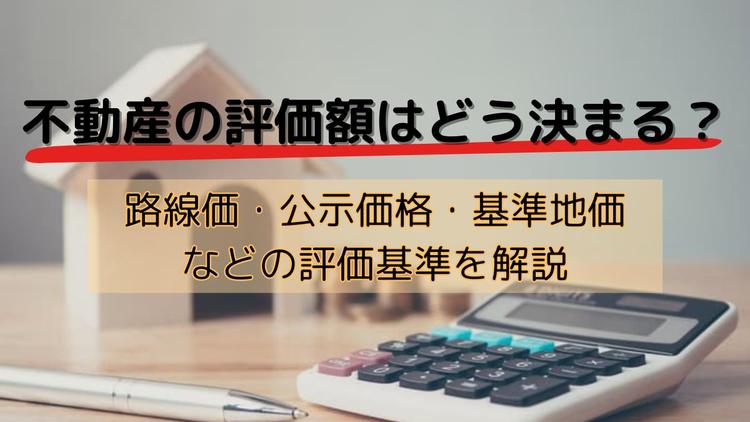住み替えでは家の購入と売却を行うため、それぞれに費用がかかります。
住み替え成功のためには、費用まで含めて資金計画を立てることが大切です。
この記事では、住み替えにかかる費用の相場や費用を抑えるポイント、住み替えの流れなどを詳しく解説します。
住み替えで家を売却するのにかかる費用相場
住み替えとは、今住んでいる家の「売却」と新居の「購入」という大きな不動産取引をともなう住居の変更です。
住み替え時には家の購入費用以外に売却と購入に対して費用がかかるため、どれくらいの費用がかかるかを事前に抑えておく必要があります。
ここでは、最初に売却にかかる費用をみていきましょう。
以下は、家を3,000万円で売却したときにかかる費用相場です。
| 特徴や算出方法 | 相場(3,000万円の場合) | |
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う手数料 上限額: | 上限額96万円 |
| 譲渡所得税・住民税 | 売却で利益が出た場合に 利益にかかる所得税・住民税税額 売却利益×20.315% or 39.63% | 利益が1,000万円だった場合 (控除を利用しない) 税額が約200万円~400万円 |
| 住宅ローンの繰り上げ返済費用 | 売却時で住宅ローンを完済する際の 繰り上げ返済のために 金融機関に支払う事務手数料 | 1~5万円ほど 金融機関によって異なる |
| 登記費用(登録免許税+司法書士費用) | 住宅ローンを完済した際に 抵当権を抹消するための 登録免許税と司法書士報酬 | 登録免許税 1,000~2,000円司法書士報酬 1~3万円ほど |
| 印紙税 | 売買契約書にかかる税金 | 2万円(軽減適用しない場合) |
| その他 | ・測量費 ・修繕費 ・ハウスクリーニング費用 ・引っ越し費用など | 売却状況により異なる |
売却にかかる費用は、売却額の5~10%ほどが目安といわれています。
それぞれの費用を詳しくみていきましょう。
仲介手数料
仲介手数料とは、仲介で売却した際に不動産会社に支払う成功報酬です。
売買成立時に発生しますが、いくらでも請求できるわけではなく法律によって上限額が以下のように定められています。
たとえば、3,000万円で売却した場合の上限額は「3,000万円×3%+6万円=96万円(税抜)」となります。
また、取引額が800万円以下の場合、双方の合意があれば一律で30万円(税抜)を請求することが可能です。
なお、上記はあくまで上限額であり不動産会社は上限の範囲内であれば自由に設定できます。
とはいえ、多くの不動産会社が上限をベースに算出しているため上限額で請求されるケースでシミュレーションしておくとよいでしょう。
ちなみに、仲介手数料は仲介での売却で発生するもので、不動産会社による直接買取では発生しません。
コストを押さえて売却したい場合は、買取も検討してみるとよいでしょう。
譲渡所得税・住民税
売却で得た利益は譲渡所得と呼ばれ、所得税・住民税の対象です。
譲渡所得は以下の計算で求められます。
売却額から、購入時にかかった費用と売却にかかった費用を差し引いた部分が売却の利益です。
さらに、3,000万円特別控除などの控除を差し引いた額がプラスになった場合に課税されます。
課税される場合は「課税譲渡所得×税率」で税額が算出できます。
税率は所有期間に応じて異なり、5年以下の短期譲渡所得で39.63%、5年超の長期譲渡所得で20.315%です。
所有期間が短いと税率が高く税負担が大きくなる点には注意しましょう。
▼関連記事:住み替え時は住宅ローン控除と3000万円控除が併用できない。どちらがお得かシミュレーションしてみよう
住宅ローンの繰り上げ返済費用
家を売却するには住宅ローンを完済する必要があります。
住宅ローンが残っている場合は、売却金で完済するケースが一般的でしょう。
繰り上げ返済して完済する場合は、金融機関で手数料が発生します。
手数料額は金融機関によって異なりますが、1~5万円ほどが目安です。
たとえば、りそな銀行では1.1~3.3万円 、みずほ銀行では3.3万円かかります。
また、金融機関によっては一括返済の手順が決まっている場合もあるので、事前に繰り上げ返済する旨は相談しておくようにしましょう。
登記費用(登録免許税+司法書士報酬)
家の売却にともない抵当権を抹消するケースでは、登記費用が必要です。
抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産の筆数×1,000円となるため、土地+建物で2,000円かかります。
また、登記手続きを司法書士に依頼する場合は別途司法書士報酬が必要です。
司法書士報酬は依頼する司法書士や依頼内容によって異なりますが、1~3万円が目安となるでしょう。
なお、登記簿には所有者の住所・氏名も記録されていますが、結婚や引越しなどで現状の住所・氏名が登記簿上と一致しない場合は、事前に住所・氏名の変更登記が必要です。
事前に、登記簿を確認して変更登記が必要ないかもチェックするよう��にしましょう。
印紙税
印紙税とは売買契約書にかかる税金です。
契約書に税額分の収入印紙を貼付・消印して納税します。
税額は、契約書に記載する金額(売買金額)によって異なり、主な不動産取引価格帯での税額は以下のとおりです。
| 契約金額 | 本則税率 | 令和9年3月31日まで |
| 500万円超 1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
印紙税は令和9年3月31日までは軽減後の税額が適用されます。
印紙税を納税し忘れると、本来の税額の3倍相当にあたる過怠税の支払いが必要になるので注意しましょう。
その他
戸建ての場合、売却時には敷地の境界線の確定が必要となるのが一般的です。
古い家など境界確定できていない場合は、測量して境界確定するため測量費がかかります。
また、売却にともない修繕やハウスクリーニングする場合なども費用がかかってきます。
その他の費用は売却状況によって異なってくるため、事前にどのような費用が必要かを洗い出しておくことが大切です。
住み替えで家を購入するのにかかる費用相場
住み替えで新居を購入する際にかかる費用は以下の通りです。
| 特徴や算出方法 | 相場(3,000万円の場合) | |
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う手数料 上限額:売却価格×3%+6万円+消費税 | 上限額96万円 |
| 登記費用 | 所有権移転登記・抵当権設定登記 にかかる登録免許税と 司法書士報酬 | 登録免許税(所有権移転登記):60万円 司法書士報酬:10万円ほど |
| 住宅ローン事務手数料や保証料 | 住宅ローンを組む際にかかる 金融機関の手数料 | 3,000万円の借入の場合 事務手数料:60万円ほど |
| 火災保険料 | 新居で加入する 火災保険料・地震保険料 | 10~30万円/年間 |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した年にかかる税金 | 120万円(軽減適用なし) |
| 固定資産税や都市計画税の清算金 | 購入した年の 固定資産税・都市計画税の 清算のための費用 | 税額や所有期間によって異なる 10~30万円 |
| 管理費や修繕積立金の清算金 | マンションを購入した場合に かかる費用 | 1~3万円ほど |
| その他費用 | 修繕費用など | 購入状況に応じてかかる費用 |
以下、それぞれについて見ていきましょう。
仲介手数料
購入時にも不動産会社に仲介手数料の支払いが必要です。
売却時同様に上限額が定めらており、上限額の範囲内で不動産会社が設定する金額を支払います。
なお、不動産会社が直接の売主の場合は仲介ではないので発生しません。
ただし、不動産会社が売主でも間に不動産会社が入ると仲介手数料が発生します。
事前に、仲介手数料が発生する販売形態かは確認するようにしましょう。
▼関連記事:売主物件とは?仲介物件との違いや購入するメリット・デメリットを解説
登記費用(登録免許税+司法書士報酬)
不動産を購入する際には、以下のような不動産登記が必要です。
- 所有権移転登記:所有権を売主から買主に変更する登記
- 抵当権設定登記:抵当権を設定するための登記
所有権移転登記の登録免許税は「不動産評価額×2%」です。
また、取得年度や住宅性能によっては軽減の特例を適用可能です。
一方、新居を住宅ローンで購入する際には、金融機関が抵当権を設定するため抵当権設定登記が必要になります。
抵当権設定登記の登録免許税は「借入額×0.4%」となり、仮に3,000万円を借入れた場合は12万円です。
登記手続きの際に司法書士に依頼する場合は、別途司法書士報酬も必要なので注意しましょう。
住宅ローン事務手数料や保証料
住宅ローンを組む際には、金融機関への事務手数料や保証料などが発生します。
事務手数料は借入額×2~3%、保証料は事前一括払いで借入額2%程が目安です。
金融機関によって手数料や保証料は異なり、住宅ローンに組み込めるかも異なります。
住宅ローンを検討する際には金利だけでなく、費用について確認して金融機関を選ぶようにしましょう。
火災保険料
住宅ローンを組む場合、原則、火災保険の加入は必須です。
ただし、火災保険では地震による火災や津波被害などは補償されません。
地震まで備える場合は、火災保険に付帯する形で地震保険への加入が必要となるので、あわせて検討するようにしましょう。
火災保険・地震保険とも毎月払いよりも長期一括払いの方が割安です。
不動産取得税
不動産を取得した年には不動産取得税の支払いが必要です。
不動産取得税の税額は「不動産評価額×4%」となりますが、取得年度・不動産の種類によっては軽減措置が適用されます。
不動産取得税は、購入時ではなく購入してから半年~1年ほど後になって納税通知書が送付されます。
納税通知書が送付されてから納税できないとならにように、事前に資金計画を立てておくようにしましょう。
固定資産税や都市計画税の清算金
固定資産税・都市計画税は毎年1月1日時点の所有者に課せられます。
このため、年の途中で購入した場合は、売主が納税義務者となりますが、決済日を境に売主・買主で日割りで按分するのが一般的です。
この場合、決算時に売主に対して清算金を支払うことになるため、清算金の額を確認しておくようにしましょう。
(マンションの場合)管理費や修繕積立金の清算金
マンションを購入するケースでは、売主が支払った管理費や修繕積立金を日割りで清算するのが一般的です。
管理費・修繕積立金が年払いか月払いかなどによっても費用が異なってくるので、確認しておくようにしましょう。
その他
購入時にリフォームする・家具家電を購入するなど購入状況に応じた費用がかかります。
とくにリフォームが必要な場合は、施工規模によっては100万円を超える場合もあるので事前に必要な費用や額を精査しておくことが大切です。
住み替えの費用は3つのパターンがある
住み替えは、売却と購入のタイミングによって以下の3パターンに分かれます。
- 売り先行:先に売却してから購入する
- 買い先行:購入してから売却する
- 同時決済:売却と購入を同時に行う
いずれのパターンであっても売却と購入に費用が必要です。
ただし、パターンによってかかる費用や注意点があるので、理解したうえでどのバターンで住み替えするかを決めるようにしましょう。
以下では、パターン別に発生する費用や費用の注意点を解説します。
売り先行は仮住まいの費用が必要になる
売り先行の場合、売却してから新居を購入します。
そのため、売却の売買契約時点では新居が決まっていないことが多いです。
新居が決まるまで仮住まいが必要となるため、仮住まいの賃料や仮住まいに関する引っ越し費用など余分に費用が発生する点に注意しましょう。
引渡し前に新居が決まれば仮住まいは必要ありませんが、その場合新居選びに十分な時間がかけられずに新居で後悔する恐れもあります。
また、事前に新居選びをある程度進めることもできますが、売却金が確定しないと新居の費用が確定できず、その結果見込んでいた物件が購入できない恐れがある点に注意しましょう
▼関連記事:売り先行で、家に住みながら売却を成功させる7つのポイントを解説
買い先行はダブルローンになる
買い先行は購入が決まってから売却を進めるため、新居選びに十分な時間を割けます。
しかし、新居を住宅ローンで購入し、売却できるまで前の家の住宅ローンが完済できないケースでは、新居と旧居の住宅ローンを二重で支払うダブルローン状態となります。
旧居の売却が長引くほどダブルローンの負担が大きくなる点には注意しましょう。
想定よりも売却金が少ないと住宅ローンの完済計画が狂う恐れもあります。
買い先行は資金計画が大きく崩れやすいというデメリットもあるため、基本的には資金に余裕があるケースでの選択をおすすめします。
同時決済は余計な費用がかからないが実現しづらい
同時決済は売却と購入を同じタイミングで行うため、売り先行・買い先行のデメリットが解消される理想的な方法です。
余分な資金も発生しないため、コストも押さえて住み替えを進めやすいでしょう。
しかし、売却と購入を一致させるのは容易ではありません。
それぞれ契約相手があり、さまざまな手続きや細かい日程調整が必要になるため、実際には実現することが困難であることも多いです。
同時決済を目指す場合でも、売り先行・買い先行どちらかになることも視野に入れて計画を立てることをおすすめします。
▼関連記事:同時決済で住み替えするための手順は?費用負担を抑えるためのコツも解説
住み替え費用を安く抑えるためのポイント
ここでは、住み替えの費用を安く抑えるためのポイントを紹介します。
買い先行より売り先行の方が費用を抑えやすい
費用面で考えると、買い先行よりも売り先行の方がメリットがあります。
買い先行は、ダブルローンになる恐れがあるだけでなく、購入資金を自己資金でまかなう必要があったり、売却額が想定より少ない場合に住宅ローンが完済できないなど、資金計画が大きく崩れやすい方法です。
一方、売り先行は売却金が確定してから新居を購入するため、資金の見通しが立てやすいという特徴があります。
仮住まいが必要になったとしても、ダブルローンやローン完済ができない状況に比べれば、負担は軽く済むでしょう。
資金計画を明確に立てたい、または費用を抑えたい場合は、売り先行が適しています。
特に住宅ローンの残債があるケースでは、基本的に売り先行が選ばれます。
これは、2軒分の住宅ローンを同時に支払い続ける「ダブルローン」では、金融機関の審査が厳しくなりやすく、融資を受けられない可能性もあるためです。
もちろん、十分な収入があり、金融機関からダブルローンを認められやすい世帯の場合は、買い先行のメリットもあります。
先に新居を購入できるため、引っ越しまでの仮住まいが不要になり、2度の引っ越し費用や仮住まいの家賃を節約できるでしょう。
また、住みながらじっくり売却活動ができるので、希望条件に近い価格で売れる可能性も高まります。
▼関連記事:住み替えのダブルローンはデメリットが大きい?注意点や賢い使い方を解説します
同時決済を目指す
3つの住み替えパターンのうち、一番費用を抑えやすいのは同時決済です。
しかし、先述したように同時決済は難度が高いです。
同時決済は無理でも売り先行なら売却から新居購入までに期間を短くする、買い先行なら売却までの期間を短くすることで費用を抑えやすくなります。
とはいえ、費用を抑えるために売り急いで売却金が安くなる、新居選びに時間をかけずに新居で後悔するとなっては意味がありません。
住み替えの本来の目的を忘れずに少しでも費用を抑えられるように心がけましょう。
特別控除や損益通算を活用する
売却で出た利益には譲渡所得税が課税されますが、さまざまな特例が用意されており節税可能です。
代表的な控除には「3000万円特別控除」があり、この特例の適用を受けることで譲渡所得3,000万円以下であれば税金が発生しません。
また、仮に売却で赤字になった場合でも、給与所得と赤字を損益通算(相殺)できる特例があるので、活用することで給与に対する所得税・住民税の節税が可能です。
控除や特例を上手に活用して、税負担を軽減すればトータルの費用の軽減につながるでしょう。
特例や控除について不安がある場合は、税理士や不動産会社に相談して適切な特例を適用できるようにアドバイスをもら��うことをおすすめします。
住み替えではローンの「借り換えが必須」だから、金融機関選びも重要
住み替えでは、新居購入のために新たな住宅ローンを組む際、現在のローンを完済する必要があります。
このとき、多くの場合は「売却代金で旧居のローンを完済+新居のローン契約」という流れになるため、結果的に「借り換え」と同じような手続きが発生します。
同じ金融機関で新旧のローン手続きをまとめられる場合もありますが、必ずしも条件が有利とは限りません。
むしろ、複数の金融機関を比較して金利や手数料、保証料、繰上げ返済条件などを精査したほうが、総返済額を抑えられる可能性が高いです。
特に注意したいのは、以下のポイントです。
- 金利タイプ(固定・変動・固定期間選択型)
- 金利差による総返済額の違い
- 保証料や事務手数料の水準
- 団信の内容(がん保障や三大疾病保障の有無)
また、住み替えのスケジュール上、同時決済や短期間での資金移動が必要になることもあります。
こうしたケースでは、手続きの柔軟性や事務処理のスピードも重要な判断材料になるでしょう。
住宅ローンは数千万円単位の契約ですから、わずかな金利差や手数料の違いが将来の支出に大きく影響します。
金融機関選びでは、不動産会社や住宅ローン専門のアドバイザーにも相談し、最終的な資金計画とスケジュールの両面で無理のない条件を整えることが大切です。
金利などを比較して損せず住宅ローンを選びたい方は「モゲチェック(PR)」の住宅ローン診断を活用してみましょう。
▼関連記事:損せず住み替えするには「住宅ローン選び」が重要!金融機関の比較方法を解説
住宅ローンを完済済みなら、抵当権抹消登記を自分で手続きする
住宅ローンを完済すると、金融機関の抵当権を外すための「抵当権抹消登記」が必要になります。
不動産売買の場面では、決済や名義変更に関わる登記手続きを司法書士に一括で依頼するのが一般的ですが、既にローンを完済済みであれば、抵当権抹消登記は売主本人でも法務局で申請可能です。
司法書士に依頼すると報酬として1~3万円ほどかかりますが、自分で行えば登録免許税(1物件2,000円程度)のみで済みます。
住宅ローンを売却金で返済する場合は、抵当権抹消登記も司法書士に委任するのが一般的です。
これは、買主への所有権移転登記や、買主が利用する金融機関の抵当権設定登記をスムーズに行うために、抵当権抹消登記もミスなく進める必要があるからです。
住み替え時は他にも仲介手数料や引っ越し代など多くの費用がかかるため、この手続きを自分で行えば諸費用を抑えることができるでしょう。
▼関連記事:住宅ローン完済後の抵当権抹消手続きの流れ
【パターン別】住み替え費用のシミュレーション
ここでは、具体的な住み替え費用をシミュレーションしていきます��。
前提となる条件は以下の通りです。
| 売却 | 売却金:3,000万円 住宅ローン残債:2,000万円/毎月の返済額9万円 売却の利益:500万円(長期譲渡所得) |
| 購入 | 購入額:4,000万円 不動産評価額:3,000万円 住宅ローンの借入額:3,000万円/毎月の返済額10万円 |
上記の条件で、売り先行・買い先行・同時決済の費用をみていきましょう。
売り先行の場合
まずは、売り先行で費用をシミュレーションします。
なお、仮住まいが半年必要として費用を算出していきます。
| 売却費用(205万円) | 仲介手数料:96万円 不動産登記費用:3万円 印紙税:2万円 譲渡所得税:101万円 住宅ローン完済費用:3万円 |
| 購入費用(540万円) | 仲介手数料:126万円 不動産登記費用: 印紙税:2万円 不動産取得税:120万円 住宅ローン契約時の手数料:130万円 火災保険・地震保険料:10万円 固定資産税・都市計画税の清算金:5万円 引っ越し費用:10万円 |
| 仮住まい費用(76万円) | 家賃8万円×半年:42万円 敷金・礼金:24万円 仮住まいへの引っ越し費用:10万円 |
上記のケースでは、売却費用・購入費用に仮住まいの費用をプラスすると821万円かかっています。
買い先行の場合
次に、買い先行で費用をシミュレーションしていきましょう。
また、ダブルローン期間が半年あると仮定して算出します。
買い先行での費用は、売り先行時に算出した売却費用(205万円)と購入費用(540万円)の合計745万円です。
しかし、旧居と新居の住宅ローンの返済が半年間被っているため、この期間の住宅ローン返済額は毎月19万円となります。
同時決済の場合
同時決済の場合は余分な費用が必要ないため、売却費用(205万円)と購入費用(540万円)の合計745万円のみで済みます。
買い先行時のダブルローン期間や売り先行時の仮住まい期間が必要ないため、資金の負担は軽くなりやすいでしょう。
住み替えの費用に関するよくある質問
最後に、住み替えの費用に関するよくある質問をみていきましょう。
「ローンの残っている家を売って新居を買いたい」は実現できる?
実現可能です。
住宅ローンと家の売却額の関係性は以下の2種類があります。
- アンダーローン:住宅ローン残債<売却額
- オーバーローン:住宅ローン残債>売却額
住宅ローン残債よりも売却額が大きいアンダーローンであれば、問題なく売却でき済み替えが可能です。
一方、オーバーローンの場合、売却額だけでは完済できません。
オーバーローンの場合でも、自己資金や住み替えローンなどを活用して住宅ローンを完済できるなら売却できます。
しかし、自己資金や住み替えローンなどが用意できない場合は売却できないため、住み替えもでき��ません。
住宅ローン残債があり住み替えを希望する場合は、まずは住宅ローン残債の正確な額と査定額を把握し、売却できるかを判断するようにしましょう。
▼関連記事:ローンの残っている家を売って新居を買う時の注意点7選
買い先行の住み替えで家が売れなかったらどうなる?
売却できるまでの期間、旧居にかかる費用の負担が続きます。
固定資産税や維持費などがかかるだけでなく、旧居の住宅ローンが残っていればダブルローンとなるので注意しましょう。
買い先行で旧居の負担を軽減するためには、少しでも早く家を売却することが大切です。
「需要は見込める物件なのに、内見が少ない」といった場合は、不動産会社による囲い込みや、売り出し価格が適切でないなどの可能性が考えられます。
また、売却を急いでいる場合は不動産会社による買取を検討するのもおすすめです(売却価格は仲介の7~8割程度になるが、早期の成約が見込める)。
▼関連記事:売れない不動産は「買取」してもらうべき?買取の手順・買取会社の探し方を解説
まとめ
住み替えでは、売却時に売却価格の5~10%、購入時の購入価格の5~10%ほどの費用がかかります。
また、住み替えのパターンによっては仮住まいの費用やダブルローンなど、パターン別の費用も発生する点に注意が必要です。
住み替えパターンや費用を慎重に考慮して、適切な住み替え計画を立てるようにしましょう。
住み替えを成功させるには、今の家をスムーズにかつ高値で売却することも大切です。
できるだけ多くの不動産会社の査定額を比較し、信頼できる不動産会社を選ぶようにしましょう。