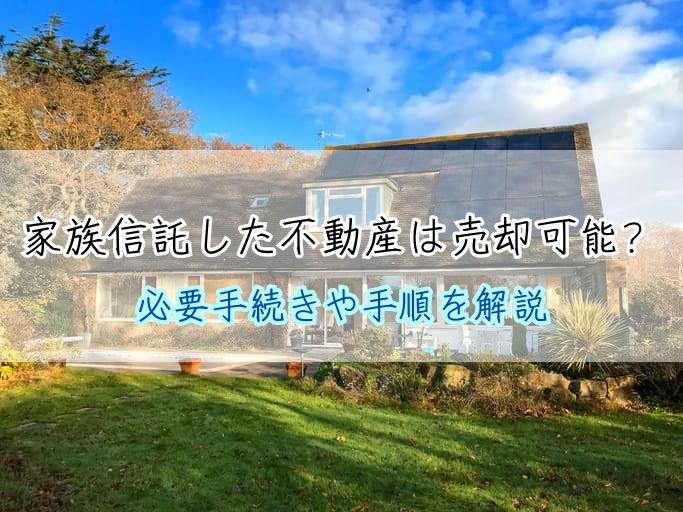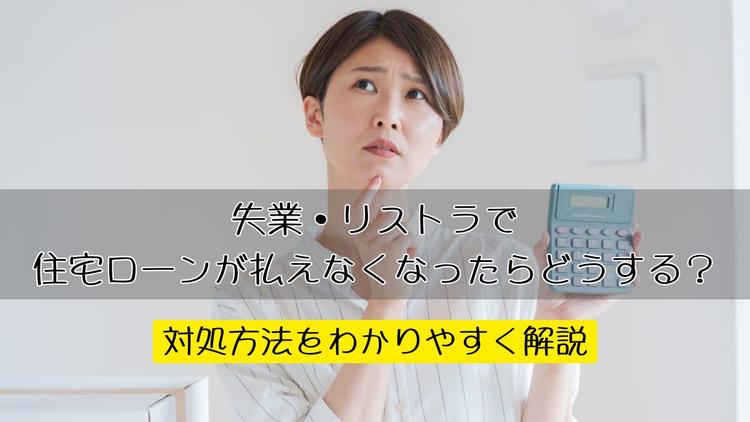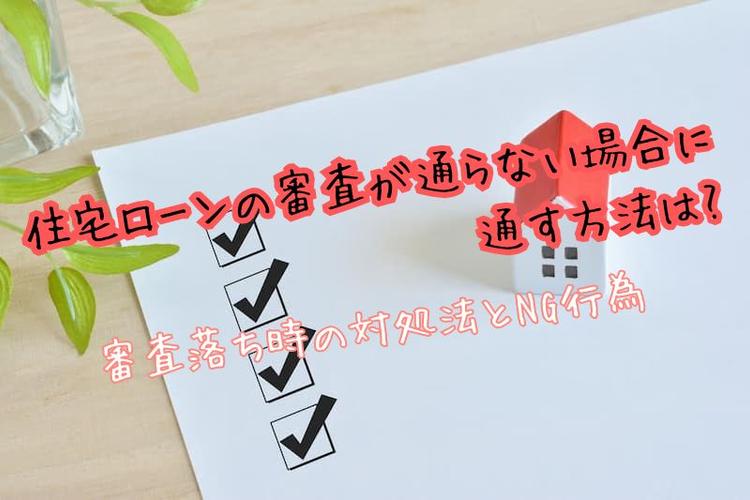社会の高齢化が顕著な昨今、認知症対策として、家族信託が注目されています。不動産の所有者が認知症になると、意思判断能力がないとして、売却が不可能になります。
意思表示がしっかりとできるうちに、信頼のおける家族に不動産の管理や処分を任せられるのが、家族信託という方法です。
さらに、不動産で得た収益を自分の収入とする流れを家族信託に組み込むことで、老後も安心して暮らすことができるのです。この記事では、家族信託をした不動産の売却方法や必要な手続きについて解説をします。
家族信託とは?家族信託を利用し不動産を売却する際のメリット・デメリットを紹介
家族信託をした不動産の売却の可能性を探るために、そもそも家族信託とはどういう仕組みで運用されるのかについて解説をしていきましょう。併せて、家族信託を利用して不動産を売却する際のメリットとデメリットも紹介します。
家族信託とは?
家族信託とは、信頼のおける家族に自己の財産の管理や処分を任せる仕組みのことです。
家族信託では、委託者、受託者、受益者の3者が当事者となります。財産の管理等を家族に依頼する人を委託者、依頼される家族を受託者、管理している財産から一定の収益を受ける人を受益者と呼びます。
管理・処分を依頼する
自己の財産は自分で管理するのが一般的な方法ですが、加齢や病気で判断能力が衰えると、必ずしも最善の方法とはいえなくなります。財産の保管や処分に関わる事務処理が覚束なくなることがあるからです。
家族信託をすれば、自分の意思が明瞭な段階で、財産の管理や処分を任せる人を選任できるので、やがて認知症などによって判断能力を失った場合にも、安心して資産を運用することができます。
たとえば、親が老後に備えて子どもと信託契約を結ぶ場合は、子どもは親の意向にしたがって財産の管理等を行います。不動産の売却をした場合にも、生じた利益を信託財産として管理します。
子どもはこの管理している資産の中から、親が必要とする資金を提供して生活を支えます。
この場合の親が委託者であり、子どもが受託者となります。また管理する財産から一定の資金の提供を受ける親が受益者です。
受益者は、第三者がなることもありますが、家族信託では、委託者が受益者になる自己信託が一般的な形です。
不動産の名義は「受託者」に変更される
不動産が家族信託の対象になれば、この不動産の名義は、受託者に変わります。登記簿上の移転の原因は「信託」とされ、併せて信託目録が作成されます。
信託目録によって、信託の目的や存続期間、受託者の管理処分権限がどこまであるか、信託監督人等の同意権者の有無等が公示されるので、この不動産を購入しようとする人も、信託の特性を確認することができるのです。
受託者は、「信託口預金通帳 〇山△男」とか「〇山△男 信託口」といった自分名義の、家族信託専用の口座を開設して、委託者の資金を入金、管理します。
受託者は、自分名義の口座なので、必要に応じて自由に出金することができます。ただし、引き出せるのは受益者(親)に必要な金銭であり、受託者(子)自身のために使うことはできません。
この口座は、信託専用であることを明確にしておくことが重要です。単なる個人名義の口座で管理をしていた場合には、贈与と見なされることがあるからです。
ただし信託用口座を取り扱っていない金融機関が多いので、開設に際しては、金融機関への確認が必要になります。
家族信託を利用して不動産を売却する際のメリット
家族信託を利用して不動産を売却する際には、どのようなメリットがあるのかみていきましょう。
1:不動産の共有回避
家族信託に限ったことではありませんが、兄弟姉妹のひとりが親の所有する不動産を賃貸に出して資産運用をしようと思っても、他の兄弟から反対意見が出されると実現できません。
また売却しようとしても、所有者である親が認知症等で意思判断能力がないと判断されると、売買契約が締結できません。
こうしたケースでは、親が亡くなった後の遺産分割協議も収拾がつかなくなることが多く、安易な妥協策として、兄弟姉妹の共有とすることで決着をつけることがあります。しかし、将来の不動産の処分を考えると、共有は、全員の承諾が必要になるといった煩わしい問題が発生するため、とうてい望ましい選択とは言えません。
家族信託を利用していれば、受託者である子どもが単独で不動産の管理や処分ができるので、貸家にすることも売却することも可能です。また、第二受益者を複数の相続人にすることで、不公平感を解消することができるので、兄弟から反対される可能性も低くなります。
2:不動産を塩漬けにすることなく売却可能
不動産の所有者である親が認知症になると、意思決定不能になったとして、売買契約が成立しなくなります。こうした不動産は、長年にわたって使用者も取引もない塩漬け状態に化してしまいます。
親の判断能力が健全なうちに、家族信託によって不動産売却の権限を子どもに与えておけば、問題なく売却することが可能です。
▼関連記事:認知症の親や親戚の家は勝手に売れない!成年後見制度を利用した売却手続きの流れ
3:受託者が不動産の継承を自由に設定できる
遺言は、自分が亡くなった時点の相続人に対する財産の配分を提示するものです。このため、不動産を妻に相続することはできますが、妻が亡くなった後に誰に相続するかまでは指定できません。
単純に考えれば、妻に思いを託せばいい話ですが、もし後に妻が認知症になったり、何かの事情で遺言を残せなかったりすれば、結局自分の思いが実現しないことにもなりかねません。
しかし、家族信託では相続による財産の受益者を遺言よりも一層多く指定することが可能になります。財産の受益権について配偶者の死後誰に相続させるかまで指定することができるのです。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
家族信託を利用して不動産を売却する際のデメリット
家族信託には、メリットばかりでなくてデメリットもあります。メリットとデメリットの双方を比較して、利用方法を考えましょう。
1:家族信託を結ぶのにコストがかかる
家族信託では、関係者の組み合わせや財産の内容によって、信託の方法が異なるため、司法書士や弁護士などの専門家へのコンサルティング費用は必須です。専門家の関与なしで、有効な家族信託を実行するのは、非常に難易度が高い分野だからです。
報酬は定まったものがありませんが、財産の総額で決められることが多く、目的と財産の内容によっては報酬が100万円を超えることも少なくありません。
しかし、家族信託をしないまま、財産所有者の判断能力が著しく低下した場合、成年後見人制度を利用することになります。成年後見人は、家庭裁判所が選任することになりますが、弁護士などの専門家を指定することが多く、この場合、年間24万円以上の費用がかかります。
成年後見人制度は一度利用するとやめることができないので、5年以上生存すれば、家族信託の費用を上回ることになります。
2:関係者を長期にわたり拘束してしまう
家族信託の受託者には、毎年委託者に向けて信託された財産の収支を作成報告し、報告書類を保管する義務があります。
金銭が絡むことであり、法的な問題や周囲の誤解を避けるためにも、おざなりな報告をすることはできません。このため、長期にわたって、受託者は家族信託に向き合わざるを得ない状況下におかれます。
3:家族信託に強い専門家がいない
家族信託は、比較的近年に一般化した制度であるため、法律の専門家の中にも、家族信託に精通した人は限られた存在になっています。
さらに、家族信託の開始から終了までを一貫して体験した人となると、かなり限られた専門家になります。
旧信託法(1922年制定)では、主に商事信託(信託銀行などが行うもの)を想定しており、家族間での信託(民事信託)はあまり現実的ではありませんでした。
2007年の信託法改正により、営利目的でない信託、つまり家族信託(民事信託)が制度的に整備され、一般の個人間でも柔軟に信託契約を結ぶことが可能になりました。
そのため、法律的には2007年から家族信託の制度がスタートし、一般に広まり始めたのは2010年代に入ってからで、特に高齢者の認知症対策や不動産の承継手段として注目されるようになったのはここ10年ほどです。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
家族信託された不動産は売却可能か?
結論から言えば、家族信託された不動産であっても、売却は可能です。ただし、そのためには、家族信託の設定を適切に行う必要があります。誤った設定をしてしまうと、せっかく家族信託をしたのに、まったく売却ができない事態に陥ることは十分にあり得るのです。
家族信託で不動産を売却するにあたっての、ポイントを解説していきましょう。
「不動産の売買に関する項目」がある場合
信託契約の条項に信託不動産の「売買」が含まれている場合は、信託の目的に従い、受託者を売主として信託不動産を売却することができます。
方法は普通の売却とほとんど変わりありません。異なる点は、所有者が売主になるのではなく、受託者が売主になることです。売却による売却益はそのまま信託財産になります。
家族信託では、受託者が複数人いることがあります。この場合は、受託者同士での同意が必要になりますから、単独で判断することはできません。
信託の条項に”売買”の名目がない場合は?
信託契約の条項に、信託不動産の「売買」が含まれていない場合は、受託者に権限がないため、そのままでは信託不動産を売却することはできません。
売却したい場合は家族信託契約書の条項を変更する(信託契約で定めた合意等が必要)か、当事者間の合意解除によりいったん信託を終了させて、委託者(所有者)が自ら売却するという方法になります。
どちらの方法も、委託者本人の売却意思が確認できることが前提になります。認知症等で、すでに意思判断能力がない場合は、信託終了事由が発生するまでは売買はできません。
信託終了事由には以下のものがあります。
- 信託の当事者(委託者及び受益者)の合意解除
- 信託の目的の達成または不達成
- 受託者が受益権の全部を固有財産で保有する状態が1年間継続したとき
- 受託者が欠けた場合であって新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき
- 受託者が費用の償還等を信託財産から受けられないことにより終了させたとき
- 信託が併合されたとき
- 信託財産の破産手続きの開始決定
- 特別の事情により信託目的・信託財産の状況その他の事情に照らし、受益者の利益に適合するに至ることが明らかで、裁判所が信託の当事者からの申立てにより信託の終了を命じたとき
親の意思判断能力が欠如した後では、不動産の処分が非常に困難な状況に陥ります。つまり、家族信託では、信託契約の条項に信託不動産の「売買」について含まれている方が、本来の目的を果たせることになるのです。
信託受益権の売却はできる?
信託受益権とは、受託者が、信託財産を管理・処分することで得られる利益を受益する権利です。たとえば、委託者である親から、経営するアパートを息子が受託します。この息子がアパート管理をして、生み出した利益をもらう権利が信託受益権です。
相続対策や分割対策として、現物の不動産ではなく信託受益権を子どもや同族法人へ売却する方法が用いられることもあります。受益権の売却では、譲渡所得税が受益者に対して課せられます。
ただし、信託受益権の売買には、第二種金融商品取引業の免許が必要です。不動産会社でこの免許を保有している会社は、ほとんどないため、取り扱いをしてくれる会社を探すことが課題となります。
不動産に抵当権がついている場合は?
住宅ローンなどの債務は、マイナスの財産なので信託財産とすることができません。抵当権の債務者は委託者のままです。
登記手続上は、債権者の承諾がなくても信託の登記はできるため、家族信託の設定は可能です。
しかし、住宅ローンを借りる際に締結した金銭消費貸借契約には、「所有者は、金融機関の承諾を得ずに担保不動産を第三者へ移転してはならない」という条項が必ず入っています。これは、債権者に無断で不動産を信託すると、最悪の場合、住宅ローンの一括返済を求められることを意味しています。
一方で、抵当権のある不動産は、基本的に売却をすることができないという現実があります。しかも委託者(債務者)に意思判断能力がなくなれば、弁済の手続きが行えないので、いつまでも抵当権を抹消することができず、不動産は塩漬け状態に陥ってしまいます。
このため、抵当権のついた不動産を家族信託するには、まず債権者である銀行の承諾を得なければなりません。そのためには、信託契約に「免責的債務引受(委託者の債務を受託者が引き受ける)」と「重畳的債務引受(委託者と連帯し、受託者も同等に債務を負担する)」といった債務を引き受けるための設定をすることが前提になります。
こうした準備を整えることで、抵当権のついた不動産の売却が可能になるのです。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
家族信託された不動産売却の手順
家族信託された不動産を売却する際の手順を説明していきましょう。
不動産の買い手を探す。
家族信託された不動産を売却するには、当然のことながら買手を探すことから始めます。売却の依頼先は、仲介会社と買取会社があります。
仲介会社に依頼するメリットは、不動産がほぼ市場の相場の価格で売れる可能性があることです。デメリットは長い期間売れ残る可能性があり、それに伴う心理的負担や売却価格の低下が考えられます。
買取会社に依頼するメリットは早く売ることができることです。早い場合、買取を依頼してから1週間以内に現金が振り込まれることもあります。デメリットは売却の価格が仲介の7割程度になることです。
買い手が見つかったら、売買契約を締結する
買主が見つかれば、売買契約を締結します。受任者の判断で契約は可能ですが、予め委託者や兄弟姉妹からの理解を得る方が望ましいでしょう。契約後に内輪のトラブルにより売買契約を解除するようなことになると、手付金の倍の金額を支払う必要があります。
不動産の引き渡し
不動産の引渡しの当日に、買主から売買代金を受領します。この際に、依頼した司法書士に必要書類の確認をしてもらい、不動産の名義を買主に変える登記手続きを行います。
信託抹消の手続きを行う
名義変更手続きと同時に不動産を信託状態から普通の不動産に戻し買主に引き渡すための信託抹消の手続きも行います。
信託用の口座に売買代金を入金
売主である子どもが受け取る売買代金は、信託用に開設した受託者名義の口座に入金してもらい、親の生活費や医療費のために使っていきます。
受託者の個人名義の口座に入れてしまうと、贈与税の対象になったり、他の兄弟から不信感を持たれたりすることがあるので、信託用であることが客観的に明白な口座に入金することが重要です。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
まとめ
家族信託とは、信頼のおける家族に自己の財産の管理や処分を依頼する仕組みのことです。
家族信託には、委託者、受託者、受益者の3者の立場の人が関わります。親である委託者が、信頼のおける子どもを受任者として、不動産や資産の管理を任せるのが一般的です。
また多くの場合、委任者自らが受益者となることで、不動産から発生する利益を得ることができます。
家族信託は、契約から成り立っているため、資産の運用を当初の思惑どおりに進めることができます。この先委託者が認知症になっても、資産運用の流れが故意に歪められることもありません。
ただし、それは、綿密な家族信託の設計と受任者の実直な資産運用の上で成り立っているということを失念してはいけません。
つ��まり、家族信託では、依頼する専門家の選定と受任者の選任が大きな鍵となるのです。