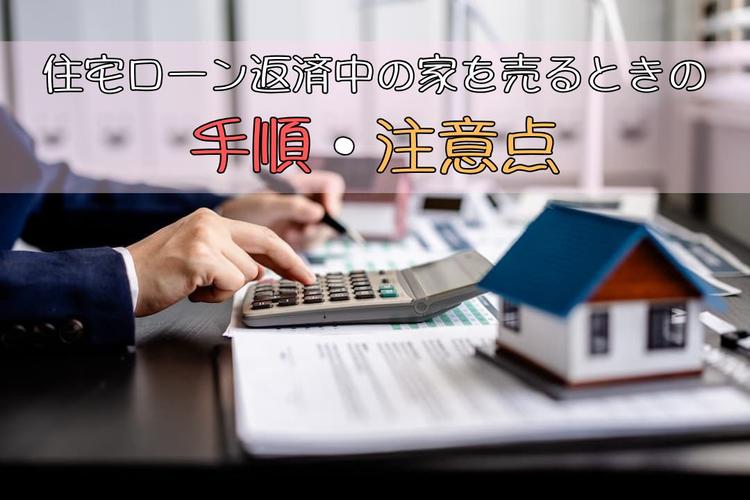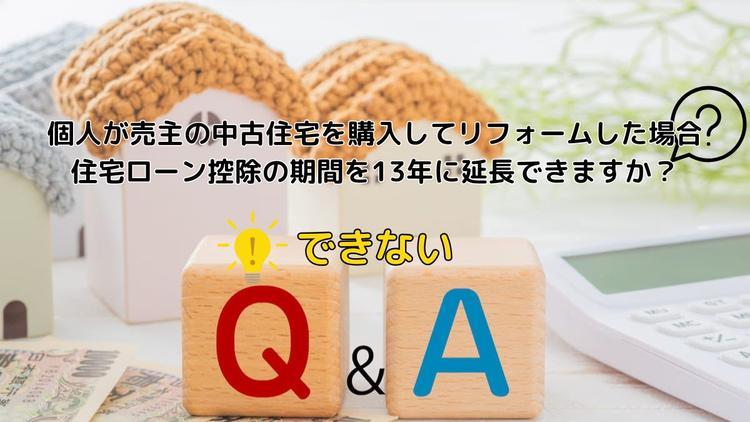住宅ローンは金利が数%変わるだけで返済額が大きく変わるため、返済中に少しでも金利を低くしたいと考える方も多いでしょう。
結論として、金利交渉ができる金融機関は多いですが、金利が下がるかどうかは交渉次第です。
この記事では、金利引き下げ成功のための交渉術や、成功しやすい状況、注意点について分かりやすく解説します。
住宅ローンの金利は交渉で下げてもらえる?
住宅ローン返済中に、収入が減少したり、支出が増えたりすることで返済が厳しくなることは十分に考えられます。
そのような場合、金利が少しでも下がると返済の負担を大きく軽減できます。
実際、住宅ローンを借りた後に交渉して金利を下げてもらうことはできるのでしょうか。
条件次第で交渉できる
少し前までは、住宅ローン返済中の金利引き下げは難しいケースがほとんどでした。
しかし、近年では借り換えが増えてきており、他の金融機関への乗り換えを防止するために金利引き下げに応じる金融機関も出ています。
金融機関にとって、住宅ローンが借り換えられると、受け取れたはずの利息収入が得られなくなってしまいます。
そのため、借り換えされて利息が受け取れないよりも、金利を引き下げた方がいいと判断する金融機関が増えているのです。
メガバンク・地方銀行・ネット銀行問わず、ほとんどの金融機関で金利引き下げ交渉自体はできます。
ただし、実際に金利を引き下げてもらえるかは交渉次第です。
フラット35など金利交渉できない住宅ローンもある
金利の引き下げについてはほとんどの金融機関で交渉できますが、一部の住宅ローンでは交渉できない場合もあります。
代表的なものが「フラット35」です。
フラット35は民間金融機関独自の金融商品ではなく、住宅金融支援機構が関わる住宅ローンであるため、個別の事情に応じて特定の人のみ優遇することはできません。
ただし、フラット35の返済が厳しくなったときの救済措置として、返済期間の延長や一定期間の返済減額、ボーナス払いの取りやめなどには対応してくれるので、相談するとよいでしょう。
なお、返済期間の延長や停止は、利息負担が増えトータル返済額が増えるというデメリットがあります。
フラット35の返済軽減を検討する際には、トータルの返済額も考慮し、借り換えを視野に入れるのも1つの方法です。
▼関連記事:住宅ローンの返済猶予は可能?(フラット35の返済猶予についても解説しています)
金利引き下げ時に再審査となるケースもある
実際に金利が引き下がるかどうかは、交渉次第です。
金融機関によっては、金利引き下げに際して再審査が必要となる場合があります。
再審査が必要なケースでは、それまでの返済状況や勤務状況、年収などがチェックされるので、不利にならないかを事前に確認し、対策しておきましょう。
金利を引き下げることで、金融機関が受け取る利息は少なくなります。
特に、すでに金利の低い住宅ローンで金利を下げることは、金融機関にとっても大きな判断になります。その点も考慮して交渉するようにしましょう。
住宅ローンの金利引き下げ交渉が成功しやすい状況とは
金利が引き下がるかは交渉次第ですが、成功の可能性が上がる状況はあります。
ここでは、金利引き下げ交渉が成功しやすい状況として以下の2つを紹介します。
- まとまった額の預金がある
- 借入時より収入が上がっている
それぞれ見ていきましょう。
まとまった額の預金がある
金融機関は審査時に、その人の信用性や返済能力の高さもチェックします。
金融機関の口座にまとまった額の預金があれば、返済能力が高いと判断され、金利交渉にも有利に働きやすくなるでしょう。
借入時より収入が上がっている
借入審査時よりも年収が上がっている場合は、そのこともアピールするとよいでしょう。
年収が上がれば返済が滞るリスクも減少し、返済能力が高くなったと判断されやすくなります。
ただし、金融機関は年収の高さだけでなく安定性も重視します。
「営業実績がよくたまたま昨年だけ高かった」といった状況では、返済能力が高いと判断されにくいので注意しましょう。
昇格・昇給など、継続的な年収の高さが期待できるなら、金利交渉にも有利に働きやすくなります。
住宅ローンの金利引き下げを成功させるための交渉術
何も準備せず金利交渉に臨んでもほぼ失敗します。
金利引き下げを成功させるには、しっかりとした下準備と交渉のコツを押さえることが欠かせません。
ここでは、金利引き下げを成功させるための交渉術として以下の3つを紹介します。
- 他行で借り換え審査の承認を得る
- 3月に交渉を持ち掛ける
- 希望の金利を明確に提示する
それぞれ見ていきましょう。
他行で借り換え審査の承認を得る
借り換えの本気度を伝えられるように、他行での借り換え審査の承認を得ておくとよいでしょう。
金融機関にとっては、借り換えされると利息が受け取れなくなるので、借り換えの意思表示があれば引き下げに応じてくれやすくなります。
ただし、「できればこの金融機関で継続したい」という姿勢で交渉に臨むことが大切です。
他行の方がメリットがあると強硬に主張すると、金融機関からの印象が悪くなります。
3月に交渉を持ちかける
交渉を持ち掛けやすいタイミングとしては、決算時期の3月がおすすめです。
金融機関にも営業目標があり、融資額などが設定されているケースが多いでしょう。
決算間際は目標達成のために新規借り入れや交渉が有利になりやすいといわれます。
また、この時期は販促のために優遇金利などのキャンペーンを打っている金融機関も多いので、交渉の材料としても活用できます。
希望の金利を明確に提示する
ただ金利を下げてほしいでは、金融機関も対応を検討しにくいものです。
明確に「○%に下�げてほしい」と交渉することで、金融機関も検討しやすくなります。
しかし、あまりに無茶な金利の引き下げを交渉しても拒否されるだけでしょう。
根拠となる数字をもとに、現実的な金利への引き下げを交渉することが重要です。
その金融機関の優遇金利や、借り換えを検討している他行の金利などを参考にすると金融機関も納得しやすなります。
優遇金利とは、一定の条件を満たした際に基準金利よりも引き下げられる金利幅です。ちなみに、基準金利から優遇金利を引いた金利が適用金利となります。金融機関ごとに公表されているので参考にするとよいでしょう。
借り換えを検討している金融機関の金利も目安の一つとなるので、借り換え審査時の資産で出た金利を交渉の材料にするのも1つの方法です。
住宅ローンの金利を交渉する際の注意点
金利交渉にあたっては注意すべき点がいくつかあります。
ここでは、金利交渉時の注意点として以下の3つを紹介します。
- 金利交渉が必ず成功するわけではない
- 強引に交渉し過ぎるのはNG
- トータルの返済額で判断する
それぞれ見ていきましょう。
金利交渉が必ず成功するわけではない
金利引き下げ交渉は必ず成功するわけではなく、交渉に応じてもらえないケースもあります。
また、金利引き下げ時には再審査が必要になるので、信用情報や年収、勤務先などが借入時よりも悪化していると、審査に通らない可能性もあるでしょう。
しかし、審査に失敗したからといってデメリットはほとんどありません。
交渉に失敗したからといって金利が上がることはなく、それまでどおりの返済が続きます。
さらに、交渉にあたって費用が請求されることもないので、チャレンジしてみるとよいでしょう。
返済が厳しく、金利が下がらないと厳しい場合には、返済プランの見直しを相談したり、他行への借り換えを視野に入れることをおすすめします。
強引に交渉し過ぎるのはNG
金利を下げるということは、金融機関にとって利益が減ることを意味します。
強引な交渉や一方的な無茶な要求をしても、金融機関は応じてくれないどころか、関係性が悪化する恐れもでてきます。
そのため、あくまで「その銀行で継続するための相談」という姿勢を忘れずに交渉しましょう。
トータルの返済額で判断する
金利の引き下げ交渉時には、引き下げられない代わりに金利タイプの��変更が提案されるケースもあります。
しかし、金利タイプが変わると目先の金利が変わっても返済総額が大きくなる恐れがある点に注意が必要です。
たとえば、固定期間選択型金利は当初の固定金利期間終了後に金利が大幅にアップし、返済の負担が今以上に大きくなるリスクがあります。
固定金利から変動金利に変更すると、金利は下がっても将来金利上昇のリスクが出てくるものです。
また、金利タイプの変更には一般的に手数料がかかるので、手数料まで含めたトータル額やリスクまで考慮して検討しましょう。
金利交渉は早めに行おう
金利交渉は検討しているけどタイミングに悩んでいる場合は、少しでも早い段階での交渉をおすすめします。
今後は金利が上昇する可能性がある
日銀は2024年に引き続き、2025年1月にも利上げ実施を決定しました。この影響で、一部の金融機関では基準金利が引き上げられる可能性があります。
その結果、2025年4月以降、変動金利が上がることが予想されています。
変動金利には5年ルールというものがあり、金利が上がっても5年間は返済額が変わることはありません。
しかし、金利が上昇すると返済額のうち金利部分が増え、元金返済部分が減少するため、結果として返済が遅くなる点には注意が必要です。
2025年1月の金融政策決定会合(日銀の政策委員会が金融政策に関わる事項の審議・決定する会合)では、さらなる利上げに前向きな意見も出ていることから、今後も利上げが実施される可能性があります。
将来の金利は正確に見通せないので上がらない可能性もありますが、わずかでも上がる可能性がある以上リスクに備えておくことが重要です。
▼関連記事:変動金利は一気に上がる?
金利上昇局面に強いのは固定金利
金利上昇局面では、変動金利・固定期間選択型金利は返済の負担が大きくなるリスクがあります。
一方、全期間固定金利は借り入れ当初に決まった金利が変動しないので、金利上昇リスクを避けることが可能です。
今後の金利上昇リスクへの考えや個々の状況によって、適切な金利タイプは異なるものです。
ライフプランを踏まえて長期的なシミュレーションをもとに、自分に合った金利タイプを選ぶようにしましょう。
変動金利より固定金利が先に上がるのが一般的
変動金利を選ぶ方の中には、変動金利が上昇したら固定金利に借り換えればいいと考えている方もいます。
しかし、この考えはあまりおすすめできません。
変動金利を選ぶ際には、こまめに繰り上げ返済する、一括返済できるように蓄えるなど、固定金利に借り換える以外の金利上昇リスク対策を講じておくことが大切です。
まとめ
住宅ローンの返済中であっても、金融機関に交渉して金利を引き下げてもらえる可能性があります。
しかし、実際に引き下げてもらえるかは交渉・再審査次第になってくるので、事前準備や交渉のコツを押さえて慎重に交渉しましょう。
仮に、交渉に成功しても希望まで引き下げてもらえる�とは限りません。
返済の負担を軽減したい場合は、借り換えコストまで含めてトータルの費用で比較し、メリットがあるなら借り換えを選択するのも1つの手です。
金利引き下げ交渉は失敗してもデメリットはないので、一度挑戦してみてはいかがでしょうか。