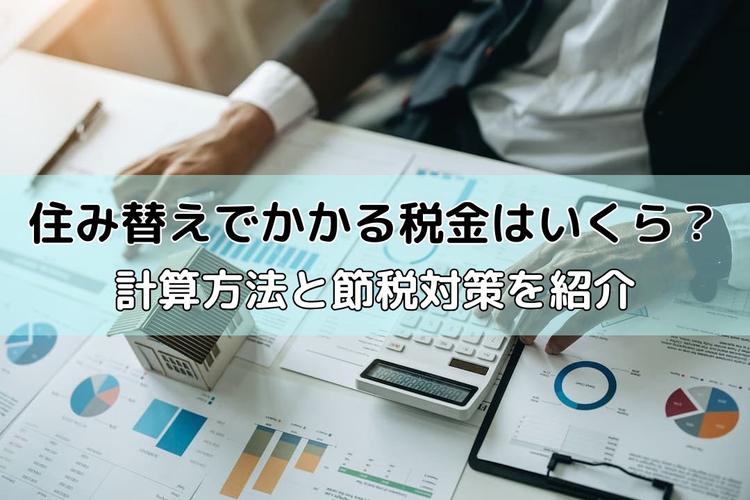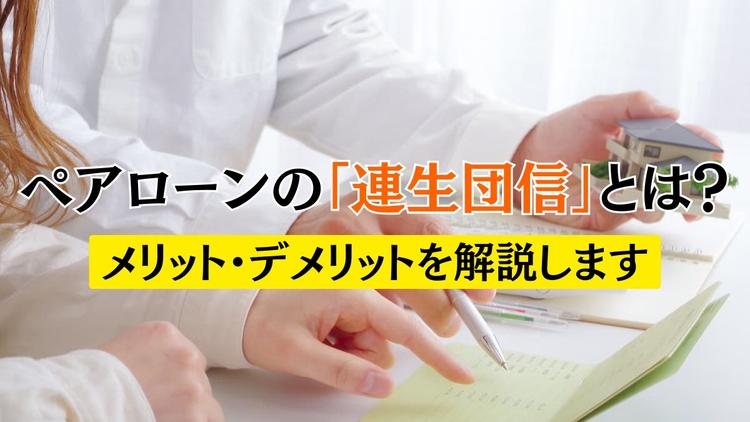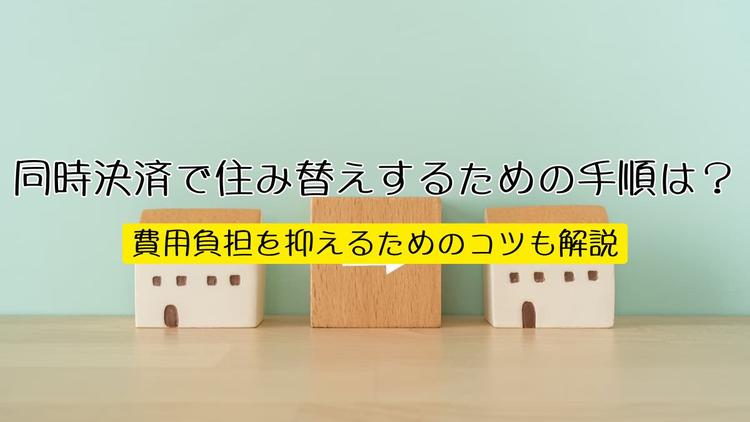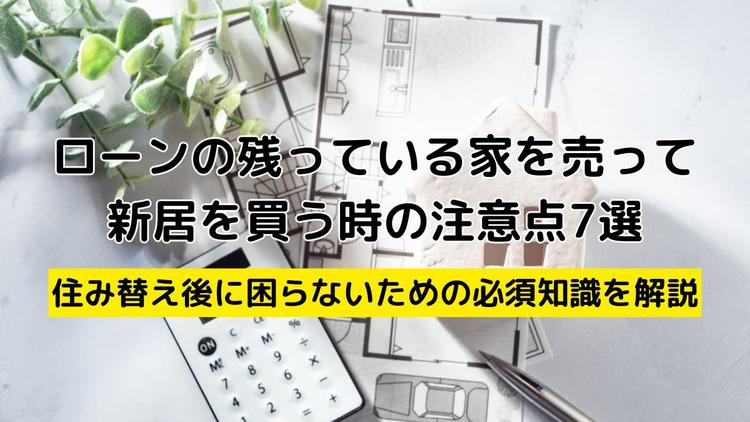家の住み替えでは「売却」と「購入」それぞれで税金がかかるため、税額を押さえておくことが重要です。
税金によっては特例や控除で節税できるものもあるので、節税対策まで理解しておくようにしましょう。
この記事では、住み替えにかかる税金の計算方法・節税対策、できるだけお金を手元に残すポイントについて解説します。
住み替えの際に家を売却して利益が出ると税金がかかる
住み替えでは、売却時と購入時で税金が発生するため、税金まで資金計画に含めておくことが大切です。
とくに、売却時の税金を考慮していないと、思ったよりも手元にお金が残らずに新居購入の資金が足りないといったことになりかねません。
住み替えでかかる主な税金は、以下の通りです。
| 売却 | 購入 |
| 印紙税 登録免許税(抵当権抹消) 譲渡所得税 | 印紙税 登録免許税(抵当権設定・所有権移転) 不動産取得税 |
売買契約書に必要な印紙税、不動産登記に必要な登録免許税、不動産取得税は基本的に必ずかかる税金です。
売却時の譲渡所得税は売却で利益が出た場合にのみかかり、特例控除を利用することもできるため、必ずしも課税されるわけではありません。
このように、必ずかかる税金と状況に応じてかかる税金とに分かれるため、違いを理解しておくことが重要です。
なかでも、譲渡所得税は税額が高額になりがちな税金です。
そのため、そもそも譲渡所得税が発生するのかと、発生した場合の計算方法も確認した上で住み替え計画を立てるようにしましょう。
譲渡所得については、下記ページのシミュレー��ターで簡易計算することも可能です。
家の売却でかかる税金の計算方法
家の売却でかかる3つの税金の計算方法は以下の通りです。
| 税金の種類 | 計算方法・目安額 |
| 印紙税 | 契約書に記載の金額(売却額)に応��じる 目安額:1万円~10万円 |
| 抵当権抹消登記 | 不動産個数×1,000円 ※別途司法書士費用が発生する |
| 譲渡所得税 | 譲渡所得×税率 |
ここでは、譲渡所得税の計算について詳しくみていきましょう。
譲渡所得税は、以下の2つのステップで計算します。
- 【課税譲渡所得の計算】売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
- 【譲渡所得税の計算】課税譲渡所得×税率
以下で、詳しい計算方法や税率を解説します。
課税譲渡所得の計算
課税譲渡所得とは、譲渡所得税の対象となる譲渡所得(売却の利益)のことです。
以下の計算式で求められます。
取得費とは、売却した不動産を購入した際にかかった費用のことです。
一方、譲渡費用は売却時にかかった費用であり、それぞれ主に以下のような項目が計上できます。
| 取得費(購入時の費用) | 譲渡費用(売却時の費用) |
| 不動産の購入額(減価償却費を差し引く) 仲介手数料 印紙税 登録免許税 不動産取得税 造成費用 測量費など | 仲介手数料 印紙税 立退料 解体費用 名義書き換え料など |
家を売却した価格から、上記の取得費・譲渡費用を差し引きます。
なお、建物取得費は購入費用から減価償却費を差し引かないといけない点に注意しましょう。
費用を差し引いた額から、さらに3,000万円特別控除などの控除分を差し引いた額が、課税対象となる譲渡所得です。
たとえば、以下の条件で売却したケースを計算してみましょう。
- 売却額:4,000万円
- 家の購入費用:5,000万円
- 減価償却費:2,000万円
- 購入時の諸費用:200万円
- 売却時の諸費用:150万円
家の取得費は減価償却を差し引くので、以下のようになります。
よって、控除を加味しない課税譲渡所得は
です。
家の売却の場合、購入時の価格よりも売却時の価格が低いケースでも、減価償却を考慮すると利益が出ることもあるので注意しましょう。
▼関連記事

課税譲渡所得の税率
課税譲渡所得を計算し、プラスとなった場合は譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税は以下の計算式で求めます。
譲渡所得税の税率は、以下の通りです。
| 所有期間 | 所得税 復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 | |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
所有期間5年以下の「短期譲渡所得」、5年超えの「長期譲渡所得」で税率が異なるので注意しましょう。
短期譲渡所得に区分されると、長期譲渡所得の2倍近い税額となるので、売却時には所有期間も考慮することが大切です。
所有期間は、売却した年の1月1日を基準に判断されます。
実際の所有期間が5年を超える場合でも、1月1日の時点で5年を超えていないと短期譲渡所得に区分されるので、5年ギリギリで売却する場合は注意しましょう。
条件を満たせば特例や控除の適用を受けられる
譲渡所得は「3,000万円特別控除」の要件を満たすことで、最大3,000万円差し引くことが可能です。
3,000万円特別控除の主な適用要件には、以下のようなものがあります。
- マイホームの売却である
- 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却
- 取り壊す場合は解体から1年以内かつ、住まなくなった日から3年以内の売却
- 他の特例を適用していない
- 親子や夫婦間など特別な関係での売却でない
3,000万円特別控除が適用できれば、譲渡所得3,000万円以下であれば譲渡所得は発生しません。
また、譲渡所得税には3,000万円特別控除以外にも「10年超所有軽減税率の特例」「買換え特例」など、さまざまな特例が用意されているので、要件を確認して検討するとよいでしょう。
買換え特例については、次の章で詳しく解説するので参考にしてください。
家の住み替えで利用できる特例とは?
家の住み替えにともなう売却では、買替え特例の適用を検討できます。
特定のマイホームを買い換えたときの特例とは
買換え特例とは、正式には「特定のマイホームを買い換えたときの特例」と呼ばれます。
この特例では、住み替えの売却にともなう譲渡所得税を、購入した新居の売却時まで繰り延べすることが可能です。
例えば、住み替えの売却で譲渡所得が2,000万円発生したとします。
このとき、買い替え特例を適用することでその年の譲渡所得税は発生しなくなります。
ただし、将来買い替えで購入した新居を売却した際に、繰延した2,000万円の譲渡所得がプラスされて、譲渡所得税が発生するのです。
買換え特例は、あくまで税金の繰り延べであり、3,000万円特別控除のように、税金が免除・減額になる特例ではない点に注意しましょう。
しかし、将来売却しないのであれば税金が発生しないため、大きな節税が見込めます。
買換え特例を検討する場合は、将来の売却まで見込んで適用すべきかを判断することが大切です。
他の特例を利用するのとどちらがお得か比較することが大切
買換え特例を適用すると、3,000万円特別控除は適用できません。
譲渡所得が3,000万円以下であれば、将来税金が発生するリスクもない3,000万円特別控除の方が適しているでしょう。
しかし、譲渡所得が高額になる場合は買換え特例の方がその年の税負担を抑えやすくなります。
ただし、買換え特例は将来の税負担が高額になる恐れもあるので、慎重に検討しなければなりません。
3,000万円特別控除についても、10年超所有軽減税率の特例とは併用できても住宅ローン控除とは併用できないという特徴もあります。
住み替えの新居を住宅ローンで購入するケースでは、住宅ローン控除が適用できないと税負担が大きくなる可能性もあるでしょう。
どの特例を適用したほうがいいかは、念入りにシミュレーションして検討することが大切です。
家の住み替えでできるだけお金を残すためのポイント
家の住み替えでできるだけお金を残せれば、生活費に充てたり新居の予算を増やしたりなど、選択肢も増えてきます。
ここでは、住み替えでできるだけお金を残すためのポイントとして、以下の3つを解説します。
- 長期的に最も節税効果の高い控除や特例を選ぶ
- あらかじめ住み替えの流れと税金を支払うタイミングを理解しておく
- 信頼できる不動産会社を見つける
長期的に最も節税効果の高い控除や特例を選ぶ
前述のとおり、譲渡所得税にはさまざま特例があり、どれを選ぶかによって税負担も大きく異なります。
買換え特例は、今の税負担を軽減できても、将来税負担が増える可能性があるでしょう。
3,000万円特別控除と住宅ローン控除が適用できないため、所得額によっては譲渡所得税よりも所得税に軽減を図ったほうがお得になるケースもあります。
どの特例を適用したほうがお得になるかを、長期的なシミュレーションで検討することが大切です。
自分で特例の適用やシミュレーションが難しいという場合は、税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
あらかじめ住み替えの流れと税金を支払うタイミングを理解しておく
住み替えで発生する税金の支払いタイミングは、それぞれ異なります。
住み替えを検討する際には、住み替え全体の流れと、税金の支払いタイミングまでを把握しておくことが大切です。
家の購入、売却それぞれの大まかな流れと税金の支払いタイミングは、以下の通りです。
| 購入 | 売却 |
| 新居選び 住宅ローン仮審査 売買契約(印紙税の支払い) 住宅ローン本審査 決済(登録免許税の支払い) 入居(不動��産取得税の支払い) | 不動産査定 不動産会社と媒介契約 売却活動 売買契約(印紙税の支払い) 決済・引き渡し(登録免許税の支払い) 確定申告(譲渡所得税の支払い) |
また、住み替えは、売却を先にしてから購入する「売り先行」、新居を購入してから売却する「買い先行」、同時に行う「同時進行」の3つのパターンに分かれます。
例えば、売り先行の場合は、上記の売買契約か引き渡し後に、新居選びや新居の売買契約がスタートします。
反対に、買い先行の場合は、新居の入居後に本格的な旧居の売却活動がスタートするという流れです。
一般的には、売り先行か買い先行のどちらかになるケースがほとんどですが、どちらで進めるかによっても流れや支払いタイミングは異なってきます。
住み替えの流れや税金のタイミング・額については、不動産会社の担当者や税理士などとよく相談しながら計画を立てることが大切です。
信頼できる不動産会社を見つける
手元に少しでもお金を残したいなら、税金を抑えるだけでなく高値で売却することが重要です。
家の売却は、不動産会社の力量に左右されます。
信頼でき、かつ高値で売却してくれる不動産会社を見つけることで、手元に残るお金を多くできるでしょう。
不動産会社を選ぶ際には、できるだけ多くの不動産会社の査定を比較することが大切です。
また、比較する際には査定額だけでなく以下のような項目も含めて検討するようにしましょう。
- 不動産会社の実績
- 対応エリア
- 評判や口コミ
- 査定時の対応
- サービス
- 担当者の人柄
住み替えの場合、売却と購入を同じ不動産会社にしておくと、日程調整などがスムーズに進みやすくなります。
大切な家の売却と新生活のための新居購入という大事な部分を任せることになるため、信頼できる不動産会社を選べるようにしましょう。
イエウリなら、不動産会社の査定額比較が効率よく行えます。
不動産会社に個人情報を伏せて査定することができるため、営業電話の心配がなく、より多くの会社の査定額を比較できます。
また、住み替え物件の購入なら仲介手数料不要な「イエカイ」で費用を抑えることもできるので、ご検討ください。
住み替えでかかる税金に関するよくある質問
最後に、住み替えでかかる税金に関するよくある質問をみていきましょう。
住み替えすると確定申告する必要がある?
確定申告が必要なケースは、以下の通りです。
- 譲渡所得が発生し譲渡所得税が課税される
- 特例を適用する(適用すれば譲渡所得税が発生しない場合も含む)
- 譲渡所得は発生しないが、損失が出た場合の特例を適用する
譲渡所得税が発生するケースでは、確定申告が必要です。
各種特例の適用は確定申告で行うため、仮に適用すれば譲渡所得税が発生しないケースでも、特例適用のための確定申告が必要な点に注意しましょう。
また、譲渡所得がマイナスの場合でも、所得税などの軽減が見込める特例もあります。
マイナスでも確定申告することでお得になるケースもあるので、検討するとよいでしょう。
確定申告や特例の適用に不安がある方は、税理士に相談することをおすすめします。
住み替えの税金はいつ払う必要がある?
それぞれの税金の支払いタイミングは以下の通りです。
- 印紙税:売買契約時に収入印紙を購入
- 登録免許税:決済時または各種登記手続き時
- 不動産取得税:�購入後半年~1年後に自治体から通知される
- 譲渡所得税:売却した年の翌年の確定申告時
譲渡所得税は、売却した年の翌年2月16日から3月15日に行う確定申告で納税するので、忘れずに準備しておきましょう。
まとめ
住み替えにかかる主な税金は以下の通りです。
- 印紙税
- 登録免許税
- 譲渡所得税
- 不動産取得税
なかでも、譲渡所得税は利益が発生した場合のみかかる税金のため、計算方法やタイミングを押さえておくようにしましょう。
また、譲渡所得税は3,000万円特別控除などの特例で節税が見込めるので、特例までチェックしておくことが大切です。
家の住み替えは、不動産会社のサポートが重要になってきます。
今の家を少しでも高く売れる、信頼できる不動産会社を選ぶことが、住み替え成功のポイントです。
できるだけ多くの不動産会社を比較し、あなたにぴったりの不動産会社を選ぶようにしましょう。