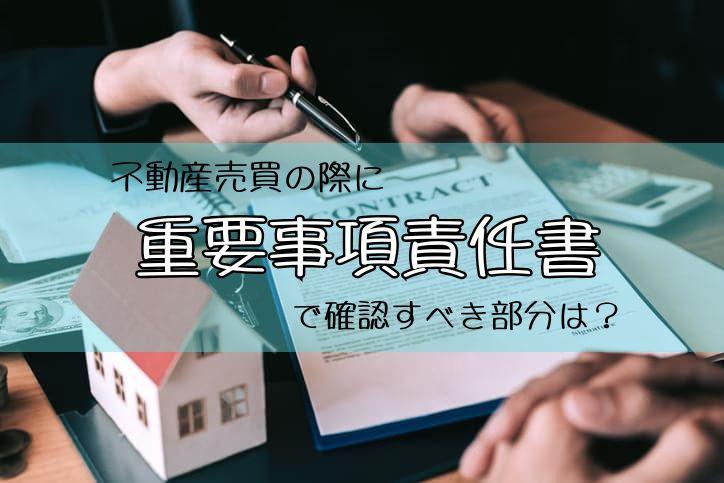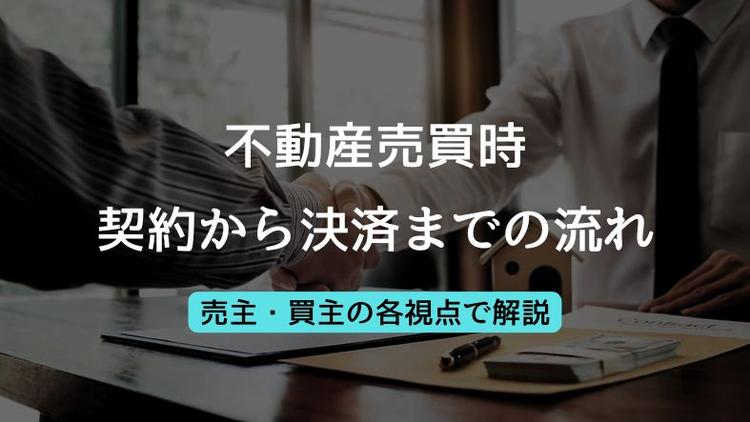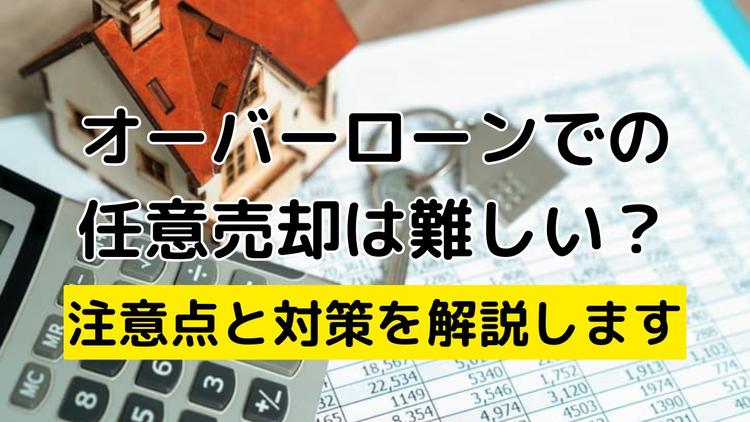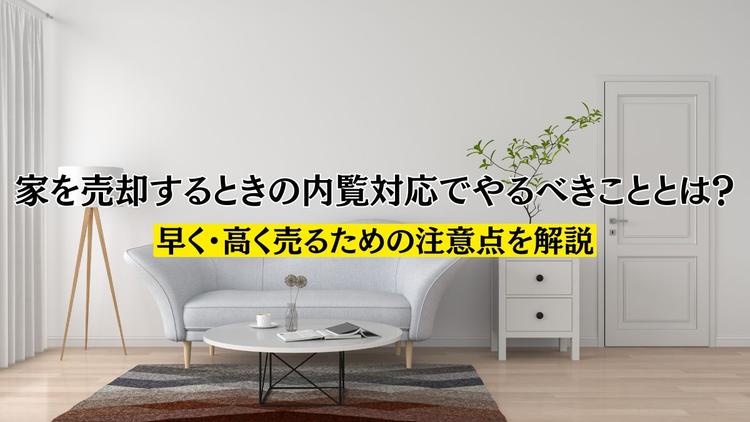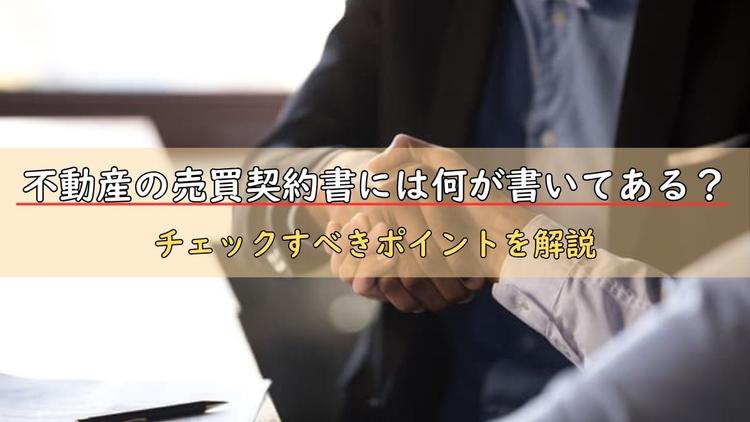不動産を売買する際には重要事項説明書について内容の説明を受けるかと思いますが…素人でもしっかりと理解できるものなのでしょうか?
難しいイメージがあるのは確かです。ただし、内容が理解できない時は正直に「分からない」と伝えてしまって問題ないですよ。
そうなんですね。なんだか堅苦しそうな印象があったので、その場の雰囲気にのまれてしまいそうで不安でした。
大切なのは、内容をしっかりと把握する事です。後から「知らなかった」は通用しないので、責任をもって臨みましょう。
そうですよね。そんなことにならないように、最低限の準備はしておきたいです!
重要事項説明書のポイントや注意点を事前に把握しておけば、普段不動産に触れることのない方でも内容を理解できるようになります。早速解説していきましょう。
重要事項説明書とは?
不動産を売買するとき、不動産会社より重要事項説明書について説明と交付を受けることになりますが、重要事項説明書とはどのようなものなのでしょうか。
不動産売買時に必ず説明&交付しなければならない
重要事項説明で購入する物件の状態を宅建士が買主に説明し、その後契約に進みます。
まず、重要事項説明書は売買する不動産に関する情報や適用される法律、金銭のやり取りに関する内容などを記載するもので、契約が成立する前に交付・説明しなければならないこととされています1。
重要事項説明は売買契約前にすればよく、重要事項説明と売買契約が同日である必要はありません。
むしろ、売主・買主が重要事項説明の内容を冷静に判断して売買契約の判断をするためには、重要事項説明と売買契約は少し間を空けた方がよいともいえます。
業者間は重要事項説明を省略可能
2017年4月に宅建業法が改正され、買主が宅建業者の場合は重要事項説明を省略できることとなりました。
買主が不動産会社の場合、重要事項説明書の内容について説明を受けなくても、自分で調査できるからです。
ただし、重要��事項説明書の説明は不要であるものの、記名押印は必要となります。
難しい箇所もあるが内容をよく確認しよう
重要事項説明書は、物件の情報の他、普段聞きなれない都市計画法や建築基準法を始めとするさまざまな法律について記述されており、その説明を受けます。
実際のところ、難しいと感じる箇所もあるかと思いますが、聞いた内容を後で「そんなの知らなかった」などと話しても通用しません。
説明を聞いて分からないと感じる場所、不安に感じる場所はその場で質問するなどして、しっかり確認しておくことが大切です。
重要事項説明の流れ
重要事項説明は以下のように手続きが進みます。
なお、重要事項説明書については、以下のページで様式例を確認できます。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
基本情報の確認
まずは基本的な情報の確認を行います。
具体的には、重要事項説明書を作成した宅地建物取引士や宅建業者の情報、取引態様(仲介や代理など)などの説明を受けます。
仲介を担当する業者がきちんとした業者なのか、設立してどれくらい経っているのかなどに注目するとよいでしょう。
物件の確認
次に、取引する物件の確認です。
取引する土地や建物について、所在地や面積、地目等が間違いないか、登記簿謄本や公図、測量図などと照らし合わせながら確認していきます。
法令等の制限の確認
日本全国、不動産は都市計画法や建築基準法など各種法令の制限を受けることになります。
例えば、都市計画区域内には用途地域を定めることとされていますが、「第一種低層住居専用地域」に指定されたら10m(もしくは12m)以上の高さの建物を建てることはできませんし、「工業専用地域」に指定された住宅を建てることはできなくなります。
ここでは、こうした法令による制限を確認することになります。
▼関連記事

インフラの確認
土地に水道は通っているのか、土地の中に降った雨水はどうやって排水するか、電気やガスはどうなっているかなどインフラについて確認します。
下水道の通っている地域であれば、建物を建てるときに土地の中に水道管を引き込む必要がありますし、下水道がない地域であ��れば合併浄化槽を設置しなければなりません。
また、周囲に電線の通っていないような場所だと、そもそも建物を建てるのが非常に難しくなることもあります。
契約条件の確認
不動産をいくらで売買するのか、その資金を住宅ローンを使って用意する場合、どこの銀行を利用するのか、お金はいつ支払う予定なのかなどを確認します。
なお、住宅ローンを利用する場合、売買契約後に仮に住宅ローンが否決となった場合に、白紙解約となる「住宅ローン特約」を特約に盛り込むかどうか、盛り込むのであれば期限をいつまでに設定するかも確認しておく必要があります。
(マンションの場合)権利関係や管理について確認
マンションの場合、他の住人がおり自分一人で管理するわけではありません。
権利関係がどのようになっているのかや、管理がどのようになされているかについて確認することになります。
修繕積立金や管理費はいくらなのか、過去にどのような修繕を行ったかなどを記載します。
告知書の確認
中古住宅を売却する場合、建物がどのような状態にあるのかを告知するものが告知書です。
例えば、住宅設備機器が故障していたり、雨漏りしていたりする箇所があれば記載します。
これらを記載せずに売買契約した場合で、売買契約後にそのことが発覚すると、買主は売主に対して「契約不適合責任」にもとづいて追完請求(補修などを求めること)や損害賠償請求できることになっています。
売主としても「知らせてしまうと売買にマイナスとなるのではないか」という意識が働いてしまうことがありますが、ここで告知しておかなければ後々もっと面倒なことになる可能性があります。
売主としては、自分が知っている不具合についてはしっかり記載しておくことが大切です。
▼関連記事

売主と買主による署名押印
重要事項説明書を交付し、重要事項説明を行なったら、売主と買主それぞれが署名押印することになります。
なお、先に売主か買主のどちらかの説明と署名押印が済んでいるケースもあります。
重要事項説明を聞くときに押さえておきたい4つのポイント
重要事項説明時に説明する内容についてお伝えしましたが、ここではその内、特に注意しておくべきポイントをお伝えします。
①共有持分や抵当権を確認しよう
「物件についての確認」の際には、共有持分や抵当権をしっかり確認しましょう。
共有持分
共有持分とは、1つの不動産を複数の人が所有することで、「2分の1」など持分が記載されています。
土地そのものの持分が間違っていないかもそうですが、道路の持分についてもよく確認しておきましょう。
例えば、売買する不動産の前にある道路が周辺の住人数人で共有持分を持つ道路の場合、その道路のうちどの程度の割合を持つか確認します。
周辺の住人6人で共有するのであれば「6分の1」などと記載されているはずです。
ここの認識がずれていると、将来さらに分筆が進み接道義務を満たさなくなるなど、後々大きな問題となることもあるため注意が必要です。
抵当権
また、不動産に抵当権が設定されていないかも確認します。
抵当権とは、住宅ローンを組むときなどに設定するもので、「借入人がローンを延滞したら差し押さえできる権利」です。
不動産に抵当権が残ったまま売買されると、次の所有者は「無関係の前の所有者がローンを延滞したという理由で差し押さえられた」ということになりかねません。
▼関連記事

②どんな建物が建つか確認しよう
「法令上の制限」を確認する際には、どんな建物が建つかを確認しましょう。
まず用途地域ごとに設定される「建ぺい率の上限」や「容積率の上限」をチェックします。
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合、容積率とは敷地面積に対する延床面積の割合のことを指します。
例えば、40坪の土地で容積率80%であれば32坪までしか建てられません。
また、先ほども触れましたが、「第一種低層住居専用地域」や「工業専用地域」など、用途地域ごとに建てられる建物の種類が決まっています。
自分の建てたい建物が、該当の用途地域で建てられるかどうかを確認する必要があります。
例えば、同じ50坪の土地であっても、上限の容積率が60%の場合もあれば200%の場合もあります。
前者の場合、延床面積30坪までしか建てられませんが、後者であれば100坪まで建てられることになります。
30坪だと戸建住宅用地やちょっとした事務所程度の用途が精一杯ですが、100坪まで建てられるのであれば、アパートやマンションを建てることも考えられます。
③災害関係の情報を確認しよう
「法令上の制限」の説明の最後には災害関係の情報も記載されています。
「土砂災害警戒区域」や「津波災害警戒区域」などです。
買主としては、それを知った上で購入するのかどうかを検討する必要があるでしょう。
一方、売主としては、実際に過去の大雨のときにどのような状況だったかなど伝えることで、買主に安心材料を与えることもできます。
④告知書の内容を確認しよう
先述の通り、告知書の内容によって、後で契約不適合責任にもとづいて損害賠償請求などなされるかが決まります。
契約不適合責任とは「契約の内容に不適合していることに対する責任」であり、より告知書の内容が重要となります。
▼関連記事

なお、重要事項説明書についてチェックしておきたいポイントは、不動産ジャパンのリストを利用すると便利です。
出所:不動産ジャパン 「不動産基礎知識・買うときに知っておきたいこと」 8-2 重要事項説明のチェックポイント
不動産売買時の重要事項説明に関する注意点
最後に、不動産売買時の重要事項説明に関する注意点をお伝えします。
説明を聞けば必ず契約しないといけないわけではない
売買契約前には重要事項説明書を交付し、その内容について説明する必要がありますが、重要事項説明を聞いたからといって必ずしも売買契約を締結しないといけないわけではありません。
重要事項説明の内容に不安な点があるのであれば、重要事項説明を聞いた後「一度持ち帰って検討する」こともできるのです。
ちなみに、売買契約書にサインしてしまうと、解約時に手付金を放棄しなければならないなど、責任が生じることになる点に注意が必要です。
住宅ローン特約(融資特約)は義務ではない
不動産売買時には、住宅ローン特約、つまり、売買契約後に買主の住宅ローンが否認となった場合に白紙解約とするという特約をつけることができますが、これは売主の任意でつけているのであり、義務ではありません。
売主としては、売買契約後、どのような理由にせよ白紙解約されてしまえば、売却活動が振り出しに戻ってしまうためデメリットが大きいです。
ただし、多くの買主が住宅ローンを利用するため、住宅ローン特約を拒否すると買手が見つかりにくくなります。
「契約前に事前審査の状況を仲介会社から聞く」といった方法で、白紙解約になりにくくするといった方法が現実的な対策です。
申し込み情報に虚偽や間違いのない場合、本審査でローンが否認されるケースは3~5%程度だと言われています。
事前審査の段階で複数の金融機関の審査をクリアしている買主であれば、より安心して契約できるでしょう。
売主の契約不適合責任(瑕疵担保責任)も交渉できる
先述の通り、売主は売却する不動産について、買主に対して契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負うことになります。
一方、「契約不適合責任を追及できるのは引き渡しから3カ月以内」など期限を定めることができます。
いずれも、買主と売主がそれぞれ納得できる内容となっているかを確認しておくようにしましょう。
なお、瑕疵担保責任が契約不適合責任に置き換わったのは2020年4月の民法改正からで、比較的最近のことです。
不動産売買時の特約をどう定めるかなどについては、不動産会社とも相談をしてしっかり確認しましょう。
まとめ
不動産売買時の重要事項説明書についてお伝えしました。
重要事項説明書は、普段聞きなれない法律に関する説明などもあるため、説明を聞くときは難しく感じることも少なくありませんが、大切な内容が記載されているものなのでしっかり確認しておくようにしましょう。
その際には、本記事でお伝えしたチェックポイントや注意点を参考にしてみてください。