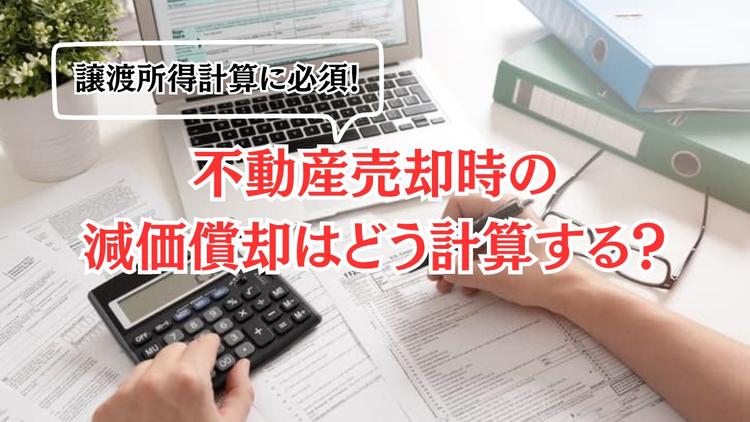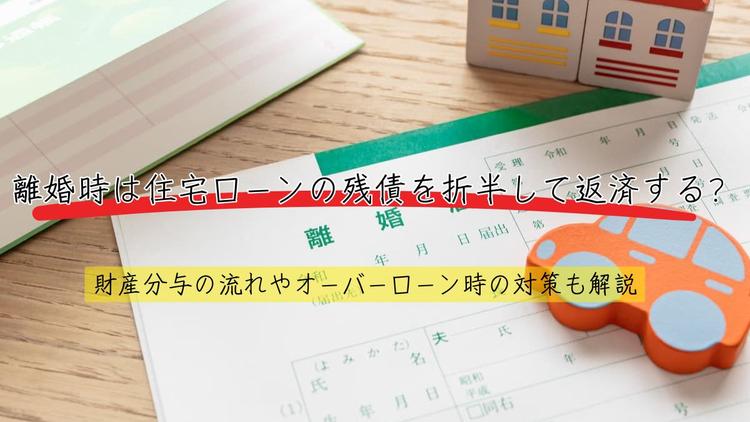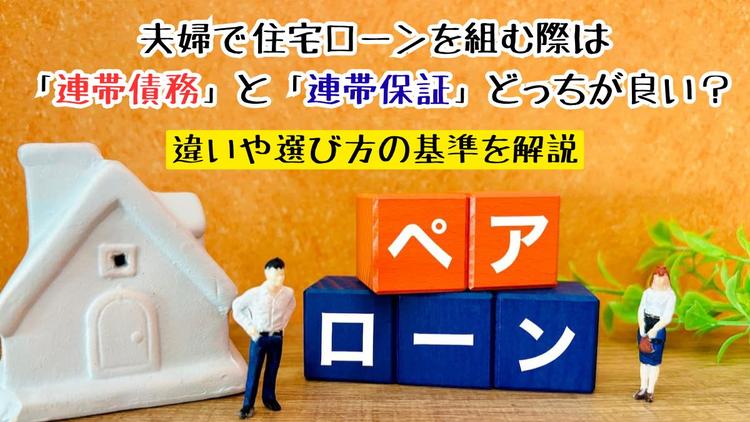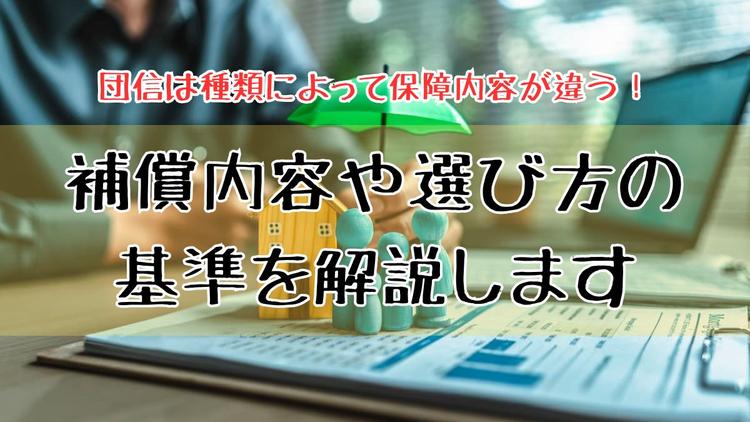不動産の売却で利益が生じると、譲渡所得税を納めることになります。この譲渡所得税を計算する際に、大きなポイントとなるのが、建物の減価償却です。
経年によって建物の価値が下がったために、取得費用からその減少分を差し引かないといけないのです。不動産の売却で適切な額の税金を納付するために、建物の減価償却の計算方法について理解を深めましょう。
この記事では、譲渡所得税について解説してから減価償却の計算を解説しています。減価償却の計算方法のみを知りたい場合は、下記リンクをクリックして解説の項目にジャンプできます。
譲渡所得税と減価償却の関係
減価償却は、不動産を売却した際に課税される譲渡所得税を算出する際に用います。
減価償却の計算方法を理解するために、まず不動産の譲渡所得税の仕組みを押さえておきましょう。
譲渡所得税とは
一戸建てやマンションなどの不動産を売却して利益があると、譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得税は分離課税といって所得税などの他の所得とは別に計算をすることになりますが、確定申告の手続きは、他の所得と合わせて行います。
譲渡所得税の税率
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。
不動産を売った年の1月1日の時点で、所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。
所有期間は、所有した日の翌年の1月1日で1年とカウントします。
「購入してから丸5年経った後、新年を迎えてから売却すれば長期譲渡所得になる」と覚えておけば良いでしょう。
税率は次のとおりです。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 | 30% | 9% |
このように、短期譲渡の方が長期譲渡所得よりも税率が高くなっています。
なお、現在、所得税には復興特別所得税2.1%が加算されるために、実務上の計算は、次のようになります。
- 長期譲渡所得 15.315%(所得税)+ 5%(住民税)
- 短期譲渡所得 30.53%(所得税)+ 9%(住民税)
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は、次の計算式によって算出します。
課税譲渡所得金額×税率=譲渡所得税
譲渡価格は、実際に不動産を売却した金額です。
この他の項目については、順に解説していきます。
取得費とは
取得費とは、売却した不動産を買い入れたときの購入代金や仲介手数料の合計額です。
ただし、建物の取得価格は経年によって価値が下がるので減価償却相当額を控除します。
この減価償却が、この記事のメインテーマになりますので、次の項で詳しく解説をします。
取得費に含まれる主なものは次のとおりです。
ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。
(1) 土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得を含む)したときに納めた登録免許税(登記費用を含む)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
(2) 借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料
(3) 土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
(4) 土地の取得に際して支払った土地の測量費
(5) 所有権などを確保するために要した訴訟費用
(6) 建物付の土地を購入して、その後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用
(7) 土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
(8) 既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金
出所:No.3252 取得費となるもの|国税庁タックスアンサー
なお住宅の購入時、不動産会社に仲介手数料を支払っていれば取得費として計上でき、売却時のものは譲渡費用として扱われます。
取得費の求め方
取得費は、土地と建物では考え方が異なります。
建物は、経年によって価値が低下するので、購入金額から減価償却分を差し引きます。
土地は、経年によって価値が下がることがないので、購入金額がそのまま適用されます。
土地建物を一体で購入した場合
建売住宅のように、土地と建物をセットで購入した場合、それぞれの価格がいくらなのかわからない方もいるでしょう。
この場合、契約書や領収書に記入された消費税額で確認可能です。
消費税は、「消費」に対して課せられる税金であり、土地の売買は「消費」には該当しません。
つまり、土地と建物を一体で購入しても、消費税は、建物価格のみに課せられているのです。
このため、それぞれの価格は次の計算式によって算出することができます。
- 建物価格=消費税額÷購入時の消費税率+消費税額
- 土地価格=購入金額-建物価格
過去、消費税率は、次のように変遷しています。
- 1989年(平成元年)4月1日~1997年(平成9年)3月31日……3%
- 1997年(平成9年)4月1日~2014年(平成26年)3月31日……5%
- 2014年(平成26年)3月31日~2019年(令和元年)9月30日……8%
- 2019年(令和元年)10月1日~……10%
たとえば、1998年に5,000万円で購入した建売住宅の契約書に「うち消費税100万円」と記されていたら、この当時の消費税率は5%ですから、それぞれの価格は次のように算出できます。
- 100万円÷5%+100万円=2,100万円……建物価格
- 5,000万円-2,100万円=2,900万円……土地価格
標準建築価格から算出する
契約書や領収書が見当たらない場合、標準建物価格から算出するという方法があります。
建物の標準価額は、国税庁のホームページに示されていますから、これをもとにして算出します。
たとえば、平成20年に建築された木造住宅の1平方メートル当たりの価額は、156,000円とされています。
120平方メートルの住宅では、次のように算出できます。
- 120平方メートル×156,000円=1,872万円
これにより、建物の価格は1,872万円として譲渡所得税の計算を進めていきます。
取得費用が分からないと税額が高くなる
上述で紹介した取得費用の算出方法は、「実態法」と呼ばれるもので、実際に不動産を取得した金額を基本にして算出します。
しかし、どうしても取得費用の手掛かりがない場合は、「概算法」によって計算をすることになります。
これは、譲渡収入金額の5%を取得費用と見なすものです。
この方法を用いた場合は、必ず譲渡所得が発生することになります。
現在の市況では、購入価格よりも低い価格で売却するケースが多数あります。
したがって、そもそも譲渡所得税が発生しないことも少なくなく、課せら�れたとしても少額になるのが一般的です。
このため概算法を用いると、本来、取得費用が分かっていれば納付しなくて済むケースでも、税金を納付することになります。
節税の観点からも、マイホームを購入した際は、契約書や領収書を大事に保管することがとても重要です。
譲渡費用とは
譲渡費用とは、譲渡のために直接要した費用で、次のようなものが該当します。
ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。
(1) 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
(2) 印紙税で売主が負担したもの
(3) 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
(4) 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
(5) 既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金
(6) 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
出所:No.3255 譲渡費用となるもの|国税庁タックスアンサー
このように、譲渡費用とは売却で直接かかった費用をいいます。
したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用には該当しません。
なぜ分離課税になっているのか
ところで、同じ所得でありながら、どうして譲渡所得は他の所得と分離して申告するのでしょうか。
その理由は、所得税の税率にあります。
次に示すのが、所得税の速算表です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
給与所得や事業所得を対象にした所得税は、累進課税となっているために、所得額が上がると、税率も高くなります。
たとえば、課税所得額が400万円の会社員が適用される税率は20%ですが、もし不動産の譲渡所得が分離課税でなければ、不動産を売却した年の税率がたちまち40%になることもあり得るのです。
一般の所得と異なり、不動産の譲渡所得は一時的なものであり、高率の税負担を強いる��のは、あまりにも納税者の負担が大きいことから、不動産の譲渡所得は分離課税で申告をするようにしているのです。
減価償却の計算方法とは
不動産の譲渡所得税の計算の対象となるのは土地と建物です。
減価償却は、このうち建物のみに適用されます。
土地は、経年によって価値が下がるということがないので、取得費は、購入したときの金額がそのまま適用されます。
それでは、譲渡所得税における減価償却の計算方法について解説をしていきましょう。
減価償却の計算式
減価償却は建物の取得費の計算をする際に用います。
取得費とは、売却対象の不動産を購入したときの金額です。
ただし、経年によって建物の価値が下がっているので、当時の購入金額をそのまま適用するのではなく、経年による減価償却分を差し引きます。
具体的には、次の計算式を用います。
償却率とは
償却率は、建物の法定耐用年数を基本にします。
法定耐用年数
法定耐用年数は構造別に次のように定められています。
- 木造……22年
- 軽量鉄骨造……27年
- 鉄筋コンクリート造 ……47年
ただし、住宅のような非事業用の建物については、建物へのダメージが少ないことから、耐用年数を1.5倍にすることが可能なので、税制上は次の耐用年数になります。
- 木造……33年
- 軽量鉄骨造……40年
- 鉄筋コンクリート造……70年
「非事業用」かつ「取得後に賃貸などの収益用途に使わない」下記のようなケースで適用可能です。
- 自己居住用の住宅(マイホーム)
- セカンドハウス(別荘など�)で収益目的で使っていないもの
- 家族や親族が無償で使っている住宅(事業用でない)
償却率
償却率は、居住用の建物では定額法を用いるため、毎年均等な金額で償却していくことになります。
建物の耐用年数から導き出した償却率は、それぞれ次のようになります、
- 木造……0.031
- 軽量鉄骨造……0.025
- 鉄筋コンクリート造……0.015
なお、経過年数は1年単位で計算をします。
所有期間が6カ月以上は年数が繰り上げられ、6カ月未満は切捨てして計算します。
減価償却費のシミュレーション
たとえば木造住宅を5,000万円で購入して、そのうち建物の費用が2,000万円だった場合、これを15年後に売却すると、減価償却は次のようになります。
これにより取得費を算出します。
※購入時に発生した諸費用(仲介手数料や印紙税など)があれば、これに加算します。
課税譲渡所得金額のシミュレーション
それではこれに基づき課税所得金額を算出してみましょう。
この住宅が4,500万円で売却できたとします。
このとき、譲渡費用が200万円かかりました。
この計算により、5,000万円で購入した家が、元の金額��よりも安い4,500万円で売却をしたのに、税金の計算上は137万円の利益を得たものとして課税されることが分かります。
譲渡所得税額のシミュレーション
このケースでは、長期譲渡所得が適用されるので、税額の計算は次の通りです。
- 所得税:137万円×15.315%=約21万円
- 住民税:137万円×5%=約7万円
- 合計:約28万円
これにより、不動産の売却によって、約28万円の譲渡所得税が課せられます。
中古住宅だとどうなる
1995年1月に新築された木造住宅を、2009年4月1日に3,000万円(内建物は2,000万円)で購入して、2019年12月1日に2,800万円で売却した場合、どのように譲渡所得税を算出すればいいのかをみていきましょう。
経過年数
購入してからの経過年数は、10年8カ月ですから、月数を繰り上げて11年とします。
減価償却の算出
11年間経年したことにより、約614万円価値が減少したと見なす計算です。
取得費の算出
- 2,000万円(取得金額)-614万円(減価償却)=1,386万円
- 1,000万円(土地の購入費用)+1,386万円(建物の購入費用)=2,386万円
3,000万円で購入した住宅ですが、譲渡所得計算上の取得費は2,386万円として計算します。
また実際の計算では、取得時に発生した諸費用をここに加算します。
譲渡所得金額の算出
譲渡費用を200万円と想定して計算をしてみましょう。
譲渡所得税の算出
11年所有していますから、長期譲渡所得の税率で計算をします。
- 214万円×15.315%=約33万円(所得税)
- 214万円×5%=約11万円(住民税)
- 約33万円+約11万円=44万円(合計)
これにより、約44万円の譲渡税が課せられることになります。
マイホーム売却の特別控除とは
マイホームを売却して、譲渡所得が発生しても、特別控除によって、所得税が課せられないことがあります。
3,000万円の特別控除がある
マイホームを売って譲渡所得が発生した場合、最高で3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
特例を受けるための条件
3,000万円の特別控除を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3) 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
(4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
出所:No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁タックスアンサー
マイホームに実際に住んでいなくても、住まなくなって3年経過する年の年末までに売却をすれば、特別控除の適用が受けられます。
たとえば、転勤で住まなくなった家を貸家に出している場合でも適用されます。
ただし、建物の維持管理が困難だといった理由で解体をしてしまうと、解体の日から1年以内に譲渡契約を結ばなければこの特例は適用できません。
また、更地にした土地を遊ばせておくのがもったいないからと、貸駐車場にしてしまうと、たとえそれが短期間であっても、3000万円控除の特例はまったく適用されないので注意が必要です。
住宅ローン控除との併用ができない
とても節税効果の高い3,000万円特別控除ですが、住宅ローン控除と併用することができないので、新居を購入するためにマイホームを売却した場合は注意が必要です。
住宅ローン控除を適用する場合、この年の前後2年間は、3,000万円控除が適用されません。
反対に3,000万円控除を適用してしまうと、初年度から3年間は住宅ローン控除が適用されなくなります。
▼関連記事:住み替え時は住宅ローン控除と3000万円控除が併用できない。どちらがお得かシミュレーションしてみよう
軽減税率の特例
マイホームの所有期間が10年を超えていれば、「3,000万円の特別控除の特例」を適用した後の課税長期譲渡所得金額に対して、次の軽減税率を適用することができます。
| 課税長期譲渡所得金額 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 6,000万円までの部分 | 10% | 4% |
| 6,000万円を超える部分 | 15% | 4% |
買換えの特例
マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームの買換えをした場合は、譲渡価額が1億円以下で、所有期間10年超、居住期間10年以上であれば、その譲渡益の課税を、将来売却するときまで繰り延べる特例が受けられます。
ただし、この場合「3,000万円の特別控除の特例」及び「軽減税率の特例」は、適用されません。
まとめ
譲渡所得税に係る減価償却の計算は、建物の取得費を現在の価値に換算するものです。
この計算を省略して、購入当時の取得金額のままで計算をすると、過少申告になるおそれがあるので注意が必要です。
また、減価償却の計算には、購入当時の正確な取得金額を把握しておく必要があります。
取得金額の手掛かりがまったく存在しない場合は、取得費を実情よりも過少に評価することになり、本来よりも高い額の納税をすることになります。
住宅を購入した際は、将来の売却に備えて、契約書や領収書をしっかりと保管しておきましょう。