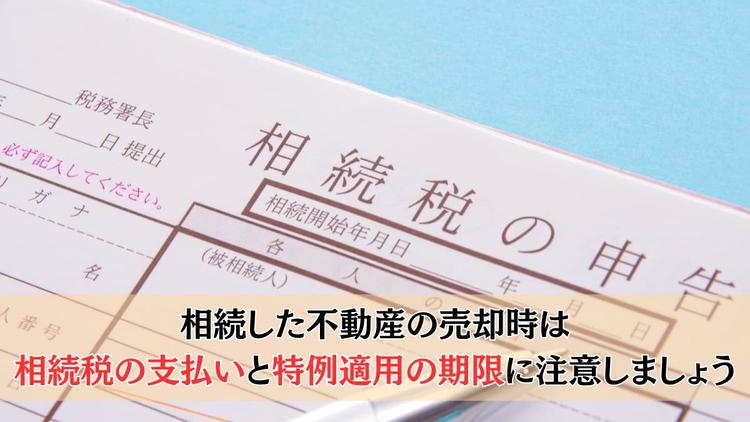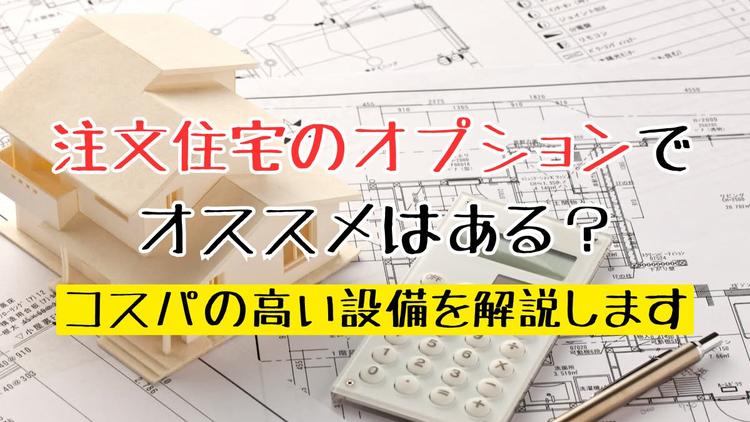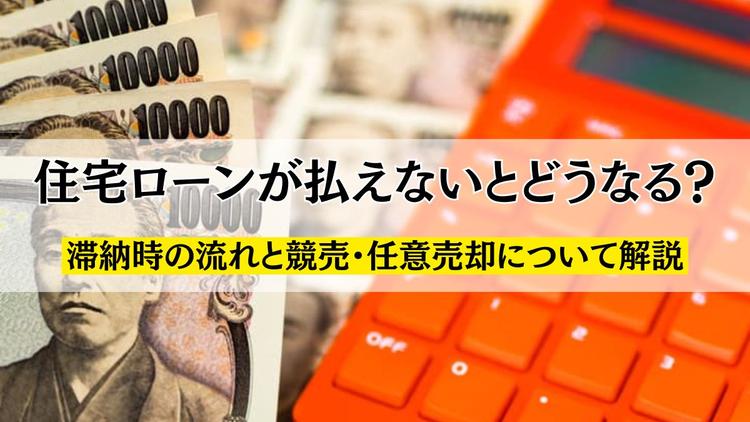フルローンを組めば、物件価格の全額を住宅ローンでまかなうことができ、いわゆる「頭金」を自己資金で用意する必要はありません。
ただし、物件の売買契約時には「手付金」を支払う必要があります。手付金は売買契約時に売主に支払うものであり、契約時点では住宅ローンの融資はまだ実行されないため、別途資金を用意する必要があります。
自己資金での準備が難しい場合は、親族からの借り入れや諸費用ローンなどで対応することになります。
手付金は、引き渡し時(残代金決済時)に売買代金の一部として充当されるのが一般的です。
手付金は売買代金の一部です。例えば3,000万円の家を購入する際、売買契約時に手付金として300万円を現金で支払い、残りの2,700万円は住宅ローン実行のタイミングで支払うといった流れになります。
そのため「手付金が戻ってくる」と表現されることもありますが、正確には戻るのではなく、代金の一部にカウントされる形です。
金融機関は物件の「担保価値」に基づいて融資額を決めます。この担保価値に対してどれだけ貸し出すかを示す指標が「LTV(ローン・トゥ・バリュー)」であり、一般的に100%ぴったりのフルローンは認められにくいからです。
「3,000万円の家をフルローンで買う」と言われる場合でも、実際には契約時に300万円ほどの手付金を現金で一時的に支払い、残り2,700万円を住宅ローンでまかなうというケースが多く見られます。
ただし、最近は諸費用込みでオーバーローン(物件価格を超える金額の融資)を認めている金融機関もあり、手付金として前払いしていた額が融資実行時に残るケースもあります。
そもそもフルローンにおける手付金とは?
フルローンにおける手付金の意味や支払いタイミングを解説します。フルローンでの手付金の利用を検討している方は確認しておきましょう。
- 売買契約を証するために買主が売主へ支払うお金
- フルローンで手付金が決済(住宅ローン実行)のタイミングに戻る(残る)ケースがある
売買契約を証するために買主が売主へ支払うお金
手付金は、契約の証拠となり、売り手に安心感を与える役割を果たします。
具体的には、手付金を支払うことで買い手は購入の意思を示し、売り手は契約の成立を確認できます。また、手付金は契約解除時の条件にも関わり、買い手が契約を破棄すると手付金を失い、売り手が破棄すると手付金の倍額を返す必要があります。
フルローンで手付金が決済(住宅ローン実行)のタイミングに戻る(残る)ケースとは
フルローンで住宅を購入する場合でも、売買契約時には通常、手付金を売主に支払う必要があります。
この時点では住宅ローンはまだ実行されないため、一時的に自己資金などで手付金を準備する必要があります。
引き渡し(残代金の決済)時に住宅ローンが実行され、物件価格の全額が売主に支払われる際、先に支払った手付金は売買代金の一部として充当されるのが一般的です。
ただし、以下のような状況では手付金部分が手元に戻る形で住宅ローンを利用できる場合があります。
- 売買契約時:親戚、知人などから手付金を借りる
- 残代金決済・引き渡し時:オーバーローン(物件の残代金以上の融資)が認められている金融機関で、手付金額を��含めた融資を実行してもらう
- 融資されたお金で物件の残代金や諸費用を振り込んだ後、手付金部分が手元に残るため、借りた分を返済する
なお、住宅ローンで物件価格は全額まかなえたとしても、登記費用、仲介手数料、火災保険料などの諸費用はローンに含められないことがあるため、別途資金計画が必要です。
また、フルローンを利用すると、自己資金の持ち出しは少なく済む一方で、借入額が大きくなる分、毎月の返済額や総返済額は増加します。長期的な家計への影響も見据えて、無理のない借入額と返済計画を立てることが重要です。
フルローンにおける手付金の費用相場
手付金の費用相場を解説します。売主が一般の個人と宅建業者によって金額が異なるため、手付金を支払う前に確認しておきましょう。
- 売買代金の5~10%が一般的
- 売主が宅建業者なら売買代金の20%が上限
売買代金の5~10%が一般的
手付金の相場は、物件価格の5〜10%とされています。例えば、3,000万円の物件なら150万〜300万円が目安です。
なお、手付金の額は売主と買主が話し合って決めるため、事前によく相談したうえで金額を設定しましょう。
売主が宅建業者なら売買代金の20%が上限
売主が不動産会社(宅地建物取引業者)である場合、手付金の上限は売買代金の20%と法律で定められています。
これは、買主が過度な負担を強いられないようにするための規制です。例えば、3,000万円の物件であれば、手付金は最大で600万円です。
20%を超える額を請求されても支払う必要がないため、売主が宅建業者の場合は覚えておきましょう。
契約解除になった場合の手付金はどうなる?
フルローンでの手付金は契約後に返ってきますが、契約締結しなくても以下に該当すれば返ってきます。
- 住宅ローン特約が適用されると戻ってくる
- 売主都合で契約解除されたときは倍額で戻ってくる
それぞれを詳しく解説します。
住宅ローン特約が適用されると全額戻ってくる
住宅ローン特約とは、ローンの審査が通らなかった場合に契約を白紙解除にして、支払った手付金を全額返してもらえる特約です。
つまり、ローンが組めなかったときのリスクを軽減するための仕組みです�。この特約が契約に含まれていれば、ローン審査が不承認となった際でも手付金を取り戻せます。
万が一ローンが通らなかった場合でも手付金を失う心配がなくなるため、住宅購入の際は必ず付けておきましょう。
売主都合で契約解除されたときは倍額で戻ってくる
手付金を支払って売買契約を結んだ後は基本的に無償で契約解除できません。具体的には、買主都合での解除時は手付金を放棄し、売主都合で解除する場合は受け取った手付金の倍額を買主へ提供して契約解除できます。
これは、契約を一方的に解除する際のペナルティとして標準的な不動産売買契約書に定められています。例えば、買主が100万円の手付金を支払っていた場合、売主は200万円を返金する必要があります。
ただし、この手付金の倍返しが適用されるのは、買主がまだ契約の履行に着手していない段階に限られます。
「履行」とは、契約内容を実際に進めることを指します。具体的には、売主が所有権移転の準備を進めることや買主が代金の支払いを行うことなどが含まれます。
実務上は、手付解除が可能な期間が売買契約書に明記され、この期限を過ぎると手付解除できなくなるので注意しましょう。
フルローン利用時に手付金が支払えない場合の対処法
フルローン利用時に手付金が支払えない場合は以下の対処法を試しましょう。
- 手付金の減額を交渉する
- 親族や知人に借りる
- つなぎ融資を利用する
それぞれを詳しく解説します。
手付金の減額を交渉する
まず売主に手付金の減額を交渉してみましょう。手付金は通常、購入価格の一部として前もって支払う金額ですが、売主との話し合いで金額を下げてもらえる可能性があります。
交渉の際には、誠実な態度で自分の状況を説明し、売主に理解を求めることが大切です。また、売主にとっても早期に買い手が見つかることはメリットとなるため、柔軟に対応してもらえる場合があります。
親族や知人に借りる
親族や知人に借りる方法は、金融機関からの借入れと比べて難易度が低く、柔軟な返済条件や低い利息で対応してもらえる可能性が高いです。
ただし、金銭の貸し借りは人間関係に影響を及ぼすことがあります。借用書を作成し、「残代金決済のタイミングで返済する」など具体的な返済意思を見せるなどして、信頼関係を損なわないよう注意しましょう。
つなぎ融資を利用する
つなぎ融資とは、住宅ローンが正式に実行される前に必要な資金を一時的に借り入れる方法です。これにより、手付金や契約金などの初期費用をカバーできます。
具体的には、金融機関やローン会社が提供する短期の融資を利用し、住宅ローンが実行された際にその融資を返済します。ただし、つなぎ融資には通常、別途の利息や手数料が発生するため、事前に詳細を確認し、総合的な返済計画を立てることが重要です。
また、金融機関によってはつなぎ融資を提供していない場合もあるため、利用を検討する際は各機関のサービス内容を確認しましょう。
▼関連記事:手付金がない時はどうする?
フルローン時の手付金以外に準備しておくべき初期費用
手付金を含めた物件の購入代金はフルローンで賄えますが、不動産購入時は以下の初期費用がかかる場合があります。
- 事務手数料・保証料:借入額の2~3%
- 登記費用:10万円前後
- 火災保険・地震保険:10万~50万円
- 引越し費用・家具購入:5万~30万円
- 固定資産税の精算:数万円~数十万円
- 仲介手数料:売買代金の3%+6万円+消費税
- 印紙税:1~3万円前後
- 不動産取得税:30~50万円
なお、これらの費用も住宅ローンに含められる場合もありますが、金融機関や利用するローン商品、借入額によってはできないこともあります。
事務手数料・保証料:借入額の2~3%
住宅ローンに関連する「事務手数料」と「保証料」は特に重要な費用です。
事務手数料は、ローンの手続きや書類作成などにかかる費用です。手数料額は金融機関によって異なり、定額で数万円の場合や借入額の数%と設定される場合があります。例えば、定額型では3万〜5万円程度、定率型では借入額の1〜3%が相場とされています。
一方で保証料は、万が一ローンの返済が困難になった際に保証会社が金融機関に返済を肩代わりするための費用です。この保証料も金融機関やローンの種類によって異なります。
一括前払いの場合、借入額の2〜3%が目安です。例えば、2,000万円の借入れであれば、40万〜60万円程度となります。
登記費用:20万円前後
不動産を購入すると、所有権を公的に記録するための登記手続きが必要です。中古物件では「所有権移転登記」「抵当権設定登記」が、新築物件では「所有権保存登記」も必�要です。
登記には登録免許税や司法書士への報酬がかかります。登録免許税は、登記の際に国に納める税金で、建物の所有権保存登記は通常0.4%、所有権移転登記(中古物件)は2.0%、抵当権設定登記は0.4%の税率が適用されます。
ただし、新築住宅の所有権保存登記は令和8年3月末までの特例措置により0.15%に軽減されるケースがあります。例えば、3,000万円の物件の場合、登記費用の総額は状況により数十万円程度になることがあります。
また、登記を依頼する司法書士への報酬も発生します。報酬額は登記の種類や依頼先によりますが、一般的に5~15万円程度かかることが多いです。住宅ローンを利用する場合は「抵当権設定登記」も必要になり、その分の報酬も追加されます。
登記費用は物件価格や融資の有無によって異なり、購入後に想定外の出費とならないよう、事前に見積もりを確認し、資金計画を立てることが重要です。
土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減
| 登記の種類 | 本則 | 軽減措置 |
| 所有権の移転の登記 | 2.0 % | 1.5 % |
| 所有権の信託の登記 | 0.4 % | 0.3 % |
住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減
| 登記の種類 | 本則 | 軽減措置 |
| 所有権の保存の登記 | 0.4 % | 0.15 % |
| 所有権の信託の登記 | 2.0 % | 0.3 % |
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
抵当権の設定の登記は本則では融資額の0.4%が適用されますが、軽減措置が適用されている期間内は0.1%となります。
引用:国税庁「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」
司法書士への報酬
「司法書士への報酬」は、登記手続きを専門家に依頼する際の費用です。物件の価格や地域によって異なりますが、一般的には5万円から10万円程度が目安とされています。
一般的には住宅ローンの融資を受ける際、金融機関が指定した司法書士に抵当権設定手続きの委任を求められるため、その他の登記も合わせて依頼する形になります。
物件の評価額や依頼する司法書士によって金額が変動するため、具体的な金額は事前に確認しておきましょう。
火災保険・地震保険:10万~50万円
生活する上で万が一に備えて加入するのが火災保険と地震保険です。
これらの保険料は建物の構造や所在地、補償内容によ�って異なります。一般的には、火災保険料は10万円から50万円程度、地震保険料は5万円から10万円程度が目安とされています。
特に、住宅ローンを利用する場合、火災保険への加入が必須となるケースが多いです。地震保険は任意ですが、地震大国である日本では加入を検討すべきでしょう。
保険料は一括で支払う場合が多いため、資金計画の段階でこれらの費用を考慮しておくことが大切です。また、保険会社やプランによって保険料は変動するため、複数の保険会社から見積もりを取り、比較検討しておきましょう。
引越し費用・家具購入:5万~30万円
引越し費用や新しい家具の購入費用は見落としがちですが重要なポイントです。
引越し費用は、移動距離や荷物の量によって異なりますが、一般的には5万円から30万円程度かかります。また、新居に合わせた家具の予算を見込んでおくと安心です。
固定資産税の精算:数万円~数十万円
固定資産税の精算は、売主がその年に支払った固定資産税を引き渡し日以降の期間に応じて買主が負担するためのものです。
例えば、引き渡し日が8月1日であれば、8月1日から12月31日までの分を日割りで計算し、売主に支払います。この金額は物件の評価額や引き渡し時期によって異なりますが、数万円から数十万円程度が目安とされています。
精算金額は売買契約書に記載されているため、契約時に確認しておきましょう。
仲介手数料:売買代金の3%+6万円+消費税
仲介手数料とは、不動産会社に支払う報酬であり、売買価格に応じて以下のように上限額が定められています。
| 売買価格 | 仲介手数料の上限額 |
| 200万円以下 | (売買価格×5%)+税 |
| 200万円超~400万円以下 | (売買価格×4%+2万円)+税 |
| 400万円超 | (売買価格×3%+6万円)+税 |
※800万円以下の物件では、不動産会社は売主・買主の合意を得た上で30万円+税の仲介手数料を上限とすることが可能。
例えば、2,000万円の物件では以下の計算となります。
仲介手数料は法律で上限が定められており、これを超える請求は違法です。不動産購入時には仲介手数料を含めた初期費用をしっかりと把握し、計画的に準備しましょう。
印紙税:1~3万円前後
印紙税とは、売買契約書や工事請負契約書などの文書に課される税金で、物件価格に応じて以下のように税額が異なります。
| 記載された契約金額 | 税額 | 税額(軽減税率) |
| 10万円を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
出典:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
不動産売買契約では、契約書に印紙を貼って印紙税を納めます。一般的に買主が負担することが多いですが、売主と分担するケースもあります。
納付しないと契約が無効になるわけではありませんが、税務調査で本来の税額の3倍の過怠税が課される可能性があるため注意が必要です。
契約締結時に現金で用意し、スムーズに対応できるようにしましょう。住宅購入を検討する際は、印紙税を含めた初期費用を把握しておくことが大切です。
不動産取得税:30~50万円
不動産取得税とは、不動産を取得した際に一度だけ課される税金です。税額は、固定資産税評価額を基に以下の計算式で求めます。
土地や住宅の税率は原則4%ですが、2027年3月31日までに取得した住宅や住宅用地については3%に軽減されます。さらに、住宅用地に該当する場合、評価額の2分の1が課税標準額となる特例があります。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の宅地を購入した場合、課税標準額は1,000万円(2,000万円×1/2)となり、税率3%を掛けると、「1,000万円×3%=30万円」となります。
また、新築住宅を取得した場合、一定の条件を満たせば課税標準額から軽減措置を受けられます。具体的には、新築住宅なら1,200万円、認定長期優良住宅なら1,300万円が控除されます。
不動産取得税は高額になる可能性があるため、購入前にしっかりと計算し、予算に組み込むことが大切です。
フルローン時の手付金に関するよくある質問
フルローン時の手付金に関するよくある質問をご紹介します。
フルローンでの住宅購入時、手付金は現金で必要?
フルローンを利用して住宅を購入する場合でも、手付金は自己資金として現金および預貯金で用意する必要があります。
通常、手付金は売買契約の締結時に支払うのが原則であり、住宅ローンに組み込むことはできません。
そのため、フルローンを利用する場合でも、契約時に支払う手付金は自己資金で準備する必要があります。
もし手付金を用意するのが難しい場合は、売主に減額交渉をする、またはつなぎ融資を活用するといった方法を検討しましょう。
また、親や祖父母から住宅購入の資金援助を受けた場合、贈与税の基礎控除とは別に「住宅取得等資金贈与の非課税制度」を利用できます。
これは、マイホームの新築や購入、リフォームに充てるために贈与を受けた資金について、一定額まで贈与税がかからない特例制度です。
- 耐震・省エネ・バリアフリー等の一定基準を満たす住宅の場合:最大 1,000万円(時期によって変動あり)
- それ以外の一般住宅の場合:最大 500万円
▼関連記事:住宅の購入で親からの金銭支援を受けたら特例が利用できる!上限金額や必要な手続きを解説
手付金が戻ってこないケースはありますか?
買主都合で契約を解除した場合、手付金は返金されません。
例えば、他の物件に興味が移り、現在の契約を解約するケースが該当します。この場合、手付金は売主に渡り、買主には戻ってきません。
手付金を支払った後に契約解除する際は、住宅ローン特約が適用される場合を除いて返金されないため、契約するかどうか慎重に検討しましょう。
契約解除したい場合はいつまでにすればいいですか?
相手が契約の履行に着手するまでであれば契約解除できます。
具体的には、売主が物件の引き渡し準備を始めたり買主が手付金以外の代金を支払ったりした時点などです。このタイミングを過ぎると手付金を放棄しての解約は難しくなります。
また、契約書には「手付解除期日」が定められていることが多く、この期日を過ぎると手付金を放棄しての解約ができなくなります。そのため、契約前に手付解除期日を確認し、解約を検討する際は早めに行動することが重要です。
まとめ
フルローンでの手付金の意味や支払いタイミングなどを解説しました。
フルローンでの手付金は、売買契約締結後に買主が売主へ支払う費用であり、契約を証する意味を持っています。売主都合や買主都合で契約解除する場合、手付金の放棄や倍額提供などのペナルティが課せられるため、十分に意味を理解したうえで支払うことが大切です。
もし、手付金を用意できないのであれば、売主へ減額交渉したり親族に借りたりする必要があります。それでも用意できない場合はつなぎ融資を利用してさらに金融機関から借りなければなりません。
その他にも、事務手数料や登記費用、仲介手数料など、さまざまな費用がかかるため、不動産売買を検討している方は、ぜひこの記事を参考にして売買活動を進めてみましょう。