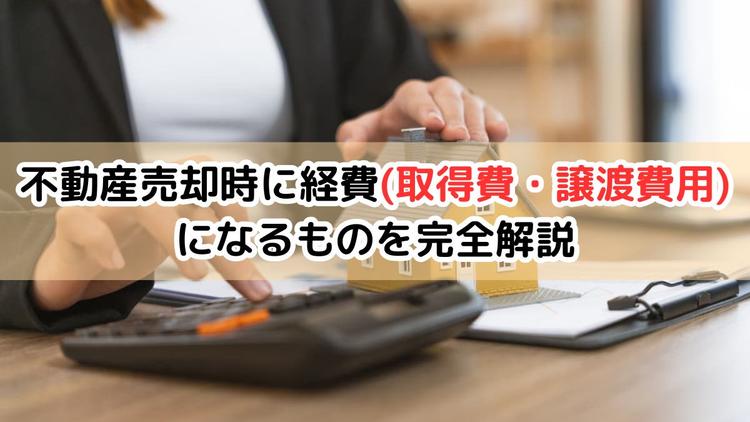山林にも固定資産税は課税されます。
面積が大きいことから固定資産税もそれなりの額になるのではと、これから相続したり所有する予定がある方にとっては不安を抱く場合もあるでしょう。
しかし、実際のところ山林の固定資産税はかなり低く、数千円から数万円ほど、中にはゼロ円というケースも少なくありません。
この記事では、山林の固定資産税の確認や納付方法、固定資産税の負担を抑える方法など解説します。
山林の固定資産税はいくら?
固定資産税とは、毎年1月1日時点の不動産の所有者に課せられる税金です。
マイホームや土地ではおなじみの税金ですが、山林も固定資産税の対象となります。
山林の固定資産税は安い
山林の固定資産税は、1ヘクタールあたり年間数千円ほどと安いのが特徴です。
高くても数万円程度で収まることがほとんどでしょう。
ちなみに、一般的な戸建ての固定資産税が年間10~30万円ほどであることからも、山林の税額の安さが分かります。
山林と宅地の固定資産税の違い
固定資産税の計算方法自体は、山林と宅地に違いはなく以下の計算式で求められます。
固定資産税課税標準額とは、固定資産税を算出する際の基となる金額のことです。
通常は、固定資産税評価額と同額になりますが、不動産によっては軽減措置が適用されることもあります。
山林の固定資産税が宅地よりも安くなる理由が、評価額の低さです。
固定資産税評価額は一般的に公示地価の70%ほどを目安に設定されますが、山林の評価額は宅地よりもかなり低くなります。
そのため、固定資産税も宅地に比べて低くなってくるのです。
ただし、登記簿上の地目が山林であっても、実際には建物が建っている、都市部に近いなどで宅地として評価されるケースもあります��。
宅地として評価されると評価額が一気に跳ね上がり、税額も高くなるので注意しましょう。
なお、固定資産税評価額は、毎年送付される固定資産税納税通知書や自治体の窓口で確認できるので、一度確認してみるとよいでしょう。
山林の固定資産税のシミュレーション
以下のケースで山林の固定資産税をシミュレーションしてみましょう。
- 公示地価:10円/1㎡あたり
- 土地面積:5ヘクタール(5万㎡)
公示地価による山林の地価は10円×5万㎡=50万円です。
固定資産税評価額は公示地価の70%が目安となるため、固定資産税評価額は50万円×70%=35万円となります。
このため、税率が1.4%のとき固定資産税額は、35万円×1.4%=4,900円と計算できます。
山林の固定資産税を支払わなくてもいいケースとは?
山林の固定資産税は、以下の2つのケースでは課税されません。
- 課税標準額が30万円以内のケース
- 保安林に指定されているケース
それぞれ詳しく見ていきましょう。
同一市区町村内の所有物件の課税標準額が30万円以内のケース
固定資産税には、課税標準額が一定以下になると課税されないとされる免税点制度が設けられており、以下の金額以下では課税されません。
- 土地:30万円未満
- 建物:20万円未満
そのため、山林の固定資産税課税標準額が30万円未満であれば、固定資産税は課税されません。
ただし、固定資産税評価額は同一市区町村内の不動産の合計額である点には注意しましょう。
山林だけの所有で山林の課税標準額が30万円未満であれば、固定資産税は課税されません。
しかし、同一市区町村内に山林だけでなく宅地も所有している場合は、山林の評価額が20万円でも、宅地の評価額が1,000万円では免税とはならず、合計の1,020万円が課税の対象となるのです。
保安林に指定されているケース
保安林とは、水源かん養機能維持(水源地周辺の森林を整備・保全することで、安全で良質な水を安定的に供給する機能を維持すること)や土砂災害防止を目的として、都道府県知事または国土交通大臣が指定する山林です。
保安林に指定されると伐採や開墾・整地などに制限がかかる一方、各種税金などで優遇措置が適用されます。
この優遇措置に固定資産税も含まれおり、保安林は固定資産税が課税されないのです。
山林の固定資産税の納付方法
山林の固定資産税は、他の固定資産税同様に毎年4~6月頃に送付される固定資産税納税通知書で納付します。
一般的な支払い時期と方法は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 支払い時期 |
|
| 支払い方法 |
|
自治体によって支払い時期や方法は異なるので、納付書で確認するようにしましょう。
また、山林を他の所有者と共有している場合は、持分に応じて共有者で按分して納税します。
納税通知書は代表者のみに送付されるので、代表者が先に払って徴収したり、最初に全員から徴収したりして納税するようにしましょう。
納税通知書が送付されたからといって、代表者のみが納税義務を負うわけではない点には気を付けなければなりません。
山林の固定資産税の負担を抑える方法
山林の固定資産税の負担を抑える方法として以下2つの方法を検討できます。
- 活用する
- 売却する
それぞれ見ていきましょう。
活用する
固定資産税自体の節税にはつながりませんが、山林を活用し収益化することで税負担の相殺を見込めます。
山林であれば、太陽光発電システムの設置やキャンプ場運営、林業経営または貸出を検討できるでしょう。
ただし、山林の立地やニーズなどを踏まえて活用方法を検討しなければ、コストだけかかって収益化できない恐れもあるので注意が必要です。
また、活用方法によっては地目の変更に伴って固定資産税評価額が上がってしまい、税額が増える可能性もある点は気を付けましょう。
売却する
山林は�固定資産税だけでなく維持管理費もかかるため、活用せずに所有しているだけならマイナスばかり大きくなってしまいます。
活用の予定がないなら売却することで、税負担も管理の負担からも解放されるでしょう。
しかし、山林は買い手が限定される点には注意が必要です。
不動産会社によっては山林の取扱い自体してくれない場合もあるので、山林の取扱がある信頼できる不動産会社を見つけるようにしましょう。
相続した山林でれば、相続土地国庫帰属制度を利用して国に返還するのも一つの方法です。
相続土地国庫帰属制度は山林も対象になっていますが、審査手数料や引き取り時に負担金を支払う必要があり、適用のハードルも高い点がネックです。
山林の固定資産税に関するよくある質問
最後に、山林の固定資産税に関するよくある質問をみていきましょう。
固定資産税がゼロの山林の相続税はどうなる?
固定資産税と相続税では、課税標準額や税金の計算方法が異なります。
固定資産税がゼロであっても相続税の対象となる場合もあるので、相続税の評価額で計算し直してみるようにしましょう。
なお、相続税は山林だけでなく相続財産の合計が基礎控除を超えると課税されるものです。
仮に、山林の評価額がほぼないとしても、他の相続財産で基礎控除を超えると相続税が課税される点には注意しましょう。
相続税の計算は複雑になりがちなため、不安があるなら税理士などのプロへの相談をおすすめします。
原野は固定資産税がかからない?
原野も固定資産税の対象です。
原野とは、不動産登記の名目の1つで林地ではない雑草やかん木類が生育する土地をいいます。
山林と似ていますが、人の背丈を超えるような木や竹が生育している土地が山林、人の背丈ほどの植物が生育している土地が原野という違いがあります。
原野を所有する場合も固定資産税が課せられます。
とはいえ、山林と同様に原野の固定資産税もそれほど高くなりません。
また、課税評価額が免税点である30万円未満であれば固定資産税が課せられないため�、課税されないケースも多いでしょう。
まとめ
山林も固定資産税の対象となりますが、税額は年間数千円~数万円とそれほど高くなりません。
また、所有状況によっては免税点以下となり固定資産税が課税されないケースもあります。
ただし、山林を所有すると税金だけでなく維持管理費の負担もあることには注意が必要です。
税金の負担を軽減したい、管理の費用や手間を避けたいという場合は、売却を視野に入れるとよいでしょう。