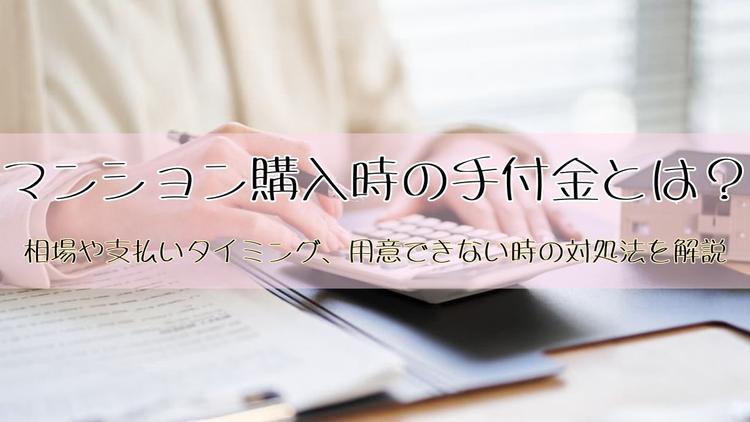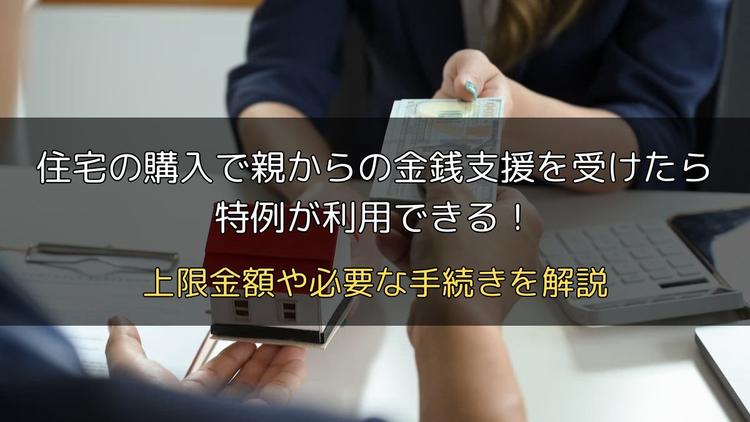中古住宅は建築時期や施工会社の水準が物件ごとに異なります。
築20年超なら設計図や保証書が残っていないケースも珍しくありません。だからこそ内見での「観察眼」と事前の資料収集が決定打になります。
この記事では、内見で注目すべきチェックポイントについて解説します。
内見前の下調べ~資料を手に入れる
中古住宅の内見は、現地で見て初めて分かることが多い反面、事前に集めた情報があるかないかで、その見え方も大きく変わります。
外観や内装に目を奪われて、構造や法的な瑕疵を見落としてしまっては本末転倒です。そこで、内見前に必ずチェックすべき資料を紹介します。
既存住宅状況調査(インスペクション)報告書
建物の劣化や不具合の有無を第三者が調査・報告する「既存住宅状況調査報告書」は、いわば建物の「健康診断書」です。構造耐力上主要な部分(基礎、柱、梁など)や雨水の侵入を防止する部分(屋根、外壁、サッシ周りなど)を中心に、目視と計測でチェックされます。
2024年の宅建業法施行規則改正により、報告書の有効期間は調査日から2年に延長され、また仲介業者は「あっせんをしない理由」を買主に説明する義務が明文化されました。つまり、インスペクション報告書が提示されない場合、その理由を確認することで、売主・仲介側のスタンスを読み取ることができます。
特に築20年以上の物件では、内部構造や配管の劣化が表面からは分かりづらく、報告書があるかどうかで判断材料の信頼度が変わります。
▼関連記事:既存住宅状況調査(インスペクション)とは|検査項目や物件売買時のメリットを解説
省エネ性能ラベル(建築物のエネルギー性能表示)
2024年から始まった「建築物省エネ性能表示制度」により、一定規模以上の建物については、断熱性能や一次エネルギー消費量を★マークや等級で表示する省エネラベルの提示が努力義務化されています。
中古住宅では表示されていないケースが多いものの、すでに評価を受けている物件も存在します。
特に、過去に「住宅性能評価(国の基準に基づく性能評価制度)」や、「BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価」を取得した住宅であれば、断熱等級や省エネ等級を確認できるラベルや書類が残っている可能性があります。
住宅の省エネ性能は「住んでからの光熱費」だけでなく、「将来の資産価値」にも影響する重要な指標です。新築住宅の義務化が進むなか、今後は中古市場でもこの指標が売買価格に反映されやすくなっ��ていくと見られています。
▼関連記事:住宅ローン控除の利用条件になる高性能住宅とは?基準を解説します
登記事項証明書・公図・測量図
法務局で取得できる「登記事項証明書」や「公図」、そして可能であれば「確定測量図」です。これらは土地や建物の法的状況、つまり誰の所有か/どんな制限があるか/どこまでが敷地かを明らかにするものです。
登記事項証明書では、所有者の名義が現売主と一致しているか、住宅ローンなどの抵当権が抹消されているかを確認します。
また、公図で確認できる土地の形状と現地が一致しているかも見ておきましょう。隣地との境界が曖昧な場合は、現地に境界標があるかどうかを確認する準備にもなります。
特に注意すべきは「未登記建物」や「違法建築(増築時の確認申請なし)」のケース。いざ買ったあとに登記できなかったり、再建築できなかったりするリスクがあります。現況と登記情報が一致しない場合は、内見時にその理由を必ず確認しましょう。
▼関連記事:増築未登記のリスクとは?売買時に売主・買主がチェックすべきポイントを解説します
外観・敷地周り~「水」と「傾き」を探す
中古住宅の内見において、まず注目すべきは建物の「外側」です。建物内部がいかにリフォーム済で見栄えが良くても、敷地や外構に問題があれば、長期的に不安定な資産となるリスクがあります。特に重要なのは、「水の流れ」と「土地・建物の傾き」に関するチェックです。
敷地の水はけと排水の流れ
敷地の形状や勾配、排水の仕組みは、日常生活の快適さはもちろん、建物の耐久性にも直結します。以下のポイントを内見時に確認しましょう。
雨水の排水ルート
敷地内のどこに水が集まり、どこに流れていくのかを想像しながら観察します。地面に水溜まりの跡が残っていたり、芝や砂利が不自然に沈んでいたりする箇所は、水はけの悪さを示唆しています。
特に注��意したいのは、建物周囲に勾配がなく、逆に水が建物側に向かって流れ込むような地形です。これは基礎内部への雨水浸入や床下の湿気の原因になり、白蟻やカビの温床となる可能性があります。
雨樋や排水マスの状態
雨樋の傾きが狂っていたり、継ぎ目に割れがあったりすると、雨水が正しく流れず、外壁や基礎にダメージを与えます。また、敷地内に設けられた排水マスのフタが開けられる場合は、中を確認し、泥がたまっていないか、詰まりがないかを見ておくと安心です。
雨天後に内見できるなら理想的
可能であれば、雨が降った翌日や当日に内見を設定するのが理想的です。実際の排水状況を観察でき、普段は気づきにくい水はけの問題が浮き彫りになります。難しい場合は、ホースで軽く水を撒くことを仲介業者に相談するのもひとつの手です。
土地と建物の傾き
土地や建物の傾きは、地盤沈下や構造不良の兆候であることがあり、見逃すと重大な瑕疵につながります。以下の点を目視と簡易な道具で確認しましょう。
土地の高低差と隣地との関係
敷地が周囲の土地や道路よりも極端に低い場合、雨水や土砂が流れ込む恐れがあります。また、擁壁や境界ブロックにひび割れや傾きがある場合は、地盤の動きを示していることもあります。特に高台造成地や盛土の区域では、造成時の履歴や地盤調査報告書があるかどうかも確認材料になります。
基礎のクラック(ひび割れ)
基礎に発生するクラックは経年による微細なものも多いですが、幅0.3mm以上の斜めの亀裂は構造的な問題のサインかもし��れません。鉄筋の露出や、指で触ってパリパリと崩れるような劣化があれば、専門家による追加調査が必要です。
建物全体の傾き
外観を斜めから眺めて、建物がわずかに傾いて見える場合は、水平器やスマートフォンの傾斜測定アプリで簡易測定してみましょう。玄関やポーチの床、縁側などで1メートルあたり6mm以上の傾斜があれば、専門的なチェックを検討すべきです。
外壁・屋根の観察ポイント
外壁や屋根材は、建物の「鎧」とも言える部分です。次の点をチェックします。
- 外壁はチョーキング(白い粉)・クラックを確認⇒塗膜劣化、雨水侵入の可能性
- 屋根はズレ・反り・苔の繁殖を確認⇒雨漏りの前兆かも
- 雨樋は傾き・外れ・詰まりを確認⇒排水不良、外壁劣化の可能性
- 基礎はヒビ・爆裂・コンクリート剥離を探す⇒構造上の劣化を疑う
構造・劣化リスク~床下と小屋裏で5分ずつ
中古住宅の内見では、目に見える部分ばかりに目が行きがちですが、建物の健全性を見極めるうえで欠かせないのが「床下」と「小屋裏」の確認です。これらは普段の生活では目に触れない「死角」ですが、劣化や構造トラブルの初期兆候が現れやすい重要な箇所です。
内見の限られた時間のなかで、たとえ5分ずつでも見ておけば、リスク回避の精度はぐっと高まります。
床下点検口~湿気と白蟻の痕跡を見逃すな
多くの戸建て住宅では、キッチンや洗面所、廊下などに床下点検口があります。ここを開けて内部をのぞくだけでも、劣化や構造状態のヒントが得られます。
床下は、次の�ポイントをチェックします。
- 土台・大引に腐食、変色、反りがないか確認する
- 基礎にクラック(幅0.3mm超)、蟻道、鉄筋の露出がないかを確認する
- 配管に水漏れ、結露、青錆がないかを確認する
- 地面に水たまり、カビ、白い粉がないかを確認する
特に注意すべきは白蟻(しろあり)の蟻道(ぎどう)です。これは、土台から基礎に沿って作られる細長い土の通路で、放置すれば構造材の内部を食い荒らされる原因になります。木材に針で刺したような小さな穴が複数ある場合も白蟻被害の兆候です。
また、配管周辺に水滴が残っていたり、給水管の金属部分に青錆(緑青)が出ている場合は、微細な漏水が起きている可能性があります。これはカビや腐朽菌を呼び寄せ、床材や構造材の寿命を縮めます。
小屋裏(天井点検口)~雨漏りと断熱の不備を見抜く
小屋裏とは、屋根裏部屋のない住宅において、天井裏の空間を指します。押入れや廊下の天井に点検口が設けられていることが多く、内見時に踏み台を借りて蓋を開けておくだけでも、得られる情報は大きくなります。
小屋裏は次のポイントをチェックします。
- 野地板・垂木に雨染み、カビ、腐朽がないか
- 断熱材にヘタリ、ズレ、欠損がないか
- 通気口があるか
- 結露がないか
天井裏でまず確認したいのが、雨漏りの形跡です。木材が一部黒ずんでいたり、断熱材にカビが生えていたりする場合は、過去または現在進行形の漏水がある可能性があります。特に棟木や野地板が柔らかくなっていたり、手で触れてふやけているようであれば要注意です。
また、小屋裏の断熱状態は室内の快適性に大きな影響を与えます。断熱材がずり落ちていたり、隙間が空いていたりする場合は、断熱性能が十分に発揮されていない証拠です。これは冷暖房効率の悪化、結露の原因にもなります。
短時間で済ませる観察のコツ
床下も小屋裏も、5分ほどの観察で最低限の状態把握が可能です。とはいえ、次の準備と心構えがあると、効率的に見抜く力が高まります。
- 懐中電灯(スマートフォンのライトでも可)
- ハンディ鏡(奥の方をのぞき込むのに便利)
- マスク(カビ臭やホコリ対策)
- 服装は、しゃがんでも汚れにくい恰好で
内見前に「点検口はどこにあるか?」「開けて確認していいか?」を仲介業者に確認しておくと、当日スムーズです。
水回り・住宅設備~「経年」より「交換履歴」
中古住宅の内見では、キッチンや浴室などの「水回り」に目が行きがちですが、大切なのは見た目の新しさよりも、いつ・どのように交換されたかという「履歴の確認」です。住宅設備の多くは寿命があり、経年劣化による不具合が出やすいため、設置時期とメンテナンスの記録がわかれば、将来の出費やトラブルを予測できます。
給湯器の製造年と能力を確認する
給湯器は、住宅設備のなかでも寿命が比較的短く、10〜15年程度での交換が目安とされています。見た目がきれいでも、内部の部品は確実に摩耗していきます。
チェックポイントは次のとおりです。
- 給湯器の型番・製造年(ラベルで確認)
- 設置場所(屋外壁掛け/室内)と劣化の具合
- 追い�焚き機能の有無・作動確認
- 配管の保温材の剥がれや劣化
製造から15年以上経っている場合、購入後すぐの交換が前提と考えた方がよいでしょう。交換費用の相場は20万〜30万円程度で、機能や設置場所によってはさらに費用がかさむ場合もあります。
配管素材と漏水リスク
壁の中や床下に隠れている給排水管は、内見時には直接見えないことが多いものの、トラブルが起きたときの修繕費が高額になるため、特に注意が必要です。
確認方法は次のとおりです。
- 給水・給湯管の材質が鉄管であれば赤さび、銅管であれば青さびが注意サインです。
- 止水栓の状態を確認して、ハンドルの固着や漏水跡があれば要注意です。
- 水圧をシャワーや蛇口で実際に流して確認します。水圧が弱すぎる場合は詰まりの可能性があります。
- 床下を覗いて、配水管に水滴、湿気、排水臭がないかを確認します。これらを見つけた場合、配管接続部から老衰している可能性があります。
▼関連記事:中古マンションの売買時にインスペクションは必要?検査項目や実施時の注意点を解説します
まとめ
中古住宅の購入では、「住みたい」「おしゃれ」「価格が手頃」といった感覚的な印象だけで決めてしまうと、入居後に思わぬ不具合や修繕費に悩まされることがあります。築年数や外観だけでは判断できない構造的なリスクや、配管・断熱など目に見えない部分の劣化こそ、内見での確認が欠かせません。
そのためには、まず事前に登記事項証明書やインスペクション報告��書といった資料を入手しておくことが重要です。現地では「水の流れ」「土地や建物の傾き」「床下・小屋裏の湿気や白蟻跡」「給湯器や配管の状態」といった、見落とされがちなポイントを意識的にチェックすることで、建物の健全性を立体的に把握できます。
また、省エネ性能や設備の交換履歴など、将来的な維持費や快適性に直結する情報も確認しておきたいところです。限られた内見の時間でも、見るべき視点を知っていれば、購入後のトラブルを大幅に回避できます。
「ここを見ておけばよかった」と後悔しないためにも、冷静で多角的な観察眼をもって臨むことが、失敗しない中古住宅選びへの第一歩です。
▼関連記事:中古マンションを購入する際の注意点を解説します