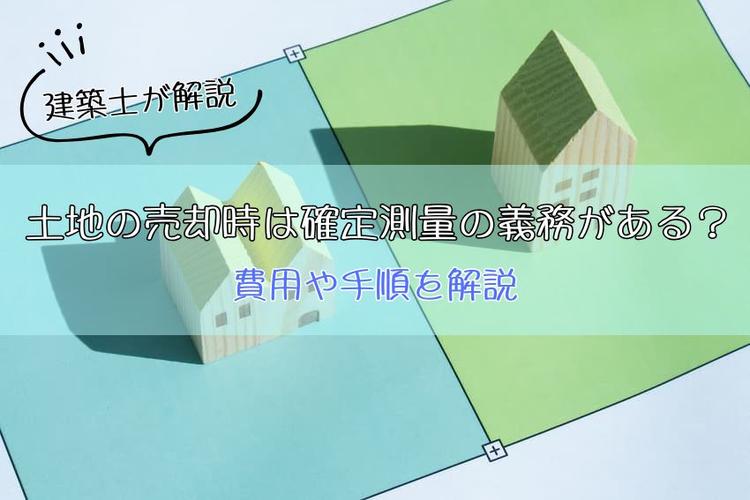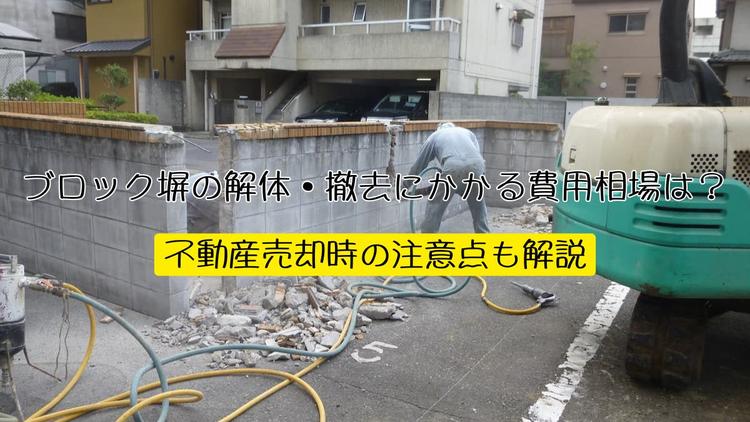近年、所有者不明土地が増加しており、その活用に関心を持つ方も多いのではないでしょうか。
「放置された土地を有効活用したい」「隣接する土地をまとめて利用したい」など、様々な目的で所有者不明土地の購入を検討されているケースもあるでしょう。
しかし、所有者不明土地の購入は、通常の不動産取引とは異なり、複雑な手続きとリスクが伴います。
この記事では、所有者不明土地の購入するときの方法、手続きの流れ、注意すべき点について解説します。
所有者不明土地とは
所有者不明土地とは、その名のとおり持ち主が分からない土地のことをいいます。具体的には、以下のいずれかに該当する土地を指します。
- 不動産登記簿に所有者が記録されていない、または記録されていても情報が古く、連絡が取れない土地
- 相続などが繰り返されるうちに、所有者が誰なのか分からなくなってしまった土地
国土交通省は、2016年度に558市町村に対して地籍調査を行いました。約62万筆の土地の所有者を調査したところ、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できなかった土地は、全体の20.1%にのぼりました。
所有者不明の土地は、売買や開発、管理などができずに放置されるケースが多く見られます。
その結果、景観の悪化や不法投棄を招くなど、大きな社会問題となっています。
地籍調査
地籍調査とは、土地の境界や所有者、面積、利用状況などを明確にするため、市町村などが主体となって実施する調査のことです。調査によって土地の正確な位置や面積が明らかになり、その結果は登記簿に反映されます。
日本では明治時代に作成された古い地図や登記情報が現在も使われている地域があり、現状と登記情報が一致しないことも少なくありません。地籍調査を進めることにより、土地所有者の所在を特定し、所有者不明土地の発生を防ぐことが期待されています。
しかしながら、調査にかかる費用や手間、所有者が特定できない場合の手続きの煩雑さなどから、全国的な調査の進捗は遅れているのが実情です。
所有者不明土地が発生する原因
土地の所有者の住所や氏名は、登記簿に記載されています。通常、登記簿謄本を取得することで、所有者の情報が判明するはずですが、どうして所有者不明の土地が発生するのでしょうか。
相続登記の未実施
所有者不明土地問題の原因のひとつとして、相続登記の未実施があります。
手続きの煩雑さや費用負担、相続人の遠隔居住、連絡の困難さ、相続意識の希薄化により、長年放置されてきた物件が多くあるのです。これは、従来、相続登記が義務ではなく任意であったことに起因します。
その結果、相続が繰り返されるたびに所有者の特定が困難になり、相続人同士の連絡も途絶え、所有者自体が不明になる事態が頻発しました。
2024年4月1日から開始された相続登記義務化は、この状況を改善し、新たな所有者不明土地の発生を抑制する重要な対策として期待されています。
住所変更登記の未実施
もうひとつの原因は、住所変更登記の放置です。
住所変更登記は、所有者の住民票の住所が変更されたときに行われる手続きです。
しかし、以前は住所変更登記が義務ではなかったため、登記簿上の住所が古い情報のまま放置されているケースが多くあります。
その結果、相続発生時などに所有者と連絡が取れず、所有者の特定が困難になる状況が生まれました。
この問題を解決するため、引越し後2年以内の住所変更登記が義務化されたのです。
また、本人の了解があれば、登記官が他の公的機関から取得した情報を基に職権で住所変更登記をする仕組みが導入されることになっています。
これ�らの改正は、2026年4月に施行予定です。住所変更登記が義務化されることで、所有者の所在を明確にし、所有者不明土地の発生を抑制することが期待されています。
所有者不明土地・建物管理制度の利用
所有者不明土地は、「所有者不明土地・建物管理制度」を利用することで、購入できる可能性があります。
利害関係人(隣地所有者、自治体、債権者などが該当)は、家庭裁判所に申立てを行い、所有者不明土地の管理を行う管理人を選任してもらうことができます。選任された管理人は、土地の保全や管理、必要に応じて土地の利用や処分を行うことができるのです。
管理人が選任されると、その管理人によって土地の管理や売買が可能になります。しかし、売買取引が成立したあとにトラブルになる恐れもあるので、リスクを把握したうえで対策をとりながら土地取得を進める必要があります。
- 後から相続人や真の所有者を主張する者が現れ、所有権を巡って法的トラブルになる。
- 隣接する土地の境界が曖昧な場合、境界線を巡り隣接する土地所有者とトラブルになる。
- 長期間放置されていた土地は、不法占拠やゴミの不法投棄、害虫の発生など、周辺住民とのトラブルを引き継いでしまうリスクがある。
- 取得後に開発や建築が困難であることが発覚し、土地の利�用価値が当初の想定より低いことが判明。
上記のようなトラブルが想定されるため、適切な手順を踏むのはもちろん、取得後に想定している利活用のための調査も怠らないようにしましょう。
所有者不明土地・建物管理制度は、民法改正により2023年4月に創設されました。先例があまりないため、利用を検討する際は、専門家への相談が欠かせません。
所有者不明土地・建物管理制度が利用できる3つの要件
所有者不明土地・建物管理制度を利用するには、次の3つの要件を満たす必要があります。
①所有者の不明または所在不明
登記簿の調査、住民票や戸籍の調査、現地調査、 関係者への聞き取り調査といった調査を尽くしても所有者が分からない場合や、登記上の所有者がすでに亡くなっており、相続人が特定できないケースが該当します。
②管理の必要性
土地・建物が適切に管理されていないために、周辺の環境や安全が損なわれている場合や、土地・建物が放置されることで、将来的に価値が著しく低下する可能性がある場合が該当します。
所有者が不明でも、第三者が適切に管理していれば、管理人による管理の必要はないと考えられることもあります。
③利害関係人による申立て
利害関係人とは、所有者不明土地または建物が適切に管理されないことにより、不利益を被る可能性がある人です(民法第264の2I、264の8I)。隣接地の所有者、自治体、債権者などが該当します。
たとえば、所有者不明土地が不法投棄の場所になっており、迷惑を被っている隣接住民や、所有者不明建物が老朽��化して崩れ落ちそうになっており、通行の妨げになっているといったケースが該当します。
所有者不明土地・建物管理制度を利用する流れ
所有者不明土地・建物管理制度を利用するには、次のような流れで手続きを進めます。
- 不動産の所在地を管轄する裁判所に申立てをする……所有者不明土地建物の所在地を管轄する裁判所に、所有者不明土地・建物管理命令の申立てをします。
- 裁判所が公告する……申立てがなされた裁判所が、1カ月以上の異議申述期間等を定めて、申立てがあった旨を公告します。
- 裁判所が管理命令を発令し管理人を選任する……異議申述期間等に誰からも申し出がなければ、裁判所は所有者不明土地・建物管理命令を発令して、管理人を選任します。
- 管理人が選任されたことが公示される……裁判所書記官が嘱託で登記申請をし、管理人が選任された旨が登記され、公示されます。
- 管理人が管理・処分する……裁判所から選任された管理人が、土地または建物を適切に管理します。
管理人は、保存行為の他に、裁判所の許可を得て土地を売却したり建物を取り壊したりするなどの処分行為も行うことができます。その際、金銭を得た場合は、管理人は供託し、公告しなければなりません。
不在者財産管理人制度の利用
所有者不明土地は、不在者財産管理人制度の利用を利用して、購入できる可能性があります。
不在者財産管理人制度は、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に対して利用されます。
財産管理者がいない場合、不在者本人や不在者の財産に利害関係を持つ第三者の利益を保護するために、家庭裁判所が申立てにより財産管理人を選任する制度です。
この制度の目的は、不在者の財産を適切に管理・保全することや、不在者の財産に関する利害関係人の法的地位を安定させることです。
たとえば、不在者の財産を管理する必要がある場合や、不在者が関係する遺産分割協議を進める際の利用が想定できます。
この制度は、2021年4月に施行された改正民法によって創設されました。
不在者財産管理人制度の利用の3つの要件
不在者財産管理人制度を利用するには、次の3つの要件を満たす必要があります。
①不在者の存在
制度の対象となるのは、「従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者」です。つまり、単に行方が分からないだけでなく、長期にわたって所在が不明であり、戻ってくる見込みがないことが必要です。
ただし、失踪宣告のように、一定期間の経過は必ずしも必要ではありません。しかし、申立ての際には、不在の事実を証明する資料を提出する必要があります。
- 住民票の除票
- 戸籍の附票
といった資料の他、
- 郵便物が届かない証明
- 近隣住民や親族の証言・陳述書
- 警察への捜索願の提出記録や回答
- 興信所・探偵等による調査報告書
などを組み合わせて、家庭裁判所に不在の事実を認めてもらう方法が考えられるでしょう。
②利害関係人の申立て
不在者財産管理人の選任は、利害関係人の申立てによって開始されます。利害関係人とは、不在者の財産に関して何らかの法的利益を有する人のことを指します。例えば、不在者の配偶者、親族、債権者などが該当します。
③財産管理の必要性
不在者の財産を保護・管理する必要性があることが要件となります。具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 不在者が所有する不動産が放置され、荒廃する可能性がある場合
- 不在者が遺産分割の対象となっている場合
- 不在者が契約当事者となっている契約の処理が必要な場合
不在者財産管理人制度の利用の流れ
不在者財産管理人制度は、次の流れによって手続きを進めることで利用できます。
- 不在者の住所地または居所地の家庭裁判所に申立て……不在者の配偶者、相続人、債権者など、不在者の財産に関して利害関係を有する人が申立てを行います。
- 家庭裁判所による審理……家庭裁判所は、提出された書類や申立人の陳述などに基づいて、不在の事実や財産の状況、申立人の適格性などを審査します。
- 不在者財産管理人を選任……家庭裁判所は、審理の結果に基づいて、適切な人物を不在者財産管理人に選任します。
- 不在者財産管理人の業務……財産調査を行い、家庭裁判所に作成した財産目録を提出します。
所有者不明土地の購入手続きの流れ
所有者不明土地の購入手続きは、通常の不動産取引と比べて複雑で、時間と労力を要する場合があります。基本的な流れを解説していきましょう。
①情報収集
法務局で購入したい土地の全部事項証明書(登記簿謄本)を取得し、次の事項について確認します。
- 所有者の氏名
- 所有者の住所
- 権利関係(抵当権、�地役権など)
- 土地の地目、地積
合わせて、法務局の同じ窓口で、公図、地積測量図なども取得し、土地の正確な位置や形状を確認します。
②調査
所有者の調査は、登記上の住所をもとに、住民票や戸籍謄本などを取得し、現在の所有者や相続人を調査します。
近隣住民や関係者への聞き取り調査を行い、所有者に関する情報を収集します。
所有者がすでに亡くなっている場合は、戸籍謄本をたどるなどの方法で、相続人を捜し当てる必要があります。
しかし、原則として一般の個人が他人の住民票や戸籍謄本を取得することはできません。これらの書類は、本人や直系の親族、または正当な理由がある場合にのみ取得が認められます。
そのため、所有者の調査を専門的に行う弁護士や司法書士に依頼するのが現実的な選択肢です。これらの専門家は、法律に基づいた調査を行い、業務上請求により必要な情報を収集することができます。
また、所有者不明土地に関する相談窓口が自治体に設置されている場合があるので、該当する自治体に確認してみるのも一つの手です。
③所有者が判明
所有者または相続人に連絡を取り、売買交渉を行います。売買条件(売買価格、支払い方法、引渡し時期など)について合意し、売買契約書を作成して締結します。
所有者が判明した場合は、一般的な方法により売買契約書を作成し、売主と契約を交わします。売買代金を支払い、同日に司法書士が所有権移転登記申請を行います。売主から土地の引渡しを受け、手続きが完了します。
所有者不明土地・建物管理制度を利用した��土地の購入方法
所有者不明土地・建物管理制度を利用した土地は、家庭裁判所から選任された管理人を通じて購入が可能です。
売却に際しては、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所は、売買価格の妥当性などを審査します。裁判所の許可が得られれば、選任された管理人との間で売買契約を締結し、所有権移転の手続きを行います。
売買契約には、必ず裁判所の許可が必要です。許可を得ずに契約した場合、契約が無効になる可能性があるので注意しましょう。
不在者財産管理人制度を利用した土地の購入方法
不在者財産管理制度を利用した土地は、家庭裁判所によって専任された不在者財産管理人を通じて購入することができます。
不在者財産管理人は、不動産を売却する際に家庭裁判所の許可を得る必要があります。これは、不在者の利益を保護するための措置です。許可を得るためには、売却の必要性や売却価格の妥当性などを裁判所に示す必要があります。
家庭裁判所の許可が得られたら、不在者財産管理人と売買契約を締結します。所有者不明土地・建物管理制度同様、許可を得ずに契約した場合は売買契約が無効になる可能性があります。
所有者不明土地を購入するときの注意点
所有者不明土地は、通常の不動産取引と比べて問題が発生する可能性が高くなります。所有者不明土地を購入する際の注意点について解説していきましょう。
権利関係が複雑なことがある
土地の所有者が不明であることから、権利関係の調査が非常に困難になります。
過去の所有者や相続関係を詳細に調査する必要があり、中には複数の相続人が関与している場合や、権利が複雑化している場合もあります。
そのため、権利関係の確定に時間がかかることがあります。
例えば、相続登記が何代にもわたって行われていない土地では、相続人が数十人に及ぶことも考えられるのです。
また、土地に抵当権や担保権が設定されている可能性もあるため、これらの権利関係も十分に調査することが求められます。
法的手続きが煩雑
所有者不明土地の取引には、裁判所の許可が必要となる場合が多く、手続きが煩雑になります。
管理人との売買契約や裁判所の許可など、通常の取引とは異なる手続きが必要です。
権利関係の調査や法的手続きには時間がかかり、費用も高額になる可能性があります。
将来にリスクがある
将来的に潜在的な権利者が現れ、所有権を主張する可能性があります。
長期間放置されていた土地の場合、地盤の問題や土壌汚染などのリスクがあるかもしれません。
土地の状況によっては、購入後に修繕や撤去などの責任を負うことになる可能性もあります。
専門家への依頼が望ましい
所有者不明土地の購入は、専門的な知識が必要になるため、弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの専門家に相談をしたうえで進めた方が安心です。
まとめ
所有者不明土地の購入は、通常の不動産取引と異なり、複雑な手続きと多くの注意点があります。所有者の調査、権利関係の確認、法的手続きなど、専門的な知識と時間が必要です。
購入を検討する際は、以下の点を�十分に理解し、慎重に進めることが重要です。
- 所有者の調査: 所有者を特定するために、法務局での調査や専門家への依頼が必要です。
- 法的手続き: 所有者不明土地建物管理制度や不在者財産管理人制度の利用には、裁判所の許可が必要です。
- リスクの把握: 権利関係の複雑さや潜在的なリスクを考慮し、専門家と相談しながら進めましょう。
- 専門家の活用: 弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの専門家のサポートを得ることで、安全かつスムーズな取引が期待できます。
所有者不明土地の購入は、適切な手続きと専門家のサポートがあれば、有効な土地活用に繋がる可能性があります。しかし、リスクも伴うため、慎重な検討と準備が不可欠です。