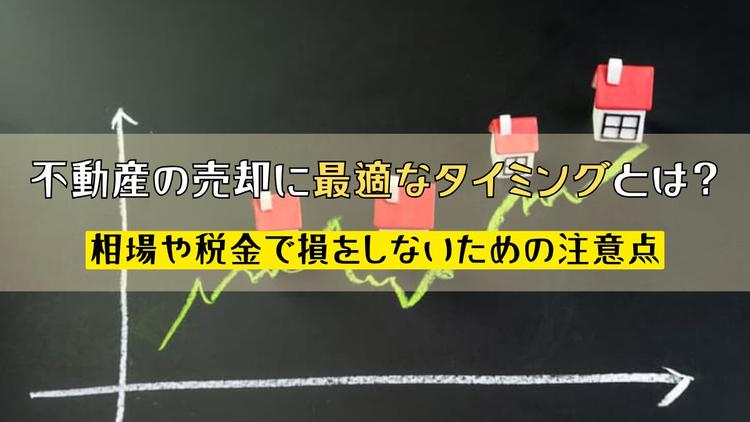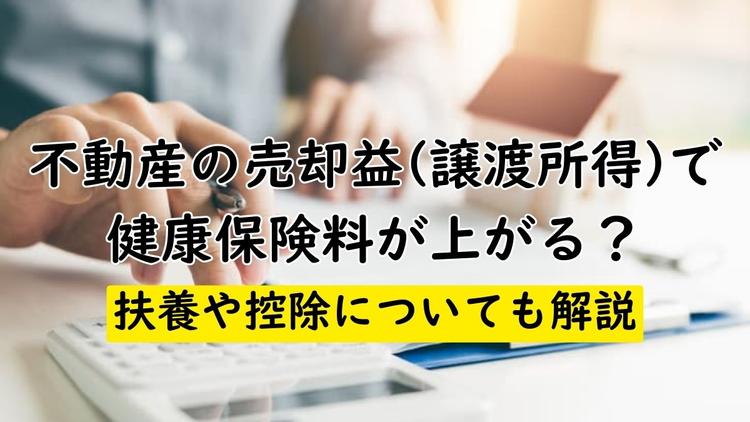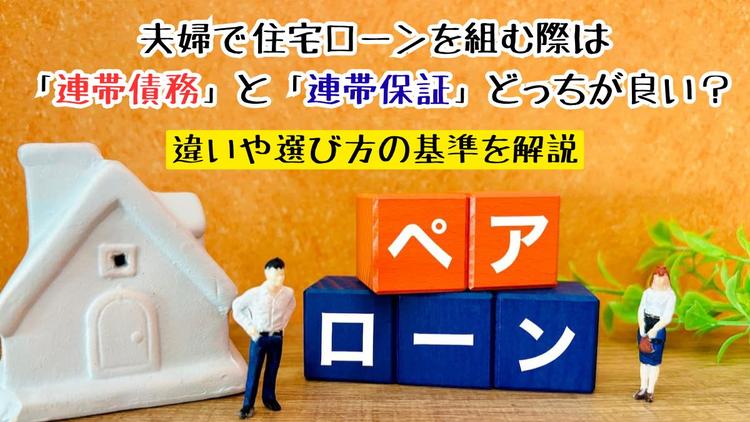家は売るタイミングによって税率や値段が変わります。自宅を売却するとなれば、引っ越しや新居購入の費用を考えてできるだけ高い値段で売りたいもの。
この記事では、不動産を大きく住宅(マイホーム)と投資物件に分けて、それぞれ売却に最適なタイミングはいつなのか、注意点はあるのかという点をお伝えしていきます。
原則:所有期間5年経過後が売却のタイミング
例えば、3,000万円で不動産を購入したとします。
そして、4,000万円で売れた場合、1,000万円の利益が発生したことになります(実際には減価償却分を考慮する必要あり)。
この場合、利益分は所得と見なされ、譲渡所得税が発生します。
購入から売った年の1月1日時点の所有年数が5年に満たない不動産の譲渡所得税率は39.63%と、非常に高い税率です。
1,000万円の利益が出た場合は400万円近い金額に税金が課されるのです。
一方、購入から5年以上経過した不動産の譲渡所得税率は、20.315%まで下がり、およそ半分になります。
そのため、購入後5年が不動産を売却する一つの目安となります。
もし不動産の売却をそれほど急ぐ必要がなければ、5年待ってから売却しましょう。
税率が大幅に下がり、手元に残るお金が増えます。
自宅を売却する最適なタイミングは
上記は不動産の売買時に所得が出た場合の課税の原則ですが、自宅(マイホーム)を売却する場合は「マイホーム売却時の特例(通称:3,000万円控除)」が適用できます。
自宅の売却は3,000万円の控除があるのでタイミングを問わない
譲渡所得税の控除は、居住用不動産と投資用不動産では異なります。
居住用の不動産は生活に必要なものであるため、税金が優遇されるのです。
一方、投資用の不動産は収益を生み出すものですから事業用であり、生活必需品ではありません。こちらは特に税制の優遇措置はありません。
自宅を売却した場合、以下の条件を満たせば3,000万円までの控除が受けられます。
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2) 売った年の前年及び前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3) 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
(4) 売った家屋や敷地に�ついて、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
特例が適用できる場合、自宅用の不動産を売却して利益が出ても、利益分が3,000万円以内であれば課税されません。
多少の利益が発生しても、そこから税金が引かれずに自分の手元に現金を残せるのです。
新築住宅を購入した場合、購入時の価格よりも売却価格が高くなることはあまりありません。
都心部など土地価格が大きく上昇している地域では、買ったときよりも高く売れることがありますので、特例について確認しておきましょう。
▼関連記事

木造戸建ては値下がりが早い
一方、最適な価格で売却するためには、建物の価格がどの程度のペースで下がるかを知っておく必要もあります。
マンションと戸建て住宅の資産価値の推移について、以下の図で示されるデータがあります。
出所:国土交通省資料「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」
このデータにあるように、築20年までの木造物件は資産価値が年々下落していきます。
理由は、木造物件の法定耐用年数が22年と定められているからです。
法定耐用年数とは、不動産の工法による種類ごとに決められた耐用年数を指し、ひいては何年間かけて減価償却を行うかを示した数値です。
法定耐用年数を経過すると、その物件が利用できなくなるわけではありません。
しかし、不動産売買時の値付けの基準として法定耐用年数が用いられるため、築22年を経過した木造物件はほとんど価値がないものと見なされてしまうのです。
したがって、木造物件を売るのであれば、できるだけ早く売ったほうが高い値段で売れますし、少しでもタイミングを逃してしまうと、どんどん価格が下がってしまいます。
ただし、住宅ローンは利用開始から数年間は毎月の返済額に占める金利分の割合が大きく、元金が減りにくいという特徴があります(元利均等返済の場合)。
元利均等返済の場合、初期の返済額に占める利息の割合が大きいため、元金が減りにくいという特徴がある。
そのため、住宅ローンが完済できる価格での売却となると、新築〜築10年程度までは土地価格の上昇が伴わない場合は難しいこともあります。
マンションは戸建てに比べて緩やかに価値が下落
先ほどのグラフが示す通り、鉄筋コンクリート造、いわゆるRC造物件の法定耐用年数は47年です。
マンションの場合、木造物件に比べれば価格下落のカーブは緩やかです。
ただし、それでも、価値が年々低下することには変わりないので、結局は早めに売った方が高く売れます。
土地の価格相場を見て売るのも一つの手段
木造で築20年以上の物件ならば、すでに建物の価値はほとんどなくなっているのは前述の通りです。
そのため、築年数がある程度経過した家の売却価格は、土地自体の価値に近くなっていきます。
例えば、東京都内の公示地価は、2014年から2019年にかけて毎年上昇しています。
土地の価値は、持っているだけで上がっていくこともあるのです。
土地相場が値上がりを続けている場合は、売却を少し待つと高く売れる可能性があります。
ただし、土地価格が値下がりすれば当然価値が下がってしまうため、相場を見極めなければなりません。
投資用物件を売却する最適なタイミングと注意点
先ほどは自宅の売却のタイミングを中心にお話ししました。
次に、マンションやアパートなどの投資用不動産を売却する最適なタイミングはいつなのか、お伝えします。
投資用物件の場合、住宅用物件とはまた異なる考え方が必要です。
投資用物件に控除はないので5年経ってから売る
住宅用物件と異なり、投資用物件には3,000万円の控除はありません。
そのため、5年以内に売却を行うと、40%近い譲渡所得税が課税されます。
利益の大半を税金に取られてしまうので、投資用物件の場合は5年以内ではなく、5年経ってから売ったほうが良いでしょう。
マンションは緩やかに価値が下がるので土地相場を見る
ワンルームマンションなどのマンション物件の法定耐用年数は47年です。
RC造物件の値下がりのカーブは緩やかで、急激に価格は下がりにくいです。
木造物件と比べて無理に売り急ぐ必要はないので、周辺の不動産の相場や土地の価格の状況などを見て、売却のタイミングを検討すると良いでしょう。
法人ならば売る時期は相場を見て判断する
不動産投資を頻繁に行う人の中には、何年も待てない人、価格が上がれば5年以内でも売って売却益を獲得したい人もいるかもしれません。
安価で不動産を購入して高値で売ることができれば、家賃収入での不動産収入ではなく、売却益による大きな不動産収入を得ることができます。
しかし、先に挙げたように5年以内という短期間での売却は、高額の譲渡所得税が発生するので利益が削られてしまいます。
そこで、検討したいのが��法人の設立です。
法人の場合は個人と違い、売却益には譲渡所得税ではなく、法人税が課税されます。
法人税は法人の売上高で変わりますが、15~23.2%です。
個人の場合の39%といった高額な税率にはなりません。
また、不動産の保有期間に関わらず、法人の売上に課せられる税率は一定です。
購入後すぐに売却して利益を出したい人は、法人を設立すれば税率を下げられる可能性があります。
法人成りで節税を狙う場合は、税理士に相談してみましょう。
反復継続に注意
不動産の購入と売却を繰り返すことを、反復継続と呼びます。
個人投資家が反復継続を行うと、宅建業法に違反していると見なされることがあるのです。
短期譲渡所得でも構わない個人投資家の中には、少しでも利益が出るのであれば不動産をどんどん売買して稼ごうと考える人もいるでしょう。
しかし、不動産の購入と売却の繰り返しは、不動産事業を営むのと同じとみなされます。
宅建業者ではない個人や法人が、短期間に何度も不動産の取得と売却を行う反復継続とみなされると、宅建業法違反として指摘される可能性があるのです。
不動産の購入と売却を繰り返す可能性があるときは、国家資格である宅地建物取引士の資格を取得、または有資格者を雇うなどして、自分で不動産会社を設立した方が良いでしょう。
参考:建設産業・不動産業:宅地建物取引業法 法令改正・解釈について|国土交通省
修繕したばかりの物件は売りやすい
不動産を売るのであれば、修繕を行ってからのほうが売りやすいです。
修繕を行った直後であれば、購入側の水漏れやひび割れなどのリスクが小さく、自分で修繕費を支払う必要がないので安心して購入できます。
最近では、中古住宅の流通を促進するために、国土交通省もインスペクション(既存住宅状況調査)の実施を促進しており、実施事例も徐々に多くなっています。
インスペクションや修繕工事を行い、家の品質を証明できる状態であれば、検査や修繕費に加えて転売利益も乗せた高い値段で売れる可能性があるのです。
買う側の立場に立って考える
自分が不動産の売主になる場合、買う側の立場や気持ちになって考えることも重要です。
買う側に立ち、「こういった不動産であれば買いたい」「こういったタイミングであれば不動産が必要になる」などを考え、相手のニーズに合わせて不動産を売却する戦略を立てていきましょう。
新耐震基準に適合した工事をしてから売る
住宅を購入する時に多くの人が気にするのは、家が地震に強いかどうかです。
日本では、震度7を超える震災に見舞われることが決して珍しくありません。
あまりにも古い物件の場合は耐震基準を満たしておらず、立地が良くてもなかなか売れないこともあります。
その場合、売却前に耐震性を高める工事を行えば、高く売れる可能性が生まれます。
これには2つのメリットがあります。
まずは購入者が安心して購入できること。
耐震性が保証されていれば、その点を評価して購入してくれる人が出てきます。
買う人にとってメリットが大きくなるので、スケジュールやコストに余裕があれば耐震工事を行ってから売却しても良いでしょう。
季節的な需要も考慮する
実の所、意外と重要なことは季節的なタイミングです。
引っ越しや住宅の購入が最も多いのは新年度に切り替わる直前、つまり2月や3月にかけてです。
新入学や新社会人だけではなく、転勤などもこの時期に多いことから、住宅の購入を検討する人が増えるのです。
人が住宅を欲しくなるタイミングで売却活動に入れば、多少は値段が高くてもすぐに住宅が必要な人が飛びつく可能性があります。
しかし、2~3月のタイミングを逃してしまうと、住宅購入の需要が減るので、高い値段ではなかなか売れません。
劇的に価格が変わるわけではありませんが、少しでも高く売りたいのであれば、年度の切り替わりに合わせるように売却活動を始めてみましょう。
最適なタイミングを見抜くのは不可能。市況の予測を分析してから売る
結局のところ、最適なタイミングというものはなかなか見定められるものではありません。
土地の相場を見るだけであれば、人口動態や鉄道の延伸計画、商業施設の開発計画などから予測できます。
人が集まる場所は住宅の需要も増え、不動産の価格が上がっていきます。
これから先に人口が増えることが見込めないエリアに不動産を持っているのであれば、少しでも早く売ってしまった方が良いでしょう。
逆に、土地の価格が上がりそうなエリアなら、少し待ってから売ると良いでしょう。
近年はコロナウイルスによる景気悪化の影響から一時的に取引数や相場が落ち込み、その後は都市部を中心に急速に需要が高まるといった大きな相場変動が見られました。
また、人の動き方・働き方が見直され、都心部の需要が落ち込んだり、地方都市は相対的に需要が高まったりという変化も現れるかもしれません。
下落相場では、今持っている不動産が高く�売れる時期を待つか、あるいは損切りをしてでも早めに売るか、どちらが正解かは数年経たないとわかりません。
やはり「不動産を損せずに売却するタイミング」の判断は非常に難しいと言わざるを得ませんが、情報収集をしっかり行って納得のいく売却ができるように準備しておきましょう。
▼関連記事