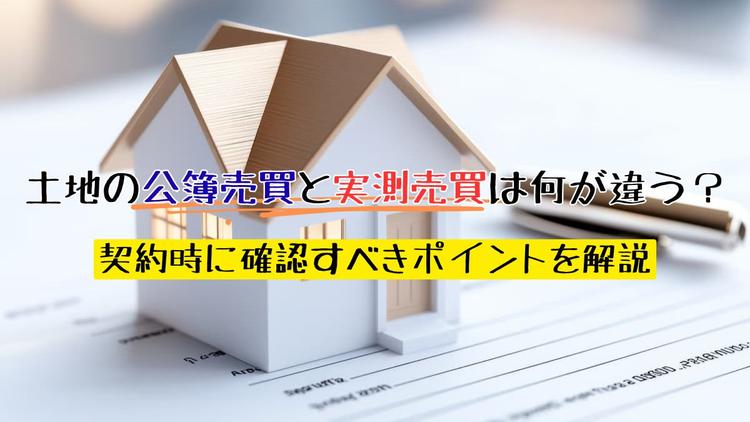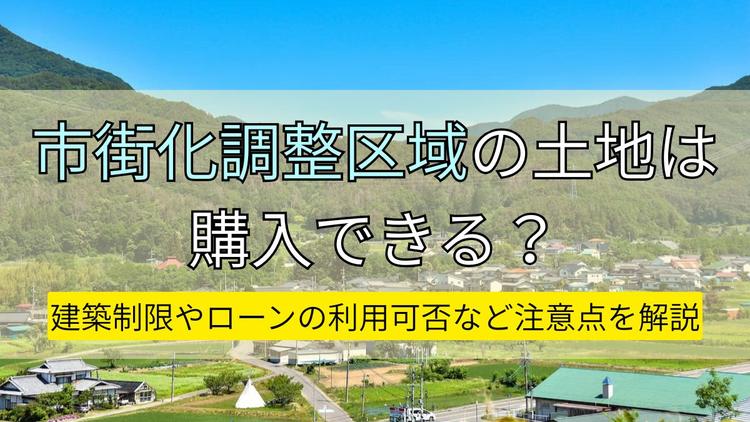土地の売却方法には、公簿売買と実測売買という2つの方法があります。
公簿売買は土地の面積を巡ってトラブルになるケースが多いため、違いや特徴を押さえておくことが大切です。
この記事では、公簿売買と実測売買の違いや契約時の確認ポイントなどを分かりやすく解説します。
公簿売買と実測売買の違いとは?
まずは、公簿売買と実測売買の違いを確認していきましょう。
公簿売買とは
公簿とは不動産の登記簿を指します。
不動産の登記簿には、不動産の種類や所在地、構造、面積などが記録されており、土地の面積も登記簿を見れば確認できます。
この登記簿上の土地面積を基準に売却価格を決めて取引する方法が公簿売買です。
公簿売買では、取引後に実際の面積が登記簿上と異なっていても価格の修正を行わないのが一般的で、その旨は契約書などにも明記されます。
実測売買とは
実測取引とは、実際に測量して判明した面積をもとに価格が決まる土地取引です。
売買契約前に測量して価格を決定するケースが一般的ですが、契約時に坪単価を定めて公簿売買し後日の測量結果に応じて差額精算するケースもあります。
どちらの方法であっても売却価格は実際の土地面積に応じて調整されるので、売却時にトラブルが少ない取引方法です。
公簿売買と実測売買の違い
公簿売買と実測売買の違いは、売却にともない土地を測量するかどうかという点です。
公簿売買は登記簿上の面積で取引するため、土地の測量は行いません。
そのため、土地を測量する時間や費用がかからずに売却できるというメリットがあります。
しかし、購入後に実際の面積が異なっているときに、トラブルになる可能性がある点には注意が必要です。
一方、実測売買は実際の測量結果に基づいて価格が決まるため、契約前もしくは契約後に測量を行います。
土地の正確な面積に応じた価格になるので、取引後に面積を巡ってのトラブルが起きにくいという点が特徴です。
土地取引では、測量の負担を避けるなどの理由から公簿売買を行うケースも珍しくありません。
ただ、近年はトラブルを避けるために実測売買を行うケースが一般的です。
公簿面積と実測面積は異なることがある?
公簿売買でトラブルになるのは、公簿面積(登記簿上の面積)と実測した面積が異なるケースです。
とはいえ、登記簿上の面積が異なることがあるのでしょうか。
公簿面積と実測面積は意外と異なることが多い
登記簿の地積がずいぶん前に測量されたケースでは、正確に測量されていない、測量後に自然災害で地形が変わっているなどで現状の地積と異なっている可能性があります。
また、2005年以前に測量、土地の分筆登記をしている場合も、分筆時の登記ルールが現在と異なるので誤差が生る可能性があるでしょう。
反対に、近年測量している場合は、測量基準変更や技術向上の点からも公簿面積と実測面積はほぼ一致します。
1~2%程度の誤差であれば許容されるケースが多い
公簿面積と実測面積の差が1~2%程度であれば許容範囲とする取引が一般的です。
とはいえ、許容範囲は人によって異なります。
たとえば、地価の高いエリアでは1%の差でも大きな価格差が生じる恐れがあるでしょう。
また、土地の面積(地積)が異なると購入後の活用にも関わってくるので、とくに建物を建築する場合は正確な面積が求められるケースもあります。
どの範囲までの差なら許容するか、面積の相違がある場合はどうやって清算するかは売主・買主との話し合いで決まります。
わずかな差異でもきっちり清算すると定めることも、一定面積内は清算しないとする契約も可能です。
いずれにしても、買主・売主共に誤差が生じるとトラブルになりやすいリスクを理��解したうえで双方納得できる契約方法を選択することが大切です。
▼関連記事:戸建てや土地を確定測量なしで購入しても大丈夫?リスクや注意点を解説
公簿面積と実測面積が異なるよくある原因
ここでは、公簿面積と実測面積が異なるよくある原因として以下の3つをみていきましょう。
- 昔の技術で測量されたまま更新されていない
- 境界標が紛失したり移動したりしている
- 地盤沈下などで土地の形状が変化した
それぞれ解説します。
昔の技術で測量されたまま更新されていない
現在の測量はGPSやレーザーを利用しており精度の高い測量が可能です。
一方、昔の測量は縄や三角測量など伝統的内測量技法というケースもあるなど、今ほど技術や器機が発達していないことから、測量していても実際の地積と誤差が生じるケースがあります。
そのため、測量されている場合でもいつ実施されているかを確認するようにしましょう。
境界標が紛失したり移動したりしている
境界標とは、境界の折れ目に接する目印のことです。
境界標と境界上を結ぶことで土地の境界線が分かるように設置されます。
境界標が設置されてから、自然災害や工事などによって紛失したり移動したりすることで、公簿面積と実測面積に誤差が生じるケースもあります。
地盤沈下などで土地の形状が変化した
測量していてもその後に地盤沈下や地すべり、洪水などで土地の形状が異なると、実測面積と公簿面積が異なる可能性があります。
このように未測量や測量から時間が経過しているケースでは実測面積が異なる可能性があるので、後々のトラブルを避けるためにも売却時に測量することをおすすめします。
公簿面積と実測面積が異なる場合の対処法
公簿面積と実測面積が異なる場合の対処法としては以下の2つが挙げられます。
- 契約書や重要事項説明書に契約条件を明記しておく
- 引き渡し前に測量を実施する
それぞれ見ていきましょう。
契約書や重要事項説明書に契約条件を明記しておく
公簿売買を行う場合、実測しない旨や実際の面積と誤差が生じる可能性がある点は、売主・買主ともに十分理解したうえで契約することが大切です。
そのうえで、契約書や重要事項説明書に「実際の面積と公簿面積に差異があっても異議を申し立てない」「面積の違いによる価格の修正は行わない」といった特約を明記しておくことをおすすめします。
これにより、後日、面積の違いを理由にトラブルとなるリスクを軽減できます。
面積の相違による契約不適合責任
また、このような面積に関するトラブルは「契約不適合責任」に関係する可能性があるため注意が必要です。
たとえば、登記面積と実際の面積に大きな差があり、それが買主にとって契約目的を達成できないほど重要な事項であれば、買主から契約不適合責任を追及されるおそれもあります。
そのため、公簿売買においては、「契約不適合責任の対象外とする」旨の特約(免責条項)を盛り込んでおくと安心です。
ただし、こうした免責特約が有効となるには、売主が買主に対して面積の誤差について十分に説明し、買主がその内容を理解・納得したうえで合意していることが前提となります。
実測売買でも面積の相違で価格修正が発生することがある
一方、実測売買の場合でも、誤差が生じた場合の契約条件や価格修正方法を明記しておくことが大切です。
実測売買で後日測量するケースでは、単価(坪単価・㎡単価)を決めて清算するケースが一般的でしょう。
ただし、誤差のうち一定範囲は精算対象外とするなど、清算の条件は売主と買主の合意によって柔軟に定められます。
価格を修正する対象となる面積や単価、清算方法などを細かく取り決めておかないと、たとえ実測売買であってもトラブルに発展するおそれがあるため、契約不適合責任の適用範囲を含め、しっかりと話し合い、契約書に明記することが重要です。
引き渡し前に測量を実施する
面積の誤差によるトラブルを防ぐには、引き渡し前に測量して確定した面積で取引するのが望ましいです。
とくに、境界線もあいまいというケースでは買主からも避けられやすくなるので、売りやすくするためにも測量することをおすすめします。
ただし、確定測量は隣地�の所有者の立ち合いも必要になるので時間がかかります。
売却にともない測量する場合は、できるだけ早い段階で測量を進めるようにしましょう。
なお、一般的には測量費用は売主が負担しますが、費用負担を巡ったトラブルになるケースもあるので契約後に測量する場合はしっかりと話し合って決めておくことが大切です。
▼関連記事:土地の売却時は確定測量の義務がある?費用や手順を解説
公簿売買と実測売買に関するよくある質問
最後に、公簿売買と実測売買に関するよくある質問をみていきましょう。
公簿売買で起こりがちなトラブルとは
公簿売買では、公簿面積と実測面積が異なることでトラブルになるケースがあります。
たとえば、坪単価50万円で30坪として売却した場合、売却価格は1,500万円です。
しかし、実際の面積が25坪だと5坪の差により250万円買主は多くお金を出していることになります。
反対に、実際が35坪なら売主は250万円損することになります。
このように実際の面積が異なるとどちらかに損失が発生することからトラブルになる恐れがあります。
また、土地の面積が小さくなることで希望の建築ができないなど、建築上のトラブルが起きるケースでもトラブルになる可能性があります。
実測売買するデメリットとは
実測販売するデメリットとしては、測量の手間や時間がかかる点が挙げられます。
確定測量を行う場合、1ヵ月程時間がかかり、とくに隣地が自治体となればより時間がかかります。
また、測量費用も50~80万円と高額になりやすい点にも注意が必要です。
▼関連記事:確定測量図は何に使う?測量図の種類や取得方法・費用を解説
公簿売買と実測売買はどちらが多い?
実際の取引における割合のデータはないため、どちらが多いとは言いきれません。
実測面積との差による差額が測量費用を上回るようであれば実測測量のメリットが大きいですが、差額がわずかな場合でも公簿売買でもよいでしょう。
とくに、農地や山林、大規模な宅地では測量費用が高額になる、時間をかなり要することになるので公簿売買の方が合理的なケースがあります。
しかし、面積が大きく異なるとトラブルなりやすいので、事前に双方納得する条件を設けて取引することが大切です。
一方、実測面積との差が大きくなることが予測される、地価が高く差額が大きくなりやすい土地ではトラブルをさけるために実測面積が適しています。
ただし、実測売買でも清算方法などしっかり話し合って契約書に明記しなければトラブルになる恐れがあるので注意しましょう。
まとめ
公簿売買は登記簿上の面積で取引するため、実際の面積と誤差が生じると買主とトラブルに発展する恐れがあります。
公簿売買を行う場合は、公簿売買の特徴や注意点を十分理解したうえで、しっかりと納得いく話し合いを行ったうえで契約することが大切です。
実際の面積でのトラブルを避けるためには実測売買が適しています。
しかし、測量が必要になるため時間や費用がかかる点には注意しましょう。
どちらの方法であっても信頼できる不動産会社のサポートを受けることが大切です。
売却時には複数査定を比較し信頼できる不動産会社を見つけるようにしましょう。