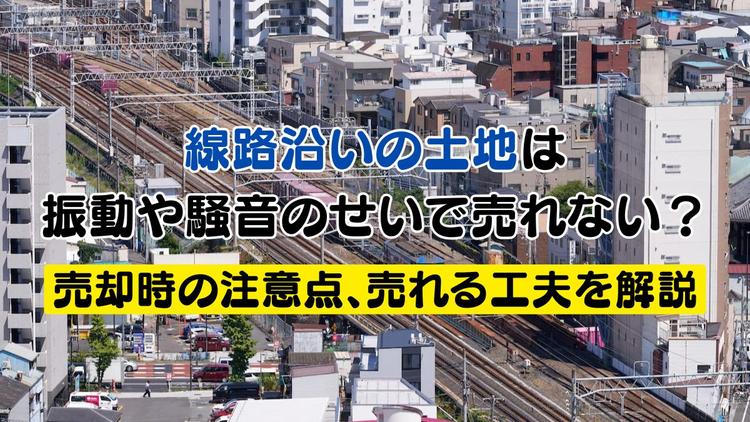私道の共有持分は、隣接する複数の住宅所有者が、共同で私道の一部を所有している状態を指します。
この共有関係は、通行権や維持管理の責任を共有することを意味しますが、同時に様々なトラブルの原因となることもあります。
ここでは、私道の共有持分でよくあるトラブルと、その対処法について解説します。
そもそも私道の共有持分とは
私道の共有持分とは、私道に面した土地を所有する人々が、その私道を共同で所有している状態を指します。
まずは、私道の共有持分の基本について押えておきましょう。
私道とは
道路は、大きく「公道」と「私道」の二種類に分類できます。
公道は、国や地方自治体が所有・管理する道路です。基本的に誰もが自由に通行することができます。
一方私道は、個人や法人などが所有・管理している道路のことです。原則として所有者または所有者から許可を得た人しか通行できません。
ただし、建築基準法や道路交通法上の道路として扱われている場合は、一般の通行が認められています。
共有持分とは
複数の人が一つの不動産を共同で所有する場合、それぞれの所有者が持つ所有権の割合を「持分」といいます。
私道の共有持分とは、私道に面した土地の所有者が、その私道の土地を共同で所有している状態を指します。
私道の共有持分の形態
私道の共有持分には、主に次の2つの形態があります。
- 共同所有型……私道に面した土地の所有者全員が、私道を均等な割合で共有する形態です。たとえば、1つの私道に5つの土地が接している場合、各土地の所有者は私道の持分を1/5ずつ所有します。
- 相互持合型……私道を分筆し、分筆された土地を各所有者が個別に所有する形態です。各所有者は、他の所有者が所有する私道部分に対して通行権などの利用権を有しています。
私道の共有持分でよくあるトラブル
複数の土地所有者が共同で所有する私道は、日常生活に欠かせない共有財産です。しかし、管理や利用を巡って、時に深刻なトラブルが発生する可能性があります。
ここでは、私道の共有持分に関する代表的なトラブル事例を項目別に解説します。
通行を巡るトラブル
私道の共有者間では、通行に関してしばしば意見が対立することがあります。特定の共有者が私道を駐車場代わりにしたり、私物を置いたりすることで、他の共有者の通行が妨げられるケースは後を絶ちません。
たとえば、日常的に私道に車を停める共有者や、引っ越し時に大量の荷物を長時間置いたままにする共有者がいます。その結果、他の共有者が車で通行できなくなったり、歩行者が安全に通れなくなったりする実害が生じるのです。
また、共有者以外の第三者が無断で私道を使用することで、トラブルに発展することも少なくありません。たとえば、家族や友人が頻繁に私道を遊び場として使う場合、私道の通常の利用範囲を超えていると見なされ、他の共有�者から異議申し立てを受けることがあります。
維持管理を巡るトラブル
私道の維持管理においても、費用負担の割合や方法を巡って対立が起こりがちです。舗装、清掃、除雪などの維持管理に対する意識の差が、合意形成を難しくする要因となるのです。
たとえば、「うちはほとんど車で通らないから費用を負担したくない」といった意見が出ることもあります。また、維持管理を業者に委託する場合、どの業者に依頼するか、費用の分担方法はどうするかで揉めることもあります。
複数の業者から見積もりをとっても、最終的に金額や仕様などで意見がまとまらないこともあるので、注意が必要です。
掘削を巡るトラブル
ライフラインの埋設を目的とした私道の掘削は、令和5年4月1日に改正民法が施行され、所有者の承諾が得られない場合でも、最小限の範囲で掘削ができるようになりました(民法第213条の2)。
しかし、民法の規定に関わらず、反対の意思表示をすることで掘削を妨害される事態も想定できます。
また、掘削後の原状回復責任や費用負担、さらには掘削工事による損害賠償責任の所在やその分担方法を巡っても、共有者間で意見が対立することがあるのです。
▼関連記事:私道の通行・掘削承諾書とは?
権利意識の差に起因するトラブル
共有者間の権利意識の差も、トラブルの要因として無視できません。
たとえば、一部の共有者が自己の利益のみを優先したり、逆に管理に対して無関心であったりすると、他の共有者に不満が募ります。
�また、引っ越しなどで連絡が取れなくなる共有者がいると、意思決定が滞ることもあります。
さらに、共有者の中には、高齢で入院している、または海外に引っ越して長期不在の人がいる場合もあり、連絡を取るだけでもひと苦労になることがあるのです。
形状変更や構造物設置によるトラブル
私道を利用している中で、形状変更や構造物の設置を提案されるケースがあります。具体的には次のようなことです。
形状変更のケース
- 車両の通行をスムーズにするために道路幅を広げる。
- 砂利道や未舗装の道路を舗装する。
構造物設置のケース
- 夜間の安全性を高めるために街灯を設置する。
- 車両の進入を防ぐために車止めを設置する。
- 私道の防犯性を高めるために防犯カメラを設置する。
- 私道の見通しの悪い場所に、ミラーを設置する。
これらの提案は、いずれも理由があり共感する人がいる一方で、メリットがない人からは反対意見が出されることがあります。
こうした意見対立は、共有者間の関係悪化を招き、私道の適切な管理を妨げる要因となります。
トラブルを未然に防ぐための対策
私道の共有持分を円滑に管理するために、トラブルを未然に防ぐことは重要です。
私道の共有は、時に予期せぬトラブルを引き起こす可能性があります。しかし、適切な対策を講じることで、これらのトラブルを未然に防ぎ、円滑な共有関係を維持することが可能です。
事前の合意形成とルールを策定する
共有者全員で私道の利用方法、維持管理、費用負担などについて徹底的に話し合い�、明確なルールを策定することが重要です。
話し合いでは、各々の意見を尊重し、全員が納得できる合意点を見つけるよう努めましょう。 策定したルールは必ず書面に残し、全員が内容を理解し、遵守するようにします。
通行に関するルール、清掃や除雪の分担、修繕に関する費用負担など、具体的な項目についても明確に定めておくことが大切です。
良好なコミュニケーションの維持する
定期的な情報共有や意見交換の場を設け、共有者間のコミュニケーションを円滑にすることが望ましいといえます。
問題が発生した場合でも、冷静かつ建設的な話し合いができるよう、日頃から良好な関係を築いておくことが重要です。
最近ではチャットツールなどを活用し、グループを作って情報共有をスムーズに行うケースも増えています。
専門家を活用する
法律や不動産に関する専門知識がない場合は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士などの専門家に相談することも有効です。
専門家は、法的な側面や権利関係について適切なアドバイスを提供し、トラブルの予防や解決をサポートしてくれます。
特に、私道の持分を売却したい場合や、私道の形状を変更したい場合などは、専門家の助言が必須になるでしょう。
書面による記録を徹底する
私道に関するあらゆる事項(話し合いの内容、決定事項、費用負担の記録など)を記録し、保管しておくことも重要です。
これらの記録は、後々のトラブル発生時に有力な証拠となり、問題解決をスムーズに進める上で役立ちます。
境界を明確にする
私道の境界が曖昧な場合には測量を行い、境界標を設置するなどして、境界線を明確にしておくことが大切です。
境界線を明確にしておくことは、将来隣地の方との間で起こる境界に関するトラブルを未然に防ぎます。
これらの対策を講じることで、私道の共有に関するトラブルを未然に防ぎ、快適な住環境を維持することができます。共有者全員が協力し、良好な関係を築いていきましょう。
▼関連記事:土地の境界トラブルでよくある事例と解決策
トラブルになったときの対処法
私道の共有持分に関するトラブルは、残念ながら完全に避けることが難しい場合もあります。
万が一トラブルが発生してしまった場合に、どのように対処すればよいのでしょうか。
ここでは、トラブルの種類に応じた具体的な対処法について解説します。
通行を巡るトラブルの対処法
特定の共有者による通行妨害でトラブルになっている場合、まずは当事者間で冷静に話し合い、解決を試みましょう。
たとえば、「いつから、どのような行為で困っているのか」「改善してもらえないと具体的にどう困るのか」を明確に伝えることが大切です。
話し合いで解決しない場合は、内容証明郵便で改善を要求する方法や、弁護士に相談して法的措置を検討することも視野に入れましょう。
第三者の無断通行でトラブルになっている場合は、まず通行を控えるように警告し、必要であれば警察に通報することも検討します。
警告書を提示したり、監視カメラを設置する、また、私道である旨の看板を設置することで、無断通行を防ぐ効果が期待できます。
通行ルールについて対立がある場合は、共有者全員で改めて話し合い、新たなルールを策定しましょう。たとえば、時間帯によって通行できる車両を制限するな�ど、具体的なルールを設けることが考えられます。
維持管理を巡るトラブルの対処法
費用負担の不公平感がある場合は、維持管理費用の内訳を明確にし、負担割合について再度協議します。
業者選定で対立している場合は、複数の業者から見積もりを取り、併せて根拠となる資料を提出してもらい比較検討する方法が有効です。
なお、私道の一部陥没に対する補修であれば、共有物の現状を維持し、損傷や劣化を防ぐために行う最低限の管理・修繕のための「保存行為」として単独で実施することができます(民法第252条第2項但し書き)。
掘削を巡るトラブルの対処法
設備配管設置のために私道を掘削する際、承諾が得られない場合は、まず掘削の必要性や安全性を丁寧に説明し、相手の理解を得るよう努めましょう。
民法第213条の2に基づき、承諾がない場合でも最小限の範囲で掘削が可能であることも併せて説明することが大切です。
また、掘削による原状回復責任や損害賠償を求められるケースでは、工事前に原状回復の範囲や費用負担について合意を得ておくことが重要です。工事前に写真撮影や記録を行い、工事前後の状況を残しておきましょう。
万が一、損害が発生した場合は、速やかに原因を特定し、責任の所在を明確にします。示談交渉が難しい場合は、訴訟の可能性も視野に入れて対応を検討しましょう。
権利意識の差に起因するトラブルの対処法
自己利益の優先や無関心によるトラブルが発生した場合、まずは共有者全員で私道の利用に関するルールを再確認し、互いの権利を尊重するように求めること�が重要です。
連絡が取れない共有者がいる場合は、戸籍謄本や住民票などを取得し、連絡先を調査します。この調査は、弁護士や司法書士に依頼することで、法律に基づいて必要な手続きを代行してもらえる場合もあります。
また、共有者が長期間にわたり生死不明である場合や、連絡が全く取れない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることも検討するべきです。
不在者財産管理人制度は不在者本人や不在者の財産に利害関係を持つ第三者の利益を保護するために、家庭裁判所が申立てにより財産管理人を選任するものです。
形状変更や構造物設置に関するトラブルの対処法
形状変更や構造物の設置をしたい場合には、反対者を含めて再度話し合いを行い、お互いに妥協できる案を模索することが重要です。たとえぱ、形状変更の範囲を小さくする、構造物の種類を変更するなど、共感を得られる方法を探ります。
私道の幅を著しく狭める、または広げる場合は「変更行為」に該当し、共有者全員の合意が必要です(民法第251条)。しかし、水道管の更新に伴う私道全体の掘削や、砂利道からアスファルト舗装への変更などは「管理行為」と見なされ、共有者の持ち分価格の過半数で実施することができます(民法第252条)。
これらの法的根拠を踏まえた上で、現実的な解決法を検討することが大切です。
自分の持ち分を売却する
私道の共有トラブルが絶えない場合、自分の持分を売却することは、状況によっては有効な解決策となり得ます。ただし、売却にはいくつかの注意点と考慮すべき事項があります。
ま��ず、私道の持分のみを購入したいという人は限られているため、買い手を見つけるのが難しい場合があります。特に、私道に関するトラブルや権利関係が複雑な場合は、さらに買い手を見つけるのが困難になるでしょう。
また、買い手が限られるため、売却価格が低くなる可能性があります。さらに、共有者との関係が悪化するリスクも考慮する必要があります。
売却方法としては、共有持分を専門に扱う不動産業者に相談することで、買い手探しのサポートを受けたり、適切な売却価格についてアドバイスを受けることができます。他の共有者に持分を買い取ってもらうことも一つの選択肢です。
まとめ
私道の共有持分は、隣接住民にとって不可欠な共有財産である一方、通行、維持管理、掘削、権利意識の違い、形状変更や構造物の設置など、様々な要因によるトラブルが発生しやすい側面も持ち合わせています。
これらのトラブルを未然に防ぐためには、共有者間での事前の合意形成と明確なルールの策定、良好なコミュニケーションの維持、専門家の適切な活用、そして決定事項や費用の記録を徹底することが重要です。境界を明確にしておくことも、将来的な隣地とのトラブルを避ける上で有効な対策となります。
万が一トラブルが発生してしまった場合には、まずは当事者間で冷静に話し合い、解決を試みることが基本です。しかし、話し合いが難しい場合は、内容証明郵便での通知、専門家への相談、第三者機関の仲裁、さらには法的な措置も視野に入れる必要があります。
また、共有関係が著しく困難な状況においては、自身の共有持分の売却も選択肢の一つとなり得ますが、買い手を見つける難しさや価格、共有者との関係悪化といった側面も考慮しましょう。