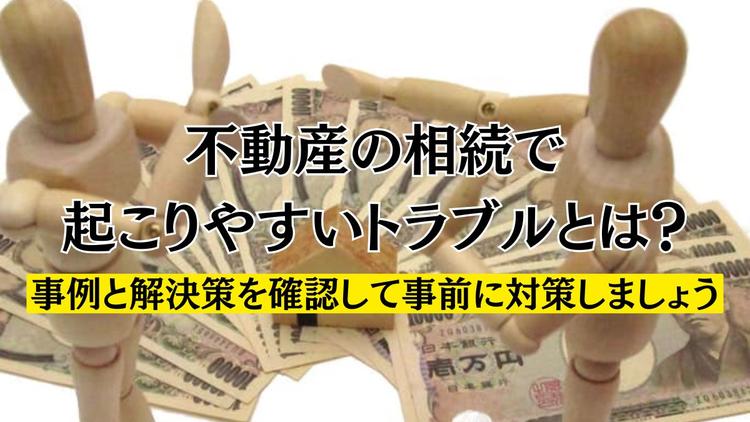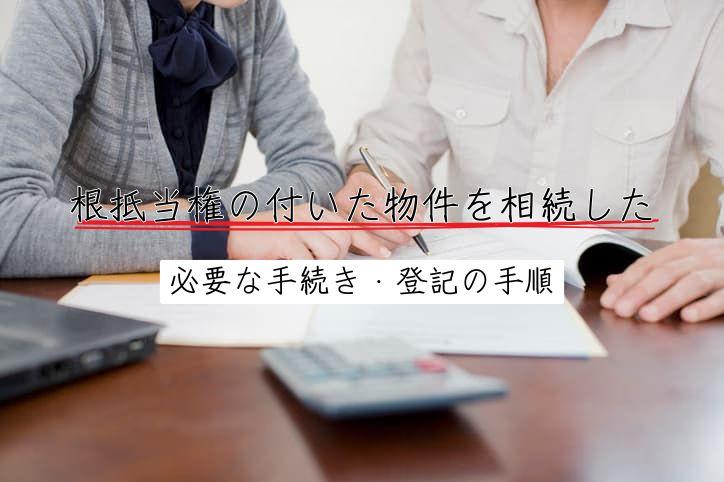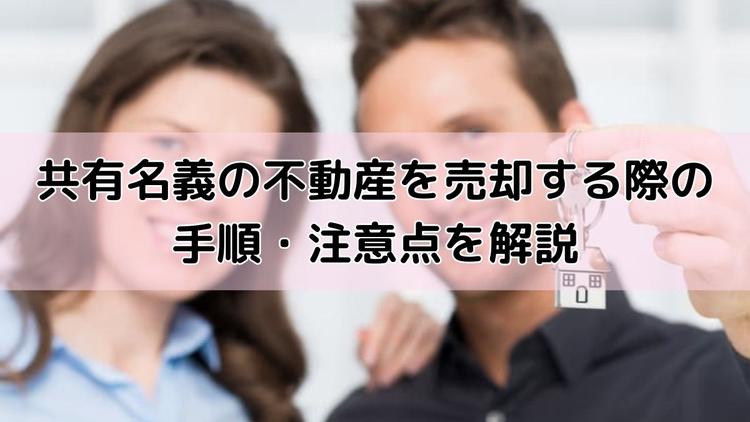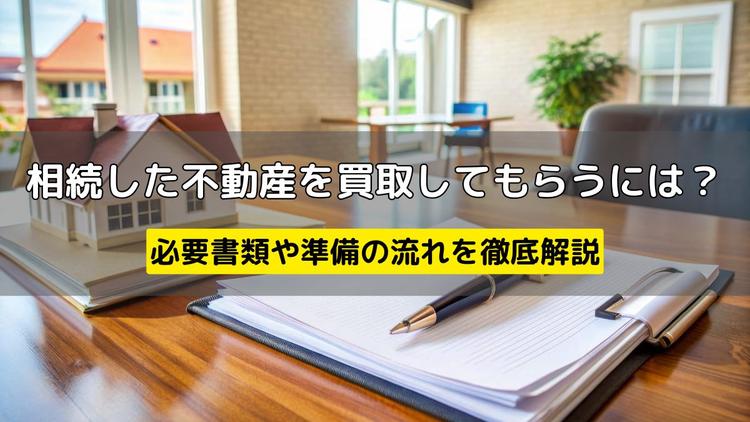不動産の相続トラブルは、けっして他人事ではありません。親が住んでいる実家の不動産が原因で、相続トラブルに発展することがあるからです。不動産が絡んだトラブルは、解決までに長い期間を要してしまいます。
複雑な事態に巻き込まれないためには、事前に対策を講じておくことが非常に大切です。この記事では、不動産の相続で起こりやすいトラブルの事例を紹介したうえで、その解決策について解説をしていきます。
不動産相続によるトラブルは他人事ではない
相続トラブルの大きな要因になるのが不動産です。
そう聞くと、資産家が保有する広大な土地や都心の邸宅が問題になるのだろうと考えがちですが、実は親が住んでいた実家などの身近な不動産の存在が、相続トラブルを誘発するケースが多いのです。
不動産相続によるトラブル発生件数は毎年増加
不動産相続によるトラブル件数は毎年増加する傾向にあります。
最高裁判所が作成した「平成24年度司法統計1」によると、家事調停や審判まで至った遺産分割事件の件数が、平成14年には約11,000件でしたが、平成24年には約15,000件まで増加しています。
相続における家事調停とは、遺産分割協議で話し合いがつかなかった場合に、裁判官と民間から選ばれた調停員が間に入り解決を目指すものです。
調停が成立しなかった場合には、審判に移ることになります。
不動産相続でトラブルになる原因
遺言書がないような場合には、民法で規定された法定相続分を相続することになります。
「相続トラブル」と聞くと、資産家の家族で発生する問題だと考えがちですが、実は遺産分割事件になった約7割が、遺産総額5,000万円以下の案件です。
1,000万円以下の案件だけでも全体の約3割を占めています。
むしろ、遺産総額が1億円を超えるような資産家の家族の間で遺産分割事件にまで至るケースは少数派なのです。
「うちの親族は相続トラブルとは無縁だ」と考えている人の多くは、「遺言書がなくても法定相続分で分割すればいい」という思いがあります。
しかし、相続財産は現金のようにきれいに分割できる物ばかりではありません。
自宅や田畑などの不動産があると、その資産価値をどう評価するのかによって、それぞれの相続額が大きく異なってきます。
実際に売却をして現金化すれば問題は解決できますが、現実はそんなに簡単に運びません。
親が住んでいた自宅に同居していた相続人がいた場合は、まず自宅を売却する選択肢を外さなければいけません。
そのうえで、他の相続人に不動産価額から割り出した現金を渡すことになります。
この際の金額によってはトラブルに発展することがあります。
あるいは長い間、親の介護をしてきた立場だと、それまで一切無関係で過ごしてきた兄弟姉妹と相続が同額だと、なかなか納得がいくものではありません。
多くの場合、親が自宅という不動産を所有しており、また�要介護者になり得ます。
その事実を捉えただけでも、相続トラブルは極めて身近な問題だといえるのです。
不動産相続による代表的なトラブル事例と解決策
不動産相続によるトラブルは、どのようなケースで発生するのでしょうか。
ここでは、不動産相続による代表的なトラブルの事例を紹介するとともにその解決策について解説をしていきます。
①相続人間でトラブルになるケース
相続トラブルは、相続人の数が多くなれば、それだけトラブルになるリスクが高くなります。
特に不動産が相続の対象になっているケースでは、分割方法で協議がまとまらないことがあります。
また、親が認知していた子どもや離婚した配偶者の間にできた子どもが名乗り出ることことで、遺産分割協議が白紙に戻ることがあります。
解決策
親が再婚をしている場合や、愛人の存在がちらつくようなケースでは、しっかりと本人から事実確認をしておくことが重要です。
相続人が多数いるようなケースや不動産が相続財産となっている場合は、法定相続だけでは解決できないことがあります。
最もトラブルなく相続を進められるのは、被相続人による遺言書の存在です。
なかなか切り出しにくいことですが、相続トラブルを回避するためにも、被相続人が元気なうちに遺言書を作成しておくように頼んでおきましょう。
②相続した不動産を平等に分けようとするケース
相続人の兄弟姉妹が円満な関係であってもトラブルになることがあります。
お互いに損得がないように、平等に分割しようとすると、それが揉め事に発展してしまうのです。
平等な分割を目指す際にトラブルの要因になるのが不動産です。
不動産の価額の指標が複数存在するため、どの値を採用するのかで意見が分かれてしまうことがあります。
解決策
不動産を平等に分割するには、次のような方法があります。
- 換価分割
- 現物分割
- 共有分割
換価分割
この中で、最もトラブルを回避できる方法が換価分割です。
換価分割とは、実際に相続不動産を売却して、売却金を相続人の間で分配する方法です。
たとえば3人の兄弟が相続人となっている場合、不動産が2,000万円で売れて200万円の経費がかかったとします。
手元に入るのが1,800万円ですから、3等分した600万円をそれぞれの兄弟が受け取ります。
現物分割
現物分割は、相続する土地を分筆して、分筆された土地をそれぞれの相続人が所有する方法です。
3人兄弟が相続する場合は、3筆に分筆してそれぞれの土地を所有します。
所有する面積が同じであれば、平等に分割できると思えますが、分筆された土地の方位や形状、接道位置が異なることから、真の意味で同価値の分筆ができる物件の方が稀なのです。
さらに家が建っている土地では、事実上分筆が困難です。
また対象の土地が一般的な宅地規模だと、分筆することで土地の間口が狭くなったり、狭隘になったりするため、土地を有効に活用をする手立てがなくなり、それぞれの土地の評価額が大幅に下がってしまうことがあります。
共有分割
共有分割は、ひとつの土地を共有持ち分とする分割方法です。
3人兄弟が共有する場合は、それぞれの持分が3分の1ずつになります。
共有分割は、遺産分割協議がもつれて、なかなか決着できない場合に用いられる手法です。
表面上解決したように見えますが、けっして望ましい方法ではありません。
土地活用に際しては、所有者全員の同意が必要になるため、意見が割れると事実上まったく有効に活用できない土地になってしまうからです。
さらに次の子どもの世代や孫の世代に相続することになれば、共有名義人が多人数になり、ますます身動きのできない土地になってしまうのです。
また共有分割の場合、固定資産税の納付についてもトラブルになることがあります。
固定資産税は、所有の持分に応じて課税されるものではなく、地方税法の規定により連帯納税義務になります。
連帯納税義務とは共有者全員が、連帯して固定資産税の納税義務を負い、負担することをいいます。
連帯納税義務であるのでそれぞれの所有者に知らせる必要はなく、納税通知書は共有名義人の代表者に送付されます。
代表者は他の共有者から納税負担分を自らが徴収しなくてはいけないので、納期ごとに煩わしい思いをすることになります。
③不動産を相続すると不均衡が起こるケース
親と同居していた子がいた場合、被相続人である親が死亡した後も引き続き子が居住するのが一般的です。
この場合、同居していた子は自宅の土地や建物を相続しないことには、その後も安心して暮らすことができません。
しかし、相続した不動産が一定の価値がある物件だった場合、他の兄弟姉妹の相続分についてトラブルになることがあります。
特に親が自宅以外に、めぼしい相続財産を保有していなかった場合には、解決への道筋が展望できなくなります。
解決策
不動産を相続人の一人の所有にせざるを得ない場合、不動産を相続した人が他の相続人に現金を支払う代償分割という方法が適しています。
たとえば時価が3,000万円の不動産を3人兄弟の長男が相続した場合、他の二人の弟に1,000万円ずつ現金で支払うという方法です。
このため不動産を相続する人は、他の相続人に代償金として渡せる資産を有していないと、代償分割は実行できません。
代償分割で争点になるのは、相続の対象となる不動産の評価額です。
ここで採用できる価額は、「相続税評価額」か「代償分割時の時価」のいずれかです。
相続税の算定基準にする場合は、相続税評価額が基本になりますが、相続税評価額は、実勢価格(時価)の80%程度です。
この価額を採用すると、代償金を受け取る相続人が納得しない可能性が高くなります。
このため実際の相続においては、代償分割時の時価の方が多く採用されています。
同居していた相続人にとって、親の所有していた家に住み続けることは切実な問題です。
将来相続が発�生した際に、代償分割をするための資金が不足するのが明らかな場合は、早い段階から他の相続人に事情を説明して理解を得る努力が必要になります。
また被相続人である親に実情を説明して、遺言書を作成してもらうという方法も有効です。
代償分割の注意点
代償金の支払いに際しては、遺産分割協議書を作成して金銭の譲渡が代償分割によるものだと明記する必要があります。
これを明記した遺産分割協議書がないと、他の相続人に渡した金銭が贈与とみなされて、贈与税の対象になってしまうことがあるからです。
また、代償金の代わりに以前から所有していた別の不動産を譲ると、譲渡所得税の対象になります。
一見、不動産の交換であり利益はないように思えますが、税制上は代償金という負債を返済するために土地を売却したという考えになるのです。
④誰が不動産を相続するかで揉めるケース
相続財産の中で、親が住んでいた実家の不動産が最も高い価値であるケースはけっして珍しいことではありません。
ところが、不動産の占める割合が高いと、不動産を誰が相続するのかでトラブルになることがあるのです。
特に親と同居していた相続人がいた場合、不動産の相続を強く主張することがあります。
民法改正によって被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした親族(六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)であれば、特別寄与料を請求できるようになりました。
このため、長年同居をして親を支えてきたことが財産の維持に寄与したとして、自宅の相続を主張することが考えられます。
また特別寄与料は、法定相続人でない親族も対象となるため、嫁いできた長男の妻が長期間、被相続人の介護をしていたようなケースだと、財産の維持に特別の寄与をしたとして、不動産の相続を主張することが考えられます。
旧民法では、遺産相続において、まったく評価されなかった同居や介護の実績が、民法改正により根拠を得たことから、貢献度の認識が大きく食い違うと、相続トラブルに発展することになります。
解決策
被相続人である親としても、介護してくれた人やその家族に対しては強い感謝の気持ちを持ち合わせているものです。
しかし気持ちだけでは、相続に反映させることはできません。
特に不動産が資産の大半を占めるような場合は、同居している相続人は生前から親としっかり話し合いをして、遺言書を準備してもらいましょう。
自筆証書遺言は、かつてすべて自筆によるものとされていましたが��、民法改正により、財産目録に関してはパソコン入力による作成が認められています。
このため、遺言書を作成する手間が大幅に削減できるようになりました。
また保管場所についても、自筆証書遺言を法務局に保管する制度が運用されています。
この制度を活用することで、不法な改ざんをされたり紛失したりすることなく、安心して遺言書を残すことができるようになっているのです。
⑤相続した不動産の名義変更ができていなかったケース
親の死亡により相続が発生したために、不動産の登記を確認してみると、物件の所有者が大昔に亡くなった祖父のままだったというケースがあります。
この場合、祖父の相続から整理していくことになり、膨大な時間と労力を要することになります。
特に親の兄弟姉妹が多人数だと、相続人の整理や事務処理は、個人で完結させるのは難しいでしょう。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼することになるので、その費用負担も発生します。
なお、相続登記の未完了により権利関係が複雑な不動産の存在は、かねてより問題視されており、2024年4月からは相続登記が義務化されています2。
解決策
不動産の名義人に不安がある場合は、親が健在のうちに不動産登記の確認をしておきましょう。
有料のサービスになりますが、自宅からインターネットによって確認することが可能です。
祖父の時代の相続は、当事者である親の主導で進めてもらうことで、より早い解決が望めます。
⑥遺言書が問題でトラブルに発展するケース
相続のトラブルを回避するのに最も有効な方法が遺言書の作成です。
故人の遺志を明確にすることで、相続人の不満を解消させることができるからです。
ところが、この遺言書自体が原因でトラブルに発展することがあるので注意が必要です。
特に相続内容が次のようなケースだと、有効性を巡って争いになることがあります。
- 遺言書の形式が無効である
- 遺留分を無視した遺言の内容である
- 特定の相続人のみに相続させる内容である
- 第三者に遺産を全部遺贈する内容である
相続財産の分割が著しく不均等な内容の遺言書だと、相続額を大幅に抑えられた法定相続人から異議が出され、遺言書の些細な瑕疵がトラブルに発展することがあります。
解決策その1(遺言書の適法性を確認する)
個人の遺志を尊重して相続財産の分割を行うのが遺言書の役割ですが、そのためには法的に適正な遺言書であるという前提が必須です。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の方式があります。
このうち秘密証書遺言はあまり一般的には採用されません。
また公正証書遺言は、公証人が法律で定められた方法で作成するので、トラブルになることはほぼありません。
したがって、適正な遺言書であるかを問われるのは、ほとんどのケースで自筆証書遺言です。
一般的に自筆証書遺言が次のような状態であると無効とされてしまいます。
- パソコンで作成している(相続財産目録については可)
- 遺言者の押印がない
- 遺言者の署名がない
- 作成した日��付がない
- 明らかに遺言者以外の人間が書いた遺言書である
- 相続する財産が不明確
- 作成した日付が明らかに虚偽である
- 動画や録音による遺言
これらの状態の遺言書は、訴訟になった場合無効となる可能性が高く、その場合改めて相続人同士で遺産分割協議を行うことになります。
また自宅などに自筆証書遺言が保管されている場合、勝手に開封することは認められません。
未開封のまま家庭裁判所に提出し、検認の請求をして、相続人の立会いの下で開封をする流れになります。
勝手に開封をしたからといって、遺言書の効力自体が無効になるわけではありませんが、開封した者は5万円以下の過料の対象になるので注意が必要です。
こうしたことから、相続財産をスムーズに分割するためには、遺言書の適法性を相続人全員で確認することが重要です。
解決策その2(遺留分侵害額請求をする)
遺言書による遺産の配分が明らかに偏った内容である場合は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の相続分のことをいいます。
相続においては、遺言書による財産の分割が優先されます。
しかも、遺言者の自由意思によって、誰にどれだけの財産を相続させるのかを決めることができます。
したがって個人的に世話になった人など、法定相続人以外の人に相続財産を渡すことも可能なのです。
しかし、そのために法定相続人の遺産がゼロ円になるというのは、あまりにも酷であるために、民法で被相続人の配偶者や子は、法定相続額の2分の1が遺留分として保証されてい��るのです。
相続発生後に遺留分の侵害が分かれば、当該相続人が侵害している受遺者・受贈者に対して遺留分侵害額請求をします。
これで相手方が遺留分を返還してくれれば問題は解決します。
相手方が納得しなかった場合は、家庭裁判所で調停をすることになります。
調停手続きにおいては、当事者の双方から事情を聞き取り、遺産の精査をしたうえで、当事者双方の意向に沿った解決案の提示をしてくれます。
調停でも解決できなかった場合は、地方裁判所(請求金額が140万円以下の場合には簡易裁判所)で民事訴訟をし、判決に従うという流れになります。
⑦相続した不動産を「空き家」にするケース
親から実家を相続した場合、思い入れがあるために売却に踏み切れず、空き家として維持することがあります。
しかし、空き家の状態で放置していると、思わぬリスクがあることを失念してはいけません。
どのような事態が想定されるのか紹介していきましょう。
固定資産税が増加するリスク
空き家の状態で放置しておくと、想定以上に建物の劣化が進みます。
台風や豪雨の際にも対策が取れないので、無防備で風雨にさらされ、知らぬ間に崩壊寸前なることもあります。
崩壊の危険がある家屋は、地方自治体が特定空き家に指定することがあります。
特定空き家に指定された土地は、固定資産税の優遇税制が適用されないため、固定資産税が一気に6倍になることがあります。
犯罪リスク
空き家であることが周囲に知られると、不審者が侵入をして、勝手に住みつくことがあります。
犯罪者が潜伏したり、犯罪行為を行う拠点として利用されたりする可能性があります。
周辺住民のリスク
空き家だと、庭木の手入れもなおざりになるため、雑草が生い茂ります。
こうした雑草地は野生動物の巣窟となることがあります。
また不法投棄の場所として利用されることもあります。
これらにより発生した悪臭などの不衛生な状態が、近隣の住宅に迷惑をかけることもあるので注意しなければいけません。
定期的メンテナンスや維持費の発生
空き家の劣化によるリスクを回避するためには、定期的なメンテナンスによる維持を欠かすことはできません。
特に空き家においては�、定期的な家屋の換気が求められるために、自らが実家に赴くか代理人による作業を依頼することになります。
これらに要する交通費や依頼費の発生も念頭に置いておく必要があります。
また空き家は日常の点検ができないため、人が居住する家に比べて屋根材や外壁の劣化が早まるリスクがあります。
室内へ雨水が浸入すれば、加速度的に家屋が劣化しますから、著しく経年をした建物だと本格的な改修工事が必要です。
解決策
兄弟姉妹の構成上、実家を相続する可能性が高い場合は、予め対応策を考えておきましょう。
対応策としては、次のような方法があります。
- 売却する
- 貸し出す
- 管理会社に管理を依頼する
- 家族で定期的に管理する
- 家族で住む
売却しようと思っても、人口が少ない地方の場合なかなか買手が見つからないことがあります。
仲介による売却が困難だと予測できる場合は、買取専門の不動産会社に買い取ってもらうという方法を検討しましょう。
また他人に貸し出すという方法は、家賃収入の他に、建物を使用することによるメンテナンス効果が期待できます。
地方では、自治体やNPOなどによる空き家バンク制度を活用する方法が有効です。
家族自らが管理するのは、自宅と距離が離れている場合、金銭的にも精神的にも負担が大きくなるので注意が必要です。
新たな仕事が得られる目途が立つのであれば、自宅を売却して、実家に移り住むという方法も考えられます。
まとめ
遺産分割事件になった約7割が遺産総額5,000万円以下の案件です。
つまり一般的な家庭にこそ、相続トラブルの芽が潜んでいるのです。
トラブルを回避するためには平等な分割が理想ですが、不動産が介在していると、なかなか思いどおりには運べません。
相続人全員が納得する分割方法を実行することが困難だからです。
不動産を平等に分割する方法としては、換価分割、現物分割、共有分割の3種類があります。
このうち、最も平等に分割できる方法が換価分割です。
実際に物件を売却した後に現金を分配するのですから、相続人の誰もが納得のできる方法でしょう。
しかし現実には、相続する家に同居家族がいると、安易に売却することはできません。
その場合には、他の相続人に自宅の不動産の価額に相当する代償金を渡す代償分割が適しています。
ただし、実際に渡せるだけの現金を用意できなければ、この方法は実行できません。
あらゆる相続で言えることですが、トラブルを回避できる最善の方法は遺言書による相続です。
法的に有効な遺言書であれば、遺留分を侵害しない限り、遺言どおりに分割することができます。
特に相続財産の中に不動産が含まれているようなケースでは、現実的に平等な分配は困難であるため、遺言書の存在はとても心強いものになります。
親が持ち家に住んでいるのであれば、元気なうちに相続をテーマにした話し合いの機会を設けて、遺言書を作成してもらうようお願いをしてみてはいかがでしょうか。
それが将来の相続トラブルを回避する道に通じます。