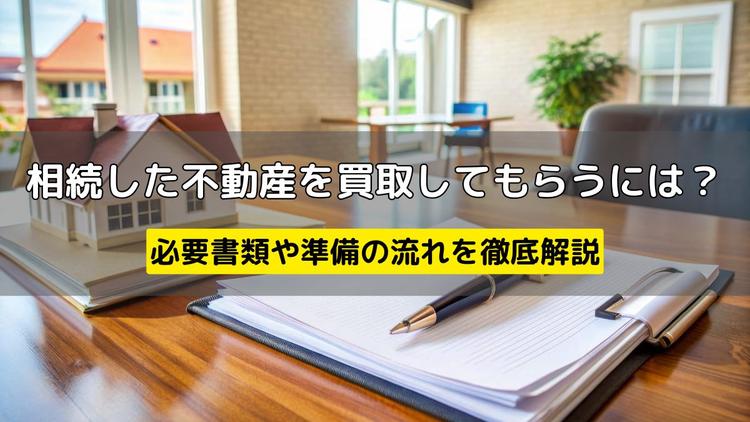相続や家庭の事情で「実家を処分したい」と考える方にとって、どのような手順で進めればよいのか分からず、不安を感じることが多いでしょう。
実家処分には、法的手続きや遺品整理、不動産売却といったさまざまな工程があり、計画的に進めることが重要です。
本記事では、実家処分の全体像をわかりやすく解説します。初めて不動産を売却する方でも理解しやすいよう、手順ごとにポイントを押さえて説明しています。
これから実家の処分を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
実家処分までの全体像
まずは実家処分までの全体像をご紹介します。
ここでは、相続不動産の処分の手順について解説します。「実家を相続したけど処分したい」とお悩みの方は参考にしてみてください。
- 遺言書を確認する
- 実家の名義変更をおこなう
- 遺品を整理・処分する
- 土地の境界を確認する
- 不動産会社の査定を受ける
- 不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 買主と売買契約を結ぶ
- 決済・実家の引き渡し
- 翌年に確定申告する
それぞれの手順を詳しく解説します。
実家処分の流れ①:遺言書を確認する
まずは遺言書を確認しましょう。
ここでは、遺言書があるケースと無いケースに分けて解説します。遺言書が無い場合は遺産分割協議をおこなう必要があるため、よく確認しておきましょう。
遺言書がある場合は遺言書に従う
遺言書がある場合は遺言書に従って相続財産が分配されます。
例えば、実家を特定の相続人に譲る、売却して得た資金を分配するなど、具体的な指示が含まれている場合があればそれに従います。
また、遺言書がある場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認手続きとは、遺言書の内容を確認し、その保管や改ざんの有無を確かめるための手続きです。
なお、検認手続き自体は、遺言書の形式的な確認や内容の保全を目的としたものであり、その遺言書が法的に有効かどうかを判断するものではありません。
検認を受けた上で「遺言書が民法で定められた形式に沿っているか」「遺言書の内容が法律に違反していないか」といった点をチェックした上で、相続手続きを進める必要があります。
遺言書がある場合、そのまま開封せずに家庭裁判所へ提出し、検認手続きについて相談しましょう。
勝手に開封してしまうと5万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。
遺言書がない場合は遺産分割協議をする
遺言書がない場合は、遺産分割協議をおこなう必要があります。
ここでは遺産分割協議の意味や方法について解説します。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意内容を文書化する手続きです。
遺産分割協議をすることで相続財産の相続人が決定するため、相続時のトラブルを防げます。
特に、不動産や預貯金の相続はトラブルが発生しやすいため、相続人同士でよく話し合って決めることが大切です。
遺産分割協議については、弁護士や司法書士などの専門家へ相談しましょう。
分割方法は3種類ある
遺産分割協議は以下3つの方法があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
現物分割とは、遺産をそのままの形で相続人に分ける方法です。例えば、土地や建物を物理的に分割して各相続人が取得します。
この際、土地を実際に分ける手続きとして「分筆」の方法があります。分筆とは、一つの土地を複数の土地に分けて登記する手続きです。これにより、各相続人が独立した土地を所有できます。
また、土地を分けずに共有のまま所有する「持分所有」という方法もあります。各相続人が土地全体に対して一定の割合(持分)を持つ所有形態です。
しかし、持分所有では、土地の利用や処分に関して他の共有者との協議が必要となるため、意思決定が複雑になる可能性があります。
代償分割とは、特定の相続人が遺産全体を取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭などで補償する方法です。例えば、長男が家を相続し、他の兄弟にはその価値に見合う金額を支払います。
換価分割とは、遺産を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。不動産などを現金化して公平に分配できます。
これらの方法で分割できるため、相続人同士でよく話し合ったうえで分割方法を決めましょう。
実家処分の流れ②:実家の名義変更をおこなう
遺言書を確認したら実家の名義変更をおこないましょう。
ここでは、名義変更が必要な理由や名義変更の方法について解説します。また、必要書類や費用もかかるため、事前に確認しておきましょう。
- 名義変更が必要な理由
- 名義変更の方法
- 名義変更に必要な書類・費用
名義変更が必要な理由
名義変更が必要な理由は、名義変更をおこなわないと売却の手続きが進められないからです。
そもそも、不動産を売却できるのは基本的に不動産の名義人のみです。被相続人が名義人となっているままでは、売却できません。
そのため、名義人を相続人に変更する必要があります。
名義変更の方法
名義変更は、対象不動産を管轄する法務局でおこないます。
相続不動産における相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に手続きを完了しなければなりません。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
相続登記の手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があるので忘れずに名義変更しましょう。
名義変更に必要な書類・費用
名義変更の際は以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 遺産分割協議書
- 固定資産税評価証明書
これらを準備して法務局へ提出します。
費用としては、登録免許税が固定資産税評価額の0.4%、司法書士に依頼する場合は報酬として数万円から十数万円が目安です。
実家処分の流れ③:遺品を整理・処分する
名義変更が完了したら、遺品の整理や処分をしましょう。
整理・処分する理由や処分できる専門業者について解説します。
- 遺品を整理・処分する理由
- 遺品処分を依頼できる専門業者
- 仏壇の引っ越しについて
遺品を整理・処分する理由
遺品を整理・処分する理由は、家の中を空にして売却をスムーズに進めるためです。
また、遺品を整理することで思い出を振り返り、必要なものと不要なものを明確にできます。
故人の思い入れのある遺品を処分することに抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、適切に取捨選択するためにも一度整理する必要があります。
遺品処分を依頼できる専門業者
遺品を整理した結果、多くの処分品が出てきた場合は専門業者へ依頼するのがおすすめです。
専門業者へ依頼することで遺品の処分や仕分け、清掃まで一括しておこなってくれます。また、遺品整理士を保有している業者であれば適切に遺品処分してくれるので安心して任せられます。
遺品の整理や処分でお困りの方は、遺品整理士認定協会に相談してみましょう。
仏壇の引っ越しについて
仏壇の引っ越しは、一般的な家具の移動とは異なり、特別な手順と配慮が求められます。
まず、移動前に「魂抜き」(閉眼供養)をおこない、仏壇からご本尊や位牌の魂を抜く儀式をします。これは多くの宗派で必要とされる重要な儀式です。
仏壇の移動方法としては、専門の仏壇店や引っ越し業者に依頼する方法、自分で運ぶ方法があります。専門業者に依頼する場合、費用は1万円から10万円程度が一般的です。
自分で運ぶ際は、仏壇の梱包や運搬に細心の注意を払いましょう。
移動後には「魂入れ」(開眼供養)をおこない、再び魂を入れる儀式をおこないます。これらの手順を踏むことで仏壇の引っ越しを適切に進められます。
実家処分の流れ④:土地の境界を確認する
次に土地の境界を確認しましょう。
土地の境界を確認しておくことで隣地との境界を把握できるため、売却時のトラブルを避けられます。
ここでは、境界の確認方法と境界が不明確だった際の対処法を解説します。
- 境界の確認方法
- 境界が不明確だった場合
境界の確認方法
境界は以下の方法で確認します。
- 確定測量図を確認する
- 境界標を確認する
まず、確定測量図があるか確認します。これは土地の正確な境界を示す図面で、法務局や市区町村の役所で保管されています。手元に無くても、過去に確定測量を実施して地積測量図として登記している場合は、法務局で取得できます。
次に、土地の四隅や境界線上に設置されている境界標(杭や石など)を探します。これらがしっかりと設置されていれば、境界��が明確である可能性が高いです。
境界が不明確だった場合
上記の方法で境界が特定できない場合は、土地家屋調査士などの専門家に依頼しましょう。専門家による測量がおこなわれるため、境界が明確になります。
依頼料は測量方法によって異なり、土地の現況を把握するだけの「現況測量」なら10万円前後、境界を確定するための「確定測量」なら40万円前後かかりますが、売却時には確定測量が求められるケースが多いです。
これらの費用はあくまで目安であり、土地や建物の面積、形状、隣接地の状況、地域差などによって変動します。
また、依頼する土地家屋調査士によっても報酬額が異なるため、複数の土地家屋調査士へ依頼して料金を比較するのがよいでしょう。
実家処分の流れ⑤:不動産会社の査定を受ける
境界を確認したら不動産会社の査定を受けましょう。
査定の種類や査定時のポイントを解説します。
- 査定には大きく2種類ある
- 複数社の査定を受けるのがおすすめ
査定には大きく2種類ある
まず、不動産会社がおこなう査定には「訪問査定」と「机上査定」の2種類があり、それぞれで特徴が異なります。
| 査定方法 | 特徴 |
| 訪問査定 | ・担当者が実際に訪問して査定 ・査定の精度が高い ・査定額提示まで1週間前後かかる |
| 机上査定 | ・不動産のエリアや利便性などの情報のみで査定 ・訪問査定より精度が低い ・2~3日で査定額がわかる |
具体的な査定額を知りたいのであれば訪問査定、相続直後に遺産分割の協議をするためにある程度の金額を把握したい場合は、机上査定で留めておいても良いでしょう。
なお、訪問査定・机上査定のいずれも無料で実施してもらうことができます。
複数社の査定を受けるのがおすすめ
査定は、できれば複数社の査定を受けましょう。
不動産会社によって査定額の精度や根拠が異なり、査定額が大きく異なる場合があるからです。
また、複数社の査定額を比較することで、おおよその相場感を把握できるため、提示された査定額が適切かどうかの判断もできるようになります。
なかには媒介契約を結ぶ目的で、極端に高い査定額を提示する不動産会社も存在するため、できれば3社程度へ依頼して査定額を比較するのがよいでしょう。
実家処分の流れ⑥:不動産会社と媒介契約を結ぶ
査定額に納得したら不動産会社と媒介契約を結びましょう。
ここでは、媒介契約の意味や種類について解説します。
- 媒介契約とは
- 媒介契約には3種類ある
媒介契約とは
媒介契約とは、売主が不動産会社に対して、物件の買主を探す仲介を正式に依頼する契約です。
不動産の買主探しは難しく、売り出したからといってすぐに見つかるとは限りません。その点、媒介契�約を結べば以下の売却活動を不動産会社が代わりにおこなってくれます。
- 物件の広告掲載
- 不動産ポータルサイトへの掲載
- チラシ配布
これらの手法を使って買主探しをしてくれるため、自分で探すよりも手間なく早く見つけられます。
また、買主探しだけでなく、売買契約書の作成や重要事項説明書の説明などもおこなってくれるため、トラブルなくスムーズに取引できるようになるのも媒介契約の魅力です。
媒介契約には3種類ある
媒介契約には3種類あり、それぞれで特徴が大きく異なります。
| 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
| 他社との契約 | × | × | 〇 |
| 買主の自己発見取引 | 〇 | × | 〇 |
| REINSへの登録義務 | 契約から7営業日以内 | 契約から5営業日以内 | 義務なし |
| 業務状況の報告義務 | 2週間に1回以上の報告 | 1週間に1回以上の報告 | 義務なし |
| 契約期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 制限なし |
専任媒介契約と専属専任媒介契約は、1社のみとしか契約を結べず、専属専任媒介契約は自分で探した買主を見つけた場合も、その不動産会社を通して取引しなければいけません。
一方で一般媒介契約は、何社とも契約を結んでもよく、自分での買主探しもできます。
ほかにも、REINSへの登録義務や業務報告義務も違いがあるため、売却目的や状況に応じて自分に合っていると思う契約を結びましょう。
実家処分の流れ⑦:買主と売買契約を結ぶ
買主が見つかったら売買契約を結びましょう。
売買契約時は、売主と買主の双方が売買契約書の確認をおこないます。不動産取引においてトラブルが起きやすい場面であるため、よく確認しておきましょう。
売買契約書は事前に確認しておく
売買契約書は事前に確認しておきましょう。
契約書には主に以下の内容が記載されています。
- 物件の詳細
- 価格
- 支払い方法
- 引渡し時期
これらを事前に確認することで後々のトラブルを防げます。
特に、手付金の額や支払い条件、契約解除の条件、違約金の設定などは注意が必要です。また、物件に関する特約事項や設備の引渡し条件も確認しておくと安心です。
売買契約書の内容は難しいため、不動産会社の担当者へ相談しながら理解するのがよいでしょう。
買主から値下げ交渉される可能性がある
買主から値下げ交渉をされる可能性があることを理��解しておきましょう。
値下げ交渉された際は、希望価格と妥協できる最低ラインを明確にしておくと、スムーズに交渉を進められます。
もし、値下げしたくないのであれば、物件の強みや付加価値などを強調し、価格が妥当であることを説明しましょう。また、交渉時は感情的にならず、冷静に対応することが大切です。
必要に応じて、不動産会社の担当者へ相談してみましょう。
実家処分の流れ⑧:決済・実家の引き渡し
売買契約が完了したら、いよいよ決済と実家の引き渡しです。
決済とは、売主と買主が売買代金の支払いと物件の引き渡しを同時に行う手続きです。
通常、司法書士が帯同して「抵当権抹消登記」や「所有権移転登記」などを行い、不動産を引き渡します。
決済当日は、売主と買主、不動産会社の担当者や司法書士が指定の金融機関などに集まって手続きを進めます。
手続きをスムーズに進めるためにも、権利証(登記識別情報)や印鑑証明書などの必要書類を準備しておきましょう。
実家処分の流れ⑨:翌年に確定申告する
実家売却により利益を得た場合は、翌年に確定申告しましょう。ここでは、確定申告が必要なケースや税金を抑える控除特例について解説します。
確定申告が必要なケース
不動産売却により、譲渡所得を得ている場合は確定申告が必要です。
譲渡所得とは、買った当時の価格より高く売れた際の所得を指します。例えば、被相続人が当初2,000万円で購入した家が3,000万円で売れた場合は黒字分の1,000万円が譲渡所得です。
ただし、実際には建物部分の減価償却を購入から差し引いたり、購入・売却時の経費を計上したりといった処理が必要なため、不動産会社や税理士へ相談することを推奨します。
また、譲渡所得が発生した場合は所得税や住民税などがかかりますが、売却した不動産の所有期間によって税率は以下のように異なります。
| 譲渡所得の種類 | 所有期間 | 税率 |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 所得税30%+住民税9%+復興特別所得税 |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 所得税15%+住民税5%+復興特別所得税 |
このように、所有期間(相続した家の場合は、被相続人の所有期間+相続人の所有期間)によって税率が約2倍も異なる点に注意しましょう。
実家処分時に利用できる控除特例
実家を売却した際は「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を受けられる場合があります。
この特例は、相続不動産を売却した際の譲渡所得から最大3,000万円控除できる制度です。譲渡所得が3,000万円以下であれば譲渡所得が発生しないため、非常に節税効果の大きい特例といえます。
ただし、利用するには以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
これらの条件を満たさなければならないため、必ず利用できるとは限りません。
相続不動産売却によって譲渡所得を得た際は、この特例を利用できないか税理士等の専門家に確認してみましょう。
▼関連記事

実家処分に関するよくある質問
実家処分に関するよくある質問をご紹介します。
解体費用はどれくらいかかるの?
一般的な木造住宅であれば1坪あたり3万〜5万円かかります。
例えば、30坪の木造住宅を解体する場合、約90万〜150万円が目安となります。
ただし、立地条件や周囲の状況、付帯工事の有�無などによって費用は変動します。複数の解体業者の見積もりを比較したうえで依頼先を決めましょう。
▼関連記事

実家を処分して後悔しない?
売却目的が明確になっていれば後悔しないでしょう。
実家を売ることは、親の住んでいた家を手放すことになるため、罪悪感や寂しさを感じる場合があります。
しかし、売却目的が明確になっていたり適切な手順を踏んで売却したりすれば後悔しないでしょう。また、家族と十分に話し合ったうえでの売却であれば全員が納得しているため、最小限の後悔に抑えられます。
実家を処分するかどうか悩んでいる方は後悔しないためにも、「本当に売ってもいいのか」といま一度よく考えたうえで判断しましょう。
▼関連記事

実家が売れない場合はどうすればいい?
実家が売れない場合は以下の対策をしてみましょう。
- 売却価格を見直す
- 「古家付き土地」として売り出す
- 更地にして売り出す
- 不動産会社へ買い取ってもらう
- 空き家バンクへ登録する
まずは売却価格を見直しましょう。相場に対して価格が高い場合は買い手が現れにくくなります。
また、「古家付き土地」や更地にして売り出すのも一つの選択肢です。古い家に需要がなくても土地自体には需要があるケースもあるため、「土地」として販売すれば買い手が現れるかもしれません。
それでも売れない場合は、不動産会社へ買い取ってもらいましょう。不動産買取は不動産会社へ直接売却する方法のため、買主を探す必要がありません。仲介での売却よりも手間なく早く売れるのでおすすめです。
ほかにも「空き家バンク」に登録すれば、空き家を探している買主へ物件をアピールできるため、簡単に買主が見つかる場合があります。
▼関連記事

まとめ
実家処分の流れや方法について解説しました。
実家を処分する際は、遺言書の確認や名義変更などの手続きを最初におこなう必要があります。
特に遺言書については知識や経験がない方がほとんどのため、困惑するかもしれません。スムーズに処分を進めるためにも、弁護士や司法書士などの専門家へ相談しましょう。
その後は遺品の整理や処分、不動産会社の査定や媒介契約の順に進んで売却活動を進めます。
実家処分は、一般的な不動産売却と比べて特殊な手順が入るため、初めての方には難しく感じるかもしれません。それでも、落ち着いて順序立てて売却を進めれば確実に売却できます。
「相続した実家を売りたい」「実家が売れなくて困ってる」とお悩みの方は、ぜひこの記事を参考に実家の売却を進めてみましょう。