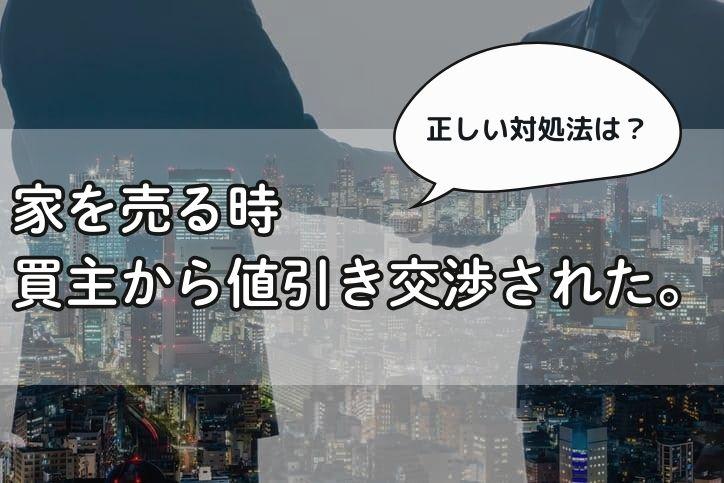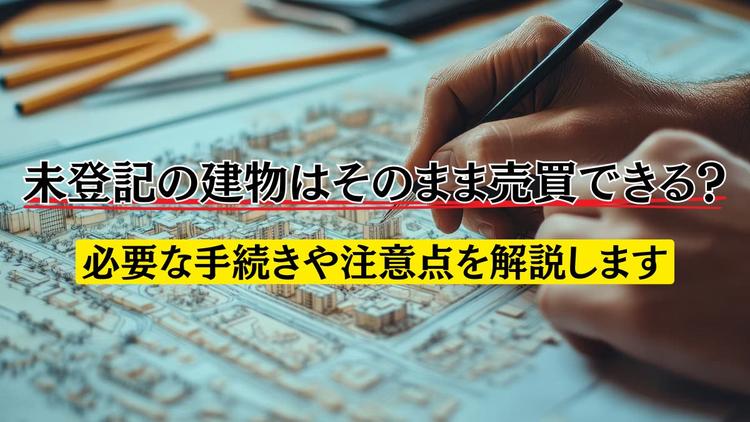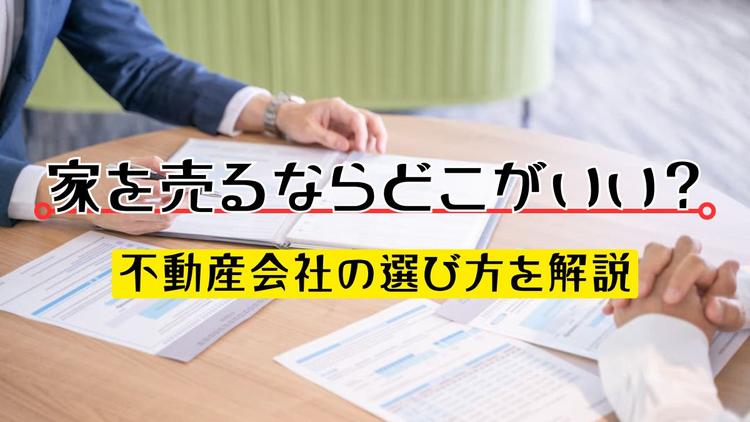自分の家を売りに出した際に、買主から値引き交渉をされるような状況って、本当にあるのでしょうか?
十分にあり得ます。希望価格で売却できるのがベストであることは言うまでもありませんが、現実はそう甘くはありません。
それでは、買主の値引き交渉にはどのように対処をすればいいのでしょうか。
あまり売り手側も強気の姿勢を見せすぎると、買い手も購買意欲が薄くなってしまうのでバランスの見極めが重要です。
なるほど。このさじ加減は難しそうですね。具体的にどのような判断基準で動けばいいのかの指標が欲しいです。
それでは早速、不動産の値引き交渉に対する正しい対処方法を解説していきましょう。
値引き交渉はどのようにして始まるのか
家の売却活動をした際に、どのようにして値引き交渉が持ち込まれるのでしょうか。
購入希望者が内覧を済ませると、やがて仲介の不動産会社を通じて「買付証明書」が届けられます。
買付証明書は購入の意志を示す書類で「購入申込書」と呼ぶこともあります。
この買付証明書には、希望購入価格が記入されておりますが、ほとんどのケースで売り出し価格(希望売却額)を下回る金額が記載されています。
売主は、これに対してどう対処するのかということを回答します。
値引きの限度額は最初から想定しておく
現在の中古住宅、中古マンション市場では、売り出し価格を値引きして契約するということが一般的になっています。
売り出し価格どおりに売却できることは、まずないと考えた方がいいでしょう。
80万円を上乗せする
そのため理想とする売却価格に80万円、90万円の端数をプラスして売り出すという手法が、頻繁に用いられます。
たとえば本音は3,300万円で売却できればいいと考えているとすれば、3,380万円で売りに出すのです。
これには2つの効果があります。
ひとつは一見安い印象を与えることができるということです。
もし購入希望者が3,300万円が購入限度額だと想定しているとすると、実際には予算オーバーしていても、3,380万円の物件は購入候補にリストアップして、3,400万円の物件は対象から外してしまうということもあり得るのです。
もう一つの効果は「値引きしろ(余地)」です。
ただし、この手法は現在では一般的に使用されているため、端数を値引きするのは当然だと捉えている買主だと、値引きの効果が思ったよりも発揮できないことがあります。
値引きを交渉する2つのタイプ
それではどうして購入希望者は、値引き交渉をしてくるのでしょうか。
大きく2つのタイプに分類できます。
「中古物件は値引きできて当たり前」と考えている人
ひとつは、現在の中古住宅市場に精通をしていて、値引きが当然だと考えているタイプの人です。
この場合、売値のままで購入をすると、あたかも大きな損失をしたかのような感覚に陥ってしまうので、値引きがない物件を購入することに対して強い抵抗感が生じるのです。
予算ギリギリのラインで申し込む人
もう一つのタイプは、住宅ローンと自己資金を合わせた限度額がシビアに決まっているタイプの人です。
この場合は、自分が捻出できる金額を上回る額を提示されると諦めざるを得なくなります。
もしこの購入限度額が決まっている人が唯一の購入希望者である場合は、慎重な交渉が必要になります。
強気で値引きを渋ると、相手が早々に諦めてしまう可能性があるからです。
こうした交渉タイプを見極めるには、ある程度の事情を把握している不動産会社の情報が頼りです。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
▼関連記事:家を高く売る方法をゲーム理論で考察|高値で売り出すことはそもそも間違いか?
値引き交渉はどのように妥協点を見出すのか
購入希望者が、売り出し価格3,380万円の物件に対して、3,000万円で購入したいと買付証明書を提示してきた際には、どのように対応すればいいでしょうか。
実に380万円の値引きになるのですから、容易に妥協できる話ではありません。
内見の申し込み・問い合わせの量を判断基準にする
まずひとつの判断材料にするのは、当該物件がどれだけ注目を集めているのかという点です。
しかし、売却活動を始めてから1カ月経過してこの希望者だけだとしたら、かなり真剣に考える必要があります。
不動産会社との仲介契約期間の3カ月が過ぎて、契約更新をするような時期になるまで売却できなかったら、3,000万円どころか、さらに下回る価格で売り出しを余儀なくされる事態も十分に想定できるからです。
これは仲介の実例ですが、あるマンションの売り相場は2,800万でした。
指値が入ることを考慮して3,000万で市場に出し、すぐに2,900万で購入したいという買主さんが現れましたが、市場に出したばかりだし、もう少し様子を見たいため100万の指値を受けたくないとのことでその購入者をお断りした結果、結局売却には1年半かかり最終的に2,500万で手放すこととなりました。1
上記は、売買に従事する不動産会社の方からお聞きした実例です。
相場の動向や、売却希望価格で買い手が現れるかどうかを正確に見極めることは難しいので、不動産会社の担当者とも話し合って、後悔しない判断ができると良いでしょう。
本筋から外れた交渉には妥協する必要はない
とはいえ、値引き交渉には、妥協してもよい事情と聞き入れる必要がない事情が存在します。
そのためには、まず交渉に入る前に、相手がどういった理由で値引きを求めているのかを知る必要があります。
たとえば、壁クロスが破れているから補修をする必要があるとか、収納庫の棚がないので取り付ける必要があるといった、相手方の事情による値引き交渉にはまったく応じる必要はありません。
補修費用を前提にした交渉を進めると、さらなる値引きを迫られる可能性が大いにあるという点にも注意しておきましょう。
購入希望者には購入の意志がある
購入希望者が3,000万円であれば購入するという意志を示しているということは、相手方には強い購入の意志があるということです。
それを前提に交渉を進めましょう。
ひとつは380万円の差額の真ん中をとって3,190万円で妥協するという方法があります。
��しかし当初の目論見であった3,300万円からもさらに110万円も値引きするのには、どうしても抵抗があるということであれば、せめて50万円は妥協して、3,250万円が最終価格の提示だとする方法もあります。
購入希望者からすれば、端数の80万円を引かせたばかりか、さらに50万円も値引きできたのですから大きな収穫といえるでしょう。
そもそも買付証明書に記載した金額どおりに売主が売却してくると考える人はまずいません。
そのために、だめで元々という考えに基づいて希望金額を提示しているのです。
住宅ローンの審査状況にも注意を
中古住宅は売り出しの期間が長くなればなるほど、売却価格は下がっていきます。
売却に際しては積極的に広告を配布していますから、周囲の人はいつ頃から売り出したのか承知しています。
長い間売れない物件は、何か問題のある物件ではないかと疑心暗鬼の目でみられたり、見下されたりすることで、どんどん価格が下がってしまいます。
そのため、購入希望者が現れた際には迅速に交渉を進める必要があります。
ところが契約を前提に交渉を進めていた相手が、最終的に住宅ローンの本審査を通過しなかったという事態になれば、売却活動は結局振り出しに戻ってしまいます。
それどころか1カ月前後の期間が無為に過ぎていま��すから、売却活動上も大きなダメージを受けることになるのです。
このため値引き交渉以前に、相手が交渉相手となり得る人物であるかを判断する必要があります。
さらに勤務先や年収などの情報を、可能な限り不動産会社から聞き出すことも重要なポイントになります。
▼関連記事:不動産の購入申し込みのキャンセル率は何%?契約が決まらなかった場合の対処法も解説します
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
長期間売れない家や訳あり物件は、値下げ交渉されやすい
一般的な仲介の不動産売却では、「最初は少し相場よりも高めの値段で売り出して、顧客の反応を見ながら値段を下げて調整する」という売り方をすることが多いです。
しかし、今はインターネット等で不動産業界人ではない一般の人も、相場の状況を簡単に調べることができる時代。
強気すぎる値段を設定するデメリット
あまりにも相場からかけ離れた値段で売り出すと、問い合わせすら来ず売れ残ってしまうことがあります。
そして、売れ残った不動産は最終的に値下げせざるを得ず、一度値下げした価格から「売れていないから」という理由でさらに値下げ交渉をされる可能性もありますので、売り出し価格と販売戦略には十分注意しましょう。
ワケあり物件を売り出すときの注意点
また、いわゆる「事故物件」のような心理的・物理的瑕疵のある物件は、どうしても普通の価格では売れにくく、割安な価格を設定しても、なお売れないことがあります。
事故があったことを隠して販売するのは契約不適合責任を問われることがありますので、そのようなことはせず、値下げの許容ラインを少し余裕を持って交渉に臨むのが良いでしょう。
例えば事故のあった家を解体して整備し、駐車場にするといった方法で金銭的に大きな損をせずに運用しているような例も存在します。
立地等の問題で全ての物件がそのように対応できるわけではありませんが、不動産会社と売却以外の選択肢を話し合うのも良いかもしれません。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
▼関連記事:訳あり・事故物件は売却できる?相場は何割引き?売る時の注意点や法律を解説
不動��産の値引き交渉に関するよくある質問(FAQ)
値引き交渉はいつ行われますか?
購入希望者が内覧を終えた後、不動産会社を通じて「買付証明書(購入申込書)」が届くことで始まります。この書類には希望購入価格が記載されており、多くの場合、売り出し価格よりも低い金額が提示されます。
値引き交渉に備えてどのように準備すれば良いですか?
売り出し価格を設定する際に、希望売却価格に余裕を持たせることが重要です。また、不動産会社と相談し、値引きの限度額を事前に決めておくと、スムーズに交渉が進みます。
値引き交渉に応じるべきケースはどんな時ですか?
購入希望者が予算上限に達している場合や、売却活動が長期化している場合は応じることを検討しても良いでしょう。
どのように値引き交渉の妥協点を見つければ良いですか?
提示された金額と売り出し価格の差額の中間で妥協する方法や、最終価格を明確に提示する方法があります。たとえば「これ以上は下げられません」と最低ラインを提示することで、購入希望者も納得しやすくなります。
値引き交渉を断る場合のリスクはありますか?
購入希望者が他の物件に流れるリスクがあります。特に購入希望者が限られる場合は、売却の機会を逃してしまう可能性があるため注意が必要です。
売却が長引いている場合、値引き以外にできることはありますか?
不動産会社と相談して販売戦略の見直しを検討したり、広告を強化することが有効です。また、物件の魅力を再評価し、写真や内覧の見せ方を工夫することで注目度を上げることもできます。
値引き交渉を進める際に確認すべき相手の事情は何ですか?
購入希望者の予算や購入動機、物件に対する要望などを不動産会社を通じて把握することが重要です。これにより、相手のニーズに応じた交渉がしやすくなります。
売り出し価格が高すぎる場合、どのような影響がありますか?
問い合わせや内覧の機会が減少し、売却期間が長引く可能性があります。また、長期間売れない物件は値下げを余儀なくされ、さらに値引き交渉をされるリスクが高まります。
値引き交渉を拒否しても良いケースはありますか?
市場に出してすぐで他にも内覧希望者が多い場合や、提示された価格が大幅に低い場合は拒否しても良いでしょう。不動産会社と状況をよく確認しながら判断することが重要です。
値引き後の価格で売却を進めるべきか迷ったときの判断基準は?
物件の市場価値や、売却期間の長期化によるリスクを総合的に考慮してください。また、不動産会社のアドバイスを受け、今後の相場の動向も確認した上で判断するのが賢明です。
心理的瑕疵のある物件は値引き交渉を受けやすいですか?
はい、心理的瑕疵がある場合は購入希望者が価格を大幅に下げる交渉をしてくることが一般的です。そのため、売却前に価格に余裕を持たせる、あるいは物件の状況に応じた代替案を検討することが重要です。
値引き交渉を受け入れた場合、どの�ように進めれば良いですか?
不動産会社を通じて相手に最終価格を伝え、書面で同意を得ることが重要です。また、交渉の過程や条件を記録し、トラブルを防ぐために明確な契約内容を提示しましょう。
まとめ
中古住宅の売買においては、値引き交渉はまず避けて通れません。
端数の値引きはもはや常態化しており、真の交渉はそれ以上の値引きを求めるところから始まります。
少しでも有利に交渉を進めるためには、常日頃から近隣の取引状況に目を光らせるなどして、より正確な実勢価格を把握しておくことが肝心です。
交渉は弱気過ぎれば相手の有利になり、強気過ぎれば相手に逃げられてしまいます。
物件の真の価値を知ることで、交渉のさじ加減も巧みに調整することができるのです。