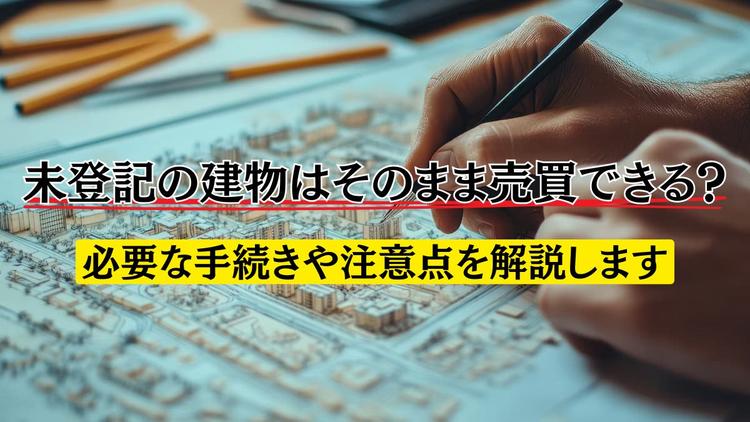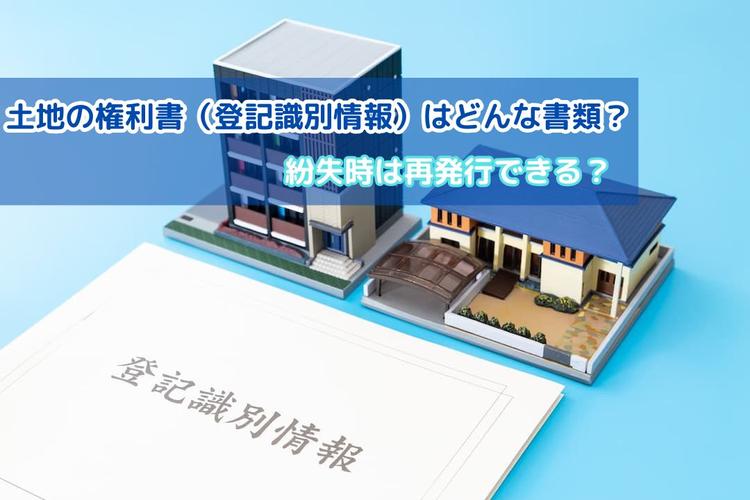建物の売買は、一般的に登記簿に記載された「所有者」から「買主」へ名義を変更する手続きを伴います。
しかし中には、建物がまだ登記されていない、いわゆる「未登記」の状態で取引されるケースもあります。
では、このような未登記建物の売買に問題はないのでしょうか?
この記事では、未登記建物の売買に関する実務上の手続きや注意点について、わかりやすく解説します。
未登記建物とは
不動産の「登記」とは、建物や土地の所在、所有者、面積などを、法務局の登記簿に記録することで、第三者に対してその権利を主張できるようにする制度です。
しかし実際には、登記がされていない、いわゆる「未登記建物」も一定数存在しています。
未登記建物の具体例
未登記建物とは、建物として完成していながらも、法務局に建物の所有権保存登記などがなされていない状態の建物を指します。
たとえば、次のようなケースが未登記建物に該当します。
- 建物を新築したが、所有権保存登記をしていない
- 増改築により建物の構造や床面積が変わったが、変更登記(表題部変更登記)をしていない
- 古い建物で、過去に登記されていなかった
- 相続や贈与により所有者が変わったが、名義変更の登記をしていない
こうした建物は、実態としては誰かが居住・利用していても、登記簿上は存在しない建物とみなされる状態にあるのです。
登記は法律上の義務がある
建物の登記は、単なる手続きではなく法律上の義務です。
まず、「表題登記」は新築から1カ月以内に行うことが不動産登記法第47条で義務づけられており、これを怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります(同法第164条)。
一方で、「所有権保存登記」は義務ではないものの、所有者であることを公的に示すためには事実上不可欠な手続きとされています。
また、建物の所有者や構造、用途、床面積などに変更が生じた場合も、一定期間内に変更登記を行う義務があります。これは、登記簿の正確性を保ち、不動産情報の社会的信頼性を支えるための制度です1。
さらに、2024年4月の法改正により、「相続登記」が義務化されました。
不動産を相続で取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なくこれを怠った場合には10万円以下の過料の対象となります。
この義務は未登記建物にも適用されるため、登記されていない建物を相続した場合は、まず表題登記を行ったうえで相続登記を進める必要があります。
つまり、未登記状態を放置することは、法律違反となる可能性があるだけでなく、後々の売買・相続・融資等において大きなトラブルの原因となり得るのです。
▼関連記事:不動産を相続せずに売却することはできない。相続登記から売却までの手順・注意点を確認
未登記建物でも売買は「可能」
結論から言えば、未登記の建物であっても売買すること自体は法律上可能です。
登記がされていないからといって、建物の所有権そのものが否定されるわけではありません。実際にその建物を所有しているという事実(いわゆる「事実上の所有」)があれば、売買契約は有効に成立します。
所有権の移転は「登記」とは別問題
民法では、不動産の売買契約は当事者の合意(契約)によって成立します。したがって、未登記の建物であっても、売買契約と引き渡しによって民法上の所有権は買主に移転します(民法第176条)。
ただし、その所有権を第三者に対して主張するには、登記が不可欠です(民法第177条)。
登記がされていないと、たとえば以下のような��トラブルが起こり得ます。
- 売主が実は真の所有者ではなかった(詐欺や二重譲渡のリスク)
- 所有権移転後に第三者が登記を先に済ませた場合、買主が所有権を主張できない
- 住宅ローンの審査が通らない
- 相続や贈与の際に複雑な手続きが必要になる
このように、未登記のまま売買はできてもリスクが大きいため、通常は売買契約に先立って登記を整備することが望ましいのです。
売買の前にすべきこと
未登記建物を売却する場合、まず次の手続きを進める必要があります。
- 建物の表題登記(建物としての存在を登記簿に登録)……原則として土地家屋調査士が調査・測量を行い、法務局に申請します。
- 所有権保存登記(誰がその建物を所有しているかを登記)……司法書士に依頼して行うのが一般的です。
これらの登記が完了すれば、正式な「登記済建物」として扱われ、売主から買主へ所有権移転登記を行うことが可能になるのです。
登記がないまま売買するとどうなる
やむを得ず未登記のまま売買する場合は、売買契約書に建物の現況や所有関係、登記予定の有無などを詳細に記載する必要があります。
状況によっては、買主が自ら登記手続きを行う旨を契約書に盛り込むこともあります。
このとき特に重要なのは、所有権保存登記は原則として売主の名義で行う必要があるため、買主が代行する場合でも売主の協力(委任状や印鑑証明書の取得など)が不可欠であるということです。
ただし、未登記物件は買主にとって非常に不安定な状態となるため、信��頼関係のある個人間取引を除き、不動産業者や金融機関を介した取引ではほとんど扱われないのが実情です。
未登記建物を売買する際の注意点
未登記の建物でも売買は可能ですが、通常の登記済み建物に比べて多くのリスクや手間が伴います。
ここでは、売主・買主それぞれの立場で特に注意すべきポイントを解説します。
所有権の証明が困難
未登記建物の場合、登記簿に所有者情報が存在しないため、売主が本当にその建物の所有者であるかを証明する手段が限られます。これにより、買主は以下のような不安に直面します。
- 売主が二重売買(他の第三者に同時に売却)をしているのではないか
- 真の所有者が別に存在するのではないか
所有権を証明するには、建築確認申請書や固定資産税の納税証明書、建築時の契約書などの客観的な書類を提示してもらうことが重要です。
住宅ローンの融資が受けられない可能性
未登記建物は、法務局の登記簿に建物の情報が記録されていないため、金融機関はその担保価値を正確に把握することができず、抵当権(金融機関が不動産を担保として設定する権利)を設定することができません。
これは、民法第369条において、抵当権は「不動産を目的とする担保物権」として、登記をもって効力を生じるものと定められているためです。さらに、不動産登記法の規定により、抵当権設定登記は登記簿上に存在する不動産に対してのみ可能とされています。
抵当権を設定�できない以上、金融機関は建物を担保として融資することができず、住宅ローンの審査においては原則として融資対象外とされます。
そのため、実質的に「現金取引」しか選択肢がない状態になるのです。
売買後の登記が煩雑
売買契約後に買主が登記を行おうとしても、前提となる表題登記や保存登記がまだ済んでいなければ、まず売主がこれらの登記を完了させる必要があります。
しかし、登記の時点で売主が亡くなっていたり、所在不明だったりする場合は、登記の前提条件が満たせず、事実上登記不能になるケースもありえます。
このようなトラブルを避けるため、売買契約を締結する前に登記を完了させておくことが理想的です。
契約書への明記が必須
未登記建物を売買する場合は、売買契約書の記載内容が非常に重要です。
具体的には、以下のような事項を契約書にしっかりと盛り込む必要があります。
- 建物の所在地・構造・規模などの現況情報
- 所有者であることの証明書類の提示状況
- 売主側が登記を行うか、買主側が代行するか
- 表題登記・保存登記・所有権移転登記の費用負担区分
- 登記手続きができなかった場合の解除条件(契約解除条項)や損害賠償の有無
これらを明記することで、後々のトラブルを防ぎ、紛争リスクを減らすことができるでしょう。
専門家の関与が不可欠
未登記建物の売買は、法的・実務的に複雑なリスクが絡むため、土地家屋調査士や司法書士、不動産業者など専門家の助言を受けながら進めることがトラブル回避には欠かせません。
とくに個人間取引の場合、「知人だから大丈夫」と安易に考えがちですが、後に登記や相続問題が発生して訴訟に発展するケースも少なくありません。
未登記建物を売る前にすべき手続き
未登記建物であっても売却は可能ですが、登記がされていない状態のまま売り出すことは、トラブルの原因になりやすく、買主にとっても大きな不安材料になります。
そのため、売却をスムーズかつ安全に進めるには、売る前に必要な登記手続きをきちんと済ませておくことが極めて重要です。
ここでは、未登記建物の売却前に売主が行うべき具体的な手続きを解説します。
建物表題登記を行う
最初に行うべきは、建物表題登記です。
これは、「この場所にこういう建物があります」という建物の客観的な情報を法務局に登録する手続きで、不動産登記法第47条に基づき、新築後1カ月以内に申請することが義務づけられています。
表題登記では、次の情報が登記簿に記録されます。
- 所在(地番)
- 家屋番号
- 構造(木造、鉄骨造など)
- 床面積
- 建築年月日
この登記は、土地家屋調査士に依頼するのが一般的で、現地調査と建物図面の作成を伴うため、完了までに2~4週間程度かかることがあります。
所有権保存登記を行う
建物表題登記が完了したら、次は所有権保存登記です。
これは、「誰がその建物の所有者なのか」を登記する手続きで、売却に必要不可欠な前提条件となります。
この手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、登記の際は次の書類を用意します。
- 表題登記完了証
- 建築確認済証や検査済証(新築時のもの)
- 所有権の証明となる資料(建築請負契約書、固定資産税課税通知書など)
- 売主の住民票や印鑑証明書
この段階で初めて、登記簿上に「○○○○所有」と明記され、買主への所有権移転登記が可能な状態になるのです。
建物の課税情報を確認しておく
未登記建物でも、多くの場合、自治体では固定資産税の課税対象になっており、課税台帳に建物の情報が登録されていることがあります。
そのため、建物が課税されているかどうかや、誰の名義で課税されているかを確認することは、所有者を証明するうえで有効です。
売却前に市区町村の資産税課などで「固定資産評価証明書」や「名寄帳(なよせちょう)」を取得しておくと、登記や契約手続きがスムーズに進みます。
「名寄帳」とは、1人の納税義務者が所有する不動産の一覧をまとめた帳票で、所有実態を確認する際に役立ちます。
契約条件に反映させる
未登記のまま売却しようとすると、登記未了により買主が融資を受けられなかったり、引渡し時にトラブルが起きる可能性があります。
そのため、売却前に登記を済ませることが重要です。
たとえば、「所有権保存登記を完了させた上で売買契約を結ぶ」 「登記手続きにかかる費用は売主が負担する」などの条件を事前に整理しておきましょう。
不動産業者や司法書士と連携しながら、スム��ーズに売却手続きが進められるよう準備を進めることが大切です。
売買後に登記を行う場合の手続き
未登記建物を売却するにあたっては、原則として売却前に登記を完了させておくことが理想的です。
しかし、実務上やむを得ず売買後に登記を行うケースもあります。この場合、登記の流れがやや複雑になるため、事前の契約内容や準備が重要になります。
ここでは、未登記建物を売却した後に登記を行う際の一般的な手続きの流れと、注意すべきポイントを整理して解説します。
表題登記と保存登記を先に完了させる必要がある
売買契約後に所有権移転登記を行うには、その前提として、建物の存在自体を登記簿に記載する「表題登記」と、売主名義で所有者情報を記載する「保存登記」を済ませておく必要があります。
したがって、売買後であっても、まずは次の手続きが求められます。
- 建物表題登記……土地家屋調査士に依頼する
- 所有権保存登記……司法書士に依頼する
ここまでの登記が完了して初めて、買主への「所有権移転登記」を行うことができます。
買主が登記の手続きを代行するケース
実務上よく見られるのが、売主が高齢・死亡・所在不明などの理由で登記手続きを行うことが困難な場合に、買主側が表題登記・保存登記を含めて代行するというケースです。
この場合、次のような点に注意が必要です。
- 売主から委任状・印鑑証明書等を取得しておく
- 保存登記は必ず売主名義で行い、その後移転登記を行う(買主名義で行ってしまうと法務局に申請が却下される)
- 費用の負担について契約書に明記しておく(買主負担とするか、価格に含めるか)
また、売買契約書や事前の覚書に、「買主が表題登記・保存登記を行い、その後に所有権移転登記を行う」と明記しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
所有権移転登記の手続き
表題登記および保存登記が完了した後は、通常の不動産取引と同様に、所有権移転登記を法務局に申請します。
この手続きは司法書士が代行するのが一般的で、必要書類は次のとおりです。
- 登記原因証明情報(売買契約書など)
- 所有権保存登記済証
- 売主・買主の住民票、印鑑証明書
- 固定資産評価証明書(登録免許税計算のため)
- 委任状(司法書士へ依頼する場合)
この手続きにより、建物の所有者が正式に買主へ移転し、登記簿にも反映されます。
売買後の登記には法的・実務的なリスクも
売買後に登記を行う場合、次のようなリスクに注意する必要があります。
- 売主が協力を拒否したり、失踪・死亡した場合、保存登記や移転登記が不可能になる
- 建物の所有権を第三者に譲渡される(二重譲渡)
- 買主は住宅ローンの審査を通過できない(担保評価が困難なため)
- 所有権を証明できない状態が長引くことで、資産価値や転売が制限される
そのため、売買契約締結時には、登記が確実に行えるよう、必要書類の取得や売主の同意を事前にしっかり確保しておくことが極めて重要です。
▼関連記事:増築未登記のリ�スクとは?売買時に売主・買主がチェックすべきポイントを解説します
まとめ
未登記の建物であっても、法律上は売買が可能です。しかし、登記がなされていないことで所有権の証明が困難となり、「住宅ローンの利用ができない」「売主が真の所有者でない可能性がある」など、買主・売主双方にとって多くのリスクが伴います。
特に不動産取引では「第三者に対して所有権を主張できるか」が重要であり、その意味でも登記は極めて大切な役割を果たします。安全かつ円滑な取引のためには、売買に先立って表題登記および所有権保存登記を完了させることが望ましく、個人間での取引であっても、土地家屋調査士や司法書士などの専門家と連携することが不可欠です。
未登記建物の売却を検討する際は、事前に法務局や市区町村で必要な資料を確認し、登記手続きを済ませた上で契約条件を慎重に整えることが、後のトラブル防止につながります。