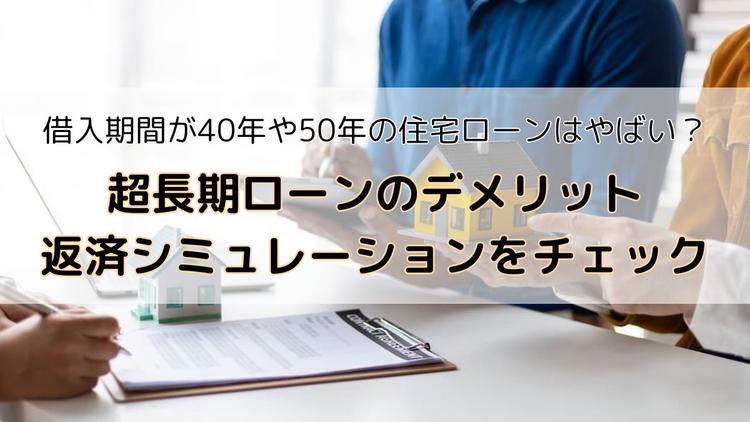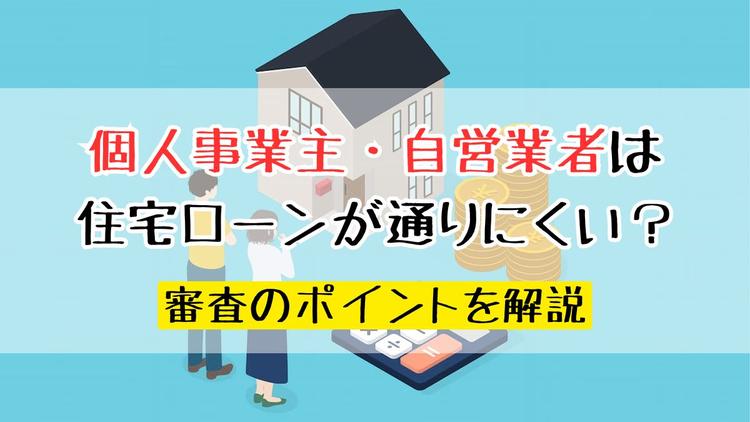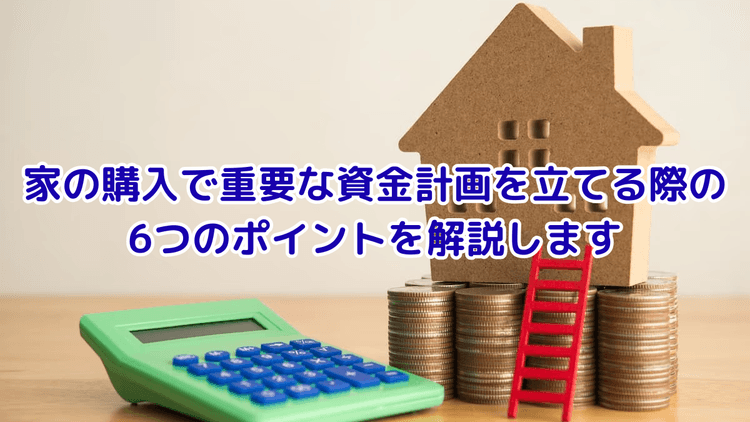不動産を売却すると、確定申告が必要なケースがあります。
確定申告が必要なケースで申告しないと、無申告加算税などのペナルティが科せられる恐れがあります。
ただし、不動産を売却すれば必ず確定申告が必要なわけではなく、必要ないケースもあるので必要かの判断基準を理解しておくことが大切です。
この記事では、不動産売却で確定申告が必要なケースや申告不要なケース、申告しない場合のリスクについて分かりやすく解説します。
不動産売却後は確定申告しないといけない?
不動産売却で利益が出ると、利益に対して所得税・住民税が課税されるため、確定申告が必要になります。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得と所得に応じた所得税を申告・納税する手続きです。
確定申告の対象となる所得は、給与所得だけでなく譲渡所得や不動産所得、事業所得など10種類に渡ります。
このうち、不動産を売却したときの利益は「譲渡所得」に区分されるため、譲渡所得が発生すれば確定申告して納税が必要です。
自営業者などは毎年確定申告していますが、会社員は年末調整で手続きが終了するので確定申告したことがない方もいるでしょう。
しかし、不動産売却で得る譲渡所得は給与所得とは区別して課税されるので、年末調整の対象になりません。
また、譲渡所得にかかる所得税・住民税は給与所得に関わらず、売却の利益の有無で課税が判断されるので譲渡所得が発生する場合は、確定申告する必要があります。
不動産売却後における譲渡所得税の計算方法
確定申告が必要になるのは譲渡所得が発生する場合ですが、譲渡所得とは単純に売却した額というわけではありません。
また、譲渡所得税は課税されると高額になりがちなので、事前に計算方法を理解しておくことが大切です。
ここでは、譲渡所得税の計算方法を押さえていきましょう。
譲渡所得税の計算方法は以下の2ステップです。
- 課税譲渡所得を求める
- 課税譲渡所得に税率を掛ける
それぞれ見ていきましょう。
課税譲渡所得を求める
課税譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
取得費とは購入にかかった費用、譲渡費用とは売却にかかった費用であり、それぞれ以下のような項目が該当します12。
| 取得費 | 譲渡費用 |
| 不動産の購入代金 仲介手数料 設備費や改良費 登録免許税 不動産取得税 印紙税 立退料 測量費 訴訟費用 取壊し費用 など | 仲介手数料 印紙税 立退料 取壊し費用や取り壊し時の建物の損失額 名義書換料 など |
なお、取得費からは建物の築年数に応じた減価償却費用を差し引く必要があります。
減価償却費の計算方法は以下のとおりです。
償却率は建物の構造ごとに定められており、たとえば木造なら0.031です。
また、経過年数は6か月以上の端数は1年、6か月未満の端数は切り捨てます。
仮に、木造を3,500万円で購入し15年3か月で売却した場合の減価償却費は以下のようになります。
この額を購入費から差し引くので、建物の取得費は3,500万円-1,464万円=2,036万円です。
この額に、土地の購入費とその他の取得経費を加えた額が取得費となり��ます。
つまり、取得費は以下のとおりです。
売却価格から取得費と譲渡費用を差し引き、さらに特別控除などを差し引いた額が課税譲渡所得です。
課税譲渡所得がプラスになる場合は、譲渡所得税が課税されるので税額の計算を行います。
▼関連記事:不動産売却時に経費(取得費・譲渡費用)になるもの
課税譲渡所得に税率を掛ける
譲渡所得税は以下の計算式で求めます。
譲渡所得税の税率は、所有期間に応じて以下の2種類に分かれます。
| 所有期間 | 所得税・復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 | |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
所有期間5年以下の短期譲渡所得は、5年超の長期譲渡所得の倍近い税率になるので、売却する際には所有期間も考慮するとよいでしょう。
ただし、所有期間を算出する基準日は売却した年の1月1日時点という点に注意が必要です。
実際の所有期間が5年超えている場合でも、売却した年の1月1日時点で5年以下であれば短期譲渡所得に区分されます。
要件を満たせば特別控除の適用を受けられる
前述の課税譲渡所得の計算のとおり、譲渡所得からは特別控除を差し引けます3。
たとえば、代表的な特別控除に「3,000万円特別控除」があります。
この控除では、譲渡所得から最高3,000万円を差し引けるので、譲渡所得が3,000万円以下であれば譲渡所得税が課税されません。
ただし、マイホームの売却であることや、売却までの期間などの適用要件を満たす必要があるので、検討する場合は国税庁のホームページで要件をチェックしましょう。
不動産売却後に申告不要なケース
不動産売却後に確定申告が不要なケースは、譲渡所得が0円やマイナスになる場合です。
たとえば、以下のケースで見てみましょう。
- 売却価格:3,000万円
- 取得費:3,500万円(減価償却後)
- 譲渡費用:200万円
- 特別控除適用なし
この場合、課税譲渡所得は3,000万円-(3,500万円+200万円)=-700万円となり、譲渡所得税は発生しないため確定申告は不要です。
ただ、取得費からは減価償却費を差し引く必要があり、一見するとマイナスのようでも減価償却費が加わると利益が出るケースもあるので注意しましょう。
反対に、以下のケースでは確定申告�が必要です。
- 譲渡所得税が発生する
- 特例を適用する(特例を適用すれば譲渡所得税が発生しないケースも含む)
計算の結果、譲渡所得税が発生する場合は確定申告で申告・納税が必要です。
また、各種特別控除などの特例を適用する場合も、確定申告しなければなりません。
特例を適用すれば課税されないケースでも、適用のための確定申告が必要になるので注意しましょう。
確定申告時期は、売却した年の翌年2月16日から3月15日(土日祝で異なる場合有)です。
売却してから時期が空きやすので、忘れることがないように早めに準備しましょう。
税金の計算方法や特例適用、申告に不安がある方は、税理士への相談をおすすめします。
不動産売却後の確定申告に関する注意点
不動産売却後の確定申告では、以下の2点に注意が必要です。
- 確定申告しないと税務署からお尋ねがくることがある
- 譲渡所得がマイナスでも確定申告することでお得になる?
それぞれ見ていきましょう。
確定申告しないと税務署からお尋ねがくることがある
税務署からの「お尋ね」とは、確定申告についての問い合わせです。
お尋ねと言っても税務署の職員が訪問してくるわけではなく、質問内容が記載された書類が郵送で送られてきます。
不動産取引は高額なお金が動き税金が発生しやすいので、税務署では登記簿の移動記録などから不動産取引を把握しています。
登記簿の記録などから税金が発生していそうな人はおおよそ推測が可能なため、確定申告していないとお尋ねがくる可能性があるのです。
ただ、譲渡所得が発生しなければ確定申告は不要であり、お尋ねが来たからと言って脱税しているわけではありません。
質問内容に合わせて事実を回答すれば問題ないでしょう。
お尋ねへの回答は法的義務がないため放置しても問題ありませんが、放置すると余計怪しまれる恐れがあるので早めに回答することをおすすめします。
お尋ねが来るのが嫌という場合は、譲渡所得が発生しなくても確定申告しておくとよいでしょう。
譲渡所得がマイナスでも確定申告することでお得になる?
譲渡所得がマイナスの場合は確定申告は不要ですが、確定申告によりマイナスで適用できる特例を活用すれば税負担の軽減が見込めます。
譲渡所得がマイナスのときに適用できる特例には以下の2つがあります45。
- 居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、住み替えによる売却で損失が出ている場合に適用できる特例です。
一方、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、住宅ローン残債のある家を売却し、その売却額が残債を下回り損失が出た場合に適用できます。
どちらの特例も、損失額を給与所得などの他の所得と損益通算できるため、所得税の節税が可能です。
さらに、その年で控除しきれない損失分は、翌年以降3年間にわたって繰り越せるため、長期に渡る節税が見込めま�す。
ただし、どちらの特例も適用するには一定の要件を満たしたうえで確定申告が必要です。
適用できればトータルの税負担を軽減できるので、マイナスが出た場合でも要件をチェックして、確定申告を検討するとよいでしょう。
譲渡所得があるのに確定申告しなかった場合のペナルティ
確定申告が必要なケースで申告を怠ると、以下のようなペナルティが科せられる恐れがあります。
- 無申告加算税が課せられる
- 延滞税が課せられる
それぞれ見ていきましょう。
無申告加算税が課される
無申告加算税とは、申告期間内に確定申告しなかった場合に、本来の税額に加えて課さられる税金です。
無申告加算税では、本来の税額に対して以下の割合の税金が加算されます6。
| 税金の額 | 割合 |
| 50万円までの部分 | 15% |
| 50万円超300万円までの部分 | 20% |
| 300万円超の部分 | 30% |
なお、税務署から通知される前に自主的に期限後申告した場合は、割合が軽減されます。
また、以下のようなケースは無申告加算税の対象外��です。
- 申告期限より1か月以内に自主的に期限後申請を行った
- 無申告に正当な理由がある
- 法定納税期限に納税している
- 期限後申請をした日から5年以内に無申告加算税または重加算税を課せられていない
期限を超えてしまった場合でもすぐにペナルティとはならないので、できるだけ早い段階で確定申告しましょう。
延滞税が課される
期限内に納税できていない場合、納税期限の翌日から納付した日までの日数に応じた延滞税が加算されます。
延滞税の計算方法は以下のとおりです7。
延滞税の割合は、原則として延滞期間が2ヵ月までの期間は「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、2カ月経過後の日数については「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。
延滞期間が長くなるほど延滞税の負担も大きくなるので、注意しましょう。
なお、「特例基準割合」は、その年の前年における日本銀行の基準割引率および基準貸付利率の平均値のことで、2024年は1.4%でした。
これは毎年国税庁によって定められ、公表されています。
不動産売却で確定申告しないことに関するよくある質問
最後に、不動産売却で確定申告しないことに関するよくある質問をみていきましょう。
不動産売却後に税務署のお尋ねがくる時期は?
お尋ねが来る時期に明確な基準はなく、税務署や売却状況などによって異なります。
一般的には確定申告時期終了後に届くケースが多いですが、売却後数カ月で届くケースもあれば1年後に届くケースもあるので注意しましょう。
また、確定申告しないとお尋ねが必ず来るわけではなく、税務署が税金は発生していないと判断すれば届くことはありません。
譲渡所得が50万円以下の場合は申告不要になる?
通常、譲渡所得は最高50万円の特別控除を差し引けますが、この控除は不動産売却の譲渡所得は対象外です。
不動産売却の譲渡所得が50万円以下であっても、0円以上であれば譲渡所得が発生しているので確定申告が必要になります。
まとめ
不動産を売却し譲渡所得が発生すると、確定申告して納税が必要です。
譲渡所得が発生しているのに確定申告を怠ると、無申告加算税などのペナルティが科せられる恐れがあるので適切な時期にきちんと確定申告を行いましょう。
また、特例を適用する場合も確定申告が必要なので注意が必要です。
譲渡所得税の計算は複雑になりがちで、確定申告が必要か判断に迷うケースもあります。
確定申告について不安がある場合は、不動産会社や税理士などに相談して適切に対応できるようにしましょう。