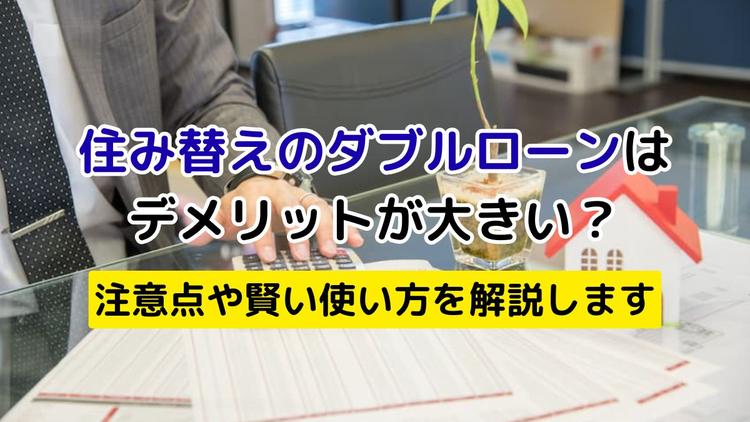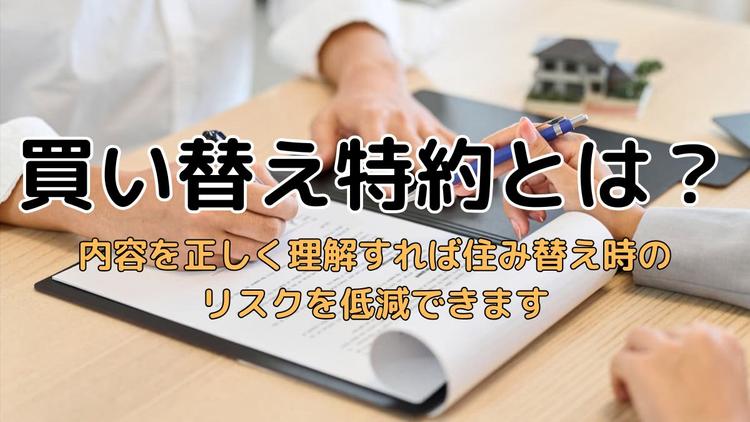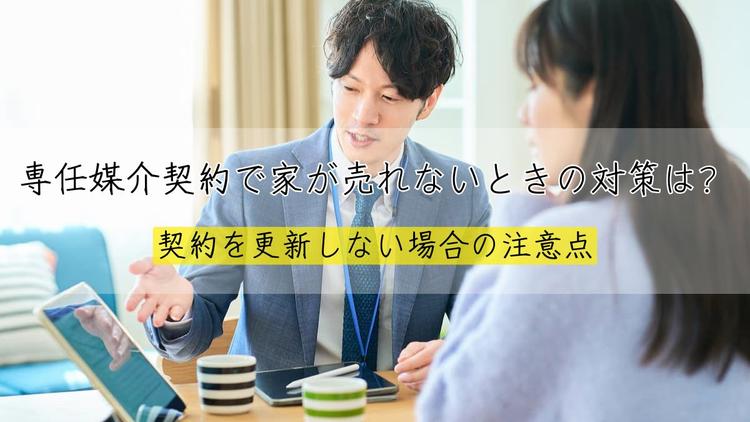親が高齢になり、介護施設やサ高住への入居を選択することがあります。
このときに頭を悩ませるのが、空き家になる親の家の取り扱いではないでしょうか。
老朽化や不審者の侵入といった様々なリスクを考え、空き家のままで放置するのは避けたいと考える人は少なくありません。
その対策として有効な方法のひとつが家の売却です。
介護施設に入った親の家を売却、あるいは賃貸にするにはどうすればいいのか、その手続きの流れを解説します。
介護施設に入った親の家が空き家のままだとどうなる
親が老人ホームなどの介護施設に入居した後、その家を空き家のままで放置していると、次のような問題が発生する可能性があります。
- 老朽化を防ぐために維持費をかける必要がある
- 毎年固定資産税を納税する必要がある。
- 定期的に家の様子を確認する必要がある
- 親が認知症になると売却手続きが複雑になる
その他にも、雑草が繁殖する、野生動物のすみかになる、不審者が侵入するといった可能性があり、心配の種は尽きません。こうした事態を回避するには、早い段階で家を売却するという方法が有効です。
一方で、家の所有権を親の名義で維持したいのであれば、賃貸に出すという方法が考えられます。
介護施設に入った親の家は売却するとどうなるのか。あるいは賃貸という選択肢も検討すべきなのか。それぞれのメリットとデメリットを押えておきましょう。
介護施設に入った親の家を売却するメリット
介護施設に入った親の家が空き家になる場合、早い段階で売却するのは有力な活用法です。売却すると、どのようなメリットがあるのか紹介していきましょう。
介護費用や医療費を捻出できる
高級とされる介護施設には高額な費用がかかります。また高齢であることから、病気になるリスクも想定しておく必要があります。
こうした費用も、自宅を売却することで資金が確保で��きるので、安心して老後を過ごすことができます。
固定資産税や維持管理費用が不要になる
家を空き家のまま放置しておくと、維持管理や定期的な点検のために費用がかかります。また、毎年固定資産税を納めなければなりません。
家を売却することにより、これらの費用は不要になります。
相続時の遺産分割が容易になる
相続人が複数いる場合、不動産の価値をめぐる解釈でトラブルになることがあります。
しかし事前に空き家を売却しておけば、相続財産が現金化されて資産価値は明瞭になるので、遺産分割をスムーズに進めることができます。
譲渡所得税で3,000万円の特別控除の特例が適用できる
マイホームを売却したときは、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
ただし、マイホームに住まなくなれば、3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しないと、この特例は使えなくなってしまいます。
不動産会社の査定などを確認して売却益(譲渡所得)の発生が見込まれる場合は、介護施設へ入居するタイミングで売却を検討しましょう。
信頼できる不動産会社をご紹介
イエウリ の不動産査定はこちら
自宅を売却するデメリット
メリットがある一方で、空き家になった家を売却することによるデメリットもあります。
なかなか売れないことがある
空き家を�売りに出しても、確実に売れるとはかぎりません。
交通の便が悪かったり、家が古かったりすることで、まったく買主が現れないこともあるので注意が必要です。
片付けが必要なことがある
空き家に廃棄物が散乱している状態では、売却することはできません。
廃棄物があまりに大量だと、個人の力では処理できないので、廃棄物処理専門の会社に依頼して家を片付ける必要が出てきます。
業者に頼むとなると、その分の出費も発生することを頭に入れておきましょう。
▼関連記事:家財道具が残った家の売却
賃貸に出したときのメリット
親が介護施設に入居したことにより、空き家になった家を売却することが難しい場合や、将来の値上がりを期待する場合には、賃貸に出すという選択肢もあります。
空き家を賃貸にした場合のメリットを紹介していきましょう。
家賃収入が得られる
空き家を賃貸に出すことで定期的に家賃収入を得ることができます。
また、その家賃収入を介護費用や医療費に充てることも可能です。
自宅を所有し続けることができる
売却してしまうと所有権が他の人に移ってしまいますが、賃貸だと不動産の所有権を維持できます。
周辺の土地が高騰しているような場所柄であれば、将来家を売却したときに高額の収入を得ることができます。
自宅を賃貸に出すデメリット
一方で、賃貸に出すことでのデメリットもあります。
適切なメンテナンスが必要
空き家を人に貸すとなると、住んでいた状態そのままで貸すのは難しいケースが多いです。
賃貸物件として維持していくためには、定期的にリフォームをするなどして、適切なメンテナンスが必要になります。
固定資産税を納める必要がある
売却しない限り所有権は維持したままなので、毎年の固定資産税を納める必要があります。
固定資産税は所有者が納税義務者となり、自分が住んでいない家でも納税しなければならないことには注意が必要です。
借家人が不在になる可能性がある
賃貸として活用している場合、常に借家人がいる状態であれば、家賃収入が定期的に入ってきます。
しかし、借家人が退去して次の入居者が決まらないと、当然その間の家賃収入は止まります。
家賃収入をあてにして資金計画を建てていた場合は見直しが必要になります。
3,000万円の特別控除の特例が適用できない
3,000万円の特別控除は、所有者が住んでいる家を売却した場合の特例です。
所有者が家を出て、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日を過ぎてしまうと、特例は適用されません。
そのため、貸家にしている間に3年が経過してからの売却で譲渡所得が発生すると、3,000万円の特別控除は適用できないのです。
賃貸契約の解除が難しい
普通借家契約では、貸主の意思だけで自由に解約することが困難です。
賃貸を止める時期があらかじめ決まっているのなら、賃貸契約の期間を限定できる定期借家契約が適しています。ただし、定めた期間を家主の都合で短縮することはできません。
介護施設に入った親の家を売却する流れ
家は所有者本人しか売ることはできません。実の親の自宅であっても、親名義の家を子が勝手に売却することはできないのです。
親から売却を頼まれた場合でも、家を売却するための準備を整えなければなりません。
親の代わりに子が家を売却する場合、親が意思を表示できるか、あるいは認知症などにより意思が表示できないかによって売却方法が異なります。
それぞれの方法について、どのように進めればいいのか流れを解説していきましょう。
親が意思表示できるのなら代理人になる
親名義の家を子が売却するには、親の代理人として手続きを行う方法があります。
民法では、「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる(第99条)」と定められています。
そのため、子が親の代理人となった場合、親に家を売却する意思があれば、子が代わりに家を売却することができるのです。
ただし、法律上、契約は親と買主の間で直接結ばれたものであり、売却によって得られた金銭は親のものになります。
委任状を作成する
子が代理人となって親の家を売却するには、親から代理権を委任されていることを第三者に証明する委任状が必要になります。
親子の関係を証明しただけでは代理人であることは認められず、委任状がなければ取引を行うことができません。
たとえ親から頼まれたことが真実だとしても、第三者から見れば疑いが払拭できないため、特に価格が高額に��なる家の売却では、委任状のない代理人とは誰も取引をしないのです。
委任状の記載内容
委任状の作成では、代理権を付与する「委任の範囲」をできるだけ詳細に書き込むことが重要です。
子が代理人になる場合、親への遠慮が少ないこともあり「家の売却を一任する」といった大まかな内容で、親が望まない金額で売却してしまう可能性があります。
委任状は一般的に、不動産会社が用意してくれます。具体的には、次のような項目が記載されていますので、これらについてあらかじめ親子で話し合って記載をします。
- 売却物件の情報
- 売却価格や手付金の額
- 振込先
- 代理人の金額交渉権の有無や交渉金額の幅
- 代理人と委任する人の情報(住所や氏名など)
- 委任状の有効期限
委任状は実印で押印して、印鑑証明書を添付します。
本人の意思確認
親の実印が押された委任状があっても、不動産の取引では本人確認と売却の意思確認は必ず行われます。
不動産会社や司法書士が委任者である親と直接面談して、本人確認を行います。
その際、家の売却の意思についても直接親本人から確認します。
特に親子の場合は、実印の保管場所を把握していることが多く、悪意があれば簡単に委任状の偽造が可能なため、本人(親)と面談をしないまま取引を開始することはありません。
仮に病気などの理由で本人が打ち合わせ場所に出向けない場合は、関係者が介護施設や医療施設に足を運んで売買契約を行うこともあります。
売却が決まれば、子が親の代理人として引渡しを行いま�す。
▼関連記事:委任を受けて売却するための流れや、必要な手続き
親が認知症であれば「成年後見制度」を活用
子が親の代理人になって家を売却しようとしても、親が認知症や病気のために、売却の意思表示ができないこともあります。
その場合、「成年後見制度」を活用するのが一般的です。成年後見制度とは、認知症や障がいなどによって判断能力が不十分な人を、法的に保護する制度のことです。
判断能力が衰えてしまうと、悪意のある人にだまされて不利な契約を結んでしまう可能性があります。
そのような場合に備えて、本人の意思を尊重しながら後見人がサポートすることによって、不利益を被らないようにすることを目的としています。
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」がありますが、法定後見制度では弁護士などの専門家が後見人になることが多く、子が代理人として不動産を売却することは実質的に難しい場合が多いです。
▼関連記事:認知症になった親や親族の家を売却する流れ
介護施設に入った親の家を賃貸に出す流れ
親の家を賃貸に出す場合の流れについても触れておきましょう。
住宅ローンの残債を確認する
住宅ローンは、自分が住むために借りる融資のことです。そのため賃貸に出すことは規約に反し、判明すれば全額返済が求められます。
つまり、賃貸に出すには住宅ローンを完済していることが前提となるのです。
委任状を作成する
子が代理人となって親の家を賃貸に出すためには、委任状が必要です。
そのため、親から代理権を委任されていることを第三者に証明する委任状を作成します。
不動産会社へ依頼する
空き家を賃貸物件にするには、不動産会社へ依頼する方法が一般的です。
依頼する不動産会社を探し、信頼できる相手だと判断したら、媒介契約を結びます。
媒介契約とは、不動産会社に賃貸に関する仲介を依頼するための契約です。この契約により、入居者募集や契約書類の作成など、所有者と入居者のあいだで結ぶ賃貸契約をスムーズに進めることができます。
入居者が見つかれば、賃貸契約の締結をします。
まとめ
空き家のままで放置しておくと、老朽化や不審者の侵入など、様々なリスクが発生します。その対策として有効なのが家の売却です。
家を売却することで、介護施設や病院に支払う費用の心配が解消されます。また固定資産税や維持費の心配からも解放されることになります。
家の所有権を維持していたいのであれば、賃貸に出すという方法もあるので、どの方法が家族にとって良い選択か、不動産会社などとも相談して決定するのが良いでしょう。
▼関連記事:実家が空き家になったらやるべきこと