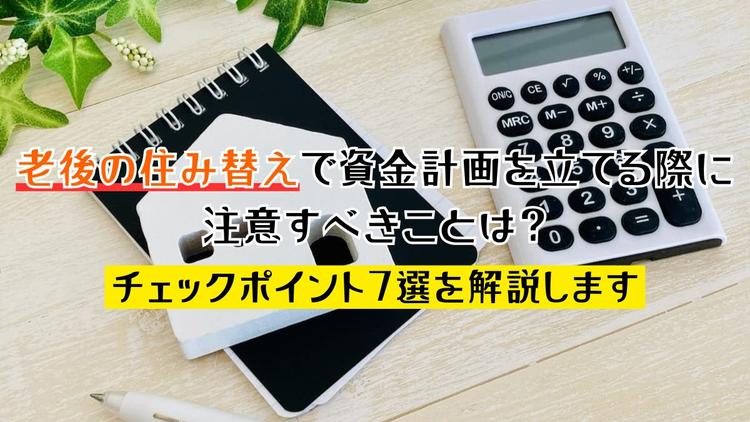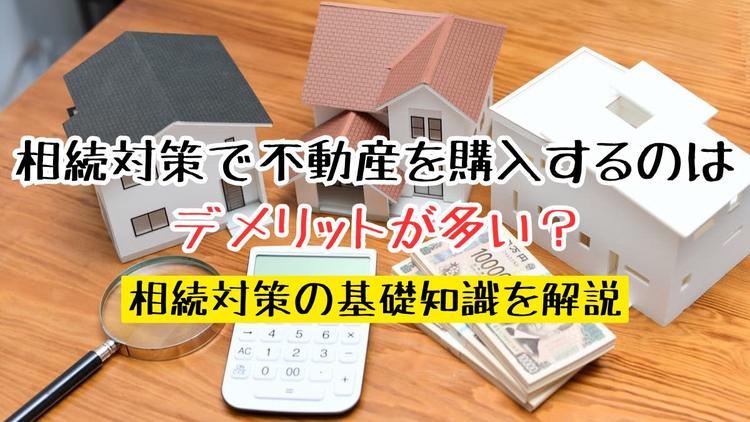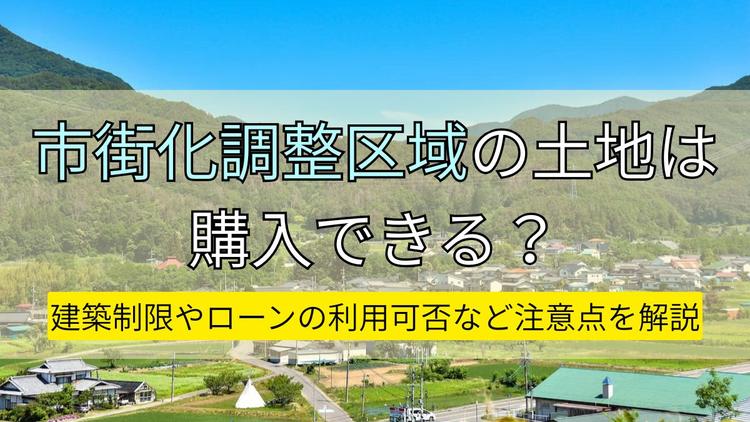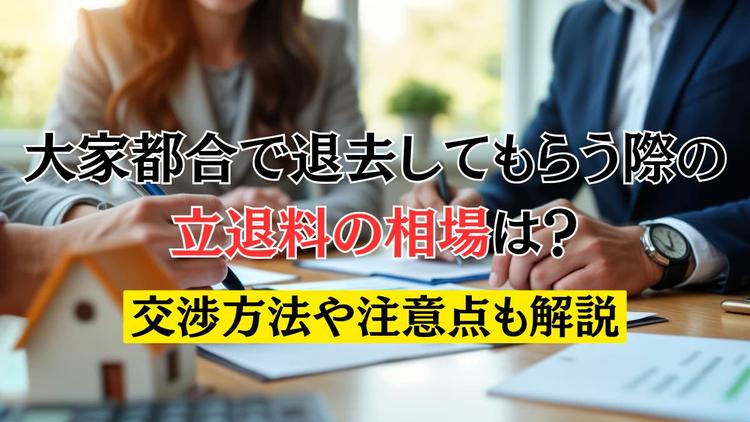住宅ローンの借入をする際には、必ず諸費用が伴います。基本的に諸費用は、住宅ローンが実行される前に現金で支払うことになります。諸費用がどれくらいの金額になるのかを前もって押さえておかないと、資金不足で住宅ローンが借りられない事態にもなりかねません。
この記事では、住宅ローンの利用でかかる諸費用について解説していきます。
住宅ローンの利用でかかる諸費用とは
住宅ローンを借りるときは、手数料や保証料などの支出が伴います。住宅ローンを借りる際に必要となる諸費用の種類と相場についていてみていきましょう。
融資手数料
融資手数料とは、住宅ローンを借入れする際の融資に伴う事務手続きに対する手数料のことです。融資事務手数料や事務取扱手数料と呼ぶ金融機関もあります。
多くの金融機関では、融資手数料の支払い方に「定率型」と「定額型」の2種類を用意しています。
定率型
定率型は、借入金額に対する一定の割合の額を手数料として支払います。そのため、借入金額が多いほど手数料は高くなります。たとえば、多くのネット銀行では消費税込みで融資額の2.2%としており、3000万円を借りると手数料は66万円になります。
定額型
定額型は、借入金額に関係なく、予め決められた手数料を支払います。概ね3〜6万円としているのが一般的です。多くの市中銀行(メガバンク・信金など)はこの方法を採用しています。
そのため、市中銀行の方が手数料が安く思えますが、ネットバンクは次に紹介する保証料をゼロとしているため、「事務手数料+保証料」で考えると大きな差は生じません。
保証料
保証料とは、保証会社に保証人になってもらうための費用です。住宅ローンの返済が不能になれば、金融機関は保証会社から保証を受けることができます。しかし、債務者にとっては、債権者が金融機関から保証会社に代わるだけで、返済義務がなくなるわけではありません。
つまり、ここでいう保証とは、金融機関への保険であって、住宅ローン利用者を救済するものではないのです。
保証料は借入時に一括で支払う「一括前払い型(外枠方式)」と、返済中の金利に上乗せする「金利上乗せ型(内枠方式)」があります。
一括前払い型(外枠方式)
一括前払い型は、借入時に一括して所定の保証料を支払います。返済期間が35年の場合で、融資額 1,000万円当たり約20万円かかるのが一般的です。たとえば 3,000万円借りた場合は、60万円が必要になります。
保証料を契約時に一括で支払うので、金利上乗せ型よりも住宅ローンの毎月の返済金額を抑えることができます。また長期で返済した場合、最終的な総支払額は金利上乗せ型よりも少なくてすみます。
金利上乗せ型(内枠方式)
金利上乗せ型は、保証料を一括で支払う代わりに、金利に上乗せして支払う方法です。保証料一括前払い型金利に年0.2%を加えた金利となります。
そのため、一括前払い型に比べて借入時に準備する諸費用を抑えることができますが、長期で返済した場合、最終的な総支払額は一括前払い型よりも多くなります。
市中銀行の中には、「融資手数料型」「保証料一括払い型」「保証料金利上乗せ型」等の選択肢を設けており、融資手数料、保証料のどちらかを一括で支払うか、あるいは、その両方を一時払いではなく金利の上乗せをするという選択ができるようにしているものもあります。
諸費用の中で、保証料の占める割合は高いですが、保証料が安い場合融資手数料が高くなっているため、住宅ローンを借りる銀行を諸費用で判断する場合は、保証料だけでなく「融資手数料+保証料」の金額で判断した方がいいでしょう。
また、一括払い金を節約したいのであれば、金利に含ませる方法もありますが、最終的な支払額は一括払い金よりも高くなる可能性があることを念頭に置いて判断してください。
印紙税
住宅ローンの契約書は課税文書なので、ひとつの契約書ごとに契約の金額に応じた収入印紙を貼る形で納税をします。
印紙税額は契約書に記載されている契約金額に応じて決まります。次のような額の住宅ローン契約をした場合、それぞれ右の印紙税額になります。
- 500万円超1,000万円以下……10,000円
- 1,000万円超5,000万円以下……20,000円
- 5,000万円超1億円以下……60,000円
たとえば、3,000万円の住宅ローンを利用すると、印紙代は20,000円になります。もし夫婦で2,000万円と1,000万円のペアローンにした場合は、契約書が2通になるので、印紙代はそれぞれ20,000円となり、合計40,000円になります。
印紙代だけに着目すると、単独の住宅ローンの方が安くつくのは当然だと思いがち�ですが、借り入れが5,000万円を超えると、印紙税額がいっきに上がるので、少し事情が変わります。
単独で6,000万円を借りると、印紙代は60,000円ですが、ペアローンで4,000万円と2,000万円ずつだと、印紙代はそれぞれ20,000円ずつで、合計40,000円になります。
つまり借りる金額によっては、2通の契約でありながら、ペアローンの方が印紙代の節約になることがあるのです(ただし、事務手数料や抵当権設定の登録免許税などローン契約ごとに発生する費用部分は2倍になるため、必ずしも諸費用の節約になるとは言えない)。
なお、印紙税は課税文書を対象にしたものであるため、電子契約だと印紙税の対象になりません。まだ電子契約を採用している金融機関は少数ですが、ネット銀行の中には、インターネットによる手続きで電子契約に対応しているところもあります。
▼関連記事:ペアローンの注意点
火災保険料
ほとんどの金融機関は、火災によって担保が失われるおそれがあるため、住宅ローンの利用者に対して火災保険への加入を求めています。
さらに、一部の金融機関では、火災保険の保険金請求権に質権を設定することを条件としていることがあります。質権を設定することで、火災によって住宅が損害を受けたとき、金融機関は、住宅ローンの利用者に代わって損害保険会社に対して保険金を請求できます。
火災保険の加入期間は、住宅ローンの返済期間に相当する期間となります。ただし、火災保険の保険期間は最長でも10年間とされており、10年を過ぎるごとに更新が必要となります。住宅ローンの�返済期間が10年を超える場合は、保険切れの期間が生じないよう、火災保険に自動継続特約を盛り込むことになります。
火災保険料は保証内容によって金額は異なりますが、15万~40万円程度のものが一般的です。
さらに近年は、地震による被害に関心が集まっています。火災保険だけでは、自然災害による火災や地震による倒壊に対応していないため、火災保険に加えて地震保険も加入しておくと安心です。
地震保険は単独での加入ができないため、火災保険とセットで加入することになります。
地震保険の保険金額は、火災保険の建物の保険金額の30~50%の範囲で、最大5,000万円まで、家財については1,000万円までです。地震保険料は、地域や構造によって異なりますが、保険金額 1,000万円当たり、1万~3万円程度です。
団体信用生命保険料
団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンを利用する人が、返済の途中で死亡したり高度障害を負ったりしてローンの返済が困難になったとき、残りの債務を返済する仕組みの保険です。
住宅ローンの残債をすべて返済することになるので、残された家族はそのまま住宅に住み続けることができます。
一般的な住宅ローンを利用する際は基本的に加入が条件となります。フラット35では、加入は任意です。
団信に加入しない場合は、金利から0.2%が差し引かれますが、万が一の事態を考えると、加入を前提にしておいた方が安心です。
団信の保険料には金利上乗せ方式と保険料外枠方式があります。
金利上乗せ方式は、返済する住宅ローンに0.1~0.4%程度の金利を上乗せする形で保険料を支払います。
返済金利に含まれるので、無料と思われがちですが事実上有料です。一般的な住宅ローンは、この方式が主流です。
保険料外枠方式は、住宅ローンの返済とは別に、一般の生命保険のように保険料を支払う方式です。住宅ローンとは分離されているので、中途解約することができます。
▼関連記事:団信なしでフラット35を利用しても大丈夫?団信なしのメリット・デメリットを解説
抵当権設定費用
金融機関は利用者がローンを返済できなくなった事態に備えて、その不動産に抵当権を設定します。
実際にローン返済不能になれば、金融機関は抵当権を設定した不動産を競売にかけ、売却した代金をローンの返済に充当することになります。
不動産に抵当権を設定する際には、登録免許税の納付と司法書士への報酬が必要となります。
登録免許税額とは、抵当権を設定登記をする場合にかかる税金です。登記申請書に印紙を貼り付ける形で納税します。
登録免許税額は次の計算式で求めます。
たとえば、住宅ローンの借入額が3,000万円であれば、登録免許税額は「3,000万円×0.4%」により、12万円となります。
抵当権設定登記の手続きは、本人申請も可能ですが、司法書士へ依頼した方が確実で安心です。多くは、不動産会社や金融機関が紹介する司法書士へ依頼します。
司法書士に抵当権設定登記の手続きを依頼した場合、5万円~10万円程度の報酬を支払います。
適合証明書交付手数料(フラット35を利用する場合)
適合証明書交付手数料は、フラット35を利用する場合のみ必要な費用です。一般的な住宅ローンでは必要ありません。
フラット35は、住宅金融支援機構が定めた技術基準を満たす住宅でなければ、利用対象にはなりません。購入する物件が技術基準を満たしているかは、専門の機関等によって検査され、交付された適合証明書によって確認します。
ただし、既に物件検査を終え、機構に登録されている新築・中古マンションや、一�定の条件を満たしている中古住宅については、適合証明書は必要ありません。
適合証明書交付手数料は、約5万円です。
▼関連記事:フラット35が使える中古住宅・中古マンションの条件
住宅ローンの諸費用はいくらになるのか
4000万円の新築一戸建ての購入に3,000万円の住宅ローンを利用した場合の諸費用の概算は、次のようになります。
- 融資手数料+保証料……63万円(保証料一括払い)
- 印紙税……2万円
- 火災保険料……20万円
- 団体信用生命保険料……0円
- 登録免許税……12万円
- 司法書士報酬……5万円
あくまで目安としての計算であり、諸条件によって異なりますが、このケースでは、合計約100万円が諸費用として必要になることが分かります。
まとめ
諸費用の中で、「融資手数料+保証料」が最も高額になります。予算に余裕がなく、初期費用をできる限り抑えたい場合には、融資手数料や保証料を一括払いにするのではなく、金利上乗せ型を選択することで、ゼロ円に近づけることができます。
ただし長期間の返済においては、返済完了時までの総額は、金利上乗せ型の方が返済額が多くなりますから注意が必要です。
市中銀行とネット銀行では、融資手数料と保証料の取り扱いが大きく異なりますから、事前に確認の上、資金計画に合った選択をしてください。