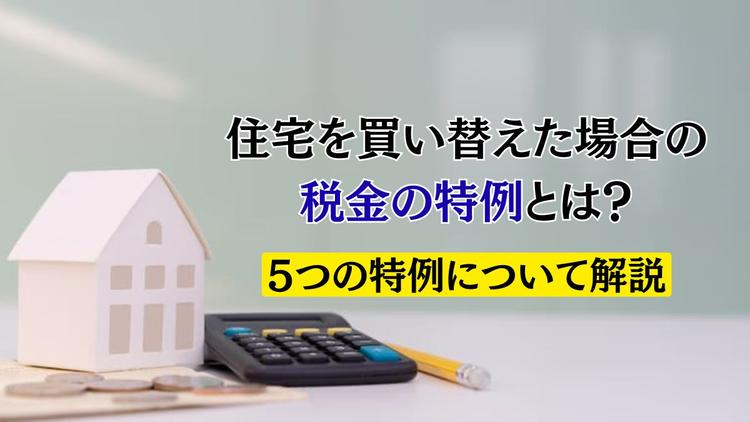家を買うには高額の資金を動かすことになるので、思い付きで進めていくと大きな失敗を招く可能性があります。
家をスムーズに買うには、入居までの流れをしっかり見通して、事前の準備をしておくことが重要です。
家を買うときにまずやるべきこととは何か。購入の流れに沿いながら、失敗をしないための準備を解説していきましょう。
家を購入する流れ
家の購入で失敗しないためには、入居に至るまでの流れをしっかりと押さえておくことが重要です。どのようなことに心がけながら準備を進めればいいのか、物件の検討から入居するまでの流れに沿ってみていきましょう。
物件の情報を収集する
家を買うには、まず条件に合う物件を探しから始めます。大きく、次の4種類の分類から選択をします。
- 新築の戸建て(注文住宅・建売住宅)
- 新築のマンション
- 中古の戸建て
- 中古のマンション
次に住みたいエリアと予算等によって、候補物件を絞り込みます。基本となる条件は、次のような項目です。
- 販売価格
- 居住エリア
- 敷地や建物の広さ
- 周辺環境・施設
これらの条件に合う物件に絞って、購入すべき物件の候補を検索します。
▼関連記事:マンションと戸建ての維持費はどれくらい?コストの差を徹底解説
注文建築は会社選びが重要
注文住宅は、会社選びが重要です。ハウスメーカーだと大手ハウスメーカーとローコスト住宅の選択があります。あるいは、在来工法で建てるのであれば、地域密着型の工務店を選ぶ方法があります。
大手ハウスメーカー
デザイン性、耐久性、各種仕様で優れているのは、大手ハウスメーカーですが、価格が高い点が大きな課題となります。
ローコスト住宅
ローコスト住宅のハウスメーカーは、価格は安く収まりますが、その価格を抑えるために、外壁、設備、建具等の規格が予め決められていることが多く、デザインの選択肢が狭いとい��う難点があります。
地域の工務店
一方、地域密着型の工務店は、設計の自由度はありますが、デザイン的には伝統的な域を超えられないことが多く、大手ハウスメーカーのような流行のデザインに対応できないことがあります。価格面では、ローコスト住宅と大手ハウスメーカーの中間になります。
▼関連記事:後悔しないハウスメーカーの選び方は?家づくりでの失敗を防ぐ5つのポイントを解説
モデルハウスや現地を見学する
大手ハウスメーカーは、住宅展示場などでモデルハウスが見学できるようにしていることが多いので、実際にどのような仕様の建物が建てられるのか確認をすることができます。
また、新築マンションも多くの場合、モデルルームを設置しています。将来住む可能性の有る家の実物を実際に見ることで、失敗のリスクを大きく軽減することができます。
また、購入候補地に実際に足を運ぶことも重要です。広告だけでは分からない、周辺の騒音や異臭などのマイナス要素に気づかされることもあります。また治安状況や周辺住民の様子など現地でなければ分からない情報を入手することができます。
現地調査や物件調査でどのような点に気をつければいいのかは、「物件選びで失敗しないために」の項で、さらに詳しく解説します。
物件を絞り込んで商談をする
購入する物件を絞り込んだら、販売や仲介をしている不動産会社と具体的に商談を進めていきます。中古戸建てや中古マンションは、この段階で実際に物件を内見します。この際に、直接物件を見て、自分の感覚がしっくりとこなかったら、断る勇気を振り絞ることも大切です。
購入申込をする
購入したい物件が決まったら、不動産会社に購入申込をします。購入申込は、今後他の購入希望者の申し込みを受け付けないということを意味します。そのため、購入申し込みの際には、2万円~10万円の購入申込金を納めるのが一般的です。
住宅ローン事前審査申込をする
購入申込をしたら、ほぼ同時期に住宅ローンの事前審査申込をします。実際に住宅ローンを利用することができるのか、希望の額の融資が受けられるのか、といったことが明白にならないと、今後の売買契約に進めることができないからです。
なお、住宅ローンを借り入れる金融機関を選ぶ際は、金利等をしっかり比較することが重要です。
住宅ローンは長ければ35年返済を続けるため、少しの金利差で総返済額が数百万円単位で変わります。
住宅ローンの金利を比較する際は「モゲチェック(PR)」が便利ですので、気になる方は下記からチェックしてみましょう。
モゲチェック(PR)の住宅ローン比較はこちら住宅ローンについては、「資金計画で失敗しないために」の項で、さらに詳しく解説をします。
▼関連記事:不動産会社提携の金融機関で住宅ローンを利用するメリット・デメリットを解説し�ます
売買契約を締結する
購入を決めたら売主と売買契約を締結します。不動産の売買は大変な高額ですから、たとえ親しい知人が売主であっても、不動産会社に仲介をしてもらった方が安心です。
不動産会社への仲介手数料の報酬はけっして安くはありませんが、様々な事態を想定した契約を結ぶことで、後に建物の問題が見つかったときの補償や契約不履行になったときの対応など、トラブルを回避することができます。
新築は販売価格で契約することがほとんどですが、中古住宅の販売価格は絶対的なものではありませんから、交渉によって価格を下げることがあります。
中古住宅の不動産取引では値下げ交渉を行うのは普通のことなので、ある程度値下げ交渉があることを前提にして、金額設定を高めにしていることも少なくありません。
売買契約時には、次の書類が必要になります。
- 実印
- 印鑑登録証明書
- 本人確認書類
実印の作成や印鑑登録には、一定の日数を要しますから、これらを持ち合わせていない場合は、家の購入の検討を始めた段階で、実印の作成と印鑑登録を済ませておきましょう。
住宅ローン申込
売買契約が成立したら、住宅ローンの申し込みをします。気をつけたいのは、たとえ仮審査(事前審査)を通過していても、正式の申し込み後に、審査が不合格になることがあるということです。
そのため、上述の売買契約においては、ローンが借りられない場合は違約金なしで契約が解除できる「ローン特約」を付けておく方が安心です。
売買契約後に住宅ローンの本審査を行い、「融資承認取得期日」までに承認が得られない、または否認となった場合は、手付金の放棄等のペナルティなしで売買契約を白紙解除できる。
ローン特約には、ローンを申し込む金融機関名と融資希望金額を確実に記入しておきましょう。これらの事項が不明確な場合、
- 他の金融機関で融資承認が得られるのではないか
- 希望額に満たないとはいえ、融資承認はあったではないか
といった理由で、違約金を請求される事態が想定できるからです。
融資が承認されれば、金融機関とローン契約(金消契約)を結びます。
▼関連記事:住宅ローン特約(融資特約)とは?不動産売買の際に確認しておくべきポイントを解説
残金決済・物件引渡し
残金決済とは、購入価格から申込金を差し引いた金額を支払うことです。ただし注文住宅の場合は、申込金の他に着手金、中間金を支払うのが一般的ですから、その残りの金額を支払うことを意味します。
残金決済の日は、契約の段階で決めておきます。それぞれの事情によって異なりますが、中古住宅の場合は、契約のおよそ1カ月後に設定されるのが一般的です。
引き渡しの際には、買主は次の書類や代金を用意します。
- 実印
- 印鑑登録証明書
- 住民票
- 抵当権等設定書類
- 住宅用家屋証明書
- 本人確認書類
- 購入金額の残金
- 仲介手数料の残金
- 固定資産税等の精算金
残金決済の段階で住宅ローンの融資が実行されます。
この際に、金融機関から直接売主の口座に振り込む方法も選択できます。同時に依頼した司法書士によって、不動産の移転登記と金融機関の抵当権設定が行われます。
これらの手続きが終了すれば、物件の引渡しが行われ、入居が可能になります。
▼関連記事:不動産売買時の契約から残代金決済までの流れを売主・買主の各視点で解説
物件を選びで失敗しないために
新居で快適に暮らすためには、物件そのものの品質はもちろんのこと、周辺環境も非常に重要な要素となります。現地調査や物件調査でどのよう点に気をつければいいのか解説していきましょう。
立地条件を調査する
家を買って失敗しないようにするためにも、建物が建っている場所の周辺環境を調査しておきましょう。主に次のような点について確認をします。
- 災害リスクを調べる……自治体が発行しているハザードマップを確認します。また国土交通省が運営しているハザードマップポータルサイトでも、洪水・土砂災害・津波・道路防災などに関する情報を入手することができます。
ハザードマップポータルサイト(国土交通省)
不動産情報ライブラリの地図検索(国土交通省)
- 周辺環境を確認する……実際に物件周囲を歩いて、風紀の乱れやごみの散乱などのマイナス要因が�ないことを確認します。犯罪発生の状況は、各都道府県警が公開している犯罪発生マップによって確認することができます。
下記記事では、物件選びの基準を「幸福度を高める」という観点から考察しています。
▼関連記事:住み替え・家の購入で大切な6つの要素を「幸福度」の観点から考察|コストをかける部分・削る部分は?
予算内で最適な住まい選びをしたい方は、ぜひご覧ください。
購入物件を調査する
物件そのものに対する調査も必要です。
特に中古住宅については、隠れた不備が存在することがあるので、次のような事項について入念な調査を実施します。
- 法の適合性を調べる……住宅は適法な物件であることが基本です。違反建物は、所有者が法的責任を問われるのはもちろんですが、それ以前に住宅ローンの審査が通過しないリスクがあります。購入に際しては、建築確認済証と検査済証があることを確認しましょう。地方自治体の建築指導担当窓口で確認することもできます。
- 耐震性能を確認する……耐震性能を有する建物を選ぶには、確認済証の交付日によって判断する方法が最も堅実です。確認済証が1981年6月1日以降に交付されていることを確認しましょう。
- 建物のゆがみはないか……簡易な水平器やさげふりで、建物に傾きがないことを確認しましょう。傾きが確認できた場合、建物の安全性や健康被害への懸念が�あるため、購入を見送った方がいいでしょう。
- シロアリの被害はないか……シロアリの被害は、床下点検口から床下を目視することで判断できます。シロアリの被害を軽視していると、やがて建物の構造に重大な不具合を起こす原因となります。
- 雨漏りはないか……雨漏りが生じた建物は、必ず小屋裏や天井に水の痕跡がありますから、目視によって有無を確認しましょう。雨漏りの痕跡を発見した場合は、その対策が実施されていることを確認しましょう。
中古住宅はインスペクションの実施を
中古住宅の不備の確認は、専門家でない場合にはどうしても限界があります。中古戸建の購入に際してはインスペクションを依頼することで、専門家の目による調査が実施できるので、大きな安心を得ることができます。
インスペクションとは、住宅の状態を建築士が検査して、劣化している箇所や欠陥の有無について報告するシステムのことです。
中古住宅の売買では、仲介の不動産会社がインスペクションを実施する会社を斡旋することが法律で義務づけられています。売主が既に実施している場合には、その報告書を入手することで一定の安心を得ることができます。
インスペクションの費用相場は10万円程度です。
▼関連記事:既存住宅状況調査(インスペクション)とは|検査項目や物件売買時のメリットを解説
資金計画で失敗しないために
家の購入では、何より資金計画が重要です。住宅ローンの返済計画の適正さを検討するのはもちろんのこと、自己資金の配分についても綿密に検討することで、大きな失敗を回避することができます。ここでは、住宅ローンと自己資金で注意すべき点について触れていきます。
住宅ローンの借入額を決める
自分の年収で、いくら住宅ローンが借入できるのかを知るためには、返済負担率による計算が適しています。
無理せず返せる返済負担率の目安は25%以内
返済負担率とは、年収における年間のローン返済額の割合のことで、次のように計算します。
金融機関は、住宅ローンの返済負担率によって上限を定めています。多くの場合、年収400万円以上で35%程度に設定しています。
ただし、これは借り入れ可能な額であり、必ずしも返済可能な額に直結するものではありません。
無理のなく返済できる住宅ローン返済負担率は、年収の25%以内とされています。
年収500万円でローンを借り入れる場合のシミュレーション
より安全に考えるのであれば、20%以内が望ましいでしょう。具体的にどのような額になるのか見ていきましょう。
なお借入額は、固定金利2.0%、35年返済で想定しています。
【年収500万円の場合】
- 返済負担率20%……毎月の返済額は約3万円(借入額2,500万円程度)
- 返済負担率25%……毎月の返済額は約4万円(借入額3,000万円程度)
- 返済負担率35%……毎月の返済額は約6万円(借入額4,000万円程度)
また、「住宅ローン総額÷年収」で算出する「年収倍率」という指標をもとに、融資額を検討する方法があります。
一般的には年収の5~7倍ほどが借入可能額とされています。年収500万円の人だと、2,500万円~3,500万円ですから、返済負担率の20%~30%の範囲になります。
注意したいのは、将来昇進や会社の成長などによって給与が増額するといった、楽天的な想定は極力しないことです。
業績の悪化によって、住宅ローンの返済に窮する事例が多く発生していますから、堅実な返済に徹することが重要です。
上記の住宅ローンシミュレーターでは、借入額・頭金・金利・借入年数を任意に設定して総返済額を計算できます。
▼関連記事:住宅ローンの平均返済額はいくら?世帯年収別に無理のない返済プランを解説
住宅ローンの金利タイプを決める
住宅ローンは、金利のタイプによって、大きく「固定金利」と「変動金利」の2種類に分かれます。
固定金利のメリット・デメリット
固定金利は、ローン借入時から、金利が固定されたローンです。代表的なものとして、フラット35があります。世の中の金利水準が上昇しても、金利が見直されないので、返済額が変わることはありません。
金利が急激に上がる不安がなく返済ができますから、収支計画が立てやすいという利点があります。
一方で、固定金利は、変動金利より金利が高めに設定されていることがあり、金利が長期間にわたって低く推移した場合には、最終的な返済額が変動金利よりも多くなります。
また、固定金利は変動金利と比べて、金融機関ごとに金利差が大きい点も特徴です。
変動金利のメリット・デメリット
変動金利は、定期的に金利が見直されるローンです。金利は半年ごとに見直され、金利の変動によって返済額が増減します。
ただし、返済額の変更自体は、5年ごとに行われるので、目まぐるしく返済額が変動するわけではありません。
変動金利は、固定金利よりも金利が低めに設定されていますが、将来金利が上昇する局面になった場合は、返済額が上昇するリスクがあります。
2024年10月には、多くの金融機関が店頭金利(基準金利)を見直しを行い、今後はさらなる利上げの可能性もあるため、住宅ローンの金利に関する情報は定期的にチェックしましょう。
また、金利タイプや金融機関ごとの金利を比較検討した上で住宅ローンを利用することで、支払総額をできるだけ抑えたい方は「モゲチェック(PR)」がおすすめです。
モゲチェック(PR)の住宅ローン比較はこちら▼関連記事:住宅ローンの賢い組み方と返し方は?リスクを抑えて節税効果が出る方法を解説
頭金の額を決める
住宅の購入では、基本的に頭金が必要です。住宅ローンを借り入れる前に支払わなくてはいけないので、自己資金で用意することになります。支払い額の2割程度が目途になります。
頭金を多く出すことで、住宅ローンの返済負担は軽減できますが、近年は超低金利時代なので、頭金が溜まるまで賃料を払い続ける��よりも、ある程度貯まった段階で購入を決断した方が、経済面では合理的だとする考え方もあります。
ただし、ローンの融資額を少しでも減らそうとして、今ある貯金をすべてマイホームの購入資金にあててしまうのはかえって危険です。急な出費が必要なときに困惑する事態になりかねないからです。
いざというときのための「生活予備費」や「子どもの進学費用」などは、住宅の購入費とは別に残しておきましょう。
▼関連記事:住宅ローンの頭金はいくら用意すべき?目安額と返済プランを考察
諸費用も想定しておく
家の購入に際しては、物件の購入代金の他に、不動産会社、銀行、司法書士などの業務に対する手数料や報酬が発生します。こうした諸費用も考慮したうえで、資金計画を立てる必要があります。
諸費用の代表的なものとして次のようなものが挙げられます。
- 仲介手数料……仲介をしてもらった不動産会社に支払う費用です。金額は「物件価格の3%+6万円+消費税」が法律で定められた上限です(物件価格800万円以上の場合)。3,000万円の物件の場合だと約105万円です。
- 融資事務手数料……金融機関に支払う、住宅ローンを組むための手数料です。金融機関によって異なりますが概ね3万円程度です。
- 保証料……住宅ローンは、途中で返済不能となった場合に保証会社が代わりに弁済するシステムになっており、そのための保証料です。一括支払いですが、住宅ローンの金利に組み込める金融機関もあります。35年ローンで100万円あたり2万円程度です。1,500万円を借りた場合は、30万��円程度になります。利息組込み型の場合は、金利が2%上乗せになります。フラット35は、金利にあらかじめ含まれているので保証料はありません。
- 団体信用生命保険料……住宅ローンを組むために、多くの金融機関では団体信用生命保険(団信)への加入を義務付けており、その保険料が必要です。通常は住宅ローンの金利に含まれています。
- 火災保険料……住宅ローンを組むために、多くの金融機関では火災保険への加入を義務付けており、その保険料が必要です。一般的な保証で30万円程度です。
- 登記手数料……司法書士に依頼する物件の所有権移転や、ローンの抵当権設定の登記手続きの代行への報酬費用です。金額は司法書士によって異なりますが、10万円です。
こうした諸費用は、注文建築の場合で物件価格の5~10%程度とされています。たとえば、3,000万円の物件を購入するのであれば、別途150万~300万円の諸費用を準備する必要があります。
▼関連記事:諸費用で住宅ローンに上乗せできるものは?家の購入で失敗しない資金計画を解説
まとめ
家の購入に際して、最も重要なことは資金計画です。住宅ローンの融資が実行されて、無事に入居ができたとしても、後の返済を滞りなく行わなければ、たちまち家を失うことになります。
現在は、かつてのように、賃金が確実に上昇する時代ではありません。経済協力開発機構(OECD)の2020年の調査によると、日本の平均賃金は424万円で、この30年間の上昇率はわずか4%という統計調査も出されています。
住宅ローンの返済につい��ては、楽観的な考えを捨てて、堅実な方法を選択していくことが重要です。
中古住宅においては、物件の質も、失敗をしないための大きなポイントになります。中でも、適法性、耐震性、雨漏りの有無が重要な要素となります。インスペクションによって、これらの課題について、貴重なアドバイスを得ることができますから、実施の検討をしてみましょう。