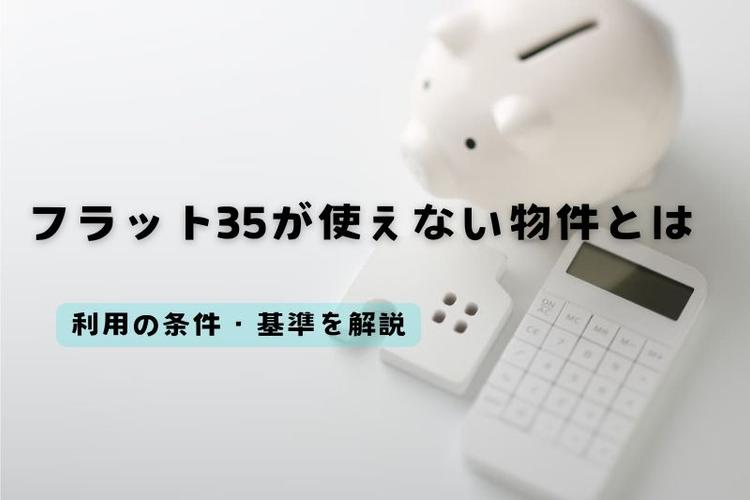フラット35は、新築住宅や中古住宅などに使える住宅ローンです。返済する全期間で固定金利となっており、返済中に市中金利が上昇しても返済額は変化しません。
フラット35は、返済期間が最長35年なので月々の返済額を抑えることができる一方で、対象となる物件には一般的な住宅ローンよりも厳しい条件があります。
そのため、購入を予定していたの住宅が、フラット35が使えなかったという事態もあり得るのです。それではフラット35が使えないのはどのような物件なのか、利用の条件や基準について確認していきましょう。
フラット35が使えない物件とは
フラット35は、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供する住宅ローンです。全期間固定金利なので、住宅取得資金を受け取ったときに、返済終了までの借入金利と返済額が確定しています。
たとえ返済中に市中金利や物価が上昇しても、月々の返済額が増えることはありません。
返済期間が最長35年なので月々の返済額を抑えることができますが、一方で借入れ対象となる物件には、一般の住宅ローンよりも厳しい基準が定められています。
そのため、検査済証を取得した適法な建築物であっても、フラット35が使えない物件も存在します。どのような物件が、フラット35が使えないのか解説をしていきしょう。
モゲチェック(PR)の住宅ローン比較はこちら適法性が証明できない
建築物が適法であることは、検査済証によって証明できます。中古住宅も検査時のままで使用しているのであれば適法な建築物です。
現在、新築住宅のほとんどが検査済証を取得していますが、かつては検査済証を取得していない建築物が多く存在していました。検査済証が交付されていない物件は、適法であることを証明することが困難なため、原則としてフラット35を使うことはできません。
また検査済証が交付されている物件であっても、検査時と建物の規模、�形態が異なっていれば適法とはいえないため、フラット35を使うことはできません。

接道義務規定に適合しない
フラット35の基準では、「住宅の敷地は、原則として一般の交通の用に供する道に2m以上接すること」とされています。
そもそも建築物は、建築基準法上の道路に2メートル以上接していないと、建てることができません。したがって、新築で検査済証を取得している物件は、基本的に接道義務規定に適合しています��。
問題になるのは、中古住宅です。昭和25年以前に建築された住宅を補強している物件だと、既存不適格建築物として、接道義務に適合しない物件も存在します。
あるいは、もともと接道義務に適合していたものの、何らかの事情で敷地の一部が使用できなくなったために、接道義務に適合しなくなった物件もあります。
こうした物件は、接道義務の規定に適合していないためフラット35を使うことができません。

住宅の規模が小さい
フラット35が利用できる住宅の規模は、一戸建てで70平方メートル以上、マンションで30平方メートル以上とされています。
住宅の規模には、車庫やマンションの共用部は含まれません。また店舗・事務所等の併用住宅は、住宅部分のみが対象となります。
住宅の規模が規定よりも小さい物件は、フラット35の適用外です。
住宅の規格に適合しない
フラット35が利用できる住宅の規格は、「住宅は、原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合も可)、炊事室、便所、浴室があり、独立した生活を営むことができるもの」とされています。
このため「離れ」のように炊事室、便所、浴室のいずれかが欠ける住宅は、フラット35を使うことはできません。
また、部屋数が2以上あったとしても、採光に有効な窓などの開口部が居室の床面積の7分の1以上なければ、居住室として扱われないので注意が必要です。
戸建ての型式が適合しない
フラット35が利用できる木造住宅(耐火構造及び準耐火構造の住宅を除く)は、一戸建てか長屋住宅です。長屋住宅の形式の場合は、連棟タイプでも重層タイプでも可能です。
二�世帯住宅だと「完全同居型」「部分同居型」「完全分離型」のいずれのタイプで利用ができますが、「離れ」については利用できない可能性があります。
住宅の耐久性の基準に適合しない
フラット35を使うためには、木造の住宅のうち外壁に接する土台を木造とする住宅は、「ヒノキ・ヒバ等の耐久性の高い樹種や防腐・防蟻薬剤処理された材料を使用していること」とされています。
この基準に適合していることが図面で確認できない場合は、床下点検口等から目視により土台及び周辺に腐朽等及び蟻害がないことを確認することで、借入対象物件とすることができます。
この他住宅の耐久性について、次のような基準に適合することが求められています。
- 基礎は地面からの高さが40センチメートル以上あること
- 換気上有効な2か所以上の小屋裏換気孔が設けられていること
- 基礎に設けた床下換気孔の間隔が4メートル以内であること
これらの基準に適合しない物件はフラット35を使うことができません。
耐震基準に適合しない
フラット35は、所定の耐震性能がない物件では使うことができません。
建築確認日が昭和56年5月31日(建築確認日が確認できない場合にあっては、表示登記における新築時期)以前の住宅は、住宅金融支援機構が定める耐震評価基準等に適合することが条件です。
▼関連記事

フラット35の基準に適合していない物件の対処方法
建物の建築年次が古いなどの理由で、フラット35の耐震基準に適合しない建物であっても、所定の検査に合格することで、借入対象建築物とすることができます。どのように進めればいいのか解説をしましょう。
適合証明書の交付を受ける
建築年次が古く、耐震基準に適合しない物件は、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることについて検査機関による物件検査を受けることで、基準への適合性が確認できます。物件検査に合格すれば適合証明書が交付されますので、これを金融機関に提出することでフラット35を借り入れることができます。
現場検査で指摘事項が発生した場合は、必要な事項を補修・補強することで再検査を受けます。この場合も写真判定ではなく、現地での調査が実施されます。
適合検査は、新築住宅の場合は検査機関で、中古住宅の場合は検査機関または適合証明技術者によって実施されます。指定機関は住宅金融支援機構のホームページで検索ができます。
検査費用はそれぞれの機関で異なりますが、3万円~10万円が目安の金額です。
▼関連記事:耐震基準適合証明書の取得方法
物件検査をしなくてもフラット35を使える中古住宅
「中古住宅が技術基準を満たすかどうか分からない」「技術基準を満たすための費用が不安」という方には、物件検査を省略できる中古住宅がありますので紹介していきましょう。
中古マンションらくらくフラット35
「中古マンションらくらくフラット35」とは、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることをあらかじめ確認した中古マンションです。該当するマンションは、物件情報サイト(中古マンションらくらくフラット35)で検索することができます。
検索したマンションの「適合証明省略に関する申出書」を印刷して、取扱金融機関に提出することで物件検査を省略できます。
一定の要件を満たす長期優良住宅
築年数が20年以内の中古住宅で、新築時に長期優良住宅の認定を受けている住宅は、「(フラット35)中古住宅に関する確認書」を取扱金融機関に提出することで、物件検査を省略できます。

安心R住宅でフラット35利用した中古住宅
「安心R住宅」である中古住宅で、新築時に「フラット35」を利用している住宅は「(フラット35)中古住宅に関する確認書」を取扱金融機関に提出することで物件検査を省略できます。
ただし新築時のフラット35の融資が「フラット35(保証型)」であった場合には、借入申込みができる金融機関は売主が新築時に「フラット35(保証型)」を利用した金融機関に限られます。
なお、「安心R住宅」とは、良質で安心できる中古住宅について、国が商標登録したロゴマークを使える住宅です。耐震性や構造上の不具合などがないかを確認済みで、実施した点検や修繕の内容、どんな保証や保険が付くのかもわかるようになっています。

築10年以内のフラット35利用した中古住宅
築10年以内の中古住宅で、新築時に「フラット35」を利用している住宅は「(フラット35)中古住宅に関する確認書」を取扱金融機関に提出することで、物件検査を省略できます。
ただし新築時のフラット35の融資が「フラット35(保証型)」であった場合には、借入申込みができる金融機関は売主が新築時に「フラット35(保証型)」を利用した金融機関に限られます。
一定の要件を満たす「スムストック」の中古住宅
協定締結団体による中古住宅で、当該運営団体があらかじめ「フラット35」の基準に適合することを確認した住宅は、「(フラット35)中古住宅に関する確認書」を取扱金融機関に提出することで、物件検査を省略できます。
なお、2019年10月時点で協定団体登録住宅として登録されているのは「スムストック」です。
「スムストック」は、大手ハウスメーカー10社で建てられた住まいを中古住宅としてストックし、不動産と建物のプロであるスムストック住宅販売士が査定から販売まで行う制度です。
参考:【フラット35】中古住宅の物件検査/住宅金融支援機構
参考:「いい家は、つづく。」スムストックの魅力とは?/大和ハウス
申込人に関する要件
フラット35は、物件が条件に適合していても、申込人に関する要件が適合しない場合は使うことができません。ここでは、申込人に対する要件について紹介していきましょう。
年齢要件
申込時の年齢が満70歳未満で、かつ完済時の年齢が80歳未満とされています。ただし、「親子リレー返済」で、親のローンを子が継承するのであれば、申込人の年齢要件は後継者の年齢が基準になります。
国籍要件
日本国籍であることが要件です。この他、外国籍で永住許可を受けている人、特別永住者の人も対象になります。
年収要件
年収に占める年間合計返済額の割合(総返済負担率)が年収400万円未満は30%以下、400万円以上は35%以下であることが要件となります。ここでいう返済額とは、フラット35の返済額だけでなく、自動車ローン、カードローン、教育ローンなどについても合算されます。
なお、一般的な住宅ローンで要件となる勤続年数はフラット35では要件になっていません。したがって、転職直後でも借入ができる可能性があります。
団体信用生命保険への加入は任意
一般的なローンでは団体信用生命保険の加入が必須の条件となりますが、フラット35では��加入は任意です。
民間金融機関の住宅ローンでは、多くが団信への加入を求められますが、フラット35では必須ではありません。
したがって、申込者の健康状態を理由に団体信用生命保険に加入できない場合であっても、フラット35を利用可能です。
ただし、団体信用生命保険しない場合は債務者が死亡すると、住宅ローンの債務は遺族が返済を引き継ぐこことなります。
フラット35に付帯できる団体信用生命保険には、死亡や所定の身体障害に備える「新機構団信」を始めとして、3大疾病にも備えられる「3大疾病付機構団信」、連帯債務者となる配偶者も保障の対象となる「夫婦連生団信」があります。

まとめ
フラット35が使える物件は、なにより適法で耐久性・耐震性のある建物であることが条件になります。
そのため、まず適法性が証明できない住宅については、使うことができません。適法性とは、検査済証が交付された建物です。さらに中古住宅においては、検査済証交付後に違法な増改築をしていないことが条件になります。
耐久性については、とりわけ土台の構造が問われます。木造の住宅のうち外壁に接する土台を木造とする住宅は、「ヒノキ・ヒバ等の耐久性の高い樹種や防腐・防蟻薬剤処理された材料を使用していること」としなければなりません。
耐震性は、建築確認日が昭和56年5月31日以前の住宅は、住宅金融支援機構が定める耐震評価基準等に適合することが条件になります。
住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることについては、検査機関による物件検査を受け、合格することで借入対象の物件とすることができます。