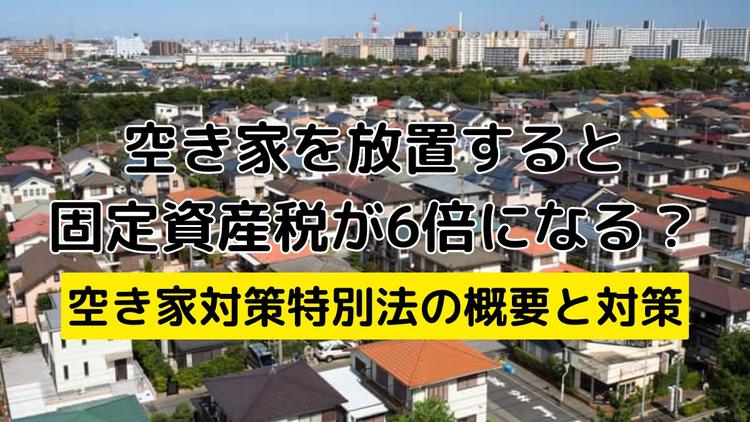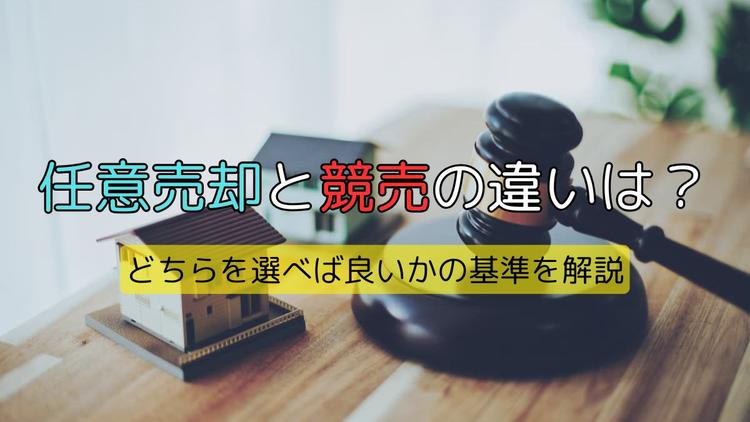空き家でもいいので、土地に家が建っている状態だと、税金の面でメリットがあると聞いたのですが。本当でしょうか?
はい、土地の上に住宅がある状態なら、固定資産税が安くなる特例があります。面積が200㎡以下の部分に関しては、最大で1/6になっちゃいます!
それなら、空き家であっても放置しておいた方がいいということですね!
ところが、老朽化した空き家の問題も増えて、2015年に「空き家対策特別措置法」ができました。倒壊、景観などの問題があって、自治体から「特定空き家」に指定されると、特例が使えなくなるんですよ。
…ということは、本来なら安くなる固定資産税も、高くなってしまうわけですか。古くなった空き家を放置しておくのはまずいですね。
ただ、「特定空き家」に指定されないように管理していればOKですし、空き家の解体や建て替えで固定資産税を減免してくれる自治体もあります。この記事で空き家の管理について考えていきましょう!
空き家でも建物が建っていると固定資産税が軽減される?
不動産を所有していると固定資産税を納める必要があります。
固定資産税は自治体ごとに定められた税率で納税額が決められますが、土地の上に住宅が建っていると、その土地の固定資産税は軽減税率の適用を受けることができます。
また、この軽減税率は空き家であっても住宅が建っていれば適用を受けられます。
ここでは、最初にこうした固定資産税の税率や軽減税率について見ていきたいと思います。
固定資産税の概要
不動産を所有していると、毎年1月1日の所有者が固定資産税を納める必要があります。
標準税率は1.4%で、課税標準(課税の元となる不動産の価格)は「固定資産税評価額」です。
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の土地であれば、1,000万円×1.4%=14万円を毎年納めることとなります。
なお、固定資産税評価額は自治体が個別に決定するもので、実勢価格の70%程度を目安に定められることとされています。
例えば、1,500万円で売買されている土地であれば、固定資産税は概ね1,050万円程度となります。
固定資産税の軽減税率
固定資産税は土地の上に住宅が建っていると「住宅用地の特例」という軽減税率の適用を受けることができます。
住宅用地の特例は土地の広さごとに軽減割合が決まっており、その割合は以下のようになっていま�す。
| 面積要件 | 軽減割合 | |
| 小規模住宅用地 | 200㎡以下の部分 | 課税標準×1/6×標準税率 |
| 一般住宅用地 | 200㎡超の部分 | 課税標準×1/3×標準税率 |
また、建物については、新築住宅において面積120㎡までの部分について3年間(一般の住宅)もしくは5年間(3階建以上もしくは耐火建築物)、固定資産税を1/2とすることができます。
軽減税率でどのくらい負担が軽くなる?
軽減税率の適用を受けると実際どのくらい負担が軽くなるのでしょうか?
ここでは土地の固定資産税のみ比較してみましょう。
面積400㎡の土地の固定資産税評価額が1,500万円の場合
(1,500万円×(200㎡÷400㎡)×1/6×1.4%)+(1,500万円×(200㎡÷400㎡)×1/3×1.4%)=5.25万円となります。
本来であれば1,500万円×1.4%=21万円納めなければならないのと比べると、かなり低く抑えられていると言えるでしょう。
また、仮に面積200㎡の土地が1,500万円であれば、1,500万円×1/6×1.4%=3.5万円と、軽減税率の適用を受けないのと比べると1/6となります。
このように、住宅用地の特例を受けると土地の面積によっては納税額を最大で1/6とすることができます。
空き家の現状と空き家対策特別措置法
固定資産税は住宅が建っているだけで最大1/6になることをお伝えしました。
これは、住宅が空き家でも同じで、軽減税率が原因で空き家が解体されない事態につながっている側面があります。
現在使っておらず、今後も使わない予定の空き家であっても、解体してしまうと軽減税率を受けられなくなり、解体しようとしない人が多いからです。
空き家の現状と将来推計
総務省のデータによると、2018年の空き家数は846万戸となっています。
1978年に268万戸、1993年に448万戸など空き家数は一貫して右肩上がりに増えています。
出所:空き家数及び空き家率の推移-全国(昭和38年~平成30年)1
また、空き家率も右肩上がりに増えており、1978年に7.6%だった空き家率は1993年に9,8%、2013年に13.6%となっています2。
さらに、総務省のデータを元にした野村総研の調査では将来推計も公表されており、2023年には空き家数1,404万戸、空き家率21,1%、2033年には空き家数2,167万戸、空き家率30.4%と急激に上昇していくことが予想されています3。
これは、日本では今後人口減少が続いていくことが予想されており、それとは逆行するように総住宅数が増え続けることがその理由の一つだと言えるで��しょう。
なぜ空き家は増えるの?
日本では今後少子高齢化が進み、高齢化率が大きく上昇していきます。
高齢の方が亡くなってしまったり、高齢者施設に移住したりして住まれなくなり、それを相続した家族の方も田舎にある土地を活用できないことが多いため、空き家が年々増加しています。
相続した家で利用されないものの多くは、解体されることがなく空き家となってしまっているのです。
建物を解体するのにはお金がかかりますし、そもそも建物を解体してしまうと固定資産税が高くなってしまうという問題も、空き家の増加に拍車をかけています。
空き家対策特別措置法の制定
こうした問題に対策するため、2015年に施行されたのが空き家対策特別措置法です。
空き家対策特別措置法は手入れされていない空き家を防災面や衛生面、景観面での保全を目指し、活用促進することを目的に作られました。
そうした施策の一つに、固定資産税に関する内容が盛り込まれています。
空き家対策特別措置法で固定資産税が6倍になる?
空き家対策特別措置法では空き家に関する固定資産税の問題をどのように解決するのでしょうか?
特定空き家に指定されると軽減税率が受けられなくなる
空き家対策特別措置法では、空き家でも住宅用地の特例を受けられることから空き家の解体が進まない状況を解決するための施策が盛り込まれています。
とはいえ、空き家対策特別措置法の施行により全ての空き家の固定資産税が高くなるわけではありません。
具体的には、自治体の調査により「特定空き家」に指定されると、住宅が建っていたとしても住宅用地の特例の適用を受けられなくなります。
特定空き家に指定されるまでの流れ
空き家対策特別措置法における「特定空き家」は、そのまま放置することで以下のいずれかの状態に該当する空き家のことを指します。
- 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
自治体による調査の結果、上記状態のいずれかに該当すると認められた空き家は特定空き家に指定されます。
特定空き家に指定されると、所有者にはその状態を改善するための「助言・指導」が行われます。
その後、状態が改善せずにいると「勧告」が行われます。
勧告が行われた段階で住宅用地特例の対象から除��外されます。
その後さらに状態が改善せずにいると、状態を改善するための「命令」が下され、最終的には「行政代執行」となります4。
空き家対策特別措置法で特定空き家に指定されないためには
空き家対策特別措置法において特定空き家に指定される状態についてお伝えしましたが、逆に言えば特定空き家に指定されないためには、それらいずれかの状態にならないように適切に管理すればよいと言えます。
「倒壊等著しく危険な状態」を解消する
倒壊など著しく経験な状態をさらに細かく分類すると、以下の3つに分けられます。
- 建物が倒壊するおそれがある
- 屋根や外壁等が脱落もしくは飛散するおそれがある
- 擁壁が老朽化し危険となるおそれがある
▼関連記事:擁壁の安全性を調査すべきケース
「著しく衛生上有害な状態」を解消する
著しく衛生上有害な状態は建物や設備の状況、もしくはごみの放置などにより以下のような状態にあることを指します。
- 石綿(アスベスト)が飛散し暴露する可能性が高い状態
- 浄化槽が破損し異臭や害虫、害獣の発生につながる状態
- ごみの放置により異臭が発生し地域住民の日常生活に支障を及ぼしている状態
- ごみの放置により多数のねずみやはえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている状態
「著しく景観を損なっている状態」を解消する
著しく景観を損なっている状態について例をあげると、以下のようなものがあります。
- 既存の景観に関するルールに著しく該当しない状態
- 汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されたりしている状態
- 多数の窓ガラスが割れたまま放置された状態
- 立木などが建築物の全面を覆う程度まで繁茂している状態
- ごみが山積したまま放置されている状態
- 看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで破損、汚損したまま放置されている状態
その他特定空き家に指定される条件
最後に、その他特定空き家に指定される条件を細かく分類すると以下の4つに分けられます。
- 立木が原因で近隣の道路や敷地に枝葉が大量に散らばっている、もしくは立朴の枝により歩行者の運行が妨げられている
- 空き家に住み着いた動物の鳴き声やふん等の臭気、毛等が原因で地域住民の日常生活に支障を来たしている
- シロアリが大量に発生して近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある
- 門扉が施錠されていない、又は窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態にある
以上はあくまでも一例ですが、上記のような状態にある、もしくは将来そうなる可能性があるのであれば早い段階で対処しておくようにしましょう。
空き家の解体や建て替えで固定資産税の減免や助成を受けられる自治体もある
空き家を空き家のままにして適切に管理しておかないと最大で6倍もの固定資産税を課されることになりました。
そうでなくとも、管理しておかないことが原因で何らかの事故が起こってしまうのは避けたいところでしょう。
しかし、空き家の解体にはお金がかかってしまいます。
自治体によっては、空き家の解体や建て替え、解体後の固定資産税について減免や助成を受けられることもあるので調べてみましょう。
東京都荒川区の例
例えば、東京都荒川区では「危険老朽空家住宅除却助成事業」が実施されています。
この助成事業の対象となる建築物は以下の通りです。
- 1年以上使用されていないこと
- 住宅部分の面積が延床面積の2分の1以上であること
- 昭和56年5月31日以前に建築されていること
- 荒川区危険老朽建築物等除却検討委員会の付議の結果、区長に倒壊等の危険性が著しく高いと判定されたものであること
また、助成を受けられる際の助成金額は26,000円/㎡(上限金額1,000㎡)で、解体に要する実支出額が対象となります。
木造住宅の解体費用の相場は30,000円/㎡程度なので、解体費用のほとんどについて助成を受けられると言えるでしょう。
岡山県遠賀郡岡垣町の例
岡山県遠賀郡岡垣町では住宅を解体した後の固定資産税について、その一部を減免する制度が用意されています。
この制度の対象となる住宅は以下の通りです。
- 今後、使用する見込みがないこと
- 居住��用の家屋であること
- 昭和56年12月31日以前に建築されたこと
- 平成30年1月2日以降に解体した後、建物を再建築しないこと
- 住宅用地の特例が適用されていること
上記要件に当てはまれば、建物を解体して更地になった後も住宅用地の特例適用を受けたのと同じ額の減免を受けられます。
この制度を利用できるのは減免を受けてから5年間で、建物が建築されたり所有者が変更されたりすると終了します。
まとめ
空き家の固定資産税についてお伝えしました。
現在、住宅が建っているだけで住宅用地の特例を受けられるという理由から、利用されないまま放置されている空き家が多く見られます。
こうした状況から、2015年に制定された空き家対策特別措置法では空き家の固定資産税に関する内容が盛り込まれ、適切に管理されていない空き家については住宅用地の特例が受けられないこととなりました。
そうでなくとも、空き家のまま放置していると近隣住民に悪影響を及ぼす可能性があるため、適切に管理できない場合には解体するなど対処する必要があるでしょう。
その際には、自治体によって助成や減免を受けられることもあるので、確認してみることをおすすめします。