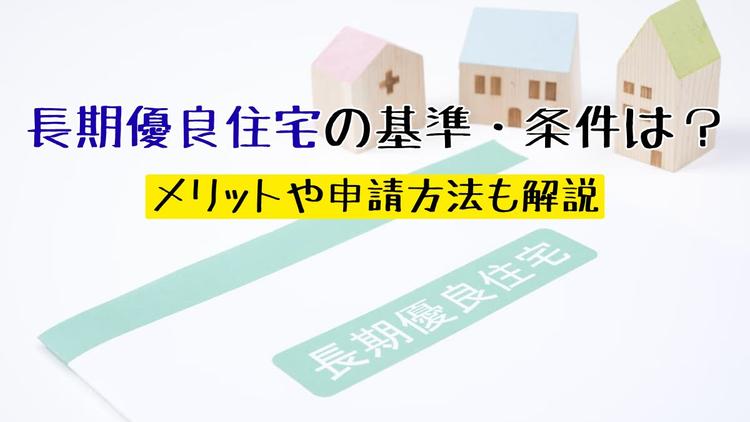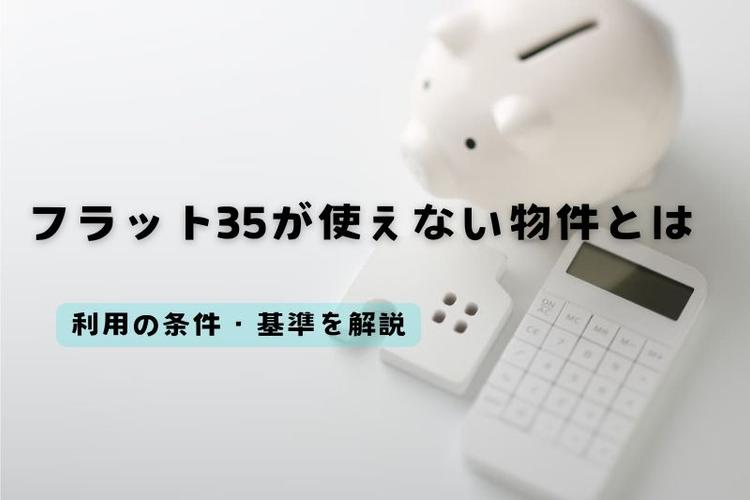「長期優良住宅」と大きく表示された不動産広告を見かけたことはあるでしょうか。
画像出典:吉永建設
長期優良住宅は、数世代にわたり良好な状態で住み続けられることを目指した住宅です。高品質で住みやすいばかりでなく、住宅ローンの金利や税制面でも優遇措置があります。この記事では、長期優良住宅に認定されるための基準や条件について解説をしています。合わせて、メリットや申請方法についても解説します。
長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、数世代にわたり良好な状態で使用するための措置が、構造や設備に講じられている優良な住宅のことです。対象住宅の設計内容説明書や維持保全計画書を作成し、所管行政庁の審査を経て長期優良住宅の認定を受けます。
長期優良住宅認定制度は平成21年6月4日に施行され、平成30年末までに累計100万戸以上が認定を受けています。
長期優良住宅の基準・条件は?
長期優良住宅(新築)の認定を受けるためには、いくつかの基準や条件をクリアしなければなりません。具体的にどのような基準等が設定されているのか解説をしていきましょう。
構造躯体の劣化対策
通常想定される維持管理の条件下において、基礎、壁、柱、小屋組、土台、梁、斜材、床、屋根などの構造躯体が少なくとも100年は使用継続ができる措置をとる必要があります。
木造住宅では、床下及び小屋裏の点検口を設置するとともに床下空間の有効高さを33センチメートル以上確保することで、通気性を高め腐食の進行を抑えます。
耐震性
極めて稀に発生する大地震が起きても、住人の生命が守れる耐震性が求められます。たとえ地震で建物が損傷しても、改修が容易に行える程度の被害に抑えなければなりません。
建築基準法では、大規模地震において、地上部分の各階の安全限界変形は、1/75以下と定められていますが、長期優良住宅では1/100以下と、さらに厳しい基準が定められています。
維持管理・更新の容易性
構造躯体と比べて耐用年数が短い内装や設備は、定期的な更新をすることで建物を長期間維持させていくことになります。
そのため、内装や配管の清掃、点検、補修、更新の際に、床、壁、天井などを壊すことなく、容易に行える措置が講じられていなければなりません。
可変性
共同住宅と長屋においては、将来の間取り変更に応じて、配管、配線のために必要な躯体天井高を確保する必要があります。
長期優良住宅が想定する、数世代にわたる建物の維持するうえにおいては、ライフスタイルや設備の仕様も大きく変化することが予測されます。使いやすい住まいを長期間維持していくうえで、水回りなどの設備配管の変更にも対応できる空間の確保が求められているのです。
高齢者対策
共同住宅と長屋においては、将来的のバリアフリー改修に対応できるよう、共用廊下などに必要なスペースが確保されていなければなりません。
この他、共同階段の幅員、勾配、エレベーターの開口部等についても、同様に必要なスペースの確保が求められます。
省エネルギー対策
建物の断熱性を高めることで、冷暖房費用を抑えるための基準です。外気に接している屋根、床や土間、壁や窓などについて、断熱性の数的基準をクリアする必要があります。
また熱が伝わりやすい、窓や玄関などの開口部の面積割合や、結露防止策についても基準が定められています。
居住環境
建物を良好な景観の形成その他の地域におけ��る居住環境の維持及び向上に配慮されたものにする必要があります。
特に、地区計画、景観計画、条例による町並み等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合においては、これらの内容との調和が求められます。
住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模として、一戸建て住宅で75平方メートル以上、共同住宅で55平方メートル以上としなければなりません。
また住戸の1階は、階段を除き40平方メートル以上確保する必要があります。
維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画の策定が必要です。
維持保全計画には、次のような項目を盛り込みます。
- 構造耐力上主要な部分の維持保全計画
- 雨水の侵入を防止する部分の維持保全計画
- 給排水設備について、点検の時期と内容(少なくとも10年ごとに点検を実施すること)
長期優良住宅のメリット
長期優良住宅の認定を受けた住宅は、高品質で快適な環境の住宅に長期間住めるという利点の他に、補助金、住宅ローンの金利引き下げ、税の特例などの措置が受けられます。具体的にどのような利点があるのか紹介していきましょう。
子育てグリーン住宅支援事業の補助金
指定事業者により建設された長期優良住宅では、子育てグリーン住宅支援事業」の補助金を受け取れる可能性があります。
詳細は下記公式サイトでご確認ください。

住宅ローンの金利引き下げ
長期優良住宅は、住宅ローンである「フラット35」の金利が引き下げられます。
フラット35は、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供される、長期固定金利の住宅ローンです。
フラット35で求められている技術基準を満たしたうえで、さらに省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性・耐久性・可変性などの面で一定の技術基準をクリアした場合、「フラット35S」を利用することができます。
長期優良住宅だと「フラット35S」の金利A・Bプランのうち、優遇性の高い金利Aプランが適用され、当初10年間、年0.25%金利が引き下げられます。
また、返済期間が最長50年で全期間固定金利となる「フラット50」も利用することができます。
税の特例措置
長期優良住宅の認定を受けることで、次のような税の特例措置が適用されます。
住宅ローン減税
「住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)」は、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に受けられる所得税と住民税の控除です。13年間にわたって、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が減税されます。
長期優良住宅においては、この控除対象になる借入限度額が優遇されています。
投資型減税
投資型減税は、現金で住宅を購入した人のための制度です。
投資型減税では、長期優良住宅を建てるために性能強化した費用相当額(上限650万円)の10%が、年末の所得税から控除されます。
その年限定の減税制度であり、かつ住宅ローン減税との併用はできません。
登録免許税
法務局で所有権保存登記や所有権移転登記を行う際には、登録免許税がかかります。長期優良住宅では、この登録免許税が次の�ように引き下げられます。
- 保存登記……1.5%⇒0.1%
- 移転登記(戸建て)……0.3%⇒0.2%
- 移転登記(マンション)……0.3%⇒0.1%
不動産取得税
不動産取得税は、家を新築したときや取得したときにかかる税金です。
一般住宅では控除額が1,200万円ですが、長期優良住宅においては1,300万円に引き上げられます。
この軽減措置により、長期優良住宅の不動産取得税は、(固定資産税評価額-1,300万円)×3%となります。
固定資産税
固定資産税は、新築の場合一定期間2分の1の減税措置が適用されます。この適用期間が、次のとおり延長されます。
- 戸建て……3年間(一般住宅)⇒5年間(長期優良住宅)
- マンション……5年間(一般住宅)⇒7年間(長期優良住宅)
地震保険料の割引
長期優良住宅は、所定の確認資料を提出することで、住宅の耐震性に応じて、次のような保険料の割引を受けることができます。
- 耐震等級2……30%
- 耐震等級3……50%
- 品確法に基づく免震建築物……50%
売却に有利
国の認定制度である長期優良住宅が、高品質な家であることが広く知られるようになりました。そのため、自宅を売却する際において、長期優良住宅であることが大きなセールスポイントとなり、一般的な住宅と比べて有利な条件で売却できる可能性があります。
長期優良住宅のデメリット
それでは反対に、長期優良住宅のデメリットを見ていきましょう。
申請費用が発生する
長期優良住宅の認定を受ける際に費用が発生します。
自分で申請することもできますが、審査書類や図面を揃えるために相当の手間がかかります。また一定の専門知識も要するため、困難な作業になることがあります。
ただし、自己申請は専門家に依頼する手数料が削減できるので、費用は5~6万円の範囲で収まります。
ハウスメーカーや工務店などに申請を依頼した場合、手数料が含まれるので20~30万円になります。
工事費が高くなる
長期優良住宅は、高品質の仕様のため、一般の住宅と比べて20~30%割高になります。ただし、ハウスメーカーの場合、標準仕様が長期優良住宅の認定規準に対応している場合が多いため、長期優良住宅でも工事費が変わらないことがあります。
着手までの期間が長くなる
一般的な住宅は、建築確認済証が交付されれば、すぐに着工することができます。しかし、長期優良住宅では、その後さらに長期優良住宅の認定審査を経る必要があるため、工事請負契約締結後から着工までの期間が一般住宅よりも長くなることがあります。
定期点検が必要
長期優良住宅は、建築した後も定期的な点検やメンテナンスを行って、良好な状態を保つ必要があります。
建築前に提出した「維持保全計画書」に基づいて定期点検を行い、その結果修繕が必要と判断されれば実施します。
特に、構造耐力上主要な部分や給排水のための配管設備については、10年以内に一度の点検が必要��になります。また、点検や修繕を実施した際には、その情報を保管しておく義務があります。
これらの点検や維持保全を計画書どおりに実施しないと、長期優良住宅の認定が取り消される可能性があります。
長期優良住宅の認定申請方法
長期優良住宅の認定申請は、次の流れで進めていきます。
- 建築確認申請
- 技術審査の依頼
- 所轄行政庁へ認定申請
また、工事完了後も報告や点検の義務があるのが、長期優良住宅の大きな特徴です。それでは、具体的にどのような手続きを行うのか解説していきましょう。
1:建築確認申請
長期優良住宅の認定申請に先立ち、予定する建築物が建築基準法に適合していることを確認するために、行政もしくは指定確認検査機関に建築確認申請をします。
審査が終了すれば、建築確認済証が交付されます。
なお、建築確認を所轄行政庁に申請する場合は、同時に長期優良住宅の認定申請を行うことができます。
2:技術審査の依頼
建築予定建物が、長期優良住宅の認定基準をクリアしているかについて、登録住宅性能評価機関に技術的審査の依頼をします。
審査終了後、適合証が交付されます。
3:所轄行政庁へ認定申請
所轄行政庁へ次の書類を作成して長期優良住宅認定申請をします。
- 認定申請書
- 設計内容説明書……認定基準に適合している根拠となる設計の内容を説明するための書類です。
- 各種図面・計算書……認定申請をする対象住宅が、申請書に添付された設計内容説明書どおりに設計されていることを確�認するための書類です。
- 所轄行政庁が必要と認める図書……登録住宅性能評価機関の技術審査を予め受けた場合における当該機関が発行する適合書や技術的審査を受けた設計内容説明書などです。
審査完了後、認定通知書が交付されます。これにより、工事を着工することができます。
工事完了後報告
長期優良住宅では、工事完了時には、原則として認定を受けた計画に基づいて工事が完了した旨の報告が必要です。
定期的な点検
住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために、長期優良住宅では、10年以内ごとの定期的な点検が必要です。また地震発生や台風飛来後に随時点検を実施します。
これらの点検の結果を踏まえて、必要に応じて修繕を行います。
まとめ
長期優良住宅は、次の項目について認定基準が定められています。
- 劣化対策
- 耐震性
- 維持管理・更新の容易性
- 可変性
- 高齢者対策
- 省エネルギー対策
- 居住環境
- 住戸面積
- 維持保全計画
これらの事項についてクリアした物件が、長期優良住宅としての認定を受けることができます。
長期優良化住宅の認定を受けると、補助金の交付や住宅ローンの金利引き下げ、さらには税制面の優遇措置を受けることができます。
一方で、工事完了後も、報告や点検の義務があります。煩わしさもありますが、建物を数世代にわたって使用していくために必要な作業だと考えれば、労力以上のメリットがあるといえます。