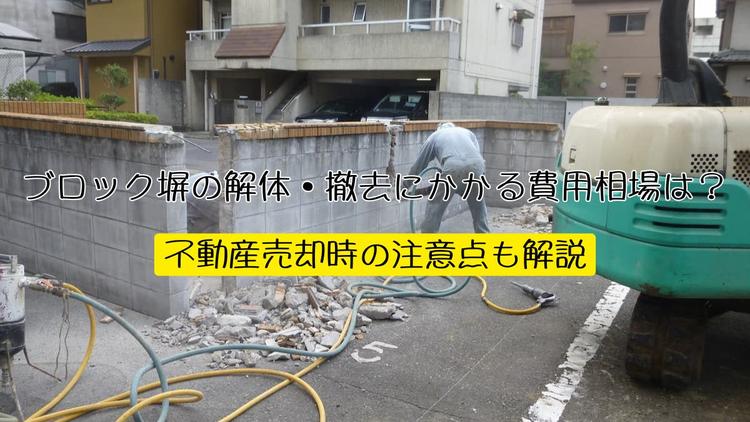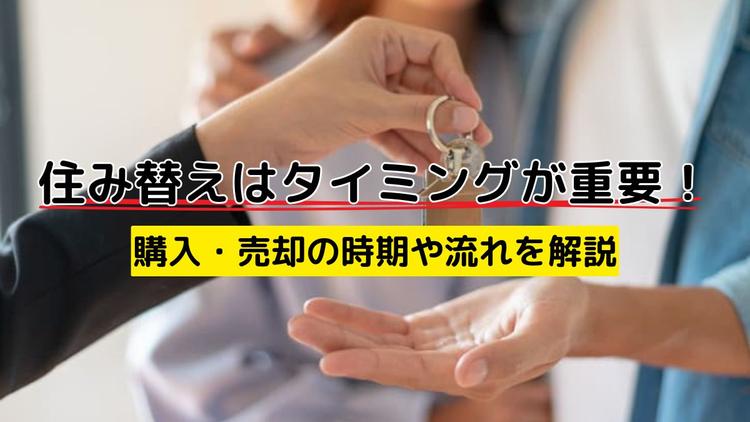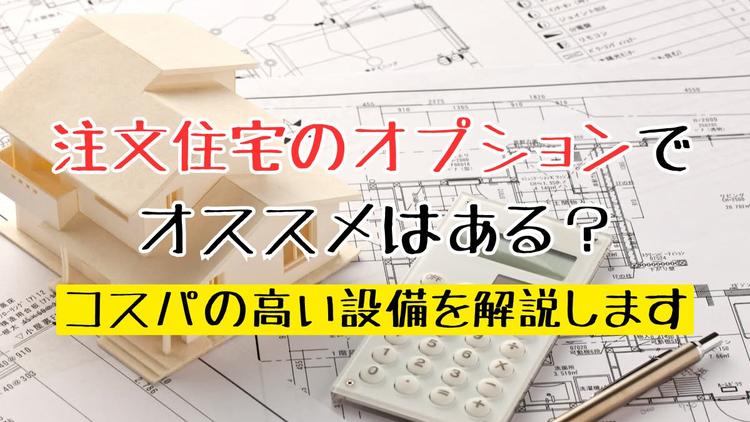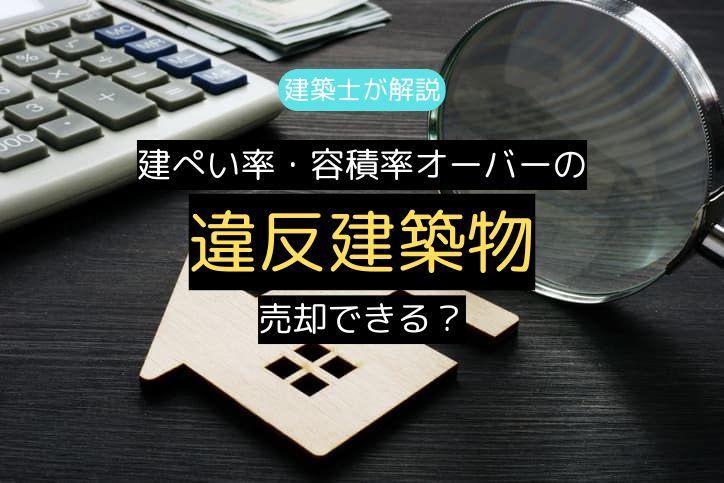私道の持分なしの不動産は、通行に許可が必要などの理由でなかなか売れないものです。
しかし、持分なしでも持分購入といった対策次第では売却できる可能性があります。
この記事では、私道持分なしの不動産が売れない理由や、売るための対策、具体的な売却事例などを分かりやすく解説します。
私道の持分がないのはどんな状態?
私道持分なしとは、敷地に接する道路が私道であり、その私道を利用する権利を持っていない状態です。
私道に複数の土地が接している場合、接する土地の所有者が私道を共有していることがほとんどで、それぞれの所有者が持つ私道の所有権は「私道持分」と呼ばれます。
私道に接する土地や家を所有している場合、不動産と一緒に私道持分も所有しているのが一般的ですが、なかには私道持分がないケースもあるのです。
私道とは
道路には、国や自治体が所有する「公道」と、個人や企業・団体が所有する「私道」の2種類があります。
国道や県道・市道などが公道であり、公道は誰でも利用可能で、管理義務は所有する自治体が負うのが特徴です。
一方、私道は公道以外の個人などが所有している道路を指します。
所有する土地に作られた道路であり、私有地内にあるため、通行には所有者や所有者に許可された人に限定されるなど、制限がかかるのが一般的です。
また、私道の管理責任は所有者にあり、修繕費の負担も所有者となります。
一見すると私道か公道か分からないケースも珍しくありません。
しかし、接する道路が私道か公道かで大きな違いが生まれるので注意が必要です。
どちらか分からないときは、自治体の道路管理課や登記簿謄本、不動産購入時の売買契約書などで調べてみましょう。
また、不動産の売買にあたっては、不動産会社が役所調査を行い、接道状況を確認してくれるケースも多いです。
特に住宅ローンを利用する場合、接道義務を満たしているかが審査に影響するため、事前にしっかり調査されます。
不安な場合は、不動産会社や自治体に相談するとよいでしょう。
私道の種類
建築基準法上の道路のうち、以下の3種類については私道が含まれています。
- 既存道路(42条1項3号)
- 位置指定道路(42条1項5号)
- 2項道路(42条2項)
それぞれ解説します。
既存道路(42条1項3号)
既存道路とは、建築基準法が制定される前からある、幅員4m以上の道路を指します。
ただし、国や自治体が所有する幅員4m以上の道路(公道)は、建築基準法42条1項1号に基づき、既存道路には該当しません。
つまり、既存道路とは、公道を除いた、昔からある幅員4m以上の道路のことです。
また、国や自治体が所有しているケースだけでなく、建築基準法以前に存在していた私道も、既存道路に該当するケースが多いです。
位置指定道路(42条1項5号)
位置指定道路とは、特定行政庁(自治体など)から認定を受けた道路を指します。
幅員は4m以上で、路面を舗装しているなどの一定の条件を満たして設置し、申請することで認定されます。
基本的には、建築基準法第43条の「接道義務」を満たすために設置されるケースが一般的です。
接道義務とは、建築物を建てる際に、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという規定のこと(建築基準法第42条・43条)。
この規定を満たさないと、建築確認が下りず、新たに建物を建てたり増改築をしたりすることができません。
位置指定道路は、私道でありながら接道義務を満たす道路として扱われるため、建築可能な土地にするために設置されることが多いです。
2項道路(42条2項)
2項道路とは、幅員4m未満で特定行政庁に認定を受けた道路を指します。
建築基準法上の道路は幅員4m(一部地域では6m)以上必要のため、4m未満では道路とみなされません。
しかし、一定の条件をクリアした道路であれば、幅員4m未満であっても2項道路として道路に認定されるのです。
このような道路は、建築基準法上の道路ではないものの、道路として使えるため「みなし道路」とも呼ばれます。
なお、前面道路が2項道路の場合、間口(土地の幅)が2m以上あれば、接道義務は満たせます。
しかし、建物を建てる際にはセットバックが必要になります。
セットバックとは、敷地を道路から後退させることで道路の幅員を広げること。
私道持分の種類
私道に接する土地の所有者で私道を共有しているケースでは、私道持分の所有方法に以下の2種類があります。
- 共同所有型
- 分割型(相互持合型)
共同所有型
共同所有型とは、複数人で私道全体の所有権を共有する方法です。
基本的には、私道に面した戸数で等分して、持分を有するケースが多いでしょう。
たとえば、私道に4戸の住宅が接している場合は、それぞれが4分の1ずつ持分を持ちます。
共同型はそれぞれが持分を有するので、通行に他の所有者の許可は必要ありません。
また、維持管理については所有者全員に責任が生じるので、修繕費を持分に応じて按分するのが一般的です。
ただし、掘削工事や全面的な舗装などの変更行為については所有者単独で実施できず、行為に応じて全員または過半数の合意が必要になります。
分割型(相互持合型)
分割型は、私道を所有者の数に分筆し、それぞれが分けられた私道を所有する方法です。
1本の私道をみんなで共有する共同型に対し、分割型では複数の私道が組み合わさって1本の私道になっている形になります。
自分の敷地に面した私道を所有すると他の所有者の通行を妨げる恐れがあるので、敷地に面した私道ではなく、離れた私道を所有するケースが一般的です。
また、分割型では、他人の土地を通行する権利である「通行地役権」が設定されることがほとんどです。
通行地役権があることで、敷地に接する私道を所有していなくても、問題なく通行できます。
しかし、私道の所有権が明確に分かれていることから、通行の仕方や工事などでトラブルになりやすい点には注意しましょう。
私道持分なしの家や土地が売れない理由
私道持分なしの家や土地は、通行や工事に許可が必要など、買主に制限がかかりやすいことから売りにくくなります。
具体的な売れない理由は、以下の4つです。
- 通行するのに所有者の承諾が必要
- 通行料を請求される可能性がある
- ガスや水道の工事で道路を掘削する場合は所有者の承諾や承諾料が必要
- 住宅ローンを組めない可能性がある
それぞれ見ていきましょう。
通行するのに所有者の承諾が必要
自分の敷地に接する私道に所有権がないと、家への出入りは他人の土地を通行する形になります。
私道は基本的に所有者か所有者が許可した人しか利用できないため、通行するためには所有者全員の許可が必要です。
ただし、土地が道路に接していない袋地であれば、道路に出るために土地(私道)を通行する権利が認められています。
また、公道に出るための通行権には、必要最低限の幅など制限があり、自由に通行できないケースが一般的です。
通行料を請求される可能性がある
私道の通行権は所有者が自由に決められるため、通行の承諾にあたり通行料を請求される可能性もあります。
また、通行の承諾は得ても、自動車の通行はダメなど、制限を設けられるケースもあるでしょう。
このように、私道持分がないと通行に許可が必要となり、制限も生まれやすいことから、買主から避けられやすくなります。
ガスや水道の工事で道路を掘削する場合は所有者の承諾や承諾料が必要
ライフライン整備で掘削工事が必要になる場合、トラックの通行や掘削に対して所有者の承諾が必要です。
承諾を得る際に、承諾料を請求されるケースもあるでしょう
承諾が得られないと工事ができなくなってしまいますが、どうしても承諾が得られないときは、裁判手続きで工事を進めることが可能です。
とはいえ、裁判を起こすには手間や費用、時間がかかります。
裁判に発展すれば、隣人との関係性が悪化するリスクもあり、工事できてもわだかまりを抱えての生活になりかねません。
住むための工事を行うために手間やリスクが生じる点も、避けられやすい理由と言えるでしょう。
▼関連記事:私道の通行・掘削承諾書とは
住宅ローンを組めない可能性がある
通行や工事に制限がかかりやすいため、私道持分なしの不動産は金融機関による担保評価が下がりがちです。
担保評価が低くなると、住宅ローンが組めなくなったり、融資額が減額される恐れがあります。
基本的に買主は住宅ローンを利用するケースがほとんどであり、住宅ローンが組めないとなると、資金の都合から不動産の購入を断念されてしまうのです。
私道持分なしの土地や家を売るための対策
私道持分なしの土地や家は売りにくくなりますが、売れないわけではありません。
ただ、売るための工夫は必要になってきます。
ここでは、私道持分なしの不動産を売るための対策として、以下の3つを解説します。
- 私道持分を購入してから売却する
- 通行や工事の承諾料を払ってから売却する
- 買取業者に買い取ってもらう
それぞれ見ていきましょう。
私道持分を購入してから売却する
私道持分は交渉により購入することができます。
持分を所有している人の1人から持分を一部でも買い取れれば、私道持分が生まれ、通行などが可能になります。
共同型の場合は、所有者から持分を一部譲渡してもらって登記を行い、分割型では土地(私道)をさらに分筆して譲渡してもらう形になります。
ただし、分筆の場合は境界確定が必要となり、手間や時間がかかります。
また、共有者と面識がない場合や関係性が悪い場合、購入に応じてくれない可能性もあるので注意しましょう。
通行や工事の承諾料を払ってから売却する
買主が通行や工事の承諾を得る必要があると、手間や費用がかかるため、避けられ��やすくなります。
事前に売主が承諾を得ておくことで、買主は購入後に手間をかける必要がなくなり、売却につながる可能性があるのです。
なお、承諾を得るときには、承諾後のトラブルを避けるために口頭ではなく書面で残すようにしましょう。
書面があれば、買主の安心材料にもなります。
しかし、共有者が多い場合や関係性が悪い場合は、承諾を得るのに手間や時間がかかることに注意しましょう。
買取業者に買い取ってもらう
私道持分や通行承諾を得るのは手間や時間、費用がかかり、関係性によっては実現が難しくなることもあります。
手間や費用をかけずにすぐに売却したいのであれば、買取業者への売却がおすすめです。
とくに、私道持分なしなど訳ありの不動産の取り扱いに慣れている業者であれば、所有者との交渉や土地活用のノウハウを持っているため、私道持分なしでもスムーズに買い取ってくれる可能性があります。
私道持分なしの土地や家を売却できた事例
私道持分なしの土地を買取で売却した事例です。
土地の売却を検討するも私道持分がなく、私道は地主1人が所有しており、所有者と売主はそれほど面識がありませんでした。
このケースでは、売主は早期の売却を希望し、買取を選択しました。
これにより、売主の土地と私道を合わせて再販できる見込み�が立ち、売主の土地が高値での買取となったのです。
買取は、不動産会社との交渉のみで売却できるため、短期間で売却を進められます。
また、私道の所有者との交渉は買取業者に任せられるので、売却後のトラブルを避けやすく、売主にとっては魅力的な方法です。
ただし、買取は査定額が売却額とほぼイコールとなるので、少しでも高値を付ける不動産会社を見つけることが重要です。
とくに、私道持分なしの不動産は売却ノウハウも必要になってくるので、ノウハウがあり信頼できる不動産会社かどうかも見極める必要があります。
不動産会社を選ぶ際には、できるだけ多くの査定を比較し、安心して任せられるかを見極めるようにしましょう。
イエウリでは、仲介だけでなく買取の査定も行っています。
数多くの買取に積極的な不動産会社が参加しているので、ぴったりの不動産会社と出会うことが可能です。
私道持分なしの不動産の売却を検討している方は、まずはイエウリでいくらで売れるかのチェックからスタートしてみてはいかがでしょう。
私道持分なしの土地や家の売却でよくある質問
最後に、私道持分なしの土地や家の売却でよくある質問をみてみましょう・
私道持分なしの土地や家の売却で起こりうるトラブルとは?
私道の所有者と、通行や工事の承諾を得る際に��トラブルが発生しがちです。
また、そのトラブルが要因となり隣人関係が悪化すると、生活しにくくなる恐れもあるでしょう。
トラブルを懸念した買主から避けられやすくなるので注意しましょう。
私道持分なしの土地は再建築できる?
私道持分がなくても、土地が接道義務を満たしていれば再建築可能です。
接道義務では「幅員4m以上の道路に土地が2m以上接する」ことを求めており、私道であっても建築基準法上の道路と認められ間口が確保できれば建築できます。
ただし、私道の持分がない場合は、建築の際に私道の所有者から掘削工事などの許可を得なければならない可能性があります。
私道持分なしの土地や家は自治体に買い取ってもらうことはできる?
私道持分なしの土地を自治体が買い取ってくれるケースはほとんどありません。
近隣に自治体の所有する施設があるなど、土地に十分な活用が期待できる場合は可能性がありますが、基本的には難しいでしょう。
相続した土地であれば「相続土地国家帰属制度」を利用して国に返還することは可能です。
しかし、この制度を利用するにも土地が一定の条件をクリアする必要があるので、事前に条件などを確認しましょう。
まとめ
私道持分がない不動産は、通行や工事に許可が必要など、買主の手間やリスクが生じやすので売れにくくなります。
売却を検討する際には、持分を購入したり、通行や工事の承諾を得ておくなどの対策が重要です。
売却の手間をかけたくない場合や、私道の所有者とトラブルになりたくないといった場合は、買取での売却を視野に入れるとよいでしょう。
買取業者であれば、私道持分がなく通行許可、工事承諾がない不動産であっても、そのままの状態で売却できる可能性があるので、気になる場合は相談をおすすめします。