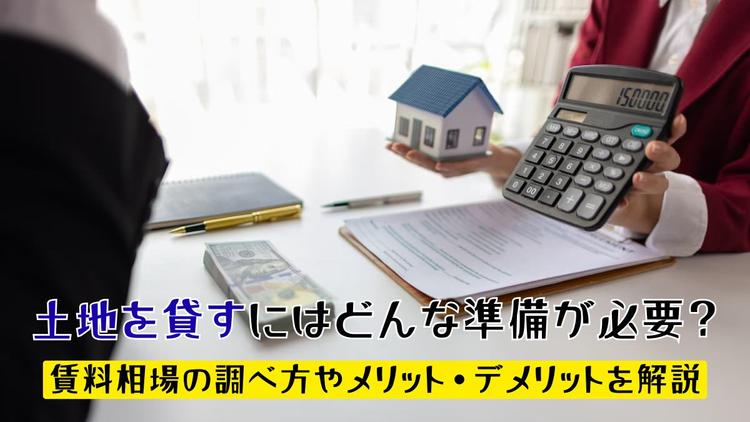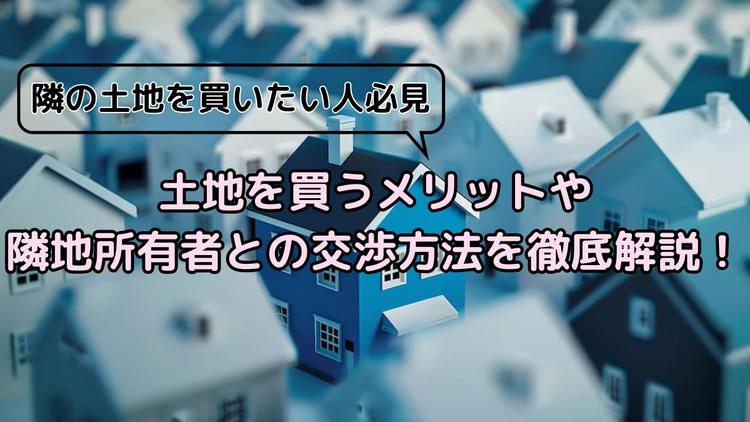土地活用に悩んだら、第三者に貸し出すのも1つの方法です。
土地を貸し出せば毎月賃料を得られる、固定資産税を軽減できるなどのメリットがあります。
しかし、貸し出すことで自分が使えないだけでなく、貸出方法によってはトラブルになるケースもあるので、慎重に準備を進めることが大切です。
この記事では、土地を貸すために押さえておきたい事前準備や、貸し出すメリット・デメリットなどを分かりやすく解説します。
土地を貸す前にやっておくべき事前準備
土地を貸すと決めたら契約方法や賃料など事前に決めておくことが大切です。
ここでは、貸す前にやっておくべき事前準備として以下の3つを解説します。
- 契約の種類を決めておく
- 土地を貸すターゲットを決めておく
- 賃料を決めておく
それぞれ見ていきましょう。
契約の種類を決めておく
土地を貸す際には、地主(貸す人)と借地人(借りる人)で契約を締結することになりますが、契約にはいくつか種類があるので適切な種類を選ぶ必要があります。
賃貸借と使用貸借
まず、賃料を得るか得ないかで契約種類は「賃貸借」か「使用貸借」に分かれます。
賃貸借は、賃料(地代)が発生する契約です。
一方、無償、もしくは著しく低い賃料で貸し出す方法が使用貸借になります。
たとえば、親が子に無償で土地を貸すといった場合は使用貸借契約を結ぶことになります。
家や土地などを無償で貸す場合には、使用貸借契約を結ぶことで、借主の権利が制限されているため将来の返還請求がしやすいといったメリットがある。
使用貸借や賃料が発生しない分、借地人の権利が弱くいつでも契約を解除できるなどのメリットがあります。
その点、賃貸借は借地人の権利が強く、簡単に契約の解除ができません。
使用貸借が結ばれるのは、親子間や資材置き場として無償で貸し出す、すでに貸し出した土地で立ち退きが決まった場合に、立ち退きまでは賃料を免除するといった場合が多いでしょう。
反対に、一般的に第三者に土地を貸し出す際には、地代の発生する賃貸借で契約するケースがほとんどです。
普通借地契約と定期借地契約
また、土地の賃貸借には大きく「普通借地契約」と「定期借地契約」の2種類があります。
普通借地契約と定期借地契約の大きな違いが契約更新の可否です。
普通借地契約では、契約期間終了後に借地人が望めば契約更新できます。
地主側が契約更新を拒絶するには正当事由が必要となり、容易に契約更新拒否ができないのです。
そのため、半永久的に土地が還ってこない可能性もあります。
対して、定期借地契約は契約期間終了後の契約更新はできず、期間終了にともない建物を解体し更地での返還が必要です。
将来的に土地を活用する予定があり一定期間後に確実に返して欲しいなら定期借地契約が適しているでしょう。
しかし、定期借地契約は契約更新できないことから、借主が現れにくく賃料も低く設定するケースが多い点には注意が必要です。
土地を貸し出す目的や、将来の活用見込みに応じて適切な契約種類を選ぶようにしましょう。
土地を貸すターゲットを決めておく
土地を借りてくれる人を探す際に、適切にアピールするためにはターゲットを絞っておくことが大切です。
借りた土地の利用方法としては以下のようなものが考えられます。
- 借地人が建物を建てて住む
- 借地人が店舗や事務所を建てて事業を営む
- 駐車場
- 資材置き場
借地人が居住用として借りることを想定するなら、ターゲットは個人でファミリー層などになります。
一方、事業を営む、資材置き場などであれば法人や個人事業主がターゲットになるで�しょう。
貸し出す方法によって、事前の土地の整備方法や適切なども異なってくるので、ターゲット選定は慎重に行うことが大切です。
ターゲットを決める際には、エリアの需要を考慮して決める必要があります。
適切なターゲット選定に悩む場合は、土地活用が得意な不動産会社などに相談するとよいでしょう。
賃料を決めておく
賃料設定が相場より極端に高いと借り手が現れにくくなります。
反対に低く設定すると貸し出しても収益性が悪くなってしまうので、注意が必要です。
賃料を設定する際には、事前に周囲の賃料相場を調べたうえで適切な賃料を設定することが大切です。
年間賃料の相場は個人用で更地価格の1~3%、事業用で4~5%と言われていますが、立地や契約方法などによって左右されます。
土地の更地価格が3,000万円の場合、以下のようなシミュレーションできます。
- 個人向け(住宅用駐車場など)
年間賃料の目安は更地価格の1〜3%程度→30万円〜90万円/年
→月額に換算すると約2.5万円〜7.5万円 - 事業用(店舗や資材置場など)
年間賃料の目安は更地価格の4〜5%程度→120万円〜150万円/年
→月額に換算すると約10万円〜12.5万円
ただし、最終的な賃料は借地人との交渉で決まるため、値下げ交渉を受ける可能性がある点には注意しましょう。
賃料相場の調べ方は以下で詳しく解説するので参考にしてください。
土地の賃料相場の調べ方
土地の賃料相場を調べる方法としては、以下の3つが挙げられます。
- 不動産ポータルサイ��トで近隣の類似物件を調べる
- 固定資産税から算出する
- 不動産会社に相談する
それぞれ見ていきましょう。
不動産ポータルサイトで近隣の類似物件を調べる
不動産ポータルサイトなどで、近隣の類似物件の賃料を比較して自分の土地の大まかな賃料を把握する方法です。
類似の土地の借地事例をいくつか抽出し単価を求めて、自分の土地の形状や特殊性なども考慮して賃料を計算します。
たとえば、類似物件の賃料平均が1㎡あたり年間5,000円であり、自分の土地が100㎡なら年間の地代は50万円と計算できます。
ただし、近隣の類似物件の賃料を調べたうえで自分の土地に合わせて補正するのは容易ではありません。
賃料は立地や借地人との交渉にも大きく左右されるので、近隣相場はあくまで目安として活用するとよいでしょう。
固定資産税から算出する
シンプルで簡単な方法が、固定資産税と都市計画税から算出する方法です。
一般的には、固定資産税+都市計画税の3~5倍を年間の地代に設定します。
固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は0.3%に設定している自治体がほとんどなので、上記の場合(1.4%+0.3%)×3~5=5.1~8.5%を固定資産税評価額の乗じるとおおよその目安が把握できます。
ただし、地域によっては都市計画税が課税されない、税率が異なるなどで上記とは異なる場合もあります。
また、周囲の賃料相場とかけ離れるケースもあるので、周囲の相場も確認したうえで用いることをおすすめします。
不動産会社に相談する
賃料は立地や土地の形状、用途などさま��ざまな要素に左右されます。
また、地域によっては地域の風習が関係している場合もあるので、相場が把握しにくいものです。
自分の土地にあわせた賃料を把握するなら、不動産会社に相談することで賃料を教えてもらえるケースがあります。
また、不動産会社であれば適切な土地活用方法についてのアドバイスを受けることもできるので、賃料や土地活用に悩んだら相談してみるとよいでしょう。
▼関連記事:土地・空き地を有効活用したい!事例とメリット・デメリットを徹底解説
土地を貸すメリット
ここでは、土地を貸すメリットをみていきましょう。
賃料を得られる
土地を貸すことで毎月地代を得ることが可能です。
土地の賃貸借契約は種類によって契約期間が異なりますが、短くても10年、長ければ50年以上という長期の契約になります。
長期的な安定収入を得られるのは大きなメリットと言えるでしょう。
賃料を得る方法としてはアパートやマンションを建築して運用する方法もありますが、コストがかかり空室リスクもあります。
その点、土地を貸すならコストはほとんどかからず、地代も安定して得ることが可能です。
固定資産税の負担を減らせる
土地は所有していると固定資産税、地域によっては都市計画税も毎年課税されます。
これは土地活用の有無にかかわらず課税されるので、活用しなければ税金だけかかることになります。
土地を貸している場合でも、所有者は地主になるので課税自体が無くなるわけではありません。
しかし、貸していれば地代収入を得られるので、その分で固定資産税・都市計画税を賄うことが可能です。
維持管理にコストがかからなくなる
土地を所有していると、活用しなくても草むしりや掃除など維持管理の手間やコストがかかります。
その点も、貸し出してしまえば維持管理の手間や費用は借地人が負担するので、地主の負担を軽減できます。
相続税評価額を下げられる
相続税評価額とは相続税や贈与税を計算する際の評価額です。
第三者に貸し出している土地は地主が自由に活用できないことから、相続税評価額が下がります。
貸している土地の相続税評価額は以下の計算で求めます。
借地権割合とは、土地の評価額に占める借地権の割合です。
国税庁によって30~90%の10%刻みで設定されており、国税庁のホームページでチェックできます。
仮に更地の価格が2,000万円で借地権割合が60%なら、貸している土地の評価額は2,000万円×(1-60%)=800万円に下がるのです。
相続税評価額が下がれば相続財産が少なくなり、相続税の節税が見込めるでしょう。
将来活用できる
貸している土地の所有権は自分にあるので、将来土地を返してもらい自分で活用することが可能です。
今は活用の予定がない場合でも一定期間だけ貸し出すことでその期間を軽減でき、さらに将来的には自分で活用するといったことができます。
ただし、普通借地契約で貸し出した場合、正当な事由がなければ契約更新を拒否できないため、希望の時期に土地が返還されない恐れがあります。
将来確実に土地を返してもらいたい場合は、定期借地契約を検討するようにしましょう。
土地を貸すデメリット
土地を貸せば賃料を得られるなど魅力はありますが、デメリットもあるので慎重に判断する必要があります。
ここでは、土地を貸すデメリットについてみていきましょう。
十分は収益を得られることは少ない
地代収入は一般的に低く、固定資産税や都市計画税を賄える程度と考えた方がよいでしょう。
そのため、アパートやマンションを建築、駐車場を経営するような土地活用に比べれば、収益性は高くありません。
土地活用で高い収益性を求める場合は、土地の貸し出しは適していないので注意が必要です。
ただし、土地の貸し出しは他の活用方法に比べ初期費用やリスクを抑えられます。
固定資産税分だけ賄えればいいのであれば、土地の貸し出しを検討するとよいでしょう。
契約期間中は土地を自分で活用できない
貸し出している期間は、土地は借地人が利用するので自分の土地であっても好きに活用はできません。
やっぱり自分で使いたい、となっても契約後であれば期間終了まで活用できない点には注意しましょう。
契約期間が長期に渡るケースが多い
土地や建物の賃貸借のルールを定めた借地借家法では、借地契約の契約期間を以下のように定めています。
- 普通借地契約:30年以上
- 定期借地契約(一般定期):50年以上
- 定期借地契約(事業用):10年以上50年未満
- 定期借地契約(建物譲渡特約付き):30年以上
一般的な契約方法である普通借地契約では30年以上の契約期間となり、30年より短い期間を定めても無効になります。
つまり、最低30年は土地が返ってくることはありません。
もっとも短い契約でも10年以上になるので、一度貸し出してしまうと長期間土地が返還されない点には注意しましょう。
契約方法によっては期間満了後に戻ってこないケースがある
前述のとおり、普通借地契約では契約期間が終了しても借地人が望めば契約の更新が可能です。
更新の種類には、「更新請求による更新」「合意による更新」「法定更新」があり、請求や合意がなくても法定更新により土地に建物が存在すれば自動的に契約が更新されます。
一方、地主側から立ち退きを要求するには、原則契約期間終了を待って更新を拒否する必要があります。
ただし、更新を拒否するには正当な事由が必要です。
正当な事由としては、地主が土地を使用する必要性が出たなどがありますが、借地人の事情も考慮されるので必ずしも認められるわけではありません。
また、正当な事由がある場合でも立退料を支払う必要はあるでしょう。
つまり、普通借地契約を一度締結すると、地主側からは土地の返還を求めるのが難しくなるのです。
そのため、いつまでも土地が返ってこないリスクがある点は理解しておきましょう。
▼関連記事:借地の立退料の相場は?拒否された際の対処法や、交渉時のポイントも解説します
土地の不適切な利用や賃料滞納のリスクがある
土地の貸し出しでは、契約時の内容とは異なる利用をされる、賃料を滞納されるなどのトラブルが起こることがあります。
たとえば、駐車場として貸し出したのに勝手に家を建てられて登記されているといった場合では、先述したように建物があることで契約が自動更新される恐れがあるでしょう。
また、賃料の滞納であれば契約違反を理由に契約解除を求めることが可能ですが、催告して裁判手続きを行うなど正式な手順を踏む必要があります。
土地の貸し出しでトラブルに発展すると裁判手続きを行うなど、地主に大きな負担がかかる点には注意しましょう。
土地を貸す前に押さえておきたい注意点
ここでは、土地を貸す前に押さえておきたい注意点として以下の3つを解説します。
- 土地の立地や形状・広さによっては借り手がいないケースがある
- 一度貸した後は値上げが難しい
- 居住以外の利用だと固定資産税が高くなる
それぞれ見ていきましょう。
土地の立地や形状・広さによっては借り手がいないケースがある
土地は貸しに出したら必ず借り手がつくわけではありません。
立地や形状などがニーズに合っていなければ借り手が付かない可能性があります。
借り手が付かなければ固定資産税や維持管理費の負担は続いてしまうので、注意が必要です。
借り手がいない場合でも、ターゲットを変えたり、売却や買取を検討することで土地を手放せる可能性はあります。
まずは、不動産会社に土地活用や売却などを相談してみるとよいでしょう。
▼関連記事:狭い土地はどんな活用方法がある?事例・アイディアを解説します
一度貸した後は値上げが難しい
賃料の値上げ自体は可能ですが、借地人の同意が必要で交渉は難航するのが一般的です。
また、値上げを要求できる要件は借地借家法で以下に定められています。
- 固定資産税・都市計画税などの増減
- 土地価格の上昇・下落
- 近隣相場に対して地代が安すぎる
さらに、値上げできるかは契約内容によっても異なります。
契約書に一定期間値上げしないと定めていれば、値上げはできません。
一度賃料を設定して契約すると値上げが難しくなるので、賃料設定は慎重に行うようにしましょう。
住居以外の利用だと固定資産税が高くなる
土地にかかる固定資産税は、土地に居住用の建物が建っていると最大6分の1に軽減されます。
しかし、居住用の建物が建っていないと軽減の特例が受けられないため、高い税額のままです。
土地を貸し出した後に借地人が家を建てれば、特例が適用でき固定資産税軽減が可能ですが、駐車場など居住用建物を建てる以外の活用となると節税できない点には注意しましょう。
まとめ
土地を貸すことで、長期的に安定した賃料を得られ、維持管理のコストや手間から解放されます。
しかし、土地を貸してしまうと自分で活用できなくなるだけでなく、土地が返ってこない・借地人とトラブルになるといったリスクがある点には注意しましょう。
土地の活用に悩んでいるなら、貸し出すだけでなく売却して手放すのも1つの方法です。
信頼できる不動産会社に土地活用や売却など相談しながら、適切な方法を選ぶとよいでしょう。