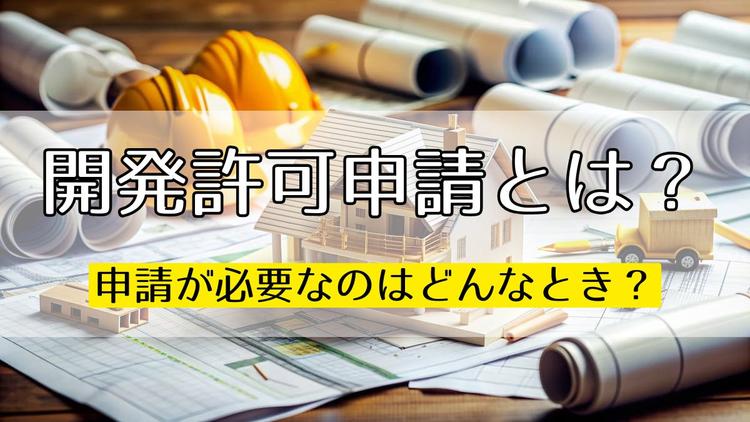土地の売買は、不動産取引の中でも高額かつ慎重な対応が求められる取引です。売主と買主の間で売買契約が締結され、引き渡しが完了すればひとまず手続きは終わったように思えますが、実際にはその後に思わぬトラブルが発覚することもあります。
とりわけ「契約不適合責任」に関するトラブルは、不動産実務において頻繁に問題となります。
この記事では、契約不適合責任とは何かを解説するとともに、土地売買において実際に生じうる典型的な不適合事例を紹介し、売主・買主双方が注意すべきポイントを整理します。
契約不適合責任とは?
土地売買において、買主が土地を取得した後に「想定していた内容と違う」「使用目的を果たせない」などの問題が発覚することがあります。このような場面で問題となるのが「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」です。
土地売買における「不適合」とは何か
土地の場合、建物のように「壊れている」「雨漏りしている」といった物理的な不具合は少ない一方で、次のような「契約内容とのズレ」が問題になることがあります。
- 地中に廃材や古い基礎などの埋設物がある
- 契約書に記載された面積と実際の面積が大きく異なる
- 隣地との境界が不明確、または越境物がある
- 法令により建築ができない土地である(接道義務違反、市街化調整区域など)
これらの問題は、契約内容や重要事項説明と齟齬がある場合、「契約不適合」と判断される可能性があります。
買主がとれる主な対応
契約不適合が認められると、買主は次のような請求をすることができます(民法第562条~566条):
- 追完請求(例:埋設物の撤去や是正工事)
- 代金減額請求(例:面積不足分の価格調整)
- 損害賠償請求(例:使用できないことで発生した損害)
- 契約解除(例:致命的な不適合により取引目的が達成不能)
ただし、契約の解除や損害賠償には一定の要件があり、また、買主は契約不適合を知った時から1年以内に通知しなければなりません(民法第566条)。
予防のためには「契約内容の明確化」が重要
契約不適合責任は、あくまで「契約との不一致」をめぐる問題です。したがって、売主・買主の双方が取引の対象となる土地について、どのような条件・状態で引き渡されるのかを明確に合意し、契約書に記載しておくことが最大の予防策となります。
たとえば、次のような条項を適切に盛り込むことで、紛争リスクを大きく減らすことが可能です。
- 「現況有姿で引き渡す」⇒現在のありのままの状態で引き渡すという意味
- 「地中埋設物については免責とする」
- 「公簿売買とし、面積の増減による代金調整は行わない」
▼関連記事:不動産の現状有姿渡し(現況渡し)とは
土地売買でよくある契約不適合の事例
契約不適合責任が問題となるのは、単なる「瑕疵」だけではなく、売主と買主が合意した内容と、実際に引き渡された土地の状態が異なる場合です。土地売買においては、目に見えない情報や隠れた制約が原因でトラブルに発展することが多くあります。
ここでは、実務でよく見られる代表的な契約不適合の事例を紹介し、それぞれの背景と対応のポイントを解説します。
地中埋設物の存在
土地を整地して建物を建てようとしたところ、地中から古い基礎、瓦礫、浄化槽、コンクリート片、金属くずなどが出てきたという事例は頻発しています。
これらの埋設物は撤去費用や工期の遅延を招き、買主にとっては当初予定していた利用計画が狂う要因となります。とくに「住宅用地」として購入した場合、地中障害物の存在は重大な契約不適合と評価されることが多いです。
たとえ売主が埋設物の存在を「知らなかった」としても責任を問われる可能性があります。そのため、契約書に「現況有姿で引き渡す」「地中埋設物については免責とする」と明記することで、一定の免責効果をもたせることがあります。
▼関連記事:土地の売却時に地中埋設物が見つかったら?撤去の費用や契約不適合責任の注意点を解説
面積の相違(公簿面積と実測面積の食い違い)
売買契約書では登記簿上の「公簿面積」が記載されることが一般的ですが、実際に測量を行ったところ、それよりも狭かった(あるいは広かった)という事例があります。
たとえば、「面積150㎡の土地を購入したつもりだったが��、実際には140㎡しかなかった」といったケースでは、土地の価値に直結するため、買主は代金減額請求や損害賠償を求めることがあります。
- 公簿売買:面積の誤差を前提としており、通常は代金の増減がありません。
- 実測売買:測量後に面積差分に応じて代金調整が行われます。
契約書で売買方式を明確に区別し、買主の理解を得ておくことが重要です。
▼関連記事:土地の公簿売買と実測売買は何が違う?契約時に確認すべきポイントを解説
境界トラブル・越境の存在
境界杭がなかったり、隣地のブロック塀や樹木、建物の一部が越境していることに後から気づくケースも少なくありません。
この場合、土地の面積や使用可能範囲に直接関係するだけでなく、隣地所有者との関係が悪化すれば、買主が不利益を被るおそれがあります。
そのため、引き渡し前に「境界確定測量」を実施することが重要です。越境物があれば、隣地所有者との間で「越境物に関する覚書」を交わしておきましょう。やむを得ず境界未確定のまま売買する場合は、契約書にリスクと免責事項を明記する必要があります。
▼関連記事:土地の境界トラブルでよくある事例と解決策
用途制限や法令上の制限
買主が住宅建築を目的として土地を購入したのに、後から「建築基準法上の接道義務を満たしていない」「市街化調整区域で原則建築不可だった」などの法令上の制限が判明するケースがあります。
この場合、本来の利用目的が��果たせず、買主は重大な損害を被るおそれがあります。売主がこうした制限を認識していた場合はもちろん、知らなかった場合でも「契約目的を達成できない」として契約不適合に該当することがあります。
そのため、売主側は事前に都市計画法・建築基準法・農地法などの確認を行い、制限内容を重要事項説明書で明示する必要があります。接道義務(原則4m以上の公道に2m以上接している必要)や、崖地・土砂災害警戒区域の該当有無も必ずチェックしておきましょう。
▼関連記事:13種類の用途地域の違いは?不動産取引や家を選ぶ際の注意点も解説
地盤の軟弱性・土壌汚染
土地の地盤が極端に弱く、建築に際して地盤改良が必要となるケース、または工場跡地などで土壌汚染が発覚する事例も存在します。
この場合、想定外の追加工事が必要になり、買主は建築費用や設計計画の大幅な見直しを迫られることになります。
そのため、特に工場跡地や埋立地など、過去の利用履歴にリスクがある土地では、あらかじめ地盤調査や土壌汚染調査を行うことが重要です。契約書で「売主は土壌汚染の存在を保証しない」といった免責条項を設けるケースもありますが、一定の説明義務は残ります。
▼関連記事:家を建てる前にチェック!土地の地盤の強さを調べる方法を解説します
売主が注意すべき点
土地の売買において、売主は物件を「契約に適合した状態」で引き渡す義務を負います。これは、契約書に記載された条件に加え、買主が�その土地を本来の目的に使用するうえで必要な基本的性質や品質を満たしているかどうかも含まれます。
ここでは、売主が契約不適合責任を問われないようにするために、契約前・契約時・契約後の各段階で注意すべき点を具体的に解説します。
契約前:事前調査と情報収集をする
土地の売主がまず行うべきは、売却対象となる土地の実態を正確に把握することです。具体的には次のような点を確認しておくことが重要です。
- 境界の確定状況(杭の有無、越境の有無)
- 地中埋設物の存在(過去に建物があった場合は特に要注意)
- 都市計画・建築制限の有無(用途地域、接道義務、建ぺい率など)
- 地盤・土壌の状態(地盤改良の有無、土壌汚染の懸念)
- 法令による制限(農地法、文化財保護法、風致地区等)
これらは将来、買主側がトラブルを主張する原因となり得る事項です。自ら調査が難しい場合は、不動産会社や土地家屋調査士、建築士などの専門家の協力を仰ぐことも検討しましょう。
契約時:説明と書面への明記をする
契約書や重要事項説明書には、把握している事実を正確に記載します。特に次の情報は、契約不適合責任を回避するうえで重要です。
- 面積に関する取り決め(公簿売買か実測売買か)
- 埋設物がある場合はその内容と位置
- 越境や未確定境界がある場合はその状況
- 接道状況、建築可否、用途制限などの法的条件
「知らなかった」では済まされない場合もあるため、知り得る限りの情報は積極的に開示することが望まれます。
▼関連記事:不動産売買の際に重要事項説明書で確認すべき部分は?
免責条項の活用
契約書に「契約不適合責任を免除する」旨を記載することで、一定のリスク回避が可能になります。具体的には次のような事項です。
- 「売主は、土地の現況について契約不適合責任を負わないものとする」
- 「地中埋設物その他隠れた瑕疵が存在する場合でも、売主は責任を負わない」
ただし、これらの免責条項が有効とされるためには、買主に対して事前に重要な情報を誠実に開示していることが前提となります。意図的な情報隠しや、重大な不適合を知っていながら告げなかった場合には、免責条項が無効となる可能性があるため注意が必要です。
契約後:誠実な対応とトラブルの予防をする
契約後、買主が不適合を主張してきた場合には、速やかに状況確認を行い、必要に応じて専門家に相談のうえで誠実に対応する姿勢が求められます。事実関係を否定したり、連絡を無視するなどの対応は、後の損害賠償請求や訴訟リスクを高めます。
媒介業者(仲介会社)が関与している場合は、情報の伝達や説明義務の分担についても確認しておくとよいでしょう。媒介業者が十分な説明を行っていなかった場合でも、売主自身の責任が免除されるとは限らないため、書類の内容には目を通しておきましょう。
買主が注意すべき点
土地の購入は、人生で最も高額な買い物のひとつです。しかし、見た目にはわかりづらい不具合や法的制限が潜んでいることも多く、��安易な判断は後々のトラブルの火種となります。
契約後に「想定していた使い方ができなかった」「余分な費用が発生した」などとならないよう、買主自身も主体的に情報を確認し、納得のいく契約を結ぶことが必要不可欠です。
この章では、買主が土地を購入する際に注意すべき具体的なポイントを段階ごとに解説します。
契約前:現地確認と法的調査を徹底する
書面や不動産会社の説明だけで判断せず、必ず現地に足を運び、実際の土地の状況を確認しましょう。次の点をチェックすることが重要です:
- 敷地内や周辺にゴミ・瓦礫・埋設物の痕跡はないか
- 接道状況(公道か私道か、幅員は十分か)
- 隣地との境界に塀や越境物がないか
- 周辺の騒音・臭気・水はけなどの環境条件
自治体・法務局での調査も忘れずに
土地は外観だけでなく、法的・制度的な制限にも目を向ける必要があります。次に挙げたものは最低限確認すべき情報です。
- 市区町村役場……都市計画区域・用途地域、建築制限、接道義務、災害リスク(土砂災害、液状化など)
- 法務局……登記事項証明書、公図、地積測量図、隣接地との筆界関係
- 不動産会社……売買契約書・重要事項説明書の内容、現況と説明の整合性
契約時:契約書の内容を理解し、免責条項に注意する
土地の面積が売買代金に大きく影響する場合、「公簿売買」か「実測売買」かを明確にする必要があります。
- 公簿売買:登記簿面積を基準とし、多少の差異があっても代金の調整なし
- 実測売買:測量結果に基�づいて実面積を確定し、代金を増減する方式
実測を希望する場合は、売主に測量を依頼するか、買主側で専門家を手配する必要があります。
多くの売買契約では、売主が契約不適合責任を免責される条項が含まれています。たとえば、次のような条文です。
「売主は、契約締結後に判明した地中埋設物その他の瑕疵について、一切の責任を負わない」
この場合、たとえ問題があっても売主に補償を求めることが難しくなります。したがって、契約書の内容をよく理解し、納得できない場合は修正を求めるか、購入を見送る勇気も必要です。
▼関連記事:戸建てや土地を確定測量なしで購入しても大丈夫?リスクや注意点を解説
契約後:問題があれば速やかに通知・対応する
「知った時から1年以内」が時効(民法566条)です。いずれの請求も、買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要があります。この通知を怠ると、法的請求自体ができなくなるため、発見後の対応は迅速に行いましょう。
契約不適合が発覚した場合の対応法
土地の売買後に、地中の埋設物、面積の相違、建築制限の発覚といった契約不適合が見つかった場合、買主は民法に基づき売主に対して一定の法的請求を行うことができます。
ただし、どの請求手段を選ぶかによって結果が大きく異なるため、問題の内容や重要度に応じて、最適な手段を見極めて選択することが重要です。
この章では、契約不適合責任が認められる場合に、買主が取り得る対応方法とその実務的な活用ポイントを解説します。
追完請求(民法562条)
「追完請求」とは、契約内容に適合するように売主に補修や代替措置を求める請求です。土地の場合、建物のように「修理」する対象は少ないですが、次のようなケースでは実際に行われます。
- 地中埋設物の撤去
- 越境物(塀や樹木)の是正
- 境界確定の手続き
▼関連記事:不動産の売買後に追完請求が行われるケースとは?不具合発見後に請求する流れや注意点を解説
代金減額請求(民法563条)
契約不適合の内容が軽微であり、追完の実施が難しい場合には、買主は土地代金の減額を求めることができます。これは、実測面積が不足していた場合など、金額調整による解決に適しています。
主な適用例は次のとおりです。
- 公簿面積と実測面積が大きく異なる
- 建築制限により想定用途での利用が制限される
- 地中障害により造成費用が追加でかかる。
損害賠償請求(民法564条)
契約不適合により、買主が実際に金銭的損害を被った場合には、その損害額について賠償を請求することができます。
主な適用例は次のとおりです。
- 埋設物撤去に数百万円の工事費がかかった
- 建築不可により設計・開発費用が無駄になった
- 取引の遅延により利息や仮住まい費用が生じた
契約解除(民法565条)
契約不適合が重大で、追完や減額では取引の目的を果たせない場合には、契約を解除して代金の返還を求めることができます。
主な適用例は次のとおりです。
- 住宅を建てるつもりだったが、法令制限で建築が不可能だった
- 面積や境界の不確定さが著しく、希望の用途に使えない
- 汚染土壌が見つかり、土地利用が著しく制限された
通知と時効の注意点
民法では、買主が契約不適合を知ったときから1年以内に売主に通知しなければ、追完請求や損害賠償などの権利が消滅すると定められています(民法第566条)。
つまり、「気づいてはいたけれど放置していた」では請求が認められないおそれがあります。
通知は口頭ではなく、内容証明郵便など記録が残る手段で行うことが望ましいです。また、通知には次の要素を含めるようにしてください。
- 契約内容との不一致点(例:地中から廃材が出てきた)
- 問題が発覚した日付と状況
- 希望する対応(追完、減額、解除など)
まとめ
土地の売買では、地中埋設物の存在や面積の相違、法的制限など、契約内容と異なる状態で引き渡されるケースが少なくありません。これらは「契約不適合責任」として、売主が追完、代金減額、損害賠償、あるいは契約解除の責任を問われる可能�性があります。
買主は契約書や現地の確認を徹底し、不適合を知った場合は1年以内に通知する必要があります。一方、売主も事前調査と誠実な説明、免責条項の明示によってトラブルを防ぐことができます。
双方が責任と情報を明確にし、慎重な契約を心がけることが、安心できる不動産取引への第一歩となります。