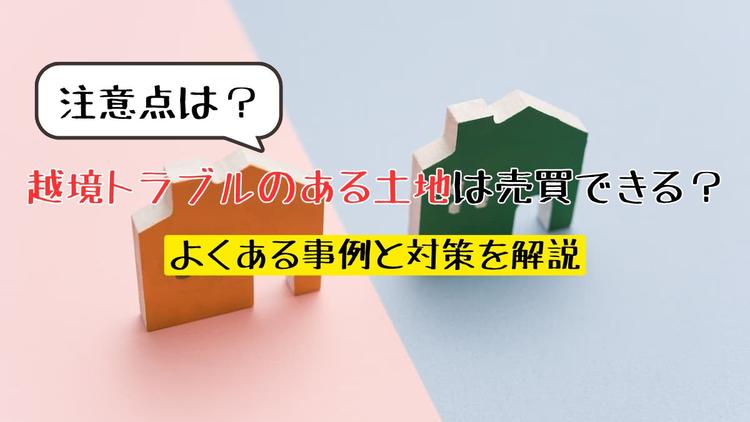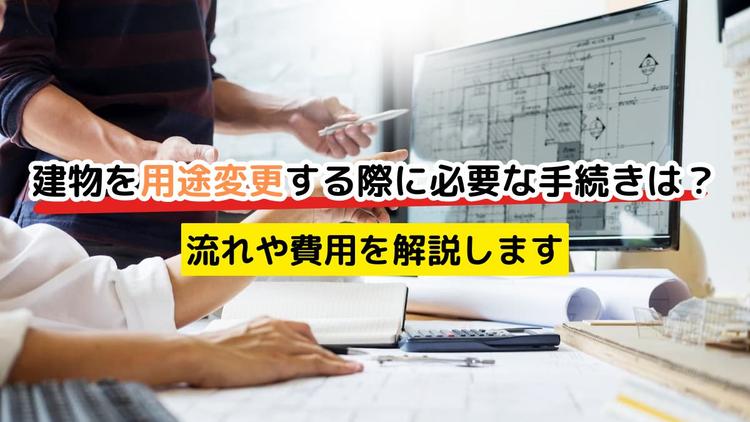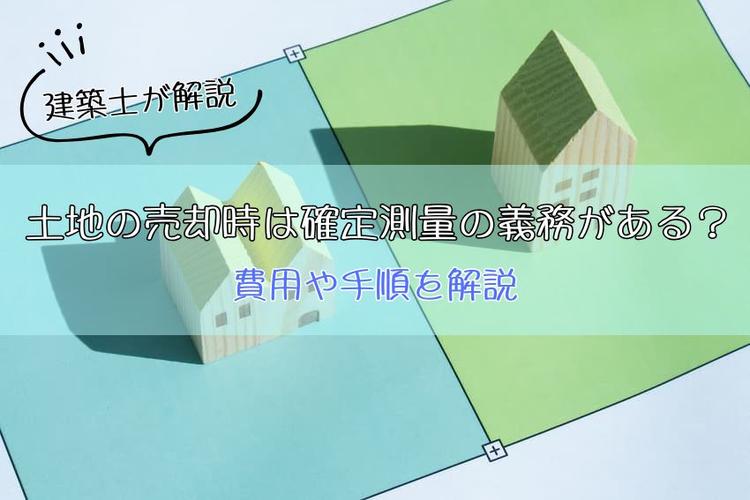土地の売買を検討する際、「隣地との境界に問題があるのでは?」と不安を抱えるケースは少なくありません。
とくに「越境トラブル」が発覚した場合、売買に支障が出ることもあります。
では、越境のある土地は売買はできるのでしょうか?できるとしたら、どのような注意点や手続きが必要なのでしょうか?
この記事では、越境トラブルの典型的な事例と、それに対する実務上の対応策、さらに売主・買主双方が確認すべきポイントを解説します。
「越境トラブル」とは
「越境トラブル」とは、土地や建物の境界を越えて、他人の敷地に物理的または利用上の干渉が生じている状態を指します。
たとえば、建物の屋根や庇(ひさし)、雨樋(あまどい)が隣地にはみ出しているケースや、境界塀・擁壁が一部他人の敷地に設置されているケース、また植栽の枝が越境して伸びているようなケースが典型的です。
越境には大きく分けて、次の2種類があります。
物理的越境……構造物や植物など、物が境界を越えて他人の土地に存在している状態。例としては、屋根の先端やエアコン室外機、給排水管、ブロック塀、木の枝などが含まれます。
利用上の越境(使用越境)……明確な物の越境がなくても、通路や駐車スペースとして隣地を継続的に使用しているなど、事実上の支配・使用が及んでいる状態です。
これらの越境状態は、民法の所有権や通行権、使用権などの法的関係に密接にかかわり、放置しておくと権利侵害やトラブルの原因となります。
とくに、土地や建物の売買を検討する際には、事前に越境の有無を確認し、発見された場合には隣地所有者と適切な合意を形成することが不可欠です。
越境トラブルのある土地は売買できるか
隣地��との境界を越えて建物や設備がはみ出している、いわゆる「越境トラブル」がある土地を売却・購入できるのかは、多くの方が気にするポイントです。
ここでは、法的な前提と実務上の注意点について整理します。
法的には売買することは可能
越境トラブルがある土地であっても、法律上は売買することが可能です。民法上、越境の存在は所有権の移転を妨げる要因とはならず、売主と買主が合意すれば契約は成立します。
ただし、売主が越境の事実を知りながら買主に告げなかった場合、契約不適合責任を問われる可能性があります。たとえば、買主が越境の存在により想定していた利用ができなくなった場合、契約解除や損害賠償の対象となることもあるのです。
そのため、越境の事実を把握している売主は、必ず事前に買主に説明し、売買契約書にもその旨を明記しなければなりません。越境が重大なものであれば、売却前に隣地所有者との間で「越境承諾書」や「覚書」を交わすといった実務対応も求められます。
買主は注意が必要
一方で、買主側にも越境リスクを見極める責任があります。購入を検討する際は、事前に境界確認や測量図の取得を行い、現地を丁寧に確認することが基本です。
また、住宅ローンを利用する場合には、越境の有無が金融機関の担保評価に影響する可能性があるため、注意しなければなりません。越境の状��態によっては、担保価値が低く見積もられ、融資額の減額や、最悪の場合には融資自体が見送られることもあります。
さらに、越境部分が撤去困難な構造物である場合や、隣地所有者との合意が得られない場合には、将来的な紛争や制限のリスクを内包することになります。
買主としては、越境に関する合意書の有無や今後の対応可能性、そしてそれらを前提とした価格評価や契約内容を総合的に判断することが重要です。
よくある越境の事例
越境トラブルは、都市部・地方を問わず、住宅地や古くからの集落などで多く発生しています。
とくに、古い建物や境界が不明確な地域では、無意識のうちに越境状態が生じていることも少なくありません。
ここでは、実務上よく見られる越境の事例を紹介します。
屋根・庇・雨樋の越境
建物の屋根や庇(ひさし)、雨樋(あまどい)が隣地に張り出しているケースは典型的な越境トラブルのひとつです。
建築当初は許容されていたとしても、後に隣地の所有者が変わることで問題化することがあります。
とくに、雨樋から隣地に雨水が落ちる場合は、排水トラブルとして訴訟に発展することもあります。
ブロック塀・擁壁の越境
境界に設置されたブロック塀や擁壁が、本来の敷地を越えて隣地に食い込んでいる事例も多数見られます。
中には、敷地全体を囲う塀が隣地の一部を取り込む形で築かれていることもあります。
塀の老朽化や建て替えを機に、境界の再確認が行われて問題が顕在化することも少なくありません。
樹木の枝や根の越境
樹木の枝が隣地にはみ出している、あるいは根が地中を越えて侵入しているケースもあります。
とくに、枝が日照や落ち葉、害虫��の原因となる場合、隣地所有者の生活に支障を与えることになり、トラブルに発展します。
2023年の民法改正により、越境した枝については隣地所有者が自ら切除できるようになりましたが、円満な関係維持の観点からは事前の協議が望ましいでしょう。
地中埋設物の越境(配管・基礎など)
地中に埋設された給排水管やガス管、建物の基礎などが隣地に越境している場合、表面からは気づきにくく、解体や改築時に発覚することがよくあります。
これらは撤去や移設が困難なため、事前に隣地所有者との合意形成や覚書の取り交わしが重要になります。
通路や駐車スペースの越境使用
敷地内の一部が実質的に隣地にまたがって使用されているケースもあります。
たとえば、玄関までの通路の一部や駐車場の一角が隣地にかかっている場合、長年の慣習として認識されていても、法的には越境使用とみなされる可能性があります。
無断使用であれば、不法行為に該当する恐れもあるため注意が必要です。
越境トラブルがある土地を売却する際の注意点
越境トラブルがある土地であっても、適切な対応を取れば売却は可能です。
しかし、越境の事実を放置したまま売却を進めると、契約後にトラブルに発展するリスクが高まります。
ここでは、売主として押さえて�おくべき実務上の注意点を解説します。
越境の有無を事前に調査する
売却を検討する段階で、現地確認に加えて、測量図や登記簿、隣接地との境界資料を確認しましょう。
とくに、精度の高い「確定測量図」がある場合は、境界位置が明確であるため、越境の有無が判断しやすくなります。
可能であれば、隣地所有者立ち会いのもとで境界確定測量を行い、境界を法的に確定させておくと、将来的なトラブルの予防につながります。
越境状態の解消または整理を検討する
越境の程度や内容によっては、売却前に次のような対応を検討します。
- 越境物の撤去・移設……越境している雨樋や植栽の剪定など
- 隣地所有者との合意形成……越境を容認してもらう覚書や承諾書の作成
これらの対応をとっておくことで、買主側の不安や金融機関の担保評価に対する懸念を払拭し、スムーズな売却につながります。
契約書に越境に関する特約を設ける
売買契約を締結する際には、越境に関する事実とその取り扱いについて、契約書に明確な特約を設けておくことが不可欠です。
たとえば、次のような条項が考えられます。
- 現在の越境状態に��ついて売主が説明し、買主がそれを承諾して購入すること
- 売主が越境状態に起因する責任を負わないこと(契約不適合責任の免除)
- 買主が将来的に隣地所有者との関係において越境の是正を行う場合、その責任を買主が引き継ぐこと
こうした特約は、売主・買主双方のリスク認識を一致させ、将来的な紛争を回避するための重要な手段です。
売却価格への反映を検討する
越境状態が買主にとって一定の負担や制限となる場合は、売却価格の調整も実務的な対応のひとつです。
あらかじめ越境があることを告知し、値引きするなどの対応を行うことで、買主の納得感が得やすくなり、契約成立に向けて前向きな交渉が可能になります。
越境のある土地を買う際の注意点
越境トラブルのある土地は、価格が相場より安く設定されていることもあり、魅力的に映る場合があります。
しかし、購入後に隣地との紛争や権利制限に直面する可能性もあるため、買主としては慎重な調査と判断が重要です。
ここでは、越境のある土地を購入する際に注意すべきポイントを整理します。
越境の有無と内容を必ず確認する
購入を検討する際には、まず現地の目視確認と境界資料の収集が不可欠です。境界標や測量図(現況測量図・確定測量図な�ど)をもとに、建物・塀・植栽・設備などが境界を越えていないか確認しましょう。
また、売主側が越境の存在を把握している場合は、重要事項説明書や売買契約書に記載されているかを確認し、記載が不十分であれば追加の説明を求めましょう。
越境に関する書面の有無を確認する
越境が判明している場合でも、隣地所有者と合意が形成されていれば、将来的なトラブルのリスクは大幅に軽減されます。次のような書面があるかどうかを確認しましょう。
- 越境承諾書……隣地所有者が現況の越境を認める文書
- 覚書・協定書……将来の移設義務、使用条件、損害責任などを明文化した合意書
- 地役権設定契約書……通行や配管など、越境状態を法律上の権利として明確にしたもの
これらの文書がない場合、越境に関する権利関係が曖昧となり、将来的な是正要求や撤去請求のリスクを抱えることになります。
融資(住宅ローン)への影響を確認する
越境のある土地を購入する際には、金融機関の融資審査にも注意が必要です。
物件に越境があると、担保評価に影響し、次のような対応をとられることがあります。
- 融資額の減額
- 越境是正を条件とした融資
- 担保価値が低いとして融資そのものが不可
特に建物の一部が越境しているようなケースでは、再建築の可能性にも制限が生じるため、評価が厳しくなる傾向にあります。事前に銀行に状況を説明し、必要書類や代替案を用意しておくことが重要です。
越境トラブルを予防するための対策
越境トラブルは一度発生すると、隣地所有者との関係悪化や売買・建て替えの妨げになるなど、長期的な問題に発展するおそれがあります。
したがって、日頃からの予防的対応が何よりも重要です。
この章では、越境トラブルを未然に防ぐために有効な対策を紹介します。
建築・リフォーム時には境界を正確に確認する
新築や増改築を行う際には、境界の正確な把握が不可欠です。境界標が設置されていない、または不明確な場合は、土地家屋調査士などの専門家による測量を依頼し、境界を明確にしておくことが推奨されます。
また、建築設計においては、構造物や設備(屋根・庇・雨樋・塀・エアコン室外機など)を敷地内に収めるよう十分な余裕を持たせることが基本です。隣地との離隔距離(民法第234条)や建築基準法の規定にも留意しましょう。
隣地との関係性を良好に保つ
越境問題の多くは、隣地所有者との関係性に起因します。日頃から挨拶や情報共有を行い、信頼関係を築いておくことで、万一のトラブル発生時も穏便に話し合いが進めやすくなります。
たとえば、植栽の管理やブロック塀の修繕時など、境界にかかわる行為を行う際には事前に声をかけることで、誤解や感情的な対立を避けることができるでしょう。
境界を明示する措置を講じる
境界をめぐるトラブルは、物理的な目印がないことで起こりやすくなります。
トラブルを未然に防ぐためには、以下のような境界の明示が有効です。
- 境界標(杭・鋲・プレートなど)の設置
- 確定測量図や筆界確認書の作成・保管
- 境界ブロックや目隠しフェンスの設置(隣地了承のもと)
とくに、相続や売却の予定がある土地については、法的に有効な境界資料を整備しておくことで、将来的なトラブル回避にもつながります。
隣地所有者立ち合いの上で作成した確定測量図があれば、相続やその後の売買をスムーズに進められる。
越境の可能性がある場合は書面で合意を交わす
すでに軽微な越境が生じている、あるいは越境の可能性がある場合には、隣地所有者との間で覚書や承諾書を交わしておくことが重要です。口頭での合意だけでは、所有者が代替わりした際に無効とされるリスクがあります。
たとえば、次のような内容を明記した書面を作成しておくとよいでしょう。
- 現在の越境状態をお互いが確認・了承していること
- 今後の是正義務の有無
- 将来的に問題が発生した場合の責任分担
▼関連記事:【建築士が解説】土地の売却時は確定測量の義務がある?費用や手順を解説
まとめ
越境トラブルのある土地であっても、法的には売買が可能です。ただし、越境の内容によっては、契約不適合責任や将来的な紛争のリスクが生じるため、売主・買主ともに慎重な対応が求められます。
売主は、越境の有無を事前に調査し、必要に応じて隣地所有者と合意形成を行うことで、リスクの整理と買主の安心感につながります。越境承諾書や覚書の作成、契約書への特約明記は、円滑な取引に不可欠です。
一方、買主は、購入前に境界や��現況を十分に確認し、越境部分の性質や解消の可能性を把握したうえで購入判断を行うべきです。特に住宅ローンを利用する場合は、金融機関による担保評価への影響も念頭に置く必要があります。
また、越境トラブルを未然に防ぐには、建築・リフォーム時の配慮や境界確認、隣地との良好な関係維持が鍵となります。トラブルが発生した場合でも、冷静な協議と書面による記録が、長期的な安心につながります。
不動産取引において境界と越境は極めて重要な論点です。実務と法の両面を意識した適切な対策を講じ、将来にわたって安心できる土地利用を目指しましょう。