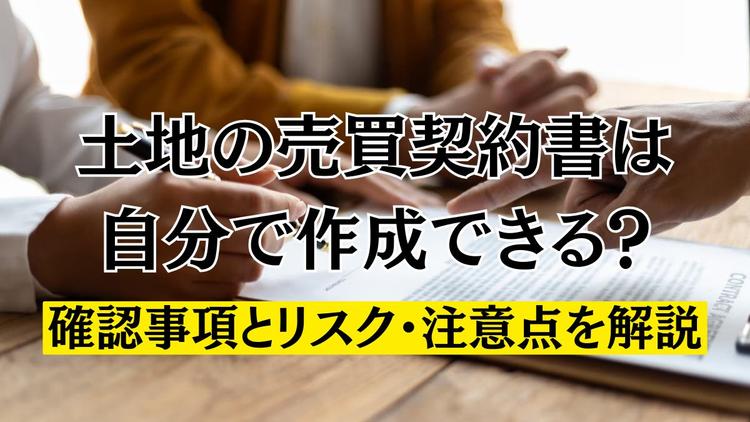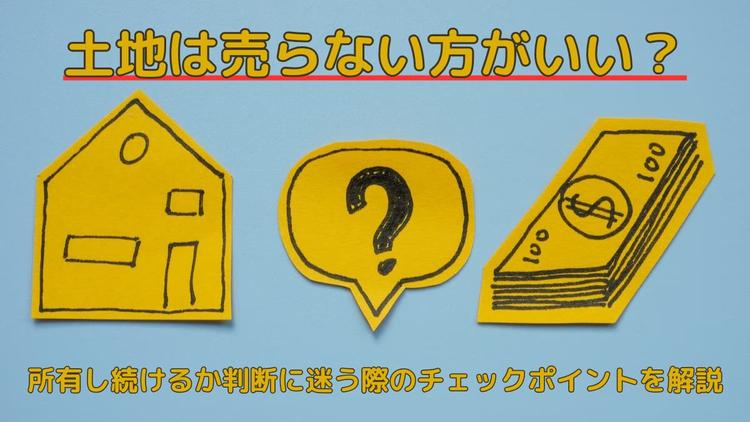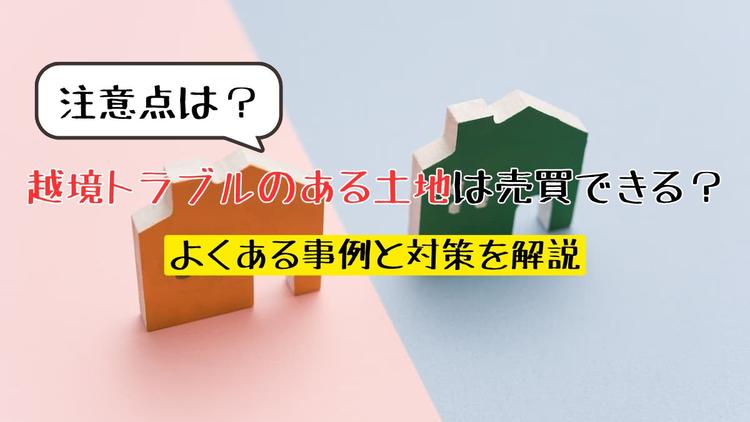不動産会社を通さずに土地の売買を行うと、売買契約書は自分で作成する必要があります。
しかし、不動産取引において売買契約書は重要な書類であり、専門知識なしで作成するとトラブルのもとになる可能性があります。
自分で作成する際には、リスクや確認ポイントを押さえたうえで、慎重に作成しましょう。
この記事では、土地の売買契約書を自分で作成するメリットやリスク、確認事項から、自分で作成が難しい場合の対処法まで分かりやすく解説します。
土地の売買契約書は自分で作成してもいい?
土地の売買契約書は、自分で作成することも可能です。
そもそも、土地の売買は売主と買主の合意で成立し、売買契約書がなくても問題ありません。
しかし、土地の売買は高額な取引になりトラブルが起きやすいので、トラブルから身を守るためにも契約書が欠かせないのです。
とはいえ、自分で売買契約書を作成するケースはそう多くはありません。
土地の売買方法には「仲介」「買取」「個人間売買」の3種類があり、自分で作成が必要になるケースは個人間売買です。
仲介や買取であれば不動産会社が作成する
仲介とは、売主と買主の間に不動産会社が入る売買方法です。
売主と契約した不動産会社が広告などで買主を探し、売買契約を成立させます。
一方、買取とは不動産会社に直接不動産を売却する方法です。
この場合、不動産会社の立場は仲介ではなく買主になります。
仲介・買取とも不動産会社が関わるので、契約書は不動産会社が作成してくれます。
仲介の場合は売主側の不動産会社が作成し、買主側の不動産会社が確認後、売主・買主が売買契約時にサインするのが一般的です。
買取では、不動産会社との売買契約成立後に条件に基づいて不動産会社が作成し、売主がサインして契約が締結します。
不動産の取引ルールを定めた宅地建物取引業法では、売買契約成立時に不動産会社による契約書の��交付を義務付けており、違反するとペナルティが科せられます。
そのため、原則として不動産会社を介した売買契約であれば、売主・買主が契約書を作成する必要はありません。
個人間売買であれば自分で作成するケースもある
個人間売買とは、不動産会社を挟まずに売主と買主が直接契約する方法です。
親子間や知人間などで土地売買するケースでは、個人間売買は珍しくありません。
個人間売買では、不動産会社が関わらないので自分で契約書を作成する必要があります。
売主・買主どちらが作成するかは話し合いで決めることになりますが、一般的には売主が作成するケースが多いでしょう。
また、前述のとおり契約書がなくても売買は有効となるため、親しい間柄であれば契約書を省くケースもあります。
しかし、契約書がなければ売主と買主の認識違いで売買後にトラブルになりやすく、万が一トラブルになっても証拠となる契約書がないことで解決が難しくなります。
そのため、個人間売買であっても契約書を取り交わすことが大切です。
土地の売買契約書を自分で作成するメリット
土地の売買契約書を自分で作成するメリットとしては、仲介手数料が不要という点が挙げられます。
仲介手数料とは、仲介で不動産を売買した際に不動産会社に支払う手数料です。
仲介手数料は、法律により上限が以下のように定められています。
| 売買代金 | 計算式 |
| 200万円以下 | 売買代金×5%+消費税 |
| 200万円超400万円以下 | 売買代金×4%+2万円+消費税 |
| 400万円超 | 売買代金×3%+6万円+消費税 |
たとえば、2,000万円で売却した場合、仲介手数料は2,000万円×3%+6万円=66万円(税抜)となり、売主・買主それぞれが支払います。
しかし、売買契約書を自分で作成する=個人間売買であれば、仲介ではないので仲介手数料は発生しません。
仲介手数料は売買コストの中でも高額になりがちなので、発生しないメリットは大きいでしょう。
また、個人間売買なら不動産会社を挟まずに直接売買交渉を進められるので、スピーディーで柔軟な契約ができる点もメリットと言えます。
土地の売買契約を自分で作成するリスク・注意点
売買契約書は自分でも作成できますが、自分での作成にはリスクや注意点があります。
ここでは、自分で作成するリスク・注意点として以下の3つを解説します。
- 売買契約書の作成には専門知識が求められる
- 売却後にトラブルに発展する可能性が高くなる
- 住宅ローンを利用できなくなる
それぞれ見ていきましょう。
売買契約書の作成には専門知識が求められる
不動産売買契約書には聞きなれない専門用語が多く、不動産の知識なしで全て理解して作成するのは容易ではありません。
インターネット上にテンプレートは提供されていますが、そのまま利用するのはおすすめできません。
不動産会社は契約内容に合わせるだけでなく、契約後に想定されるトラブルまで見越して、契約ごとに適切な内容で契約書を作成します。
それを自分で作成する必要があるので、テンプレートを利用するにしても内容をすべて読み解いたうえで適切な修正が必要になってくるのです。
また、不動産取引に関わる法律は適宜改定されており、テンプレートによっては、現行に適していないケースもあるので注意が必要です。
正しく作成するには、専門知識を調べながら慎重に作成する必要があり、手間や時間がかかることも覚えておきましょう。
売却後にトラブルに発展する可能性が高くなる
契約書の内容に漏れやミスがあれば、そのことが原因となりトラブルに発展しかねません。
たとえば、土地売買では以下のようなトラブルが考えられます。
- 契約書に記載された面積と実際の面積が異なった
- 契約後に契約書に記載のない地中埋設物や土壌汚染が見つかった
- 近隣トラブルがある土地だと契約書に記載していなかった
契約書は、契約内容や土地の状態を漏れなく正しく記載する必要があります。
また、万が一トラブルに発展した場合に備えて、違約金や解除条件などの対応も記載しているものです。
専門知識がないまま作成すると、必要な項目に漏れが生じやすいので注意しましょう。
住宅ローンを利用できなくなる
土地の売買契約書を自分で作成した場合、基本的に買主は住宅ローンを利用できません。
住宅ローンを利用するには、不動産会社が作成した売買契約書と重要事項説明書の提出が必須となるケースがほとんどです。
土地とはいえ、現金一括で購入できるケースはそう多くはありません。
また、仮に親子間だからといって相場よりも極端に安値にすると、みなし贈与として贈与税の対象となる可能性がある点にも注意が必要です。
買主が住宅ローンの利用を前提としているなら、仲介を検討することをおすすめします。
▼関連記事:不動産会社を介さない個人間売買の注意点
土地の売買契約書を自分で作成する場合に事前に話し合うべき確認事項
自分で売買契約書を作成する場合、必要な内容を漏れなく記載することが重要です。
ここでは、作成前に相手方と話し合い決めておくべき項目をいくつか紹介します。
取引価格
売買価格は、売主と買主の合意で成立します。
いくらで売買するのかだけでなく、手付金をいくらにするのかまで話し合って決めましょう。
手付金とは、売買契約時に買主から売主に対して支払われるお金で、一般的には売買代金の10%ほどが目安とされています。
また、手付金には解約手付の性質があり、買主は手付金を放棄することで、売主は受け取った手付金の2倍額の支払いで、それぞれ契約を解除できます。
個人間売買では、合意のうえで手付金を0円にすることも可能です。
しかし、売買の意志を明確にし、安易な契約解除を防ぐ意味でも、一定の手付金を設けることを検討するとよいでしょう。
決済のタイミング
取引価格の額だけでなく、支払い期日や方法も明確にしておくことが重要です。
一般的には、売買契約後の引き渡し時に銀行振込で支払うケースが多いでしょう。
その際、振込手数料がかかる場合は、売主・買主のどちらが負担するかまで決めておくことが大切です。
また、分割で支払��う場合は、各支払期日や金額を明確にし、お互いが認識を一致させておく必要があります。
不動産の名義人
不動産は、登記簿上の所有者でなければ売却できません。
たとえ親子であっても、親の土地を子どもが勝手に売却することはできないのです。
そのため、売主が本当に名義人であるかどうかを事前に確認しておく必要があります。
名義人は、登記簿を確認すれば分かるので、登記簿を取得したり、売主が所有する権利済証(所有権を証明する書類)をチェックしてみるとよいでしょう。
また、売買後は名義人を売主から買主に移転することになるので、移転時期についても明確な期日を決めておく必要があります。
所有権移転の期日に決まりはありませんが、一般的には決済・引き渡しと同日に行われることが多いです。
不随する設備の状態
土地と一緒に建物も売買する場合は、付随する設備の有無や状態について、売主・買主で認識を一致させておく必要があります。
「エアコンがあると思ったのに引き渡し時に撤去されていた」「設備が故障していた」などでトラブルになるケースは珍しくありません。
不随設備については、売主が設備の有無や状態を記載した「付帯設備表」を作成し、買主と共有しておきましょう。
事前の整地等の有無
更地や建物を解体後に引き渡す場合、どのような状態で引き渡すのかを事前に明確にしておくことが大切です。
とくに、解体後に引き渡すケースでは、解体の範囲や整地作業についてトラブルになることがあります。
- 基礎や浄化槽の撤去が不完全だった
→更地として売買契約を結んだにもかかわらず、建物の基礎や地中埋設物(古い配管、浄化槽など)が残っていたため再度工事を実施する必要があり、費用を売主・買主のどちらが負担するかで揉めた。 - 残置物が放置された
→建物の内部や敷地内に古い家具や廃材が残っており、「撤去費用を誰が負担するのか」で揉めた。 - 地面が不自然に傾いていた/整地が不十分だった
→解体後の整地が雑で、土地がでこぼこしていたり、水はけが悪い状態で引き渡されたため、買主が不満を抱くケース。 - 越境物の対応が不明確だった
→隣地との境界にあるブロック塀や樹木などが解体後も残され、越境の解消についてトラブルに発展。
引き渡し時の条件についても、事前に売主・買主の認識を一致させておきましょう。
契約不適合責任の期間
契約不適合責任とは、契約書に記載のない不具合が見つかった場合に、売主が問われる責任です。
土地売買では、たとえば告知していない土壌汚染や地中埋設物などの問題が後から発覚した場合に、売主が責任を問われることがあります。
契約不適合責任は、引き渡し後ずっと追及できるわけではなく、一定の期間が設けられています。そのため、責任追及の期限についても明確にしておきましょう。
一般的には引き渡し後3ヵ月程度が多いですが、売主と買主の合意があれば、それより短くしたり、免責にしたりしても問題ありません。
固定資産税分担金の取り扱い
土地に課される「固定資産税」は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となり、その年の納税義務は売主が負います。
しかし、それでは売主の税負担が大きいため、通常は所有期間に応じて売主と買主で按分するのが一般的です。
たとえば、5月1日に引き渡すなら、1月1日から4月30日までの分を売主が負担し、5月31日から12月31日までを買主が負担することになります。この場合、決済時に買主が自分の負担分を売主に支払うことになります。
そのため、どのように按分するかを事前に明確にしておきましょう。
なお、土地によっては固定資産税だけでなく都市計画税も課されることがあるため、その場合についても話し合っておく必要があります。
所有権移転登記費用をどちらが負担するかの確認
売却後に売主から買主に所有権を移転する登記を、「所有権移転登記」と呼びます。
売買での所有権移転登記時には、不動産評価額×2%の登録免許税が必要です。
また、司法書士に登記手続きを依頼する場合は、別途司法書士報酬も発生するので、どちらがその費用を負担するかをあらかじめ決めておきましょう。
一般的に、所有権移転登記は買主が負担するケースが多いですが、話し合いによっては売主が負担するケースもあります。
土地の売買契約書の作成が難しい場合はどうすればいい?
土地の売買契約書の作成は、専門知識が必要なうえ手間や時間がかかり、自分で作成するにはハードルが高くなります。
また、トラブルのリスクもあるので、基本的には自分での作成はおすすめできません。
自分での作成が難しい場合や、トラブルを避けたいといった場合は、以下の方法を検討するとよいでしょう。
- 不動産会社に作成を依頼する
- 司法書士に作成を依頼する
- 仲介を検討する
- 買取を検討する
それぞれ解説します。
不動産会社に作成を依頼する
不動産取引のプロである不動産会社であれば、契約内容に合わせた適切な売買契約書の作成が可能です。
ただし、不動産会社に依頼する場合、仲介を含めた契約になるケースが多く、契約書の作成のみでは対応していない会社も少なくありません。
そのため、事前に契約書の作成のみ依頼できるかを確認することが必要です。
また、依頼できる場合でも、仲介手数料などの費用に関するトラブルが発生する恐れもあるので、費用の詳細についてもしっかり確認しましょう。
司法書士に作成を依頼する
法的な文章の作成を専門としている司法書士にも、売買契約書の作成依頼は可能です。
また、司法書士は登記手続き代行もできるので、所有権移転登記の手続きまであわせて依頼できます。
仲介を検討する
すでに売却先が決まっている場合でも、不動産会社に仲介を依頼することで、契約書作成まで行ってくれます。
また、親しい間柄での個人間売買では、ルールがあいまいになりやすく、トラブルに発展するリスクがあります。
そのため、間に不動産会社を挟むことで、契約内容が明確になり、トラブルを避けやすくなるでしょう。
買取を検討する
売却先が決まっていない場合は、買取を選択する方法もあります。
買取であれば、不動産会社が買主となり、契約書を作成してくれるので、自分で作成する必要はありません。
また、仲介とは異なり、広告を出して買主を探す必要がないため、短期間で売却できる点もメリットです。
さらに、仲介手数料が不要で、契約不適合責任も基本的に免責になるため、売却後のトラブルを避けやすくなるでしょう。
ただし、不動産会社が買取した後に再販売する際のコストや利益を差し��引いた金額で売買されるため、仲介よりも価格が安くなる点はデメリットです。
土地の売買契約書を自分で作成する際によくある質問
最後に、土地の売買契約書を自分で作成する際によくある質問をみていきましょう。
雛形やテンプレートはある?
売買契約書の雛形やテンプレートは、インターネットで検索すれば見つけられます。
ただし、雛形をそのまま利用するのではなく、内容をよく理解して契約内容に合わせて修正する必要がある点には注意しましょう。
また、雛形を提供しているサイトの信頼性も確認することをおすすめします。
登記を自分で済ませることはできる?
所有権移転登記は、自分で行うことも可能です。
必要書類を揃えて、不動産を管轄する法務局に提出すれば手続きできます。
ただし、契約書の作成や登記をすべて専門家を介さずに行うと、ミスが起きやすく、トラブルに発展する可能性が高くなります。
そのため、基本的には契約書作成や登記手続きは、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
まとめ
土地を個人間売買で取引する際、契約書は自分で作成することになります。
作成する際には、売主・買主で事前に売買条件をしっかり話し合い、合意した内容を契約書に漏れなく記載しましょう。
しかし、不動産売買契約書は不動産取引の専門的な知識が必要となり、漏れやミスがあると大きなトラブルになりかねません。
たとえ親族間であっても、大きなお金の動く土地取引はトラブルに発展しやすいものです。
個人間売買するケースでも、仲介の段階から不動産会社のサポートを得ることで、トラブルのない売却を目指せるでしょう。