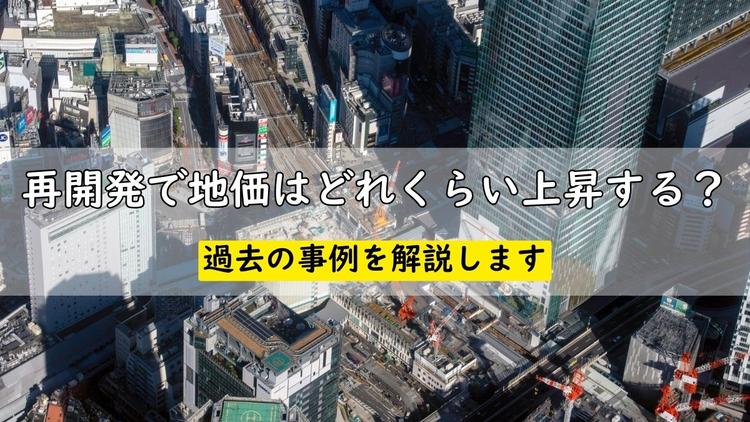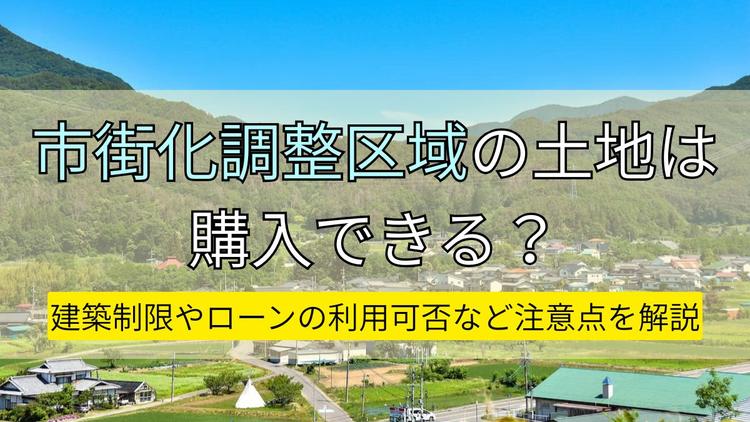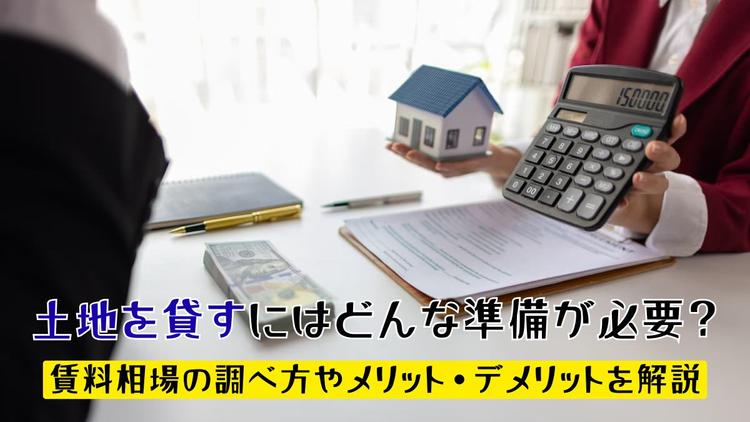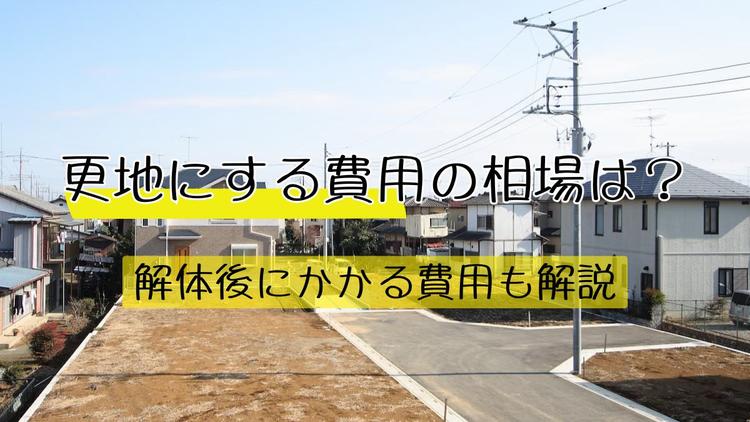地価の上昇は不動産売買にも大きく影響するので気になる方もいるでしょう。
再開発のあるエリアは利便性が上がり、地価の上昇が見込まれます。
では、実際どれくらい上昇するのでしょうか。
この記事では、再開発で地価が上昇した過去の事例や、上昇する理由などを分かりやすく解説します。
地価が上昇する代表的な再開発とは?
再開発とは、時代に合わせて街や建造物などを改修し、機能性や居住性を向上させることです。
企業や団体・自治体などを事業主として、都市計画法に基づき長期間かけて計画的に行われます。
再開発にも、民間ビルの建て替えといった小規模なものから区画一体の取り壊しをともなる大規模なものまで、さまざまな種類があるのです。
規模やエリアによって地価上昇への影響は異なりますが、地価上昇につながりやすい代表的な再開発には以下が挙げられます。
- 大規模な再開発計画
- 新線・延伸の計画
- 新駅の計画
それぞれ見ていきましょう。
大規模な再開発計画
街全体・駅周辺といった地域一帯で行われる大規模な再開発は、地価上昇が期待できる代表的なケースです。
大規模な再開発では、商業施設や交通インフラの整備、景観の向上などで利便性・居住性が向上します。
また、街としてのブランド価値も高まり、街の活性化だけでなく、居住者・観光客の増加も見込めます。
このように需要が高まることで地価上昇につながるのです。
新線・延伸の計画
新しい線や既存の線が延伸されると、交通の利便性が向上します。
とくに、通勤・通学の利便性の向上につながれば、単身者・ファミリー世帯の需要が高まり地価の上昇につながりやすくなるのです。
新駅の計画
新しい駅ができれば交通手段が増え利便性が向上するだけでなく、駅周辺が整備され地域全体の発展も期待できるでしょう。
新たな居住エリア・ビジネス・商業地の拠点として発展する可能性が高くなり、地価の向上が見込めます。
再開発で地価が上昇する理由
ここでは、再開発で地価が上昇する理由として以下の3つを解説します。
- 商業施設の新設や交通インフラの整備により利便性が向上する
- 新しいビルや商業施設の開発による雇用が生まれる
- 未来への期待から活発に取引される
それぞれ見ていきましょう。
商業施設の新設や交通インフラの整備により利便性が向上する
新しい商業施設が建設されると、買い物や娯楽などの選択肢が増え生活利便性の向上につながります。
また、新駅の開業やバス路線拡充、高速道路のインターチェンジ新設は、アクセス性の大幅な向上につながるものです。
通勤・通学や買い物などの利便性が高くなれば、居住需要が増加します。
地価は需要の高さにも影響されるため、需要が高くなる=地価上昇につながります。
エリア一体のブランド価値が高まれば高級マンションも増え、エリア全体の賃料相場が上がり、土地相場の底上げにもつながってくるでしょう。
新しいビルや商業施設の開発により雇用が生まれる
新しい商業施設やオフィスビルができれば、当然そこで働く人が必要です。
企業や店舗で雇用が生まれることで人口流入が促進され、エリアの活性化だけでなく居住需要増加にもつながります。
未来への期待から活発に取引される
再開発により「将来値上がりするかも」という期待が高まると、不動産取引も活発になります。
将来の利便性や資産価値向上を期待して購入するのは�、居住目的だけではありません。
投資目的の取引も増えてくるので、より取引が促進され価格の向上につながりやすくなるのです。
再開発で地価が上昇した事例
ここでは、実際に再開発で地価が上昇した事例をいくつか紹介していきます。
秋田駅周辺の再開発により地価が上昇した事例
秋田駅周辺は、平成以降の郊外型店舗の進出や郊外開発により、空き店舗の増加や居住人口の減少など、衰退が進んでいました。
そんな中、活性化を目的として策定されたのが「秋田市中心市街地活性化基本計画」です。
この計画に基づき、秋田駅周辺の開発が進められており、駅前広場や文化施設、民間マンション、ショッピングモール、ホテル、オフィスビルなどが完成しています。
また、「男鹿のナマハゲ」がユネスコの無形文化遺産に登録された話題性もあり、観光客の増加による商業地需要の高まりがプラスに影響しています。
こうした施設利用者や居住人口の増加により、2019年には秋田駅前商業地の公示地価が27年ぶりに上昇に転じました。
北大阪急行線延伸により地価が上昇した事例
2024年3月、大阪府でも居住エリアとして高い人気を誇る北摂エリアにおいて、北大阪急行電鉄の延伸区間が開業しました。
開業にともない、新駅周辺では高層マンションや商業施設、学校設備の整備も進められました。
延伸による都心へのアクセス向上や、商業施設の充実による生活利便性の向上が、住宅需要の上昇をもたらしたのです。
その結果、大阪府内で住宅地の地価上昇率がトップとな��る大幅な地価上昇が見られました。
熊本市の再開発により地価が上昇した事例
熊本市中央区の下通地区の再開発事業では、地価が21.0%上昇し、地価上昇率が商業地の地方圏で16位と大きな上昇を見せました。
下通アーケード街では、平成29年に大型商業施設が開業し、来客数が著しく増加しています。
また、近隣ではバスターミナルを備えた大型複合施設の再開発が予定されており、回遊性や利便性の向上から店舗需要が高まり、地価の上昇につながっているのです。
再開発以外で地価の上昇が見込めるエリアとは?
地価上昇の要因となるのは再開発だけではありません。
以下のようなエリアでも地価上昇が見込めるので、今後の動向にも注視し不動産売買を検討するとよいでしょう。
- インバウンド需要の高いエリア
- 規制緩和が実施されるエリア
- 災害からの復興が進んだエリア
それぞれ見ていきましょう。
インバウンド需要の高いエリア
日本政府観光局の調査によると、令和6年の訪日外国人旅行者は3,687万人で、令和5年の2,507万人を大きく上回っています1。
これは、コロナ前の令和元年の3,188万人も上回っており、インバウンド需要は増加傾向にあります。
これにより、地価の上昇につながる可能性があります。
外国人観光客が増加すれば、ホテルや別荘などの需要が高まり、土地取引が活発に行われ、地価の上昇に促進するのです。
実際、外国人観光客から人気の高い北海道ニセコや京都では、地価の大きな向上が見られています。
今後もインバウンド需要が高まることが予測され、人気エリアでの地価向上が期待できるでしょう。
規制緩和が実施されるエリア
高さ制限や容積率など、建築に対する規制が緩和されるエリアでは、高層ビルの建設が進み、需要増加や地価向上が期待できます。
たとえば、規制緩和によって大幅に地価が上昇したエリアとして福岡市天神地区が挙げられます。
福岡市の天神地区は、世界で一番ビジネスをしやすい環境作りと目的とし、平成26年に大幅な規制緩和を行える「国政戦略特区」に選ばれています。
これにより、航空法の高さ制限の特例や市独自の容積率緩和を組み合わせて、ビルの建て替えが促進されているのです。
ビルの建て替えによる収益力向上や雇用創出などが、地価上昇を促しています。
災害からの復興が進んだエリア
大規模な災害は地価の下落につながる恐れがありますが、反面、復興が順調に進み経済が活性化すれば、地価の上昇につながる可能性があります。
たとえば、平成28年の熊本地震後の熊本県の地価平均推移 は以下のとおりです2。
| 年 | 地価(中央5-8/商業地) |
| 平成28年 | 189,000円 |
| 平成29年 | 193,000円 |
| 平成30年 | 202,000円 |
| 平成31年 | 212,000円 |
| 令和2年 | 219,000円 |
| 令和3年 | 221,000円 |
| 令和4年 | 228,000円 |
| 令和5年 | 237,000円 |
| 令和6年 | 252,000円 |
地価が大きく上昇しているのが分かります。
地震復興以外にも上昇要因はありますが、復興による経済活動の活発化や需要アップも地価上昇の一因と言えるでしょう。
まとめ
再開発が行われると利便性向上や人口流入、住宅需要増加により地価の向上が見込めます。
とくに、大規模な再開発や新駅の開業などは地価が高まりやすいので、周辺の開発予定の動向をチェックしてみるとよいでしょう。