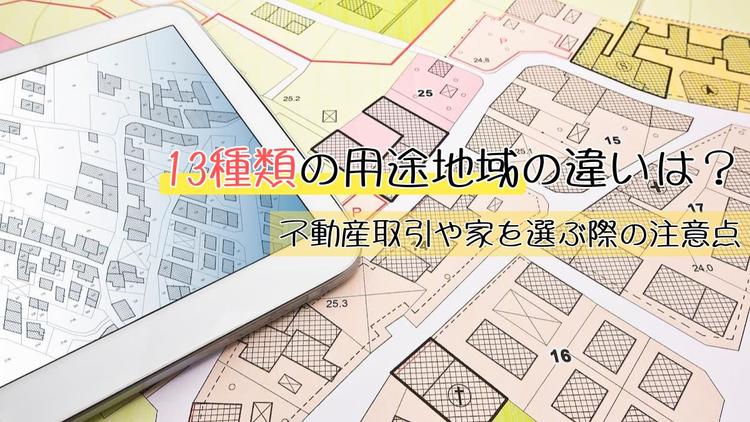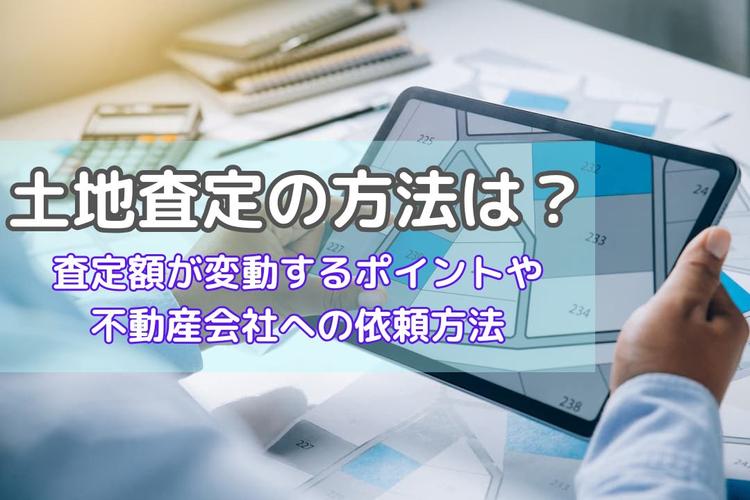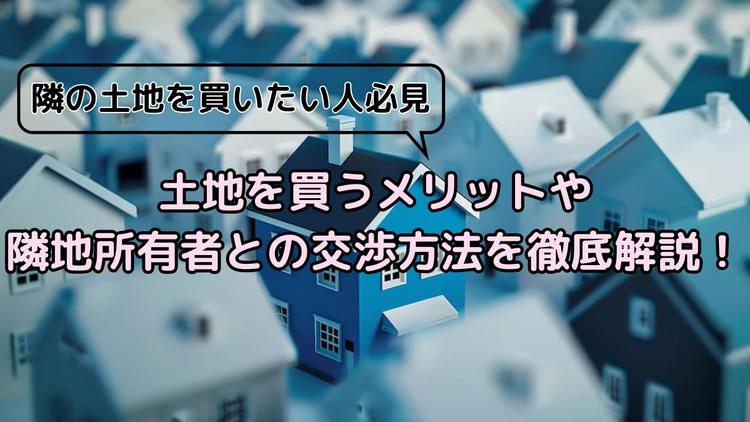用途地域とは、その地域に建つ建物の用途を制限するための規制です。
家を購入する際には、目的の土地がどの用途地域なのかを知ることがとても重要になってきます。
用途地域によっては、ある日突然、隣地に工場が建つという事態もあり得るからです。
この記事では、13種類の用途地域の違いを知るとともに、用途地域に関わる不動産取引や家を選ぶ際の注意点について解説します。
用途地域とは何か
用途地域とは、都市計画法により土地の用途を地域ごとに制限した規制です。
都市計画区域のうち市街化区域において用途地域を配置して、それぞれの地域で建てられる建物の種類や規模を定めています。
既に市街地となっている地域や、今後の開発などで市街化が進められる地域は「市街化区域」となっており、後述の用途地域が定められています。一方で、農村や山林などは開発・建築が制限される市街化調整区域に定められています。
用途地域は、住宅、商業施設、製造工場などの施設を適切に配置することで、機能的な都市活動を確保することを目的としています。たとえば、閑静な住宅街に突然大きな工場が建つことがないように設定されています。
用途地域には、大きく分けて「住宅系」「商業系」「工業系」の3系統があり、さらに細かく13種類に分類されています。用途地域によって、建てられる建物の用途だけでなく、高さや規模などが制限されるのです。
用途地域は、自治体のホームページや都市計画課などの担当窓口で図面の閲覧をすることができます。
13種類の用途地域
用途地域は、2019年4月に「田園住居地域」が追加されて、現在13種類が設定されています。
どのような用途地域があるのか、紹介していきましょう。
住居系
住居系の用途地域は、主に良好な住居の環境を保護するための地域で、次のような種類があります。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
商業系
商業系用途地域は、店舗や事務所、商業などの利便を増進するための地域で、次のような種類があります。
- 近隣商業地域
- 商業地域
工業系
工業系用途地域は、主に工業の利便を増進するための地域で、次のような種類があります。
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
住居系用途地域の制限
主に良好な住居の環境を保護するために定められた住居系用途地域。
ここでは、それぞれの用途地域について、どのような制限があるのか解説していきます。
第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域では、次の用途の建物が建てられます。
- 住宅
- 店舗兼用住宅
- マンション
- 小、中、高校
- 神社、寺院、教会
- 老人ホーム、保育所
- 診療所
建てられる建物は3階建て以下の低層建物です。条件によっては、2階建てまでになることがあります。
マンションも建築可能ですが、低層建物しか建てられないので、近くに高層マンションが建つ心配はありません。
近隣が他の用途地域に指定されていて、そこに高層ビルが建ったとしても、そのビルに対して第1種低層住居専用地域に定められた厳しい制限が適用され、十分な時間日照時間が確保できるように日影規制の基で建設が行われるのです。
そのため、長時間にわたり日影の影響を受けることはありません。
また、第一種低層住居専用地域では店舗兼用住宅の建築ができますが、店舗は日常生活で必要な物品の販売やサービスで、面積は50平方メートル以下という決まりがあります。
住居兼用が条件なので、一般的なスタイルのコンビニは建築できません。
第二種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域では、次の用途の建物が建てられます。
- 第一種低層住居専用地域で建築できるもの
- 150平方メートル以下の店舗
基本的に第一種低層住居専用地域に準じていますが、150平方メートル以下の店舗が建築できる点に特徴があります。
閑静な住宅地において、コンビニなどの小さな店舗を建てることができます。
▼関連記事

第一種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域では、次の用途の建物が建てられます。
- 第一種低層住居専用地域で建築できるもの
- 大学、高等専門学校、専修学校
- 病院
- 福祉施設
- 500平方メートル以下で2階以下にある店舗、飲食店
3階建て以上の中高層マンションの建築も可能で�すが、高度地区やその他の制限がある場合、定められた高さを超える高層建物は建てられません。
物販店や飲食店も建築可能ですが、その場合は延べ床面積500平方メートル以下という制限があります。
中高層のビルに店舗がテナントとして入る場合も、3階以上では営業ができません。
第二種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域では、建築できる建物ではなく、建築できない建物が示されています。
そのため、建築できる用途の選択肢が大きく広がるところに特徴があります。
第二種中高層住居専用地域で禁じられているのは、次の用途の建物です。
- ぱちんこ屋、場外馬券売場、劇場、映画館、ナイトクラブ、カラオケボックス
- 工場
- ボーリング場、スケート場などの運動施設
- ホテル、旅館
- 自動車動車教習所
- 畜舎
制限されていない店舗は、2階以下であれば1500平方メートルまで認められます。
物販店舗や飲食店は3階以上にも設けることができます。
▼関連記事

第一種住居地域
第一種住居地域では、3,000平方メートルまでの店舗や事務所が建てられます。
ぱちんこ屋、場外馬券売場、劇場、映画館、ナイトクラブ、カラオケボックスは建築できませんが、ホテルは建てることができます。ただし、ラブホテル(専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設)は、商業地域以外には建築できません。
第二種住居地域
店舗や事務所は1万平方メートルまで建築できます。遊戯施設やカラオケボックスなども建築可能です。
大規模な工場は建築できません。
準住居地域
準住居地域は、主に国道や幹線道路沿いに指定されるため、住居系地域では比較的にぎやかな環境になります。
150平方メートル以下の自動車修理工場や200平方メートル以下の劇場や映画館が建てられます。
田園住居地域
田園住居地域は、第一種低層住居専用地域に準じた制限です。
農地が広がる地域に指定されるため、農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するものや、農業の生産資材の貯蔵に供するものが建築できる点に特徴があります。
農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店であれば、500平方メートル以下��、一般的な店舗、飲食店であれば、150平方メートル以下のものを2階以下に設けることができます。
商業系用途地域の制限
店舗や事務所、商業などの利便を増進するために定められた商業系用途地域。
それぞれの用途地域について、どのような制限があるのか解説していきます。
近隣商業地域
近隣商業地域は、店舗や事務所、劇場、映画館を面積の制限なく建てられます。
また、環境を悪化させる恐れのない150平方メートル以下の工場を建てることもできます。
住居系の建物も建築できることから、中高層マンション、大規模商業施設、遊戯施設、小規模工場が混在するエリアとなります。
商業地域
商業地域では、あらゆる商業施設の建築ができます。他の用途地域では禁じられている風俗営業の店舗も建築が可能です。
主にターミナル駅の周辺エリアや繁華街に指定されます。高層マンション、大規模商業施設、金融機関、小規模工場などが混在するエリアとなります。
日影規制が適用されないため、高層ビルの影響で日中もほとんど日が射さない室内環境になることがあります。
商業の利便性が優先されるため、あまり住環境には配慮されていませんが、生活の利便性や交通の利便性が特に高い場合、マンションでも人気が高くなることがあります。
工業系用途地域の制限
主に工業の利便を増進するための地域で定められた工業系用途地域。
それぞれの用途地域について、どのような制限があるのか解説していきます。
準工業地域
準工業地域は、危険性や環境への影響がある場合�を除いてほとんどの工場を建てることができます。
日影規制があることから、住宅であっても一定の日当たりを確保することができます。
そのため、住居と工場、商業施設が混在するエリアとなります。商業地域のように極端に地価が高くなることもないので、マンションだけでなく、一戸建て住宅も多く建てられている点に特徴があります。
工業地域
工業地域では、すべての工場を建てることができます。住宅や店舗は建てられますが、ホテル、映画館、病院、教育施設は建てられません。
工業地域はあらゆる種類の工場が建てられますが、住宅や店舗も建設可能です。湾岸エリアなども工業地域に指定されることがあり、タワーマンションなどが立ち並ぶエリアになることがあります。
工業専用地域
工業専用地域は、工場に特化したエリアです。すべての工場を建てることができますが、一方で、住宅を建てることができない唯一の用途地域です。
不動産取引や家を選ぶ際の注意点
家を購入する際に、用途地域に起因する問題が生じることがあります。用途地域に関してどのような点を注意すればいいのか、解説をしていきましょう。
建ぺい率に注意
用途地域が指定される際に、合わせて建ぺい率や容積率も指定されます。
気をつけたいのは、同じ用途地域でも、エリアごとに建ぺい率や容積率が異なる点です。
たとえば住居系用途地域の建ぺい率に着目してみると、第1種低層住居専用地域では、30%、40%、50%、60%の中から指定できるとされています。同じ住居系でも第1種住居専用地域では、50%、60%、80%の中から指定されます。
住環境を考えれば、建ぺい率が低い方が良い環境を整えられますが、一方で自分が望む規模の建物が建てられないという事態も考えられるでしょう。
土地を選ぶ際には、建ぺい率や容積率といった規模の制限にも注意を払う必要があります。
容積率は前面の道路幅も影響する
敷地面積に対する延べ床面積の制限として容積率があります。たとえば、容積率制限が300%の地域で敷地面積が100平方メートルの場合、延べ床面積300平方メートルの建物が建てられます。
ところが、前面の道路幅員が狭い場合、必ずしも指定容積率が容積率制限になるわけではないのです。住居系用途地域だと、道路幅員のメートルの数に、10分の4を乗じた値が容積率制限になります。住居系以外は10分の6を乗じた値です。
たとえば、第1種中高層住居専用地域で、前面道路の幅員が4メートルだと、
という計算で160%になります。
これを指定容積率と比較して、値の小さい方が制限を受ける容積率となります。これは、狭い道路に面する敷地で過密な建築を防ぎ、地域の安全性や住環境を守るためです。
容積率が300%の地域だとすれば、値の小さい160%が、この敷地の容積率制限です。
以上の理由で「前面道路の幅によっては、指定容積率よりも小さな建物しか建築できないことがある」ことを押さえておき�ましょう。
用途地域は過半の地域を適用する
用途地域は、敷地に沿って指定されているのではなく、敷地境界とは無関係に指定されています。
特に、準住居地域や近隣商業地域など、道路沿線に指定されることの多い用途地域では、「道路境界から○○メートル」と指定されることがあります。
そのため、敷地の中に用途地域界が存在することも珍しくはありません。
敷地内に二つの用途地域がある場合は、敷地の過半を占める用途地域がその敷地全体の用途を制限することになります。
なお、用途地域は敷地に対する制限なので、実際に建物が建つ位置とは無関係です。
用途規制を受けない建物がある
用途制限は、建築基準法が施行された1950年から規定されていました。
しかし、当初は都市計画によって用途地域が指定されている都市やエリアが少なく、現在のような規模で用途地域が指定されるようになったのは1970年頃からです。
このため、用途地域が指定される前に建てられた建物は数多く存在しています。
たとえば、菓子製造工場や自動車修理工場が、後から指定された第一種低層住宅専用地域の真ん中に建てられていることもあります。
こうした建物は、すべて解体して営業を止めない限り、既存不適格建築物として適法に存在することができます。
特に、遠隔地の敷地を購入する際などに、第一種低層住居専用地域だからといって静かな環境が維持されていると思い込み、現地を確認せずに購入を決めると、思わぬ事態に直面して驚くこともあるでしょう。
やはり、自分の家を購入する際は、現地やその周囲をしっかり自分の目で確認することが大切です。
第一種低層住居専用地域はどこにも店舗がないことも
第一種低層住居専用地域では、店舗兼用住宅の建築が認められています。店舗の規模は50平方メートル以内で、過半を住居部分が占めるという要件があります。
店舗として営業が認められるのは次のような業種です。
- 日用品や食材の販売
- 食堂
- 喫茶店
- 理髪店
- 美容院
- クリーニング取次
- 洋服店
- 自転車店
- 家庭電器点
住居兼用が要件なので、一般的なスタイルのコンビニを建てることができません。
さらに、店舗面積も50平方メートル以内に制限されているので、利用者は周辺地域に限定され、経営側からすれば大きな集客は見込めません。
近年、新たに開発された住宅地では、高額の資金を投じて店舗兼用住宅を建てようとする人がほとんどいないのが実情です。
そのため、広大な範囲に第一種低層住居専用地域が指定されたエリアでは、徒歩圏内に店舗が一切存在しないという事もあり得るのです。
静かな環境で暮らせる一方で、文房具やパンなどの日常的な品物が身近で購入できないという不便さを感じることがあるかもしれません。
日影規制が適用されない用途地域がある
快適な住環境を維持するためには、室内に日照を確保することが重要です。
そのため建築基準法では、日影規制により、冬至の日(12月21日頃)を基準として、午前8時から午後4時までの間に一定時間以上日照が確保できるように建築物の高さを規制しています。
しかし、商業地域��、工業地域、工業専用地域には日影規制が適用されません。そのため、極端なケースでは終日日照がない家や部屋が存在することになります。
工業専用地域ではマンションや住宅を建てることはできませんが、商業地域や工業地域では建築可能なため、生活空間に日当たりを求める方は、十分注意が必要です。
二世帯住宅が建てられないことがある
用途を制限する規制は用途地域だけでなく、地区計画という制度もあります。
地区計画は、自治会単位程度の限られたエリアに設定されるもので、用途地域よりもさらに細かな用途規制を行うことができます。
たとえば、第一種低層住居専用地域で建築が可能なアパートや老人ホームの建築を禁止し、一戸建ての住宅に特化したエリアにすることも可能です。
地区計画は、行政による「まちづくり」の一環として、各都市でさかんに取り組まれており、決して珍しい制度ではありません。
ただし、設定されるエリアが狭いことから、不動産の規制調査を行う際に見落とされることがしばしばあります。
もし、二世帯住宅を建てる目的で購入した土地が、一戸建て住宅に特化した地区計画区域に該当していた場合は、二世帯住宅が建てられない可能性があります。
そもそも、建築基準法上では「二世帯住宅」という概念はなく、完全独立型の二世帯住宅は「共同住宅」か「長屋」として扱われます。
そのため、一戸建て住宅に特化した地区計画区域では、建築ができないのです。
用途地域の調査では、用途地域を調べる他に地区計画の制定の有無を併せて調べることが重要です。
ま��とめ
用途地域は、現在13種類が設定されています。大きく、住宅系、商業系、工業系に分類でき、次のような地域があります。
【住宅系】
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
【商業系】
- 近隣商業地域
- 商業地域
【工業系】
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
住宅やマンションは、工業専用地域以外の用途地域に建てることができます。
「閑静な住宅地に住みたい」「利便性の高い家に住みたい」といった住宅を購入する目的を明確にしたうえで、理想の環境に近づける用途地域を選択することが重要です。