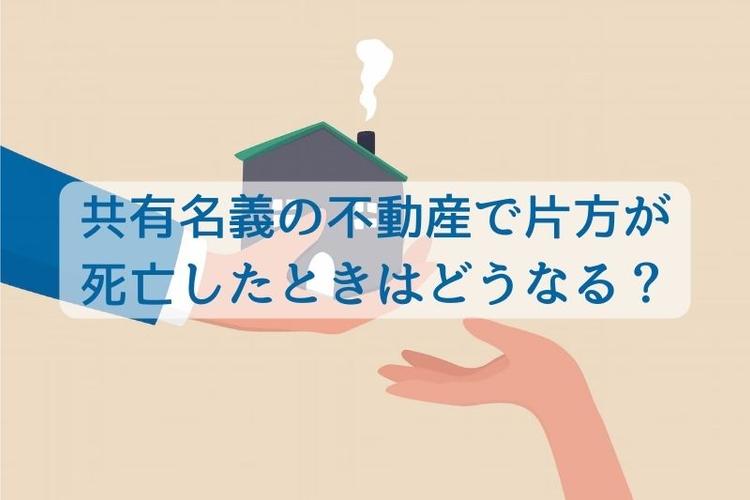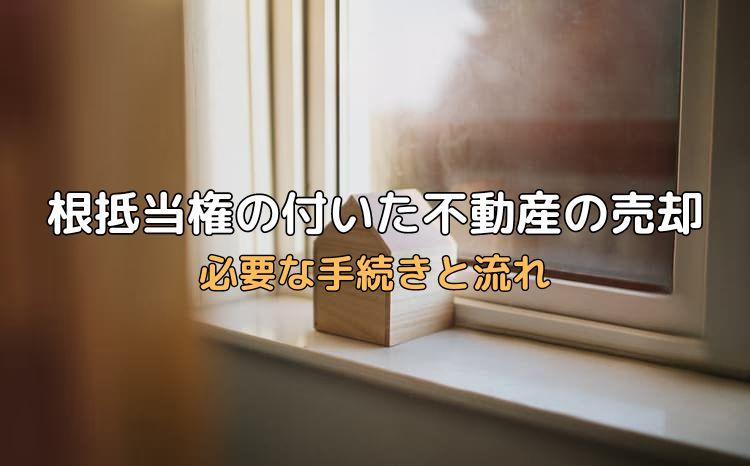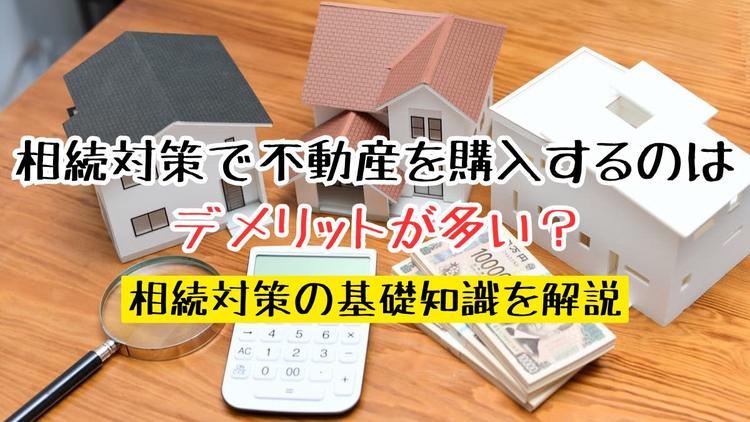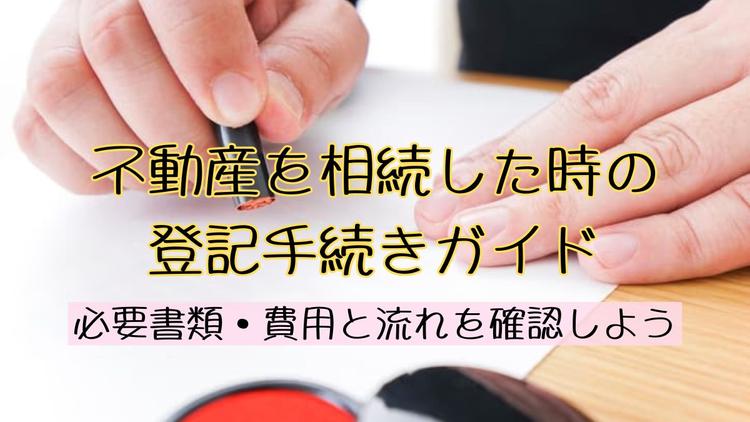住宅の購入で、夫婦がそれぞれが資金を出し合い、不動産を共有することがあります。しかし、片方が死亡すると、共有名義であっても、亡くなった人の持分がそのまま生きている方の所有になるわけではありません。相続上のルールがあるからです。
この記事では、共有名義の不動産で片方が死亡した場合、不動産の相続はどうなるのかについて、そしてその手続きの流れや売却方法について解説します。
共有名義の片方が死亡した場合の相続の流れ
不動産の共有名義の片方が死亡した場合、そのまま生きている方の所有になるわけではありません。亡くなった人の遺産がどのような配分で相続されるのかによって、新たな不動産所有者が決まります。
ここでは、不動産の共有名義の片方が死亡した場合の相続の流れを追っていきましょう。
誰が相続人になるのか
被相続人の配偶者は常に相続人になります。それに加えて、血縁関係者が、次の順序で相続人となります。
- 第1順位:被相続人の子供(子供が死亡している場合は孫)
- 第2順位:被相続人の直系尊属(父母が死亡している場合は祖父母)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
最上位の人が相続人となるので、上位の順位の人がいれば、相続人にはなれません。たとえば、被相続人に子どもがなく、直系尊属の中で母親が存命であれば、配偶者と第2順位の母親が相続人となります。
相続人を確定する
相続人は、死亡時の戸籍謄本だけでは確定できません。他に認知した子どもがいないことを証明しなくてはならないからです。相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本をすべて入手する必要があります。
ここでいう戸籍謄本とは、次の書類をいいます。
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍謄本
遠方等の理由で、直接役所の窓口に出向くことが困難な場合は、郵送で取り寄せることも可能です。当該市区町村役場のホームページなどで、戸籍の請求方法を確認のうえ、要領に従って請求をすれば、必要な戸籍が送られてきます。
被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本を入手するために、順番に過去に遡って請求することになるので、必要な戸籍が多いと、すべて揃えるのに1カ月以上の期間を要することがあります。
相続人が確定し、法定相続によって遺産分割する場合は、次のような配分になります。
被相続人に配偶者と子どもがいる場合
相続人は、配偶者と子どもです。配偶者が1/2、子どもが1/2の相続をします。子どもが2人いれば、1/2の遺産を2人で分けるので、全体の遺産からみれば、子どもは1/4ずつになります。
被相続人の配偶者は既に亡くなり、子どもと兄弟がいる場合
すでに配偶者が亡くなっている場合、子どもが遺産を均等に分けます。子どもが2人いれば、1/2ずつ、3人いれば1/3の割合で分配されます。
被相続人の兄弟姉妹は相続人ではありません。
被相続人に配偶者がいるが、子どもがいない場合
被相続人の親が健在で、子どもがいない場合、配偶者は遺産の2/3を相続します。親は1/3を相続します。両親ともに健在であれば、父は1/6、母は1/6がそれぞれの相続分です。
親が既に亡くなっている場合は、配偶者は3/4を相続します。残りの1/4は、被相続人の兄弟姉妹で均等に分割します。
法定相続人がいない場合は内縁の妻などに財産分与が行われる
死亡した共有者に法定相続人がいない場合、特別縁故者へ相続財産分与がおこなわれます。特別縁故者とは、生前の被相続人と特別な関係性がある人物で、次に該当する人をいいます。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
「被相続人と生計を同じくしていた者」は、内縁の妻や被相続人と親子同然の関係で同居していた人です。
「被相続人の療養看護に努めた者」は、被相続人の生前に身の回りの世話を無報酬で行った人を指します。業務で介護や身の回りの世話をしていた人は対象になりません。
したがって、亡くなった共有者の法定相続人でなかった場合でも、法定相続人が存在せず、かつ共有者と生計を同じくしていたのであれば、不動産の財産分与が行われることがあります。
特別縁故者への財産分与の流れ
特別縁故者への相続財産分与は、相続のように自動的に決まるものではなく、「相続財産管理人選任の申立」によって、自分が特別縁故者であることを主張する必要があります。
相続財産管理人選任の申立は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所でおこないます。申立を受けた家庭裁判所は、相続財産管理人を選任します。多くの場合、相続財産管理人は、弁護士や司法書士から選ばれます。
相続財産管理人は、官報の公告によって相続人の捜索をします。6カ月の間に相続人が現れなければ「相続人の不存在」が確��定します。
相続人の不存在が確定した後に、改めて「特別縁故者に対する財産分与の審判」を申し立てると、家庭裁判所が、特別縁故者と認められるかどうかや、具体的にどの程度の財産を分与すべきかについて決定します。
法定相続人も特別縁故者もいなければ共有者に帰属する
死亡した不動産の共有者に法定相続人も特別縁故者もいない場合、民法では、次のように定められています。
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する(民法第255条)。
民法は、共有者に相続人がいなければ、生きている方の共有者のものになるとしています。ただし、判例により、内縁の妻などの特別縁故者がいれば、そちらの方が優先されます。
すべての条件を満たしたとしても、共有者への帰属は自動的に決まるものではなく、「相続財産管理人選任の申立」が必要です。
家庭裁判所と相続財産管理人は、他の相続人や債権者、受遺者、特別縁故者といった利害関係人がいないかを捜索し、該当者がいなければ、共有持分は共有者へ帰属されます。捜索や法的な手続きがあるため、最初の申し立てからおよそ1年を要します。
遺言書の有無を確認する
被相続人が遺言書を残していた場合、遺言の執行が優先されます。たとえば、「共有の不動産を妻のA子にすべて相続する」と書かれていれば、法定相続分に関係なく、不動産を配偶者のA子に譲渡する手続きをとらなければなりません。
遺言書は主に自筆証書遺言書と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言書は被相続人が保管��しているため、自宅などの保管の可能性がある場所を探すことになります。自筆証書遺言が見つかっても、すぐに開封することはできません。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ開封し、検認を行わなければならないからです。
遺言書検認の申し立てに必要な書類
遺言書検認の申し立ては、次のような書類と費用を添えて、家庭裁判所に提出とします。
- 遺言書の検認申立書……家庭裁判所で直接入手するか、裁判所のホームページからダウンロードします。
- 申立人・相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手
家庭裁判所は、検認の申立てがあると、相続人に対し検認を行う日の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断によるので、全員がそろわなくても検認手続は行われます。
検認期日に、申立人が未開封の遺言書を提出し、出席した相続人等の立会のもと、裁判官は、遺言書の開封をしたうえで遺言書を確認します。
検認済証明書の申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。
なお、被相続人が自筆証書遺言の法務局保管制度を利用している場合や公正証書遺言の場合は、検認の手続きは不要です。
遺産分割協議を行う
遺言書がなく法定相続とは異なる分割を行いたい場合は、遺産分割協議を行います。特に不動産の相続がある場合には、法定相続どおりに分割するのが困難なため、遺産分割協議によることになります。
相続登記で提出する遺産分割協議書とは
相続登記の際には、遺産分割協議書の提出が求められます。遺産分割協議書には、誰がどの遺産を相続するのかを記載します。作成した書面は、すべての相続人が確認し、各自が実印を押印します。
たとえば、妻と息子が相続人であり、妻が100%不動産を相続する場合は、次のような文面になります。
遺産分割協議書の文例
遺産分割協議書
令和〇年4月20日、〇〇市〇〇町○○番地 見本正の死亡によって開始した相続の共同相続人である見本文子及び見本例次は、本日、その相続財産について、次のとおり遺産分割の協議を行った。
相続財産である下記の不動産は、見本文子が相続する。
この協議を証するため、本協議書を2通作成して、それぞれに署名、押印し、各自1通を保有するものとする。
令和〇年6月7日
〇〇市〇〇町○○番地 見本文子 (実印)
東京都中央区○○町〇丁目〇〇番○○号 見本例次 (実印)
記
不動産の表示
所 在 〇〇市〇〇町○○番地
地 番 ○○番地
地 目 宅地
地 積 150・75平方メートル
所 在 〇〇市〇〇町○○番地
家屋番号 ○○番地
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 89・59平方メートル
2階 45・28平方メートル
遺産分割協議が不調になれば遺産分割調停
遺産分割協議は、必ず整うとはかぎりません。どうしても合意できない場合は、遺産分割調停によります。家庭裁判処理調停により、調停委��員や家事審判委員が相続人の話し合いを仲介して、全員が合意する分割案をまとめるための援助をしてくれます。
資産分割調停の申し立てに必要な書類
遺産分割調停は、相続人のうちのだれかの住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意できる家庭裁判所です。次のような書類と費用を提出します。
- 遺産分割調停の申立書……家庭裁判所で直接入手するか、裁判所のホームページからダウンロードします。
- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票または戸籍附票
- 遺産目録と当事者目録
- 遺産に関する証明書……不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、無預貯金通帳写しまたは残高証明書など
- 収入印紙1,200円
- 連絡用の切手
調停分割でも合意に至らなかった場合は、家庭裁判所の審判による審判分割を行うことになります。
相続登記を行う
遺産の分け方が決まったら、相続する不動産の相続登記手続きを行います。
相続登記は、それほど複雑な手続きではないので、自分で行うことも可能です。手続きをする時間がない場合は、司法書士に依頼するという方法があります。
相続登記は、直接法務局の窓口に提出する他、郵便による提出も可能です。次のような書類を提出します。
- 登記申請書
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本または除籍謄本
- 相続人であることが分かる戸籍謄本
- 登記対象の不動産を相続することになった相続人全員の住民票
- 登録免許税……収入印紙
- 固定資産税・都市計画�税(土地・家屋)課税明細書の写しまたは固定資産税課税証明書
登録免許税とは
登記申請では、登録免許税として収入印紙を申請書に貼って納めます。
相続登記の登録免許税は、不動産の価額の0.4%です。不動産の価額は、毎年市町村から送られてくる「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税明細書」に記載されています。手元にない場合は、市町村役場が発行する証明書を取得します。
共有名義の片方が死亡した場合の注意点
共有名義の片方が亡くなった場合に、遺産分割協議の流れ次第で、生きている方の共有者が不利益を被ることがあります。共有者の心構えとして、共有名義の相続での注意点を解説していきましょう。
他人との共有は回避する
不動産を夫婦共有としていた場合、遺産分割協議によって、死亡した共有者の持分を配偶者以外の者が相続するケースも想定できます。
たとえば夫が亡くなった場合だと、妻が、まるで面識のない人物と共有することもあり得ます。夫婦共有だったときには、話し合いで解決したことも、他人との共有では意見を通すことが困難になります。
共有名義の場合、不動産を売却や賃貸しようとするときは、必ず共有者の全員の同意が必要です。共有者との間で意見がまとまらなかったり、協議が成立しなかったりすると、不動産を思うように運用できません。
しかも、権利の主張に持分の比率は全く関係ありませんから、たとえ1割以下の所有しかないとしても、所有者の権利は主張できるのです。
共有関係が嫌になれば、自分の持分だけを売ることができます。しかし、現実的に考えれば、わざわ��ざ他人と共有することになる物件を購入しようとする人は、まずいません。たとえ現れたとしても、相当に売却額を下げなければ売れないことは、容易に想像がつきます。
共有は、不動産の運用に著しい支障がでるため、遺産分割協議の流れがどのようになろうと、他人と共有する選択は避けるべきです。
夫婦共有の場合は遺言書を作成しておく
夫婦に子どもがいない場合、亡くなった配偶者の両親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。こうした事態を未然に防ぐには、遺言書の作成が最も有効です。遺言書がある場合は、その内容が優先されることになっています。双方で遺言書を作成し、片方が亡くなった際はもう片方に不動産の持分全てを相続する旨を記載しておけば、他人と共有を避けることができます。
特に内縁の関係の場合、法定相続人にはなれません。法定相続人がいれば、そちらに相続されることになりますから、遺言書の作成は確実に実施しておきましょう。
兄弟姉妹に遺留分はない
相続には、「法定相続分の1/2」を取得できる遺留分があります。遺言書などで自身の遺留分が侵害されていた場合、その相続人は、遺留分侵害額請求を行うことで、遺産の中から、遺留分相当を取り返すことができます。
相続人が自分と子どもの場合、たとえ遺言書で配偶者にすべて相続する旨の記載があっても、子どもからの遺留分侵害額請求が認められれば、相当額を渡すことになります。
子どもがいない場合、被相続人の両親も亡くなっていると、兄弟姉妹が相続を主張してくることがあります。法定相続だと、主張どおり、遺産の1/4を渡すことになります。しかし、兄弟姉妹には遺留分は認められていないので、遺言書があれば、亡くなった共有者の思いどおりの相続ができます。
生前に遺留分を放棄させる
遺言書による相続を実施しても、他の相続人が遺留分を主張してきて、思いどおりの相続ができないことがあります。それを防ぐためには、遺留分放棄の制度を利用するのが有効です。
相続開始前(生前)に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所は、次のような許可基準で判断をします。
- 遺留分を放棄する本人の自由意思に基づくもの
- 遺留分を放棄する理由に合理性がある
- 代償性がある……贈与がすでに行われているか遺留分放棄と同時に贈与がある
たとえば、夫が不動産の持分をすべて妻に相続したい場合に、すでに住宅資金等の贈与を受けている息子が納得をして遺留分放棄の意思表示をすれば、➀の基準により、家庭裁判所から認められることになります。
そのうえで、遺言書によって妻を相続人に指定することで、不動産の持分を妻がすべて相続できます。
離婚したらただちに共有関係を解消する
夫婦が不動産を共有名義にすることは一般的に行われていますが、離婚後も共有名義を維持していた場合、元配偶者が死亡した場合の対応が複雑になります。
離婚した元配偶者は法定相続人ではありません。単に不動産の共有者という関係性にすぎないため、当然遺産分割協議には関与できません。
遺産分割協議の結果によっては、元配偶者の親や兄弟姉妹と共有関係になってしまい�ます。多くの場合、離婚すれば、相互の家族間の関係性は破綻していますから、不動産の処分がままならない事態も想定できます。離婚の際には、同時に不動産の共有名義を解消しておくのが賢明です。
住宅ローンが残っていたら団信の加入を確認
被相続人が団体信用生命保険(団信)に加入している場合は、住宅ローンを借り入れている金融機関に必要書類を揃えて、保険金支払の手続きを行います。保険金が支払われることで、住宅ローンは完済されます。
一般的な住宅ローンでは、団信の加入は利用条件になっていますが、フラット35では、加入は任意となっています。そのため、少なからず、諸事情で団信に加入していない人もいます。
もし被相続人が団信に加入しておらず、住宅ローンを相続人が相続する場合には、相続人が住宅ローンを引き継ぐ手続を行い、不動産についている抵当権の変更登記をすることになります。
相続した共有不動産を売却する方法
相続した共有不動産を売却する方法について解説していきましょう。
不動産の分割方法は4種類ある
相続人が複数いる場合、不動産の分割方法には、次の4種類があります。
- 共有
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割(売却)
それぞれどのような、分割方法なのか説明をしていきましょう。
共有
共有は、相続した不動産を共有名義にする方法です。共有すると売却する際に、すべての権利者の同意が必要になります。将来、それぞれの共有者の相続が発生すると、さらに相続人が増えることになり、実質的に売却が不可能な状態�に陥ることにもなりかねません。
不動産の相続において「共有」は、極力避けるべき選択です。
現物分割
現物分割は、土地を分筆して分ける方法です。相続の対象が広大な土地の場合には、適した方法ですが、戸建ての住宅の場合は、現実的な方法とはいえません。
代償分割
代償分割とは、特定の相続人が不動産を相続することを前提して、他の相続人に現金や他の不動産などの譲渡することによって合意する方法です。不動産を引き続き有効活用できるメリットがありますが、不動産に見合った資金が必要になることと、不動産の価格判定について納得のできる指標の選定が課題になります。
等価分割(売却)
等価分割は、相続した不動産を売却して、売却代金を相続人で分割する方法です。平等な分割ができますが、対象の不動産に相続人が居住していた場合、次の住まいを探す必要があります。
名義変更をしてから売却する
等価分割では、相続が発生してから、早い段階で売却をすることになります。しかし、すでに亡くなっている被相続人の名義のままでは売却できませんから、相続登記を済ませてから売却しなければなりません。
売却が前提であれば、相続人全員の共有名義にするという選択も大きな問題はありません。ただし、売却には全員の同意が必要であり、売買契約書も全員の捺印が必要になります。そのため、それぞれが遠方に住んでいると、不動産の引渡しまでの間に、かなりの労力を要することになります。
売却をスムーズに進行させるためには、代表人を決めて、単独名義にする方法が合理的です。この場合、口約束だけでは不安なのであれば、遺産分割協議書に換価分割をおこなう旨を明記しておきます。
遺産分割協議書の書式が整えば、約1カ月で相続登記が完了します。その後一般的な売却方法によって売却を進めていきます。

まとめ
共有名義の不動産で片方が死亡した場合、その持分は相続されます。相続は、法定相続によって分割されますが、さらに共有者が増える選択は、将来不動産の売却に支障をきたすので、可能な限り回避しましょう。
さらなる共有を避けるためには、共有者がそれぞれ遺言書を作成しておく方法が最も有効です。遺言書の中で、自分の持分を共�有者に渡すことが明記されていれば、スムーズに生きている方の所有になります。
特に内縁関係の場合、相続権がありません。もし法定相続人がいれば、その相続が優先されることになりますから、遺言書の作成は、きちんと実行しておきましょう。
相続した不動産を売却して、現金によって分割する「換価分割」を行う場合は、まず相続登記が必要です。一時的な名義変更であるため、この場合共有でも大きな問題はありません。
しかし、売却活動や売買契約をスムーズに行うためには、単独名義である方が合理的です。口約束だけで、単独登記にすることが不安な場合は、遺産分割協議書に、等価分割を目的とした登記であることを明記することで、不安は解消できます。