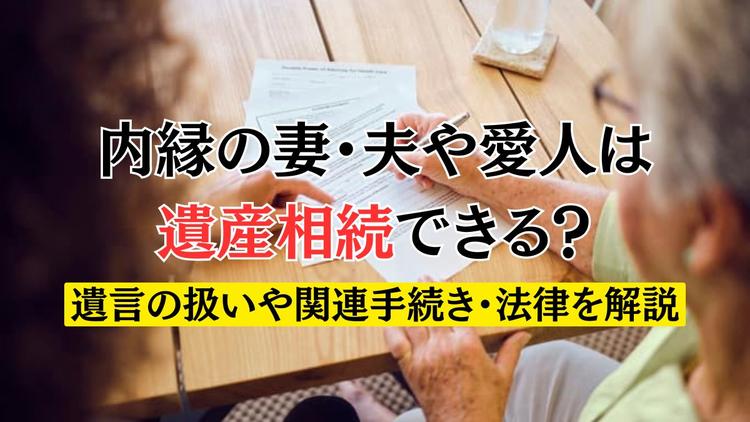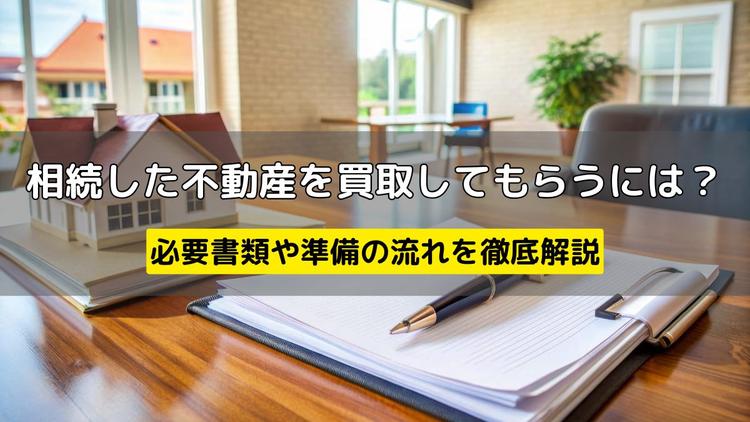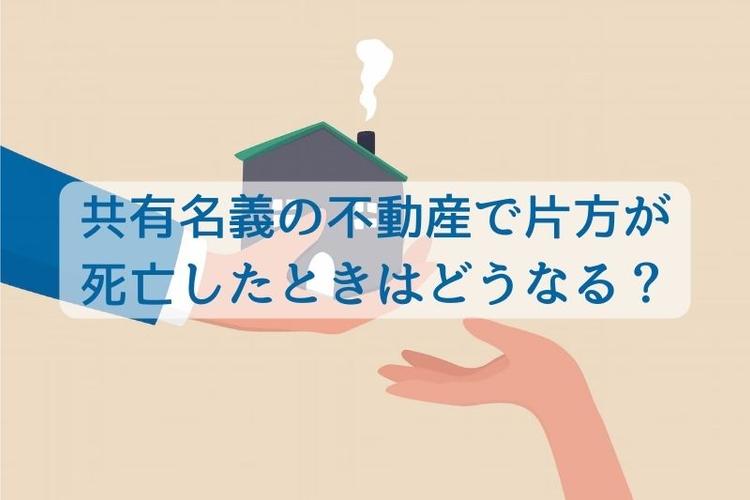相続税における現金と不動産の評価額の違い
不動産を取得することで得られる相続税の節税効果にはさまざまなものがありますが、単に現金で不動産を取得するだけで得られる効果として、現金と不動産との評価額の違いがあります。
具体的には、土地については相続税路線価を用いて、家屋については固定資産税評価額を用いて算出します。
土地:相続税路線価
相続税の算出において、土地の評価額は相続税路線価を用いて計算されます。
例えば、ある道路の相続税路線価が100,000円/㎡で、この道路についた土地の面積が200㎡であれば、100,000円/㎡×200㎡=20,000,000円と計算されます。
相続税路線価は、「国税庁」が「毎年7月1日」に発表するのですが、1年間の間の地価の変動により、納税者間で不公平が生じないように、概ね時価の80%程度を目安に設定することとされています。
これにより、例えば、相続税の節税対策として1億円の土地を購入した場合、その評価額は8,000万円で計算され、2割分の節税効果を得られることとなります。
家屋:固定資産税評価額
一方、不動産のうち家屋の相続税評価額は「固定資産税評価額」を用いて算出します。
固定資産税評価額の更新が3年に1回となっているのは、市町村内にある全ての不動産を評価するのに大変な労力がかかるからであり、3年の間に起こる地価の変動を盛り込んでいません。
このことにより、納税者間で不公平が生じないよう、固定資産税評価額は時価の概ね70%程度を目安に定めることとされています。
つまり、相続税の節税対策として1億円の家屋を取得した場合、その価値は7,000万円程度で計算され、3割分の節税効果を得られることとなります。
土地における倍率方式による評価
路線価は国税庁が定めるものですが、日本全国全ての地域に設定されているわけではありません。
郊外など、路線価の設定されていない地域においては「倍率方式」と呼ばれる方法で土地の評価額が算出されます。
倍率は国税庁の上記ページで確認できますが、1.0倍~1.2倍程度に設定されている場合が多く、固定資産税評価額が時価の70%程度ですから、概ね70~80%程度の評価額、2割~3割程度の節税効果を得られることになります。
相続税の計算方法
相続時の不動産評価額の算出方法が分かったら、相続税の計算方法を確認しましょう。
相続税の計算は、単純に相続税の対象となる資産に対して税率をかけるのとは異なり、いくつかの計算過程が必要となります。
以下、それぞれについて解説していきます。
正味遺産額の把握
まずは土地は相続税路線価、建物は固定資産税評価額にて不動産評価額を把握します。
また、不動産以外に現金や株式などもっている場合は、それらの合計額から借金や葬儀費用などマイナスの資産を差し引いて遺産額を算出します。
例えば、不動産1億円の他、現金2,000万円、株式1,000万円の相続財産があり、一方でマイナスの資産として借金が1,000万円あるのと、葬儀費用として200万円支出した場合には、正味遺産額を以下のように計算します。
正味遺産額の計算例
| 現金 | 2,000万円 |
| 不動産 | 1億円 |
| 株式 | 1,000万円 |
| 総遺産額 | 1億3,000万円 |
| 借金 | △1,000万円 |
| 葬儀費用 | △200万円 |
| 正味遺産額 | 1億1,800万円 |
基礎控除を差し引いて課税遺�産総額を求める
正味の遺産額を計算したら、相続税の基礎控除を差し引き、課税遺産総額を求めます。
相続税の基礎控除は、「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」となっています。
例えば、妻と子2人が法定相続人の場合、3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円が基礎控除額です。
このため、先ほど計算した正味の遺産額から基礎控除額を差し引くと、1億1,800万円-4,800万円=7,000万円が課税遺産総額となります。
基礎控除額の計算における「法定相続人の数」には相続放棄した人も含まれます。
先ほどの例で、妻と子2人のうち1人が相続放棄した場合でも基礎控除額は変わりません。
法定相続分で相続したものとして相続税の総額を計算する
相続税の計算では、実際には分割割合が異なっていたとしても、法定相続分で分割したものとして税金を計算します。
法定相続分で分割する
まずは課税遺産総額をそれぞれの法定相続分で分割します。
| 妻 | 7,000万円(課税遺産総額)×1/2(法定相続分)=3,500万円 |
| 長男 | 7,000万円(課税遺産総額)×1/4(法定相続分)=1,750万円 |
| 次男 | 7,000万円(課税遺産総額)×1/4(法定相続分)=1,750万円 |
法定相続分に応じた各人の相続税を計算する
次に、法定相続分に応じた各人の相続税額を以下の速算表を用いて計算します。
相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
上記速算表で各人の相続税額を計算すると以下の通りです。
法定相続分に基づいた各人の相続税額
| 妻 | 3,500万円×20%-200万円=500万円 |
| 長男 | 1,750万円×15%-50万円=212.5万円 |
| 次男 | 1,750万円×15%-50万円=212.5万円 |
各人の相続税額を足し合わせて「相続税の総額」を求める
最後に、法定相続分に基づいた各人の相続税額を足し合わせて、相続税の総額を求めます。
計算例の場合、妻500万円+長男212.5万円+次男212.5万円=925万円となります。
なお、相続放棄者がいる場合、相続放棄したとしても「放棄はなかっ��たもの」として扱われます。
各人の納税額を計算する
相続税の総額を求めたら、実際の相続財産の配分割合に応じて納税額を計算します。
例えば、妻が40%、子どもがそれぞれ30%だった場合、それぞれの納税額は以下のようになります。
各人の納税額
| 妻 | 925万円×40%=370万円 |
| 長男 | 925万円×30%=277.5万円 |
| 次男 | 925万円×30%=277.5万円 |
このように、相続税の計算では一度相続税の総額を求め、そこから各人の配分割合に応じて納税額を計算する必要があります。
複雑ではありますが、自分で計算することも可能なので、相続を控えている方は一度シミュレーションしてみるとよいでしょう。
なお、この章の最後に法定相続分について簡単に説明しておきたいと思います。
法定相続分とは
法定相続分とは、法律に定められた相続財産を受け取る割合のことです。
法定相続分は、以下のように割合が定められています。
| 相続人の状況 | 配偶者 | 配偶者以外 | |
| – | 配偶者のみの場合 | 全額 | – |
| 第1順位 | 配偶者と子がいる場合 | 1/2 | 子1/2 |
| 第2順位 | 配偶者と親がいる場合 | 2/3 | 親1/3 |
| 第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹がいない場合 | 3/4 | 兄弟姉妹1/4 |
法定相続分は、配偶者以外の相続人について、子がいる場合は子(第1順位)が対象になり、子がいない場合で親がいると親(第2順位)が対象に、子も親もいなくて兄弟姉妹もいると兄弟姉妹(第3順位)が対象になるといった仕組みになっています。
また、配偶者以外の相続人については、同順位の相続人が複数いる場合、その人数で法定相続分を分けることになります。
例えば、いくつか具体例を挙げると以下のようになります。
| 妻と子2人 | 妻1/2 | 子1/2×1/2=1/4ずつ |
| 妻と両親 | 妻2/3 | 親1/3×1/2=1/6ずつ |
| 兄弟姉妹4人のみ | – | 兄弟姉妹1/4ずつ |
不動産の相続税を下げる方法
不動産は、現金と比べて評価額を下げることができることをお伝えしましたが、それ以外にいくつかの方法を活用することで、相続税を下げることができます。
それぞれについて、見ていきましょう。
※なお、被相続人の生前に対策できるものを<生前>、死後の対策となるものを<相続後>と表記しています。
<生前>養子縁組するなどして基礎控除額を拡大する
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に応じて以下のように定められている旨をお伝えしました。
このことから、生前に養子縁組するなどして法定相続人の数を増やせば、基礎控除額を大きくすることができます。
ただし、いくつかの注意点があります。
養子を法定相続人の数に含める際の制限
養子を法定相続人の数に含める場合、被相続人(亡くなった方)に実子がいる場合1人まで、実子がいない場合2人までが上限となっています。
| 実子 | 養子の数の上限 |
| あり | 1人まで |
| なし | 2人まで |
実子と認められる養子
また、以下のような要件を満たす養子は実子として数えることができます。
- 特別養子縁組で養子となった人
- 配偶者の実子で養子となった人
- 結婚前に配偶者と特別養子縁組を組んだ養子で、結婚後に被相続人(亡くなった方)の養子となった人
なお、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があり、以下のように異なります。
| 特別養子縁組 | 普通養子縁組 | |
| 目的 | 子どもの福祉や利益を図るため | 親のため(家存続のため等) |
| 養親 | 夫婦のいずれかが25歳以上の婚姻している夫婦 | 成人以上/独身可 |
| 養子の年齢 | 申立て時に6歳未満 | – |
| 実父母の同意 | 必要 | 親権者の同意が必要 |
| 養子縁組の理由 | 実父母による教育が困難 子どもの監護が不当 | – |
| 手続き | 6カ月の試験養育期間と家裁の審判が必要 | 契約により成立 |
| 離縁 | 養親からの離縁不可 | いつでも可 |
| 実父母との血縁関係 | 終了する | 存続する |
| 戸籍 | 実子 | 養子 |
一般的に、「基礎控除額を引き上げる」目的で養子縁組するのであれば、普通養子縁組を選択することになるでしょう。
生命保険金や死亡退職金の非課税限度額も増える
法定相続人の数が増えると、相続税の基礎控除額だけでなく、以下の3項目について節税効果を期待できます。
- 生命保険金の非課税限度額
- 死亡退職金の非課税限度額
- 相続税の総額の計算
生命保険金の非課税限度額は、死亡保険金に相続税がかかる際に設けられるもので、以下の計算式で求められます。
また、死亡退職金についても非課税限度額がありますが、こちらも生命保険金の非課税限度額と同様、以下のように計算されます。
さらに、相続税の計算では、計算過程で相続税の総額を計算しますが、このとき、相続財産を法定相続人のそれぞれの相続分に一度分けて計算します。
基本的に、相続税は相続する額が大きい程税率も高くなるため、法定相続人の数が増えて分ける数が増えれば、それだけ税率が下がる可能性は高くなります。
法定相続人を増やせば、相続税の基礎控除額だけでなく、これら全てについて節税効果を得られるということになります。
<生前>賃貸に出して評価減を受ける
不動産は他人に貸して家賃収入を得ることもできます。
他人に貸した状態の不動産を相続した場合、相続人は新しく賃貸オーナーとなりますが、自分ですぐに住めるわけではありません。
このことから、相続時点で他人に貸していた土地は、そうでない土地と比べて評価減を受けることができます�。
ここでは、話を分かりやすくするため以下の3つに分けてそれぞれの評価額の計算方法を見ていきましょう。
- 自己所有の土地の上に自己所有の家が建っている場合:自用地
- 自己所有の土地を他人に貸し出し、その上に他人の建物が建っている場合:貸宅地
- 自己所有の土地の上に自己所有の建物があり、建物を他人に貸している場合:貸家建付地
自用地
自用地は、自己所有の土地の上に自己所有の家が建っているケースです。
普通のマイホームを相続したと考えるとよいでしょう。
この場合、通常通り不動産の評価を行います。
貸宅地
貸宅地は、自己所有の土地を他人に貸し出し、その上に他人の建物が建っているケースです。
土地を借地していると考えるとよいでしょう。
貸宅地は以下のように計算します。
なお、借地権割合は土地のあるエリアによって異なり、路線価図や倍率表で確認できます。
例えば、土地の評価額が1億円、借地権割合が70%のエリアであれば、貸宅地の評価は以下のようになります。
貸家建付地
貸家建付地は、自己所有の土地の上に自己所有の建物があり、建物を他人に貸しているケースです。
戸建てを他人に貸したり、賃貸アパートや賃貸マンションを所有していたりするケースを考えるとよいでしょう。
貸家建付地は以下のように計算します。
借地権割合はエリアごとに異なる数値が定められていますが、借家権割合は国税庁が公示する財産評価基本通達によって一律30%と定められています。
また、賃貸割合は建物のうちの一部を自己居住用としていたような場合にその分を差し引くものです。
例えば、土地の評価額を1億円、借地権割合を70%、賃貸割合を100%とした場合、以下のように計算できます。
このように、建物を他人に貸している場合、不動産の評価額よりさらに2割程度評価額を減らすことができる計算となりました。
<生前>生前贈与を活用する
相続財産は、原則として、被相続人(亡くなった方)の相続発生時の財産に対して課される税金です。
このため、生前から財産を他人に贈与しておくことで相続財産を減らすことが有効となることがあります。
以下、それぞれを活用した節税対策について見てみましょう。
暦年課税の110万円基礎控除を活用する
贈与税には毎年110万円の基礎控除枠が設けられています。
つまり、1年間につき110万円までであれば贈与しても課税されないで済む�ということです。
この制度を活用して、数年~十数年の間、毎年110万円ずつ贈与することで相続財産を減らしていくという節税対策を取ることができます。
ただし、この方法を取る場合、贈与契約書を作成したり、いつ贈与したか記録に残したりといった作業が必要となります。
場合によっては、税務署に指摘されて遡って課税されることもあるため、税理士など専門家の手を借りて手続きを進めるようにしましょう。
相続税精算課税を活用する
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫へ相続する際選択できる制度で、一度選択すると2,500万円までについての贈与が非課税となります。
相続時精算課税制度の適用を受けて贈与した財産については、相続時にその他の相続財産と合算して計算しますが、相続時精算課税制度で贈与した財産は贈与時の時価で計算するため、贈与時より相続時に評価が高くなっているものを贈与することで節税効果を得ることができます。
例えば、贈与時には1,000万円の価値のものが、相続時に2,000万円に値上がりしていたような場合でも、1,000万円の評価額で計算できます(このように確実に値上がりする財産はあまりないかもしれませんが…)。
また、上記節税効果以外にも、例えば賃貸アパートを生前に贈与する場合、賃貸アパートから受け取れる家賃は相続人のものになるため、相続財産が増えることを防ぐとともに、相続人の納税資金の準備に役立てるといったことが可能となります。
ただし、一度相続時精算課税制度を選ぶと、暦年課税に戻ることはできない点に注意が必要です。
<生前>住宅取得等資金の非課税制度を活用する
住宅取得等資金の非課税制度とは、2026年12月31日までの間に18歳以上の人がマイホームを新築、取得、増改築するための資金を父母や祖父母などの直系尊属から贈与された場合、一定額が非課税となる制度です。
省エネ住宅は1000万円、それ以外の住宅は500万円まで贈与税が非課税となります。
土地の(実質的な)贈与にも使える
住宅取得金等非課税制度は、マイホームの取得に充てる「金銭」のための非課税制度です。
一方、以下のように手続きすることで実質的に土地を贈与するのにも使うことができます。
- 親から子へと土地を売却する売買契約書を締結する
- 親から子へマイホーム取得資金として売買額と同程度の贈与をする旨の贈与契約書を作成する
- 親から子へマイホーム取得資金を贈与する
- 子から親へ土地の購入額を支払う(3.と4.は逆でも可)
※上記のように手続きできるのは、実際にマイホームを建てる場合に限ります。
こうすることで、実質的なお金の動きはなく、土地の所有権は親から子供に移転します。
とはいえ、制度としては金銭の贈与のための非課税制度のため、実際に金銭を贈与したことが分かる通帳を残しておくようにしましょう。
また、税務署により対応が異なる可能性があるため、実施するのであれば税理士と相談の上進めることをおすすめします。
<相続後>小規模住宅地等の特例を活用する
小規模住宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった方)と一緒に住んでいた方が土地を相続した場合、土地の面積のうち330㎡までの分について、80%の減額を受けることができるというものです。
例えば、1億円の土地で、その面積が330㎡以下であれば、8,000万円もの節税効果を得られます。
なお、仮に土地の面積が500㎡だった場合、330㎡分までについて80%の減額を受けられ、残りの170㎡は減額を受けられません。
- 1億円×(330㎡÷500㎡)×(1-80%)=1,320万円
- 1億円×(170㎡÷500㎡)=3,400万円
- 合計:1,320万円+3,400万円=4,720万円
相続人が複数いる場合、該当の土地を相続する相続人が、被相続人(亡くなった方)と「同居していたかどうか」で本特例の適用を受けられるかどうかが決まります。
全体から(もしくは同居していた相続人から)見ると、遺産分割協議で、被相続人と同居していた相続人に不動産を相続してもらうよう取り決めするのがよいこととなりますが、そのことにより不公平が生じてしまうこともある点は留意する必要があるでしょう。
不動産相続の税金における注意点
不動産相続時の税金について、以下のようなことに注意しましょう。
生前から売買契約書などがどこにあるか確認しておこう
相続人が、相続した不動産を将来的に売却する場合、売却して得た利益には譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税は、以下のように計算されます。
納税額=課税譲渡所得×税率
この中で重要なのが取得費です。
取得費とは、売却した不動産を取得したときに要した費用のことで、相続不動産の場合は、被相続人が購入したときに要した費用を適用することができます。
取得費の額を証明するには、売買契約書や当時の領収書などの書類が必要となるため、不動産を相続する予定の人は、生前からそれらの費用がどこに保管されているのか確認しておくとよいでしょう。
もしこれらの書類がない場合には、取得費は概算法といって、売買価格の5%しか計上できなくなってしまいます。
相続人が複数いる場合、換価分割がおすすめ
相続人が複数いる場合、相続財産の分け方については以下の3つの方法があります。
- 現物分割:相続財産を現物のまま相続する
- 代償分割:多く相続した相続人が他の相続人に対して現金を支払う
- 換価分割:相続財産を売却して得た代金を分配する
この中でおすすめなのは換価分割です。
相続財産の中に不動産があると、誰がその不動産を相続するかでもめることが多いですが、換価分割では不動産を売却して現金にするため、公平に配分できます。
ただし、相続財産を売却するとなると、相続人の誰かが中心となって動き、その売却方法等に不満のないよう進める必要があります。
こうしたときには、依頼する業者やタイミングによって大きく価格の異なる仲介売却より、不動産会社に直接買い取ってもらう買取の方が話も進みやすく、他の相続人からの賛同も得られやすくおすすめです。
「イエウリ」では売主と買取業者のマッチングサービスを提供しており、登録した物件に対して1週間程度で複数の買取会社から査定を受け取る事ができます。また、オークション形式を取り入れていることから買取業社間で査定額の価格競争が起こり、より高い価格での売却を目指しやすいシステムになっています。
納税資金を準備できないときはどうする?
不動産を相続すると、その評価額に応じた税金を納める必要があります。
税金は基本的に現金で納める必要があり、不動産を相続するのであれば、その納税資金をしっかり準備しておかなければなりません。
しかし、どうしても納税資金を用意できないこともあるでしょう。
そのような場合、どのようにするとよいのでしょうか。
延納��・物納
財産を相続したものの、その相続税を納税できない場合には、以下の要件を満たす場合に限り、延納(年賦)することができます。
- 相続税が10万円超であること
- 担保を提供すること
- 相続税の納期限日までに延納申請書を提出すること
また、延納によっても相続税を納付することが困難である場合に限り、一定の相続財産による物納(不動産による物納など)も認められています。
売却する
相続した不動産の納税資金の準備がどうしても難しいようであれば、売却して納税資金を作るのもよいでしょう。
相続税の納税は、相続開始から10カ月後までが期限となっているため、こちらの場合でも、話がまとまればすぐに売却できる「イエウリ」買取マッチングサービスの利用をおすすめします。
トラブルを防ぐために遺言書を書いてもらっておこう
相続発生後、その相続財産をどう配分するかについて、相続人全員で集まって遺産分割協議をする必要がありますが、原則として、遺言書があれば遺言書通りに配分し、遺産分割協議を開く必要もありません。
被相続人(亡くなった方)の財産なのですから、被相続人の意向であれば、よっぽど不公平な内容でなければ相続人間で不満が生じることも少ないでしょう。
相続人となる方は、生前から遺言書を書いてもらうよう話をしておくと共に、その保管場所についても話を聞いておくようにしましょう。
相続税を節税したいなら相続税専門の税理士に相談しよう
ここまで相続税の計算方法や節税方法、注意点についてなどお伝えしてきました。
相続税の計算方法や節税方法については、自分で知っておくことも大切なことですが、基本的には、専門的な知識を持って総合的に判断してくれる税理士に相談しながら進めるようにしましょう。
2015年相続税法改正で基礎控除枠が縮小
相続税の基礎控除額が3,000万円+(600万円×法定相続人の数)であることはすでにお伝えしましたが、実はこの基礎控除額は2015年に縮小されたものです。
2015年より以前の相続税の基礎控除額は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)でした。
これにより、これまで相続税を納める必要のなかった一般的な家庭においても、相続税を納付しなければならないケースが多くなっています(国税庁のデータによると、課税割合は2014年4.4%から2015年8.0%に上昇)2。
これまで以上に相続税に対する対策が必要になってきたと言えるでしょう。
相続税を少しでも節税したいなら相続税専門の税理士へ
相続税は、どの制度を活用するかや、どのように配分するかによって、大きく納税額が変わることがあります。
こうしたこともあり、少しでも相続税を節税したいのであれば税理士に相談することもおすすめします。
また、単に税理士といっても専門分野が異なるため、相続について税理士に相談するのであれば相続専門の税理士を探して相談するようにしましょう。
まとめ
相続における不動産の評価方法や相続税の計算方法、不動産を相続する際の節税方法や注意点などお伝えしました。
不動産を活用した相続税の節税対策にはさまざまな方法があり、それぞれにメリットや注意点があるため、基本的には相続専門の税理士に相談しながら進めることをおすすめします。
また、場合によっては不動産を売却して相続人間で配分したり、納税資金に充てたりすることがあるでしょう。
そうしたときには、興味を持ってくれた不動産会社と直接交渉ができ、話がまとまればすぐに売却できる「イエウリ」を活用すると便利です。