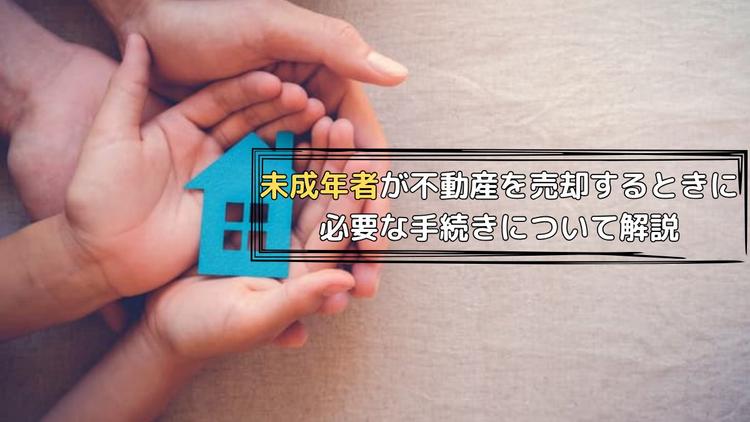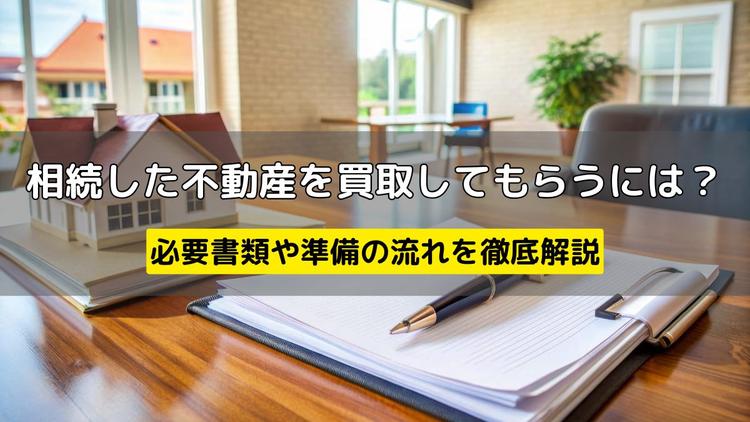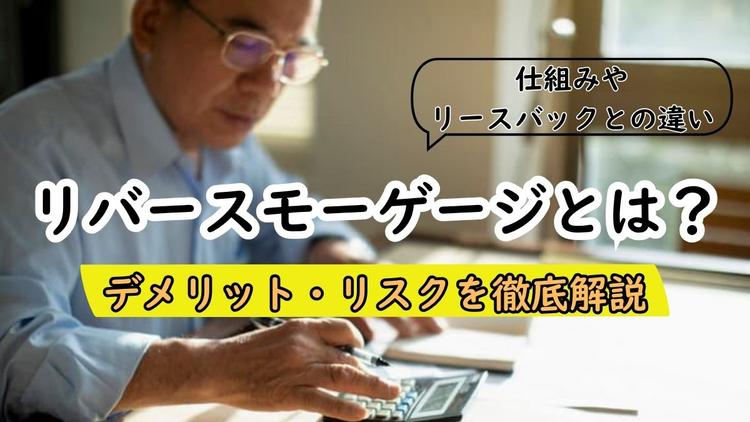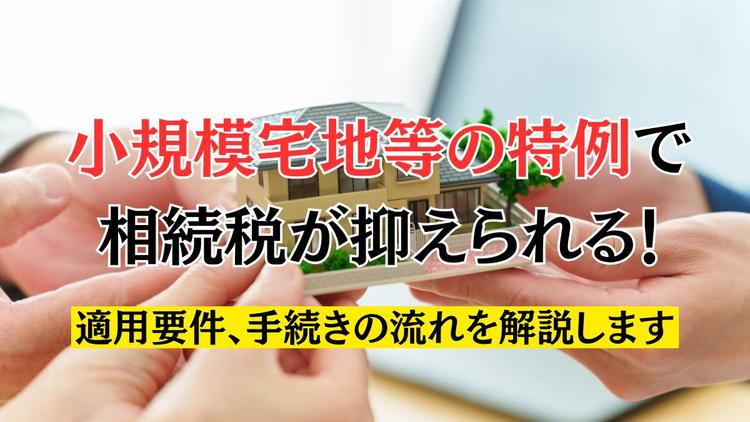不動産の名義変更をする方法として、生前に選択できるのが、譲渡と贈与です。それでは、親から子に不動産を引き継ぐ場合、どちらの方法を選択すればいいのでしょうか。いずれのケースも税金が発生しますが、経済状況や家族構成などによって、選択すべき方法は異なってきます。
この記事では、譲渡と贈与の違いを明らかにするとともに、手続き上の注意点や関連する税金について解説をします。
不動産を渡す(名義変更する)方法は大きく分けて3つ
不動産を他者に渡す方法は、大きく分けて「譲渡」「贈与」「相続」の3種類に分けられます。それぞれの特色を挙げると、次の通りです。
- 譲渡……売買や交換のように何らかの対価を受け取って不動産の権利を譲り渡すこと
- 贈与……無償で不動産の権利を譲り渡すこと
- 相続……亡くなった人の不動産の権利を特定の人が引き継ぐこと
不動産の名義変更は、法務局に必要書類を提出して手続きを進めますが、無条件に受理されることはありません。必ず、不動産移転の「原因」とそれを裏付ける資料が必要です。また原因に基づく、税金対策も必須です。
不動産の譲渡をするにあたって、どの方法を選択すればいいのか。その手掛かりをつかむために、それぞれの方法の違いを比較してみましょう。
「譲渡」と「贈与」の違い
贈与とは、親族や第三者に不動産を無償で譲り渡すことをいいます。法律上では、贈与は、無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生じます(民法549条)。この場合の意思表示と承諾は、書面に限らず口頭でも可能です。
一方、譲渡は対価を受け取って不動産を譲り渡すことをいいます。つまり、譲渡と贈与は対価の有無に大きな違いがあるのです。
不動産会社を仲介して不動産を売却する場合などが譲渡にあたります。親子間であっても譲渡は可能ですが、有償で売買をしたことを示すために、一般の売買と同様に売買契約書を締結するとともに、銀行の振込履歴などにより、金銭が動いた痕跡を残すことが求められます。
「相続」と「贈与」の違い
相続とは、ある人が亡くなったときに、その財産を特定の人が引き継ぐことをいいます。さらに相続の方法によって、「法で定められた配分による相続(法定相続)」「遺言による相続」「遺産分割協議による相続」の3種類に分類できます。
一方、贈与は、生前に本人の意思で特定の人に無償で譲ることをいいます。つまり、相続と贈与は、財産の譲り渡しが所有者の死後なのか生前なのかに違いがあるということです。また、贈与は確実に意中の人に不動産を渡せるのに対して、相続の場合、遺言を残さない限り、不動産が誰のものになるかは、判然としません。
不動産を「譲渡」するときのポイント
不動産における譲渡とは、売却や交換のように何らかの対価を受け取って土地や建物の権利を譲り渡すことをいいます。たとえ親子であっても、対価が支払われれば売買とみなされます。ここでは不動産を譲渡する際の注意点について見ていきましょう。
注意点:「所得税」と「住民税」を支払う必要がある
所有している土地や建物を売却して得た利益を譲渡所得といいます。譲渡所得には、一般的に「譲渡所得税」と呼ばれる所得税や住民税がかかります。
「所得税」と「住民税」の計算方法
不動産の譲渡所得にかかる所得税と住民税の税額は、次の計算式で課税の対象になる譲渡所得金額を求め、所有期間に応じた税率を乗じて計算します。
「収入金額」は売却金額、「取得費」は購入したときの金額とそのと�きの諸費用の合計、「譲渡費用」は売ったときの諸費用です。
税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって異なります。
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」に分類されます。それぞれの税率は次のとおりです。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 | 30% | 9% |
投機的な不動産の売買を抑制するために、短期譲渡所得の税率が高く設定されています。
不動産を「贈与」するときのポイント
不動産における贈与とは、無償で土地や建物の権利を譲り渡すことをいいます。不動産の名義人が存命の間に不動産を親族や第三者に贈る「生前贈与」の方法が一般的です。
また遺言により法定相続人以外の第三者へ不動産を贈与する「遺贈」という方法が用いられることもあります。ここでは、不動産を贈与する際の注意点について解説します。
注意点①贈与税を納める必要がある
不動産は一定の価値があるため、贈与があれば基本的に贈与税が発生します。このため、環境や状況によっては、不動産の贈与に向いていない人もいます。
�不動産の贈与に向いていない人は、ただ単に「不動産の名義を変更したい」という人です。変更した後に発生する税金のことを考えると、贈与税として納めるよりは、相続税の方が安く収まるからです。後述する所有権移転手続きに係る手鵜六免許税も相続の方が安くなります。
一方、不動産の贈与に向いている人は、贈与税や取得税を支払ってでも、不動産の所有者を変更する必要がある人です。
たとえば、収益不動産から発生する家賃収入を子供の収入としたい場合や相続が発生すると相続人同士でもめることが予想されるために、特定の相続人に不動産を引き継いでもらいたいといった事情がある場合には、不動産の贈与を選択した方が望ましいです。
注意点②登録免許税を納める必要がある
登記記録を変更する際には登録免許税を申請と同時に納める必要があります。登録免許税は、変更の原因によって、次のように異なります。
- 売買 ……不動産の価額×2%
- 相続……不動産の価額×0.4%
- 贈与……不動産の価額× 2%
贈与の場合には、相続の場合の5倍もの税金がかかります。
「贈与税」の計算方法
贈与税は財産を譲渡された人が支払う税金です。贈与税の計算は、まず「1年間に贈与を受けた財産の合計額」から「基礎控除110万円」を差し引いて「基礎控除後の課税価格」を算出します。
これに対応した税率を乗じますが、贈与税は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」によって税率と控除額が異なります。
一般贈与財産が適用されるのは、次のような贈与の場合です。
- 直系尊属以外の親族(配偶者、配偶者の親や兄弟姉妹など)や他人から贈与を受けた場合
- 直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が贈与を受けた年の1月1日現在において20歳未満の者の場合(20歳未満の子どもや孫などの場合)
たとえば、親子などの親族関係ではない、一般的な個人同士で贈与される場合には「一般贈与財産」に該当します。
一般贈与財産における税率と控除額は次のとおりです。
【一般贈与財産】
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | --- |
| 300万円以下 | 15% | 10万円以下 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円以下 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円以下 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円以下 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円以下 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円以下 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円以下 |
特例贈与財産は、直系尊属(祖父母や父母など)から、20歳以上の者(子・孫など)への贈与が適用されます。
特例贈与財産における税率と控除額は次のとおりです。
【特別贈与財産】
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | --- |
| 400万円以下 | 15% | 10万円以下 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円以下 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円以下 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円以下 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円以下 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円以下 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円以下 |
特例贈与財産は、一般贈与財産よりも税率が低く、かつ控除額が高く設定されており、優遇されています。
不動産を「相続」するときのポイント
不動産の相続とは、亡くなった人の土地や建物の権利を特定の人が引き継ぐことをいいます。相続で不動産を引き継ぐ際の注意点について解説していきましょう。
注意点①相続税を納める必要がある
土地を相続した場合、土地を含めた相続財産の総額が「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えると、相続税の申告が必要です。
たとえば、相続人が妻と子ども2名の場合は、相続財産が4,800万円を超える場合、相続税の課税対象です。
注意点②登録免許税を納める必要がある
相続を原因として名義の変更を行う際には、不動産価格の0.4%が課税されます。登録免許税は原因によって税率が異なり、贈与の場合は2%が課税されます。
「相続税」の計算方法
相続で不動産を譲り受けた相続人は、不動産を含めた相続財産の額に応じて、相続税を納めます。相続税の税額は、次の計算式で相続税の課税対象になる課税遺産総額を求め、金額に応じた税率を乗じて計算します。
課税遺産総額=正味の相続財産-(基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人の数)
課税遺産総額に乗じる税率
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | --- |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円以下 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円以下 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円以下 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円以下 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円以下 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円以下 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円以下 |
相続税は、贈与税と比較して税率が低く設定されています。また、そもそも控除額が大きいため、税額は大きく軽減されます。
不動産の名義変更で「贈与税」が発生するケースに要注意
不動産を手放すときに注意をしたいのが、有償で売却したにもかかわらず、相手方に贈与税がかかることがあるということです。どのような売却をした場合に、贈与税の対象になるのかについて解説します。
「みなし贈与」に当てはまるケース
親子だからということで、相場の価格よりも著しく低い金額で不動産を購入した場合、贈与税の対象になることがあります。
たとえば、5,000万円の市場価値がある不動産を買主が100万円で購入した場合は「みなし贈与」とみなされ、差額の4900万円が贈与税の対象になります。
親族に不動産を引き継ぐ際に、贈与税を回避するために、契約書を締結して売却という体裁を整えたとしても、結局贈与税を納めることになるのです。
��「借金の免除」を受けたケース
市場価値と同等の金額で親族に売却し、売主に利益があれば、「不動産譲渡所得税」が課税されることになります。しかし、現実に支払いの痕跡がないと、「ダミーによる売買」や「債務を免除された取引」と税務署にみなされ、不動産を購入した人が贈与税の対象になることがあります。
売買をした限りは、銀行振込などの記録を残すのは当然のこととして、さらにその資金を捻出した根拠を示す必要があります。実際に、購入した家に住むのであれば、住宅ローンの融資を受けたうえで、親の家を購入することで、売買実績の確かな裏付けになります。
「実質タダ」で不動産を渡すケース
金銭のやりとりがなく不動産の名義変更がおこなわれると、新たに土地の所有者になった人に贈与税がかかります。
親族間であれば、両者の合意だけで不動産の登記(名義)は自由に変更することができます。しかし税務署は、法務局より、定期的に登記情報を入手していますから、きちんと税金が納められたか否かの確認をします。そのうえで、税金が未納であったり、納付されても極端に金額が低い場合、物件の所有者に対して、「お尋ね」という文書を送達します。
「お尋ね」では、次のような質問事項が記載されています。
- 不動産の購入(取得)価格
- その支払い方法
- 購入資金の調達方法(手段)
この回答によって、事実上無償で不動産を譲り受けたことが明らかになった場合は、贈与税が課税されることになります。また状況によっては、延滞税等のペナルティが加えられることがあります。
身内間の名義変更だからといって税務署が看過することはありません。贈与税や相続税の徴収に直接関わる案件ですから、むしろ、金銭のやり取りについては、一般の取引以上に目を光らせていると考えるべきでしょう。
「扶養義務以上」の援助を受けたケース
民法において、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある(877条1項)」とされています。このため、贈与税の基礎控除110万円とは別に、扶養義務の範囲内と考えられる財産の援助であれば、贈与税はかかりません。つまり、食費や教育費などの妥当な範囲であれば課税をされることはありません。
しかし、不動産をプレゼントするのは妥当な範囲を超えているため、贈与税の課税対象になります。
不動産の名義変更で税金を軽減する方法
不動産の名義を変更すると、何らかの形で税金の対象になります。しかし、譲渡や相続では、控除制度があるため、これを活用することで大幅な節税ができることがあります。どのような方法があるのか紹介します。
①贈与額を年間110万円以内にする
不動産をそのまま親族に贈与するのではなく、いったん第三者に売却して得た現金を贈与するという方法があります。この場合、1人に対して年間110万円ずつ生前贈与をしていくことで、贈与税の対象から外れます。
ただし、現金の贈与に関しては、何らかの記録に残しておくことを失念してはいけません。送金の記録を銀行振込などで形に残したり、贈与契約書を作成したりすることで、たしかに110万円以内で贈与を行ったことを証明できるようにしておくことが必要です。
�注意したいのは、こうした毎年の贈与が必ずしも暦年贈与として扱われるわけではないということです。たとえば、最初に2,200万円の贈与をする約束をして、毎年110万円を20年間にわたって贈与したような場合は、連年贈与と見なされ、約束をした年あるいは最初の履行があった年にまとめて贈与税が課税されることになります。
このため、毎年違う時期に、毎年違う金額を贈与するといった、当初に約束のないその年単発の贈与であることを誇示する工夫をした方が安心です。
また相続開始の3年以内の贈与は、暦年贈与として非課税となっていても、遡って相続財産に加算されるため注意が必要です。
②「相続時精算課税制度」を利用する
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への親族間生前贈与に対して、譲り受ける者の選択により利用できる制度です。
生前贈与があったときにこの制度を活用すると、控除額によって軽減された贈与税を支払うことができます。適用される控除額は2,500万円です。2,500万円を超えると、超えた金額に対して一律20%の贈与税が課せられます。
その後、贈与者が亡くなれば、相続する際に、贈与された財産と贈与者の相続財産を合計した価額を基に相続税額を算出します。その中から既に支払った贈与税額は差し引いて、残りの金額を相続税として納付します。
つまり、この制度は、贈与税が軽減されたり、非課税になったりするのではなく、相続する時に相続財産と合わせて清算するという仕組みです。贈与税の扱いは形式に過ぎず、最終的には相続税として税金を納めるのです�。
また「相続時精算課税制度」と暦年贈与は、どちらか一方しか適用できません。暦年贈与から、「相続時精算課税制度」への切り替えは可能ですが、一度「相続時精算課税制度」を選択すると、もう暦年贈与に戻すことはできませんから、制度の活用に際しては、時期を慎重に見極める必要があります。
③「夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」を利用する
「夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」は、結婚から20年以上経った夫婦が受けられる控除です。結婚から20年が経過していることを条件に、居住用の不動産を贈与した場合、2,000万円まで控除を受けることができます。この控除は、基礎控除110万円に追加される控除ですから、この年は併せて2,110万円の控除が適用されます。
ただし、控除を受けられるのは夫婦1組につき一度限りです。
まとめ
不動産を他者に渡す方法は、大きく分けて「譲渡」「贈与」「相続」の3パターンがあります。このうち、不動産の所有者が生前に選択できるのが、譲渡と贈与です。
不動産を親子で引き継ぐ場合、できれば無償で渡したいと多くの方が考えています。しかし、そこには贈与税という壁が立ちはだかっているために、譲渡という選択をするケースがあります。
譲渡では、実際に現金のやりとりがありますから、不動産を譲り受ける子ども自身が資金を持ち合わせているか、住宅ローンの融資を受けることになります。一方で、親が手にした現金は、やがて相続財産となりますから、相続人が複数いる場合、家を譲り受けた人の負担だけが残るという事態にも陥りかねませ�ん。
このため、親子で不動産を譲渡した場合、実際に資金を負担した子どもに対するケアも忘れてはいけません。不動産を譲渡した親は、法定相続に委ねるのではなく、遺言書によって、遺産の配分を指定するといった配慮が必要です。
あるいは、暦年贈与によって、不動産購入資金を少しずつ、子どもに還元するといった工夫も効果的です。