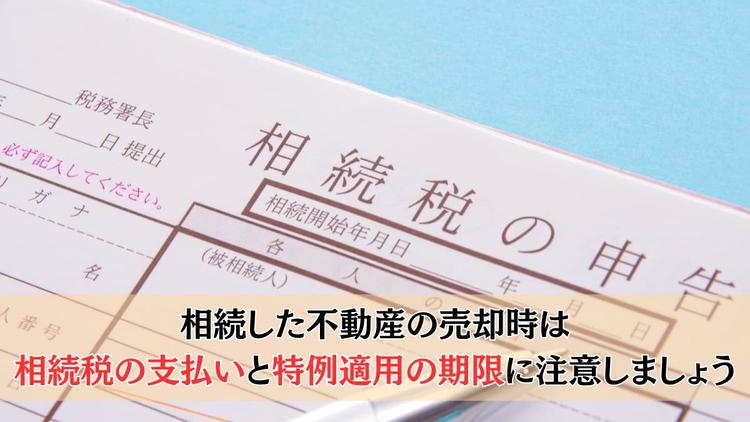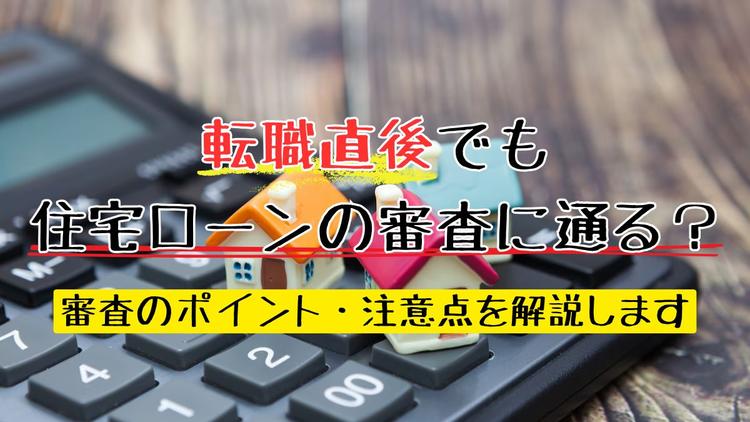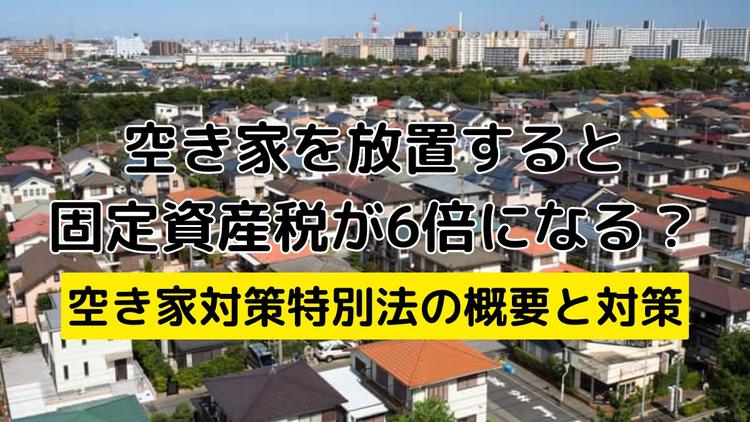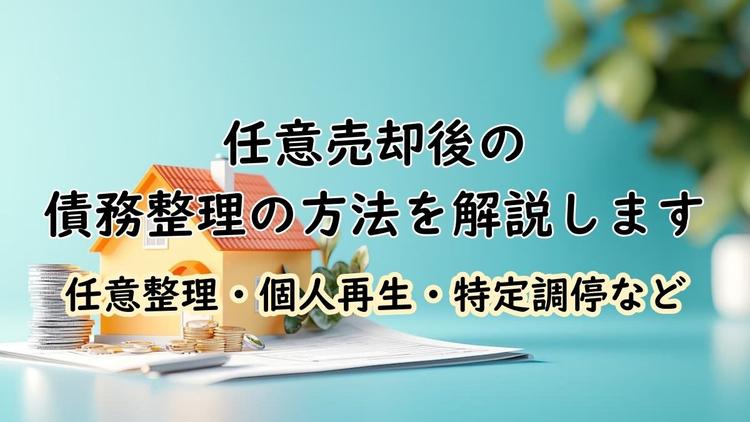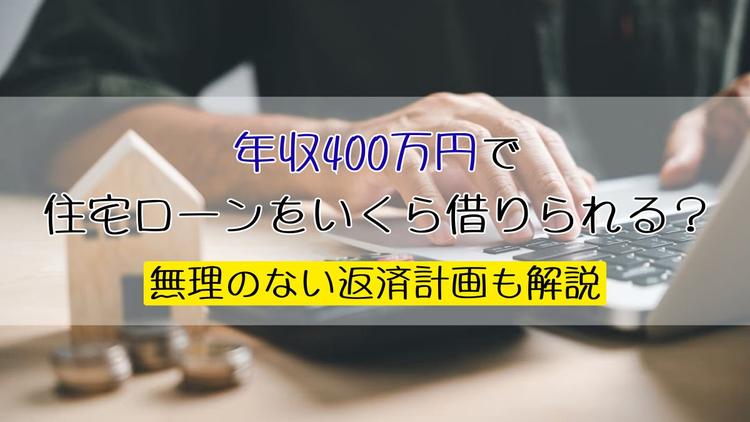「相続した不動産をいつ売ればいいだろう?」と悩んでいる方もいるでしょう。
相続した不動産の売却タイミングを決める基準に「相続税」と「特例適用」の期限があります。
タイミングを誤ると納税できない、税負担が大きくなるなど不都合が生じる恐れがあるので、適切なタイミングを理解しておくことが重要です。
この記事では、相続した不動産の売却期限について詳しく解説します。
相続した家の売却は相続税の支払い期限や税制優遇の期限を押さえておこう
実家を相続したものの活用予定がないという場合は、家を売却することが有効な選択肢になります。
相続した家は相続登記を終えれば、いつ売却しても問題なく、いつまでに売却しなければならないという期限もありません。
そのため、固定資産税などの負担を避けたいから早く売却したい、活用の余地を検討したい、地価が上がりそうだから売却を遅らせたいなど、個々の事情に応じたタイミングで売却を進めることができます。
ただし、家を売却したお金で相続税を支払いたい場合や、売却益にかかる税金の特例を適用したい場合では、売却までに期限が生じます。
これらの特例は期限を過ぎると適用できなくなり、大きな損につながる可能性があるため、事前に確認しておくことが重要です。
また、そもそも家を相続したくないというケースでも、相続放棄の手続きには期限があるので注意しましょう。
家の相続、相続後の売却で期限が生じる要因とその期限には、主に以下の4つがあります。
- 【相続開始の翌日から3ヶ月】相続放棄の期限
- 【相続開始の翌日から10ヶ月】相続税の納税期限
- 【相続開始から3年を経過する年の年末】被相続人の空き家を売ったときの3,000万円特別控除
- 【相続開始の翌日から3年10ヶ月】取得費加算の特例
なお、相続放棄と相続税の期限は、厳密には「相続開始があったことを知った日の翌日」が起算日です。
相続開始の日とは、基本的に被相続人(故人)が亡くなった日を指します。
それに対し、相続開始があったことを知った日とは、被相続人の死亡を知った、かつ自分が相続�人であることを知った日を指します。
一般的な相続では、被相続人が亡くなった日を相続人もすぐに知るため、「相続開始を知った日」は通常、死亡日と同じ日になります。
ただし、たとえば被相続人と疎遠だったなどで死後しばらくして死亡を知った場合や、他の相続人が相続放棄したことで後から相続人になった場合などは、相続開始を知った日が死亡日と異なるケースもあります。
いつが起算日になるかは手続き上重要になってくるので、起算日に悩む場合は専門家に相談するようにしましょう。
以下では、それぞれの期限について詳しく解説していきます。
【相続開始の翌日から3ヵ月】相続放棄の期限
被相続人の死亡後最初に来る期限が、相続放棄の手続きの期限です。
実家を相続したくない場合、この期限までに手続きが必要になります。
相続には3つの方法がある
相続が発生した場合、以下の3つの選択肢から相続の仕方を選ぶことになります。
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
単純承認とは、被相続人の財産をプラスもマイナスもすべて相続する方法です。
一般的な相続といえば、単純承認を指します。
単純承認は、限定承認または相続放棄の手続きを行わなければ自動的に成立します。
限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスを負う相続方法です。
たとえば、現預金などのプラスの財産が500万円で借金が1,000万円の場合、限定承認することで500万円を超える部分の借金は負う必要がなくなります。
プラスの財産があり、なおかつマイナス��の財産を明確に把握できないケースなどで有効な手段ですが、実際に限定承認するケースは多くはありません。
単純承認・限定承認共に相続財産を継承する選択肢ですが、相続しない選択肢となるのが相続放棄です。
相続放棄とは、すべての財産の相続を放棄する方法です。
一般的に借金が明らかに多い場合で選択されますが、不動産を相続したくない場合も選択肢の1つとなります。
相続放棄するには裁判所に申し立てが必要となり、申し立てまでの期限は相続開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月です。
3ヵ月を超えると、基本的に相続放棄は認められません。
一方、期限内であればよほどのことがない限り相続放棄は認められます。
期限内であれば認められる相続放棄が、期限を超えたことで認められなくなる恐れがあるので、相続放棄を検討する場合は早い段階で手続きを進めるようにしましょう。
相続後は不動産を放棄することが難しい
相続前であれば相続放棄で不動産を所有しない選択肢を選べますが、一度相続すると不動産を手放すのは難しくなります。
相続後に手放す方法としては売却が一般的ですが、築年数が古い、立地が悪いなどでは売りたくても売れない可能性があるでしょう。
売却以外にも、無償譲渡や寄付と言った選択肢も検討できますが、あまり現実的ではありません。
たとえ売れなかったり、自分で活用する予定がなくても、相続し所有者となれば管理義務が生じます。
所有している限り固定資産税は毎年課税され、維持管理の手間や費用も必要です。
活用予定のない不動産を相続しても、相続後の負担が大きくなる恐れがある点は覚えておきましょう。
なお、相続しても活用予定のない土地であれば、相続土地国家帰属制度を利用して国に返却することが可能です。
しかし、この制度では建物が対象とならず、土地にも一定の条件があるため、利用できないケースがある点には注意しましょう。
▼関連記事:相続土地国庫帰属制度を利用するための条件を解説します
相続放棄すると不動産以外のすべての財産の相続を放棄する必要がある
相続放棄をする場合は、すべての相続財産を放棄する必要があります。
たとえば、「不動産は放棄して現預金は相続する」といった選択はできません。
そのため、不動産以外にプラスの財産や相続したい財産がある場合は、相続放棄は適していないでしょう。
また、一度相続放棄を選択すると、後から「やっぱり相続したくなった」という理由で取り消すこともできません。
まずは、相続財産の内容を明確にしたうえで、相続放棄が適切か慎重に判断するようにしましょう。
【相続開始の翌日から10ヶ月】相続税の納税期限
相続財産が相続税の基礎控除を超える場合、相続税が課税されます。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出できます。
たとえば、相続財産の総額が6,000万円で法定相続人が3人の場合、4,800万円が基礎控除となり、これを超えた1,200万円が相続税の課税対象となります。
相続税が課税される場合、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告・納税が必要です。
そのため、相続税を相続した不動産の売却金で支払おうと考える場合は、10ヵ月以内に売却する必要があります。
相続税は現金で納める必要がある
相続税は原��則として現金で納付する必要があります。
そのため、相続財産に不動産が含まれると、納税資金となる現金が不足する恐れがあるので注意が必要です。
たとえば、相続財産が不動産1億円と現預金1,000万円、相続税が2,000万円課税される場合では、現預金だけでは納税資金が足りません。
この場合、相続人は自己資金で納税するか、自己資金だけでは納税できないなら早期での不動産売却が必要になります。
実際には、相続財産が家と現預金がわずかというケースも珍しくないので、相続税が課税されたときに対応できるかを確認しておくことが重要です。
なお、相続税は金銭での納税が困難と認められると、相続財産自体で物納が認められるケースがあります。
ただし、不動産の物納では抵当権が設定されていない、境界が明確である、権利に争いがないなど一定の条件を満たすことが必要です。
物納を認めてもらうのは容易ではないので、納税資金が足りない場合はできるだけ早く売却するとよいでしょう。
納税期限を過ぎるとペナルティが課される
相続税を期限内に申告・納税できない場合、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される恐れがあります。
とくに延滞税は、期限を超えた日から納付が完了するまでの日数に応じて課税され、納税期限の2カ月後からは税率がさらに高くなるため、遅れるほど負担が大きくなる点に注意が必要です。
一方、たとえ期限を超えてしまった場合でも、1ヵ月以内に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は免除されます。
つまり、納税期限を超えてしまった場合でも��、放置せず、できるだけ速やかに申告・納税することが大切です。
申告期限を過ぎると各種税制優遇を受けられなくなる
相続税には、節税につながる控除がいくつか設けられています。
しかし、これらの控除は申告期限内の申告が適用条件となっている場合が多いため、期限を過ぎてしまうと控除が受けられず、税負担が大きくなる恐れがあるのです。
申告期限を過ぎることで適用できなくなる代表的な控除に、以下があります。
- 相続税の配偶者控除
- 小規模宅地の特例
配偶者控除とは、被相続人の配偶者であれば、相続した財産のうち「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで、相続税がかからない特例です。
たとえば、被相続人(夫)が亡くなり、妻と子どもが相続人である場合、妻の法定相続分は2分の1となります。
このとき、妻が相続する財産がその法定相続分か1億6,000万円のどちらか多い金額までであれば、相続税は非課税となります。
この制度の趣旨は、残された配偶者の生活を保護することにあります。
そのため、相続財産が大きい家庭でも、配偶者がある程度まとまった資産を相続しても、すぐに相続税が課されない仕組みになっています。
この特例を適用することで、配偶者に相続税が課税されることはほとんどありません。
一方、小規模宅地の特例は、一定の要件を満たす土地について相続税評価額を最大80%減額できる特例です。
小規模宅地等の特例が適用されると、相続した不動産の評価額が低くなるため、課税される相続税も少なくなる。
どちらも節税効果が大きいため、適用できないと税負担が大幅に増える恐れがあります。
なお、これらの控除を適用するためには相続税の申告が必要です。
たとえ相続税が課されない場合でも、特例適用のために申告手続きを忘れずに行いましょう。
▼関連記事:小規模宅地等の特例で相続税が抑えられる!適用要件、手続きの流れを解説します
【相続開始から3年を経過する年の年末】被相続人の空き家を売ったときの3,000万円特別控除
被相続人の空き家を売ったときの3,000万円特別控除とは、相続した不動産を売却した際の譲渡所得税の節税が見込める特例です。
相続した不動産を売却すると譲渡所得税が課される
相続だけに限りませんが、不動産を売却すると売却益に対して譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税の計算は以下のとおりです。
- 課税譲渡所得:売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
- 譲渡所得税:課税譲渡所得×税率
取得費とは、売却した不動産を購入した際にかかった費用です。不動産の購入代金だけでなく、仲介手数料や印紙税なども計上できます。
譲渡費用とは、売却した際にかかった仲介手数料や解体費用などの費用です。
これらの費用を差し引いた後に、さらに特別控除を適用して利益がプラスの場合、その金額に対して譲渡所得税が課�税されます。
譲渡所得税は、譲渡所得に以下のいずれかの税率を乗ずることで算出できます。
| 所有期間 | 所得税・復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 | |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
なお、相続した不動産などで取得費が不明な場合、概算の取得費として売却額×5%を計上します。
概算の取得費は本来の取得費より小さくなるため、利益が出やすく税負担も大きくなる点には注意しましょう。
一定の要件を満たすことで3,000万円特別控除の適用を受けられる
3,000万円特別控除は、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例です1。
これにより、売却額が3,000万円未満であれば、税金は発生しないことになります。
大きな節税効果が見込める特例ですが、適用には以下のような要件を満たす必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築されている
- 相続の開始の直前において被相続人以外に�居住をしていた人がいない
- 相続または遺贈により取得している
- 売却時に更地にするか一定の耐震基準を満たすようにする
- 売却代金が1億円以下である
- 買主と売主が夫婦など特別な関係でない
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却
築年数や売却時に解体もしくは耐震補強が必要など、適用条件のハードルが高い点には注意しましょう。
また、売却までの期限も相続開始から3年後の年末までとなっているので、適用を検討する際には早い段階で売却を進めることが大切です。
譲渡所得税における所有期間による税率の判定は被相続人が取得した日を適用できる
譲渡所得税の税率は、所有期間5年を境に短期譲渡所得と長期譲渡所得に分かれます。
5年以下の短期譲渡所得に区分されると長期譲渡所得の倍近い税率になるので、売却時には所有期間も考慮することが大切です。
なお、相続した不動産の場合、所有期間は相続人が相続してからの期間ではなく、被相続人が取得してからの期間で判断されます。
たとえば、被相続人が10年所有し、その後相続人が相続後1年で売却した場合、所有期間は11年となり長期譲渡所得となるのです。
そのため、相続した不動産では長期譲渡所得に該当するケースがほとんどでしょう。
しかし、被相続人が相続開始前5年以内に住み替えなどで取得していると短期譲渡所得になる可能性があるので、事前に所有期間を調べておく必要があります。
また、所有期間を判断する場合、売却した日ではなく売却した年の1月1日時点の所有期間が基準となる点にも�注意が必要です。
実際の所有期間が5年を経過していても、売却した年の1月1日時点で5年以下だと短期譲渡所得に区分されます。
【相続開始の翌日から3年10ヶ月】取得費加算の特例
譲渡所得税の節税につながる特例として、取得費加算の特例もあります。
取得費加算の特例を適用するには「相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日」までの売却が必要です。
納付した相続税額の一部を課税譲渡所得の取得費に計上できる
取得費加算の特例では、相続時に支払った相続税の一定額を、譲渡所得計算時の譲渡費用に加算できます2。
取得費を多く計上できることで利益が少なくなり、譲渡所得税の課税額を抑えることが可能です。
なお、取得費加算の特例を適用するには、期限以外にも「相続や遺贈により財産を取得した者であること」「その財産を取得した人に相続税が課税されていること」という要件を満たす必要があります。
そもそも、相続税を支払っていないケースでは適用できないので注意しましょう。
被相続人の空き家を売ったときの3,000万円特別控除と併用できない
取得費加算の特例は、前述した「相続空き家の3,000万円特別控除」とは併用できません。
�仮に、両方の適用要件を満たしている場合でも、適用できるのはいずれか一方のみとなるため、どちらを適用した方がより節税できるかをシミュレーションしたうえで検討することが大切です。
多くのケースでは、3,000万円特別控除を適用した方が有利になります。
ただし、相続税が高額だった場合などでは、取得費加算を適用した方が有利になるケースもあるので、注意しましょう。
どちらを適用したほうがいいか悩む場合は、税理士に相談することをおすすめします。
代償分割した場合取得費加算の特例の効果が薄くなる
代償分割とは、不動産を取得した相続人が他の相続人に対して代償金を支払う分割方法です。
たとえば、相続人が子ども2人で不動産の評価額が2,000万円の場合、それぞれの相続分は1,000万円ずつとなります。
このとき、どちらかの子どもが不動産を丸ごと相続し、もう片方に対して1,000万円を代償金として支払う方法が代償分割です。
代償分割で取得した不動産であっても、適用要件を満たすことで取得費加算の適用はできます。
しかし、代償分割で取得した場合、加算できる取得費の計算方法が本来の計算方法とは異なり、代償金を支払ってないケースよりも加算できる額が減少します。
結果として、譲渡所得税の節税効果が薄れてしまうので注意しましょう。
取得費加算の適用を検討している場合は、遺産分割協議の時点で不動産の分割方法を考慮する必要があるため、税理士などプロへの相談をおすすめします。
まとめ
相続した不動産を売却する場合、売却金で相続税を支払いたい場合�は10ヵ月以内、売却益にかかる譲渡所得税の特例を適用したい場合は3年または3年10ヵ月以内の売却が必要です。
とくに、相続税に間に合わせたい場合、売却までの期限が短くなるのでできるだけ早く売却に動くことが大切です。
仮に3年猶予がある場合でも、相続してから3年はあっという間に過ぎていくので注意しましょう。
相続した不動産を売却するなら、信頼できる不動産会社を見つけることが重要です。
できるだけ多くの不動産会社を比較し、期限内の売却を目指していきましょう。