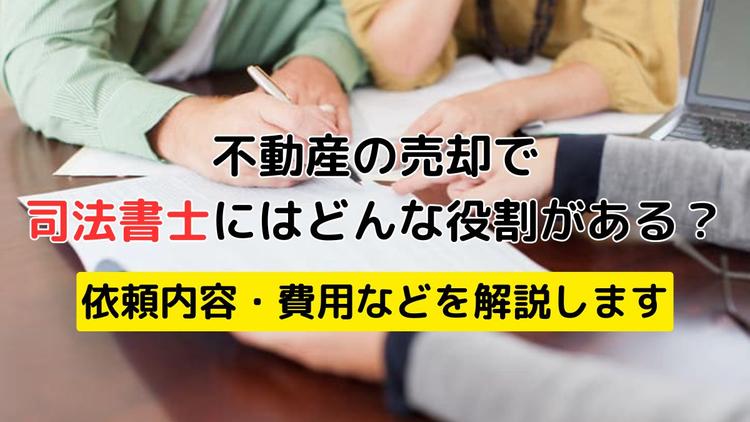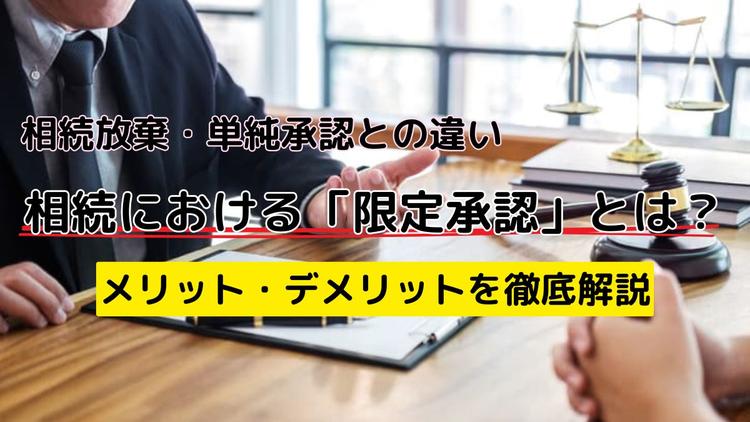バブル期に別荘を購入した層が高齢になることで、子どもが別荘相続で悩むケースが増加傾向にあります。
別荘は相続すると相続税や維持管理費用などの負担があり、かといって売却も容易ではありません。
別荘を相続する予定なら、相続後に発生する負担や活用方法、相続や売却手続きなどを理解しておくことが重要です。
この記事では、別荘相続の負担や活用方法、売却の流れに売れない場合の対処法などを詳しく解説します。
別荘を相続すると発生する負担とは
別荘を相続すると、税金や維持費など、さまざまな負担が生じます。
ここでは、相続後に発生する負担をみていきましょう。
相続時に相続税を納税する必要がある
別荘は、実家の相続同様に相続税の対象です。
別荘を含めた相続財産の総額が基礎控除を超えると、相続税が課税されます。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となり、仮に法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら基礎控除は4,800万円です。
このとき、相続財産が6,000万円であれば1,200万円が相続税の対象となります。
相続財産を算出する際、別荘だからと言って減額されるようなことはありません。
別荘であっても他の不動産同様に、不動産の相続税評価額が相続財産に加算されます。
ただ、不動産の相続税評価額は時価よりも下がるため、現金で相続するのと比較して相続税節税効果が見込めるでしょう。
相続税評価額は土地部分は主に相続税路線価を用いて算出され、建物は固定資産税評価額が評価額として用いられます。
これらの評価額は実際の売買価格の70~80%程度になるため「現金より不動産で残した方がお得」と言われることがあるのです。
なお、実家を相続する場合、土地は「小規模宅地等の特例」で評価額の軽減が可能ですが、適用できるのは被相続人が住んでいた家の土地部分になるので、別荘の土地は特例の対象外です。
大きな節税効果が見込める小規模宅地等の特例は、別荘地には適用できない。
毎年固定資産税を納税する必要がある
固定資産税とは、不動産の所有者に毎年課税される税金です。
おおむねすべての不動産が課税対象となるので、別荘も課税されます。
仮に、相続前から長年活用しておらず相続後も活用の予定がないケースでも、所有する以上は固定資産税が毎年課税され続けます。
また、別荘の所在地によっては都市計画税も徴収されるので、事前に税額を押さえておくようにしましょう。
維持管理の手間や費用が発生する
別荘も持ち家と同じように、維持管理の手間や費用が発生します。
たとえば、建物を維持するには定期的な掃除や換気、修繕などの手間が必要です。
自分で定期的に出向くのが難しい場合は管理会社に委託可能ですが、毎月委託料が発生します。
さらに、屋根・外壁の塗り替えや老朽化修繕のためのメンテナンス費用、万が一に備えて保険料や水道光熱費などの費用も必要です。
また、別荘の場合、場所によっては温泉使用料や共益施設管理費、借地料などが発生するケースもあります。
事前に維持管理に必要な費用をシミュレーションし、負担し続けられるかを判断しておくことが大切です。
相続した別荘の活用方法
相続した別荘の活用方法としては、以下の3つが挙げられます。
- 別荘として利用する
- 賃貸に出す
- 売却する
それぞれ見ていきましょう。
別荘として利用する
別荘として自分で利用するのが、スムーズでシンプルな活用方法でしょう。
週末や長期休暇などで利用できるなら、そのまま保有しても問題ありません。
ただ、別荘の所在地や自身のライフスタイルによっては、当初は活用しても徐々に足が遠のくケースも多いので、長期的に活用できるか検討しましょう。
利用できる場合、別荘よりもセカンドハウスとして活用するのがおすすめです。
セカンドハウスとは、定期的に居住するための第2の住まいを指します。
別荘がセカンドハウスと認められると、固定資産税の軽減など税制優遇を受けやすくなります。
ただし、セカンドハウスは月1回以上利用しているなど生活を目的とした住居であると認められる必要があるので注意しましょう。
賃貸に出す
自分で利用しない場合は、賃貸として貸し出す方法もあります。
借り手が付けば毎月賃料収入を得られるので、固定資産税などの負担の軽減もできるでしょう。
別荘であれば、賃貸以外にも民泊やレンタルオフィスなどの貸出方法も検討できます。
ただし、賃貸として活用できるかは、物件の状態や立地によっても左右されます。
事前にエリアの賃貸ニーズなどを徹底的にリサーチしたうえで、検討するようにしましょう。
また、別荘地によっては賃貸や民泊などが禁止されているケースもあるので、自治体の条例や別荘地の規約などをチェックすることも大切です。
売却する
自分で活用する予定がなく、維持管理の手間や費用も避けたいなら売却が適しています。
売却すれば売却金が手に入るので、相続人で分割したり相続税の資金にしたりすることも可能です。
売却後は、固定資産税や維持費などの負担、管理の手間の必要もありません。
ただし、別荘は持ち家の売却よりも買い手が限定され、立地や状態によっては売却が難しいケースもあります。
別荘を売却する場合は、別荘の取扱い実績が豊富な不動産会社に相談するとよいでしょう。
▼関連記事:別荘を売却する時に注意すべきことまとめ
別荘を相続する場合の手続き
別荘を相続する場合、活用や売却の前に相続の手続きをする必要があります。
相続手続きの大まかな流れは以下のとおりです。
- 遺言書の有無を確認する
- 遺言書がない場合は遺産分割協議を行う
- 別荘を相続することになったら相続登記と相続税の納税を行う
それぞれ見ていきましょう。
遺言書の有無を確認する
相続の仕方は遺言書が優先されます。
そのため、まずは故人が遺言書を残していないか確認しましょう。
なお、遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、自筆証書遺言・秘密証書遺言は見つけても勝手に開封できません。
開封には家庭裁判所の検認手続きが必要になるので、見つけたら速やかに手続きを行いましょう。
一方、公正証書遺言と自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は見つけ次第開封しても問題ありません。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行う
遺言書がない場合、遺産の分割の仕方は遺産分割協議で話し合って決めることになります。
遺産分割協議では相続人全員の合意が必要になるので、あらかじめ相続人と遺産を明確にしておくことが大切です。
仮に、遺産分割協議後に新たな相続人が判明すると、協議のやり直しが必要になります。
また、相続人のうち誰か1人でも反対する人がいると協議は成立しません。
協議が長引く場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てることになります。
別荘などの不動産は現金のようにきっちり分割できないため、相続の仕方で揉めやすい点には注意しましょう。
不動産の相続の仕方には、以下の4つの方法があるので相続状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。
- 現物分割:相続財産をそのままの形で相続する
- 代償分割:不動産を相続する人が相続しない人に対して代償金を支払う
- 換価分割:不動産を売却して売却金を分割する
- 共有分割:不動産を共有する
遺産分割協議で決まった内容は、遺産分割協議書に記録します。
遺産分割協議書はこの後の相続手続きで必要になる書類なので、作成後は大切に保管しておきましょう。
別荘を相続することになったら相続登記と相続税の納税を行う
別荘の相続人が決まれば、相続登記を行います。
相続登記とは、不動産の名義人を被相続人から相続人に変更する登記手続きです。
相続登記は、相続から3年以内という期限があるので、相続したら速やかに手続きを行いましょう。
自分でも手続きできますが、必要書類が煩雑になりやすいので司法書士に依頼を検討するのも1つの方法です。
また、相続税が発生する場合は相続税の申告・納税が必要になります。
相続税の期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
10ヵ月あると思っていても、相続開始後は必要な手続きが多くあっという間に10ヵ月になります。
とくに、売却して納税を検討する場合は、相続手続きをして更に売却と時間もかかりやすいため、早めに動くようにしましょう。
相続した別荘を売却する場合の手続き
相続した別荘の売却を検討するなら、売却の全体像を押さえておくことも大切です。
相続した別荘を売却する大まかな流れは以下のようになります。
- 不動産会社の査定を受ける
- 不動産会社と媒介契約を締結する
- 売却活動
- 売買契約を締結する
- 決済~引き渡し
相続登記が終われば、相続した別荘であっても通常の不動産同様に売却できます。
一般的な不動産では売却に3ヵ月~6ヵ月ほどかかりますが、買い手が限定されやすい別荘はより時間がかかる可能性があるので注意しましょう。
不動産会社の査定を受ける
まずは、不動産会社の査定を受けます。
この際、査定額は不動産会社によって大きく異なるので、複数の不動産会社の査定を比較することが大切です。
比較するときは、査定額だけでなく実績や評判、対応など多角的にチェックすると信頼できる不動産会社を見極めやすくなるでしょう。
また、別荘は特殊な不動産でもあるので、別荘の取扱い実績がある不動産会社を��選ぶことも大切です。
不動産会社と媒介契約を締結する
売却を依頼する不動産会社を見つけたら、媒介契約を締結します。
媒介契約の種類には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があるので、適切な種類を選ぶようにしましょう。
それぞれの大まかな違いは以下のとおりです。
| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
| 契約できる不動産会社数 | 複数可能 | 1社のみ | 1社のみ |
| レインズへの登録義務 | なし | あり(7日以内) | あり(5日以内) |
| 営業活動報告義務 | なし | あり(2週間に1回以上) | あり(1週間に1回以上) |
| 契約期間 | 定めなし(一般的には3か月) | 最長3か月 | 最長3か月 |
売却活動
媒介契約後は、不動産会社が売却活動をスタートします。
売主は、内覧に備えて別荘の清掃や整理整頓を徹底的に行っておきましょう。
なお、内覧自体は不動産会社に鍵を預けて任せることが可能です。
また、売却活動中はこまめに進捗状況をチェックして、適宜値下げなどの売却判断を下していくようにしましょう
売買契約を締結する
買主と売買条件が合意できれば、売買契約を締結します。
売買契約時は、契約書の内容をしっかり確認�し不明点や疑問点は必ず解消してからサインすることが大切です。
決済~引き渡し
売買契約後1か月以内を目安に、決済と引き渡しが行われます。
決済・引き渡しでは、代金の支払いを確認し、必要書類や鍵を引き渡して取引完了です。
売却後に利益が発生する場合は、確定申告が必要になるので忘れずに手続きを行いましょう。
相続した別荘が売れない場合の対処法
別荘は、そもそも買いたいという人が少ないものです。
さらに、自然の中など不便な立地のケースも多いことから売却が難しくなります。
ここでは、相続した別荘が売れない場合の対処法として以下の3つを解説します。
- 値下げを検討する
- 買取を検討する
- 管理会社に引き取ってもらう
それぞれ見ていきましょう。
値下げを検討する
大幅に値下げすることで、移住希望者などに売却できる可能性があります。
ただし、相場より極端に価格を下げ過ぎると手元に入るお金が少なくなるだけでなく、事故物件を疑われて売却しにくくなる恐れがあります。
どれくらい値下げした方がいいか判断に迷う場合は、不動産会社にアドバイスをもらいながら決めるとよいでしょう。
買取を検討する
仲介での売却が難しい場合、買取を視野に入れることでスムーズに売却できる可能性があります。
買取業者であれば、別荘を買い取った後にリフォームして賃貸運営したり売却するなど活用のノウハウがあるので、適正価格での買取が可能です。
相場より大きく値下げして売れるのを待つよりも、買取で短期間で手放す方がメリットは大きいでしょう。
ただし、買取業者にも得意不得意はあるので、別荘の買取実績が豊富な業者を選ぶことが重要です。
管理会社に引き取ってもらう
別荘の日常の管理を管理会社に委託しているケースも多いでしょう。
管理会社によっては別荘を引き取ってくれる可能性があるので、相談するのも1つの方法です。
しかし、管理会社の引き取り�は買取とは異なりほとんど価格はつきません。
無償ならまだしも、管理費の数年分や数百万円など費用を請求されるケースもあるので注意が必要です。
まとめ
別荘を相続すると、相続税が課税される可能性があります。
さらに相続して所有している期間中は、活用しなくても固定資産税や維持管理費用などの費用や手間が必要です。
相続した別荘には、自分で活用する・賃貸するなどの活用方法がありますが、活用予定がないなら売却を視野に入れる方がよいでしょう。
ただし、別荘は買い手が限定され売りにくくなるので、買取まで含めて検討することが大切です。