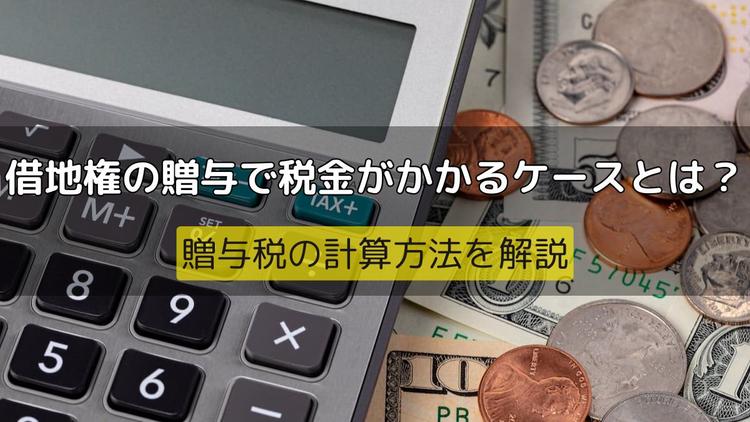不動産で二次相続が起きると、基礎控除の減少や控除が適用できないなどで、相続税の負担が大きくなる恐れがあります。
また、不動産の二次相続は相続トラブルも起きやすいため、対策しておくことが大切です。
とはいえ、二次相続がそもそも何なのか、どんなトラブルになるのかが分からないという方もいるでしょう。
そこで、この記事では二次相続の基本や二次相続での問題点、対策について分かりやすく解説します。
二次相続とは
二次相続とは、一次相続で相続人となった配偶者が亡くなったときに発生する次の相続です。
たとえば、父親・母親・子ども2人という家族で考えてみましょう。
はじめに父親が亡くなったとすると、父親の財産は配偶者である母親と子ども2人に相続されます。
これが一次相続です。
そして、次に母親が死亡すると母親の財産は子ども2人が相続することになり、これが二次相続になります。
二次相続での母親の財産には、母親が相続した父親の財産も含まれます。
つまり、二次相続により親世代の財産がすべて子ども世代に相続されるのです。
二次相続で相続税が増える理由
二次相続の問題点の1つが、1次相続よりも相続税が増える可能性があることです。
相続税が増える理由には以下の3つがあります。
- 基礎控除額が減る
- 生命保険の非課税限度額が減る
- 配偶者控除が使えない
それぞれ見ていきましょう。
基礎控除額が減る
相続税は、基礎控除を超えた部分に課税されるものです。
相続税の基礎控除は、以下の計算式で求めます。
法定相続人の人数は、一次相続よりも二次相続の方が減少するため、相続税が課税されやすくなります。
たとえば、父親・母親・子ども2人のケースでみてみましょう。
父親が死亡した際の一次相続での法定相続人は、母親・子ども2人の合計3人です。
よって、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
一方、母親が死亡した際の二次相続では、相続人は子どもの2人だけとなるため、基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円に減少します。
このように、二次相続では配偶者の分の基礎控除600万円がなくなるのです。
また、この場合の相続財産には、母親自身の財産に加えて、母親が父親から相続した財産も含まれます。
そのため、母親の資産状況によっては、一次相続よりも相続財産の総額が高額になる一方で、基礎控除は減少するため、相続税がより高額になる可能性があります。
生命保険の非課税限度額が減る
被相続人(亡くなった人)の死亡により支払われる生命保険金は、契約者および被保�険者が被相続人であれば相続税の対象です。
たとえば、契約者・被保険者が父親で、受取人が母親の場合、母親が受け取る生命保険金は相続税の課税対象となります。
しかし、生命保険金には相続税の基礎控除とは別に、「生命保険金の非課税枠」が適用されます。
生命保険金の非課税枠は以下のとおりです。
たとえば、母親と子ども2人が相続人であれば、500万円×3人=1,500万円までは非課税となります。
なお、非課税枠を超えた部分については、他の相続財産と合算されたうえで、相続税の基礎控除が適用されます。
相続税の基礎控除と同様に、二次相続では法定相続人の数が減ることで生命保険金の非課税枠も小さくなるため、相続税が発生しやすくなるのです。
配偶者控除が使えない
配偶者控除とは、配偶者が相続する場合に「遺産額1億6,000万円」または「法定相続分」までが非課税となる制度です。
そのため、一般的な家庭であれば、この配偶者控除を適用することで、配偶者に相続税が課税されることはほとんどありません。
一次相続ではこの配偶者控除を見越して、配偶者が多くの財産を相続するケースも珍しくありません。
しかし、二次相続では配偶者控除が適用されません。
さらに、一次相続で配偶者が多くの財産を取得していた場合、二次相続時に子どもが相続する財産が多くなり、その分相続税の負担が重くなる可能性があるのです。
また、不動産に関しても、二次相続では「小規模住宅地等の特例」の適用が難しく�なる点に注意しなければなりません。
小規模住宅地等の特例とは、被相続人が自宅として使っていた土地を、配偶者または同居していた親族が相続した場合に、土地の評価額が最大8割軽減される制度です。
一次相続で配偶者がその土地を相続すれば、この特例を適用できます。
一方で、二次相続でこの特例を適用するには、子どもが被相続人と同居しているか、子どもが賃貸暮らしであることが条件になるため、適用できない可能性が高いのです。
このように、二次相続では一次相続よりも適用できる控除が限定されやすいことも相続税が増える要因と言えます。
【シミュレーション】一次相続と二次相続の相続税の違い
ここでは、一次相続と二次相続で相続税がどれくらい異なるかを具体的に見てみましょう。
条件は以下のとおりです。
- 遺産の額:1.5億円(生命保険金を除く)
- 家族構成:父親・母親・子ども3人(父親→母親の順で亡くなる)
- 生命保険:【父親】3,000万円【母親】3,000万円
- 相続条件①:一次相続では母親が70%相続し、残り30%を子どもが均等に分ける
- 相続条件②:二次相続時は生命保険金以外の母親個別の財産の加算はなく母親が相続した分が対象
一次相続
一次相続の相続人は、母親と子ども3人の計4人です。
生命保険金の非課税限度額は、500万円×4人=2,000万円となるので、課税対象は3,000万円-2,000万円=1,000万円となります。
また、相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×4人=5,400万円です。
よって、課税対象となる財産は以下のようになります。
相続税の計算はやや複雑で、まず法定相続分に従って相続したものと仮定して各相続人の相続税額を算出し、それらを合算します。その後、実際の相続割合に応じて税額を按分していきます。
1億600万円を母親と子ども3人で法定相続分どおりに相続すると、それぞれの取得分と相続税は以下のとおりです。
| 相続人 | 取得分 | 相続税 |
| 母親 | 5,300万円 | 890万円 |
| 子ども3人 | 1人1,767万円ずつ | 1人215万円ずつ 合計645万円 |
| 相続税合計1,535万円 |
相続税合計額は1,535万円となるので、実際の取得分で按分するとそれぞれの相続税額は以下のようになります。
- 母親(70%):1,074万円
- 子ども(1人10%):153万円ずつ
なお、母親の実際の取得分は1億500万円であるため配偶者控除を適用すれば相続税が課税されません(配偶者は「法定相続分または1億6,000万円まで」無税。つまり、母の890万円は全額控除できる)。
よって、この場合での相続税は子どもの分の459万円となります。
二次相続
次に、母親が死亡したときの二次相続を見てみましょう。
母の保険金の非課税枠
500万×子3人=1,500万円
相続税の基礎控除
3,000万+600万×3人=4,800万円
課税遺産総額
1.05億+1,500万−4,800万=7,500万円
法定相続分による想定取得額(子3人均等)
7,500万÷3=2,500万円
累進税率での税額(2,500万の場合)
| 合計税額 | 子ども1人あたり | |
| 一次相続 | 645万円 | 215万円 |
| 二次相続 | 975万円 | 325万円 |
| 合計 | 1,620万円 | 540万円 |
一次相続の相続税総額が459万円であるのに対し、大幅に相続税額が増えているのです。
このように、配偶者控除や基礎控除の額が変わることで、相続税にも大きく影響することは覚えておきましょう。
ただし、実際の相続では相続財産の変動やその他の控除の活用などで税額が大きく変わる可能性があります。
二次相続まで含めた相続税額が気になる場合は、税理士に相談するとよいでしょう。
二次相続はトラブルが多い理由
二次相続の問題点としては、相続トラブルが起きやすいことも挙げられます。
一次相続時には、被相続人の配偶者、つまり親のどちらかが生存していことから、子どもも親を優先して相続する・親の意向で相続するなど配慮が生まれ相続トラブルを避けやすくなります。
一方、二次相続は両親が亡くなっているため子どもたちだけでの相続です。
そのことから、相続に対する意見の衝突が起きやすく、トラブルに発展するケースがあります。
前述したように、相続税も高額になりやすいことから相続財産を多く取得したいという心理も働きやすいのもトラブルの要因でしょう。
また、一次相続で不動産(実家)がある場合では、配偶者が住むために親が取得し、その他の資産を子どもが分けることが多くあります。
しかし、二次相続になると親の住まない実家という不動産の相続方法で揉めやすくなってしまうのです。
【よくある事例】二次相続に備えるための対策
二次相続でトラブルにならないための対策として、以下を検討できます。
- 生前贈与を活用する
- 一次相続のときに二次相続を想定した遺産分割を行う
- 一次相続でできるだけ多く子どもに相続させる
- 相次相続控除を活用する
それぞれ見ていきましょう。
生前贈与を活用する
不動産が相続財産に含まれると、分割方法を巡って相続トラブルが起きやすくなります。
生前に不動産を特定の誰かに譲っておけば、相続財産から外れるため、分割方法で揉めることを避けやすくなります。
また、相続財産が高額になりそうな場合、不動産や現金などを生前贈与することで相続財産を減らし、相続税の節税につながるでしょう。
ただし、生前贈与は贈与税の対象です。
贈与税は相続税よりも税率が高いため、財産の額よっては税負担が大きくなる恐れがあるので注意しましょう。
さらに、生前贈与が偏ると相続時にトラブルになりやすい点も考慮が必要です。
一次相続のときに二次相続を想定した遺産分割を行う
一次相続の際に二次相続も踏まえた遺産分割を行うことで、二次相続時の負担の軽減が可能です。
一次相続では、配偶者控除を適用できることから配偶者の相続分を多くするケースもありますが、その場合二次相続の財産が多くなり相続税が高額になる恐れがあります。
二次相続までのトータルの税負担も考慮して、慎重に分割方法を決めるようにしましょう。
また、二次相続に実家があると、まとめ役となる親がいないことからトラブルにもなりやすいので、一次��相続の段階から実家の対策を検討していくことも大切です。
一次相続でできるだけ多く子どもに相続させる
一次相続では、まず配偶者の十分な生活資金を確保し、そのうえで余剰分を子どもに相続させておくことで、二次相続時の税負担が増えるリスクを抑えやすくなります。
ただし、配偶者にも相続に対する希望があるうえ、「十分な生活資金」がどの程度かは人によって異なります。
子どもが勝手に自分たちの相続分を増やそうとすれば、一次相続の段階でトラブルに発展する恐れもあるでしょう。
どれくらいの相続がベストなのかは、相続人や遺産状況によって異なるものです。
不安な場合は税理士などの専門家のアドバイスをもらいながら話し合っていくとよいでしょう。
相次相続控除を活用する
相次相続控除とは、10年以内に次の相続が発生した場合、前回の相続時に支払った相続税額の一定額を次の相続税から控除できる制度です。
適用条件を満たせる場合は、二次相続時に申告することで税負担を軽減できるでしょう。
まとめ
二次相続では配偶者控除や小規模住宅地の特例が適用できない、相続税の基礎控除と生命保険金の非課税限度額が下がるといった理由で、相続税の負担が大きくなる恐れがあります。
また、二次相続時には相続のまとめ役となる両親がいないことも相続トラブルに発展しやすい要因です。
とくに、二次相続時に不動産が含まれると分割方法を巡ってトラブルになりやすいので、生前贈与や一次相続時などから対策しておくことが大切です。
子どもが使う予定のない実家であれば、二次相続前に売却しておくとスムーズな相続を目指しやすくなります。
相続対策を含めた実家の売却を検討している場合は、まずは信頼できる不動産会社に相談するとよいでしょう。