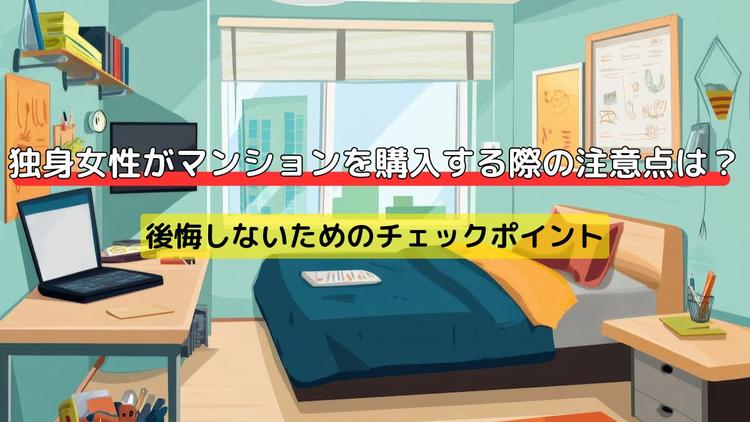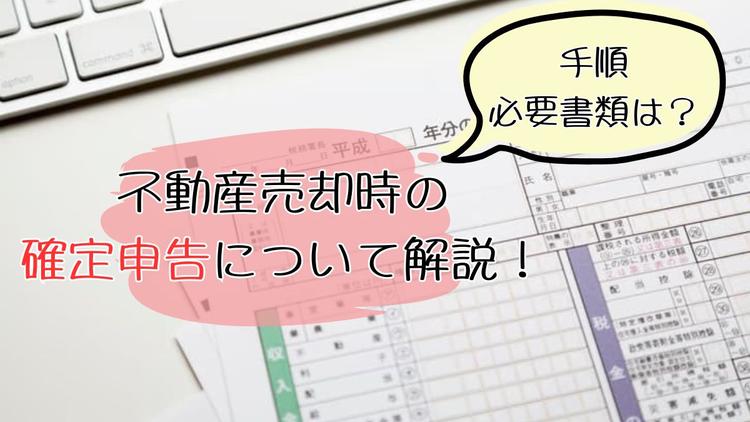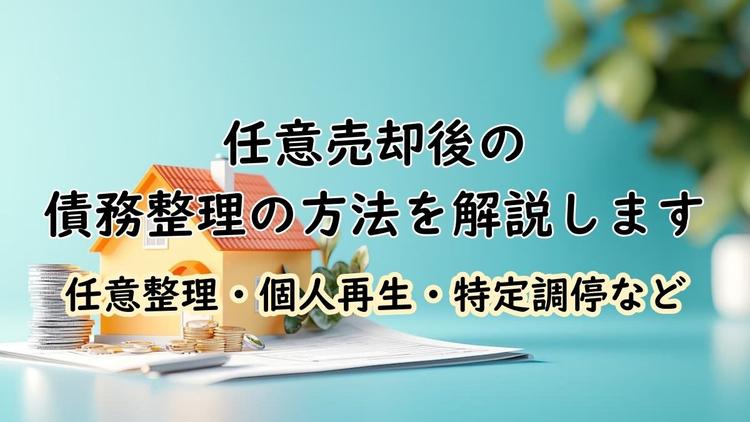親の土地をもらって家を建てる場合や、親の家を相続した場合は、不動産の名義を親から子に変更する必要があります。
しかし、名義変更のケースによっては贈与税がかかる可能性があるのです。
贈与税は高額になりがちなので、課税されるかどうかや節税方法まで押さえておくことが重要です。
この記事では、親から子への名義変更で贈与税がかかるケース、かからないケースや、安く抑える方法、注意点などを分かりやすく解説します。
親から子への家の名義変更で贈与税がかかるケースとかからないケース
親名義の家や土地は、親の資産です。
その名義を子に変更するということは、親から子への資産の譲渡にあたるので、贈与税がかかる可能性があります。
ここでは、親から子への名義変更で贈与税がかかるケース・かからないケースをそれぞれみていきましょう。
贈与税がかかるケース
贈与税がかかるケースとしては、以下が挙げられます。
- 生前の贈与で基礎控除を超えている
- 相場よりも極端に安い価格で子に売却している
親が生前中に行う子への資産の譲渡は、贈与税の対象です。
不動産の名義変更では、土地や建物などの評価を表す「不動産評価額」が贈与税の対象となります。
ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があり、基礎控除を超えた部分に贈与税が課税されるのです。
たとえば、評価額1,000万円の土地の名義を変更すれば、1,000万円-110万円=890万円が贈与税の対象となります。
また、親から子への売却であっても、相場よりも極端に売却額が低いと「みなし贈与」として課税される恐れがあります。
仮に、相場1,000万円の土地を100万円で子に売却すると、差額の900万円が贈与とみなされ、贈与税が課税されるのです。
相場よりどれだけ価格が低いとみなし贈与になるかの明確な基準はないので、不安な場合は不動産会社や税理士に相談するとよいでしょう。
▼関連記事:不動産を評価額より安く売ることはできる?リスクや税金の注意点を解説
贈与税がかからないケース
贈与税がかからないのは以下のケースです。
- 基礎控除以内に収まる
- 適正価格で売買する
- 相続により名義変更する
贈与税の基礎控除である110万円以下に評価額が収まるなら、贈与税は発生しません。
とはいえ、不動産の評価額が110万円に収まるケースは稀な点に注意しましょう。
また、相場価格に対して適正な価格での売買であれば贈与ではないので、課税されません。
しかし、売買の場合は親の売却利益に対して譲渡所得税が課税されるので、発生する税額はあらかじめ押さえておきましょう。
そもそも、子に不動産を購入できる資金があることも条件となってきます。
仮に、資金援助をしたとすれば、資金に対して贈与税がかかるので注意が必要です。
贈与も相続も個人の資産を譲るという点は同じですが、贈与は譲る側が生前中に行うものであるのに対し、相続は譲る側の死亡をきっかけに成立するという違いがあります。
そのため、親の死亡を理由に名義変更する場合は相続となり、贈与税は課税されません。
ただし、相続による不動産の取得は贈与税ではなく相続税の対象です。
そもそも贈与税とは
ここでは、贈与税の基本を押さえていきましょう。
財産を贈与された人が納める必要のある税金
贈与とは、個人の資産を第三者に譲ることです。
贈る側(贈与者)と贈られる側(受贈者)の合意で成立し、いつでも・誰にでも贈与できます。
この際、贈られる側に対して課税されるのが贈与税です。
贈与税は贈られる側が負担するため、良かれと思って贈与したのに贈られた側が思わぬ税負担で苦しむケースもあります。
贈る側・贈られる側ともに贈与税について理解したうえで、贈与を行いましょう。
贈与税の計算式
贈与税は、基礎控除である110万円を超えた部分に、贈与税の税率を乗じ控除を差し引いて求められます。
不動産の場合は、売買額や時価ではなく、相続税評価額が贈与税の対象です。
土地の場合
国税庁が毎年公表する路線価や倍率方式によって評価します。
路線価の無い土地は「倍率方式」で相続税評価額が算出される。
- 市街地などでは、路線価(1㎡あたりの価額)に土地の面積を掛けて算出します。
- 路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。
建物の場合
- 固定資産税評価額がそのまま相続税評価額として使われます。
- 固定資産税評価額は、市町村から送られてくる「固定資産税納税通知書」で確認できます。
贈与税は年内のすべての贈与額で計算する
また、贈与税は年間の贈与額に対して課税されるので、その年に不動産以外の贈与を受けた場合はその額も含めます。
贈与税の税率は、贈与者と受贈者の関係性によって以下の2つに分かれます。
- 一般税率(一般贈与財産用):特定贈与財産以外の贈与
- 特例税率(特例贈与財産用):直系尊属から18歳以上の者への贈与
特例税率は、贈与を受けた年の1月1日時点で、18歳以上の人が直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた場合に適用される税率です。
祖父母から孫や親子間での贈与が該当します。
しかし、直系尊属からの贈与であっても、贈られる側が1月1日時点で18歳を超えていないと一般税率になるので、孫への贈与などでは年齢も確認するようにしましょう。
特例税率での税率は以下のとおりです1。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
一般税率の税率は以下のとおりです。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
一般税率よりも、特例税率の方が税負担を抑えられます。
たとえば、親から子へ3,000万円の家を名義変更した場合、贈与税(特例税率)は以下のとおりです。
一般税率・特例税率いずれであっても、贈与税は贈与額が大きくなるほど税率が高くなり、税負担も高額になります。
不動産は評価額も高額になりやすいので、いくら税負担があるかを事前に把握しておくようにしましょう。
家や土地を親から子へ名義変更するときに贈与税を安く抑える方法
贈与税の負担は、できるだけ安く抑えたいものです。
ここでは、親から子への名義変更で贈与税を安く抑える方法として以下の3つを解説します。
- 暦年課税で計画的に贈与を進める
- 相続時精算課税制度を活用する
- 住宅取得等資金の贈与特例を活用する
それぞれ見ていきましょう。
暦年課税で計画的に贈与を進める
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの贈与額に対して課税される方式です。
年間の贈与額合計から110万円の基礎控除を除いた額が、贈与税の対象となります。
暦年贈与であれば、年間110万円以内であれば贈与税が課税されないので、贈与額を110万円以内に抑えることで税負担を回避できます。
不動産の名義変更を目的としているなら、毎年110万円以下の資金を贈与し、数年後にその資金を用いて売買契約を結べば、贈与税が課税されないでしょう。
ただし、毎年一定額を数年間贈与すると「定期贈与」とみなされる恐れがある点に注意が必要です。
たとえば、毎年100万円を10年間贈与する契約を交わした場合、定期贈与に該当し、この場合は契約した年に1,000万円の贈与があったとして、1,000万円に対して課税されます。
定期贈与とみなされないためには、
- 毎回贈与契約書を締結する
- 贈与額や頻度を変える
- 110万円を少し超える額を贈与して贈与税を納める
などの方法が検討できますが、判断は難しいので税理士に相談するとよいでしょう。
相続時精算課税制度を活用する
相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与を非課税にできる制度です2。
さらに、年間110万円の基礎控除も適用できるので、最大2,610万円までが非課税となり、超えた額に一律20%の贈与税がかかります。
不動産などの、一度にまとまった贈与を行う場合に適しているでしょう。
しかし、相続時精算課税制度では、非課税になった贈与額が将来の相続財産に加算される点に注意が必要です。
相続財産によっては、相続税の負担が大きくなる恐れがあります。
さらに、贈与で取得した相続税評価額が抑えられる「小規模宅地等の特例」は適用できない点にも注意しましょう。
親と同居していた子どもが家と土地を相続する場合に適用しやすい特例であるため、特に評価額が高くなりがちな都市部では大きなメリットがある。
また、一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税には戻れないので、慎重に判断しなければなりません。
ただし、贈与者ごとに相続時精算課税制度か暦年課税かは選択できるので、父親からの贈与は相続時精算課税制度、母親からは暦年課税と分けることは可能です。
住宅取得等資金の贈与特例を活用する
住宅取得等資金の贈与特例とは、直系尊属から住宅取得のための資金援助を受けた場合に、以下の額までが非課税となる制度です。
- 省エネ等住宅の取得のため資金:1,000万円まで
- それ以外の住宅取得のための資金:500万円まで
さらに、基礎控除も適用できるので、最大1,110万円までが非課税となります。
この特例は、土地を先行して購入するための資金でも適用可能です。
ただし、土地の購入翌年3月15日までに住宅を新築する必要があるなど、一定の要件があるので、詳細は国税庁のホームページを確認しましょう。
なお、非課税の対象となるのは資金であり、土地をそのまま贈与した場合は適用されません。
また、建物を親子間など特定の関係で売買した場合も適用外となるので、適用に不安がある方は税理士に相談しましょう3。
▼関連記事:親族・親子間で不動産を売買する時の注意点を解説
家や土地を親から子へ名義変更するときにかかる贈与税以外の税金
親から子に名義変更すると、贈与税以外にも以下のような税金がかかります。
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 印紙税
それぞれ見ていきましょう。
登録免許税
登録免許税とは、登記手続きにかかる税金です。
親から子への名義変更では、所有権を親から子へ移す「所有権移転登記」を行うので、その際に課税されます。
所有権移転登記の登録免許税は、登記の理由によって以下のように異なります。
| 土地 | 建物 | |
| 売買 | 不動産評価額×2% | 不動産評価額×2% |
| 相続 | 不動産評価額×0.4% | 不動産評価額×0.4% |
| 贈与 | 不動産評価額×2% | 不動産評価額×2% |
登記手続きを司法書士に依頼する場合は、別途司法書士報酬が必要なので注意しましょう。
司法書士報酬は、依頼先や依頼内容によって異なり、贈与による所有権移転登記なら2~8万円ほどが目安です4。
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得した時にかかる税金です。
不動産評価額×4%で課税されますが、令和9年3月31日までに住宅を取得した場合は、3%になる軽減措置が適用されます。
また、相続による不動産の取得であれば基本的に課税されません。
ただし、遺言などにより法定相続人以外が取得した場合や生前贈与では課税されるので注意しましょう。
印紙税
印紙税とは、特定の文書を作成した際に課税される税金です。
贈与であれば贈与契約書が印紙税の対象となり、不動産の無償贈与であれば200円課税されます。
印紙税は収入印紙を契約書に貼付・消印して納税するので、契約時には忘れないようにしましょう。
家や土地を親から子へ名義変更するときの注意点
家や土地の親から子への名義変更には、贈与や相続が関わってくるので慎重に行う必要があります。
ここでは、名義変更時の注意点として以下の3つを紹介します。
- 事前に必要書類を集める必要がある
- 兄弟とよく話し合うことが大切
- 贈与税の税率は相続税の税率よりも高い
それぞれ見ていきましょう。
事前に必要書類を集める必要がある
名義変更手続きにはさまざまな書類が必要です。
なかには取得に時間がかかるものもあるので、早めに用意するようにしましょう。
必要書類は名義変更の理由によって異なりますが、贈与の場合は以下です。
- 贈与を証明する書類(贈与契約書など)
- 登記申請書
- 登記識別情報または権利証
- 贈与者の印鑑証明
- 受贈者の住民票
- 固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
贈与契約書には決まった書式はありませんが、以下の記載が必要です。
- 贈与者・受贈者の氏名と住所
- 贈与した物件の情報
- 贈与日
物件の情報は登記簿に記載されたとおりに正確に記載しましょう。
そのうえで、贈与者・受贈者それぞれが署名・捺印して契約を締結します。
契約書の雛形はインターネットで検索できますが、作成に不安がある方は専門家に相談するとよいでしょう。
また、登記識別情報・権利済証は所有者が保管する書類であり、紛失すると再発行できません。
紛失している場合は、別の方法で所有者を明らかにする必要があるので、早めに司法書士などに相談しましょう。
兄弟と��よく話し合うことが大切
自分以外にも兄弟姉妹などの相続人になる予定の人がいるなら、家や土地の贈与についてしっかり話し合っておくことが重要です。
特定の相続人が生前贈与を受けたケースでは、「生前贈与を受けたのに相続財産も取得するのは不公平」と、相続トラブルになることは珍しくありません。
他の兄弟の中には、親の家や土地が欲しい人がいるかもしれません。
親と自分だけで贈与を進めると、不公平感からトラブルになりがちです。
事前に、兄弟姉妹など関係する人とも話し合い、納得したうえで贈与することでトラブルを避けやすくなります。
贈与税の税率は相続税の税率より高い
贈与税と相続税では税率が異なるので、どちらの方法で不動産の名義を変更したほうがよいかは、慎重にシミュレーションして決めるようにしましょう。
贈与税の最高税率は、特例税率で贈与額4,500万円超の55%です。
一方、相続税の最高税率は、相続財産取得分6億円超で55%となります。
同じ4,500万円であれば、相続税の税率は5,000万円以下の20%に下がるため、贈与税よりも負担が軽くなります。
また、相続税には「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」という基礎控除に加え、さまざまな特例が設けられているため、税負担が少ないケースが多いのです。
そのため、相続税がかからないケースで高額な生前贈与を行うと、税負担の面では不利になる可能性があります。
どちらを利用したほうがいいかは、資産状況などによって異なるので、税理士などのプロに相談するとよいでしょう。
なお、相続開始前7年以内の生前贈与は相続税の対象となります。
高齢になってからや健康に不安を覚えてからの生前贈与では、相続税の節税効果は期待しにくいので、生前贈与は早い段階から計画的に行うことが重要です。
ただし、7年以内の生前贈与ですでに贈与税を支払っているケースでは、支払った額を相続税から控除できるので、二重課税にはなりません。
まとめ
親の生前中に家の名義を親から子に変更すると、不動産の評価額が基礎控除を超えた部分に贈与税が課税されます。
一方、売買や相続を理由とした名義変更や、基礎控除以内の贈与であれば贈与税は課税されません。
しかし、相続では相続税の対象となるので、贈与と相続どちらが適しているかは、慎重な判断が必要です。
どの税金がいくら課税されるかはケースによって異なり、節税方法も違ってきます。
親から子への不動産の名義変更を検討している場合は、早い段階で税理士などのプロに相談するとよいでしょう。