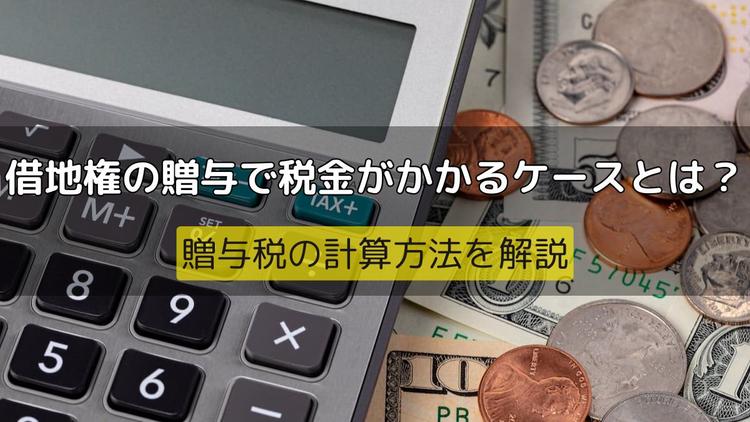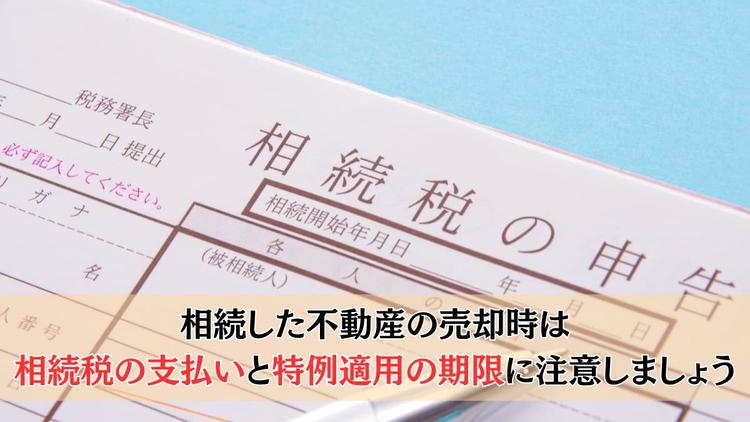借地権の設定されている土地でも贈与は可能です。
しかし、贈与の仕方によっては贈与税がかかるため、課税されるかどうかを理解しておく必要があります。
贈与税は控除が少なく税率も高いため、課税されると負担が大きくなりかねません。
事前に課税されるかの判断や税額を計算できるようになっておくことが大切です。
この記事では、借地権の贈与に贈与税がかかるケース・かからないケース、贈与税の計算方法などを分かりやすく解説します。
借地権の贈与に税金がかかる?
親の土地に子どもが家を建てるケースは珍しくないでしょう。
しかし、その土地が借地権付きである場合は贈与や税金計算が複雑になりがちです。
ここではまず、借地権と借地権の贈与について押さえておきましょう。
そもそも借地権とは
借地権とは建物を建てることを目的として土地を借りる権利です。
土地を借りる側を借地権者や借地人と呼び、貸す側は借地権設定者や底地人・地主などと呼ばれます。
借地権者は土地を借りる代わりに対価として毎月地代の支払いが必要です。
通常の所有権では土地に建物を建てると土地・建物それぞれの所有権を有しますが、借地権付きの土地に建物を建てると土地の所有権は地主、建物の所有権は借地人となります。
また、借地権には「地上権」と「貸借権」の2つがあります。
地上権は、地主の許可なしに土地を貸したり建物を売却でき、借りる側の権力が強いため、一般的に設定されることはありません。
一方、賃借権では建物の売却や建て替えには地主の許可が必要です。
なお、借地権は建物を建てることが目的で設定されるため、駐車場利用など建物を建てない土地では設定できない点も覚えておきましょう1。
▼関連記事:地上権とはどんな権利?借地権や地役権との違いを解説します
借地権は他人に贈与できる
借地権は第三者に贈与できます。
しかし、贈与には地主の承諾が必要となり、承諾料や名義書換料を支払うケースが一般的です。
また、相続が発生すれば借地権は相続できます。
相続の場合は地主の承諾や承諾料は必要ありません。
よくある借地権の贈与のケースが、親が借りていた土地に子どもが家を建てる、親が借りた土地に建てた家を子が贈与してもらうといったケースでしょう。
親子間だけでなく、第三者に借地権を贈与する場合もあるます。
いずれであっても贈与は可能ですが、贈与税の対象となりえます。
ただし、賃借権の贈与では、贈与税が発生するケース・発生しないケースがあるので注意が必要です。
以下では、それぞれのケースを詳しく解説するので参考にしてください。
借地権の贈与で贈与税がかかるケース
借地権の贈与で贈与税がかかる代表的なケースが以下の4つです。
- 借地権を第三者に贈与するケース
- 借地上の建物の名義を変更したケース
- 親が借地権を持つ土地に家を建てたケース
- 借地権の親子間売買で相場よりも著しく安価で売買したケース
贈与と明確に分かるケースだけでなく、当事者で贈与の意識がなくても贈与税の対象となるケースもあるので注意しましょう。
以下で、それぞれ詳しく解説します。
借地権を第三者に贈与するケース
贈与は、送る側と送られる側の合意があれば成立します。
贈与する相手も親子や親族間に限らず誰にでも贈与可能です。
そのため、地主の承諾があれば第三者に借地権を贈与できます。
しかし、第三者への贈与は贈与税の対象となるため、贈与を受ける側は贈与税の支払いが必要です。
良かれと思ってした贈与が思わぬ負担になる可能性もあるので、事前に贈与税額を計算し相手側に了承を得て�贈与を行うようにしましょう。
なお、たとえ親子間の贈与であっても地主の承諾が必要となり、贈与税の対象となります。
借地上の建物の名義を変更したケース
借地権の設定された土地に建物を建てた場合、建物の権利は借地権者にあります。
また、借地上の建物は借地権者単独で登記でき、公的に所有権を主張できるというメリットがあります。
建物の名義を変更する場合、名義変更により贈与を行ったとされるため贈与税の対象となります。
さらに、借地権についても贈与したとみなされるため、同じく贈与税の対象となります。
なお、建物の名義を変える場合でも地主の承諾は必要です。
承諾なしに勝手に名義を書き換えると、契約違反として契約を解除される恐れもあるので注意しましょう。
親が借地権を持つ土地に家を建てたケース
親が借りている土地に子どもが家を建てるケースでも、借地権の使用権貸借とみなされ贈与税の対象となります。
ただし、後ほど説明する使用貸借書を提出すれば課税されないので、忘れずに手続きするようにしましょう。
借地権の親子間売買で相場より著しく安価で売買したケース
借地権は地主の承諾があれば売却可能です。
売買であれば贈与ではないため贈与税は発生しません。
ただし、売買価格が適切でなければみなし贈与として贈与税の対象となる恐れがあるので注意が必要です。
たとえば、相場が2,000万円であるのに、100万円で売却すると1,900万円を贈与と見なされ課税されてしまいます。
とくに、親子間では相場よりも著しく安値で売買するケースもあるので、価格を設定する際には適正価格を心がけるようにしましょう。
借地権の贈与で贈与税がかからないケース
贈与税がかからない代表的なケースには以下の3つが挙げられます。
- 相応の権利金と地代を支払うケース
- 事前に税務署に使用貸借に関する確認書を提出して親が借地権を持つ土地に家を建てたケース
- 地主から底地を買い取り借地権の所有者に地代を支払うケース
それぞれ見ていきましょう。
相応の権利金と地代を支払うケース
権利金とは、借地権を取得する対価として支払う一時金のことで、通常は返還されません。
商業地や慣習がある地域で一般的に見られ、更地価格と借地権割合を基に算出されるのが通常です。
たとえば、更地価格が1,000万円で借地権割合が80%なら、権利金の目安は800万円となります。
権利金が法律で義務付けられているわけではありませんが、慣習がある地域では省略すると贈与とみなされる可能性があります。
また、権利金がない場合や著しく低い場合、地代が相場通りであっても贈与税が課される恐れがあるため、注意が必要です。
適正な権利金を設定するには、地域の慣習や相場を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
事前に税務署に使用貸借に関する確認書を提出して親が借地権を持つ土地に家を建てたケース
親の借りている土地に子どもの名義の家を建てると、「借地人=子ども」とみなされます。
しかし、名義を子どもにする場合でも「使用貸借に関する確認書」を税務署に提出することで「借地人=親��」のままにすることが可能です。
上記ケースで「使用貸借に関する確認書」を提出すると、「借地権=子ども」とならず、「親が子どもに又貸ししている」とみなされ、贈与税は発生しません。
なお、広大な土地で親の建物はそのままで、新たに子どもの建物を建てるケースでも、上記の書類を提出する必要があります
また、確認書には以下3人の連名が必要になる点に注意が必要です。
- 借地権者
- 借地権者から借りる人
- 地主
地主から底地を買い取り借地権の所有者に地代を支払うケース
底地とは、借地権が設定されている土地です。
底地の所有者は地主ですが、所有権を地主から買い取ることで新たな地主となることができます。
たとえば、親が借りている土地の底地を子が買い取るケースをみてみましょう。
子が底地を買い取ることで地主は子となり、新たに親と子で賃貸借契約が発生します。
この場合、親が子に地代を支払うことで贈与にはならないため贈与税は発生しないのです。
しかし、子が底地を買い取るケースでは親が地代を払わないケースもあります。
地代を支払わない場合、「子が土地の完全所有者となる=子に借地権が贈与された」とみなされます。
その場合、子は贈与税を納める必要があるので注意しましょう。
ただし、この場合でも税務署に「借地権者の地位の変更がない旨の申出書」を提出することで贈与税がかからなくなります。
借地権にかかる贈与税の計算方法
贈与税が発生すると高額になる恐れがあるため、事前にいくらかかるか把握しておくことが大切です。
ここでは、贈与税の計算方法を解説します。
暦年課税と相続時精算課税制度
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。
暦年課税とは、1月1日から12月31日の1年間で受けた贈与額合計に対して課税される制度です。
一方、相続時精算課税制度とは、贈与額2,500万円までを控除できる制度です。
父母または祖父母などから18歳以上の子または孫に対する贈与で適用できます。
相続時課税制度では2,500万円+基礎控除年間110万円までを贈与額から控除でき、控除額を超えると一律で20%の税率で贈与税が課せられるのです。
ただし、相続時精算課税制度では贈与額は相続財産に加算されます。
そのため、相続財産によっては贈与税ではなく相続税が課せられる点に注意が必要です。
以下では、暦年課税での贈与税の計算方法として次の3ステップを紹介します。
- 借地権の相続税評価額を算出する
- 暦年課税の基礎控除額を差し引く
- 税率を掛ける
それぞれ見ていきましょう。
借地権の相続税評価額を算出する
暦年贈与では年間の贈与額の合計に対して課税されるため、まずは、贈与税の対象となる借地権の相続税評価額を算出します。
借地権の相続税評価額の計算方法は以下のとおりです。
自用地の評価額とは、借地権を設定せずに自由に利用できる状態としての評価額です。
路線価の設定されている地域であれば「路線価×地積×補正率」で算出できます。
路線価が設定されていない場合は、「固定資産税評価額×倍率」の倍率方式で算出することになります。
路線価・倍率ともに国税庁のホームページで確認しましょう。
また、借地権割合とは土地の権利に対する借地権の割合です。
国税庁が地域ごとに30~90%と段階的に定めているので、自身の土地の借地権割合をチェックするようにしましょう。
たとえば、路線価が10万円/㎡・土地の面積150㎡、補正なし・借地権割合が80%なら評価額は以下のようになります。
暦年課税の基礎控除を差し引く
暦年贈与には年間110万円の基礎控除が設けられており、基礎控除を超えた部分が課税対象となります。
そのため、贈与額から基礎控除を差し引きます。
上記の例での課税対象額は以下のとおりです。
なお、贈与税の対象となるのは1年間の贈与額合計であり、贈与者や贈与したものの種類ごとではありません。
仮に、借地権を父親から現金を母親から贈与されている場合は、合算した額が贈与税の対象となります。
税率を掛ける
贈与額が基礎控除を超えると、贈与税の税率で課税されます。
贈与税の税率は誰からの贈与かによって「一般税率」と「特例税率」に分かれ、一般税率は以下の速算表で求められます。
| 基礎控除額後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
前述の例では贈与税は以下のようになります。
贈与税は最高55%と税率が高い税金です。
課税されると負担が大きくなる恐れもあるので、事前に額を計算しておくようにしましょう。
借地権贈与時の税金に関するよくある質問
最後に、借地権贈与時の税金に関するよくある質問をみていきましょう。
借地権付き建物の贈与に贈与税はかかる?
借地権付き建物とは、借地権の付いている土地に建てられた建物です。
借地権付き建物であっても贈与に該当すれば贈与税の対象となります。
借地権を贈与する際の承諾料の相場はどのくらい?
承諾料とは地主に贈与の許可を得る際に支払うお金です。
承諾料に明確な規定はありませんが、一般的には借地権価格の1割ほどが相場となります。
ただし、実際は地主との合意になってくるため承諾料が発生しないケースや相場よりも高くなるケースなどさまざまです。
事前に周辺の相場�などを調べ交渉にあたるようにしましょう。
親の借地権を相続した場合に税金はかかる?
借地権は相続税の対象です。
贈与税同様に借地権の評価額に対して相続税が課税されます。
ただし、相続税は相続財産合計が基礎控除を超えた場合に課税されるため、借地権だけでは相続税の課税が判断できない点には注意しましょう。
まとめ
建物を建てるために土地を借りる権利である借地権は贈与が可能です。
しかし、借地権を贈与すると贈与税の対象となります。
贈与税が課税されると最大55%と高い税率が課せられるので、贈与税が発生しないケースを理解して上手に節税できるように工夫するのがおすすめです。
借地権の贈与や売却は贈与税や地主の了承が必要など複雑になりがちです。
売却を検討している場合は、不動産会社など専門家への相談をおすすめします。