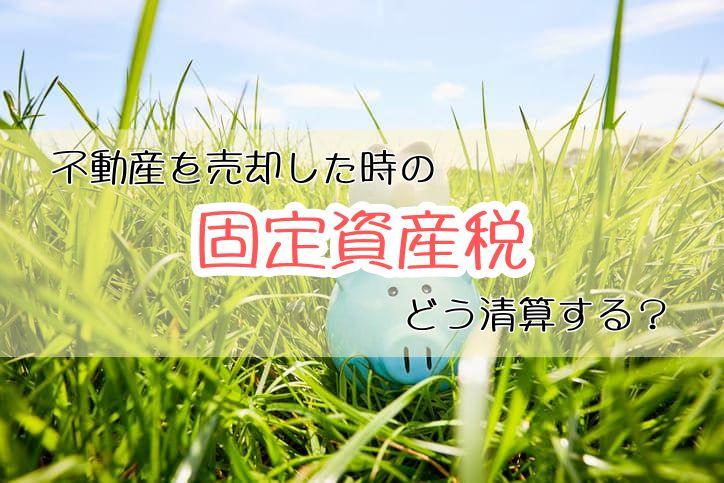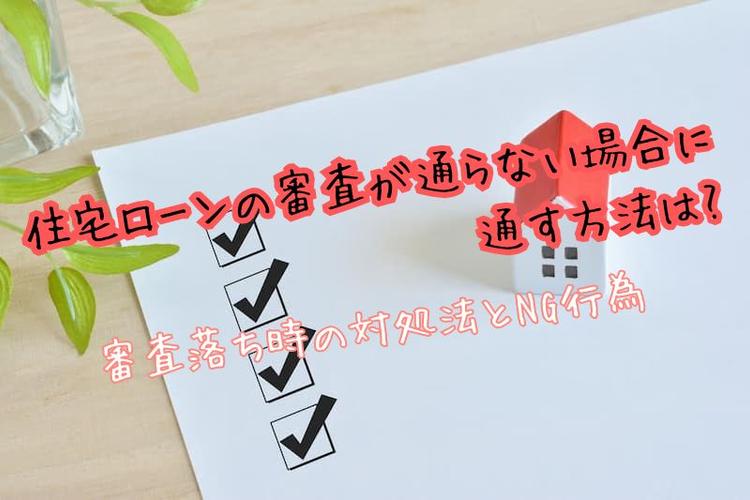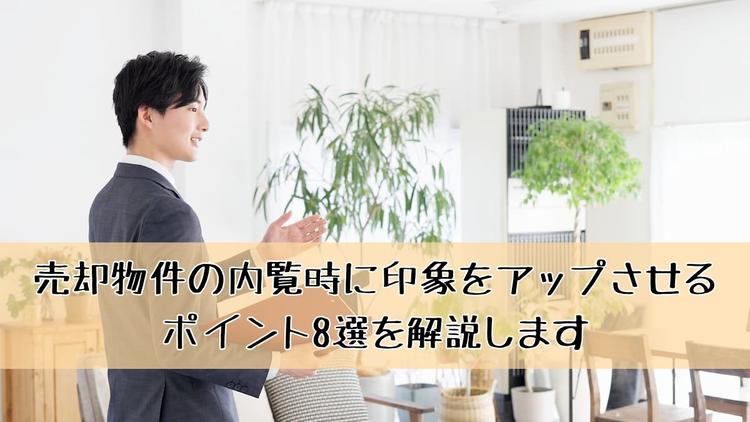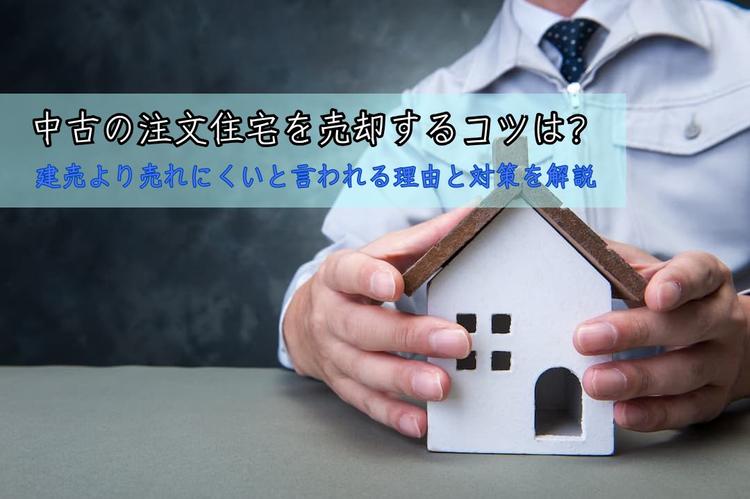不動産を売却したとき、その年度に納める固定資産税の清算が、買主との間で行われます。ただし、固定資産税の清算は法律で定められた手続きではなく慣習として行われている側面があるため、取引時に売買主の間で意見の相違が出てしまうことがあります。
多くの場合は仲介の不動産会社が説明・調整をしてくれますが、売主の立場でも明瞭に説明ができれば、より買主の信頼を得ることができます。不動産の売却をスムーズにすすめるために、固定資産税の清算の方法や注意点について理解を深めていきましょう。
不動産売却時の固定資産税は「売主が清算」する
不動産売却時に固定資産税を清算するのは、法律で定められた義務ではありません。
いわば、不動産取引における慣習のようなものです。
中には、固定資産税の清算を扱わない不動産会社もありますから、ややもすれば、売却後に固定資産税の清算が行われなかったことに気づく事態もあり得ます。
現実的に、引渡し後に改めて清算金を請求するのは困難であるため、固定資産税の清算を想定しているのであれば、仲介の不動産会社に取り扱いを確認するといった、売主の主導が必要です。
そのためにも、不動産売却における固定資産税の取り扱いについて理解を深めることは重要だといえます。
なお、固定資産税と同時に納税する都市計画税も同じ扱いになりますので、本記事で「固定資産税」と表記されているものは、特記の無い限り「固定資産税・都市計画税」に関する内容であることを予めお断りしておきます。
固定資産税は1月1日時点の所有者に対して課税される
まず、固定資産税に関する基本的なルールを理解していきましょう。
固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に対して課税されることになっています。
このため、売却をした年に地方自治体から届く納税通知書は、必ず元の所有者である売主に届けられます。
固定資産税の清算は「引渡し日」を基準にするのが一般的
固定資産税の清算をいつの時点を基準にするのかという問題がありますが、これは不動産取引の慣習上は、「引渡し日」を基準にするのが一般的になっています。
固定資産税を日割り計算して、不動産の引渡し以降分の税金相当分を買主に負担してもらいます。
この金額は、売買金額に清算金を上乗せする方法が一般的で、引渡し日に売買代金と一緒に買主が売主の口座に振り込む流れになります。
固定資産税の清算は「起算日」がポイント
固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し、地方自治体が、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税です。
このため、清算の起点日を4月1日とする考えがある一方で、確定申告者の会計年度の始まりである1月1日を起点日とするケースも少なくありません。
一般的に関東は1月1日、関西は4月1日 を起算日とする傾向がありますが、絶対的なルールではありません。
このようなケースでは、もっともらしい説明を加えるよりも、過去に大多数が実行した方法であることの方が説得力があります。
したがって、地域の慣習や不動産会社の経験に基づく前例に従って決める方法が無難です。
固定資産税の日割り計算法
固定資産税が年20万円課税されている不動産を7月1日に引き渡した場合、起点日の設定の違いによって、どのように清算されるかシミュレーションをしてみましょう。
起算日が1月1日のケース
- 売主 181日 20万×181日÷365日= 99,178円
- 買主 184日 20万×184日÷365日=100,822円
売主の所有期間は1月1日~6月30日までの181日間です。
したがって、売主が365日のうち181日分の固定資産税を負担し、買主は7月1日~12月31日までの184日分の固定資産税を支払います。
1月1日を起点日とした場合、7月1日の引渡し日には、買主から100,822円が支払われます。
起算日が4月1日のケース
- 売主 91日 20万×91日÷365日= 49,863円
- 買主 274日 20万×274日÷365日= 150,137円
売主の所有期間は4月1日~6月30日までの91日間です。
したがって、365日のうち91日分の固定資産税を負担します。
買主は7月1日から翌年の3月31日までの274日分の固定資産税を支払います。
4月1日を起点日とした場合、7月1日の引渡し日には、買主から150,137円が支払われます。
このケースでは、4月1日を起点日にすると、1月1日を起点日とした場合と比べて、売主の所有期間が短くなるので、買主の負担が大きくなる点は押さえておきましょう。
清算方法について
固定資産税額の清算方法を協議する際に問題になるのが、その年の納税額が判明していないケースです。
固定資産税の納税通知書は5月頃に地方自治体から送られてきます。
このため、引渡し日が5月までか、6�月以降なのかによって清算の方法が異なってきます。
1月~5月に引渡しをする場合
固定資産の評価額は、基準年度(3年ごと)に全体の評価替えが行われます。
また土地に関しては、地価下落があって据え置くことが適切でないと判断されれば、基準年度以外でも評価額が修正されます。
こうした見直しがなされると、清算額を今年度とするのか、昨年度を基準にするのかで金額が大きく変わってくることがあります。
このため、今年度の固定資産税額が判明していない、1月~5月に引渡しをする場合は、次のような清算方法が想定できます。
- 今年度の納税通知書が届いてから清算する
- 前年の固定資産税額を基にいったん清算し、今年度の納税通知書が届いた時点で再清算をする
- 前年の固定資産税額を基に清算し、再清算はしない
売主と買主の考えが一致すれば、どの方法を選択しても自由です。
ただし、1の方法だと、引渡し後改めて清算することになるため、その時点で買主が応じてくれない可能性があります。
2の方法も、買主が追加金を支払うような形の清算だと応じてもらえない可能性があります。
したがって、買主に特に異論がなければ、3による方法が最もトラブルなく進められる方法だといえます。
6月~12月までに引渡しをする場合
この時期であれば、今年度の固定資産税の納税通知書が売主に届いていますから、確実な納税額を基本にして清算することができます。
ただし、納税義務者はあくまで売主であることを失念してはいけません。
分割納付する場合、清算後も売主自らが納付を�する義務があります。
清算の手間を省くために、固定資産税納付書の残りを買主に預けて、代わりに納付してもらう方法は、厳に慎みましょう。
買主が故意か意図的かにかかわらず、納付期限までに納付しなかった場合は、売主が滞納の責任を問われることになります。
固定資産税の納付は、売主が最後まで責任をもって行いましょう。
不動産売却後の固定資産税を清算する際の注意点
不動産売買契約締結後に固定資産税を清算することになりますが、些細な行き違いから買主との間にトラブルが発生することがあります。
ここでは、スムーズに清算をするための注意点について解説をしていきましょう。
固定資産税の清算は義務ではない
固定資産税を清算するときに注意しておきたいのは、清算は売買の当事者同士間で行われるものであり、法律で定められた手続きではないという点です。
もし買主が法的義務がないことを盾に清算を拒否すれば、それ以上は無理強いはできません。
清算ができなかったからといって滞納をすれば、法的に責任を負うのは、元の所有者である売主の方です。
固定資産税の清算を拒否したからといって、契約が白紙に戻らない限り、買主にはまったく実害はありません。
つまり、当然の義務のようなスタンスで売主が固定資産税の清算を求めると、トラブルに発展する可能性があるということです。
また、固定資産税の清算について合意を得られたとしても、起算日を決めないままだと負担額を巡ってトラブルになりますから、契約が決まった段階で、すぐに金額を明確に提示しておいた方がいいでしょう。
最終的なトラブルを避けるためにも、固定資産税の清算額、支払時期、支払方法については、売買契約書または重要事項説明書に記載しておくことが重要です。
固定資産税の清算では契約日は関係ない
固定資産税の清算は契約日ではなく引渡し日が基準になりますから、万が一、引渡しが伸びた場合はその時点でもう一度協議を行うことになります。
ただし、売買契約書に金額を書き込んでいた場合は、契約の変更手続きが生じますから、手間を考えれば、買主側の負担が多少軽減する程度であれば、そのままの金額で支払うケースが多数です。
固定資産税の清算するうえで費用はかかる?
不動産の売却をすれば、仲介手数料や印紙代が発生します。
さらに抵当権抹消のために司法書士への報酬も必要になります。
これらの他に気になるのが、固定資産税の清算の金額計算や清算書の作成に関する費用です。
これは仲介する不動産会社に依頼することになりますが、仲介手数料の中に含まれる作業として解されるので、新たに費用が発生することはありません。
ただし、すべてを不動産会社任せにするのは危険です。
ほとんどの不動産会社で行ってくれる固定資産税清算金額計算ですが、まったく介入しない不動産会社も皆無ではありませんから、売主としては扱いを注視する必要があります。
仲介手数料や登記関係費用などが記載されている諸費用表に「固定資産税の清算分」という記載がない場合には、基本的に取り扱いをしていないことになります。
こうした不動産会社は、固定資産税の清算を行わないことで、売却を促進させる効果があるという戦略に立っていることも想定できますが、固定資産税の清算を希望するのであれば、不動産会社にしっかりと依頼をしましょう。
これにより不動産会社の負担が増えても、新たに費用が発生することはありません。
更地で売却する場合はいつ建物を解体すればいい?
建物の老朽化が著しいと、建物を解体して更地で売り出した方が買手が現れる可能性が高いことがあります。
また建物の不備による契約不適合を問われるリスクも回避できます。
しかし、建物の解体は、固定資産税に大きく関わってきますから、解体の時期をいつにするのかが非常に重要です。
解体時期によって、固定資産税がどのような影響があるのか解説をしていきましょう。
なお、都市計画税は基準が異なるため、この項に関しては固定資産税に限った記述になります。
年末に建物を解体すると増税に
固定資産の評価は、毎年1月1日の時点の状況で行われます。
年末までに建物を解体すると、翌年の1月1日には建物が存在しませんから、建物に対する固定資産税額はゼロ円になります。
一見、固定資産税が節税できるかに思えますが、実は大幅な増税を招くことになるのです。
土地の固定資産税額は、「課税標準額×1.4%」で算出します。
基本的に課税標準額は、土地の評価額と同額ですが、住宅用地は特例で評価額の6分の1を課税評価額としています。
つまり、建物を解体して、1月1日の時点で更地だと、住宅用地の特例が適用されないため、その年の土地の固定資産税額が一気に6倍に跳ね上がることになります。
なお、課税評価額が評価額の6分の1になるのは「小規模住宅用地」とされる200平方メートル以下のものに限られます。
それ以外の住宅用地については、評価額の3分の1が課税評価額になります。
建物を解体した場合のシミュレーション
それでは実際に前年に建物を解体した場合、固定資産税がどのように変化するのかシミュレーションをしてみましょう。
前年(建物解体前)
- 土地の評価額:3,000万円⇒3,000万円×1/6×1.4%=7万円(固定資産税額)
- 建物の評価額:500万円⇒ 800万円×1.4%=7万円(固定資産税額)
- 固定資産税額:14万円⇒7万円+7万円
本年(建物解体後)
- 土地の評価額:3,000万円⇒3,000万円×1.4%=42万円(固定資産税額)
- 建物の評価額:なし
- 固定資産税額:42万円
これにより、建物解体前の固定資産税が14万円だったものが、建物解体後には、42万円になることが分かります。
固定資産税が高額になれば、建物の売却価格にも影響を及ぼしかねません。
また固定資産税の清算についても、買主とトラブルになるリスクが高くなります。
建物はいつ解体すればいいのか
建物の解体後に�年を越すと、固定資産税の増税を招く事態になってしまいます。
しかし、建物を解体した年に売却をすれば、固定資産税にはまったく影響を及ぼしません。
つまり、更地で売却するのであれば、その年の前半に解体を済ませて、年内に売却をする方が結果として固定資産税の節税になるのです。
まとめ
不動産売却に伴う固定資産税の清算は、法律で定められた手続きではありません。
売主と買主の合意が合って初めて成り立つものですから、買主の理解を得るよう丁寧に説明をしていきましょう。
清算額は、起点日を1月1日にするのか、4月1日にするのかによって異なります。
その地域の慣習や不動産会社の経験に基づき、前例に従う方法が、最もスムーズに進めることができます。
不動産の売却には、契約書の締結、残金の支払い、引渡しといった大きな節目がありますが、固定資産税の清算は、引渡し日を基準に算出します。
清算時にトラブルが発生しないよう、清算日、金額、支払方法を売買契約書や重要事項説明書に記載しておくことが重要です。