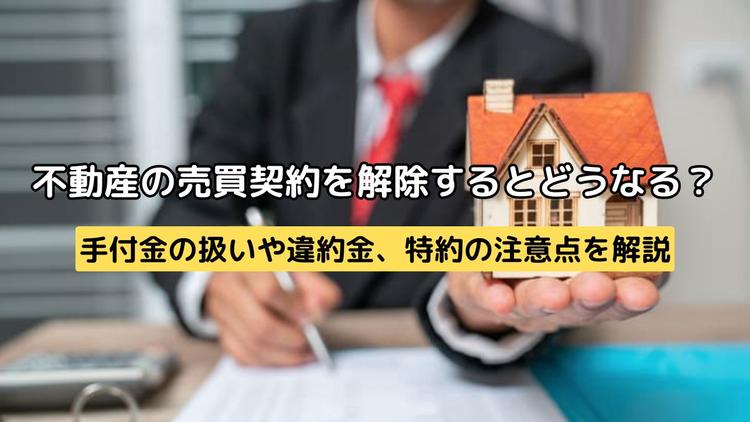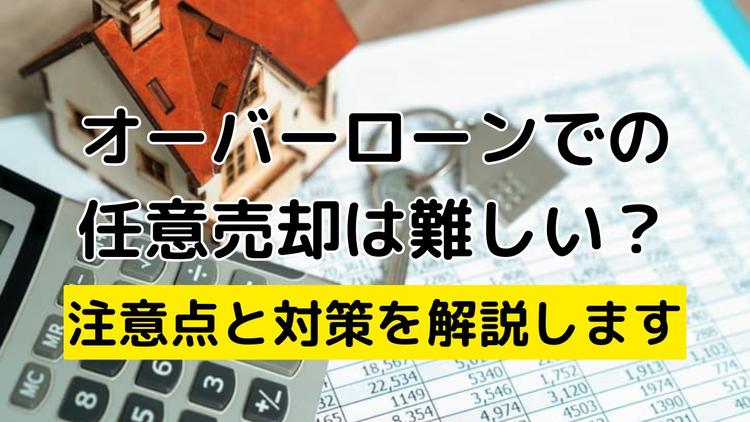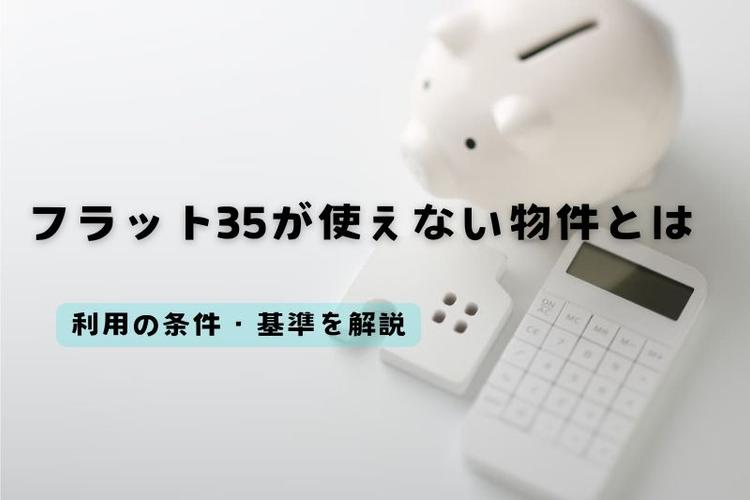不動産売買契約を結んだものの、家族の猛反対にあったり、気が変わったりして売買契約を解除したくなるということもあるでしょう。
しかし、一度売買契約を結んでしまったら、支払った手付金を放棄したり、場合によっては違約金を払ったりなど何らかのペナルティを追わなければならないことがあります。
本記事では、不動産売買契約を解除する際の手付金の取扱いや違約金、特約の注意点をご紹介します。
まずは不動産売買契約の内容を把握しよう
不動産売買契約を解除するにあたっては、まずは売買契約の内容を把握することが大切です。
ここでは、不動産売買契約の基本的な内容についてご紹介していきたいと思います。
不動産売買契約の流れ
不動産の売買契約にはいくつかのステップがあります。
契約を取りやめにしたいと思ったタイミングによっては、実は申込をしただけで売買契約を結んでおらず、ペナルティなく手続きを進められることもあれば、手付放棄だけでは契約を解除できないところまで進んでしまっていることもあります。
まずは不動産売買契約の流れを確認して、自分がどの段階にいるのか把握するところから始めましょう。
一般的な不動産売買契約の流れは以下のようになっています。
上記の通り、買付申込や重要事項説明の段階であれば、契約するつもりで話を進めていたとしても、契約を取りやめることにペナルティはありません。
一方、一度売買契約を結んでしまうと、買主が契約解除するには手付金を放棄する必要があります。
また、決済した後に契約を解除することは原則としてできません。物件に何らかの問題があるといった場合には、直接不動産会社や売主と交渉するか、弁護士に相談するといった対応が必要です。
重要事項説明書は契約上必須
不動産の売買契約では、契約を結ぶ前に宅建士から重要事項説明書の交付を受け、その内容の説明を受けます。
重要事項説明書とは、その名の通り不動産の取引で重要な事項を説明するもので、例えば取引の相手の住所氏名、仲介先の住所氏名、取引する物件の所在地や面積といった内容の他、物件に適用される法律の説明やお金の取扱いに関する説明等がなされます。
不動産売買契約では、売買契約締結までの間に宅地建物取引士の資格保有者により、重要事項説明を行うことが義務付けられています。
売買契約までの間であれば、どのタイミングで行ってもよいのですが、契約の当日に行われ、重要事項説明書の説明がなされた後に売買契約を締結するのが一般的です。
不動産売買契約で準備するもの
ここでは、売主、買主別に不動産売買契約をする際に用意しなければならないものをお伝えします。
売主、買主がそれぞれ用意しなければならないものは以下の通りです。
買主
代理人が契約に立ち会う場合
| 売主
|
不動産売買契約に署名、押印する必要があるため、印鑑を持参しましょう。
不動産売買契約書や重要事項説明書に押印する印鑑は必ずしも実印である必要はありませんが、住宅ローンを利用する場合は、住宅ローンの契約書に実印を利用する必要があることから、実印を押しておいた方が無難でしょう。
また、不動産売買契約にあたって不動産会社に仲介を依頼していた場合、売買契約成立と同時に、仲介手数料の額の半分を支払うのが一般的です。
なお、仲介手数料は売買契約時に半分、決済時に半分支払うケースの他、売買契約時に全額とするケースや、決済時に全額とするケースもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
契約日に本人が立ち会えない場合は代理人契約も可能ですが、その際には委任状の他、代理人の印鑑や本人確認書類も持参するようにします。
不動産売買契約書に記載される内容
次に、不動産売買契約書に記載される内容をお伝えしていきたいと思います。
具体的には、以下のような内容が記載されます。
- 物件の表示
- 売買金額と支払い日
- 住宅ローン特約
- 危険負担について
- 契約不適合責任について
物件の表示
まずは、物件について所在地や面積の記載があります。
こちらの内容が、最新の登記簿の内容と相違していないかを確認する必要があります。
万が一相違する場合には、その理由を確認しておくことが大切です。
売買金額と支払い日
次に、売買金額と支払い日についての記載があります。
また、売買契約日に支払う手付金についても記載があるため、あらかじめ金額を確認しておくようにしましょう。
住宅ローン特約
住宅ローン特約とは、売買契約後、住宅ローンが否決となったことを理由に契約を解除する場合には無条件で白紙解約できるというものです。
住宅ローンの本審査は売買契約締結後しかできないのが一般的で、住宅ローンの否決という、買主の都合によらない契約解除にもペナルティを課してしまうのはあんまりだということでつけられる特約です。
住宅ローン特約には期日があり、その日を過ぎて住宅ローンが否決となってしまった場合には、白紙解約できないことになっているため、期日を確認することが大切です。
危険負担について
危険負担とは、例えば不動産売買契約後、雷や台風を初めとした天災などの理由により、契約の目的(物件の引き渡し)を達することができない場合、売主と買�主どちらがその責任を負うかを取り決めるものです。
個人間の取引においては、建物が滅失してしまったようなケースでは契約はなかったことにするのが一般的です。
上記の場合、売主が危険負担を追う形になります。
危険負担についても重要な項目なので、しっかり確認しておくようにしましょう。
契約不適合責任について
契約不適合責任とは、契約書の内容と契約の対象が異なる場合に、売主がその責任を取るというものです。
以前は瑕疵担保責任という名前でしたが、物件引き渡し後に物件に何らかの不具合があった場合、そのことが契約書に記載されていなかった場合に売主が責任を取る必要がある責任だと考えるとよいでしょう。
契約不適合責任には期限があり、民法では「不適合を知ったときから1年以内に通知する」とされていますが、これだと売主は売却後、いつまでも契約不適合責任を負わなければならない可能性があることから、「引渡しから3カ月間」といった条件の特約で期限を定めるのが一般的です。
契約解除に関しての項目はどこにある?
不動産売買契約書において、契約解除に関して書かれている部分を探す際には「契約違反による解除・違約金」の項目を参照しましょう。
通常、買主は支払った手付金を放棄することで、売主は受け取った手付金の2倍を支払うことで契約を解除できると定めます。
また、手付金とは別に「売買価格の2割」等、別途違約金を定めることもできます。
売買契約において、手付金の額は売主と買主の合意により決定されますが、特に��この手付金の額が少ないときには、契約解除を防ぐ目的で違約金の額が設定されることが多いです。
買主は手付金の放棄、売主は手付け倍返しでの解除が一般的
上記通り、売買契約は買主から解除するときには手付金を放棄することで、売主は受け取った手付金の倍額を支払うことで解除できることになっています。
一方、手付放棄、手付倍返しで解除できるのは両者が「契約の履行に着手するまで」とされています。
具体的には、「売買代金を全額支払った」といったことや「リフォーム工事を実施した」といったことが当てはまります。
相手方が契約の履行に着手した後は、手付放棄や手付倍返しによる契約解除はできません。
この段階に進んだ後、契約を解除しようと思えば、売主と買主が双方話し合って行う合意解除をする必要があります。
例えば、手付金の額以外に、リフォーム費用を負担するといった内容で合意解除することになります。
実際の不動産売買では「履行の着手」が曖昧になってトラブルになることを防ぐために、手付金の放棄または倍返しによる契約解除ができる期限を1~2週間後までに定めて売買契約書に記載することもあります。
売買契約締結後の契約解除は不可能ではない
売買契約を結んだ後、契約解除するには手付放棄や手付2倍返しなどのペナルティが発生するとはいえ、不可能なことではありません。
ちなみに、手付放棄や手付2倍返しはあくまでも「相手方に請求できる(支払う)」と定めるだけであって、相手方が納得してくれればペナルティなしで契約を解除することもできます。
その他、売買契約の解除にはいくつかのパターンがあります。
ここでは、それぞれのパターンについてご紹介します。
話し合いで両者合意のもと契約解除
まずは、合意解除と呼ばれるもので、この場合、売主と買主の話し合いで条件を決めて契約解除します。
合意解除は両者合意さえすれば、どのタイミングでも行うことができます。
本来であれば手付放棄などペナルティが発生するケースでも、ペナルティが発生しないように解除することもありますし、具体的にいくらの損害があるから、その損害を支払うことで契約を解除するといったものもあります。
手付放棄による契約解除
次は手付放棄による契約解除です。
先述の通り、買主側から契約解除するには、支払った手付金を放棄することで、売主側から放棄するには受け取った手付金の倍額を支払うことで契約解除できます。
ただし、手付放棄による方法で契約解除できるのは、相手側が「契約の履行に着手するまで」の間となっています。
契約不適合による契約解除
契約不適合による契約解除とは、売買対象の不動産について、シロアリが発生していることが契約書に記載されていなかったのに関わらず、引き渡し後にシロアリが発生していることを知ったようなケースで売主が責任を負わなければならないものです。
なお、契約の内容に適合しないときは、まずは追完請求(補修請求)、つまり補修するように請求する必要があります。
契約解除するには、追完請求をしたのにも関わらず、売主が応じないときに行使できる催告解除か、契約内容の不適合により契約の目的を達成できないときに行える無催告解除かのどちらかの方法を取る必要があります。
ローン特約等による契約解除
ローン特約とは、住宅ローンを組んで不動産を購入する計画で進めていたものの、住宅ローンが否決になってしまって、物件を購入できないときに行使できる権利です。
ローン特約を行使すると、白紙解約、つまり契約は初めからなかったものとして、支払った手付金は無利息で返還してもらうことができます。
ただし、ローン特約では売買契約の日から2週間など期限を設定し、期限を超えてからローンが否決となった場合には権利を行使できません。
このため、ローン特約の期限の日に住宅ローンの審査結果が出ていない場合には、延長の申出を行う必要があります。
なお、ローン特約は必ず設定されるものではなく、売主の合意を得た上で設定されるものです。
クーリング・オフによる契約解除
不動産売買契約では、一定の条件下で売買契約が締結された場合、クーリング・オフできることになっています。
一定の条件とは、具体的には以下のようなものです。
- 売主が宅建業者であること
- 買主が宅建業者でないこと
- 売買契約が事務所等以外の場所で行われること
具体的には、個人が不動産会社から建売住宅や新築マンション、リノベーションマンションを購入するといったケースが該当するでしょう。
ただし、売買契約が不動産会社の事務所等で行われた場合には正常で安定的な購入意思を維持できると判断され、クーリング・オフの対象外となります。
例えば、喫茶店やファミリーレストランで売買契約が締結された場合には、不動産会社の事務所等以外での契約となり、クーリング・オフの対象となります。
なお、クーリング・オフは契約解除等の方法について告げられた日から起算して8日以内に行う必要があります。
ちなみに、不動産会社がクーリング・オフの契約解除等の方法について伝える際には、その旨が記載された告知書を交付する必要があります。
この告知書の交付を受けていない場合にはいつまでもクーリング・オフによる契約解除ができることとされています(ただし、不動産の引渡しを受け、かつその代金の全額を支払った後には契約解除できません)。
消費者契約法による契約解除
不動産取引に関わらず、さまざまな契約において適用される消費者契約法ですが、不動産取引においても一定の条件を満たしていれば、契約解除できることがあります。
まず、消費者契約法は事業者と消費者との間で交わされる契約において、消費者を保護することを目的としているため、不動産会社同士の売買契約等には適用されません。
消費者契約法が適用されるのは、不動産会社から建売住宅を購入するケースや、不動産会社に不動産を買い取ってもらうケースです。
ちなみに、不動産会社に仲介に入ってもらって不動産を売買する際には、実際に取引するのは個人対個人ですが、仲介においても不動産会社の違反行為があった場合には、消費者契約法に基づいで契約解除できる可能性があります。
消費者契約法に基づいて契約解除できるケースとしては、以下のようなものが考えられます。
- 不実告知
- 断定的判断の提供
- 不利益事実の不告知
- 不退去・監禁
不実告知
不動産会社が消費者に対して、不動産の取引に関する重要事項について事実と異なる説明を行った結果、消費者が誤認した場合に契約を取り消せるというものです。
例えば不動産に抵当権が設定されているのにも関わらず、設定されていないと伝えたうえで契約した場合に適用されます。
これは、不動産会社に悪意がなく、勘違いしていたという場合にも適用されます。
断定的判断の提供
不動産会社が消費者に対して、まだ計画段階であるのにも関わらず、新しい駅や道路ができるから地価が上がるといったことを断定し、そのことを理由として契約した場合に、契約を取り消せるというものです。
こちらも、不動産会社側に悪意がなかったとしても適用されます。
不利益事実の不告知
不動産会社が消費者に対して、新しく大きなマンションが建設されることを知ったうえで、陽当たりや風通しがよい物件といったことを伝え、そのことを理由に契約した場合に契約を取り消せるというものです。
こちらは、不動産会社に悪意があることが前提となります。
不退去・�監禁
不動産会社が消費者に対して、契約させるために消費者の自宅や不動産会社の事務所から帰らなかったり、消費者を帰らせなかったりして契約した場合に、契約を取り消せるというものです。
契約違反による契約解除
最後は契約違反による契約解除です。
不動産売買契約では、買主は売主に対して「契約の対価となるお金を支払う」義務があり、一方の売主は買主に対して「契約の対象となる不動産を引き渡す」義務があります。
不動産売買契約において、契約違反とはこの義務を守らないことが当てはまります。
例えば、買主が売主に対してお金を支払わなかったのにも関わらず、物件の引き渡しを行わなかったり、売主が買主に対して物件を引き渡したのにも関わらず、お金を支払わなかったりした場合に適用されます。
こうした契約違反があった場合、相当の期間を定めて催告し、それでも義務の履行がない場合には損害賠償請求や契約解除ができます。
解除違約金が発生するのはどんな時か
契約を解除すると手付放棄や手付2倍返し以外に違約金というペナルティが発生することがありますが、こうした解除違約金が発生するのはどんなケースなのでしょうか。
違約金が発生するケース
手付放棄や手付2倍返しによる契約解除ができるのは、相手方が契約履行に着手した後とされていることはお伝えしましたが、この相手方が契約履行に着手した後に契約解除する場合には、違約金が発生することになります。
ちなみに、不動産売買契約では違約金の額をあらかじめ定めるのが一般的で、この額は売買代金の1割~2割程度とするのが一般的です。
実際に契約違反により違約金が支払われることになった場合、実損額がこの違約金の額を超えていたとしても、違約金の額を超えて請求することはできないこととなっています。
違約金が発生しないケース
通常、取引の一方が契約の履行に着手しているのにも関わらず、他方が義務を全うしない(債務不履行)場合には契約を解除した後、違約金を請求することができます。
このとき、何らかの事情により義務を全うできないという場合には、違約金が発生しないケースもあります。
契約の履行に着手できない理由が発生した場合には、できるだけ早く相手方にその旨を伝えるようにするとよいでしょう。
【注意】不動産売買契約で得た「手付金」や「違約金」は課税対象
ちなみに、不動産売買契約で得た手付金(相手方の放棄・倍返しによって受け取ったもの)や違約金
→売買が成立せずに受け取った金銭
は一時所得として所得税や住民税の課税対象となります。
税金の計算上、一時所得は以下のように計算します。
例えば、違約金で200万円を得て、その年に他に一時所得がなかった場合には、200万円-50万円×1/2=75万円が課税対象となる計算です。
一時所得は総合課税に分類されるため、給与所得など他の所得と合算して計算し、所得税や住民税を納める必要があります。
手付金や違約金について受け取ったお金があるときには、お金を受け取った年の翌年2月16日~3月15日までの間に確定申告をして納めましょう。
なお、住民税は所得税の確定申告をすることで、自動的に納税額が計算される仕組みになっています。
よくある不動産売買契約の解除事例5つ
最後に、不動産売買契約においてよくある解除事例を5つご紹介していきたいと思います。
事例①仕事の都合で転勤になった
まずは、住宅を購入する予定で進めていたものの、仕事の都合で転勤となり、住むことができなくなったというものです。
奥様や子供を残して単身赴任するというケースもあるでしょうが、家族全員一緒に行くとなった場合、住まない家を所有していても仕方がないでしょう。
こうしたケースでは、できるだけ早いタイミングで不動産会社を通して売主に解除の申し入れをするようにしましょう。
売買契約締結前であれば、基本的にはノーペナルティで契約をなしにできますが、売買契約後、相手方が契約履行に着手するまでの間であれば、手付金を放棄する必要があります。
また、相手方が契約の履行に着手した後であれば、相手方と話し合って合意解除することになります。
具体的な損失が出ていた場合は話は別ですが、買主側に転勤等の事情がある場合、例え売買契約締結後でも、手付金を返還してくれるケースも珍しくはありません。
相手方次第ではありますが、まずは相談してみることをおすすめします。
事例②婚約の破談
夫婦で一緒に住む予定で住宅の購入を進めていたものの、婚約が破断になってしまったため、契約を解除するといったものです。
夫婦、もしくは家族で済む予定だった家を、独身のまま購入しても必要以上に大きな家ということが多いでしょうし、そもそも夫婦で住宅ローンを組む予定で進めていた場合には、購入すること自体できないということもあるでしょう。
こちらも、売買契約の進み具合に応じて手付金の放棄や合意解除等の手続を進める必要があります。
なお、合意解除でまとまったお金を支払う必要がある場合は、婚約関係にあった2人でどのくらいずつ負担するかといったことも話し合う必要があるでしょう。
話がまとまらず、相手方に連絡できないでいたまま相手方が履行に着手してしまい、負担が大きくなることのないように気を付ける必要があります。
事例③別の物件を見つけた
住宅を購入する予定で話を進めていたものの、より理想に近い物件が見つかったため、契約を解除するといったケースです。
こちらも、契約の進展具合によって手付放棄や合意解除といった手続きを進める必要があります。
転勤等と比べて、買主側の都合によるところが大きく、相手方が譲歩してくれる可能性は低いといえるでしょう。
手付放棄や違約金を支払ってでも別の物件を購入する方がよいのか、ペナルティの程度に応じて総合的に判断することが求められます。
事例④家族の反対にあった
住宅を購入する予定で話を進めていたものの、家族の反対にあって契約を解除するというものです。
夫婦で話を進めており契約まで進めたものの、そのことを両親や親戚に報告したときに反対に遭うというもので、特に親戚に建築関係者や大工さんがいる場合にこのような事態に進展することが多いといえます。
買主としては、両親や親戚の中に、住宅の購入について口を挟みそうな人がいるようであれば、できるだけ早い段階で話を通しておくと共に、契約前の段階で一度一緒に物件を見学するといったことをしておくと万全です。
特に、売買契約後に家族の反対に遭ったという場合、支払った手付金を放棄しないといけない点に注意が必要です。
買主としても、最初はいい物件と思っていても親や親戚から反対に合ってしまうと気持ちが萎えてしまうということも多いものです。
とはいえ、両親や親戚がいうことが必ずしも正しいとは限りません。
ペナルティの程度に応じて、場合によっては両親や親戚の反対を押し切ってでも契約を進めるといった判断をすることも考えるとよいでしょう。
事例⑤土地改良工事の予算がオーバー
土地を購入して土地の上に住宅を新築するケースでは、土地決済後に地盤調査を行うのが一般的です。
売主としても、土地売却前に地盤調査をして、地盤改良工事の費用が高いことを理由に契約が不意になってしまうのは嫌だからです。
このようなケースでは、すでに土地の決済をしてしまっているため、契約を解除することはできません。
建物の工事については、工事に着工していないのであれば契約解除することもできなくはありませんが、土地代金について住宅ローンのつなぎ融資を受けるのが一般的で、この場合はすでに融資を受けてしまっているので先に話を進めるしかないでしょう。
土地決済とつなぎ融資
通常、住宅ローンは完成された土地と建物に対して融資を行うものなので、家が完成してからでないと融資を受けることはできません。
しかし、土地を購入して住宅を購入するケースでは、先に土地を購入する必要があることから、住宅ローン実行前に土地代金を用意しなくてはなりません。
このときに利用するのが、つなぎ融資です。
つなぎ融資は、土地代金や着手金などを住宅ローン実行の前に借りて、建物完成と同時に住宅ローンの融資を受けて完済するものです。
ここでご紹介しているような、土地の改良工事が高額で売買契約を解除したいというケースでは、先につなぎ融資を受けている以上、土地の契約を解除して新しく土地を探すというのはかなり難しいといえます。
土地の費用だけ自己資金で購入しているケースであればつなぎ融資の問題はありませんが、それにしても、一度決済した契約を、買主の都合で解約することは難しいでしょう。
特約を設けることで問題を回避できる
こうしたケースでは、売買契約時に「土地改良工事に〇〇万円以上の費用がかかる場合には契約を白紙解約する」といった特約を設けておくとよいでしょう。
もちろん、売主によっては、あらかじめ地盤調査させてくれるケースもあるため、事前に地盤調査させてもらえないか交渉するのも一つの方法です。
このように、土地を購入して住宅を新築するケースでは、土地の改良工事費用がネックになることがあるため、慎重に進めることが大切だといえます。
まとめ
不動産売買契約における契約解除について売買契約の内容や契約解除のパターン、よくある契約解除の事例などご紹介しました。
不動産売買契約において、途中で契約がとりやめになったり、契約解除となったりすることは珍しいことではありませんが、そのタイミングによっては多大な負担が生じる可能性がある点に注意が必要です。
特約を設けることで、あらかじめ対策できることも少なくないため、本記事の内容を参考に売買契約を進めていくことをおすすめします。