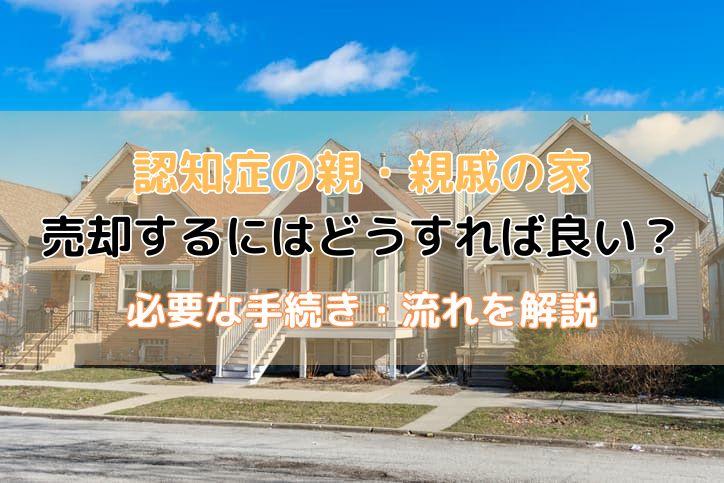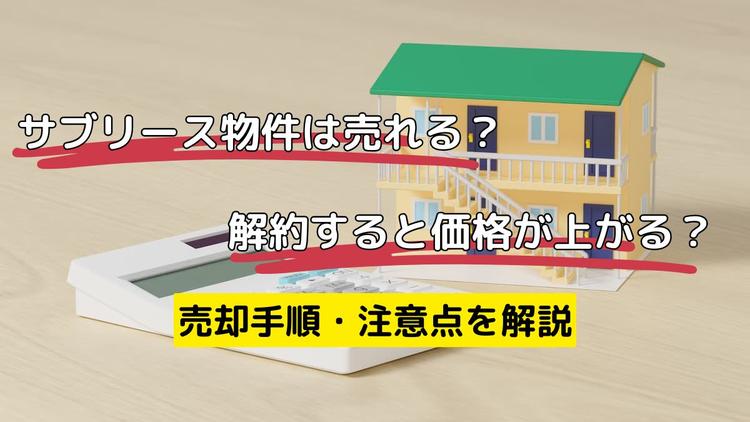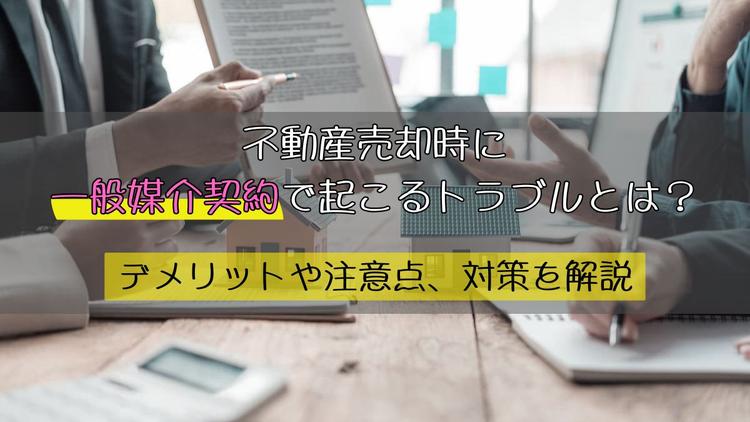不動産を売ったあとで、何か欠陥が見つかったら…。あとで契約解除される可能性があると思ったら、不安なのですが。
何か欠陥があったときには、売主が責任を負う必要があって、これを「瑕疵担保責任」といいます。普通は責任を負うべき期間を決めます。
欠陥のことを「瑕疵」というんですね。雨漏りやシロアリ被害などが思い浮かびます。
他にも、土地や建物に関する法律的な基準に違反しているものや、隣にゴミ屋敷があるといった環境に対するものがあります。それから、過去に事故があった物件などでは、心理的瑕疵もありますね。
瑕疵担保責任を負うべき期間は、一般的にどのくらいになるのですか?
民法上は「瑕疵があると知ってから1年以内」とされていますが、ケースバイケースです。瑕疵担保責任は、2020年4月から「契約不適合責任」にかわるので、その情報についても確認しておきましょう!
瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任と聞くと、なじみの薄い言葉と感じられるかと思いますが、不動産の売買においては重要な言葉です。
売主が買主に対して負う必要のある責任で、売主としては売却後いつまでも損害賠償請求や契約の解除されてしまう可能性があると安心できないため、売買契約時に責任を負う期間を定めるのが一般的です。
なお、瑕疵にはさまざまな分類があり、買主が瑕疵について売主に損害賠償請求などするためには「買主が通常の注意を払ってでも発見できない瑕疵である」必要があるとされています。
このことを隠れた瑕疵と呼びます。
以下、瑕疵担保責任について詳しく見ていきましょう。
瑕疵の4つの種類
まずは何が瑕疵にあたるのか、見てみましょう。
瑕疵は以下の4つに分類することができます。
- 物理的瑕疵
- 法律的瑕疵
- 環境的瑕疵
- 心理的瑕疵
物理的瑕疵
物理的瑕疵とは建物そのものにある物理的な欠陥を指すもので、4つの瑕疵の中でもっとも分かりやすいものだと言えるでしょう。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 雨漏り
- シロアリ被害
- 地盤沈下
- 地中埋設物
- 建物の傾き…など
法律的瑕疵
法律的瑕疵とは、土地や建物に関する法律的欠陥により建物の再建築が出来ないと言ったケースが該当します。
例えば、建物を建てるには幅4m以上の道路に2m以上接道していないといけない接道義務といった規制がありますが、何らかの理由により接道義務を満たさなくなってしまっているものや、建築面積や延べ床面積の上限を決める建ぺい率や容積率に違反しているようなケースが挙げられます。
その他、以下のようなものが該当します。
- 開発行為が認められない市街化調整区域内にある
- 構造上の安全基準が満たされていない
- 防災設備を備えていない…など
環境的瑕疵
環境的瑕疵とは、ゴミ屋敷が隣にあるといったことや、暴力団事務所が近くにあるといった、周辺環境を要因とする瑕疵です。
次の心理的瑕疵と同じく、売主は気にしていなかったものの、買主からするととても住めない、といった感想を持つなど、住む人によって感じ方が変わるものもあります。
その他、以下のようなものが該当します。
- 繁華街による騒音
- 電車やトラックによる振動
- 高層マンションによる日照問題
- 火葬場や産廃施設など嫌悪施設がある…など
▼関連記事:環境的瑕疵に該当する「嫌悪施設」とは?
心理的瑕疵
心理的瑕疵はその物件で過去に自殺や事故があったような場合や周辺に暴力団事務所などがあるといったことが該当します。
環境的瑕疵でご紹介した暴力団事務所があることが心理的瑕疵に含まれているように、同じことでも状況に応じて環境的瑕疵となったり、心理的瑕疵となったりします。
この場合、実際に暴力団事務所が事故を起こしていたような場合には環境的瑕疵に、事件は起こしていないが不安を感じる場合には心理的瑕疵になるといった形で分けられます。
心理的瑕疵は、住む人がどう感じるか次第で多くのことが該当するように思えてしまいますが、過去の判例では、心理的瑕疵と判断するには「買主が瑕疵とするのと同じく一般人がその物件を瑕疵だと感じること」が重要だとしています。
隠れた瑕疵とは?考え方の3つのポイント
次に、瑕疵担保責任を原因として損害賠償請求や契約解除するための要件となる「隠れた瑕疵」の考え方について確認しておきましょう。
ポイント①買主の善意無過失
瑕疵担保責任では瑕疵が「隠れている」必要があり、「買主が通常の注意を払ってでも瑕疵を発見できなかった」瑕疵である必要があります。
これを法律用語に置き換えると、買主がその瑕疵について善意無過失である、ということになります。
ポイント②売主の過失の有無は無関係
瑕疵担保責任を追及するには、買主がその瑕疵について善意無過失である必要がありますが、売主の過失の有無は関係がありません。
仮に売主が瑕疵について善意無過失であっても、買主が善意無過失であれば、瑕疵担保責任を追及することができます。
ポイント③売買契約前に伝えておくことが大切
以上のようなことから、物件について瑕疵だと思われることがあれば売却前に買主に伝えておくことが大切です。
「買主に知らせると契約がなくなってしまうかも…」と思って黙っていると、後でバレてしまった時に大きな損害となってしまいます。
少しでも不安に思うことがあれば伝えておくようにしましょう。
瑕疵担保責任の期間
引き続き、瑕疵担保責任の期間について見てみましょう。
瑕疵担保責任がいつまでも請求可能な状態だと売主は不安がなくなりません。
瑕疵担保責任の特約
しかし、「瑕疵があることを知ってから1年以内」では、仮に物件を引き渡してから10年後に瑕疵があることを知ったとしたら、そこから損害賠償請求などすることが可能となってしまいます。
一方、瑕疵担保責任は売買当事者の合意を得られれば原則を変更できる「任意規定」となっています。
そこで、不動産の売買契約の特約で瑕疵担保責任の期間を「引渡後3カ月以内」などとするのが一般的です。
瑕疵担保責任免責も可能?
瑕疵担保責任の期間は売主と買主の同意のもと決められます。
このため、引渡後3カ月以内と言わず、「引渡後2週間」や「引渡後3日間」とすることもあります。
さらに、双方合意が得られれば「瑕疵担保責任免責」とすることも可能です。
ただし、仮に瑕疵担保責任免責とした場合でも売主が瑕疵の存在を知りながら買主に告げなかった場合には免責は無効となります。
宅建業者の瑕疵担保責任
ただし、宅建業者が売主の場合は話が違います。
不動産取引のプロである宅建業者については、宅建業者に有利となりすぎないよういくつかの規制が設けられており、その内の一つに「瑕疵担保責任の期間を引渡しから2年以上とする特約を除き、買主に不利となる特約はできないこと」というものがあります。
これにより買主に不利となる特約をつけてしまった場合はその特約は無効となり、民法の規定通り「引渡しから1年以上」となります。
瑕疵担保責任に基づいて買主が請求できる権利
売却した不動産に瑕疵があることが分かった場合、買主は売主に対して2つの権利を行使することができます。
・損害賠償請求
・契約の解除
それぞれについて見ていきましょう。
損害賠償請求
売却した不動産に瑕疵があることが分かった場合、買主はその瑕疵により生じた損害について、損害賠償請求することができます。
なお、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求で請求できる範囲は信頼利益に限定されるとされています。
信頼利益とは「その契約が有効であると信じたために生じた損害」のことで、分かりやすく言うと「本来であれば支払う必要のなかった損失」ということになります。
契約の解除
売却した不動産に瑕疵があることが分かった場合、その瑕疵により契約目的が達せられない場合には、買主は契約を解除することが可能です。
また、解除後は契約時に支払われた代金について買主から売主に請求する代金返還請求権が生じます。
なお、これら損害賠償請求権や契約の解除権、代金返還請求権には引き渡しから10年間の消滅時効があるとされています。
瑕疵担保責任保険とは
2000年4月に住宅の品質確保の促進等に関する法律が施行され、建築会社など新築住宅を販売する事業者は、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任を負わなければならないこととなりました。
しかし、いくら瑕疵担保責任があったとしても、事業者に資力がなければ、何かあった時に対応してもらうことができません。
そこで、2009年に施行された瑕疵担保履行法により、事業者は瑕疵担保責任を果たすための資力確保の措置を講じなければならなくなりました。
この時に事業者が利用するのが住宅瑕疵担保責任保険です。
これにより、新築住宅引渡し後に瑕疵が見つかった時、事業者の資力に関わらず補修費用などを請求することが可能となり、安心して新築住宅を購入できるようになったのです。
改正民法の契約不適合責任で売主の責任はどう変わる?
ここまで瑕疵担保責任について解説していきましたが、実は2020年4月1日より民法が改正され、瑕疵担保責任という概念がなくなりました。
改正後、瑕疵担保責任の代わりとなるのが契約不適合責任です。
契約不適合責任では、売買契約の対象物が契約内容に適合しているかどうかが問われます。
瑕疵担保責任から契約不適合責任になることで変わることは多岐に渡りますが、ここではその内代表的なものをお伝えしていきます。
隠れた瑕疵である必要がない
まず、瑕疵担保責任では瑕疵が隠れたものである必要がありました。
つまり、買主が通常の注意を払えば見つけられたような瑕疵であれば責任を追及できませんでしたが、契約不適合責任では瑕疵が隠れているかどうかは関係ありません。
あくまでも売買の対象物が契約内容に適合しているかどうかだけが見られることになります。
損害賠償の責任の範囲が変わる
また、瑕疵担保責任に基づいて損害賠償できる損害の範囲は信頼利益に限るとされていましたが、契約不適合責任では信頼利益だけでなく、履行履歴にまで責任の範囲が及ぶことになります。
履行履歴とは「その契約が履行されていればその利用により発生したであろう利益」のことで、簡単に言うと「受け取れるはずだった利益」ということになります。
瑕疵担保責任の時より責任の範囲が広がり、契約不適合責任により損害賠償請��求された場合にはより多額の請求がなされる可能性があります。
契約書の内容がより重要になる
契約不適合責任で見られるのは売買の対象物が契約の内容に適合しているかどうかです。
このため、契約不適合責任に基づいて損害賠償請求などをされないためには、契約書に物件の状況を事細かに書き、必要に応じて特約事項を設けるなどの対策が必要です。
瑕疵担保席にから契約不適合責任に変わることで、これまで以上に契約書の内容が重要になるのです。
まとめ
不動産の売買では売主は買主に対して瑕疵担保責任を負う必要があります。
瑕疵担保責任は、売主は無過失責任、つまり瑕疵について知らなくても責任を負わなければなりません。
いざ瑕疵が見つかってトラブルになることを防ぐためにも、瑕疵担保責任期間を短く設定するなど交渉していくことが大切です。
また、2020年4月に改正民法が改正され、これまでの瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わり、より契約書の内容が重要となります。
インスペクションを活用するなどして、自分の物件についてよく知った上で売却することが大切だと言えるでしょう。