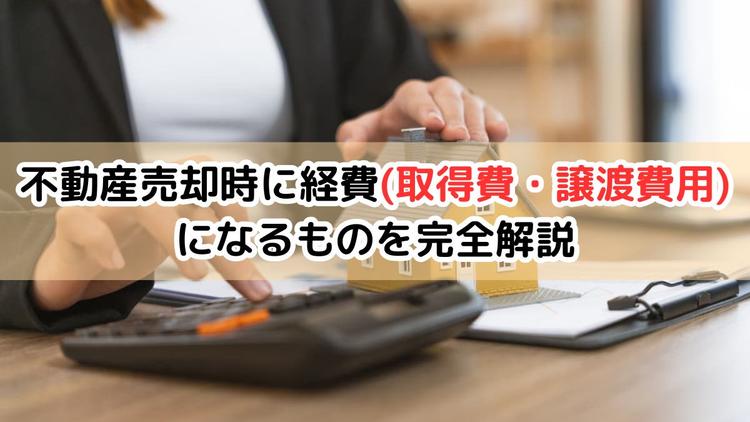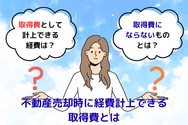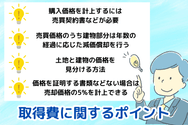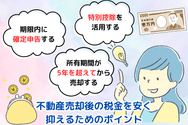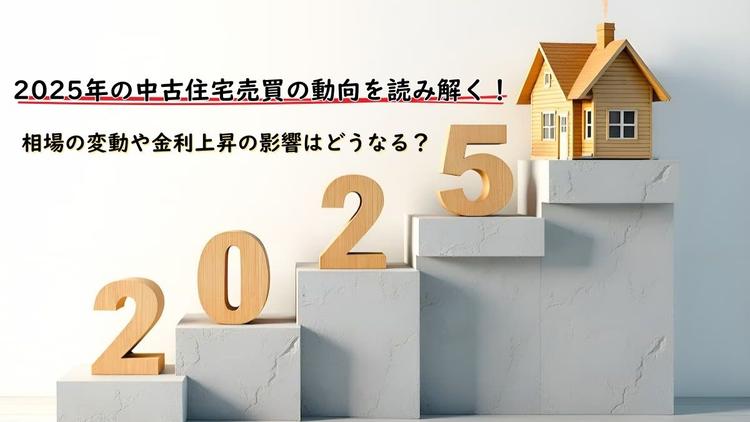不動産売却による利益には税金がかかります。
税金を抑えるためには、経費をしっかり計上し利益を抑えることが重要です。
とはいえ、経費には計上できるもの・できないものがあるので、何を経費にできるかを理解しておく必要があります。
この記事では、不動産売却時に経費になるものや、税金の計算方法、抑え方について分かりやすく解説します。
不動産売却益には税金がかかる
不動産を売却した利益は譲渡所得に区分され、所得税・復興特別所得税・住民税が課税されます。
高額な取引になる不動産売買では、譲渡所得にかかる税金も高額になりがちです。
そのため、税金の計算方法を押さえ事前に額を把握し、資金計画を立てておく必要があります。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、売却額から売却時と購入時の費用を差し引いた部分です。
具体的には、以下の計算式で求めます。
譲渡所得からはさらに3,000万円特別控除などを控除し、その結果プラスになれば譲渡所得にかかる税金が発生します。
この場合、プラス部分に以下の税率を乗じて税額を計算します。
| 所有期間 | 所得税・復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 | |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
所有期間は1月1日時点で計算するため、「購入から丸5年経過した後の1月1日以降の売却で長期譲渡所得の税率が適用される」点を覚えておきましょう。
税率は、不動産の所有期間に応じて異なるので注意してください。
譲渡所得の計算では2種類の経費がある
計算式のとおりに譲渡所得を求める際には、売却額から「取得費」と「譲渡費用」の2種類の経費を差し引きます。
つまり、取得費と譲渡費用をより多く計上すれば譲渡所得の額が小さくなり、結果としてかかる税金も抑えられるのです。
そのため、取得費・譲渡費用について理解し、しっかり経費計上できるようにしておくと、節税効果を得られるでしょう。
以下では、取得費・譲渡費用それぞれを詳しく解説していくので参考にしてください。
不動産売却時に経費計上できる取得費とは
まずは、取得費について詳しくみていきましょう。
不動産を取得したときに要した費用
取得費とは、不動産を取得した際に支払った費用です。
不動産そのものの価格だけでなく、手数料などの費用を計上できます。
ただし、取得費からは建物の減価償却費を差し引く必要があります。
減価償却費とは、建物の経過年数に応じた資産価値の減少分を考慮する費用です。
たとえば、10年前に5,000万円で購入した建物でも、10年後に5,000万円の価値が続くわけではありません。
この場合、所有していた期間10年分の価値は売主が享受したものと考え、10年分の価値を差し引く必要があるのです。
なお、減価償却は土地が対象外となるため、建物のみで計上します。
つまり、取得費は以下のようになります。
このように、取得費で計上した全額が売却費用から差し引けるわけではない点は覚えておきましょう。
取得費として計上できる経費一覧
不動産そのものの価格以外で、取得費として計上できる主な費用は以下のとおりです。
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 印紙税
- 仲介手数料
- 設備費や改良費
- 購入時に借主を立ち退かすための立退料
- 造成費用
- 測量費
- 所有権確保のために要した訴訟費用
- 土地の利用が目的と認められる場合の建物購入費や取り壊し費用
- 不動産購入時の借入のうち実際に不動産を使用するまでの期間の利子
- 不動産を取得するため�にすでに行った契約を解除した際の違約金
取得費にならないもの
不動産購入時の費用であっても、以下のような費用は計上できません。
- 固定資産税
- 住宅ローンの金利
- 入居後に支払った修繕費
- 引越し費用
- 火災保険料
取得費は、原則として不動産を購入するために必要な費用です。
不動産を維持・管理するための費用は計上できないので注意しましょう。
取得費に関するポイント
ここでは、取得費を計上するうえで押さえておきたいポイントとして以下の4つを解説します。
- 購入価格を計上するには売買契約書などが必要
- 売買価格のうち建物部分は年数の経過に応じた減価償却を行う
- 土地と建物の価格を見分ける方法
- 価格を証明する書類などない場合は売却価格の5%を計上できる
それぞれ見ていきましょう。
購入価格を計上するには売買契約書などが必要
取得費を計上するためには、売買契約書や領収書などの価格を証明する書類が必要です。
売買契約書は、売買契約の際に不動産会社が内容を説明して買主に引き渡されます。
見つからない場合は、保管していそうな書斎や書類棚などを探してみるようにしましょう。
物件を購入した際の不動産会社や売主が保管しているケースもあるので、連絡を取ってみるのも1つの方法です。
また、以下のような書類が売買契約書や領収書の代わりに利用できる可能性があります。
- パンフレット
- 通常の振込履歴
- 住宅ローンや住宅ローン関連の書類
- 仲介手数料の計算明細書
できるだけ複数の資料で信ぴょう性を高めれば、認められる可能性があります。
ただし、認められるかは税務署の裁量にもよるので、できるだけ売買契約書を探すようにしましょう。
売買価格のうち建物部分は年数の経過に応じた減価償却を行う
前述のとおり、取得費からは建物の減価償却費を差し引く必要があります。
減価償却費の計算方法は以下のとおりです。
償却率は、建物の構造ごとに定められており、たとえば木造なら0.031です。
また、経過年数では6ヵ月以上の端数は1年、6ヵ月未満は切り捨てます。
仮に、木造を3,000万円で購入し15年経過した場合の減価償却費は以下のとおりです。
そのため、建物の取得費としては3,000万円-1,255万円=1,745万円を計上することになります。
売却額よりも取得費が大きく赤字になると思っていても、減価償却を計上することで利益が出て課税されるケースもあるので注意しましょう。
▼関連記事:不動産売却時の減価償却費の計算方法
土地と建物の価格を見分ける方法
マンションのように土地と建物の総額で取引すると、土地と建物がそれぞれいくらか分からないケースもあります。
しかし、建物は減価償却を行う必要があるため、購入時の金額は土地と建物の内訳を明確にしなければなりません。
総額で取引した場合でも、売買契約書に内訳が記載されているなら、その金額を用いることが可能です。
売買契約書を紛失している場合や、あるけれど内訳が分からないという場合は、以下のような方法が検討できます。
- 消費税から建物価格を算出する
- 購入時点の固定資産税評価額割合を売買金額に換算する
- 標準建築価額表を用いる
消費税は建物にしかかからないため、売買契約書に消費税額が記載されているなら、そこから建物価格を算出できます。
たとえば、6,000万円で購入し、消費税が450万円と記載されている場合、450万円÷10%=4,500万円が建物価格です。
この場合、土地価格は6,000万円-4,500万円-450万円=1,050万円となります。
ただし、消費税の税率は取引した年月日で異なるので注意しましょう。
消費税率が分からない場合は、土地と建物それぞれの固定資産税評価額の割合に売買価格を乗じて算出することも可能です。
それらでも分からない場合は、国税庁の標準建築価額表から建築費を算出できます1。
価格を証明する書類などない場合は売却価格の5%を計上できる
所有期間が長期に渡るといった理由で、購入時の売買契約書などの書類を紛失しているケースは珍しくありません。
この場合、概算の取得費として売却価格×5%を計上することになります。
ただし、概算取得費は本来の取得費よりも低くなることがほとんどで、利益が発生し課税されやすくなる点に注意しましょう。
たとえば、本来の取得費が3,000万円(減価償却後)の不動産を3,000万円で売却すれば、税金は発生しません。
しかし、本来の取得費を証明できないと、概算取得費として3,000万円×5%=150万円しか計上できない為、利益が2,850万円発生してしまうのです。
概算取得費しか計上できない場合は税負担がかかりやすので、かかった費用を証明する書類を提出できるようにあらかじめ保管場所を決めておくなど対策しておきましょう。
不動産売却時に経費計上できる譲渡費用とは
次に、売却価格から差し引くもう一つの経費である「譲渡費用」についてみていきましょう。
不動産を売却したときに要した費用
譲渡費用とは、不動産を売却したときにかかった費用です。
取得費同様、不動産を売却するために直接かかった費用が計上でき、反対に不動産を維持・管理するための費用は計上できないので注意しましょう。
譲渡費用として計上できる経費一覧
譲渡費用として計上できる主な経費は以下のとおりです2。
- 仲介手数料
- 売主が負担した印紙税
- 貸家を売るために賃借人に支払った立退料
- 土地を売るために家屋を解体した時の取り壊し費用と建物の損失額
- すでに締結した売買契約をより条件の良い取引に変えるために支払った違約金
- 名義書換料など
譲渡費用にならないもの
一方、以下のような費用は譲渡費用として計上できません。
- 抵当権抹消費用
- 住所・氏名変更登記の費用
- 引越し費用
- 遺産分割にかかる弁護士費用 など
売却にともない住宅ローンを完済し、不動産登記簿から抵当権を削除する「抵当権抹消登記」を行うケースは多くあります。
この場合、登録免許税や司法書士報酬などの費用が発生しますが、これらの費用は計上できません。
抵当権抹消登記は、住宅ローンを完済すれば売却に限らず行う手続きであることから、売却に直接かかった費用とはみなされないのです。
また、登記簿上の所有者の住所や氏名を変更する「住所・氏名変更登記」の費用も、本来なら変更があった際に行うべき手続きのため、譲渡費用には含められません。
譲渡費用や取得費は、項目によって計上できるかの判断が難しいケースもあります。
判断に悩む場合は、税務署や税理士などに確認するとよいでしょう。
不動産売却後の税金を安く抑えるためのポイント
経費を計上する以外にも、不動産売却益にかかる税金を抑える方法はいくつかあります。
ここでは、税金を抑えるためのポイントとして以下の3つを解説します。
- 特別控除を活用する
- 不動産の所有期間が5年を超えてから売却する
- 期限内に確定申告する
それぞれ見ていきましょう。
特別控除を活用する
譲渡所得にかかる税金は、譲渡所得からさらに特別控除を差し引いた部分が対象です。
具体的には、以下の計算式で求められます。
そのため、取得費と譲渡費用を差し引いてプラスになる場合でも、特別控除を活用することで税負担を軽減できる可能性があります。
代表的な特別控除に「3,000万円特別控除」があります。
この控除では、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるため、譲渡所得3,000万円以下であれば税金が発生しなくなるのです。
たとえば、以下のケースでみてみましょう。
- 売却額:5,000万円
- 取得費:3,000万円(減価償却後)
- 譲渡費用:400万円
この場合、5,000万円-(3,000万円+400万円)=1,600万円が譲渡所得であり、プラスになるので税金の対象です。
しかし、3,000万円特別控除が適用できれば、課税譲渡所得が0円となるので税金は発生しません。
譲渡所得で利用できる特例には、3,000万円特別控除以外にも「買い替え特例」や「10年超所有軽減税率の特例」などいくつか用意されています。
それぞれ適用要件や併用の可否が異なるので、要件をチェックし、どの特例を適用したほうがお得になるかシミュレーションして検討するとよいでしょう。
特例の適用に不安がある方は、税理士などのプロへの相談をおすすめします。
▼関連記事:住宅を買い替えた場合の税金の特例とは?5つの特例について解説
不動産の所有期間が5年を超えてから売却する
譲渡所得にかかる税金の税率は、所有期間5年を境に以下のように異なります。
| 所有期間 | 所得税・復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 | |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
5年以下で売却すると5年超の倍近い税率となり税負担も増えるため、節税の面でいえば、所有期間が5年を超えてから売却した方がよいでしょう。
なお、所有期間を算出する基準となるのは「売却した年の1月1日」です。
実際の所有期間では5年を超えていても、売却した土地の1月1日時点で5年経過していないと、短期譲渡所得に区分されるので注意しましょう。
また、相続した不動産の場合は、被相続人(亡くなった人)の所有期間を含められます。
ただし、特例などの活用により税金が発生しないのであれば、所有期間を気にする必要はありません。
不動産は築年数が経過するほど資産価値も下がるので、まずは税金をシミュレーションしたうえで5年待つかどうかを判断するとよいでしょう。
期限内に確定申告する
不動産売却では、以下のケースで確定申告が必要です。
- 譲渡所得税が課税される
- 特例を適用する
譲渡所得の計算の結果、譲渡所得税が発生する場合は確定申告して納税が必要です。
また、特別控除などの特例の適用にも確定申告が必要になります。
そのため、特例を適用すれば税金が発生しないケースや、譲渡損失が出て特例を適用するケースでも、確定申告しなければいけません。
「特例を適用すれば税金が発生しないから確定申告は不要」とはならいないので注意しましょう。
確定申告時期は、売却した年の翌年2月16日から3月15日です。
この期間に確定申告できないと、無申告加算税などのペナルティで税負担が大きくなります。
税負担を増やさないためにも、期限内にきっちり確定申告しましょう。
不動産売却時に経費になるものに関するよくある質問
最後に、不動産売却時に経費になるものに関するよくある質問をみていきましょう。
譲渡所得の取得費で領収書がない場合はどうなる?
売買契約書や領収書がなければ、基本的に経費計上できません。
ただし、通帳の振込履歴などで代替えできる可能性もあるので、税理士などに相談してみるとよいでしょう。
また、書類がなく取得費を証明できない場合は、概算取得費として売却額×5%の計上が可能です。
不動産売却前のリフォーム費用は確定申告で経費計上できる?
リフォーム費用は、タイミングや目的によって譲渡費用や取得費になったり、計上できなかったりするので注意が必要です。
売却目的のために、売却直前に行った資産価値を高めるためのリフォームであれば、譲渡費用に計上できます。
一方、自分たちの生活のために住宅の性能向上を行うリフォームは取得費になります。
さらに、住宅の性能向上を伴わない日常的なメンテナンスであれば、経費計上できないのです。
判断が難しくなるため、税理士などに相談するとよいでしょう。
交通費は不動産売却時の確定申告で経費計上できる?
売買契約や内覧など、売却のための交通費であれば譲渡費用として計上できます。
ただし、仕事や帰省を兼ねているなど他の目的が含まれると全額計上できないので注意しましょう。
まとめ
不動産売却では、利益が出ると譲渡所得税が課税されます。
税負担を抑えるためには、取得費・譲渡費用として計上できるものを押さえ、すべて計上することが大切です。
不動産会社によっては税理面もサポートしてくれるので、不安な方は相談しながら売却を進めるとよいでしょう。
また、税負担を押さえる以上に高値で売却できれば手元に残るお金も大きくなります。
信頼できる不動産会社を見つけ、売却や税理面のサポートを受けながら満足いく売却を目指しましょう。