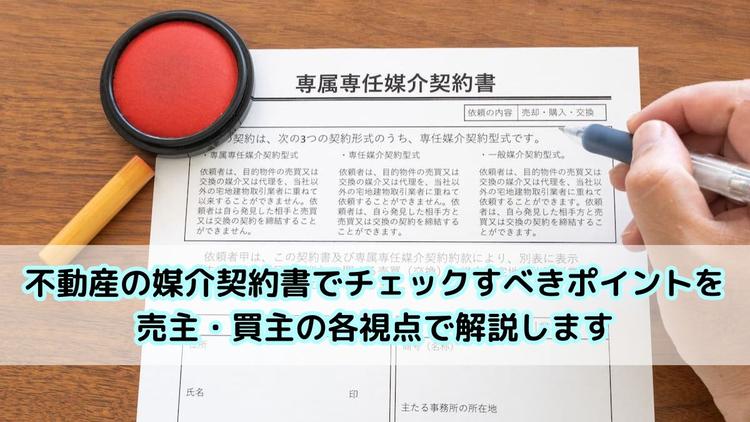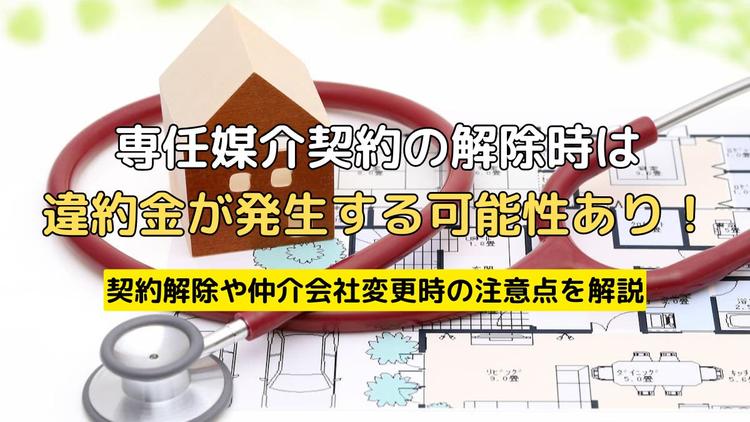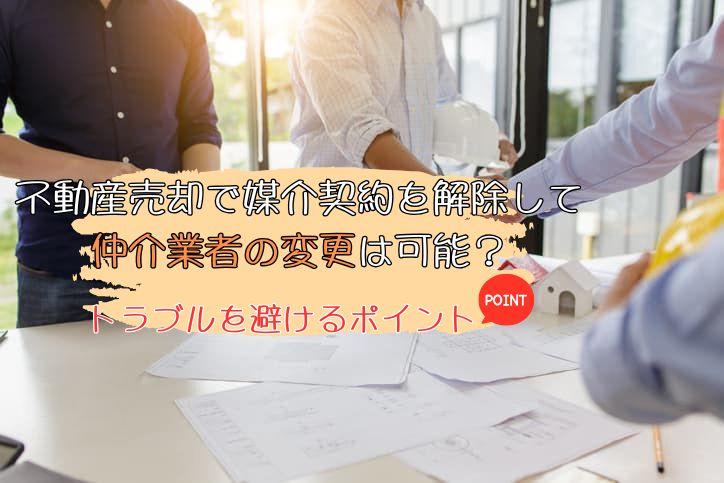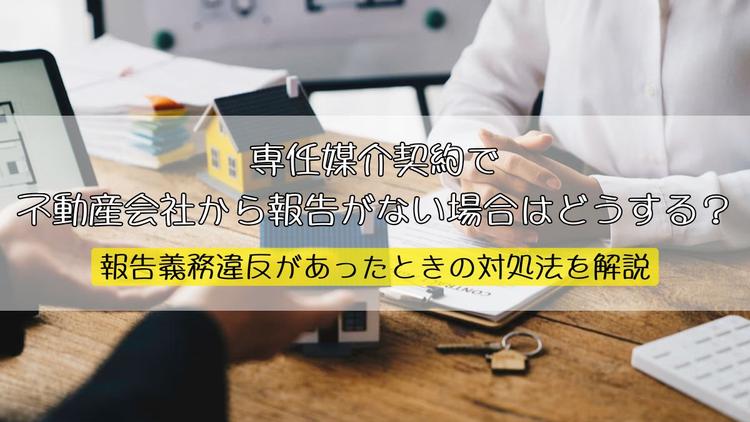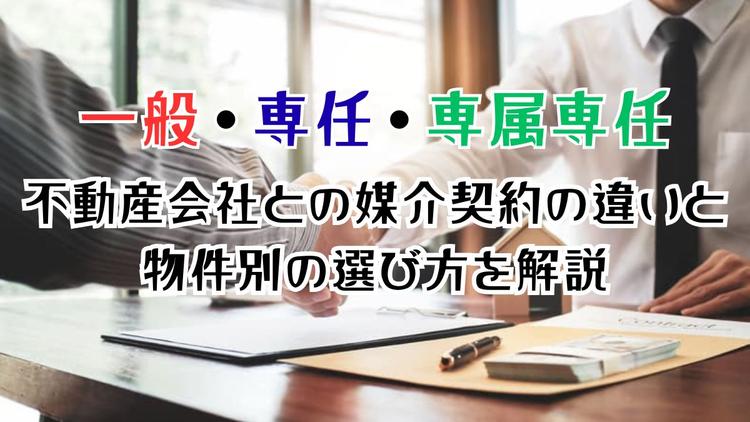不動産を売却する際には、不動産会社と媒介契約を結ぶのが一般的です。
媒介契約書は不動産会社とのトラブルを避けるうえでも重要な書類になるので、契約時には入念なチェックが欠かせません。
とはいえ、媒介契約書の内容は専門的でよく分からないという方もいるでしょう。
そこで、この記事では媒介契約書のチェックポイントと契約の流れを、売主・買主それぞれの視点で詳しく解説します。
媒介契約書とは
媒介契約書とは、仲介で売買する際に不動産会社と結ぶ媒介契約の書類です。
仲介での売却では、売主が不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社が買主を探して売買が成立します。
この際、売主と不動産会社の権利や義務、責任、報酬などを明らかにし、トラブルを避けるために交付されるのが媒介契約書です。
媒介契約書の交付は、宅地建物取引業法に仲介業務を行う不動産会社の義務として定められています。
また、契約書の書式は不動産会社で自由に決められますが、ほどんとの不動産会社で国土交通省が告示している「標準媒介契約約款」に基づいて作成されているので、確認の際に参考にするとよいでしょう。
なお、売主だけでなく買主側も不動産会社を通して不動産の紹介を受けるので、この際にも媒介契約を結びます。
そのため、売主・買主ともに媒介契約書の内容を理解しておくことが大切です。
【売主視点・買主視点】媒介契約書のチェックポイント
ここでは、媒介契約書でとくにチェックしておきたいポイントを紹介します。
媒介契約の種類
媒介契約の種類には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
大まかな違いは以下のとおりです。
| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
| 契約できる不動産会社 | 複数 | 1社のみ | 1社のみ |
| レインズへの登録義務 | なし | あり 契約から7日以内 | あり 契約から5日以内 |
| 営業活動の報告義務 | なし | あり 2週間に1回以上 | あり 1週間に1回以上 |
| 自己発見取引 | 可 | 可 | 不可 |
| 契約期間 | 定めなし 一般的には3ヵ月 | 最長3ヵ月 | 最長3ヵ月 |
一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約できる形態です。
一方、専任媒介契約・専属専任媒介契約は1社のみとしか契約できません。
専任媒介契約・専属専任媒介契約を結んでいるのに他の不動産会社と契約してしまうと、契約違反として違約金を請求される恐れがあるので注意しましょう。
媒介契約の種類は売却にも影響するので、売主は希望した種類かどうかをしっかり確認することが大切です。
契約期間
専任媒介契約・専属専任媒介契約の契約期間は最長3ヵ月です。
3ヵ月より短くはできますが、特約でも3ヵ月を超える契約はできません。
また、期間終了後に引き続き契約する場合は更新手続きが必要となり、自動更新はできないので注意しましょう。
契約を解除する場合は、契約期間終了のタイミングで更新しなければ解除となり、違約金などは発生しません。
反対に、契約期間内の売主都合の解除は違約金が発生する恐れがあります。
ただし、不動産会社の落ち度が理由の契約解除であれば違約金は発生しません�。
契約期間は解除や更新を検討するうえでも重要になるので、いつまでが期間となるかを確認しておきましょう。
なお、一般媒介契約では契約期間の法的な定めはありませんが、3ヵ月ほどで設定されているケースがほとんどです。
しかし、3ヵ月を超える契約でも問題ないので、期間は確認しておくようにしましょう。
レインズへの登録義務
専任媒介契約・専属専任媒介契約では、レインズ(不動産情報交換のためのネットワークシステム)への登録義務があります。
不動産会社は、専任媒介契約の場合は契約の翌日から7営業日以内、専属専任媒介契約の場合は5営業日以内に登録しなければいけません。
レインズへの登録後は登録証明書が発行され、売主であれば自分の物件の情報をチェックできます。
レインズの登録内容は売却活動にも大きく影響するので、登録内容と実際の状況が一致しているかは定期的にチェックするようにしましょう。
なお、一般媒介契約ではレインズへの登録義務はありません。
活動内容の報告義務
専任媒介契約・専属専任媒介契約では、売主への活動内容の報告義務があります。
専任媒介契約で2週間に1回以上、専属専任媒介契約で1週間に1回以上が必要です。
活動内容としては、問い合わせや内覧件数、広告などの状況が報告されるので、売主が状況把握や売却戦略を立てるうえで重要な役割を果たします。
そのため、報告方法や内容を契約書で確認し、必要に応じて内容は追加してもらうようにしましょう。
一般媒介契約では、活動内容報告の義務はありません。
売主は、自分でこまめに状況を確認する必要があるので注意しましょう。
仲介手数料の額
仲介で売却が成立すれば、不動産会社に仲介手数料を支払うことになります。
仲介手数料の額は上限が以下のように定められており、上限を超えての請求はできません。
| 売買代金 | 計算式 |
| 200万円以下 | 売買代金×5%+消費税 |
| 200万円超400万円以下 | 売買代金×4%+2万円+消費税 |
| 400万円超 | 売買代金×3%+6万円+消費税 |
たとえば、売買代金が3,000万円なら3,000万円×3%+6万円=96万円(税抜)が上限です。
ただし、売買代金800万円以下の場合、合意を得ることで一律30万円(税抜)の請求が可能です。
仲介手数料は高額になりやすく、追加費用を請求されたなどトラブルになるケースもあります。
また、仲介手数料は売主だけでなく買主も支払う必要があるお金です。
売主・買主共に仲介手数料の発生条件はしっかり確認しておくようにしましょう。
仲介手数料の支払いタイミング
仲介手数料は高額になりがちなので、売主・買主共に支払いタイミングを押さえて準備を進める必要があります。
仲介手数料の支払いタイミングは不動産会社によって異なりますが、一般的には以下の2パターンのいずれかです。
- 売買契約時に半額・決済時に残額
- 決済時に全額
売買契約時に全額というケースもありますが、不動産売買では売買契約後も不動産会社のサポートが必要です。
売買契約後に全額支払ったからといって手を抜かれることはないでしょうが、万が一も考え決済・引き渡しまでは全額を支払わない方がよいでしょう。
また、タイミングとあわせて支払い方法も確認しておくことが大切です。
一般的には現金や銀行振込になりますが、都合の良い支払い方法が利用できるかは確認しておきましょう。
違約金の額
契約期間内に「売却する気がなくなった」など、売主都合で解約すると違約金が発生します。
また、専任媒介契約にもかかわらず他の不動産会社と契約したなどの契約違反でも、違約金が請求される恐れがあります。
一般的に売主都合の解約では、それまで行った営業活動の実費が請求されます。
ただし、実費の請求では本来発生するはずだった報酬(仲介手数料)の額を超えることはできません。
解約時の違約金はトラブルになりやすいので、事前に違約金の発生条件と額を確認しておきましょう。
▼関連記事:媒介契約を解除する際の違約金などに関する注意点
特別な依頼に関する内容と費用
仲介手数料にはそれまでの営業活動の必要経費も含まれているので、不動産会社は基本的に仲介手数料以外の費用を請求できません。
�しかし、売主が特別な依頼を行った場合は、その費用の請求が可能です。
たとえば、新聞の一面への広告を依頼した、遠方に交渉に行ってもらったなど、通常の営業活動となみなされない業務が該当します。
仲介手数料以外の費用が請求されてトラブルになるケースは珍しくありません。
そのため、特別な依頼には何が該当し、いくらかかるのかは事前に確認しておきましょう。
標準約款に基づいているか
媒介契約書には、国土交通省の「標準約款」に基づいて作成されているか否かが記載されます。
基本的には標準約款に基づいて作成されているケースがほとんどですが、義務ではないため、基づかなくても問題はありません。
しかし、標準約款は不動産取引のトラブルを防ぐために利用が推奨されているものです。
基づいていない場合はその理由まで確認し、内容に不安があれば司法書士などのプロに確認してもらうことも検討しましょう。
【売主側】媒介契約の流れ
ここでは、売主が媒介契約を結ぶまでの流れをみていきましょう。
大まかな流れは以下のとおりです。
- 不動産会社に査定依頼を出す
- 査定結果の報告を受ける
- 売却を依頼する不動産会社と媒介契約を結ぶ
それぞれ見ていきましょう。
不動産会社に査定依頼を出す
不動産会社の査定には、「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。
机上査定
机上査定は、築年数や所在地などのデータのみで査定する方法です。
インターネット上で簡単に依頼でき、結果も即日から数日で入手できるというメリットがあります。
しかし、データのみで算出するため、査定額の精度は訪問査定ほど高くありません。
訪問査定
訪問査定とは、不動産会社の担当者が家を訪れて査定する方法です。
データに加え、実際の家の状態や周辺環境なども加味して査定するので、精度の高い査定額が分かりますが、日程調整など手間や時間がかかります。
とりあえず価格が知りたいなら机上査定で問題ありませんが、売却を本格的に検討する場合は訪問査定が必要です。
机上査定で複数社比較し、その中から2~3社に絞って訪問査定を受けると、効率よく不動産会社選びができるでしょう。
▼関連記事:机上査定と訪問査定の違い
査定結果の報告を受ける
不動産会社の査定結果をもとに、不動産会社選びを進めていきます。
この際、査定額の高さだけで選ぶのはおすすめできません。
査定額が相場よりも高い場合、不動産会社は媒介契約を目的としているケースがあります。
仮にその会社で契約しても、売れないことを理由に値下げを要求される恐れがあるでしょう。
不動産会社の査定を比較する際には、以下の要素も考慮することが大切です。
- 不動産会社の実績
- 評判や口コミ
- 査定額の根拠まで説明してくれるか
- 担当者の対応
- レスポンスの早さ
総合的に評価して、信頼できる不動産会社を見つけるようにしましょう。
▼関連記事:高すぎる不動産の査定額には注意が必要
売却を依頼する不動産会社と媒介契約を結ぶ
売却を依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を結びます。
媒介契約時には前述したポイントをしっかりチェックし、納得してからサインするようにしましょう。
媒介契約締結後、媒介契約書が交付されます。
【買主側】媒介契約のタイミング
買主側は媒介契約を結ぶ印象が薄いですが、仲介手数料が発生する以上、媒介契約を結んでいることが前提となっています。
売主ほどチ��ェックポイントは多くありませんが、仲介手数料の額や内容、違約金などはしっかり確認し、契約書にサインすることが大切です。
ただし、売主側と違い買主側の媒介契約のタイミングは、不動産会社によって異なるので注意しましょう。
買主は気に入った物件があったときに問い合わせするのが一般的
媒介契約書は、買主と不動産会社の権利、義務、報酬を明らかにするため、買主が物件の紹介を依頼した時点で契約を結ぶのが理想的です。
とはいえ、買主側は、気に入った物件が見つかると、その物件を取り扱う不動産会社に問い合わせるのが一般的であり、最初から不動産会社を決めて物件探しを依頼するケースは稀です。
物件案内の前に媒介契約をいちいち結んでいると、不動産会社の業務が煩雑になります。
そのため、売買契約時に他の書類と合わせて、媒介契約書にサインするケースが多く、契約形態は一般媒介契約になるのが一般的です。
売買契約まで媒介契約を結ばないケースもある
以前は、買主側とは媒介契約を結ばずに、売買契約時に仲介手数料の約定書にサインするだけというケースも珍しくありませんでした。
また、不動産会社が知り合いである場合、媒介契約を明示せずに売却するケースもあります。
媒介契約は、契約者側と不動産会社が依頼・引き受けるという合意で成立し、契約書の有無は必ずしも成立条件ではありません。
そのため、契約書がなくても媒介契約は有効に成立します。
この場合であっても、きちんと仲介手数料が支払われるなら問題はないで��しょう。
しかし、媒介契約書がないと、仲介手数料の額、支払い期限、違約金などの約束が明確にならないため、トラブルの原因になることがあります。
たとえば、買主が途中で売主と直接交渉し仲介手数料を支払わない、あるいは不動産会社が高額な仲介手数料を請求するといった問題に発展しやすいのです。
仮に、トラブルが発生した場合、媒介契約書がなければどちらの主張が正しいかを判断する材料がなく、言った・言わないの状況に陥り、解決が難しくなるので注意しましょう。
購入の申し込みや価格交渉の際に媒介契約を結ぶケースが増えている
上記のようなトラブルを避けるため、近年では買主側とも媒介契約書を取り交わすケースが一般的です。
また、契約するタイミングについては、購入申し込みや価格交渉するタイミングで結ぶケースが多いようです。
買主側の媒介契約書のタイミングは不動産会社によって異なるので、事前に確認し契約時には契約書の内容をしっかり確認しましょう。
契約内容に疑問がある場合は、その場で質問するなどし、しっかりと解消したうえで契約することが大切です。
媒介契約書を結ばないケースもある?
仲介で不動産売買を行う際には、売主・買主側とも媒介契約書を交わすのが一般的です。
しかし、なかには媒介契約書を交付しないケースもあります。
宅建業法の取り決め
不動産売買のルールを定めた宅地建物取引業法では、媒介契約書について以下のように定めています。
(媒介契約)
第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
つまり、宅建業者(不動産会社など)と媒介契約を結ぶ際には、不動産会社は媒介契約書を交付する必要があります。
ただし、契約を締結した時点で交付が必要というルールではありますが、契約書がなくても契約は成立します。
媒介契約は口頭でも有効
法的に、媒介契約は当事者の合意で成立するとされています。
たとえば、売主が媒介を依頼する・不動産会社が依頼を引き受けるという合意があった時点で媒介契約が成立し、媒介契約書の有無は関係ありません。
そのため、口頭でも上記のやり取りが交わされれば契約として有効です。
トラブルを避けるために書面(媒介契約書)の交付を受けることが大切
口頭でも有効に成立しますが、口頭のみの契約はトラブルのもとです。
媒介契約書は、不動産会社の仲介業務内容や報酬など、重要な項目を明確にするためにあります。
また、仮にトラブルになっても契約書という書面があることで、根拠が明確になりトラブルの解決を図りやすくなるのです。
そのため、たとえ知り合いの不動産会社であっても、媒介契約書を作成しておくようにしましょう。
ただし、契約書があれば安心というわけではありません。
契約書の内容をしっかり確認しないままサインすると、トラブルになった際に不利になる恐れがあります。
契約書はすみずみまで確認し、納得してから契約するようにしましょう。
▼関連記事:口頭で売却を依頼する場合の注意点
媒介契約書に関するよくある質問
最後に、媒介契約書に関するよくある質問をみていきましょう。
媒介契約書に印紙を貼る必要はある?
媒介契約書は収入印紙が不要です。
収入印紙の貼付が必要なのは、印紙税の対象となる課税文書を作成したときであり、媒介契約書は該当しません。
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約いずれの契約種類であっても不要です。
なお、不動産売買で収入印紙が必要になるのは売買契約書ということもあわせて覚えておきましょう。
媒介契約書の雛形はある?
媒介契約書は、国土交通省の標準約款に基づいて作成されているケースがほとんどです。
ただし、標準約款に基づくかは義務ではないので、不動産会社が加入している保証協会や、フランチャイズ本部が用意したフォーマットで作成されるケースも多く、不動産会社独自で作成している場合もあります。
標準約款に基づいているか否かは、媒介契約書に記載が必要です。
基づいていない場合はその理由まで確認したうえで、より慎重に内容をチェックするようにしましょう。
媒介契約書の交付義務違反のペナルティとは?
媒介契約は口頭で�も成立しますが、不動産会社は媒介契約書を交付しなければいけません。
(指示及び業務の停止)
第六十五条
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
媒介契約書の交付義務に違反した場合、不動産会社は宅地建物取引業法に基づき、行政から営業停止処分を受ける可能性があります。
まとめ
媒介契約書は、売主・買主と不動産会社の権利や義務、報酬、違約金などを明確にし、トラブルを避けるための重要な書類です。
媒介契約書があることでトラブルを防ぎやすいとはいえ、内容をしっかりチェックしていることが前提となります。
媒介契約時には本記事で解説したポイントを押さえながら、納得したうえで契約を進めるようにしましょう。
また、そもそも信頼できる不動産会社を選ぶことも重要になってくるので、できるだけ多く比較し自分にぴったりの不動産会社を選ぶことが大切です