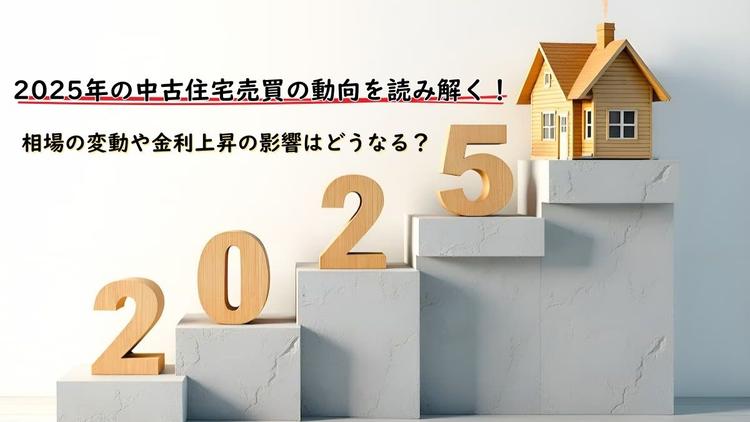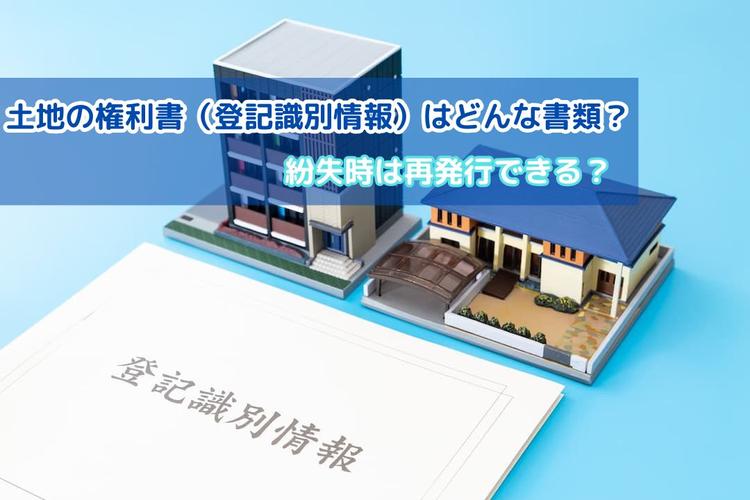建築資材の世界的な需要増や円安の影響もあり、近年は「新築住宅は高すぎて買えない」という人も少なくない状況です。
特に首都圏では新築のマンション価格は短期間で大きく上昇し、それに引っ張られる形で中古マンション・中古戸建てにも需要増が見られます。
物価高や金利上昇の動きも見られる中、2025年の中古住宅売買はどのような状況になるのか、データとともに考察していきましょう。
販売期間の推移
家を売るにあたっては、AI査定等の台頭もあり、一般の方でもある程度の相場観を掴みやすくなりました。
一方で、「売れるまでにどれくらいかかるか」は市場の動向や不動産会社の販売力も影響するため、個人の売主が予測を立てるのは依然として難しい状態です。
マンションと戸建ての売れやすさ(成約案での日数)
中古戸建てと中古マンションの売却に要する期間(登録から成約までの日数)は、概ね3~4か月程度が平均とされており、首都圏の「レインズ登録から成約までの日数」は以下の通りです。
これまではマンションの方が需要者層が広く流動性が高いため、戸建てより成約までの期間が短めとなる傾向がありましたが、新型コロナウイルスの感染拡大と収束を経た現在では、それほど大きな差がない状態になっています。
コロナ禍の影響
2020年は新型コロナウイルス拡大による緊急事態宣言下で市場活動が停滞し、成約までの日数が長期化しました。
しかし2021年には住宅需要が盛り返し、首都圏中古マンションで平均74.7日まで期間が短縮しています。
これはコロナ禍による在宅需要増や新築高騰で中古ニーズが伸び、市場が活発化したためと考えられるでしょう。
アフターコロナの市場
一方、2022年以降は再び売却期間がやや延びる傾向にあります。首都圏中古マンションでは2022年上期に3.11か月、下期に3.22か月と若干長期化しましたが、それでもコロナ前(2019年頃)より短い水準を維持していました。
しかし2023年になると、価格高騰による買い手の様子見や在庫増加もあって売却期間が再び拡大し、首都圏で上期3.75か月、下期4.15か月と4か月超の水準に戻りました。
このように、2020年の停滞→2021年の短縮→2022~2023年の再長期化という推移が見られ、現在は強気な売出価格の物件増加により、売却までに時間がかかるケースも増えつつあります。
販売価格の動向
中古住宅市場の価格はこの数年で大きく上昇トレンドを描いています。首都圏中古マンションの成約価格は2014年から2023年まで一度も下落せず上昇を続け、2014年平均2,727万円から2023年4,575万円へと約1.6倍に高騰しました。
特に2019年以降の上昇幅が大きく、首都圏平均成約価格は2021年→2022年で+10.0%(4,343万円)と急伸し、2024年10月時点でも東京都の中古マンション平均価格は6,081万円と前年比+3.2%で高値を更新しています。
中古戸建ても緩やかですが着実に値上がりし、首都圏平均成約価格は2014年に3,000万円弱だったものが2024年6月には4,016万円と、この10年で約1.4倍に上昇しています。
2020年春先のコロナショックで一時的に中古戸建て価格は下落したものの、その後は在宅勤務の広がりで戸建て需要が高まり、停滞していた価格上昇が再加速する動きも見られました。
▼関連記事:2025年は不動産相場が上昇中?価格の変動要因と現在のトレンドを解説
建築資材高騰の影響
2015年平均を100とした場合、2025年5月の建設資材総合の物価は141.2となっている。
建設物価調査会:建築資材物価指数(2025年5月)
2021年頃からのウッドショック(木材価格急騰)や世界的な資材価格の高騰、2022年以降のウクライナ情勢などによる原材料費・物流費上昇は、新築住宅価格を押し上げただけでなく中古住宅市場にも波及しました。
建築コストの先行き上昇感や歴史的円安を背景に、新築と同様に中古マンション価格も全般的に押し上げられる要因となり、売主が強気の価格設定を行う傾向が強まりました。
結果として2022年頃には中古住宅価格にも資材高騰の影響によるプレミアムが織り込まれ、買主にとって割高感が出始めています。
ただし、2023年後半以降は資材価格高騰も一服し、新築供給の回復や金利上昇観測も相まって、中古マンション価格は2024年に入り停滞気味となっています。
実際、首都圏中古マンションの平均成約価格は、2024年(年間)に都心部を除いて前年比マイナスとなり、約4年ぶりに反落に転じたとのデータもあります1。
住宅ローン控除改正の影響
中古住宅市場において追い風と�なったのが、2022年度の住宅ローン控除(減税)制度改正です。この改正で中古住宅への適用要件だった「築年数要件」が緩和されました。
築年数の制限緩和
従来は木造など非耐火住宅は築20年以内、耐火住宅(マンション等)は築25年以内という築年制限があり、それを超える旧耐震の住宅は耐震適合証明などを取得しないと減税を受けられませんでした。
しかし2022年以降の税制では、1982年1月1日以降に建築された住宅であれば中古でも住宅ローン減税の対象となり、築年数による足切りがなくなっています。
これは新耐震基準(1981年施行)への適合が一つの目安となっており、古い住宅でも新耐震基準に適合していると証明できれば減税を受けられる形です。
築年数要件の緩和により、これまで減税対象外だった築古物件も購入検討しやすくなりました。
適合証明のための手続き負担も軽減され、中古住宅購入希望者にとってハードルが下がったことは市場の追い風だと言えるでしょう。
中古住宅需要への影響
実際、近年は流通する中古住宅の築年数が高まる傾向にあり、LIFULL HOME’Sの調査では築30年以上の中古マンション在庫が2019年は全体の41.9%だったのに対し、2024年には54.5%と過半数を占めるまでになっています。
この背景には新築マンションが軒並み高騰しており、手ごろな中古住宅を選択する人が増えたことがありますが、税制優遇により築古の中古住宅にも買い手が付きやすくなっ��たことも一因と考えられます。
さらに住宅ローン減税は控除率が1%→0.7%に下げられたものの、控除期間は最長13年(中古は基本10年)継続となり、中古住宅でも一定の減税メリットが享受できる制度設計が維持されています。
総じて、2022年改正は中古住宅の取得を後押しし、市場の裾野拡大につながったと言えるでしょう。
地域ごとの傾向
大都市圏では中古住宅市場が活発で、価格上昇の牽引役となってきました。
首都圏
特に東京圏は中古マンション価格の上昇が顕著で、過去10年で平均成約価格が約1.9倍に達しています(東京都は1.9倍、隣接3県は1.5倍程度)2。
東京都心部などでは需要過多によりコロナ禍後も売却期間は短縮傾向が続きました。
ただし価格高騰が続いた結果、2023年以降は買い手の予算オーバーによる売れ残り在庫も増え始め、強気の価格設定をした物件ほど成約まで時間がかかる傾向が見えています。
一都三県のデータでも、2023年は売出から成約まで3か月以内に売れるケースの比率が前年より大きく低下し、販売期間が長期化する事例が増えました。
一方、大阪・名古屋など他の都市部でも中古住宅価格は上昇基調でしたが、その伸び率は東京ほどではなく比較的緩やかです。
近畿圏・中部圏
��とはいえ近畿圏・中部圏でもコロナ後に中古需要が高まり、成約件数は増加傾向を示しました。
例えば近畿圏中古戸建ての平均成約価格もこの10年で約1.2倍に上昇し、中部圏でも同程度の伸びを示しています。
都市部全体として、新築価格の高止まりを背景に中古物件への関心が高く、高立地・良質な中古は短期間で売却できるケースが多い状況です。
地方都市・郊外の動向
地方都市や首都圏郊外では、市場の動きに地域差がみられます。郊外エリアではコロナ禍を機に広い住居を求める動きが強まり、中古戸建ての需要が増えました。
在宅勤務の定着で「都心のマンション」から「郊外の一戸建て」への住み替えを選ぶ人も出てきたため、都心から離れたエリアでも戸建てが売れやすくなる傾向がありました。
例えば首都圏近郊の茨城・千葉などでは、都内通勤圏でありながら割安な中古戸建てに注目が集まり、成約件数が増加したとの見方もあります3。
一方で地方都市の中でも、福岡市や札幌市など人口流入や再開発が活発な都市では中古マンション市場が堅調で、成約までの期間が大都市圏と同等に短いケースも見られます。
福岡県ではマンション平均売却期間が約3.3か月と、東京など他の大都市圏より短いとのデータもあり、アジア圏からの投資需要�や地元需要に加えて、九州内外からの転入者増加が影響しています。
これに対し、人口減少が進む地方郊外では中古住宅の買い手探しに時間がかかるケースが多く、売却まで半年以上要する物件も少なくありません(不便な立地や築古の戸建てなど)。
このように、都市圏 vs. 地方・郊外で中古住宅の流通速度や価格動向には差異があり、地域の経済状況や人口動態、利便性などが売れ行きを左右する要因となっています。
2025年の中古住宅売買の展望
2023年以降は、在庫増加や金利上昇観測から、やや売れにくい局面にシフトしつつあります。
中古マンションは強気な価格設定の物件ほど売却期間が延びる傾向が顕著化し、戸建ても高額物件や郊外物件を中心に成約まで時間がかかるケースが増えました。
もっとも、総じて中古住宅の流通市場規模自体は拡大しており、売却件数はコロナ禍前より増加傾向にあります。
そのため適切な価格設定や魅力付けを行えば、マンション・戸建てともに中古住宅は以前より売却チャンスが高まっていると言えるでしょう。
金利上昇の影響
2025年の中古住宅市場は、金利動向と価格調整がカギとなります。
日本銀行の金融政策転換(マイナス金利解除・金利上昇の方針)により、中長期的には住宅ローン金利が上昇し購買力に影響を与える可能性があります。
金利上昇局面では、買い手の慎重姿勢から売却期間の長期化や価格交渉の増加が予想されます。
▼関連記事:住宅ローン金利の上昇で不動産売却が難しくなる?
住宅ローン控除はどうなる?
住宅ローン減税の拡充策は2025年入居分まで継続予定です。
仮に廃止されれば、消費税増税前のように一時的な需要増が起こる可能性はあるものの、その後の住宅需要には大きなマイナス影響が予想されます。
そのため、今後も一定の水準で制度が継続されると考えられます。
直近2022年の税制改正において、高性能住宅が借入限度額・適用期間の延長(業者販売の新築・買取再販住宅の場合)という形で優遇を受けています。
また、2025年4月の改正建築基準法施行により、省エネ基準への適合が厳格化されます。
こうした動向を踏まえると、ローン控除額やリフォーム時の適用範囲にも住宅性能に関する一定の基準が設けられるのは確実だと言えるでしょう。
築22年の耐用年数を超える中古戸建ての売買
これまでは、税制上の法定耐用年数が住宅の減価償却を示す1つの指標として、不動産売買価格の参考にされてきました。
「築20年を超えると木造住宅の価値はほとんどなくなる」というのが業界の共通認識としてありました。
しかし、ローン控除の築年数条件の緩和によって、金融機関も新耐震基準であれば、これまでよりも柔軟に融資判断・担保価値の算出を行うようになっています。
また、一定の基準を満たす住宅はローン控除の適用額にも影響するため、2009年ごろから普及した長期優良住宅などの高性能住宅は、基準適合を証明することで売れやすさや価格面で有利になるでしょう。
住み替え等で売却を検討されている方は、こうした相場や業界の変化も踏まえて、自分にとって良い選択を探してみてはいかがでしょうか。