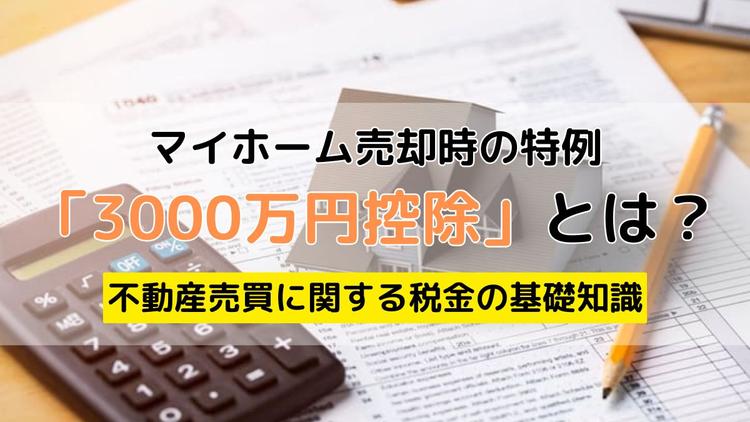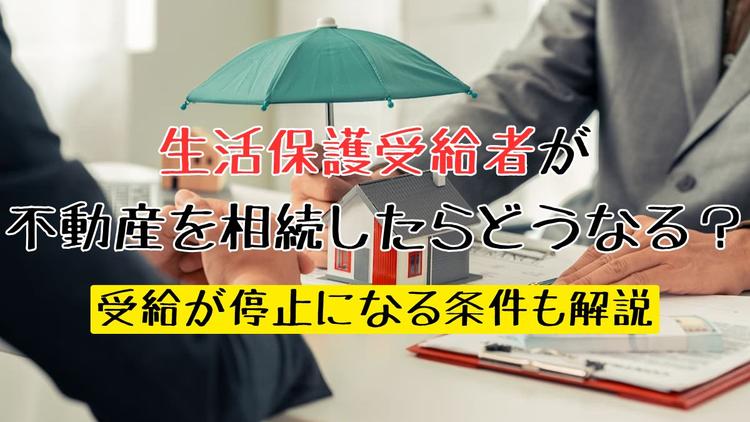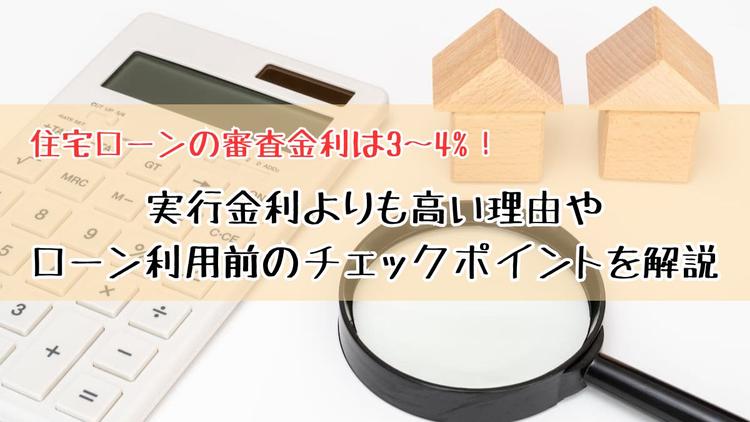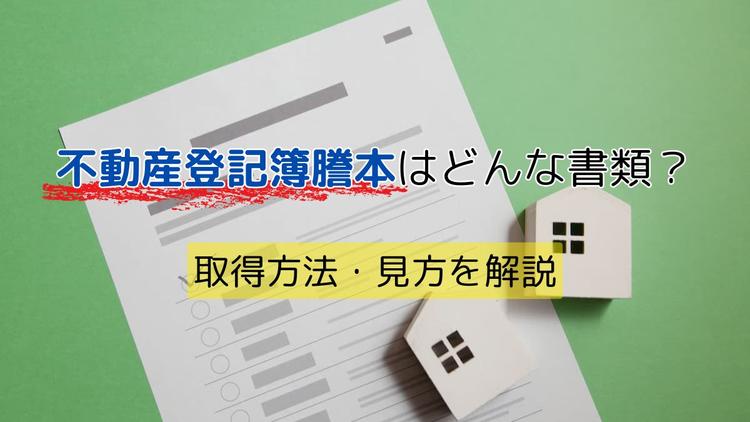「年金受給中に不動産を売却したら年金が減るのでは?」
家を売却して老人ホームや子どもとの同居を検討している方にとって、売却で年金が減額されると大きな問題となります。
しかし原則として、不動産を売却しても年金の受給額が減らされたり支給停止になったりといったことはありません。
ただし、年金の受給額には影響なくても税金が課税される点には注意が必要です。
この記事では、年金受給中の不動産売却と年金の関係や注意点、売却時に課せられる税金について詳しく解説します。
不動産を売却して利益が出ても原則として年金支給の停止や減額はない
結論を言えば、原則として年金受給中に不動産を売却しても、年金が減額されたり支給停止されたりすることはありません。
年金は、「厚生年金」「国民年金」ともに現役時代中の納付額によって支給額が決まるものです。
前年の所得額で支給額や受給資格が変動するものではないため、不動産の売却が年金に影響を与えることはありません。
なお、支給額に影響するのではと考える人が多い理由に「在職老齢年金」という制度が挙げられます。
在職老齢年金とは、60歳以上で老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金に加入して働く人に対し、賃金と年金額に応じた一部または全額の年金が支給停止される制度です。
しかし、在職老齢年金で賃金の対象となるのは会社から支給される給与や賞与であり、不動産売却時の譲渡所得は対象となりません。
そのため、働きながら年金を受給する人であっても不動産売却を理由に年金が減額されることはないのです。
ただし、障害年金と後期高齢者の国民保険料は不動産売却が左右される恐れがあるので、気を付けましょう。
以下、老齢厚生年金と老齢基礎年金の概要を確認した上で、年金受給者が不動産を売却した際の注意点を説明していきます。
対象者
- 老齢厚生年金:厚生年金に加入していた人(会社員・公務員など)
- 老齢基礎年金:国民年金に加入していた全ての人
受給額の計算基準
- 老齢厚生年金:現役時代の給与・賞与に基づく
- 老齢基礎年金:納付期間に基づく(収入額は無関係)
加入期間
- 老齢厚生年金:厚生年金加��入期間のみ
- 老齢基礎年金:国民年金加入期間全般
不動産売却による譲渡所得と年金の関係についてのまとめ
「在職老齢年金」は賃金と年金額のバランスで支給停止や減額が行われる制度ですが、対象となるのは給与や賞与のみで、不動産売却で利益が出ても影響はありません。
そのため、年金受給中に不動産を売却しても原則として支給額が減額される心配はありません。
ただし、障害年金や後期高齢者の国民保険料に影響が出る可能性がある点には注意が必要です。
年金受給者が不動産を売却するときの注意点
年金受給者が不動産を売却する際には、以下の3つに注意が必要です1。
- 障害年金は一定条件を満たすと支給停止や減額の可能性がある
- 75歳以上の後期高齢者は国民健康保険料が高くなる
- 年金受給者でも不動産を売却した利益には所得税や住民税がかかる
それぞれ見ていきましょう。
障害年金は一定条件を満たすと支給停止や減額の可能性がある
障害年金とは、病気やケガで仕事や生活に制限が出る場合に受け取れる年金です。
一定の要件を満たすことで高齢者だけでなく現役世代でも受け取ることができます。
障害年金は20歳前であっても受け取ることができますが、20歳前は受給者本人が保険料を納めていないことから以下のような所得税制限が設けられているのです。
- 前年の所得額が472.1万円を超える場合:全額支給停止
- 前年の所得額が370.4万円を超える場合:2分の1の支給停止
初診日が20歳前の傷病により障害年金を受給する際には、毎年前年度の所得確認が必要です。
その際、上記に該当する場合は、10月分から翌年9月分までの支給分に影響します。
ただし、20歳前でも初診日時点で年金に加入していた場合は所得制限が適用されませ��ん。
また、所得制限を超えた場合でもその後所得が制限未満に戻れば障害年金の支給は再開されます。
75歳以上の後期高齢者は国民健康保険料が高くなる
75歳以上は、それまで加入している医療保険や会社勤めかに関わらず、自動的に後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度の保険料は、前年の所得額に応じて算出されます。
この所得には不動産売却の所得も含まれるため、売却で利益が出た翌年は保険料が高くなる可能性があるのです。
後期高齢者医療制度の保険料の支払い方は、年金からの天引きか納付書による納付(普通徴収)の2種類があります。
年金からの天引きの場合、年金支給額は変わらなくても差し引かれる保険料が増えることで、年金額が減ったように感じてしまう点には注意しましょう。
年金受給者でも不動産を売却して得た利益には所得税や住民税がかかる
不動産売却は年金には影響が出なくても、税金が発生する点に注意が必要です。
不動産売却の利益は譲渡所得と呼ばれ、所得税・住民税の対象となります。
高額な不動産売買ではかかる税金も高額になりやすく、100万円を超えるケースも珍しくありません。
また、年金受給者を理由として免除されることもないため、あらかじめ税額を把握して売却することが大切です。
以下では、譲渡所得にかかる所得税・住民税の計算方法を解説するので参考にしてください。
年金受給者が不動産を売却したときの譲渡所得の計算方法
年金受給者であっても、不動産売却時の譲渡所得の計算は通常の方法と同じです。
譲渡所得にかかる税金は、以下の2ステップで算出できます。
- 課税譲渡所得の計算
- 課税譲渡所得に税率を乗じる
それぞれ見ていきましょう。
課税譲渡所得の計算式
課税譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
取得費とは、売却した不動産を購入した際にかかった費用です。
不動産の価格だけでなく仲介手数料や印紙税なども含めることができます。
一方、譲渡費用は売却時にかかった仲介手数料や解体費用などが該当します。
売却額からこれらの費用を差し引いた部分が譲渡所得(利益)です。
なお、取得時に価格が分からない・書類がなくて証明できないといった場合は「売却額×5%」の概算で取得費を計上します。
しかし、本来の取得費よりも計上できる額が少ないため、利益が出やすく税額が高くなる点に注意しましょう。
取得費や譲渡費用の証明には、売買契約書や領収書などの書類が必要です。
税額を抑えるためには、思い当たる場所を探してできるだけ費用を計上できるようにしましょう。
また、譲渡所得からは特別控除などの特例適用分を差し引くことが可能です。
特例まで差し引いてプラスが出た場合は、プラス部分が所得税・住民税の対象となります。
反対に、計算結果がマイナスであれば課税されません。
売却時の手取り額や譲渡所得の計算はこちら譲渡所得の税率
課税譲渡所得がプラスの場合、税率を乗じることで税額を算出できます。
税率は不動産の所有期間に応じて、以下の2種類に分かれます。
| 所有期間 | 所得税・復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 | |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
たとえば、以下の条件で計算してみましょう。
- 売却額:3,000万円
- 取得費:2,000万円
- 譲渡費用:100万円
- 所有期間:10年
課税譲渡所得は「3,000万円-(2,000万円+100万円)=900万円」です。
所有期間10年は長期譲渡所得に区分されるため、税額は900万円×20.315%=約183万円となります。
なお、実際に課税譲渡所得を計算する際には取得費から減価償却を差し引く必要があったり、経費計上できるか分からなかったりと複雑になる恐れがあります。
計算に不安がある人は、税理士や不動産会社に相談するとよいでしょう。
不動産売却時に利用できる3,000万円特別控除などの特例
不動産売却では節税につながる特例がいくつか設けられています。
マイホームの売却で利用できる代表的な特例に以下の2つがあります。
- 3,000万円特別控除
- 10年超所有軽減税率の特例
3,000万円特別控除では、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるため、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金が発生しません。
また、所有期間が10年を超える場合は、税率を20.315%から14.21%に軽減できる特例が10年超所有軽減税率の特例です。
両方の特例は併用できるので、要件を満たせば大きな節税効果が見込めるでしょう。
ただし、特例ごとに細かく適用要件が定められています。
特例を検討する場合は、事前に要件をチェックして検討するようにしましょう。
年金受給者が不動産を売却したときの確定申告の書き方や手続きの流れ
不動産を売却して税金がかかる場合、確定申告して納税が必要です。
年金受給者であっても確定申告が必要なので、手続きの流れを押さえておきましょう。
大まかな流れは以下の通りです。
- 必要書類を準備する
- 確定申告書を作成する
- 期限までに確定申告する
それぞれ解説します。
必要書類を準備する
確定申告では以下のような書類が必要です。
- 確定申告書
- 譲渡所得の内訳書
- 本人確認書類
- 登記事項証明書
- 取得費用を証明できる書類の写し(売買契約書や領収書)
- 譲渡費用が証明できる書類の写し(売買契約書や領収書)
また、特例を適用する場合は特例ごとの必要書類があります。
必要書類は状況次第で異なる場合もあるので、事前に税務署のホームページなどで確認するとよいでしょう。
確定申告書を作成する
必要書類を揃えたら確定申告書を作成します。
国税庁のホームページに記入例があるので参考にするとよいでしょう2。
また、ホームページを利用してオンラインで申告書を作成することも可能です。
記入ミスがあると申告のし直しが必要になるため、慎重に作成するようにしましょう。
期限までに確定申告する
確定申告時�期は、売却した年の翌年2月16日~3月15日(曜日によって前後する場合あり)です。
確定申告時期を過ぎてしまうと無申告加算税などのペナルティの恐れもあるので、期限内に申告できるように準備を進めましょう。
譲渡所得の確定申告は、計算や特例の適用などで複雑になりがちです。
専門的な知識も必要になるので、税理士や自治体の相談コーナー・不動産会社などに相談しながら確定申告することをおすすめします。
不動産を売却したときの年金に関するよくある質問
最後に、不動産を売却したときの年金に関するよくある質問をみてきましょう。
土地を売却して年金が停止されることはある?
原則として、土地を含め不動産の売却で年金が停止されることはありません。
ただし、20歳前に初診日がある障害年金は、一定の所得で支給停止になる恐れがあるので注意が必要です。
また、後期高齢者医療制度の保険料が上がることで、年金から差し引かれる額が大きくなり、手元に入る年金額が減少する点にも気を付けましょう。
不動産を売却したら遺族年金に影響はある?
不動産売却による譲渡所得が出ても、遺族年金の支給に影響はありません。
遺族年金の支給額は亡くなった方の支払っていた保険料や遺族の年齢などで決まります。
高齢者の確定申告を家族が代理できる?
確定申告の代理は税理士しかできないため、家族であっても代わりに申告することはできません。
ただし、代書や代理提出などの税理士の代理業務にあたらない部分についてはできる場合があります。
とはいえ、資格のない家族が代理提出をすると税務署に誤解される恐れがあるうえ、確定申告は間違えるとトラブルになりやすいため、専門家に依頼することをおすすめします。
まとめ
不動産の売却は年金の受給に影響はありません。
しかし、一部の障害年金と後期高齢者医療保険料には影響��が出るので注意しましょう。
また、年金には影響がなくても譲渡所得には所得税・住民税が課税されるので、納税について理解しておくことが大切です。
不動産会社によっては税理面もサポートしてくれるので、不安がある方は相談してみるとよいでしょう。