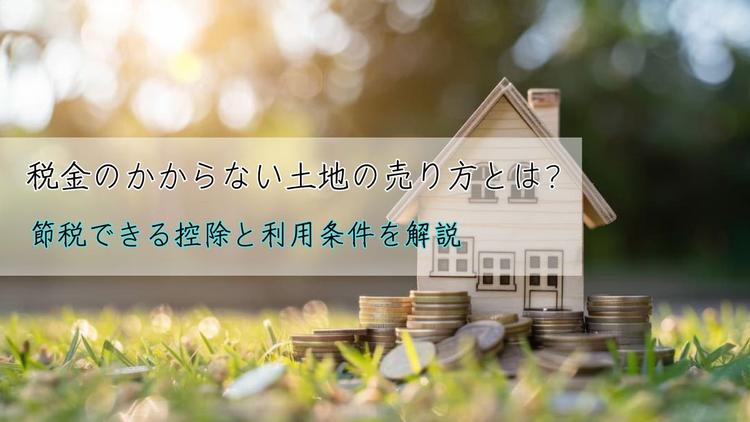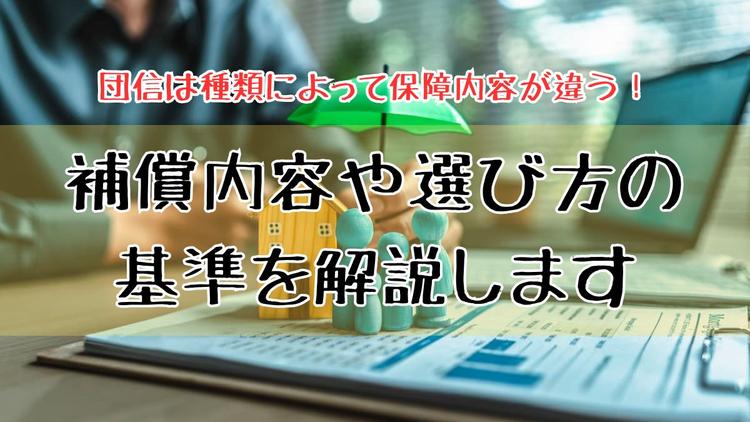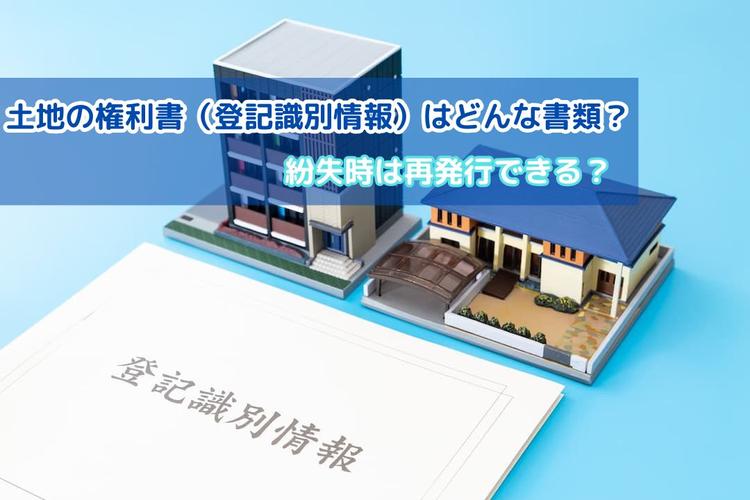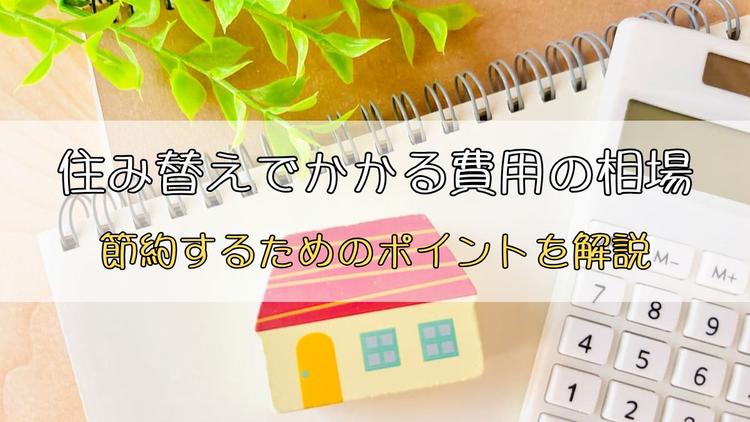「税金のかからない土地の売り方ってあるだろうか?」
土地を売却すると税金がかかります。
せっかく土地を売却できたのに高額な税金がかかって手元に残るお金が少なくなる、というのは避けたいところです。
土地売却にかかる税金にはいくつか種類があり、税金の種類によっては節税につなげることも可能です。
この記事では、土地売却にかかる税金や税金の種類ごとの節税方法について詳しく解説します。
土地売却にかかる税金
土地を売却すると以下の4つの税金が課税されます。
- 印紙税
- 登録免許税
- 消費税
- 譲渡所得税
印紙税と消費税は基本的に必ずかかりますが、登録免許税と譲渡所得税はケースによってかかる税金です。
以下で、それぞれの税金の概要を押さえていきましょう。
印紙税
印紙税とは、契約書や領収書といった一定の書類を作成する際にかかる税金です。
土地売却においては、売買契約書が課税の対象となります。
登録免許税
登録免許税とは、不動産登記の新設や変更の際にかかる税金です。
土地を売却すると所有者が売主から買主に変更になるため、所有者を変更する登記を行います。
また、土地に抵当権が設定されている場合は売却時に抵当権抹消の登記が必要です。
登録免許税はこれらの登記手続きの際に法務局に支払います。
消費税
商品やサービスの提供にかかる税金である消費税は、土地売却でも課税されます。
ただし、土地は消費税の対象外のため土地売却自体に消費税は発生しません。
一方で、不動産会社への仲介手数料や司法書士報酬など土地売却の過程で利用するサービスに対して消費税が発生します。
譲渡所得税
譲渡所得税とは、土地売却の利益に対して課税される所得税・住民税のことで、2037年までは復興特別所得税も加わります。
土地の購入価格よりも高値で売却して利益が発生した場合、その利益が課税対象になります。
なお、売却で利益が出ない場合(損失)は、譲渡所得税は課税されません。
以下では、それぞれの税金の詳しい内容と税金がかからない売り方について詳しく解説していきます。
印紙税のかからない土地の売り方
まずは、印紙税の税額と、印紙税のかからない土地の売り方をみていきましょう。
土地の売買契約書に印紙税がかかる
土地の売買契約書は課税文章と呼ばれ、印紙税の対象です。
そのため売買契約書作成時には、収入印紙を契約書に貼付・消印して納税します。
印紙税は法律で定められた手続きであり、納税忘れには過怠税というペナルティが発生するので注意しましょう。
印紙税の税額は1~2万円程度が一般的
印紙税の額は、契約書に記載された金額(売買価格)に応じて異なります。
主な土地取引の価格帯での税額は以下のとおりです。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減後の税率(2027年3月31日まで) |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
たとえば、売却額が2,000万円なら2万円が課�税されます。
また、2027年3月31日までに作成した契約書であれば軽減が適用されるため、売却額2,000万円の場合は本来の2万円から1万円に減額となるのです。
売買契約書は基本的に2通作成し、売主と買主がそれぞれ保管します。
印紙税は、売主と買主がそれぞれ負担するのが一般的です。
印紙税をかけずに土地を売る方法
印紙税をかけずに土地を売る方法としては、以下の2つが挙げられます。
- 写しのみ保管する
- 電子契約にする
写しのみ保管する
印紙税は契約書であっても、原本の写し(コピー)であれば課税されません。
買主が原本を保管し売主がコピーを保管するケースでは、印紙税の負担は基本的に買主のみとなります。
ただし、どちらかが保管する分を写しにする場合は、契約書にその旨を記載する必要があります。
また、写しであっても署名・押印した場合は印紙税が必要なので注意しましょう。
契約書の写しであっても契約の効力は原本と変わりません。
しかし、万が一トラブルになった場合、原本の方が証拠力が高くなる点には注意が必要です。
さらに、買主のみが印紙税を負担することでトラブルになる可能性もあるので、事前にどちらが印紙税を負担するかは話し合っておくようにしましょう。
電子契約にする
電子契約とは、紙ではなく電子データで締結する契約です。
印紙税は紙の契約書が対象となるため、契約書であっても電子データでは課税されません。
また、電子データで交わした契約書を紙に印刷した場合も、写しとみなされるので収入印紙は不要です。
ただし、電子データを印刷して紙を契約書として利用し、署名・押印する場合は印紙税の対象となります。
電子契約に対応しているかは不動産会社によって異なるので、確認してみるとよいでしょう。
登録免許税のかからない土地の売り方
土地や建物などの不動産は、登記簿に不動産情報や所有者などが記録されています。
登記簿上の所有者であることで、所有者としての権利を第三者に公的に証明できるのです。
そのため、土地を売却すると登記簿の変更の手続き(不動産登記)が必要となり、その際の手数料としての登録免許税が課税されます。
所有権移転登記や抵当権抹消登記で登録免許税がかかる
不動産登記は登記の目的に応じて種類や登録免許税の税額が異なります。
土地売却で必要になる登記は以下の2つです。
- 所有権移転登記:所有権を売主から買主に変更する登記
- 抵当権抹消登記:抵当権を抹消する登記
それぞれ詳しくみていきましょう。
所有権移転登記は一般的に買主が負担する
所有権移転登記は所有権を移転する理由、不動産の種類によって税額が異なり、土地の売却では「固定資産税評価額×2%」が原則課税されます。
ただし、所有権移転登記は買主が負担するのが一般的であり、売主の税負担はありません。
とはいえ、どちらが負担するかは合意によって決められるので、事前に確認するようにしましょう
抵当権が残っている場合には登録免許税は負担する必要がある
抵当権とは、住宅ローンなどを利用して土地を購入した場合に金融機関が土地に設定する権利です。
抵当権が設定されている土地は、ローンの返済が滞った場合強制的に売却され、ローン残債の回収を計られる恐れがあります。
抵当権が設定されている土地は基本的に売却できません。
住宅ローン残債がある場合は、ローンを完済して抵当権の抹消が必要になります。
また、すでに住宅ローンを完済していても、抵当権抹消登記を放置していたケースででは、売却前に抵当権抹消登記が必要になります。
抵当権抹消登記の登録免許税は、「不動産の筆数×1,000円」です。
たとえば、土地1筆のみ抹消なら1,000円ですが、土地と建物セットの場合は2,000円かかります。
抵当権抹消登記は抵当権が抹消されていないケースでのみ必要です。
もともと抵当権が設定されていなかったり、すでに抵当権が抹消済というケースでは、抵当権抹消登記に登録免許税は発生しません。
消費税のかからない土地の売り方
消費税とは、商品やサービスの取引の際に発生する税金です。
2024年現在では、10%(軽減税率8%)が課税され、土地取引でも消費税が発生するケースがあります。
土地は非課税
そもそも消費税は消費されるものに対して課税される税金です。
一方、土地は消費されるものではないため、消費税の対象外となります。
これは土地を取引する当事者が個人・法人に関わらず、いずれであっても消費税が非課税となります。
また、土地の定着物(庭木や石垣)なども非課税の対象となるので、定着物まで一体で土地を売却するケースでも消費税��はかかりません。
ただし、土地・建物をセットで売却するケースでは、建物は消費税の対象です。
しかし、個人や免税業者が住宅を売却する場合は消費税はかからないため、個人が土地込みでマイホームを売却するケースでは消費税を気にする必要はないでしょう。
仲介手数料や司法書士報酬に消費税がかかる
土地売却自体に消費税は課税されませんが、売却の過程で利用するサービスなどについては消費税の対象です。
主な消費税が発生する項目には以下のようなものが挙げられます。
- 不動産会社に支払う仲介手数料
- 不動産登記を司法書士に依頼した場合の司法書士報酬
- 建物を解体する場合の解体業者への支払い
- 測量や造成工事を行った場合の業者への支払い など
司法書士報酬や解体費用、その他費用は売却の状況によっては発生しない場合もあります。
仲介手数料は課税事業者である不動産会社から売買主にそれぞれ請求されるもので、消費税がかかります。
買取であれば仲介手数料は発生しませんが、仲介よりも売却額が下がるので消費税を抑えるために検討するのは賢明とは言えません。
消費税を抑えるために必要なサービスを削ると、売却額に影響が出る恐れがあります。
消費税を抑えることに固執せず高値で売却することを優先したほうが、手元に残るお金は大きくなるでしょう。
譲渡所得税のかからない土地の売り方
土地売却にかかる税金の中でも、高額になりがちなのが譲渡所得税です。
課税されると100万円を超えるケースも珍しくないので、譲渡所得税を抑えること�でトータルの税負担の大きな軽減が見込めます。
土地を売却した利益には譲渡所得税が課される
譲渡所得税は、不動産を売却した際の利益にかかる所得税・住民税・復興特別所得税です。
利益が出れば課税されますが、売却で損失となる場合には課税されません。
売却時の利益が高額になると納税額も高額になるため、あらかじめ利益や課税額を自分でも計算できるようにしておくことが大切です。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は、以下の2つのステップで計算します。
- 【ステップ1】課税対象譲渡所得の計算:売却額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
- 【ステップ2】譲渡所得税の計算:課税対象譲渡所得×譲渡所得税の税率
まずは、課税対象となる譲渡所得を計算します。
譲渡所得は、売却額から土地の購入にかかった費用(土地代や仲介手数料など)と売却時にかかった費用を差し引いた額です。
また、譲渡所得からはさらに特別控除を差し引くことができ、控除後のプラス部分が課税譲渡所得になります。
課税譲渡所得が発生した場合、課税対象額に譲渡所得税の税率を乗じて税額を算出します。
譲渡所得税の税率は以下のとおりです。
| 所有期間 | 所得税 復興特別所得税 | 住民税 | 合計税率 | |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
所有期間5年を境に短期譲渡所得と長期譲渡所得の2種類に区分され、税率も異なります。
たとえば、以下のケースで計算してみましょう。
- 売却額:1,500万円
- 取得費:1,200万円(土地代+諸経費)
- 譲渡費用:50万円
- 所有期間:10年
上記の場合の課税譲渡所得は「1,500万円-(1,200万円+50万円)=250万円」です。
所有期間10年は長期譲渡所得に区分されるため、税額は「250万円×20.315%=約51万円」となります。
譲渡所得税をかけずに土地を売る方法
譲渡所得税をかけずに土地を売る方法としては、以下の2つがあります。
- 課税譲渡所得がマイナスであれば譲渡所得税はかからない
- 特別控除の適用で譲渡所得税がかからないケースがある
課税譲渡所得がマイナスであれば譲渡所得税はかからない
譲渡所得税は譲渡所得が発生した場合のみ課税されるため、取得費と譲渡費用が売却額を上回れば発生しません。
そのため、取得費と譲渡費用をいかに正確に計上できるかによっても税額が異なってきます。
取得費と譲渡費用を計上するには、売買契約書や領収書などの書類が必要です。
譲渡費用は売却時に発生するため、領収書などを保管している人は比較的多いですが、古くから所有する土地などでは取得費が証明できないケースも少なくありません。
取得費が証明できない場合、概算取得費として「売却額×5%」を計��上します。
しかし、概算取得費は本来の取得費よりも少額になりやすく利益が大きく出てしまうので、事前に領収書などを探しておくようにしましょう。
なお、譲渡所得がマイナスの場合は税金が発生しないため確定申告は不要です。
ただし、損失が出た際は損失額を所得から控除できる特例があり、利用することで節税が可能です。
基本的には不動産を売却したら確定申告すると考えておくとよいでしょう。
特別控除の適用で譲渡所得税がかからないケースがある
譲渡所得の計算でもお伝えしたように、譲渡所得からは特別控除が差し引けます。
たとえば、代表的な控除である3,000万円特別控除なら譲渡所得から最大3,000万円を控除できるので、大きな節税が期待できるのです。
他にも譲渡所得にはいくつか特例が用意されていますが、それぞれ適用要件などが異なるので注意しましょう。
特例については、次の章で詳しく解説します。
譲渡所得税を節税できる特別控除の内容と利用条件
土地の売却で適用を検討できる主な特別控除は以下の3つです。
- 3,000万円特別控除
- 10年超所有の軽減税率
- 居住用財産の買換え特例
3000万円特別控除
マイホームの売却であれば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
譲渡所得が3,000万円未満であれば、適用することで税金は発生しません。
また、マイホームを解体した更地であっても一定の要件を満たすことで適用可能です。
主な適用要件には、以下のようなものがあります。
- 自分が住んでいる家屋の売却
- 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却
- 家屋を解体する場合は解体後1年以内に譲渡契約が締結され、かつ住まなくなった日から3年以内の売却
- 更地にしてから駐車場などに利用していない
- 他の特例を適用していない
- 売主・買主が親子や夫婦など特別な関係でない
なお、相続した建物を解体して更地にして売却した場合は「相続空き家の3,000万円特別控除」が検討できます
それぞれの詳しい適用要件は、国税庁のホームページを確認するようにしましょう1。
10年超所有の軽減税率
所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合の、譲渡所得税の税率を引き下げる特例です。
この特例では、譲渡所得6,000万円以下の部分の譲渡所得税が20.315%から14.21%に引き下げられます。
また、この特例は3,000万円特別控除と併用可能なので、両方の条件を満たすことでより大きな節税が見込めるでしょう。
主な適用要件は以下のとおりです2。
- 売った年の1月1日時点で家屋・敷地の所有期間が10年を超えるマイホーム
- 家屋を取り壊す場合は取り壊した日の属する年の1月1日時点で所有期間が10年を超える
- 取壊しの日から1年以内に売買契約が締結され、かつ住まなくなった日から3年以内の売却
- 売主・買主が親子や夫婦など特別な関係でない
居住用財産の買換え特例
住み替えに伴う売却であれば、譲渡所得税を将来に繰り延べできる特例です。
たとえば、今の家を売却して出た利益は今年課税されず、将来購入した新居を売却する時まで繰延されます。
将来的に新居を売却しないなら、大きな節税が見込めるでしょう。
主な適用要件は以下のとおりです3。
- 売った人の居住期間が10年以上かつ売った年の1月1日の所有期間が10年を超える
- 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却
- 家屋を解体する場合は解体後1年以内に譲渡契約が締結され、かつ住まなくなった日から3年以内の売却
- 売却代金が1億円以下
この特例は免税では��なく繰延なので、将来新居を売却するとより高額な税負担になる恐れがあります。
適用する場合は、将来的な売却計画まで視野に入れて検討することが大切です。
また、3,000万円特別控除との併用ができないため、どちらを適用したほうがお得になるかはしっかりとシミュレーションするようにしましょう。
まとめ
土地の売却では「印紙税」「登録免許税」「消費税」「譲渡所得税」の4つの税金がケースによってかかります。
とくに譲渡所得税は課税されると高額になるので、計算方法や適用できる特例を押さえて上手に節税することが大切です。
土地売却で、手元により多くのお金を残したいなら、節税だけでなく高く売ることも重要です。
できるだけ多くの不動産会社を比較し、信頼できる不動産会社を選ぶようにしましょう。