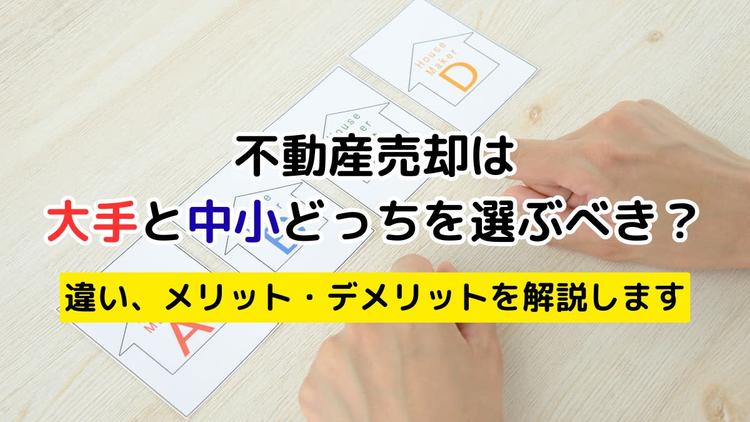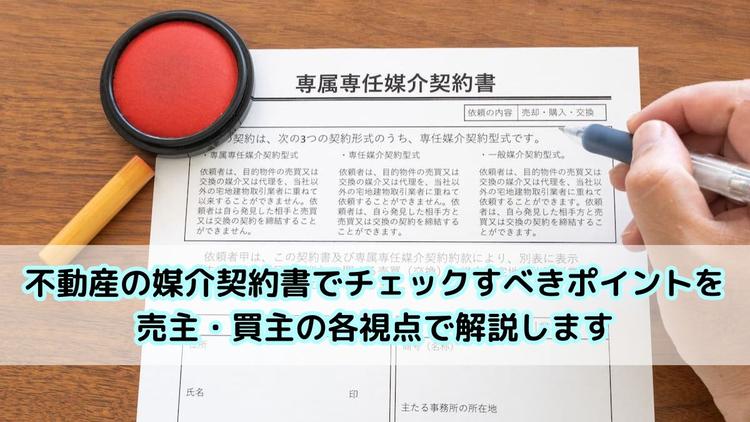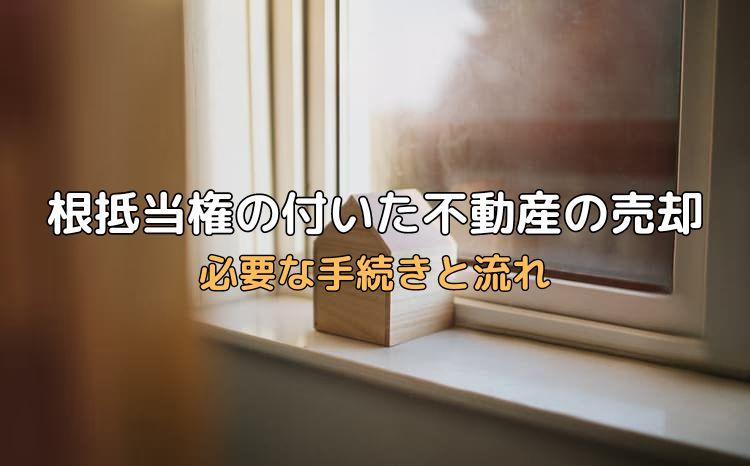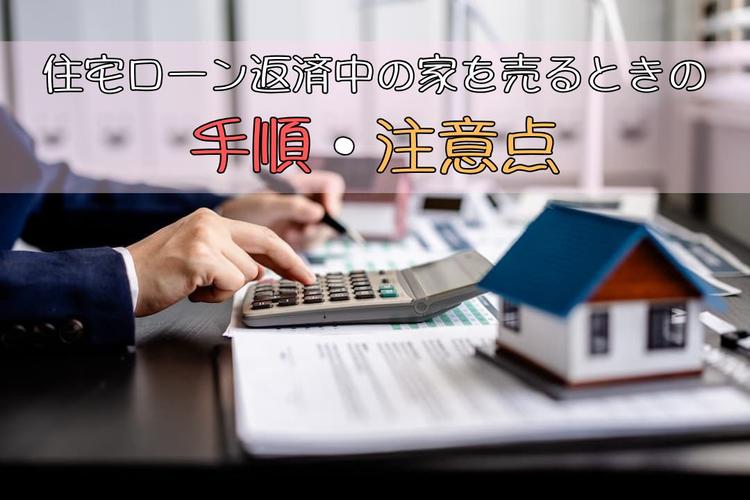不動産取引で家を高く売りたいと考えるのは自然なことですが、単に「高値で売り出して様子を見る」戦略は、ゲーム理論の視点から見ると効果が薄い場合があります。
本記事では、ゲーム理論を応用して売主、買主、仲介業者それぞれの思惑を整理し、家をより高く売るための最適な戦略を探ります。
さらに、両手取引や囲い込みといった仲介業者の戦略、マンションと戸建ての市場特性の違い、そして相場分析の重要性も踏まえ、家の売却を成功させるための戦略を考察します。
不動産売買におけるゲーム理論とは?
ゲーム理論は、プレイヤーが他者の行動を予測しながら自らの利益を最大化するために最適な戦略を選択する状況を分析する学問です。
「家を売ること」も一種の「ゲーム」と言えます。
ここでは、売主、買主、仲介業者それぞれの戦略を考察し、それが売却プロセスにどのように影響するかを分析します。
プレイヤー(売主、買主、仲介業者)の思惑とリスク
①売主の思惑
売主の目標は、物件をできるだけ高く売却することです。
「家の売却」での利益最大化戦略
売主は高めの価格で売り出し、交渉を通じて利益を引き上げることを狙いますが、相場を超えた価格設定をすると買主の関心を得られず、売却が長引くリスクがあります。
リスク
東京カンテイの資料によると、首都圏のマンション市場では、売り出し価格から5~6%程度の値下げを実施する物件が多いことが判明しています1。
たとえば、5,000万円で売り出された物件が、4,750万円程度まで値下げされることは頻繁に起こっているので��す。
この間に反響がまったく無いのであれば、「高く売り出す期間は時間の無駄」とも言えるでしょう。
さらに、売り出し価格は成約価格ではないため、売り出し価格を値下げした後、実際に取引が成立する価格はさらに下がる傾向があります。
過大な価格設定は、仲介業者が広告に積極的でなくなり、売却がさらに遅れるリスクもあります。
②買主の思惑
買主の目標は、できるだけ安く理想の物件を購入することです。
「家の購入」での利益最大化戦略
買主は市場の動向を注視し、適正価格で物件を購入できるタイミングを狙います。
市場が下落していると判断すれば、待つことも戦略の一つです。
リスク
値下がりを期待して待っている間に、他の買主に物件を取られるリスクや、金利の上昇により資金計画が狂うリスクがあります。
③仲介業者の思惑
仲介業者の目標は、物件の早期売却による手数料の獲得です。
「売買主の仲介」での利益最大化戦略
仲介業者は早期の売却を目指し、売主に適正な価格を提案します。
しかし、売主視点では両手取引(自社が売主と買主双方から手数料を得る取引)を狙い、他社の買主を排除する「囲い込み」のリスクも存在します。
リスク
売主が高値を設定しすぎると、売却が長引き、手数料が得られるまでの期間が延びるリスクが高まります。
両手取引を狙っている場合は、売主が一般媒介契約を選択して複数の業者に依頼することで、自社が手数料を得られないリスクが生じます。
両手取引と囲い込みのリスク
不動産取引では、「仲介��業者が売主と買主の双方から手数料を得る両手取引」で成約するケースも少なくありません。
しかし、これが売主にとって不利に働く場合もあります。
特に、仲介業者が囲い込みを行うことで売却が遅れ、売主が損をするケースがあります。
両手取引
両手取引では、仲介業者が自社で買主を見つけることで、売主と買主双方から手数料を得られます。
このため、他社の買主を紹介しないようにする囲い込みが行われるリスクもあるのです。
囲い込み
囲い込みを行うことで、他の仲介業者が持つ買主との取引が妨げられ、売主は最良の買主に物件を売却できない可能性があります。
これにより、売却が遅れたり、最終的に値下げを余儀なくされたりするリスクも生まれてしまうのです。
囲い込みを防止するためには、売主が仲介業者に対してしっかりと活動報告を求め、どの程度の反響があるのかを確認することが重要です。
また、一般媒介契約で複数の業者に依頼し、広く市場に情報を公開する方法も有効です。
ナッシュ均衡と不動産取引
ゲーム理論におけるナッシュ均衡は、不動産取引においても非常に重要です。
ナッシュ均衡とは、各プレイヤーが最適な戦略を取った結果、他のプレイヤーがその戦略を変更しても誰も利益を増やせない状態を指します。
売主と買主のナッシュ均衡
- 売主:できるだけ高く売りたい
- 買主:できるだけ安く購入したい
という利害が対立していますが、交渉を通じて最適な合意に達すれば、それがナッシュ均衡の状態だと言えます。
たとえば、売主が5,000万円で売りたい一方、買主が4,500万円を提示して交渉を始め、最終的に4,750万円で合意すれば、それがナッシュ均衡です。
ナッシュ均衡でない状態とは?
ナッシュ均衡でない状態とは、プレイヤーの誰かが自分の戦略を変更することで利益を増やせる可能性がある状態を指します。
つまり、プレイヤー同士の戦略の組み合わせが最適ではなく、どちらかが戦略を変えることで全体の利益が改善される余地がある状況です。
不動産売買におけるナッシュ均衡でない状態の例
- 売主が市場価格よりも高い6,000万円で物件を売り出している。
- 買主はその価格を高すぎると感じ、購入を見送っている。
- 仲介業者は高値のために買主を見つけられず、積極的な広告活動を控えている。
この状況では、取引が成立しておらず、各プレイヤーが現状に不満を持っています。
- 売主は物件が売れず、維持費や市場の変動リスクを負い続けている。
- 買主は希望する物件を購入できず、他の物件を探す手間が増えている。
- 仲介業者は手数料を得られず、時間とリソースを無駄にしている。
状況を改善する戦略の変更
売主が価格を相場付近の5,000万円に下げる。
効果:買主の関心を引き、交渉が開始される。
この金額なら、一度内見してみたいな!
買主が予算を見直し、多少高くても購入を検討する。
効果:売主との価格交渉が可能になる。
4,500万円で売るのはちょっと厳しいけど、4,750万円ぐらいならアリかなぁ……。
仲介業者が市場データを提供し、売主に価格調整を提案する。
効果:取引成立の可能性が高まり、手数料獲得につながる。
4,750万円でも、相場と比較すると高めなので売却のチャンスですね。
上記のような戦略の変更により、各プレイヤーがより大きな利益を得られる可能性が生まれます。
このように、誰かが戦略を変えることで全体の状況が改善される場合、その状態はナッシュ均衡ではありません。
ナッシュ均衡でない状態の特徴
- 最適でない戦略の選択:プレイヤーの戦略が互いに最適な反応となっていない。
- 利益の改善余地:戦略を変更することで、少なくとも一方が利益を増やせる。
- 不満足な現状:取引が成立しない、または全員が利益を最大化していない。
なぜナッシュ均衡でない状態が起こるのか
- 情報の非対称性:市場価格や物件の価値に関する情報がプレイヤー間で共有されていない。
- 過度な期待や固執:売主や買主が自分の希望条件に固執し、柔軟性を欠く。
- コミュニケーション不足:仲介業者からの適切なアドバイスや市場分析が提供されていない。
実際の不動産売買市場では、「高値で売り出す」という状態を続けたとしても、他に相場価格付近の物件が売り出されれば、買主はほぼ確実にそちらに流れるでしょう。
家が売れないリスクを避けるためには「まず売主が相場価格を把握した上で、買主が検討できる価格で売り出す」ことが重要なのです。
高めに販売を開始しても、「結局売れずに値下げしなければいけない」リスクは認識しておきましょう。
これは仲介の実例ですが、あるマンションの売り相場は2,800万でした。
指値が入ることを考慮して3,000万で市場に出し、すぐに2,900万で購入したいという買主さんが現れましたが、市場に出したばかりだし、もう少し様子を見たいため100万の指値を受けたくないとのことでその購入者をお断りした結果、結局売却には1年半かかり最終的に2,500万で手放すこととなりました。
株式会社アイホーム(ヤマダ不動産神戸本店)
代表取締役 告野 亘 様 よりヒアリング2
上記は、不動産会社の方から聞いた「高値での成約を狙ったものの、売却が長期化して、最終的に金額が下がってしまった」ケースです。
株や為替のような金融商品、あるいは車や時計といった資産性のある動産と比較して、不動産の売買は「個別の物件状態」が全て異なり、取引数も少ないです。
売れ行きを正確に予測することはできず、見込み客を1人逃すリスクが想像以上に大きくなってしまう可能性も考えられるでしょう。
高値で販売すると広告の効果も薄くなってしまう
最近はSUUMOやHOME’Sなどのポータルサイトで家探しをする人が多くなっています。
買主は予算や希望条件を絞ってさまざまな物件情報を確認していますから、売主よりも相場に詳しいケースも珍しくありません。
HOME’Sより:物件情報を検索した際に、上部に設けられた広告枠に掲載することにより、反響を獲得しやすくできる。
ポータルサイトでは、物件情報を掲載する不動産会社が広告費を支払って露出の機会を増やすことができます。
上記はHOME’Sで物件情報を検索した際の例ですが、リスト上部にある「PR」の表記部分は、不動産会社がポータルサイト側に別途費用を支払って広告掲載されています。
このように広告費をかけて広く目に入れてもらえるようにすることで、より早く・より良い条件での取引が目指せますが、値段設定が高すぎると参考程度に閲覧されるに留まってしまい、反響・申し込みは得られず仕舞いで広告の効果が悪くなってしまいます。
そのため、適切な値段に下げることを売主が納得するまで、広告掲載は行わないといった対応をされる可能性も十分考えられるでしょう。
仲介会社としても「成約に繋がる見込みの薄い物件情報の拡散に力を入れることはできない」という状態です。
仮に内見の申し込みが入ったとしても「高すぎるから別の物件を買う予定だけど、参考程度に見ておきたい」といった確度の低い内見者しか訪れない確率が高まり、対応にかかる時間・手間も無駄になってしまう点もデメリットだと言えるでしょう。
適正な相場価格で売り出されている物件が無い場合、値下げはチャンスかも?
実際の不動産取引では、売主・買主・仲介業者はどれも複数の参加者が存在します。
「他の売り物件の価格が強気すぎて、買主が交渉できる余地が無い」ことが原因でナッシュ均衡ではない状態にあるなら、売主は他の売り物件に先んじて相場に近い金額への値下げをすることで、有利な条件で売却できる可能性があります。
非ナッシュ均衡時に「他よりは安い」条件を提示
たとえば、成約が見込める相場価格が4,500万円のマンションが複数売りに出ているものの、全て5,000万円以上の値段が設定されているようなケースを考えてみましょう。
- 5,250万円
- 5,200万円
- 5,100万円
どの物件も相場の4,500万円よりは高すぎるなぁ。予算は4,700万円だから、もう少し安い物件が出てこないかなぁ……。
この状態で1つの物件が4,850万円に値下げされれば、依然として4,500万円よりは高いため、買主から指値が入る可能性はあるものの、他の物件よりも買主プレイヤーの注目を集めやすいです。
- 5,250万円
- 5,200万円
- 4,850万円
少し希望額に近い金額が出た! この物件なら、予算の金額付近で価格交渉ができるかもしれない。
相場より10%以上高い5,000万円は無理でも、4,800万円など、少し高いラインで成約できる可能性は十分考えられます。
価格設定に柔軟性を持たせる
買主プレイヤーからしても「検討候補だった物件が値下げされた」タイミングは非常に魅力的に見えるため、「この値下げのチャンスは逃さない方が良さそうだ」という心理が働く可能性もあります。
気になってた物件が値下げされたから、今がチャンスかも……。
「家を高く売りたい」という気持ちばかりを優先して、高値を設定し続けるよりは、状況に応じて価格を変更する柔軟性を持っておくことが、高値で売る可能性を生むのです。
ただし、こうした「市場の反応を的確に予測した値下げ」を行うのは非常に難しく、売主本人の相場価格への理解と、仲介業者との連携が求められます。
囚人のジレンマと不動産取引
ゲーム理論の囚人のジレンマは、不動産取引においてもよく見られます。
囚人のジレンマは、各プレイヤーが協力すれば全体の利益が最大化されるにもかかわらず、個々の利益を優先することで、全体として損をする状況を指します。
売主の強気な価格設定によるジレンマ
売主が強気の価格設定を行い、他の売主もそれに追従すると、市場全体で物件が売れ残る結果に陥ることがあります。
これが典型的な囚人のジレンマです。
解決策
市場価格に応じて適正な価格を設定することで、早期に売却を成功させ、全体の利益を最大化することが可能です。
強気すぎる価格設定は、他の物件と競合し、結果的に値下げを強いられるリスクが高まります。
売主が相場を分析する重要性
売主が成功裏に物件を売却するためには、相場をしっかりと分析することが非常に重要です。
過去の取引事例を活用する
自分の物件を過去の取引事例や現在の売り出し中の物件と照らし合わせることで、適切な価格や売却戦略��の設定が可能になります。
同じエリア、同じ規模や条件(築年数、土地の形状、リフォームの有無等)の物件がどのような価格で売却されたのかといった情報は、必ず確認しておきましょう。
利益最大化戦略
市場の実勢価格に基づいて、高すぎず、低すぎない適正価格を設定することで、売却を早期に進め、最終的に望む価格に近づけることができます。
リスク回避
過去のデータに基づいた価格設定を行うことで、無謀な高値設定を避け、売却の長期化や、最終的に大幅な値下げを強いられるリスクを軽減できます。
売り出し中の物件情報と比較する
SUUMOやHOME’Sといった不動産ポータルサイトでは、現在販売中の不動産情報が閲覧できます。
現在売り出し中の物件情報もまた、売主にとって重要な参考材料です。
同じエリアで競合する物件の価格や条件を把握し、自分の物件をどう位置づけるかを考えましょう。
競合分析
売り出し期間が長い物件がある場合、それは市場価格より高すぎる可能性があり、これを参考にして自分の物件を適正な価格で売り出すことが有効です。
自分の物件の条件を分析する
さらに、自分の物件の立地、築年数、広さ、設備などの条件を分析し、それを相場と比較することも不可欠です。
同じエリアでも、駅に近いか、リフォームが必要かどうかなど、細かな条件が価格に影響します。
戦略的価格設定
自分の物件が他の物件に対してどう差別化できるか、またはどの程度価格競争力があるかを理解することで、より有利な売却を��進めることができます。
適正価格の重要性
相場を理解した上で適正価格を設定することは、売却を有利に進めるための基本です。
適正価格で売り出された物件は、買主の注目を集めやすく、早期に取引が成立する可能性が高まります。
過大な価格設定のリスク
高すぎる価格設定を行うと、仲介業者が積極的に広告を行わなくなるリスクが生じ、売却機会を逃す恐れがあります。
不動産会社がSUUMOやHOME’Sなどのポータルサイトに物件情報を掲載する際は、オプション料金を支払って買主に見つけてもらいやすくすることが可能です(広告枠の利用)。
仲介業者は売れやすい物件に対して広告費やプロモーションのリソースを割り当てます。
しかし、価格が高すぎる場合、そこから申し込みに繋がらないため、不動産会社は有料オプションを選択しにくくなるのです(仲介業者のリスク回避)。
仲介業者の過大査定を見抜くためにも相場分析が有効
相場を分析しておくことは、媒介契約を結ぶ際に高い査定額を提示して契約を取ろうとする仲介業者を見抜くためにも役立ちます。
仲介業者は媒介契約を取るために高すぎる査定額を提示することがあるため、売主自身が市場の実勢価格(実際に取引が成立した値段)を理解していることが、リスク回避のために不可欠です。
売主が相場を把握していれば、このような過大査定を見抜き、適正な価格で販売できるでしょう。
マンションと戸建てにおける売却市場の違い
マンションと戸建てでは市場の特性が大きく異なります。
これを踏まえて売却戦略を立てることが重要です。
マンション:類似物件が多い競争市場
マンションは、同じ建物内や近隣に似た条件の物件が多く売り出されるため、他の物件と競争になることが一般的です。
競争の激化
価格や条件が僅かに違うだけでも、買主に選ばれにくくなるため、適正価格の設定が特に重要です。
高すぎる価格設定は、他の類似物件に買主を取られ、結果的に売却が長期化するリスクがあります。
差別化戦略
他の物件との差別化を図るために、リフォームや内装の充実、設備のアピールなどが有利になることもあります。
戸建て:物件数が少ない希少市場
戸建ては、同じエリア内で売り出される物件が少ないため、マンションに比べて直接的な競争が少なく、希少性が高い市場です。
希少性を活かす
戸建てはマンションほどの価格競争が発生しにくいため、相場の上限に近い価格設定でも売却が進む可能性があります。
しかし、レインズのデータでは、戸建てはマンションに比べて「売り出し価格よりも成約価格の値下げ率が大きい」という特徴もあるため、「相場よりも高い金額で売れる」わけではないのです3。
そのため、当該エリアでどんな物件が好まれているかといった情報を参考にした上で、売り出し後は反響数を見ながら、必要に応じて価格交渉にも応じる姿勢が求められます。
「最初は高く出して様子を見る」という戦略が無駄になる可能性
売主が「最初は高めに出して様子を見よう」と考える戦略は、不動産市場でのゲームに参加すらできないリスクを伴います。
高すぎる価格設定で市場から無視されるリスク
不動産市場では、買主は多くの物件の中から購入を検討します。
高すぎる価格設定を行った物件は、買主の検索条件に合致せず、興味を持たれない可能性があります。
これにより、売主は市場に物件を出しているにもかかわらず、実質的に市場に存在していないのと同じ状態です。
「高く売りたい」という願望のある売主は、どうしても「仲介会社による囲い込み」などのリスクを懸念する傾向にありますが、「買主に検討されない」という意味では、高すぎる値段設定もリスクが非常に大きいのです。
戦略として無駄な高値設定
「高く売れたらラッキーと考えて、高い値段で様子を見る」戦略は、実際には無駄な行為となることが多いです。
買主の関心や仲介業者のインセンティブが生まれないため、時間だけが経過し、売却機会が失われることになります。
また、その間に市場の相場が変動すれば、さらに売りにくくなる可能性もあるでしょう。
時間の浪費
高値で長期間売り出していても反応がない場合、最終的に大幅な値下げが必要とな�るだけでなく、物件が「売れ残り」として市場で悪い印象を与え、適正価格に戻した時でも注目されにくくなります。
リスクの増大
買主の注目を集めないまま市場に長く残り続けることで、仲介業者のモチベーションが下がるほか、市場の価格が下落するリスクもあります。
そのため、最初から適正価格を設定することが、取引を有利に進めるための鍵です。
ただし「値下げをする」ことは買手の注目を集めることができるため、ナッシュ均衡の項目で説明したように、タイミングを見計らって値下げをする前提で高めの値段を掲げることは、売れやすさ・売れる値段両方の観点からポジティブな影響が生まれることもあります。
仲介会社との効果的な協力方法
不動産の売却を成功させるためには、仲介会社と連携し、売却戦略を共有することも重要です。
仲介会社に売却事情やローンの残債等を伝える
売主は売却の目的や、価格設定の意図を仲介業者にしっかりと伝えることで、双方の戦略を一致させることができます。
特に「住宅ローン残高を売却金額でクリアできないのであれば売らない」といった事情があるならば、そのことは明確に伝えておくべきです。
場合によっては「その金額では売れない可能性が高いから、一度売却を考え直す」方が、時間や費用を無駄に使わずに済みます。
宣伝活動を積極的に行ってもらうための工夫
仲介業者が広告や購入検討者への紹介を積極的に行えるよう、広告費の一部負担などのインセンティブを提供することも効果的です。
柔軟な価格調整の姿勢を示す
定期的に仲介業者に販売状況をヒアリングし、市場の動向に基づいた柔軟な価格調整を行うことで、売却機会を逃さずに高値で売れるチャンスを広げます。
売り出しタイミングを遅らせる戦略のリスク
周囲に競合物件が多い場合、売主がタイミングを見計らって売り出しを遅らせ、競合が減るのを待つという戦略を考えることがあります。
しかし、この戦略にはリスクも伴います。
タイミングを遅らせることのメリット
競合物件が減る可能性
周囲に売り出し中の物件が多いと、買主に選択肢が増えます。
他の物件が売れてから売り出せれば、自分の物件を目立たせることができるでしょう。
タイミングを遅らせることのリスク
しかし、売り出しを遅らせる戦略にはリスクもあります。
新たな物件が市場に出てくる可能性
売却を遅らせても、他に新しい物件が市場に出る可能性が高く、競争を完全に避けることは難しいです。
待った結果、さらに多くの物件が売りに出され、競争が激しくなる可能性もあります。
市場全体の下落リスク
市場の動向によっては、売り出しを遅らせることで価格が下がるリスクがあります。
特に経済情勢や不動産市場の調整期に入ると、タイミングを逃してしまうと逆に不利な状況に追い込まれる可能性もあります。
売主の仲介手数料無料の不動産会社を利用するデメリット
「売却後に手元に残るお金を多くする」という観点では、「売主の仲介手数料を無料にします」と謳う不動産会社と契約し��たくなる方もいるかもしれません。
仲介手数料が無料になることで一見コストが削減されるように見えますが、これにより仲介業者のモチベーションや活動が制限され、結果的に売主が得られる利益を減らすリスクがあります。
売主が支払う手数料がゼロになることで仲介業者のインセンティブが弱くなり、全体の利益が最大化されない状況が発生する可能性があるのです。
仲介業者のインセンティブ低下リスク
仲介業者は、手数料によって収益を得るビジネスモデルです。
手数料が無料であれば、その物件の売却に対するインセンティブが低くなります。
結果として、仲介業者が物件の販売促進に費やすリソースや時間が限られ、十分な広告やプロモーションが行われなくなる可能性があります。
サービスの質が低下するリスク
仲介手数料が無料の業者は、コスト削減のために対応するスタッフの数を減らしたり、広告にかける予算を抑えたりすることが多いです。
その結果、売主が受けられるサービスの質が低下する可能性があります。具体的には、以下のようなリスクが考えられます。
市場分析の不十分さ
不動産市場の適切な価格分析が行われないまま物件が売り出されると、売却が長引いたり、適正価格に修正する必要が生じることがあります。
契約や交渉サポートの低下
価格交渉や契約の締結に関するサポートが不十分であれば、売主は自分にとって不利な条件で契約を進めてしまうリスクがあります。
両手取引や囲い込みのリスクが増える
手数料無料の仲介業者は、売主から手数料を得られないため、買主からの手数料に依存するビジネスモデルになりがちです。
このため、両手取引を狙った囲い込みを行うリスクが高まる可能性があります。
買主の仲介手数料割引・無料戦略が売主に有利な理由
ゲーム理論の観点では、「買主の仲介手数料を割引・最大無料」などとする不動産会社に売却を依頼することは、売主の立場から見ても悪い選択肢ではありません。
買主のインセンティブを強化する
買主に対して仲介手数料を割引または無料とすることで、物件購入時のコストが低減され、より多くの買主がその物件に興味を持ちやすくなります。
これは、ゲーム理論におけるプレイヤー(買主)の選択肢を広げる戦略です。
買主のコストが下がるメリット
購入意欲の増加
購入時の仲介手数料が割引・無料になることで、買主が支払う総コストを下げられるため、物件購入を決断しやすくなります。
競争の活性化
複数の買主が同じ物件に関心を持つことで、買主間の競争が激化し、結果として売主に有利な条件で取引が成立する可能性が高まります。
このように、買主のインセンティブが高まることで、より多くのプレイヤー(買主)が市場に参加し、売主にとっても高い価格での売却が期待できる状況が作り出されます。
売主が受ける間接的な利益
買主の手数料が無料または割引になると、売主にとっても間接的な利益が生まれるのです。
具体的には、取引のスムーズさやスピードが増し、売主が利益を得る機会が高まります。
取引成立のスピードが上がる
買主にとって金銭的な負担が少なくなるため、物件購入に対する決断が早まります。
これにより、売主が物件を早期に売却できる可能性も高まります。
売却が長引くと売り出し価格を下げざるを得なかったり、他の競合物件が市場に出たりするリスクがありますが、取引が早期に成立すればそうしたリスクも軽減できるでしょう。
価格交渉の余地が広がる
買主の手数料が割引・無料である場合、買主は他の物件よりも少し高い価格でも購入を検討する傾向があります。
ゲーム理論の視点では、プレイヤー(買主)の仲介手数料分の金銭的な負担が軽減されることで、購入に際して余裕を持てるため、売主との価格交渉が売主に有利に進む可能性が高まります。
例えば、物件価格3,000万円の物件が取引される際、売主・買主はそれぞれ105.6万円の手数料を仲介業者に支払います。
| 仲介手数料率 | 買主の総支払額 |
| 仲介手数料上限 | 3,105万円 |
| 仲介手数料5割引き | 3,053万円 |
| 仲介手数料無料 | 3,000万円 |
買主が支払う手数料は、上記の通りです。
買主としても「安く買いたい」と考えているため、3,100万円まで価格を引き上げるのは難しいかもしれません。
しかし、仲介手数料が無料の場合、3,050万円付近であれば売主・買主双方が50万円ずつ得をするため、成約する可能性が生まれやすいです。
仲介手数料が発生しない分、売主の値下げ額が小さくても、合意できる余地が生まれやすいのです。
仲介業者のモチベーションは保たれる
売主・買主それぞれから満額の手数料を受け取ることと比較すると、1回分の取引で得られる手数料は減ってしまいます。
しかし、仲介手数料を割引・無料とする場合でも、売主からの手数料は通常通り発生します。
また、仲介手数料が無料であることにより、より多くの買主を引き寄せることができ、仲介業者は取引を成立させやすくなります。
さらに「買主から手数料を取らない」ということは、他の業者から買手を紹介されたとしても断ることはほとんど無いと想定できます。
つまり、囲い込みのリスクも低減できるのです。
「買主の仲介手数料を割引・無料」などとしている不動産会社は少ないのが現状ですが、全くないわけではありません。
業者を選定して売却するまでの時間に余裕があれば、こうした方針を取る仲介業者への依頼も視野に入れてみるのが良いでしょう。
ゲーム理論を活用した家の売却戦略
不動産取引において、ゲーム理論を応用して売主、買主、仲介業者の行動を分析することで、最適な売却戦略を立てることができます。
売主は特に、高値での売却を目指す場合で�も、適正価格から大幅に値上げした価格では「そもそも申し込みが入らない・検討すらしてもらえない」というデメリットがあることを認識しましょう。
この点を理解しなければ「媒介契約の取得を目的に、大幅な高値で査定する」といった営業方針の不動産会社に騙されて「高く売れるどころか、売れ残って損をしてしまう」リスクがあります。
また、両手取引や囲い込みのリスクに対しては、仲介業者の動向をしっかり把握し、必要に応じて複数業者と契約するなどの対策が重要です。