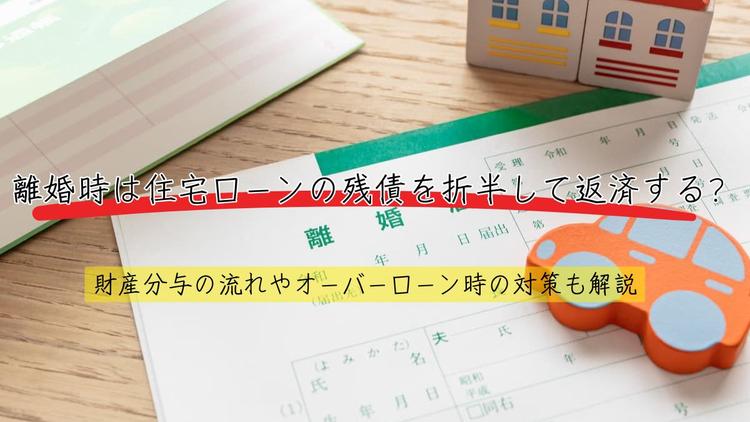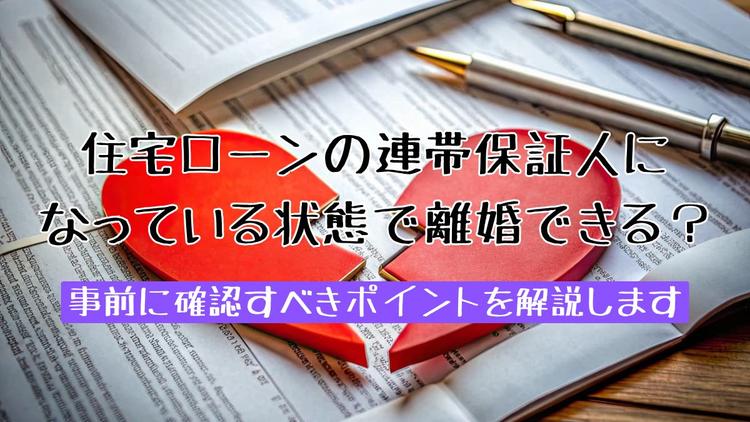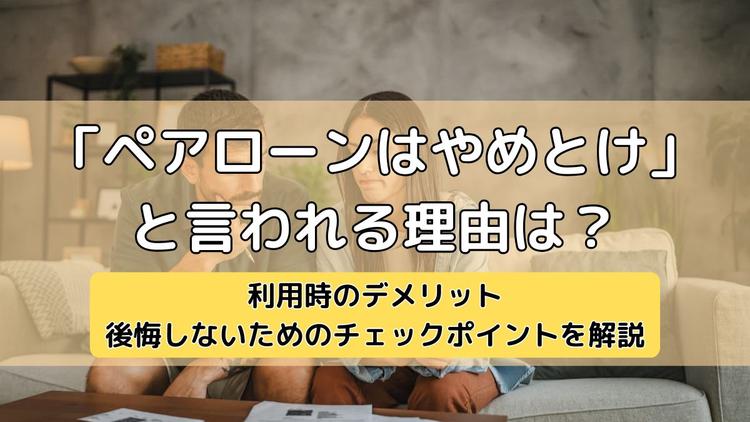離婚の際には、夫婦で財産を公平に分ける財産分与を行います。
しかし、財産分与の対象となるのは共有財産に限られるので、結婚前に買った家は含まれません。
ただし、結婚前に買った家でも交渉によっては財産分与できる可能性があります。
この記事では、財産分与の対象や、結婚前に買った家が財産分与の対象となるケース、さらに財産分与の対象とならない家を離婚時に取得する方法などを分かりやすく解説します。
離婚で財産分与の対象となる財産とならない財産
離婚における財産分与とは、夫婦の財産を公平に分けることをいいます。
基本的には、夫婦それぞれの収入差や財産の名義にかかわらず、1:1の割合で分けることになります。
家についても、財産分与の対象となる場合は、たとえ夫名義であっても夫婦で公平に分ける必要があります。
しかし、すべての財産が財産分与の対象とは限りません。
まずは、財産分与の対象となる財産と、対象外となる財産の違いを確認していきましょう。
結婚後に夫婦で築き上げた共有財産が対象
財産分与の対象となるのは、共有財産です。
共有財産とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を指します。
現預金や有価証券、不動産など、婚姻期間中に取得・形成・維持された財産は、名義に関わらず共有財産として財産分与が必要です。
たとえ妻が専業主婦であったとしても、妻の家事や育児の貢献を含めて財産が形成されたとみなされるので、公平に財産分与することになります。
また、将来どちらかが受け取る退職金や年金も、財産分与の対象です。
なお、離婚成立前に別居していた場合、別居までに築いた財産が共有財産となり、別居期間中に取得した財産は基本的に対象となりません。
結婚前から所有していた特有財産は対象外
特有財産とは、夫婦それぞれが相手方の協力なしで築いた財産のことを言います。
特有財産にもいくつか種類がありますが、代表的な特有財産が婚姻前から所有していた財産です。
たとえば、独身時代に貯めていた貯金や、購入した車・有価証券などがこれに該当します。
そのため、家であっても独身時代に購入しているものであれば特有財産とみなされ、財産分与の対象になりません。
なお、特有財産か共有財産かが明らかでない財産は、共有財産として財産分与の対象となります。
結婚前に買った家が離婚後に財産分与となるケースとは?
結婚前に購入した家は、特有財産・共有財産の判断が複雑になりがちです。
ここでは、結婚前に購入した家について詳しくみていきましょう。
原則:結婚�前に購入していた特有財産は財産分与の対象とならない
前述のとおり、結婚前に購入した家は特有財産となるので、財産分与の対象とはなりません。
特有財産であることを証明する際には、不動産登記簿や売買契約書が用いられるのが一般的です。
結婚後に住宅ローンを返済していた場合は返済した分が共有財産となる
結婚前に購入した不動産でも、婚姻期間中に住宅ローンを返済した場合は、完全には特有財産とはなりません。
この場合、婚姻期間中に返済した住宅ローンの割合で、特有財産と共有財産を分けることになります。
ただし、共有財産となるのは返済したローン額ではなく、以下の計算式で求めます。
たとえば、今の家の価値が3,000万円、購入価格が4,000万円で婚姻期間中に1,000万円の返済を行った場合の共有財産は以下のとおりです。
この場合、750万円を共有財産として、それぞれ375万円ずつで財産分与することになります。
ただし、オーバーローンの家は基本的に財産分与の対象とはなりません。
オーバーローンの家は財産分与で揉めやすいので、弁護士に相談して分割方法を検討することをおすすめします。
結婚後に買った家でも特有財産になるケースとは?
結婚後に取得した家は、どちらか一方の名義であっても共有財産として財産分与の対象です。
しかし、以下のケースでは結婚後の取得であっても一部または全部が特有財産となります。
- 結婚後に相続によって取得した家
- 夫婦どちらかの親から援助を受けたケース
- 結婚前に貯めたお金を頭金にしたケース
それぞれ見ていきましょう。
結婚後に相続によって取得した家
相続によって取得した財産は、夫婦の協力によって得たものではないため、共有財産とはみなされません。
そのため、相続によって取得した家は、相続人の特有財産として扱われます。
たとえば、結婚後に妻が自分の親から実家を相続した場合、実家は妻の特有財産になるので財産分与の対象にはならないのです。
これは家に限らず、現預金などの相続財産すべてが特有財産に該当します。
ただし、相続で取得後、夫婦共同で家を修繕した場合や、相続した土地に夫婦で家を建てた場合では、例外的に財産分与の対象となる可能性があります。
夫婦どちらかの親から援助を受けたケース
家を購入する際、親から援助を受けたケースでは、援助された部分は特有財産になります。
親からの資金援助は親の財産の贈与であり、相続同様、夫婦で協力した財産ではないため、贈与を受けた側の特有財産です。
そのため、家の価値から援助の部分を差し引いて財産分与を行うことになります。
結婚前に貯めたお金を頭金にしたケース
結婚前に貯めたお金は特有財産になるため、特有財産から出した頭金の部分は財産分与の対象にはなりません。
この場合、家の購入価格に占める頭金(特有財産)の割合を算出し、現在の家の価値にその割合をかけて差し引いた残りの部分が共有財産として財産分与の対象になります。
たとえば、以下のケースで見てみましょう。
- 家の購入額:3,000万円
- 特有財産から出した頭金:600万円
- 現在の家の価値:2,000万円
頭金の割合は、600万円÷3,000万円=0.2、つまり20%です。
今の家の価値2,000万円にこの割合をかけると、400万円が特有財産に該当します。
そして、家の価値から特有財産を引いた1,600万円が財産分与の対象となるのです。
家の頭金を親からの援助や独身自体の貯金から出す場合、財産分与の仕方が複雑になります。
さらに、夫婦それぞれが特有財産から捻出すると、より複雑になり財産分与でトラブルに発展しやすいため、財産分与の仕方は弁護士などに相談するとよいでしょう。
特有財産でも離婚後に財産を貰う方法とは?
家が相手の特有財産であると財産分与の対象とならないため、出ていく必要があります。
家だけに限らず、相手の特有財産は取得できないため、離婚後の生活に支障が出る場合もあるでしょう。
しかし、相手の特有財産であっても取得できるケースがあります。
ここでは、相手の特有財産でも取得できる代表的な方法として以下の3つを解説します。
- 話し合って相手の承諾を得て財産分与の対象にしてもらう
- 慰謝料として受け取る
- 差し押さえの対象とできるケースがある
それぞれ見ていきましょう。
話し合って相手の承諾を得て財産分与の対象にしてもらう
財産分与の仕方は、夫婦の合意で決めることができます。
話し合いにより、特有財産を財産分与の対象にすることに相手が合意すれば、本来は対象外である特有財産であっても分与の対象とすることが可能です。
たとえば、共有財産として現金が2,000万円、相手の特有財産である家が1,000万円の場合、財産分与の対象は現金の2,000万円となり、1,000万円ずつが分配されます。
しかし、相手が話し合いで「自分が家を受け取る代わりに、現金2,000万円を渡す」ことに合意すれば、家の取得が可能です。
また、財産分与の割合も話し合いで決めることができるため、相手の合意があれば家と現金を取得できる可能性もあります。
なお、話し合いで財産分与の仕方がまとまらない場合、裁判所の調停を申して立てて決めることになります。
調停でもまとまらない場合は訴訟になりますが、訴訟になると相手の特有財産の取得は難しくなるので注意しましょう。
慰謝料として受け取る
慰謝料とは、離婚の原因を作った有責者に対して、損害賠償として請求する金銭です。
たとえば、相手の不貞行為により離婚になるケースでは、相手に慰謝料を請求できます。このとき、相手が慰謝料を支払えない場合などには、代わりに家をもらうことも可能です。
また、相手が一方的に離婚を要求するようなケースでも、解決金の名目で家を取得できる可能性があります。
差し押さえの対象とできるケースがある
財産分与で決まった財産を渡してくれない場合や、慰謝料や養�育費を支払ってくれない場合では、家を差し押さえできる可能性があります。
しかし、差し押さえは裁判手続きが必要になり、時間も労力もかかります。
また、夫婦間で作成した離婚協議書だけでは差し押さえできない可能性があるので、離婚協議書は法的効力のある「公正証書」として作成しておくことが大切です。
離婚時に夫婦間で合意した内容(慰謝料、財産分与、養育費など)を記録するのが「離婚協議書」です。
しかし、これは私文書であり、法的拘束力が弱いため、相手が約束を守らなかった場合、すぐに差し押さえなどの強制執行はできません。強制力を持たせるには、裁判を起こし、判決や和解調書を得る必要があります。
一方、「公正証書」は、公証役場で公証人に作成してもらう公文書であり、特に「強制執行認諾条項」を付けることで、相手が支払いを怠った際には裁判を経ずに差し押さえなどの強制執行が可能になります。
そのため、特に慰謝料や養育費など将来的に支払いが続く内容を取り決める場合には、離婚協議書をもとに公正証書を作成しておくことが重要です。
結婚前に買った家の財産分与に関する注意点
結婚前に買った家の財産分与では、以下の2点に注意が必要です。
- 離婚訴訟になると家をもらうことが難しくなる
- 家の財産分与を受ける場合は住宅ローン残債に注意
それぞれ見ていきましょう。
離婚訴訟になると家をもらうことが難しくなる
先述のとおり、財産分与の仕方で揉めて離婚訴訟になると、相手の特有財産である家の取得は難しくなります。
離婚訴訟とは、調停でも解決できない場合に、裁判所が離婚の可否や条件を判断して審判を下す手続きです。
離婚訴訟では、基本的に法的に権利のあることしか認められません。
特有財産の権利は相手にあるため、訴訟では相手の特有財産を財産分与の対象として請求することはできません。
そのため、裁判所の判断では、相手の特有財産は財産分与の対象から外したうえで、財産分与の仕方などが決められます。
仮に慰謝料が発生する場合でも、支払いは金銭となるため、慰謝料代わりに家を譲渡するという審判は下されません。
相手の特有財産である家を取得したい場合は、離婚訴訟の前の段階で合意できるように、慎重に話し合いを進めることが大切です。
家の財産分与を受ける場合は住宅ローン残債に注意
家が共有財産であっても、オーバーローンの家は財産分与の対象とはなりません。
オーバーローンとは、住宅ローン残債が家の価値を上回る状態です。
たとえば、住宅ローン残債が2,000万円のとき、今の家の価値が1,500万円ならオーバーローンとなります。
新築で家を購入してから数年しかたっていない、住宅ローンを組む際にフルローンで組んでいるといったケースで、家の価値の減少率より住宅ローンの返済の進みが悪くオーバーローンになる恐れがあります。
財産分与の対象となるのはプラスの共有財産であり、借金などのマイナスの財産は対象とはなりません。
オーバーローンの家は負債であることから、財産分与の対象とはならないのです。
仮に、�住宅ローン残債が2,000万円、家の価値が1,500万円である場合、差し引いた負債500万円を夫婦で分ける必要はありません。
この場合、家の価値は0円として残りの共有財産を財産分与で分割することになり、住宅ローン残債は名義人だけが返済の義務を負います。
ただし、オーバーローンの家のマイナス分は共有財産で相殺するという方法も選択できます。
オーバーローンの家は財産分与での取り扱いが複雑になりやすいので、弁護士などに相談をおすすめします。
なお、オーバーローンの家は、マイナス分を自己資金などで完済できない場合は、売却もできない点には注意しましょう。
▼関連記事:離婚時は住宅ローンの残債を折半して返済する?財産分与の流れやオーバーローン時の対策も解説
まとめ
結婚前に買った家は、購入者の特有財産になるため離婚の財産分与の対象とはなりません。
ただし、結婚前に買った家であっても住宅ローンを婚姻期間中に支払っているケースでは、一部が共有財産とみなされます。
反対に、結婚後に取得した家でも、相続で取得した、一方の親から援助を受けた、独身時の貯金を頭金にしたというケースでは、特定財産になる場合があります。
離婚時の家の取り扱いは複雑になりやすいので、弁護士などのプロに相談するとよいでしょう。
また、離婚後に家が残るとローンの支払いなどでトラブルになるケースも珍しくありません。
そのような場合は、売却して売却金を分けた方がトラブルを避けやすくなるので、信頼できる不動産会社に相談してみるとよいでしょう