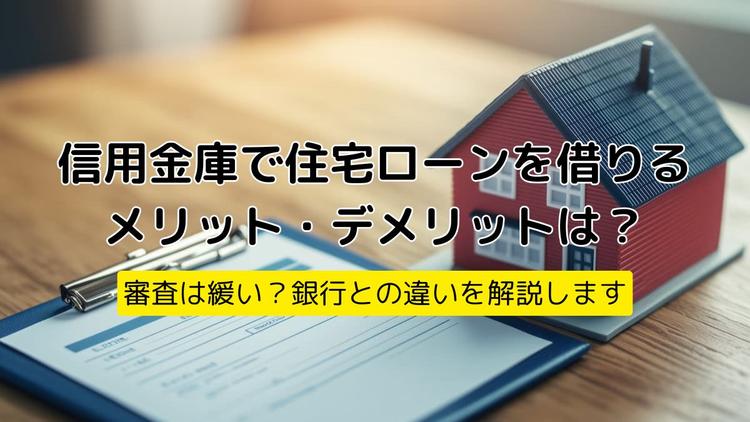※本記事は2019年の消費税増税前に作成したため、消費税の表記に変更がある場合があります。
不動産売却時に課される4つの税金
不動産売却時には、以下4つの税金が課されます。
- 所得税/住民税
- 登録免許税
- 印紙税
- 消費税
それぞれについて見ていきましょう。
①所得税/住民税
まず、不動産を売却して利益があると、その利益分に対して所得税と住民税が課されます。
売却した不動産を購入したときに支払った費用を経費として計上できたり、マイホームの売却の際には特別控除の適用を受けられたりしますが、最大で40%弱の税率が課されるため、事前にいくらくらい税金がかかるかしっかり把握しておくべきだといえます。
②登録免許税
登録免許税は登記に対して課される税金です。
不動産を売却するときの登記には所有権移転登記や抵当権抹消登記などありますが、このうち、所有権移転登記については買主が負担するのが一般的です。
(ただし、登録免許税ではありませんが、売渡証書の作成を司法書士等に依頼する必要があります。)
抵当権抹消登記
住宅購入時に住宅ローンを組んでいる場合、対象の住宅に対して抵当権を設定しますが、住宅売却時にはこの抵当権が抹消されていなければなりません。
すでにローンを完済している場合には、住宅を売却するまでに、ローンが完済されていない場合には、住宅の売却時に、その売却代金などでローンを完済し、抵当権を抹消します。
| 住宅売却時にローンを完済している | 売却までに抵当権抹消する |
| 住宅売却時にローンを完済していない | 売却と同時に抵当権抹消する |
なお、抵当権抹消に関する登録免許税は1筆につき1,000円となっています。
例えば、戸建ての売却で土地1筆、建物1筆であれば2,000円となりますが、1つの土地でも登記上数筆に分かれているような場合には、筆数の分だけ登録免許税がかかります。
住所変更登記
不動産の登記簿謄本には、所有者の住所も記載されています。
住宅購入時から、売却までの間に売主の住所が変わっていて、なおかつ住所変更登記を済ませていない場合には、売却と同時に住所変更登記をしなければなりません。
住所変更登記の登録免許税は、抵当権抹消登記と同じく1筆につき1,000円です。
③印紙税
住宅売却時には、買主との間で住宅に関する不動産売買契約書を取り交わしますが、売買契約書には、契約書に記載されている売買価格に応じた額の印紙を貼って印紙税を納める必要があります。
なお、2027年3月31日までの間に作成された不動産の売買契約書については、以下のように軽減税率の適用を受けることができます1。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
④消費税
最後は消費税です。
基本的に「個人が住宅を売る場合には消費税はかからない」という認識で構いません。
もう少し踏み込んで見てみると、消費税の課税条件は以下のようになっています。
- 土地の取引は非課税
- 建物も、個人が売却する場合は課税されない
- 事業者として建物を売却した際は、消費税が加算される場合がある
なお、仲介手数料や、登記を司法書士に依頼する際の司法書士報酬については消費税がかかる点に注意が必要です。
不動産売却時の譲渡所得税の計算方法
不動産を売却して利益がでると、その利益に対して税金が課されます。
この税金のことを譲渡所得税と呼びますが、譲渡所得税は以下の式で計算できます。
- 課税譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除
- 納税額=課税譲渡所得×税率
取得費の計算では減価償却がポイント
上記計算式のうち、取得費は「売却した不動産を購入したときに要した費用2」で、譲渡費用は「不動産を売却したときに要した費用(仲介手数料など3)」です。
例えば、5,000万円(本体価格+各種経費)で購入した不動産を200万円の経費をかけて3,000万円で売却したような場合には、以下のように計算します。
上記計算式を見ても分かるように、取得費を計上できれば納税額を大きく減らすことができます。
ただ��し、実際には、不動産のうち建物部分については「年数の経過による劣化分」を差し引く必要があり、これを減価償却と呼びます。
仮に、5,000万円で購入した不動産が30年かけて3,000万円にまで価値が落ちていた場合、上記の取得費も3,000万円となるのです。
ただし、土地については減価償却を考慮する必要はありません。
減価償却の計算については下記の記事で詳しく解説しています。

特例の適用を受けて控除を受ける
また、売却する不動産がマイホームであるなど一定の要件を満たすことで、特例の適用を受けられます。
例えば、「3,000万円特別控除」の特例の適用を受けると、先ほど計算した課税譲渡所得の額からさらに3,000万円差し引くことができます。
3,000万円で購入した不動産が30��年かけて1,000万円まで価値が落ち、200万円の経費をかけて3,000万円で売却したような場合で、3,000万円特別控除の適用を受けると以下のようになります。
譲渡所得税の税率は所有期間5年以上かどうかで大きく変わる
譲渡所得税の税金は、売却した不動産の所有期間によって異なります。
具体的には、所有期間が5年以下か、5年超かによって以下のように分けられています。
| 所有期間 | 区分 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 15.315% | 5% | 20.315% |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 30.63% | 9% | 39.63% |
売却するときの所有期間が5年以下の場合には、1~2年待つだけで納税額を半分以下に抑えられる可能性があることを覚えておくようにしましょう。
相続した不動産を売却したときの税金は?
不動産をご両親から相続するなどしたものの、使い途がなく、売却したいというケースではどのように税金を計算するのでしょうか?
相続した不動産を売却しても譲渡所得税は課される
基本的には、相続した不動産を売却する場合でも、通常の売却と同じように、その利益額に対して譲渡所得税が課されます。
相続した不動産を売却する場合、同居していた場合を除き、3,000万円特別控除などマイホームであることを条件とする特例の適用を受けることが出来ない点には注意が必要です。
契約書や領収書など書類を確認しておこう
なお、課税譲渡所得の計算上、取得費は購入時の契約書や領収書を元に算出します。
相続した不動産についても、それらの書類があれば取得費を計上できるため、相続するときには購入時の契約書や領収書などの書類がどこにあるのか事前に確認しておきましょう。
ちなみに、こうした書類がなく取得費が分からないときには「売買価格の5%」を取得費として計上することになります。
相続した不動産の所有期間に関する取扱い
譲渡所得税の税率は、所有期間が5年以下か5年超かによって大きく変わることをお伝えしましたが、相続した不動産については、被相続人(亡くなった方)の所有期間も合算して計算できます。
登記簿謄本などで、いつ取得した不動産なのかを確認しておくとよいでしょう。
所得税/住民税の納期限と相続税の納期限
譲渡所得税は、�売却した年の翌年3月15日までに確定申告して、納税する必要があります。
また、不動産を相続すると、その不動産の価値に応じて相続税を納める必要があり、相続税の納期限は、「相続の開始があることを知った日から10カ月以内」となっています。
例えば、2025年4月に被相続人が死亡して相続が開始され、9月に売却したとすると、所得税の納期限は2026年3月15日まで、相続税の納期限は2026年2月までです。
不動産を相続すると、手元にお金は入ってこないのにも関わらず、多額の税金を現金で支払わなければならないことがあります。
その納税資金の準備のためにも、相続税の納期限までには売却を決めたい、ということもあるでしょう。
こうした期限のある売却については、いつまでに売れるか分からない仲介による売却より、業者買取のような条件がまとまればすぐに売却できる方法を選ぶことをおすすめします。
不動産売却時の税金について具体的にシミュレーション
ここで、不動産売却時の税金について、具体的なケースを想定して納税額をシミュテーションしてみたいと思います。
<ケース1>マイホームを売却する
まずは、以下のような条件でマイホームを売却したケースを見てみたいと思います。
- 売却価格5,000万円(土地1筆/建物1筆)
- 所有期間9年
- 取得費1,000万円(減価償却済)
- 譲渡費用200万円
まず、譲渡所得税を計算します。
5,000万円(売却価格)-1,000万円(取得費)-200万円(譲渡費用)-3,000万円(3,000万円特別控除)=800万円800万円(課税譲渡所得)×20.315%(長期譲渡所得)=162.52万円
また、その他の税金を計算してみると以下のようになります。
| 譲渡所得税 | 162.52万円 |
| 登録免許税 | 0.2万円 |
| 印紙税 | 2万円 |
| 合計 | 164.72万円 |
<ケース2>相続した不動産を売却する
次に、相続した不動産を以下の条件で売却するケースを見ていきましょ�う。
- 売却価格5,000万円(土地1筆/建物1筆)
- 別居
- 所有期間35年(被相続人の所有期間)
- 取得費に関する書類なし
- 譲渡費用200万円
こちらも、まずは譲渡所得を計算していきます。
4,700万円(課税譲渡所得)×20.315%(長期譲渡所得)=954.805万円
その他の税金も考慮すると以下のようになります。
| 譲渡所得税 | 954.805万円 |
| 登録免許税 | 0.2万円 |
| 印紙税 | 2万円 |
| 合計 | 957.005万円 |
このように、取得費が計上できるかどうか、また3,000万円特別控除の適用を受けられるかどうかで納税額が大きく変わることが分かります。
なお、ここでは売却時にかかる税金について説明しています。
相続税については、以下の記事で解説していますので、ご確認ください。
▼関連記事

不動産売却に関する税金の納付手続き
最後に、不動産売却に関する税金の納付手続きを見ていきましょう。
所得税と住民税の確定申告
所得税と住民税については、不動産を売却した年の翌年2月16日~3月15日までの間に確定申告をして、3月15日までに納付する必要があります。
確定申告の手続きについては、期間中に税務署にいくことで申請できますが、その他、e-Taxを使えば自宅からインターネットで手続きを済ますこともできます。
税務署は、原則として平日しか空いていないため、土日休みの仕事をされている方はe-Taxを利用して手続きするとよいでしょう。
登録免許税は司法書士に支払う
登録免許税については、不動産の売却と同時に抵当権抹消登記するパターンでは、司法書士に依頼して手続きすることになります。
この場合、司法書士から「司法書士報酬」と合わせて「登録免許税」についても請求されます。
一方、すでに住宅ローンを完済している場合、自分で抵当権抹消登記することもできます。
この場合、法務局に登記申請書を提出する必要がありますが、提出する申請書に該当額の印紙を貼り付けることで登録免許税を納付します。
印紙税は契約書に貼り付けする
印紙税は、売買契約書を取り交わした後に、売買契約書に該当の額を貼り付けて納付します。
確定申告時に契約書の提出などする必要があるため、少なくともそれまでには貼り付けておくようにしましょう。
なお、印紙を貼らなければならないのにも関わらず貼り付けしていなかった場合には、過怠税が課されることもあるため注意が必要です。
まとめ
不動産売却時にかかる税金についてお伝えしました。
シミュレーションでもお伝えした通り、不動産売却時の税金の多くは譲渡所得税によるものです。
譲渡所得税については、「取得費をいくら計上できるか」や、「3,000万円特別控除の適用を受けられるか」、「所有期間は5年超か」といったことで納税額が大きく変わります。
それぞれについて、少しでも税金が安くなるよう事前に準備していくことが大切だといえるでしょう。
▼関連記事